27 / 27
第三章 冬
第二七話 そして
しおりを挟む
翌朝。
出発を控えた大型の客車がこの町一番の宿屋の前に停まっている。
九人は乗れるだろう客車を牽くのは輓竜の中でも大型の二頭だ。
「くれぐれも寄り道などなさらないようお帰りくださいませ」
「何度も言うでないわ! 大体、お主こそここに残るじゃと?」
宿屋の前、出発を控えた客車の窓から外に立つペッテにナイチアビーナは問い掛けた。
「こちらでの仕事が残されてございます」
まるで動かない表情からは、その真意が窺い知れない。
これに先立ってホーリーに膨れっ面をさせた時からそうなのだから、ここで揺るごう筈もない。
曰く、殿下をお送りするのも立派なお勤めでございます。
そのお勤めをメイドを同伴でなければできないなど、この小娘はいつまでお子様気分でいらっしゃるのでしょうか。
昨夕の食事の後でナイチアビーナとホーリーに抱き付かれて気持ち悪いくらいに喜んでいた人物とは思えない台詞だった。
残されていると言う仕事で考えられるのは俺の家に持ち込んだ荷物の処分だが、俺ならそのままで構わないし、ペッテから何も言われていない。
だからもっと別の何かだろう。
「額面通りには受け取れんが、まあいいじゃろう」
ペッテの真意をナイチアビーナも掴めないらしく、好きにさせることとしたようである。
「出発じゃ!」
御者台に座るガンツが竜の手綱を引き、客車が動き始める。
すると、今し方まで客車の窓から膨れっ面を覗かせていたホーリーが、表情をもの言いたげに変えて俺を見る。
しかし口惜しいかな、俺ができるのは小さく手を振ることだけだ。
開いて行く竜車との距離は不意に空いた心の隙間のそれのようであった。
竜車が町を出て木々に隠れて見えなくなるまで見送った後、俺達は帰宅した。
ペッテが最初にしたのはお茶汲みで、その後も特別何かを始めることもない。
何をしたいのかさっぱりだ。
俺はと言うと、そのお茶を飲みながら、そこはかとない寂しさを感じていた。
ホーリーのことばかりを思い出す。
「ペッテ、ホーリーに相応しくなるにはどうしたらいいんだろう?」
「シモン様がお望みでございましたら、その一端をお教えいたしましょう」
「本当に?」
「勿論でございます。
私からどのように切り出そうかと考えていたところでございます。
シモン様自らがお望みとは重畳にございます」
ペッテが口角を上げて答えた。
明らかにホーリーに向ける時とは違う上がり方だ。
嫌な怖気を感じた。
「では、早速レッスンと参りましょう」
「何の?」
問い返す声が震えた。
胸や手首に触れずとも鼓動が速くなっているのが自分で判る。
糸目で判然としないのに視線に射竦められる感覚。
ヘビに睨まれたカエルも斯くやであろうか。
「貴族の作法でございます。
お嬢様に相応しくあるには絶対的な条件でございます」
ペッテが更に口角を吊り上げ、ずずずいっと迫って来る。
「ちょうどお茶をお飲みでございます。
お茶の作法からにいたしましょう」
ぎゃああ。
ペッテの指導は厳しかった。
できなければ何度でもやり直させられる。
体罰も辞さじだ。
一方で身体を密着させての手取り足取り。
ホーリーとは違って全身が柔らかいため、少し触れられただけで色々な何かが鎌首を上げる。
しかしそうして邪念に囚われれば、人格を破壊せんばかりに容赦の無い叱責が待っている。
言い訳しようものなら更に厳しくなる。
邪念を抱いた罪悪感から有効な反論もできず、言われるがままだ。
そんな叱責を受ける内、途中で何が何だか判らなくなって、記憶も怪しくなった。
ある時、くしゃみをした自分に気付いたら、全裸だった。
訳が判らなかった。
混乱したままペッテに尋ねたら、何度繰り返しても挨拶が上手くできないので「全裸で反省なさいませ」と冗談で言ったら俺がその通りにしてしまったのだと言う。
全然記憶に無い。
ただそれ以降、少しだけペッテの指導が優しくなった。
そんなこんなで、ペッテが居残った理由が俺への指導のためかと思い始めた六日目の夜のこと。
「シモン様、ご確認でございますが、今はお嬢様を伴って召喚なさったままでございますね?」
「え? あ!」
今の今まで忘れていたが、ホーリーとダンジョン探索を続ける間に召喚を日課にしなくなっていた。
召喚する度、送還する度に俺もホーリーも全裸になるので無為な召喚は憚られたのだ。
ロベンスに会いに行ったあの日以来、召喚し直していない。
このままにしておこうものなら、不意の送還にホーリーを巻き込んでしまう。
かと言って、今となっては迂闊に送還もできない。
「どうしたら……」
「送還なさいませ」
「でも、ホーリーが今何処に居るのか判らないよね?」
「寄り道などなさらなければ、今日の午後にも王都にご到着なさっておいでですので、今頃は宿舎でございましょう」
それで寄り道をしないように念を押していたのか……。
最初からこうすると決めていたと思しきことにも驚きと疑問が有る。
「でも、どうして……」
「双方が未練たらたらなままお別れになっては、お嬢様の心に傷を残しかねないためでございます」
全てはホーリーのためだった。
そこは良い。
だが、未練とはどうしたことか。
「俺はホーリーが王都に帰るのに納得してるけど」
「ご自分ではお気づきではございませんでしたか? 何かと捨てられた子犬が縋り付くような目をなさってございました」
未練は確かに有った。
しかしそれが駄々漏れだとは思ってもみなかった。
「それでも、未練が有ったくらいでホーリーの心に傷は大袈裟なんじゃ?」
「シモン様の魔法のせいでございます」
ペッテがそう言った瞬間、空気が張り詰めた。
「以前、私はシモン様の魔法を『罪作り』と申したことがございます。
ここに至りましてはその理由をお話しなければなりません」
俺は黙って頷いた。
「シモン様の魔法は、いえ、恐らくは召喚魔法はでございますが、大袈裟に申しますと召喚する対象の心を縛るのでございます」
以前から仮説は立てられていたと言う。
召喚者は召喚対象を使役するのだから当然だ。
この時、召喚対象が賢ければ賢いほど召喚者に懐き、次回も同じ個体が召喚される傾向が強いのだとか。
「シモン様の魔法にご一緒した場合、シモン様への好意が募るのでございます。
個人差もございましょうが、私の場合でございますと、二度目にはシモン様がお求めならば肌を許しても良い心持ちとなってございました」
そんな魔法の影響と思われる心境の変化は時間の経過と共に薄れ、今はもう消えているらしい。
「『手遅れ』と申しましたのはお嬢様のことでございます。
心境の変化にお気づきでいらっしゃらなかったことから、一回毎の影響は小さいものだったと存じますが、幾度となく魔法にご一緒していらっしゃいますので、累積した影響は計り知れません。
そして今もシモン様の魔法の影響の中にいらっしゃいます」
「そ、それって……、ホーリーが俺に好意を示してくれるのは魔法の影響でしかない……?」
「いえ、元よりある程度の好意と覚悟が無ければご一緒できなかったでございましょう」
その根拠は、対象の知能が高いほど召喚を拒絶しやすいことだと言う。
知能が高くなるほど召喚された例が減る。
輓獣であっても知能が高い竜はめったに召喚されず、人が召喚された例が公式には確認されていない。
公式でない例が、俺自身、俺に伴ったホーリーとペッテ、メーアに召喚されたロベンスである。
ペッテの言う通りなら、メーアはロベンスしか人を召喚できず、ロベンスはメーアからしか召喚を受け付けないことになる。
しかし、そう言われても釈然としない。
好意の大半が魔法の影響、つまり幻だったかも知れないことに変わりないのだから。
「もっと前に送還して、ホーリーから魔法の影響が消えていた方がペッテにとっても良かったんじゃない?」
「この町に滞在する理由もございます。
この町には世界を左右しかねない方々がいらっしゃいますので」
「世界って、大袈裟な……」
「何を呑気になさいますか。
シモン様のことでございます。
他にもメーア様とロベンス様がそうでございます」
「俺!?」
「例えばでございますが、魔物の大群が発生したといたしましょう。
シモン様の召喚に伴ったお嬢様であれば最終的には無傷で全てを殲滅可能でございます。
ましてや、戦争ともなりませば、敵国にとっては悪夢以外の何ものでもないことでございましょう」
同様に、万が一にもメーアとロベンスが人の世界に叛旗を翻した場合、対抗できるのは俺と、俺と一緒に召喚されたホーリーくらいだとも言う。
逆も然りだが、俺に付いているのがホーリーであればその可能性が極めて低いとか。
出会って直ぐの頃に聞いた通りにホーリーの嫁入りが俺を除いて絶望的なことも判断の一つらしい。
ペッテの言うことは尤もだ。
でも……。
「考えすぎだよ」
メーアとロベンスがそんなことになるとは思えないし、俺に至っては過剰評価でしかない。
「左様でございますか」
ペッテの答えには何の抑揚も無い。
「いずれにいたしましても、送還はなさいませ」
「うん」
この機会に送還しなければ今後の俺の活動に障るのだから否やは無い。
いつもの場所に立ち、数回深呼吸して気持ちを静めてから呪文を唱える。
暗転、そして光が戻る。
目の前に現れたのは、目を白黒させた一糸纏わぬホーリーだ。
「ホーリー」
「シモン!? ペッテ!?」
「召喚したままだったろ?」
ホーリーは驚きを顔に浮かべ、それが静まるに連れて目に涙を浮かべる。
「寂しかったのだ! シモンもペッテも居なくて寂しかったのだ!」
不意に俺は身体を締め付けらた。
胸に押し付けられるのは柔らかい感触。
続けて唇が柔らかい感触で塞がれる。
何をされたのか理解するまで数秒を要し、その時にはもう脳が溶けたようにされるがままだ。
更には唇の隙間から柔らかいものが侵入して来る。
この時、俺はホーリーの身体に有る柔らかい部分を新たに知った。
そのまま求められるまま、本能のままに舌を絡め合う。
ところが、ガツンと頭に衝撃を受けた。
舌を噛んだ。
俺とホーリーはそれぞれに口を押さえて涙目だ。
「ひゃひをふゅふゅペッフェ、ひひゃをひゃんひゃひぇひゃひゃいひゃ」
「何をおっしゃっているのか判りません。
シモン様もその汚らわしいものを早々にお仕舞いください」
ペッテにてんこ盛りの威圧感で言われたために忽ちの内に子猫ちゃんとなった我が息子を光の速さで隠す。
無論、比喩だからそこまでの速さは無い。
一瞬前までは猛々しかったのだが、ホーリーのけしからんものが障害となってホーリーとの接触は避けられていた。
もし接触していたら理性など完全に吹き飛んでいたかも知れないので大変危険だ。
まさに一触即発の危機であったが、ペッテのお陰で冷静になれたのだった。
俺とホーリーは背中合わせになり、それぞれに散らばっていた服、ペッテが用意していた服を着る。
再度向き合った時、ホーリーは恥ずかしそうに顔を真っ赤にした。
今し方の痴態を思い出したらしい。
多分俺も真っ赤だ。
顔が熱い。
しかし、恥ずかしがっている場合ではない。
俺には言わなければならないことが有る。
「ホーリー、俺はホーリーが好きだ。
きっと世界で一番好きだ」
ホーリーが目を瞬かせる。
「だから、王都に帰ってくれ」
ホーリーの目が驚きに見開かれた。
「な! 何故だ!? どうしてそうなるのだ!?」
「今のままだと俺は俺を好きでいてくれるホーリーに甘えて、縋ってしまう。
ホーリーの気持ちが俺の魔法で歪められたものかも知れないのにだ」
「歪められてなどいるものか!」
俺は頭を振った。
「それでも、今の俺がホーリーに相応しくないのは間違いない。
だから、二年。
二年だ。
二年経って俺がホーリーに相応しくなれたら、その時にホーリーもまだ俺を好きでいてくれるなら、俺の方から交際を申し込みに行くよ」
「え……?」
「そこで『求婚する』と言えないところが頼りないのでございます」
ホーリーが困惑げに眉尻を下げ、ペッテがやれやれとばかりに頭を振った。
そんな反応に焦るのは俺だ。
「いや、だって、ほら……」
いよいよもってペッテが盛大な溜め息を吐いた。
「お嬢様、懸念するべき点はございますが、ここはシモン様が望まれるようにいたしましょう」
「し、しかしだな……」
「シモン様に望まれないままここに滞在し、殿下の護衛も蔑ろになさるおつもりでございますか?」
反論しかけたところをペッテに遮られ、畳み掛けられたことでホーリーは言葉を詰まらせた。
沈黙の中で苦しげに表情を変える。
「解ったのだ」
表情を曇らせながらもホーリーが頷いた。
この日、夜が深まっても俺はまんじりともできなかった。
ドアの向こうに人の気配をずっと感じていたのだ。
翌日。
昼前にホーリーとペッテは荷物を纏め、少し早めの昼食を三人で摂る。
その後片付けをペッテが終えると、ホーリーとペッテが並んで俺の前に立った。
「見送らないよ」
俺は言った。
「それがようございますね」
ペッテが答えた。
「また会う日を楽しみにしているのだ」
「俺もだ」
振り返り振り返りしながら居間を出るホーリーを俺は見詰めた。
幾許かの後、戸口が開いて閉じる音がした。
この家がもの凄く広く感じる。
そんな寂寥感を振り払うためにも俺は声に出して言う。
「明日から頑張るぞ!」
ただ、明日にまた同じ台詞を言わないためにも、今日の内に準備だけはしておこうか。
出発を控えた大型の客車がこの町一番の宿屋の前に停まっている。
九人は乗れるだろう客車を牽くのは輓竜の中でも大型の二頭だ。
「くれぐれも寄り道などなさらないようお帰りくださいませ」
「何度も言うでないわ! 大体、お主こそここに残るじゃと?」
宿屋の前、出発を控えた客車の窓から外に立つペッテにナイチアビーナは問い掛けた。
「こちらでの仕事が残されてございます」
まるで動かない表情からは、その真意が窺い知れない。
これに先立ってホーリーに膨れっ面をさせた時からそうなのだから、ここで揺るごう筈もない。
曰く、殿下をお送りするのも立派なお勤めでございます。
そのお勤めをメイドを同伴でなければできないなど、この小娘はいつまでお子様気分でいらっしゃるのでしょうか。
昨夕の食事の後でナイチアビーナとホーリーに抱き付かれて気持ち悪いくらいに喜んでいた人物とは思えない台詞だった。
残されていると言う仕事で考えられるのは俺の家に持ち込んだ荷物の処分だが、俺ならそのままで構わないし、ペッテから何も言われていない。
だからもっと別の何かだろう。
「額面通りには受け取れんが、まあいいじゃろう」
ペッテの真意をナイチアビーナも掴めないらしく、好きにさせることとしたようである。
「出発じゃ!」
御者台に座るガンツが竜の手綱を引き、客車が動き始める。
すると、今し方まで客車の窓から膨れっ面を覗かせていたホーリーが、表情をもの言いたげに変えて俺を見る。
しかし口惜しいかな、俺ができるのは小さく手を振ることだけだ。
開いて行く竜車との距離は不意に空いた心の隙間のそれのようであった。
竜車が町を出て木々に隠れて見えなくなるまで見送った後、俺達は帰宅した。
ペッテが最初にしたのはお茶汲みで、その後も特別何かを始めることもない。
何をしたいのかさっぱりだ。
俺はと言うと、そのお茶を飲みながら、そこはかとない寂しさを感じていた。
ホーリーのことばかりを思い出す。
「ペッテ、ホーリーに相応しくなるにはどうしたらいいんだろう?」
「シモン様がお望みでございましたら、その一端をお教えいたしましょう」
「本当に?」
「勿論でございます。
私からどのように切り出そうかと考えていたところでございます。
シモン様自らがお望みとは重畳にございます」
ペッテが口角を上げて答えた。
明らかにホーリーに向ける時とは違う上がり方だ。
嫌な怖気を感じた。
「では、早速レッスンと参りましょう」
「何の?」
問い返す声が震えた。
胸や手首に触れずとも鼓動が速くなっているのが自分で判る。
糸目で判然としないのに視線に射竦められる感覚。
ヘビに睨まれたカエルも斯くやであろうか。
「貴族の作法でございます。
お嬢様に相応しくあるには絶対的な条件でございます」
ペッテが更に口角を吊り上げ、ずずずいっと迫って来る。
「ちょうどお茶をお飲みでございます。
お茶の作法からにいたしましょう」
ぎゃああ。
ペッテの指導は厳しかった。
できなければ何度でもやり直させられる。
体罰も辞さじだ。
一方で身体を密着させての手取り足取り。
ホーリーとは違って全身が柔らかいため、少し触れられただけで色々な何かが鎌首を上げる。
しかしそうして邪念に囚われれば、人格を破壊せんばかりに容赦の無い叱責が待っている。
言い訳しようものなら更に厳しくなる。
邪念を抱いた罪悪感から有効な反論もできず、言われるがままだ。
そんな叱責を受ける内、途中で何が何だか判らなくなって、記憶も怪しくなった。
ある時、くしゃみをした自分に気付いたら、全裸だった。
訳が判らなかった。
混乱したままペッテに尋ねたら、何度繰り返しても挨拶が上手くできないので「全裸で反省なさいませ」と冗談で言ったら俺がその通りにしてしまったのだと言う。
全然記憶に無い。
ただそれ以降、少しだけペッテの指導が優しくなった。
そんなこんなで、ペッテが居残った理由が俺への指導のためかと思い始めた六日目の夜のこと。
「シモン様、ご確認でございますが、今はお嬢様を伴って召喚なさったままでございますね?」
「え? あ!」
今の今まで忘れていたが、ホーリーとダンジョン探索を続ける間に召喚を日課にしなくなっていた。
召喚する度、送還する度に俺もホーリーも全裸になるので無為な召喚は憚られたのだ。
ロベンスに会いに行ったあの日以来、召喚し直していない。
このままにしておこうものなら、不意の送還にホーリーを巻き込んでしまう。
かと言って、今となっては迂闊に送還もできない。
「どうしたら……」
「送還なさいませ」
「でも、ホーリーが今何処に居るのか判らないよね?」
「寄り道などなさらなければ、今日の午後にも王都にご到着なさっておいでですので、今頃は宿舎でございましょう」
それで寄り道をしないように念を押していたのか……。
最初からこうすると決めていたと思しきことにも驚きと疑問が有る。
「でも、どうして……」
「双方が未練たらたらなままお別れになっては、お嬢様の心に傷を残しかねないためでございます」
全てはホーリーのためだった。
そこは良い。
だが、未練とはどうしたことか。
「俺はホーリーが王都に帰るのに納得してるけど」
「ご自分ではお気づきではございませんでしたか? 何かと捨てられた子犬が縋り付くような目をなさってございました」
未練は確かに有った。
しかしそれが駄々漏れだとは思ってもみなかった。
「それでも、未練が有ったくらいでホーリーの心に傷は大袈裟なんじゃ?」
「シモン様の魔法のせいでございます」
ペッテがそう言った瞬間、空気が張り詰めた。
「以前、私はシモン様の魔法を『罪作り』と申したことがございます。
ここに至りましてはその理由をお話しなければなりません」
俺は黙って頷いた。
「シモン様の魔法は、いえ、恐らくは召喚魔法はでございますが、大袈裟に申しますと召喚する対象の心を縛るのでございます」
以前から仮説は立てられていたと言う。
召喚者は召喚対象を使役するのだから当然だ。
この時、召喚対象が賢ければ賢いほど召喚者に懐き、次回も同じ個体が召喚される傾向が強いのだとか。
「シモン様の魔法にご一緒した場合、シモン様への好意が募るのでございます。
個人差もございましょうが、私の場合でございますと、二度目にはシモン様がお求めならば肌を許しても良い心持ちとなってございました」
そんな魔法の影響と思われる心境の変化は時間の経過と共に薄れ、今はもう消えているらしい。
「『手遅れ』と申しましたのはお嬢様のことでございます。
心境の変化にお気づきでいらっしゃらなかったことから、一回毎の影響は小さいものだったと存じますが、幾度となく魔法にご一緒していらっしゃいますので、累積した影響は計り知れません。
そして今もシモン様の魔法の影響の中にいらっしゃいます」
「そ、それって……、ホーリーが俺に好意を示してくれるのは魔法の影響でしかない……?」
「いえ、元よりある程度の好意と覚悟が無ければご一緒できなかったでございましょう」
その根拠は、対象の知能が高いほど召喚を拒絶しやすいことだと言う。
知能が高くなるほど召喚された例が減る。
輓獣であっても知能が高い竜はめったに召喚されず、人が召喚された例が公式には確認されていない。
公式でない例が、俺自身、俺に伴ったホーリーとペッテ、メーアに召喚されたロベンスである。
ペッテの言う通りなら、メーアはロベンスしか人を召喚できず、ロベンスはメーアからしか召喚を受け付けないことになる。
しかし、そう言われても釈然としない。
好意の大半が魔法の影響、つまり幻だったかも知れないことに変わりないのだから。
「もっと前に送還して、ホーリーから魔法の影響が消えていた方がペッテにとっても良かったんじゃない?」
「この町に滞在する理由もございます。
この町には世界を左右しかねない方々がいらっしゃいますので」
「世界って、大袈裟な……」
「何を呑気になさいますか。
シモン様のことでございます。
他にもメーア様とロベンス様がそうでございます」
「俺!?」
「例えばでございますが、魔物の大群が発生したといたしましょう。
シモン様の召喚に伴ったお嬢様であれば最終的には無傷で全てを殲滅可能でございます。
ましてや、戦争ともなりませば、敵国にとっては悪夢以外の何ものでもないことでございましょう」
同様に、万が一にもメーアとロベンスが人の世界に叛旗を翻した場合、対抗できるのは俺と、俺と一緒に召喚されたホーリーくらいだとも言う。
逆も然りだが、俺に付いているのがホーリーであればその可能性が極めて低いとか。
出会って直ぐの頃に聞いた通りにホーリーの嫁入りが俺を除いて絶望的なことも判断の一つらしい。
ペッテの言うことは尤もだ。
でも……。
「考えすぎだよ」
メーアとロベンスがそんなことになるとは思えないし、俺に至っては過剰評価でしかない。
「左様でございますか」
ペッテの答えには何の抑揚も無い。
「いずれにいたしましても、送還はなさいませ」
「うん」
この機会に送還しなければ今後の俺の活動に障るのだから否やは無い。
いつもの場所に立ち、数回深呼吸して気持ちを静めてから呪文を唱える。
暗転、そして光が戻る。
目の前に現れたのは、目を白黒させた一糸纏わぬホーリーだ。
「ホーリー」
「シモン!? ペッテ!?」
「召喚したままだったろ?」
ホーリーは驚きを顔に浮かべ、それが静まるに連れて目に涙を浮かべる。
「寂しかったのだ! シモンもペッテも居なくて寂しかったのだ!」
不意に俺は身体を締め付けらた。
胸に押し付けられるのは柔らかい感触。
続けて唇が柔らかい感触で塞がれる。
何をされたのか理解するまで数秒を要し、その時にはもう脳が溶けたようにされるがままだ。
更には唇の隙間から柔らかいものが侵入して来る。
この時、俺はホーリーの身体に有る柔らかい部分を新たに知った。
そのまま求められるまま、本能のままに舌を絡め合う。
ところが、ガツンと頭に衝撃を受けた。
舌を噛んだ。
俺とホーリーはそれぞれに口を押さえて涙目だ。
「ひゃひをふゅふゅペッフェ、ひひゃをひゃんひゃひぇひゃひゃいひゃ」
「何をおっしゃっているのか判りません。
シモン様もその汚らわしいものを早々にお仕舞いください」
ペッテにてんこ盛りの威圧感で言われたために忽ちの内に子猫ちゃんとなった我が息子を光の速さで隠す。
無論、比喩だからそこまでの速さは無い。
一瞬前までは猛々しかったのだが、ホーリーのけしからんものが障害となってホーリーとの接触は避けられていた。
もし接触していたら理性など完全に吹き飛んでいたかも知れないので大変危険だ。
まさに一触即発の危機であったが、ペッテのお陰で冷静になれたのだった。
俺とホーリーは背中合わせになり、それぞれに散らばっていた服、ペッテが用意していた服を着る。
再度向き合った時、ホーリーは恥ずかしそうに顔を真っ赤にした。
今し方の痴態を思い出したらしい。
多分俺も真っ赤だ。
顔が熱い。
しかし、恥ずかしがっている場合ではない。
俺には言わなければならないことが有る。
「ホーリー、俺はホーリーが好きだ。
きっと世界で一番好きだ」
ホーリーが目を瞬かせる。
「だから、王都に帰ってくれ」
ホーリーの目が驚きに見開かれた。
「な! 何故だ!? どうしてそうなるのだ!?」
「今のままだと俺は俺を好きでいてくれるホーリーに甘えて、縋ってしまう。
ホーリーの気持ちが俺の魔法で歪められたものかも知れないのにだ」
「歪められてなどいるものか!」
俺は頭を振った。
「それでも、今の俺がホーリーに相応しくないのは間違いない。
だから、二年。
二年だ。
二年経って俺がホーリーに相応しくなれたら、その時にホーリーもまだ俺を好きでいてくれるなら、俺の方から交際を申し込みに行くよ」
「え……?」
「そこで『求婚する』と言えないところが頼りないのでございます」
ホーリーが困惑げに眉尻を下げ、ペッテがやれやれとばかりに頭を振った。
そんな反応に焦るのは俺だ。
「いや、だって、ほら……」
いよいよもってペッテが盛大な溜め息を吐いた。
「お嬢様、懸念するべき点はございますが、ここはシモン様が望まれるようにいたしましょう」
「し、しかしだな……」
「シモン様に望まれないままここに滞在し、殿下の護衛も蔑ろになさるおつもりでございますか?」
反論しかけたところをペッテに遮られ、畳み掛けられたことでホーリーは言葉を詰まらせた。
沈黙の中で苦しげに表情を変える。
「解ったのだ」
表情を曇らせながらもホーリーが頷いた。
この日、夜が深まっても俺はまんじりともできなかった。
ドアの向こうに人の気配をずっと感じていたのだ。
翌日。
昼前にホーリーとペッテは荷物を纏め、少し早めの昼食を三人で摂る。
その後片付けをペッテが終えると、ホーリーとペッテが並んで俺の前に立った。
「見送らないよ」
俺は言った。
「それがようございますね」
ペッテが答えた。
「また会う日を楽しみにしているのだ」
「俺もだ」
振り返り振り返りしながら居間を出るホーリーを俺は見詰めた。
幾許かの後、戸口が開いて閉じる音がした。
この家がもの凄く広く感じる。
そんな寂寥感を振り払うためにも俺は声に出して言う。
「明日から頑張るぞ!」
ただ、明日にまた同じ台詞を言わないためにも、今日の内に準備だけはしておこうか。
0
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説

【最強モブの努力無双】~ゲームで名前も登場しないようなモブに転生したオレ、一途な努力とゲーム知識で最強になる~
くーねるでぶる(戒め)
ファンタジー
アベル・ヴィアラットは、五歳の時、ベッドから転げ落ちてその拍子に前世の記憶を思い出した。
大人気ゲーム『ヒーローズ・ジャーニー』の世界に転生したアベルは、ゲームの知識を使って全男の子の憧れである“最強”になることを決意する。
そのために努力を続け、順調に強くなっていくアベル。
しかしこの世界にはゲームには無かった知識ばかり。
戦闘もただスキルをブッパすればいいだけのゲームとはまったく違っていた。
「面白いじゃん?」
アベルはめげることなく、辺境最強の父と優しい母に見守られてすくすくと成長していくのだった。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !
本条蒼依
ファンタジー
地球とは違う異世界シンアースでの物語。
主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。
その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。
そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。
主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。
ハーレム要素はしばらくありません。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!
HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。
跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。
「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」
最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!
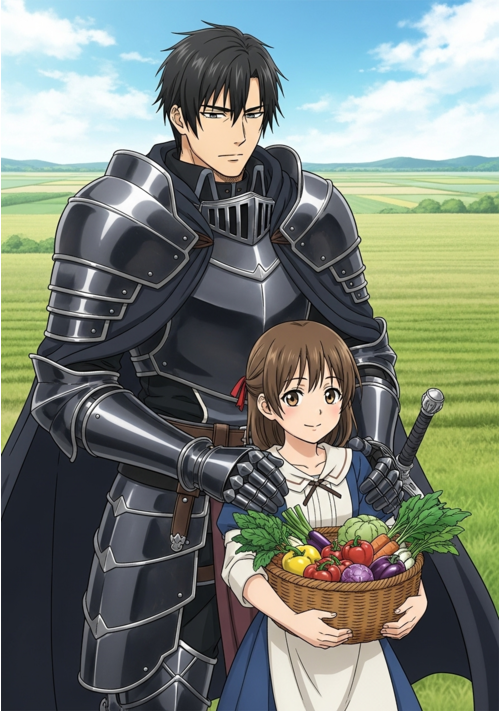
婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!
黒崎隼人
ファンタジー
「君は偽りの聖女だ」――。
地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。
しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。
これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。
王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~
名無し
ファンタジー
とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















