1 / 3
私は京子
しおりを挟む
小さなバーで、私の目を見つめてペドロは言った。
「京子、結婚しよう」
私は深くうなずいた。
その二年前、若かった私は、わずかばかりの貯金を手に、ファッションデザインの勉強がしたくて、ニューヨークへ来た。でも、生活は想像以上に厳しく、アルバイトに明け暮れた。そのアルバイト先の日本レストランで知り合ったのがペドロだ。ブラジル人の彼は、陽気で一緒にいるのが楽しかった。
ある時、彼が言った。
「京子、このままでは僕たちは二人とも勉強を続けられない。決めたんだ。僕が働く。貯金を合わせて京子は続けるべきだ。僕はもう建築の勉強はあきらめた」
私はガーンと胸を撃ち抜かれてしまった。
「なんでやねん。ありえへーん」
ニューヨークのダウンタウンで、私は関西弁で叫んでいた。手をつないだペドロは、大きなグレーの目を見開いたまま、つっ立っていた。
その日、結婚許可書をもらおうと出かけた私たちは、クローズされた区役所の前で震え上がった。数時間前、ライフルを持った男が発砲し、けが人も出たという。私は、決めていたのだ。結婚は私の誕生日の十二月十五日にと。しかたなく翌日、隣の区役所へ行った。そこでは何と、牧師さんまでいて結婚式も挙げることができ、結婚証明書を発行してもらった。でも、やはり誕生日の日付がほしかったのだ。
「あれがケチのつきはじめだったのよね。ライフル男め」
ペドロと口喧嘩するたびに、そう思う。
一年ほどのニューヨーク生活にピリオドを打ち、日本で暮らすことに決めた。その前に、ペドロの実家に挨拶してからと、ブラジルのベリホリゾンテに向かったのだ。空港を出ると、高層ビルが立ち並ぶ大都会に度肝を抜かれたが、ペドロの家は、そこからバスで何時間もかかった。
トウモロコシ畑が延々と続く中に建つ家に、たくさんの人が集まった。
「ペドロが子供を誘拐してきた!」
そう大騒ぎになり、ペドロは汗だくになりながら、『結婚証明書』を見せてまわった。豊満な女性が魅力的という土地柄で、ガリガリの私は、子供にしか見えなかったそうだ。やっと誘拐ではないことが分かると、みんなが私を抱きしめ、お祝いを口々に言った。ポルトガル語が全く分からない私は、
「オブリガーダ」「オブリガーダ」
ただにこにこと、そう繰り返していた。ご両親も、十人もいる兄弟も、誰が誰なのか分からなかったけれど、親戚が多いことだけは確かだった。
その中でも、ゴッドマザーは特別な存在で、パブロの留学の旅費を出したのも彼女だったし、今もこの集まりの中心だった。笑顔いっぱいの彼女にギュッと抱きしめられると、体中がほんわかした。
あれから十五年、あの家をまだ訪れていない。今、日本に帰ってきて、実家の近くの小さな家で暮らしている。双子の女の子を授かったことが何よりもうれしい。
ペドロは英語塾の講師、私は、パートで、ファッションデザインの仕事についている。折に触れてニューヨークのこと、ベリホリゾンテのことを懐かしく思い浮かべている。
つづく
「京子、結婚しよう」
私は深くうなずいた。
その二年前、若かった私は、わずかばかりの貯金を手に、ファッションデザインの勉強がしたくて、ニューヨークへ来た。でも、生活は想像以上に厳しく、アルバイトに明け暮れた。そのアルバイト先の日本レストランで知り合ったのがペドロだ。ブラジル人の彼は、陽気で一緒にいるのが楽しかった。
ある時、彼が言った。
「京子、このままでは僕たちは二人とも勉強を続けられない。決めたんだ。僕が働く。貯金を合わせて京子は続けるべきだ。僕はもう建築の勉強はあきらめた」
私はガーンと胸を撃ち抜かれてしまった。
「なんでやねん。ありえへーん」
ニューヨークのダウンタウンで、私は関西弁で叫んでいた。手をつないだペドロは、大きなグレーの目を見開いたまま、つっ立っていた。
その日、結婚許可書をもらおうと出かけた私たちは、クローズされた区役所の前で震え上がった。数時間前、ライフルを持った男が発砲し、けが人も出たという。私は、決めていたのだ。結婚は私の誕生日の十二月十五日にと。しかたなく翌日、隣の区役所へ行った。そこでは何と、牧師さんまでいて結婚式も挙げることができ、結婚証明書を発行してもらった。でも、やはり誕生日の日付がほしかったのだ。
「あれがケチのつきはじめだったのよね。ライフル男め」
ペドロと口喧嘩するたびに、そう思う。
一年ほどのニューヨーク生活にピリオドを打ち、日本で暮らすことに決めた。その前に、ペドロの実家に挨拶してからと、ブラジルのベリホリゾンテに向かったのだ。空港を出ると、高層ビルが立ち並ぶ大都会に度肝を抜かれたが、ペドロの家は、そこからバスで何時間もかかった。
トウモロコシ畑が延々と続く中に建つ家に、たくさんの人が集まった。
「ペドロが子供を誘拐してきた!」
そう大騒ぎになり、ペドロは汗だくになりながら、『結婚証明書』を見せてまわった。豊満な女性が魅力的という土地柄で、ガリガリの私は、子供にしか見えなかったそうだ。やっと誘拐ではないことが分かると、みんなが私を抱きしめ、お祝いを口々に言った。ポルトガル語が全く分からない私は、
「オブリガーダ」「オブリガーダ」
ただにこにこと、そう繰り返していた。ご両親も、十人もいる兄弟も、誰が誰なのか分からなかったけれど、親戚が多いことだけは確かだった。
その中でも、ゴッドマザーは特別な存在で、パブロの留学の旅費を出したのも彼女だったし、今もこの集まりの中心だった。笑顔いっぱいの彼女にギュッと抱きしめられると、体中がほんわかした。
あれから十五年、あの家をまだ訪れていない。今、日本に帰ってきて、実家の近くの小さな家で暮らしている。双子の女の子を授かったことが何よりもうれしい。
ペドロは英語塾の講師、私は、パートで、ファッションデザインの仕事についている。折に触れてニューヨークのこと、ベリホリゾンテのことを懐かしく思い浮かべている。
つづく
0
あなたにおすすめの小説
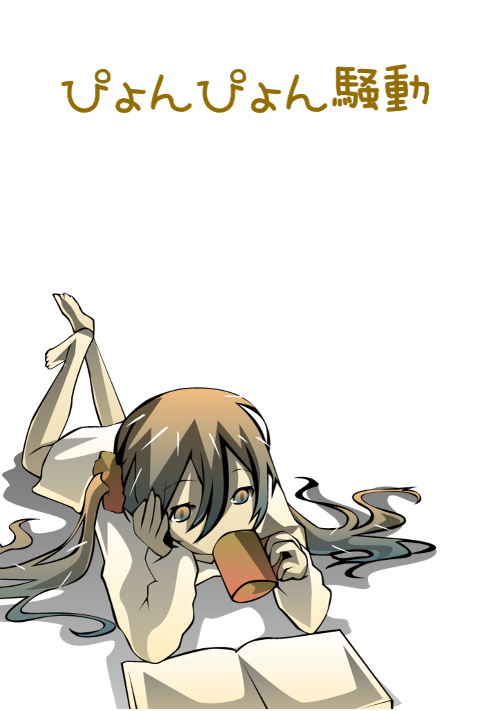
ぴょんぴょん騒動
はまだかよこ
児童書・童話
「ぴょんぴょん」という少女向け漫画雑誌がありました 1988年からわずか5年だけの短い命でした その「ぴょんぴょん」が大好きだった女の子のお話です ちょっと聞いてくださいませ

リヤカー、駆けぬける
はまだかよこ
児童書・童話
中学入学を控えていた、 あの春の日、 僕は急に母の田舎へ行った。 そこであったことを、なつかしく思い出すのだ。 リヤカーが駆けぬけたあの日の話を聞いて下さい。





悪女の死んだ国
神々廻
児童書・童話
ある日、民から恨まれていた悪女が死んだ。しかし、悪女がいなくなってからすぐに国は植民地になってしまった。実は悪女は民を1番に考えていた。
悪女は何を思い生きたのか。悪女は後世に何を残したのか.........
2話完結 1/14に2話の内容を増やしました

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















