1 / 1
執着系狼獣人が子犬のような伴侶をみつけると
しおりを挟む
男性が大半を占める狼獣人の里で、ロシェは珍しい女性の狼獣人だった。
小さい頃は周囲から子犬を可愛がるように大切にされるのがくすぐったかった。でも最近の周りの男の人は、ちょっと違う目でロシェを見る。
思春期のロシェは感覚でその変化に気づいて、元々の内向的な性格も手伝ってか、家にこもりがちな毎日を送っていた。
そんなロシェも、ある日海の向こうの王国から届いた荷車の列には興味津々だった。誰かが引っ越してくるのだろうかと、物陰からそろそろとみつめていた。
「ロシェ?」
声をかけられて、ロシェはすぐに家の中に隠れようとした。耳をぺたんと伏せて、慌てて踵を返そうとする。
「待って。噛んだりしないから」
でもそのひとはロシェに優しく言葉を続けて、その声音はロシェに記憶を呼び起こさせた。
「ジェイドだよ。小さい頃はよく遊んだだろう?」
ロシェが顔を上げたそこには、銀灰の髪と尻尾を持つ、背の高い青年が立っていた。獣の本性などどこにも見せない柔らかな物腰に、ロシェは警戒を解いた。
「……あ」
ジェイドはロシェより一回りほど年上で、まだ他愛ない子どもだったロシェにも優しく、たくさん遊んでくれた狼獣人だった。
ロシェは慌てて頭を下げて言う。
「ご、ごめんなさい。異性の獣人と話すのは久しぶりなんです」
ロシェはぷるぷると耳を震わせると、忙しなく尻尾で地面に丸をかく。
ロシェは亜麻色の髪と尻尾で、肌もすぐに赤くなってしまうほど弱い。狼というよりは子犬に近い風貌をしている。
それでいてロシェは鮮やかな赤茶色の瞳をしていて、ジェイドは目を細めて彼女の目をのぞきこんだ。
「だろうね。……そういう約束だったから」
ロシェはふっと息を止めてしまった。ジェイドの瞳が、雨の日の夕暮れのような色を帯びた気がした。
でもそれはロシェの気のせいだったようで、ジェイドはゆっくりとほほえんで、優しく言った。
「お父さんとお母さんにあいさつさせてくれる?」
彼の住む海の向こうの人間の国はいろんな複雑なことがある。昔、人間と狼獣人は戦争した過去もあって、彼のように宰相を務める狼獣人はとても珍しい。
ジェイドは里の商いを担っているロシェの両親と、長く貿易交渉をしていた。
自分のような子どもとは住む世界が違うのだ。彼に淡い憧れを持っても叶わないと思って、ロシェは苦笑して家の戸に向かった。
戸を開けた先にいた両親は、ロシェを見ていつものようにおかえりと言おうとして、その先に続いたジェイドに表情を強張らせた。
お父さん、お母さん、どうしたの。ロシェがそうたずねようとしたとき、先にジェイドが口を開く。
「約束通り、お迎えに上がりましたよ。もう俺は十二分に待った」
ジェイドの口の端の牙が光ったように見えた。彼が今まで見せることのなかった、野生の映る瞳とともに、ロシェには怖いように感じた。
「財は存分に贈りましょう。引き換えに、ロシェはいただいていきます」
ロシェの背後で閉ざされた扉の音が、殊更ロシェの耳に大きく響いた。
ロシェには両親と名残を惜しんでいる時間も少なかった。
「生活に必要なものはこちらですべて用意するよ。ロシェは身一つでいい」
ジェイドはロシェには優しく言ったものの、彼女の両親には脅しじみた結婚の申し込みをしていた。
ロシェが子どもの頃から、ジェイドと両親の間には約束があったらしい。里との商いを絶やさない代わりに、ロシェに異性を近づけないこととしていた。
ロシェはジェイドが初めて怖いと思った。小さい頃の優しい彼が違う人になったような気がして、せめて海の向こうに発つのを待ってもらえないかと頼んだ。
船着き場で船に乗るのをためらっているロシェに、ジェイドは手を差し伸べて問う。
「俺はロシェじゃないと嫌なんだ。ロシェは俺の事、嫌いか?」
「きらいじゃない……です。でも、結婚なんて、まだ」
「里の男たちはとっくにロシェをそういう目で見てるよ」
息を呑んだロシェに、ジェイドは優しくさとす。
「ロシェの柔らかいところを噛んで、味わおうと狙ってる。でも俺は絶対にロシェを乱暴に扱ったりしない。ロシェの嫌がることはしないと約束する」
ロシェは里の男性獣人たちの野蛮さを耳にしたことがあった。時々人の世界から迷い込んだ女性を家に閉じ込めて、悲鳴が聞こえるようなことをしているのを知っていた。
ジェイドはいつもロシェを労わって、慈しんでくれた。その記憶をたどるようにして、ロシェはそろそろとジェイドを見上げる。
「ほんとに……しない?」
「ああ。大切にするから、ロシェも俺のことを選んでくれないか」
その問いにすぐに答えを出すのは難しかった。ロシェが口ごもると、ジェイドはひょいとロシェを横抱きにしてしまう。
「……俺が人の性を保てるうちに、俺を受け入れてほしいな」
ジェイドは苦い声音でつぶやくと、ロシェの額に口づけて体を離した。
航海の間、ジェイドはロシェと共に過ごすことを避けているようだった。けれど遠目にロシェをいつも見ていて、たまらなく甘い実を前に待っているように、苦々しい表情をしては踵を返していた。
二十日間の航海の後、ロシェとジェイドを乗せた船は人間の国の港に到着した。ロシェはベールとふくらんだスカートで耳と尻尾を隠されて降りると、獣人と悟られないようにすぐに馬車の中に導かれた。
そこでもジェイドとロシェは別々の馬車で、ロシェは少し寂しいように感じていた。
獣人が心に決めた伴侶以外と子を成すことは決してないが、人の世界には愛妾というひとたちがいて、男性は伴侶以外の女性に子を産ませることがあると聞く。ジェイドも人の世界で暮らすうちそういう習慣に慣れて、ロシェを愛妾の一人として屋敷に入れようとしているのかもしれないと思った。
「ここには、他に何人……私のような女性がいるんですか?」
だからようやくロシェが大きなお屋敷に到着し、ジェイドと再会したとき、ロシェはそう訊ねていた。
「え?」
「ジェイドさんが恥ずかしくないように、一生懸命いろんなことを覚えます。私、刺繍くらいしか得意なこと、ないですけど……あ」
言葉の途中で、ロシェはジェイドにきつく抱きしめられた。
荷物を下ろしたばかりで、まだ周囲には下男や侍女たちがいる。ロシェは慌てたが、ジェイドは手で下男たちに下がるように命じた。
ロシェの首筋に顔を埋めながら、ジェイドの速い呼吸が聞こえていた。ジェイドはロシェが苦しいくらいに背を腕で包んで、低くつぶやく。
「俺がロシェ以外と? ……はは。俺がここまでとこれまでの人生、どれほど我慢してきたか、知らないんだ?」
気が付けばジェイドの体はひどく熱くて、体を離したジェイドの瞳は雨上がりの夕暮れのように濡れていた。
ロシェはその瞳に、ぞくっとするような色を感じた。それは獣性の色だと、聞いただけの噂が実感となって迫ってきた。
「知ってるね。獣人は一度伴侶と選んだら、死ぬまで伴侶を愛しぬく」
ジェイドはロシェを横抱きにすると、隣室に入って歩んでいく。
屋敷はジェイドの人柄を表すように、落ち着いた色調と精緻な刺繍が施された品のいい調度で満ちていた。
けれどその寝台だけは奇妙に広く、頑丈な柱が天井につながった、一種牢獄のような作りをしていた。
ジェイドはロシェの靴を脱がせると、その足に口づけて上目遣いに言う。
「しばらくはここから出さないよ。ロシェの中にたっぷり俺の匂いが染みついて、けだものが寄り付かないと安心できるまで」
扉が閉ざされる音で、ロシェははっと息を呑んだ。
ジェイドのまとう空気が、彼女の知る今までの穏やかなジェイドと真逆だと気づいたときには、ロシェは彼と二人きりになっていた。
ロシェはなぜかはわからないまま、寝台の上で不安を口にする。
「……ジェイド、さん?」
「今日この日を待ちわびていた。ロシェ、逃さないよ」
反射的に身を引いたロシェを、ジェイドはたやすく寝台に縫い留める。
ジェイドはロシェの顎をつかむと、唇を合わせる。それは初めてのロシェには混乱するくらいに激しいキスだった。ロシェの唇を食み、牙同士がこすれ合うくらいにロシェの口腔内を蹂躙する。
ようやく口を解放された頃、ロシェはジェイドの手によって着衣を解かれていた。室内はまだ夕暮れの残光が残っていて、ロシェは生まれたままの自分の体を抱いて隠そうとする。
ジェイドはたやすくロシェの手を外して、ロシェの裸体を愛おしそうに眺めて言う。
「食い破りたいくらい薄い皮膚、果物みたいな胸、まぁるいお尻……きれいだよ、ロシェ」
「や、見ないで……」
「じゃあ、こうしたら見えないかな」
ジェイドは寝台に身を横たえて、ロシェを自分の体の上に抱いた。
「あ、あう、や……いたずらしないで」
でもそれだけではなくて、ジェイドはロシェの乳首をつまんで転がしたり、お尻をやわやわと揉みしだく。
「……ひゃうっ」
ふいにロシェの体の中心にジェイドの指先が入り込んで、ロシェは悲鳴を上げる。
「だ、だめ。ジェイドさん、そこは」
「ここは?」
ロシェはジェイドの問いに、口ごもりながら言う。
「おしっこが……でちゃうとこだから」
ロシェが真っ赤になって幼い言葉を返すと、ジェイドは目を細めて言う。
「……知らないのか。かわいい子だ」
「あ、ひゃ、んんっ」
ジェイドは指を動かして、ロシェのそのくぼみをくりくりとなでる。
そうするとロシェのそこにはじんわりと滲んでくるものがあって、ロシェは恥ずかしさに隠れたいような思いになる。
「ここは道だよ。いずれロシェと俺の子どもが、何人も生まれてくるところ」
「子ど……も?」
「そのたびに、俺がいっぱいロシェに愛を注ぐところ」
ジェイドはくぼみの中で探るように指を動かして、ふいに小さな突起をつまむ。
「んぁぅっ」
ロシェは雷に打たれたように震えて、その正体がわからないまま声を上げた。
「や、わたし、変……」
「変じゃないよ。ロシェの気持ちいいところなんだ」
ジェイドに殊更そこをいじめられると、ロシェは身をよじって体にまとわりつく悦に震えた。尻尾はシーツの上で悩ましげに揺れて、亜麻色の髪からのぞく耳も忙しなく動いていた。
ロシェが上がった息を押さえようとジェイドの肩を甘噛みすると、ジェイドがお返しとばかりにロシェの耳を噛んだ。ぺろりと耳の中をなめられて、ロシェは声を殺せなくなる。
「は、離し……て。へん、なの……っ。嫌われ、ちゃう……っ」
「どうして? ロシェがとろけた分だけうれしい。俺の手、べたべたにして」
ジェイドはロシェのそこをくちゅくちゅと音を立てて乱すと、時にその手をフンフンと満足げに嗅ぐ。
「これがロシェの匂いなんだ。たまんない。ロシェの甘い蜜、もっと味合わせて」
「や、ぁっ」
ジェイドはふいに身を屈めて、ぴちゃぴちゃと音を立ててそこを舐め始めた。
ざらついた舌がロシェの敏感なところを激しく擦って、ロシェはけいれんを起こしたみたいに震える。
「ふ……あぅっ」
ロシェの目の前が真っ白になって、ロシェのその道から殊更蜜があふれたのを感じた。ジェイドはそれをざらついた舌で舐めとると、ごくんと喉を鳴らして飲み込む。
ロシェはとんでもないことをしてしまったと思って、慌ててジェイドに謝る。
「あ、あう。ご、ごめんなさいっ!」
ジェイドはからかうように笑っていたが、ロシェもそれがおしっこでないことは感じていた。でももっと恥ずかしいことをしてしまった自覚はあって、耳をぺたんと伏せる。
ジェイドは子犬のようなその反応に喉を鳴らして、ふいにロシェを組み敷いた。
「……可愛い。俺の伴侶はなんて可愛いんだろ。他の男になんて見られたら……やっぱり子どもができるまでは鎖でつないでおこうかな」
ジェイドはぞっとするようなことを言って、ロシェの下腹部に何か大きなものを押し当てた。
「ロシェ。……ロシェ。三日はつながったまま過ごそうね」
ズブ……っとロシェの中心に強烈な異物感が突き抜けて、ロシェは悲鳴を上げていた。
「あうっ……。痛……あぁうっ」
「ゆっくりするよ。大丈夫、力を抜いて……。ロシェ……奥で、俺を感じるんだ」
「ひゃぅ……ん、ぁう。抜い……て、あう」
ジェイドは宣言どおり奥の奥までゆっくりとロシェに自分を押し込めていく。
ロシェは額に汗をにじませて、浅い息を繰り返した。ジェイドはそんなロシェの頬やまなじり、あちこちにキスを落としながら、大丈夫、すぐ良くなると優しく緊張を解く。
「……ほら、ロシェ。ひとつになったよ」
やがてジェイドはロシェの最奥に自身でキスをすると、柔らかく笑ってロシェの頬をなでた。
ジェイドの瞳は今は鮮やかな金色に輝いていて、ロシェはその色にみとれた。体にももう痛みはなく、ジェイドとつながったところからしびれるような波が流れ込んでくる。
ふいにロシェの心が点滅するように動いて、ああ、そうだったんだと実感が迫って来る。
「……すき」
ロシェは胸に迫るその言葉を口にして、自ら腰をくゆらせ始めた。
「ジェイドさん……ゆるし、て。はしたないくらい、したいの……っ」
ロシェは獣人の本性を初めて自覚した。伴侶と交わって、その精を奥で浴びたい。その欲求のままに腰を振るロシェを、ジェイドは笑みを深めてみつめた。
「……愛してる」
ジェイドはうめくようにつぶやくと、狼獣人の本性のままに律動をはじめた。
「ロシェ、愛してる。いっぱい突いてあげようね。乾く間がないくらい注ぐから、俺の子を孕んで」
「あ……ぅ。うん、欲しい……。ジェイドさんとの赤ちゃん、欲しいの……」
ロシェも亜麻色の尻尾を振って、体を波打たせた。
水音と激しい律動、口づけの合間の呼吸が部屋に満ちていく。
伴侶となった獣人の交わりは甘く激しく、昼も夜も関係なく続く。
食事をしながら、湯舟に浸かりながらも二人は交わって、それは結局五日も続いたのだった。
小さい頃は周囲から子犬を可愛がるように大切にされるのがくすぐったかった。でも最近の周りの男の人は、ちょっと違う目でロシェを見る。
思春期のロシェは感覚でその変化に気づいて、元々の内向的な性格も手伝ってか、家にこもりがちな毎日を送っていた。
そんなロシェも、ある日海の向こうの王国から届いた荷車の列には興味津々だった。誰かが引っ越してくるのだろうかと、物陰からそろそろとみつめていた。
「ロシェ?」
声をかけられて、ロシェはすぐに家の中に隠れようとした。耳をぺたんと伏せて、慌てて踵を返そうとする。
「待って。噛んだりしないから」
でもそのひとはロシェに優しく言葉を続けて、その声音はロシェに記憶を呼び起こさせた。
「ジェイドだよ。小さい頃はよく遊んだだろう?」
ロシェが顔を上げたそこには、銀灰の髪と尻尾を持つ、背の高い青年が立っていた。獣の本性などどこにも見せない柔らかな物腰に、ロシェは警戒を解いた。
「……あ」
ジェイドはロシェより一回りほど年上で、まだ他愛ない子どもだったロシェにも優しく、たくさん遊んでくれた狼獣人だった。
ロシェは慌てて頭を下げて言う。
「ご、ごめんなさい。異性の獣人と話すのは久しぶりなんです」
ロシェはぷるぷると耳を震わせると、忙しなく尻尾で地面に丸をかく。
ロシェは亜麻色の髪と尻尾で、肌もすぐに赤くなってしまうほど弱い。狼というよりは子犬に近い風貌をしている。
それでいてロシェは鮮やかな赤茶色の瞳をしていて、ジェイドは目を細めて彼女の目をのぞきこんだ。
「だろうね。……そういう約束だったから」
ロシェはふっと息を止めてしまった。ジェイドの瞳が、雨の日の夕暮れのような色を帯びた気がした。
でもそれはロシェの気のせいだったようで、ジェイドはゆっくりとほほえんで、優しく言った。
「お父さんとお母さんにあいさつさせてくれる?」
彼の住む海の向こうの人間の国はいろんな複雑なことがある。昔、人間と狼獣人は戦争した過去もあって、彼のように宰相を務める狼獣人はとても珍しい。
ジェイドは里の商いを担っているロシェの両親と、長く貿易交渉をしていた。
自分のような子どもとは住む世界が違うのだ。彼に淡い憧れを持っても叶わないと思って、ロシェは苦笑して家の戸に向かった。
戸を開けた先にいた両親は、ロシェを見ていつものようにおかえりと言おうとして、その先に続いたジェイドに表情を強張らせた。
お父さん、お母さん、どうしたの。ロシェがそうたずねようとしたとき、先にジェイドが口を開く。
「約束通り、お迎えに上がりましたよ。もう俺は十二分に待った」
ジェイドの口の端の牙が光ったように見えた。彼が今まで見せることのなかった、野生の映る瞳とともに、ロシェには怖いように感じた。
「財は存分に贈りましょう。引き換えに、ロシェはいただいていきます」
ロシェの背後で閉ざされた扉の音が、殊更ロシェの耳に大きく響いた。
ロシェには両親と名残を惜しんでいる時間も少なかった。
「生活に必要なものはこちらですべて用意するよ。ロシェは身一つでいい」
ジェイドはロシェには優しく言ったものの、彼女の両親には脅しじみた結婚の申し込みをしていた。
ロシェが子どもの頃から、ジェイドと両親の間には約束があったらしい。里との商いを絶やさない代わりに、ロシェに異性を近づけないこととしていた。
ロシェはジェイドが初めて怖いと思った。小さい頃の優しい彼が違う人になったような気がして、せめて海の向こうに発つのを待ってもらえないかと頼んだ。
船着き場で船に乗るのをためらっているロシェに、ジェイドは手を差し伸べて問う。
「俺はロシェじゃないと嫌なんだ。ロシェは俺の事、嫌いか?」
「きらいじゃない……です。でも、結婚なんて、まだ」
「里の男たちはとっくにロシェをそういう目で見てるよ」
息を呑んだロシェに、ジェイドは優しくさとす。
「ロシェの柔らかいところを噛んで、味わおうと狙ってる。でも俺は絶対にロシェを乱暴に扱ったりしない。ロシェの嫌がることはしないと約束する」
ロシェは里の男性獣人たちの野蛮さを耳にしたことがあった。時々人の世界から迷い込んだ女性を家に閉じ込めて、悲鳴が聞こえるようなことをしているのを知っていた。
ジェイドはいつもロシェを労わって、慈しんでくれた。その記憶をたどるようにして、ロシェはそろそろとジェイドを見上げる。
「ほんとに……しない?」
「ああ。大切にするから、ロシェも俺のことを選んでくれないか」
その問いにすぐに答えを出すのは難しかった。ロシェが口ごもると、ジェイドはひょいとロシェを横抱きにしてしまう。
「……俺が人の性を保てるうちに、俺を受け入れてほしいな」
ジェイドは苦い声音でつぶやくと、ロシェの額に口づけて体を離した。
航海の間、ジェイドはロシェと共に過ごすことを避けているようだった。けれど遠目にロシェをいつも見ていて、たまらなく甘い実を前に待っているように、苦々しい表情をしては踵を返していた。
二十日間の航海の後、ロシェとジェイドを乗せた船は人間の国の港に到着した。ロシェはベールとふくらんだスカートで耳と尻尾を隠されて降りると、獣人と悟られないようにすぐに馬車の中に導かれた。
そこでもジェイドとロシェは別々の馬車で、ロシェは少し寂しいように感じていた。
獣人が心に決めた伴侶以外と子を成すことは決してないが、人の世界には愛妾というひとたちがいて、男性は伴侶以外の女性に子を産ませることがあると聞く。ジェイドも人の世界で暮らすうちそういう習慣に慣れて、ロシェを愛妾の一人として屋敷に入れようとしているのかもしれないと思った。
「ここには、他に何人……私のような女性がいるんですか?」
だからようやくロシェが大きなお屋敷に到着し、ジェイドと再会したとき、ロシェはそう訊ねていた。
「え?」
「ジェイドさんが恥ずかしくないように、一生懸命いろんなことを覚えます。私、刺繍くらいしか得意なこと、ないですけど……あ」
言葉の途中で、ロシェはジェイドにきつく抱きしめられた。
荷物を下ろしたばかりで、まだ周囲には下男や侍女たちがいる。ロシェは慌てたが、ジェイドは手で下男たちに下がるように命じた。
ロシェの首筋に顔を埋めながら、ジェイドの速い呼吸が聞こえていた。ジェイドはロシェが苦しいくらいに背を腕で包んで、低くつぶやく。
「俺がロシェ以外と? ……はは。俺がここまでとこれまでの人生、どれほど我慢してきたか、知らないんだ?」
気が付けばジェイドの体はひどく熱くて、体を離したジェイドの瞳は雨上がりの夕暮れのように濡れていた。
ロシェはその瞳に、ぞくっとするような色を感じた。それは獣性の色だと、聞いただけの噂が実感となって迫ってきた。
「知ってるね。獣人は一度伴侶と選んだら、死ぬまで伴侶を愛しぬく」
ジェイドはロシェを横抱きにすると、隣室に入って歩んでいく。
屋敷はジェイドの人柄を表すように、落ち着いた色調と精緻な刺繍が施された品のいい調度で満ちていた。
けれどその寝台だけは奇妙に広く、頑丈な柱が天井につながった、一種牢獄のような作りをしていた。
ジェイドはロシェの靴を脱がせると、その足に口づけて上目遣いに言う。
「しばらくはここから出さないよ。ロシェの中にたっぷり俺の匂いが染みついて、けだものが寄り付かないと安心できるまで」
扉が閉ざされる音で、ロシェははっと息を呑んだ。
ジェイドのまとう空気が、彼女の知る今までの穏やかなジェイドと真逆だと気づいたときには、ロシェは彼と二人きりになっていた。
ロシェはなぜかはわからないまま、寝台の上で不安を口にする。
「……ジェイド、さん?」
「今日この日を待ちわびていた。ロシェ、逃さないよ」
反射的に身を引いたロシェを、ジェイドはたやすく寝台に縫い留める。
ジェイドはロシェの顎をつかむと、唇を合わせる。それは初めてのロシェには混乱するくらいに激しいキスだった。ロシェの唇を食み、牙同士がこすれ合うくらいにロシェの口腔内を蹂躙する。
ようやく口を解放された頃、ロシェはジェイドの手によって着衣を解かれていた。室内はまだ夕暮れの残光が残っていて、ロシェは生まれたままの自分の体を抱いて隠そうとする。
ジェイドはたやすくロシェの手を外して、ロシェの裸体を愛おしそうに眺めて言う。
「食い破りたいくらい薄い皮膚、果物みたいな胸、まぁるいお尻……きれいだよ、ロシェ」
「や、見ないで……」
「じゃあ、こうしたら見えないかな」
ジェイドは寝台に身を横たえて、ロシェを自分の体の上に抱いた。
「あ、あう、や……いたずらしないで」
でもそれだけではなくて、ジェイドはロシェの乳首をつまんで転がしたり、お尻をやわやわと揉みしだく。
「……ひゃうっ」
ふいにロシェの体の中心にジェイドの指先が入り込んで、ロシェは悲鳴を上げる。
「だ、だめ。ジェイドさん、そこは」
「ここは?」
ロシェはジェイドの問いに、口ごもりながら言う。
「おしっこが……でちゃうとこだから」
ロシェが真っ赤になって幼い言葉を返すと、ジェイドは目を細めて言う。
「……知らないのか。かわいい子だ」
「あ、ひゃ、んんっ」
ジェイドは指を動かして、ロシェのそのくぼみをくりくりとなでる。
そうするとロシェのそこにはじんわりと滲んでくるものがあって、ロシェは恥ずかしさに隠れたいような思いになる。
「ここは道だよ。いずれロシェと俺の子どもが、何人も生まれてくるところ」
「子ど……も?」
「そのたびに、俺がいっぱいロシェに愛を注ぐところ」
ジェイドはくぼみの中で探るように指を動かして、ふいに小さな突起をつまむ。
「んぁぅっ」
ロシェは雷に打たれたように震えて、その正体がわからないまま声を上げた。
「や、わたし、変……」
「変じゃないよ。ロシェの気持ちいいところなんだ」
ジェイドに殊更そこをいじめられると、ロシェは身をよじって体にまとわりつく悦に震えた。尻尾はシーツの上で悩ましげに揺れて、亜麻色の髪からのぞく耳も忙しなく動いていた。
ロシェが上がった息を押さえようとジェイドの肩を甘噛みすると、ジェイドがお返しとばかりにロシェの耳を噛んだ。ぺろりと耳の中をなめられて、ロシェは声を殺せなくなる。
「は、離し……て。へん、なの……っ。嫌われ、ちゃう……っ」
「どうして? ロシェがとろけた分だけうれしい。俺の手、べたべたにして」
ジェイドはロシェのそこをくちゅくちゅと音を立てて乱すと、時にその手をフンフンと満足げに嗅ぐ。
「これがロシェの匂いなんだ。たまんない。ロシェの甘い蜜、もっと味合わせて」
「や、ぁっ」
ジェイドはふいに身を屈めて、ぴちゃぴちゃと音を立ててそこを舐め始めた。
ざらついた舌がロシェの敏感なところを激しく擦って、ロシェはけいれんを起こしたみたいに震える。
「ふ……あぅっ」
ロシェの目の前が真っ白になって、ロシェのその道から殊更蜜があふれたのを感じた。ジェイドはそれをざらついた舌で舐めとると、ごくんと喉を鳴らして飲み込む。
ロシェはとんでもないことをしてしまったと思って、慌ててジェイドに謝る。
「あ、あう。ご、ごめんなさいっ!」
ジェイドはからかうように笑っていたが、ロシェもそれがおしっこでないことは感じていた。でももっと恥ずかしいことをしてしまった自覚はあって、耳をぺたんと伏せる。
ジェイドは子犬のようなその反応に喉を鳴らして、ふいにロシェを組み敷いた。
「……可愛い。俺の伴侶はなんて可愛いんだろ。他の男になんて見られたら……やっぱり子どもができるまでは鎖でつないでおこうかな」
ジェイドはぞっとするようなことを言って、ロシェの下腹部に何か大きなものを押し当てた。
「ロシェ。……ロシェ。三日はつながったまま過ごそうね」
ズブ……っとロシェの中心に強烈な異物感が突き抜けて、ロシェは悲鳴を上げていた。
「あうっ……。痛……あぁうっ」
「ゆっくりするよ。大丈夫、力を抜いて……。ロシェ……奥で、俺を感じるんだ」
「ひゃぅ……ん、ぁう。抜い……て、あう」
ジェイドは宣言どおり奥の奥までゆっくりとロシェに自分を押し込めていく。
ロシェは額に汗をにじませて、浅い息を繰り返した。ジェイドはそんなロシェの頬やまなじり、あちこちにキスを落としながら、大丈夫、すぐ良くなると優しく緊張を解く。
「……ほら、ロシェ。ひとつになったよ」
やがてジェイドはロシェの最奥に自身でキスをすると、柔らかく笑ってロシェの頬をなでた。
ジェイドの瞳は今は鮮やかな金色に輝いていて、ロシェはその色にみとれた。体にももう痛みはなく、ジェイドとつながったところからしびれるような波が流れ込んでくる。
ふいにロシェの心が点滅するように動いて、ああ、そうだったんだと実感が迫って来る。
「……すき」
ロシェは胸に迫るその言葉を口にして、自ら腰をくゆらせ始めた。
「ジェイドさん……ゆるし、て。はしたないくらい、したいの……っ」
ロシェは獣人の本性を初めて自覚した。伴侶と交わって、その精を奥で浴びたい。その欲求のままに腰を振るロシェを、ジェイドは笑みを深めてみつめた。
「……愛してる」
ジェイドはうめくようにつぶやくと、狼獣人の本性のままに律動をはじめた。
「ロシェ、愛してる。いっぱい突いてあげようね。乾く間がないくらい注ぐから、俺の子を孕んで」
「あ……ぅ。うん、欲しい……。ジェイドさんとの赤ちゃん、欲しいの……」
ロシェも亜麻色の尻尾を振って、体を波打たせた。
水音と激しい律動、口づけの合間の呼吸が部屋に満ちていく。
伴侶となった獣人の交わりは甘く激しく、昼も夜も関係なく続く。
食事をしながら、湯舟に浸かりながらも二人は交わって、それは結局五日も続いたのだった。
27
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説





【ヤンデレ蛇神様に溺愛された貴方は そのまま囲われてしまいました】
一ノ瀬 瞬
恋愛
貴方が小さな頃から毎日通う神社の社には
陽の光に照らされて綺麗に輝く美しい鱗と髪を持つ
それはそれはとても美しい神様がおりました
これはそんな神様と
貴方のお話ー…

ヒョロガリ殿下を逞しく育てたのでお暇させていただきます!
冬見 六花
恋愛
突如自分がいる世界が前世で読んだ異世界恋愛小説の中だと気づいたエリシア。婚約者である王太子殿下と自分が死ぬ運命から逃れるため、ガリガリに痩せ細っている殿下に「逞しい体になるため鍛えてほしい」とお願いし、異世界から来る筋肉好きヒロインを迎える準備をして自分はお暇させてもらおうとするのだが……――――もちろん逃げられるわけがなかったお話。
【無自覚ヤンデレ煽りなヒロイン ✖️ ヒロインのためだけに体を鍛えたヒロイン絶対マンの腹黒ヒーロー】
ゆるゆるな世界設定です。
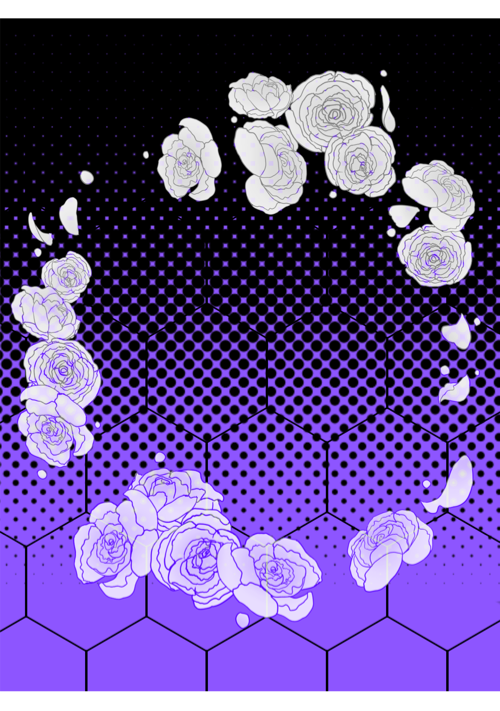
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?

ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















