93 / 144
想の章【紅い蝶に恋をした】
聖夜の宴会 其の二
しおりを挟む
部屋の外では既にクリスマスパーティーという名の宴会の準備が始まっているようだ。
妖怪の癖に朝から大はしゃぎでご苦労なことだねぇ、とそれらを横目に彼女は玄関から外へ出て急ぎ足で現世への門を目指す。
「よぉー、ベニコ! 今日もあいつんとこか?」
「おやおや? デートのお誘いだね? そうなんだね? 是非とも私にもお話を聞かせてほしいね! 恋文が必要なときはきちんと〝 れくちゃあ 〟するから教えてもらえるかな?」
通り過ぎざま、亡霊の魔女ペチュニアと文車妖妃のよもぎに出会い、彼女は苦笑をこぼす。
「必要になるときは永遠に来ないから安心してくれていいよ? やるなら紙切れに託すのではなくて、自分でやるだろうからねぇ。いや、ありえないけれど」
「むう、恋文に残すのは良いことなのだよ? 先の世にも語り継がれるのだから」
「語り継がれたりなんてしたらとんだ恥だよ…… 少なくともアタシはね。キミを否定するわけではないけれど、アタシはそういうの好きじゃないんだよ」
気まずくなる前にと足早に立ち去る。
終始仲の良い亡霊魔女と付喪神はその様子を微笑ましげに見送って互いに顔を合わせた。
長く退屈な生の中で、人外というものは刺激を求める。
それは他人の色恋沙汰でも同様のことなのだ。滅多にない〝 イベント 〟が喜劇に終わるか悲劇に終わるか。そんな予測を立てながら下世話に楽しむのが常である。
短い生を生き肉体を主体とした人間とは違い、人でないものは精神に重きを置いて生きる者達である。
人外にとっての〝 長い退屈 〟は致死毒にもなり得る恐ろしい概念なのだ。
「…… あれ、アルフォードさん…… が、2人?」
そうして門へ向かっている途中で、飛びながら樹木の飾り付けをする影が2つあることに気づく。
それも、その影はどちらも赤く長い髪を揺らし、頭上に突き出た大きなアホ毛がくるりと揺れるアルフォードのものである。
ただし、片方は本来のアルフォードよりもかなり小さい。
分霊でも出して協力して飾り付けているのだろうか…… と紅子が疑問に思って近づくとその会話が漏れ聴こえてくる。防音用の結界すら張られていないので、特に聞かれても困る内容ではないのだろう。
そう判断して聞き耳を立てると…… 小さいほうが随分と幼気な話し方をしているのが分かった。
「そっかぁ、お前が楽しくやってるみたいでよかったよ。いじめられでもしてたらオレが令一ちゃんを捌きに行くところだった」
「れーちゃんはそんなことしないからだいじょうぶだよ」
…… 捌く? いや、お兄さんの話なのか?
そう思って紅子が近づいていくとぱきりと小枝を踏み、一斉に2人の爬虫類のような黄色い瞳が向けられ、背筋を駆け抜けるような怖気に襲われた。
隠れたり足音を抑えて幽霊のように気配を消すことが得意な彼女ではあったが、今回ばかりは少し動揺していたらしい。
けれど、彼女はまるで動じていないというように振る舞いながら、いつもと同じように薄く笑みを浮かべて彼らに向かい合う。
「アルフォードさん、なにをしてるのかな? それと、そっちのアルフォードさんは…… ?」
一瞬の沈黙。しかし、彼らは相手が紅子だと分かると途端にその顔をふにゃりと笑みに変えて何事もなかったように 「なんだー、紅子ちゃんか! えっと、こっちの小さいオレのこと? 紅子ちゃんもいつも見てるはずだよ、分からない?」 と明るい声で応える。
「べにちゃん、わかんない? たしかに、いつもはあんまりかおをあわせたりしないかもだけど……」
そこまで言われて紅子は 「もしかして」 と呟く。
「赤竜刀…… リン、なのかな?」
「わー、すごい! だいせいかい! いつも、あるじちゃんがおせわになってまぁす!」
「リン…… ってキミの分霊だろう? なんでこんなに違うのかな」
困惑しつつも確認のために紅子がアルフォードに問うと、彼は 「名前をつけてもらったからだよ」 と非常に嬉しそうに答える。
「名前…… リン、だね。鱗だからリン、なんて聞いてるけれど…… そんな単純なものでもいいのかな?」
「そりゃあね! オレ達にとっては名前ってとても大事だからさ。元はオレの分霊。でも、今は赤竜刀になって名付けもされた。だから今のこの子は分霊としての意識と刀剣としての意識が半分ずつくらいなんだよね。ねー?」
「ねー?」
大きなアルフォードと小さなリンが目を合わせながら 「ねー?」 と言って笑い合う。まったく同じ顔のようで、少しだけ凛々しいような気もするリンは心底嬉しそうにしている。紅子も令一と仲良くしている姿を見ていたが、神の分け御霊のカケラとはいえ、ここまで慕っているとはと驚いた。
(…… 案外お兄さんってすごいのかねぇ)
神妖に好かれるのはその優しさ故か。
それとも、彼がどうしようもなく愚かで人間らしい傲慢さを持つからか。
…… 紅子には、神妖の言う 「愚かしく醜いからこそ愛おしい」 という感覚が理解できない。嫌いなものは嫌いだし、苦手なのだ。
「あ、でもオレのことはれーちゃんにはないしょにしてほしいんだよね!」
「ううんと、どうしてか聴いてもいいかな?」
身長120㎝程しかないリンが紅子を見上げる。口元に人差し指を立て、ご丁寧に 「しいー」 のポーズだ。その仕草のひとつひとつがどことなく幼いように見えるが、中身はアルフォードと同じ年齢のはずだ。刀剣のほうの意識に体が引っ張られているのかもしれない。
「だってさ、れーちゃんはオレがひとがたになれることしったら…… いままでみたいにかわいがってくれなくなっちゃうでしょ?」
少なくとも令一は人型になれることを知ったくらいで態度を変えたり邪険にするような人間ではない。
紅子が訝しんでいると、リンは 「ぺっとかんかくでさ、なでなでしてくれなくなっちゃわない?」 と弁解する。言い方が悪かったのだと思ったのだろうか。
思い返してみれば確かに、令一はリンのことを四六時中鞄の中に娯楽用品やおやつまで入れて連れ歩き、顎の下を撫で回したり頭をこちょこちょとくすぐったりと猫可愛がりしている。
その小さな小さなドラゴンが人型になれる上にアルフォードと同一の知識を持つ存在であることを自覚すれば、子供扱いやペット扱いはしなくなるのかもしれない。そういう意味であれば、確かに対応が変わってしまうだろう。
「べにちゃんはあるじちゃんにこのこと、いう?」
蛇が睨むような、そんな目をしなくとも当然そんなことはしない。
紅子は困ったように微笑みリンの頭に手を乗せる。
「言わないよ、誓ってね。アタシは嘘なんてつかないよ。知ってるだろう?」
「うん、 しってるよ! ありがと、べにちゃん!」
幼い笑顔に釣られて彼女もにっこりと笑みを浮かべる。
クールぶってる彼女も子供の笑顔には弱いのだ。
「っと、そうだ。アルフォードさん、今回の宴会って人間の参加はありなのかな」
「れーちゃんつれてきてくれるの!?」
「ありだよ。好きにしていい…… あ、そうだ。令一ちゃんって料理できるんだよね? なら、参加費ってことで令一ちゃんに料理かお菓子作ってきてもらってよ。紅子ちゃんはこっちのメンバーだからなくてもいいけど、夜まで時間はあるし…… ……ゆっくりしてきたらいいよ」
「下世話だよねぇ……」
嫌そうな顔をしながら言う紅子を見て 「ごめんごめん、でもほら…… 色恋沙汰は最高の娯楽だから」 とアルフォードが笑う。
他人の感情の浮き沈みを娯楽と言い切るところはやはり人外なのだなぁ、などと改めて認識して紅子は溜め息をついた。
これはさっさと退散したほうがいいらしい。ずっと会話を続けていたらもっと気疲れしそうだと歩みを再開する。
「それじゃあ、夜にまた来るよ」
「うんうん、またねー紅子ちゃん」
「あるじちゃんのてりょうり、ちゃんとさいそくしておいてね!」
「はいはい、伝えとくよ」
妖怪の癖に朝から大はしゃぎでご苦労なことだねぇ、とそれらを横目に彼女は玄関から外へ出て急ぎ足で現世への門を目指す。
「よぉー、ベニコ! 今日もあいつんとこか?」
「おやおや? デートのお誘いだね? そうなんだね? 是非とも私にもお話を聞かせてほしいね! 恋文が必要なときはきちんと〝 れくちゃあ 〟するから教えてもらえるかな?」
通り過ぎざま、亡霊の魔女ペチュニアと文車妖妃のよもぎに出会い、彼女は苦笑をこぼす。
「必要になるときは永遠に来ないから安心してくれていいよ? やるなら紙切れに託すのではなくて、自分でやるだろうからねぇ。いや、ありえないけれど」
「むう、恋文に残すのは良いことなのだよ? 先の世にも語り継がれるのだから」
「語り継がれたりなんてしたらとんだ恥だよ…… 少なくともアタシはね。キミを否定するわけではないけれど、アタシはそういうの好きじゃないんだよ」
気まずくなる前にと足早に立ち去る。
終始仲の良い亡霊魔女と付喪神はその様子を微笑ましげに見送って互いに顔を合わせた。
長く退屈な生の中で、人外というものは刺激を求める。
それは他人の色恋沙汰でも同様のことなのだ。滅多にない〝 イベント 〟が喜劇に終わるか悲劇に終わるか。そんな予測を立てながら下世話に楽しむのが常である。
短い生を生き肉体を主体とした人間とは違い、人でないものは精神に重きを置いて生きる者達である。
人外にとっての〝 長い退屈 〟は致死毒にもなり得る恐ろしい概念なのだ。
「…… あれ、アルフォードさん…… が、2人?」
そうして門へ向かっている途中で、飛びながら樹木の飾り付けをする影が2つあることに気づく。
それも、その影はどちらも赤く長い髪を揺らし、頭上に突き出た大きなアホ毛がくるりと揺れるアルフォードのものである。
ただし、片方は本来のアルフォードよりもかなり小さい。
分霊でも出して協力して飾り付けているのだろうか…… と紅子が疑問に思って近づくとその会話が漏れ聴こえてくる。防音用の結界すら張られていないので、特に聞かれても困る内容ではないのだろう。
そう判断して聞き耳を立てると…… 小さいほうが随分と幼気な話し方をしているのが分かった。
「そっかぁ、お前が楽しくやってるみたいでよかったよ。いじめられでもしてたらオレが令一ちゃんを捌きに行くところだった」
「れーちゃんはそんなことしないからだいじょうぶだよ」
…… 捌く? いや、お兄さんの話なのか?
そう思って紅子が近づいていくとぱきりと小枝を踏み、一斉に2人の爬虫類のような黄色い瞳が向けられ、背筋を駆け抜けるような怖気に襲われた。
隠れたり足音を抑えて幽霊のように気配を消すことが得意な彼女ではあったが、今回ばかりは少し動揺していたらしい。
けれど、彼女はまるで動じていないというように振る舞いながら、いつもと同じように薄く笑みを浮かべて彼らに向かい合う。
「アルフォードさん、なにをしてるのかな? それと、そっちのアルフォードさんは…… ?」
一瞬の沈黙。しかし、彼らは相手が紅子だと分かると途端にその顔をふにゃりと笑みに変えて何事もなかったように 「なんだー、紅子ちゃんか! えっと、こっちの小さいオレのこと? 紅子ちゃんもいつも見てるはずだよ、分からない?」 と明るい声で応える。
「べにちゃん、わかんない? たしかに、いつもはあんまりかおをあわせたりしないかもだけど……」
そこまで言われて紅子は 「もしかして」 と呟く。
「赤竜刀…… リン、なのかな?」
「わー、すごい! だいせいかい! いつも、あるじちゃんがおせわになってまぁす!」
「リン…… ってキミの分霊だろう? なんでこんなに違うのかな」
困惑しつつも確認のために紅子がアルフォードに問うと、彼は 「名前をつけてもらったからだよ」 と非常に嬉しそうに答える。
「名前…… リン、だね。鱗だからリン、なんて聞いてるけれど…… そんな単純なものでもいいのかな?」
「そりゃあね! オレ達にとっては名前ってとても大事だからさ。元はオレの分霊。でも、今は赤竜刀になって名付けもされた。だから今のこの子は分霊としての意識と刀剣としての意識が半分ずつくらいなんだよね。ねー?」
「ねー?」
大きなアルフォードと小さなリンが目を合わせながら 「ねー?」 と言って笑い合う。まったく同じ顔のようで、少しだけ凛々しいような気もするリンは心底嬉しそうにしている。紅子も令一と仲良くしている姿を見ていたが、神の分け御霊のカケラとはいえ、ここまで慕っているとはと驚いた。
(…… 案外お兄さんってすごいのかねぇ)
神妖に好かれるのはその優しさ故か。
それとも、彼がどうしようもなく愚かで人間らしい傲慢さを持つからか。
…… 紅子には、神妖の言う 「愚かしく醜いからこそ愛おしい」 という感覚が理解できない。嫌いなものは嫌いだし、苦手なのだ。
「あ、でもオレのことはれーちゃんにはないしょにしてほしいんだよね!」
「ううんと、どうしてか聴いてもいいかな?」
身長120㎝程しかないリンが紅子を見上げる。口元に人差し指を立て、ご丁寧に 「しいー」 のポーズだ。その仕草のひとつひとつがどことなく幼いように見えるが、中身はアルフォードと同じ年齢のはずだ。刀剣のほうの意識に体が引っ張られているのかもしれない。
「だってさ、れーちゃんはオレがひとがたになれることしったら…… いままでみたいにかわいがってくれなくなっちゃうでしょ?」
少なくとも令一は人型になれることを知ったくらいで態度を変えたり邪険にするような人間ではない。
紅子が訝しんでいると、リンは 「ぺっとかんかくでさ、なでなでしてくれなくなっちゃわない?」 と弁解する。言い方が悪かったのだと思ったのだろうか。
思い返してみれば確かに、令一はリンのことを四六時中鞄の中に娯楽用品やおやつまで入れて連れ歩き、顎の下を撫で回したり頭をこちょこちょとくすぐったりと猫可愛がりしている。
その小さな小さなドラゴンが人型になれる上にアルフォードと同一の知識を持つ存在であることを自覚すれば、子供扱いやペット扱いはしなくなるのかもしれない。そういう意味であれば、確かに対応が変わってしまうだろう。
「べにちゃんはあるじちゃんにこのこと、いう?」
蛇が睨むような、そんな目をしなくとも当然そんなことはしない。
紅子は困ったように微笑みリンの頭に手を乗せる。
「言わないよ、誓ってね。アタシは嘘なんてつかないよ。知ってるだろう?」
「うん、 しってるよ! ありがと、べにちゃん!」
幼い笑顔に釣られて彼女もにっこりと笑みを浮かべる。
クールぶってる彼女も子供の笑顔には弱いのだ。
「っと、そうだ。アルフォードさん、今回の宴会って人間の参加はありなのかな」
「れーちゃんつれてきてくれるの!?」
「ありだよ。好きにしていい…… あ、そうだ。令一ちゃんって料理できるんだよね? なら、参加費ってことで令一ちゃんに料理かお菓子作ってきてもらってよ。紅子ちゃんはこっちのメンバーだからなくてもいいけど、夜まで時間はあるし…… ……ゆっくりしてきたらいいよ」
「下世話だよねぇ……」
嫌そうな顔をしながら言う紅子を見て 「ごめんごめん、でもほら…… 色恋沙汰は最高の娯楽だから」 とアルフォードが笑う。
他人の感情の浮き沈みを娯楽と言い切るところはやはり人外なのだなぁ、などと改めて認識して紅子は溜め息をついた。
これはさっさと退散したほうがいいらしい。ずっと会話を続けていたらもっと気疲れしそうだと歩みを再開する。
「それじゃあ、夜にまた来るよ」
「うんうん、またねー紅子ちゃん」
「あるじちゃんのてりょうり、ちゃんとさいそくしておいてね!」
「はいはい、伝えとくよ」
0
あなたにおすすめの小説


帰国した王子の受難
ユウキ
恋愛
庶子である第二王子は、立場や情勢やら諸々を鑑みて早々に隣国へと無期限遊学に出た。そうして年月が経ち、そろそろ兄(第一王子)が立太子する頃かと、感慨深く想っていた頃に突然届いた帰還命令。
取り急ぎ舞い戻った祖国で見たのは、修羅場であった。

私を家から追い出した妹達は、これから後悔するようです
天宮有
恋愛
伯爵令嬢の私サフィラよりも、妹エイダの方が優秀だった。
それは全て私の力によるものだけど、そのことを知っているのにエイダは姉に迷惑していると言い広めていく。
婚約者のヴァン王子はエイダの発言を信じて、私は婚約破棄を言い渡されてしまう。
その後、エイダは私の力が必要ないと思い込んでいるようで、私を家から追い出す。
これから元家族やヴァンは後悔するけど、私には関係ありません。

おっさん料理人と押しかけ弟子達のまったり田舎ライフ
双葉 鳴
ファンタジー
真面目だけが取り柄の料理人、本宝治洋一。
彼は能力の低さから不当な労働を強いられていた。
そんな彼を救い出してくれたのが友人の藤本要。
洋一は要と一緒に現代ダンジョンで気ままなセカンドライフを始めたのだが……気がつけば森の中。
さっきまで一緒に居た要の行方も知れず、洋一は途方に暮れた……のも束の間。腹が減っては戦はできぬ。
持ち前のサバイバル能力で見敵必殺!
赤い毛皮の大きなクマを非常食に、洋一はいつもの要領で食事の準備を始めたのだった。
そこで見慣れぬ騎士姿の少女を助けたことから洋一は面倒ごとに巻き込まれていく事になる。
人々との出会い。
そして貴族や平民との格差社会。
ファンタジーな世界観に飛び交う魔法。
牙を剥く魔獣を美味しく料理して食べる男とその弟子達の田舎での生活。
うるさい権力者達とは争わず、田舎でのんびりとした時間を過ごしたい!
そんな人のための物語。
5/6_18:00完結!
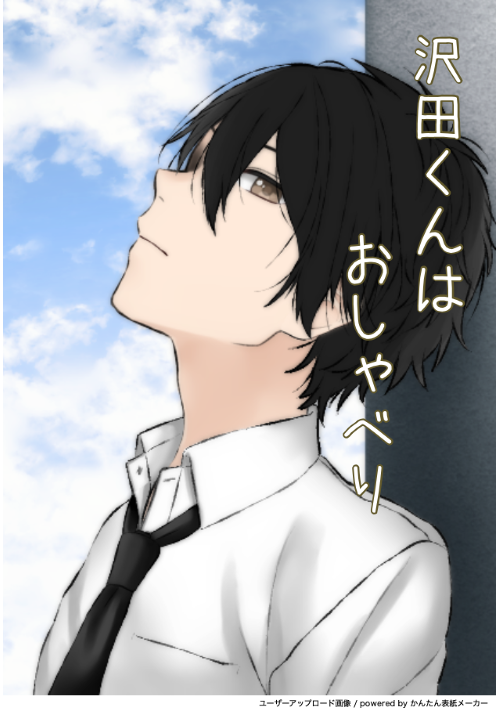
沢田くんはおしゃべり
ゆづ
青春
第13回ドリーム大賞奨励賞受賞✨ありがとうございました!!
【あらすじ】
空気を読む力が高まりすぎて、他人の心の声が聞こえるようになってしまった普通の女の子、佐藤景子。
友達から地味だのモブだの心の中で言いたい放題言われているのに言い返せない悔しさの日々の中、景子の唯一の癒しは隣の席の男子、沢田空の心の声だった。
【佐藤さん、マジ天使】(心の声)
無口でほとんどしゃべらない沢田くんの心の声が、まさかの愛と笑いを巻き起こす!
めちゃコミ女性向け漫画原作賞の優秀作品にノミネートされました✨
エブリスタでコメディートレンドランキング年間1位(ただし完結作品に限るッ!)
エブリスタ→https://estar.jp/novels/25774848

【完結】婚約者なんて眼中にありません
らんか
恋愛
あー、気が抜ける。
婚約者とのお茶会なのにときめかない……
私は若いお子様には興味ないんだってば。
やだ、あの騎士団長様、素敵! 確か、お子さんはもう成人してるし、奥様が亡くなってからずっと、独り身だったような?
大人の哀愁が滲み出ているわぁ。
それに強くて守ってもらえそう。
男はやっぱり包容力よね!
私も守ってもらいたいわぁ!
これは、そんな事を考えているおじ様好きの婚約者と、その婚約者を何とか振り向かせたい王子が奮闘する物語……
短めのお話です。
サクッと、読み終えてしまえます。

私と子供より、夫は幼馴染とその子供のほうが大切でした。
小野 まい
恋愛
結婚記念日のディナーに夫のオスカーは現れない。
「マリアが熱を出したらしい」
駆けつけた先で、オスカーがマリアと息子カイルと楽しげに食事をする姿を妻のエリザが目撃する。
「また裏切られた……」
いつも幼馴染を優先するオスカーに、エリザの不満は限界に達していた。
「あなたは家族よりも幼馴染のほうが大事なのね」
離婚する気持ちが固まっていく。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















