128 / 138
願わくは
10.
しおりを挟む
すったもんだありつつも皆ほぼ今まで通りの生活を続け(られ)ている。千晶は南極でスノーモービルに牽かれることも、東京湾に浮かぶこともなく。慎一郎もこの5年でそれなりの人選で脇を固めての蛮行だったのだから。彼もまたアラスカに送られることもなく、多摩川で泳ぐこともなく。
慎一郎側は金で解決させようとはしなかったし、千晶側もなぁなぁ穏便に済ませる態度はとらなかった。よくある解決策に走るならもっと早くに当人たち抜きで手打ちにしていただろう。
慎一郎は千晶に説明した以上のことは口にしなかった。千晶も子供のことに関しては黙秘を貫き、慎一郎もなにひとつ詫びることはなかった。
ラスカルズについてはなんの手続きもされていなかった。つまり選択肢は残されたままだ。
『あーあ、やっちゃった』『慎ちゃんが前科者でもあたしたち困らないしねー』『僕たちのことより、まずは二人が夫婦になれるか、そこがだいじでしょ』彼らはしれっと慎一郎らにのたまい、千晶にだけ舌を出してウインクしてみせた。
住まいも今まで通り、慎一郎がやってくる――帰宅する頻度が格段に増えただけ。千晶が帰京時の部屋探しを弟と友人に頼み、希望の学区に格安でペット可のルーフテラス付き2LDKが見つかったのは偶然だ。ただし、子供らは既に不登校気味である。
*
「おかえりー」
「ただいま」
インターフォンを押さずに玄関を開けたのに、待ち構えていたようにツインテールが壁から顔を覗かせる。以前はこんばんは、お疲れ様とやりとりしていた。小さな言葉の変化が慎一郎は嬉しい。
「ひよちゃん、ブラン ただいま」
床の上のベッドの老猫はもう出迎えず片目を開けるだけだ。そんな横着さも愛しいと膝をついて猫たちの頭を撫でる。そして部屋に漂うスパイスの香り。
「おかえりなさい、今日はキーマカレーです」
「ホワイトソースもつくったからーあたしとあこちゃんはドリアにするー。あとーおやつにシナモンロール焼いたの、小豆とレーズンと――」
「楽しみだ、先にお風呂入っちゃおうか」
毎週金曜日は鍋一杯にカレーやシチューを作りおき、週末を食べつなぐ。
あれは二人がまだ幼いころ、千晶が呼び出しを受けて三人で留守番をしていた。辛くないカレーを食べながらこういうのもいいねと他愛ない話をしていた。そこでつい口が滑った。
『アキはきみたちの父親についてなんて言ってるの?』
二人は顔を見合わせてから面倒くさそうに向き直り。
『そういうのはさぁ、おとなならわかってよ』
『シンちゃんには教えてあげるよ、あのね、耳かして。――なひとだって』
『……』
『シンちゃ、ひみつだからね。さんにんだけのひみつだよ、あこちゃんはオニババだからね。やつざきにされてシチューにされちゃうからね』
たまに会えればよかった、それだけで十分だと思ったのに。
『重たい荷物は一緒に持つと軽くなるよ、直ちゃんに渡すまでの間でしょ?』
千晶が慎一郎と直嗣のことを話したとは思えなかった。家のことも。子供らの言葉に、やっぱり欲が湧いてしまった。
シチューにされて食べられるなら本望だ。でも、まだ食べられるわけにはいかない。
千晶の手抜――合理的メニューも変わらない。サイドメニューは島民からの差し入れに代わり、宅配のミールキットと家庭菜園の成果が並ぶ。猫たちのスぺシャルは刺身からクリームへ。
「ただいまぁー、お腹空いたー」
「おかえりー、ちょうど焼けたよ」
遅れて帰ってきた千晶と共に皆で一日の出来事を振り返る――仕事も守秘義務に触れないことは報告し合う。そこへラスカルズが『ぼくらの考える最強』を突っ込んでくる、慎一郎にはそれがたのしい。たのもしい。
*
慎一郎の祖父が千晶に問うた。
「千晶さん、これでも可愛い孫でね」
「いいえ。殿方の許すってなかったことにしてしまうでしょう、二度と追及を許さない。私には無理です」
「では、どうする」
「さぁ、好きにしたらいいと思います。気が済むまでやったらいい。黙って受け入れたら未消化のままでずっと過ごすことになる。たとえ無駄な抗いでも、たどり着く先が同じでも」
問答はかみ合っていないようで通じている。譲歩も提案もない千晶の他人事な言い方を、慎一郎も他人事のように聞き、軽く肩を下げた。千晶の横に座る兄も他人事のように聞き流し、出された茶とどら焼きを妹のぶんのまで平らげる。
祖父も海千山千、こういう輩を交渉に引きずりだす手段は心得ている、が、そうしなかった。
「もう答えは出ていても、か」
「だからですよ」
最後の答えは千晶より先に慎一郎が口にした。
千晶の兄は満足そうに腹をさすり、馬鹿は死ぬまで治んねーと笑った。そっくりだな、直嗣は誰にも聞こえない位に小さくつぶやき、自分のどら焼きを半分にして無言で千晶に渡した。千晶はその白あんのどら焼きの断面をみつめてふっと微笑み、言った。
「そしていつか、あんなことはどうでもいいことだったと思える日がきたら、いいんじゃないですか」
祖父は孫とつれあいを見てふっと笑い、父親はしかめっ面のままにこりともしなかった。彼が蚊帳の外に置かれて拗ねているのは皆わかっている。素直になれない理由も。彼自身も千晶に対する態度が八つ当たりなのは自覚している、自分がまず誰と向き合うべきなのかも。
食べないのか――と訊くなり祖父は答えを待たずに息子のどら焼きを搔ってかぶりついた。息子は表情を変えなかったが、また血圧が上がったようだ。
慎一郎は自分のどら焼きを半分に割り、小さいほうを無言で父親に差し出した。
慎一郎側は金で解決させようとはしなかったし、千晶側もなぁなぁ穏便に済ませる態度はとらなかった。よくある解決策に走るならもっと早くに当人たち抜きで手打ちにしていただろう。
慎一郎は千晶に説明した以上のことは口にしなかった。千晶も子供のことに関しては黙秘を貫き、慎一郎もなにひとつ詫びることはなかった。
ラスカルズについてはなんの手続きもされていなかった。つまり選択肢は残されたままだ。
『あーあ、やっちゃった』『慎ちゃんが前科者でもあたしたち困らないしねー』『僕たちのことより、まずは二人が夫婦になれるか、そこがだいじでしょ』彼らはしれっと慎一郎らにのたまい、千晶にだけ舌を出してウインクしてみせた。
住まいも今まで通り、慎一郎がやってくる――帰宅する頻度が格段に増えただけ。千晶が帰京時の部屋探しを弟と友人に頼み、希望の学区に格安でペット可のルーフテラス付き2LDKが見つかったのは偶然だ。ただし、子供らは既に不登校気味である。
*
「おかえりー」
「ただいま」
インターフォンを押さずに玄関を開けたのに、待ち構えていたようにツインテールが壁から顔を覗かせる。以前はこんばんは、お疲れ様とやりとりしていた。小さな言葉の変化が慎一郎は嬉しい。
「ひよちゃん、ブラン ただいま」
床の上のベッドの老猫はもう出迎えず片目を開けるだけだ。そんな横着さも愛しいと膝をついて猫たちの頭を撫でる。そして部屋に漂うスパイスの香り。
「おかえりなさい、今日はキーマカレーです」
「ホワイトソースもつくったからーあたしとあこちゃんはドリアにするー。あとーおやつにシナモンロール焼いたの、小豆とレーズンと――」
「楽しみだ、先にお風呂入っちゃおうか」
毎週金曜日は鍋一杯にカレーやシチューを作りおき、週末を食べつなぐ。
あれは二人がまだ幼いころ、千晶が呼び出しを受けて三人で留守番をしていた。辛くないカレーを食べながらこういうのもいいねと他愛ない話をしていた。そこでつい口が滑った。
『アキはきみたちの父親についてなんて言ってるの?』
二人は顔を見合わせてから面倒くさそうに向き直り。
『そういうのはさぁ、おとなならわかってよ』
『シンちゃんには教えてあげるよ、あのね、耳かして。――なひとだって』
『……』
『シンちゃ、ひみつだからね。さんにんだけのひみつだよ、あこちゃんはオニババだからね。やつざきにされてシチューにされちゃうからね』
たまに会えればよかった、それだけで十分だと思ったのに。
『重たい荷物は一緒に持つと軽くなるよ、直ちゃんに渡すまでの間でしょ?』
千晶が慎一郎と直嗣のことを話したとは思えなかった。家のことも。子供らの言葉に、やっぱり欲が湧いてしまった。
シチューにされて食べられるなら本望だ。でも、まだ食べられるわけにはいかない。
千晶の手抜――合理的メニューも変わらない。サイドメニューは島民からの差し入れに代わり、宅配のミールキットと家庭菜園の成果が並ぶ。猫たちのスぺシャルは刺身からクリームへ。
「ただいまぁー、お腹空いたー」
「おかえりー、ちょうど焼けたよ」
遅れて帰ってきた千晶と共に皆で一日の出来事を振り返る――仕事も守秘義務に触れないことは報告し合う。そこへラスカルズが『ぼくらの考える最強』を突っ込んでくる、慎一郎にはそれがたのしい。たのもしい。
*
慎一郎の祖父が千晶に問うた。
「千晶さん、これでも可愛い孫でね」
「いいえ。殿方の許すってなかったことにしてしまうでしょう、二度と追及を許さない。私には無理です」
「では、どうする」
「さぁ、好きにしたらいいと思います。気が済むまでやったらいい。黙って受け入れたら未消化のままでずっと過ごすことになる。たとえ無駄な抗いでも、たどり着く先が同じでも」
問答はかみ合っていないようで通じている。譲歩も提案もない千晶の他人事な言い方を、慎一郎も他人事のように聞き、軽く肩を下げた。千晶の横に座る兄も他人事のように聞き流し、出された茶とどら焼きを妹のぶんのまで平らげる。
祖父も海千山千、こういう輩を交渉に引きずりだす手段は心得ている、が、そうしなかった。
「もう答えは出ていても、か」
「だからですよ」
最後の答えは千晶より先に慎一郎が口にした。
千晶の兄は満足そうに腹をさすり、馬鹿は死ぬまで治んねーと笑った。そっくりだな、直嗣は誰にも聞こえない位に小さくつぶやき、自分のどら焼きを半分にして無言で千晶に渡した。千晶はその白あんのどら焼きの断面をみつめてふっと微笑み、言った。
「そしていつか、あんなことはどうでもいいことだったと思える日がきたら、いいんじゃないですか」
祖父は孫とつれあいを見てふっと笑い、父親はしかめっ面のままにこりともしなかった。彼が蚊帳の外に置かれて拗ねているのは皆わかっている。素直になれない理由も。彼自身も千晶に対する態度が八つ当たりなのは自覚している、自分がまず誰と向き合うべきなのかも。
食べないのか――と訊くなり祖父は答えを待たずに息子のどら焼きを搔ってかぶりついた。息子は表情を変えなかったが、また血圧が上がったようだ。
慎一郎は自分のどら焼きを半分に割り、小さいほうを無言で父親に差し出した。
0
あなたにおすすめの小説

【R18】純粋無垢なプリンセスは、婚礼した冷徹と噂される美麗国王に三日三晩の初夜で蕩かされるほど溺愛される
奏音 美都
恋愛
数々の困難を乗り越えて、ようやく誓約の儀を交わしたグレートブルタン国のプリンセスであるルチアとシュタート王国、国王のクロード。
けれど、それぞれの執務に追われ、誓約の儀から二ヶ月経っても夫婦の時間を過ごせずにいた。
そんなある日、ルチアの元にクロードから別邸への招待状が届けられる。そこで三日三晩の甘い蕩かされるような初夜を過ごしながら、クロードの過去を知ることになる。
2人の出会いを描いた作品はこちら
「純粋無垢なプリンセスを野盗から助け出したのは、冷徹と噂される美麗国王でした」https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/443443630
2人の誓約の儀を描いた作品はこちら
「純粋無垢なプリンセスは、冷徹と噂される美麗国王と誓約の儀を結ぶ」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/183445041

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

人狼な幼妻は夫が変態で困り果てている
井中かわず
恋愛
古い魔法契約によって強制的に結ばれたマリアとシュヤンの14歳年の離れた夫婦。それでも、シュヤンはマリアを愛していた。
それはもう深く愛していた。
変質的、偏執的、なんとも形容しがたいほどの狂気の愛情を注ぐシュヤン。異常さを感じながらも、なんだかんだでシュヤンが好きなマリア。
これもひとつの夫婦愛の形…なのかもしれない。
全3章、1日1章更新、完結済
※特に物語と言う物語はありません
※オチもありません
※ただひたすら時系列に沿って変態したりイチャイチャしたりする話が続きます。
※主人公の1人(夫)が気持ち悪いです。

橘若頭と怖がり姫
真木
恋愛
八歳の希乃は、母を救うために極道・橘家の門を叩き、「大人になったら自分のすべてを差し出す」と約束する。
その言葉を受け取った橘家の若頭・司は、希乃を保護し、慈しみ、外界から遠ざけて育ててきた。
高校生になった希乃は、虚弱体質で寝込んでばかり。思いつめて、今まで養ってもらったお金を返そうと夜の街に向かうが、そこに司が現れて……。

俺様上司に今宵も激しく求められる。
美凪ましろ
恋愛
鉄面皮。無表情。一ミリも笑わない男。
蒔田一臣、あたしのひとつうえの上司。
ことあるごとに厳しくあたしを指導する、目の上のたんこぶみたいな男――だったはずが。
「おまえの顔、えっろい」
神様仏様どうしてあたしはこの男に今宵も激しく愛しこまれているのでしょう。
――2000年代初頭、IT系企業で懸命に働く新卒女子×厳しめの俺様男子との恋物語。
**2026.01.02start~2026.01.17end**
◆エブリスタ様にも掲載。人気沸騰中です!
https://estar.jp/novels/26513389

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
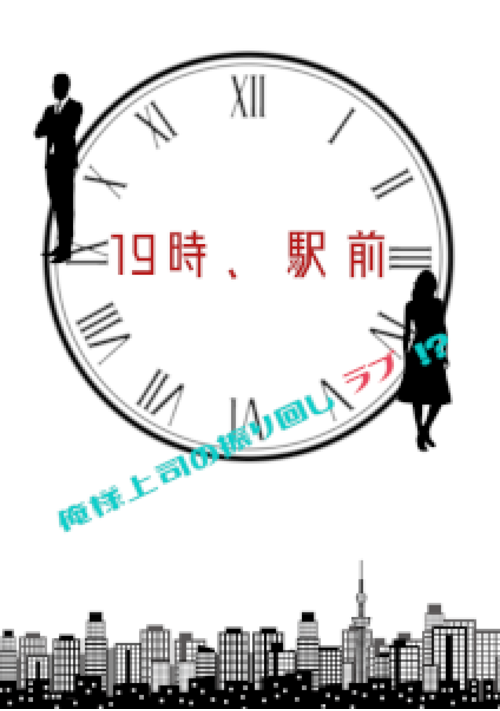
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?

出逢いがしらに恋をして 〜一目惚れした超イケメンが今日から上司になりました〜
泉南佳那
恋愛
高橋ひよりは25歳の会社員。
ある朝、遅刻寸前で乗った会社のエレベーターで見知らぬ男性とふたりになる。
モデルと見まごうほど超美形のその人は、その日、本社から移動してきた
ひよりの上司だった。
彼、宮沢ジュリアーノは29歳。日伊ハーフの気鋭のプロジェクト・マネージャー。
彼に一目惚れしたひよりだが、彼には本社重役の娘で会社で一番の美人、鈴木亜矢美の花婿候補との噂が……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















