133 / 138
徒然
父②
しおりを挟む
東京郊外、緑あふれる街の小さな邸宅。入母屋根の平屋をはさんで前庭は紅葉の盛り、奥庭は常緑樹と砂が陰影を深めている。
「本邸とはまた違った趣のお宅ですね」
「身の丈といいますか、私らの箱庭暮らしにはちょうどいい」
食後、蕎麦焼酎を蕎麦湯で割り楽しむ馨と次郎、慧一は庭をぐるりと歩いている。
この住まいは本邸から使用人が通って来る他は、次郎夫婦で手入れをして過ごしている。庭も年に数回庭師が茶飲みがてらダメ出しにくるだけ、夫婦でままごと遊びだと笑う。
「…禅など詳しくないんですが、来し方行く末でしたか」
「借景あってのものですよ」
庭の奥行は十メートルほど、侘びと瓦塀とその先の森の木々との対比が美しい。その隅に一本の柿の木が色を残している。
「さて、外界があって成り立つならもう箱庭とは呼べないか」
「箱庭から見る、箱庭を見る、ふむ、庭はどちらに開かれているのか」
次郎のつぶやきに、馨も独り言のように返す。あの森は公立公園で皆に開かれている。ここは客人のための間なのか、台所からは小さな菜園も見えた。外周にはセキュリティが掛かっていたが、立場上仕方ないだろう。
「慎一郎は慎一郎で何か考えはあるんでしょうが。あれはもう――78年前になりますか。彼がここへ尋ねてきましてね」
いつも縁側からひょっこりとアライグマのように顔を出すんですよ、と柿をひとつもいで縁側に腰掛けた息子を見ながら、次郎はそう切り出した。卒業したら日本に戻る予定が、そのままむこうで経験を積むことにしたと、事後承諾の挨拶だった。
「慎一郎さんから持って行ってと言われたんですよ」
「あの子ったら。ふふ、ここだけの話ですよ。昔ね――」
庭の隅では慎一郎の祖母と千晶の母とが熾きにくべた焼きいもの様子をみている。仕切り塀の向こう、彼女らの後ろが菜園だ。慧一は、母親たちを見ながら、耳だけを後ろに向ける。
「私は結婚はしない。そういう話は濁さず断ってくれ、後継は養子をとる、と」
千晶とは関係のない時期のはず、馨がやや首を傾げると、次郎も軽く頷いた。
実際の会話はもっと根回し的なやりとりだったのだが、あえて言ってきたことに意味がある。慎一郎の複雑な危うさは次郎も気づいていた。それまでもその手の話にはにべもなかったが、物分かりのいい孫のこと、いつかは係累を持つものだと思っていた。
「さも当然のようにいうものだから、こちらも『そうか』とにやりと笑ってやったら『違いますよ、向こうじゃ日本の男は相手にされない、よくご存じでしょう』とはぐらかしてきましてね」
慎一郎が父でなく祖父に言ってきたのは、藤堂は一世代空けて縁を結んできたからだ。いつからそう決まったのかは知らないが、次郎の時も決めたのは彼の祖父だった。父の計らいだったらどうなっていたか、親子でも女性に対する考えは違ったのだから。
一代目二代目は実直を絵にかいたような人物だった、三代目四代目はその反動か、人間らしさに忠実だった。四代目はあちこち手をだしては、息子の妻にまで粉を掛ける始末。同じ好色でも三代目は飄々とした艶福家で、次郎も祖父が好きだった。
どちらにせよ現代とは事情が違う、きちんと面倒はみたのだからよしとしよう。
「高遠さんも事業承継の難しさはご存じでしょう。そして日本は独特の身内意識がある」
「ええ」
系列にはたたき上げの責任者もいる。だが、そこから先の――この話題は朝までかかっても終わらないだろう、直系にはこだわってはいない、とだけ述べるに留めた。
「慧一の時も色々ありまして」次郎の声は聞こえたかどうか、慧一は誰とも目を合わせず、塀の向こうの森に頭を向けた。
馨も事情は知らないが、こういう人種はバランスを取るために難しい選択をするものだと理解している。
「そういう時代だった、というには私らの罪は大きい。高遠さん、慧一とは6っつ違いましたかな。年齢以上の隔世の感をお持ちでしょう。転換点はあった、気づいても止められない流れがある、今もです」
もしも、あの時と仮定しても仕方ない。過去は過去。馨は、妻らと慧一の背と次郎を見、頷いた。彼自身も、彼らもまた、色々あったのだ。
「この時世どう転ぶかわからない、いずれ気が変わることもあるだろう頷きました。そうして慎一郎が帰国し、こちらに挨拶にきて、その次でしたね。今日みたいに蕎麦を食べに来いと言ったら、蕎麦より細めのうどんにしてくれと。仕方なく見様見真似でうどんをね。これも奥が深い。
ほどなく慎一郎が直嗣とやって来ましたよ。それぞれ小さな子を抱えて。慎一郎は友人の子と遊んだ帰りだと、直嗣は兄さんの友人はだいぶお疲れなんだとね。それ以上何もいいませんでした、ええ。誰もね。
妻が喜んで。女の子はかわいいかわいいと」
次郎と、馨も庭で楽しそうな声のするほうを見やる。馨には次郎とさよの心の内はわからない。生と死はすぐ隣にある。
「私が調べなくてもあれこれ言ってくるものは多い、娘さんの名は何度か出てきました。しかしそれは昔の、慎一郎がまだ学生の時でしたかな、珍しい苗字だから覚えていましたが、驚きましたよ」
それから、何度か慎一郎と直嗣が友人の子供らの顔を見せに連れてきた。成長のはやいことはやいこと。
「慧一もいつ知ったのか、私には何も言ってきませんでしたがね。一度そこから覗いて、な」
「……」
息子が聞き耳を立てているのも次郎はお見通しだ。
慧一は渋々と言った態で父らに向かい直る。
「娘には会っていなかったと聞きましたが、目の前で倒れてみせる御仁はいなかったとかなんとか」
馨は疑問に思っていたことをひとつ。なんとか、の部分はインテリ眼鏡がアタッシュケースに札束詰めて――、せいぜいA4の茶封筒だろ、という千晶と弟の掛け合いだった。
「…そんなことをしたら留めを刺されかねんだろ」
「はは、娘からくれぐれも貴方(の血圧)を刺激しないようにと言われておりましてね。総領にまで何かあって恨まれるのは御免だそうですよ。息子さんは遠慮するなと言ってくれましたが」
次郎は、物調面と笑顔の二人に笑いながら頷く。
「ふっ、興味はありましたが慎一郎やあの子らの態度をみれば、不思議となぁ」
千晶と次郎夫婦とは礼状のやりとりが数回だけ。それで証人欄に署名するのもどうか、判断が甘すぎるのでは――。馨と慧一とが不安混じりに目を見合わせた。初めて意見の一致をみた瞬間である。
「今年の夏ですよ、初めて千晶さんにお会いしたのは」
双子らが夏休みでしばらく別荘に滞在するのに合わせ、千晶らも一緒にやってきた。祖父母とその友人が来ているとは知らず驚きはしたようだったが、孫の友人らしい態度ですぐに馴染んだ。島で飼い始めた犬はマンションより穴を掘れる実家の庭が、さらには駆け回れる別荘が気に入った。猫たちも探索を終えると昼寝をはじめていた。
「実際不思議な娘さんだったね――あなた方によく似ていて、こう私のほうが色々と話をしてしまった」
千晶は久しぶりのカレーに舌鼓をうち、祖父のあれやこれや――食べ物の思い出から初恋まで聞き出し、祖母や慎一郎も初耳だと笑い合っていた。祖父の苦手な食べ物はニシンで、キュウリのサンドウィッチが嫌いなのは慎一郎の父だ。
「他愛ない話だけで、妻は友人の姉を思い出したと言っていました。慎一郎は友人と紹介してきたので、届はまだ保留か断られたか、それも仕方ないと確認はせなんだ。翌月の為に余計なことを吹き込んで警戒されてもまずいじゃろとね」
そこは確認しろよ、と息子らはまた目を合わせる。祖母があの企みに加わっていたら、サプライズは成功していなかっただろう。
「『いい子がいるなら連れてこい』と言う機会がないままでしたな」
「私も言ってみたかった、『いい子じゃないか』と……それが」
息子は『父さん、会ってほしい人が居ます』とは終ぞ口にしてくれなかった。千晶とは『お義父さま、慎一郎さんは悪くないんです――』『君にお義父さんと呼ばれる筋合いはない』という喧嘩をやめてな場面を期待していたのに、あの態度だ。止める素振りさえみせなかった、誰も。そして今も『藤堂さん』だ。
「はは、どこのホームドラマですか。私も『君に娘はやらん』と言ってみたかったですよ『馨さん、そういうわけなんでよろしく』だそうで」
『よろしくじゃないでしょ』と千晶がお掃除スリッパで突っ込み、父はまた殴る機会を逃した。馨は慧一に笑って返すが、次郎は息子の言い草が情けなくてたまらない。
「お前は本当に…、俺はそんな意味で言ったんじゃない。そんなだから――」
「わかってる。わかってるんだ」
最後まで言わなくても分かっている、次郎の言葉を制し、馨に向き直った。
「私が謝罪すべきなんでしょうな、でも、あいつはそれを望まないでしょう」
「私も娘を止めませんでした」
どちらの父親も、万感の思いを口には出さなかった。その様子に祖父、次郎は眦を下げた。
***
数寄屋門の前には先にネイビーブルーの車が停まっていた。慎一郎と千晶の友人がその横に立っている。
千晶があとについて砂利敷きに車を止めると、前の車から誠仁が降りてきた。
「誠仁早かったねー」
「ちっ、勝ったのに嬉しくない」
「私は安全運転ですからー、いやー、V8は余裕の安定感ありますねー」
「だろ、アレはトルクがさぁ――」
慎一郎の愛車を運転してきたのは誠仁で、千晶は隣に弘樹を乗せ、誠仁の愛車を運転してきた。
慎一郎は三人でがやがやっているのを見て安心する。今日はちゃんと蕎麦を食べにこいという祖父からのしつこい誘いに応じた。
なかなかカオスな顔ぶれなのは、蕎麦なら行かないというラスカルズに、代わりに食べたい誠仁と、なら他の蕎麦好きにも声をかけた結果。千晶と誠仁(と祖父)からの集中砲火は回避されたと思いたい。慎一郎自身は蕎麦を好きでも嫌いでもない。
「帰り運転してみる?」
「いいんですか、うわー渋いお宅ですね」
「まだ新しいんだよ」
慎一郎は千晶の友人と右手の玄関ではなく、左手の竹垣へ足を向けた。残りの三人も続く。
「いいねー、俺もこういう家に住みたい」
「ねー。場所もいいよね、静かだし。ここなら水害の心配もないし」
慎一郎を除いてこの家にくるのは皆初めて、こじんまりとした古きよき日本家屋を懐かしむ。
「そっち?」
「ああ、いつもこっちから」
「ちょっと、それ。子供が真似するからやめてちょうだい」
千晶が留め石をまたいでいく慎一郎をとがめる。ラスカルズがいたら『外じゃちゃんとやってる』と千晶をなだめていただろう。(※進入禁止の意、関守り石)
「いいんだよ。ほら、爺さんも呼んでる」
「おお、来たな。ちょうどいい柿をもいでくれ」
「失礼しまーっす」
「ッっす。ご相伴」
弘樹と千晶は顔を見合わせたのち、breaking all the rules、つびなだーさい、と声をかけあって進んだ。
二人が遅れたのはジャンク屋に寄って車のCDを全部入れ替えておいたから。誠仁が気づくのは後日。
「本邸とはまた違った趣のお宅ですね」
「身の丈といいますか、私らの箱庭暮らしにはちょうどいい」
食後、蕎麦焼酎を蕎麦湯で割り楽しむ馨と次郎、慧一は庭をぐるりと歩いている。
この住まいは本邸から使用人が通って来る他は、次郎夫婦で手入れをして過ごしている。庭も年に数回庭師が茶飲みがてらダメ出しにくるだけ、夫婦でままごと遊びだと笑う。
「…禅など詳しくないんですが、来し方行く末でしたか」
「借景あってのものですよ」
庭の奥行は十メートルほど、侘びと瓦塀とその先の森の木々との対比が美しい。その隅に一本の柿の木が色を残している。
「さて、外界があって成り立つならもう箱庭とは呼べないか」
「箱庭から見る、箱庭を見る、ふむ、庭はどちらに開かれているのか」
次郎のつぶやきに、馨も独り言のように返す。あの森は公立公園で皆に開かれている。ここは客人のための間なのか、台所からは小さな菜園も見えた。外周にはセキュリティが掛かっていたが、立場上仕方ないだろう。
「慎一郎は慎一郎で何か考えはあるんでしょうが。あれはもう――78年前になりますか。彼がここへ尋ねてきましてね」
いつも縁側からひょっこりとアライグマのように顔を出すんですよ、と柿をひとつもいで縁側に腰掛けた息子を見ながら、次郎はそう切り出した。卒業したら日本に戻る予定が、そのままむこうで経験を積むことにしたと、事後承諾の挨拶だった。
「慎一郎さんから持って行ってと言われたんですよ」
「あの子ったら。ふふ、ここだけの話ですよ。昔ね――」
庭の隅では慎一郎の祖母と千晶の母とが熾きにくべた焼きいもの様子をみている。仕切り塀の向こう、彼女らの後ろが菜園だ。慧一は、母親たちを見ながら、耳だけを後ろに向ける。
「私は結婚はしない。そういう話は濁さず断ってくれ、後継は養子をとる、と」
千晶とは関係のない時期のはず、馨がやや首を傾げると、次郎も軽く頷いた。
実際の会話はもっと根回し的なやりとりだったのだが、あえて言ってきたことに意味がある。慎一郎の複雑な危うさは次郎も気づいていた。それまでもその手の話にはにべもなかったが、物分かりのいい孫のこと、いつかは係累を持つものだと思っていた。
「さも当然のようにいうものだから、こちらも『そうか』とにやりと笑ってやったら『違いますよ、向こうじゃ日本の男は相手にされない、よくご存じでしょう』とはぐらかしてきましてね」
慎一郎が父でなく祖父に言ってきたのは、藤堂は一世代空けて縁を結んできたからだ。いつからそう決まったのかは知らないが、次郎の時も決めたのは彼の祖父だった。父の計らいだったらどうなっていたか、親子でも女性に対する考えは違ったのだから。
一代目二代目は実直を絵にかいたような人物だった、三代目四代目はその反動か、人間らしさに忠実だった。四代目はあちこち手をだしては、息子の妻にまで粉を掛ける始末。同じ好色でも三代目は飄々とした艶福家で、次郎も祖父が好きだった。
どちらにせよ現代とは事情が違う、きちんと面倒はみたのだからよしとしよう。
「高遠さんも事業承継の難しさはご存じでしょう。そして日本は独特の身内意識がある」
「ええ」
系列にはたたき上げの責任者もいる。だが、そこから先の――この話題は朝までかかっても終わらないだろう、直系にはこだわってはいない、とだけ述べるに留めた。
「慧一の時も色々ありまして」次郎の声は聞こえたかどうか、慧一は誰とも目を合わせず、塀の向こうの森に頭を向けた。
馨も事情は知らないが、こういう人種はバランスを取るために難しい選択をするものだと理解している。
「そういう時代だった、というには私らの罪は大きい。高遠さん、慧一とは6っつ違いましたかな。年齢以上の隔世の感をお持ちでしょう。転換点はあった、気づいても止められない流れがある、今もです」
もしも、あの時と仮定しても仕方ない。過去は過去。馨は、妻らと慧一の背と次郎を見、頷いた。彼自身も、彼らもまた、色々あったのだ。
「この時世どう転ぶかわからない、いずれ気が変わることもあるだろう頷きました。そうして慎一郎が帰国し、こちらに挨拶にきて、その次でしたね。今日みたいに蕎麦を食べに来いと言ったら、蕎麦より細めのうどんにしてくれと。仕方なく見様見真似でうどんをね。これも奥が深い。
ほどなく慎一郎が直嗣とやって来ましたよ。それぞれ小さな子を抱えて。慎一郎は友人の子と遊んだ帰りだと、直嗣は兄さんの友人はだいぶお疲れなんだとね。それ以上何もいいませんでした、ええ。誰もね。
妻が喜んで。女の子はかわいいかわいいと」
次郎と、馨も庭で楽しそうな声のするほうを見やる。馨には次郎とさよの心の内はわからない。生と死はすぐ隣にある。
「私が調べなくてもあれこれ言ってくるものは多い、娘さんの名は何度か出てきました。しかしそれは昔の、慎一郎がまだ学生の時でしたかな、珍しい苗字だから覚えていましたが、驚きましたよ」
それから、何度か慎一郎と直嗣が友人の子供らの顔を見せに連れてきた。成長のはやいことはやいこと。
「慧一もいつ知ったのか、私には何も言ってきませんでしたがね。一度そこから覗いて、な」
「……」
息子が聞き耳を立てているのも次郎はお見通しだ。
慧一は渋々と言った態で父らに向かい直る。
「娘には会っていなかったと聞きましたが、目の前で倒れてみせる御仁はいなかったとかなんとか」
馨は疑問に思っていたことをひとつ。なんとか、の部分はインテリ眼鏡がアタッシュケースに札束詰めて――、せいぜいA4の茶封筒だろ、という千晶と弟の掛け合いだった。
「…そんなことをしたら留めを刺されかねんだろ」
「はは、娘からくれぐれも貴方(の血圧)を刺激しないようにと言われておりましてね。総領にまで何かあって恨まれるのは御免だそうですよ。息子さんは遠慮するなと言ってくれましたが」
次郎は、物調面と笑顔の二人に笑いながら頷く。
「ふっ、興味はありましたが慎一郎やあの子らの態度をみれば、不思議となぁ」
千晶と次郎夫婦とは礼状のやりとりが数回だけ。それで証人欄に署名するのもどうか、判断が甘すぎるのでは――。馨と慧一とが不安混じりに目を見合わせた。初めて意見の一致をみた瞬間である。
「今年の夏ですよ、初めて千晶さんにお会いしたのは」
双子らが夏休みでしばらく別荘に滞在するのに合わせ、千晶らも一緒にやってきた。祖父母とその友人が来ているとは知らず驚きはしたようだったが、孫の友人らしい態度ですぐに馴染んだ。島で飼い始めた犬はマンションより穴を掘れる実家の庭が、さらには駆け回れる別荘が気に入った。猫たちも探索を終えると昼寝をはじめていた。
「実際不思議な娘さんだったね――あなた方によく似ていて、こう私のほうが色々と話をしてしまった」
千晶は久しぶりのカレーに舌鼓をうち、祖父のあれやこれや――食べ物の思い出から初恋まで聞き出し、祖母や慎一郎も初耳だと笑い合っていた。祖父の苦手な食べ物はニシンで、キュウリのサンドウィッチが嫌いなのは慎一郎の父だ。
「他愛ない話だけで、妻は友人の姉を思い出したと言っていました。慎一郎は友人と紹介してきたので、届はまだ保留か断られたか、それも仕方ないと確認はせなんだ。翌月の為に余計なことを吹き込んで警戒されてもまずいじゃろとね」
そこは確認しろよ、と息子らはまた目を合わせる。祖母があの企みに加わっていたら、サプライズは成功していなかっただろう。
「『いい子がいるなら連れてこい』と言う機会がないままでしたな」
「私も言ってみたかった、『いい子じゃないか』と……それが」
息子は『父さん、会ってほしい人が居ます』とは終ぞ口にしてくれなかった。千晶とは『お義父さま、慎一郎さんは悪くないんです――』『君にお義父さんと呼ばれる筋合いはない』という喧嘩をやめてな場面を期待していたのに、あの態度だ。止める素振りさえみせなかった、誰も。そして今も『藤堂さん』だ。
「はは、どこのホームドラマですか。私も『君に娘はやらん』と言ってみたかったですよ『馨さん、そういうわけなんでよろしく』だそうで」
『よろしくじゃないでしょ』と千晶がお掃除スリッパで突っ込み、父はまた殴る機会を逃した。馨は慧一に笑って返すが、次郎は息子の言い草が情けなくてたまらない。
「お前は本当に…、俺はそんな意味で言ったんじゃない。そんなだから――」
「わかってる。わかってるんだ」
最後まで言わなくても分かっている、次郎の言葉を制し、馨に向き直った。
「私が謝罪すべきなんでしょうな、でも、あいつはそれを望まないでしょう」
「私も娘を止めませんでした」
どちらの父親も、万感の思いを口には出さなかった。その様子に祖父、次郎は眦を下げた。
***
数寄屋門の前には先にネイビーブルーの車が停まっていた。慎一郎と千晶の友人がその横に立っている。
千晶があとについて砂利敷きに車を止めると、前の車から誠仁が降りてきた。
「誠仁早かったねー」
「ちっ、勝ったのに嬉しくない」
「私は安全運転ですからー、いやー、V8は余裕の安定感ありますねー」
「だろ、アレはトルクがさぁ――」
慎一郎の愛車を運転してきたのは誠仁で、千晶は隣に弘樹を乗せ、誠仁の愛車を運転してきた。
慎一郎は三人でがやがやっているのを見て安心する。今日はちゃんと蕎麦を食べにこいという祖父からのしつこい誘いに応じた。
なかなかカオスな顔ぶれなのは、蕎麦なら行かないというラスカルズに、代わりに食べたい誠仁と、なら他の蕎麦好きにも声をかけた結果。千晶と誠仁(と祖父)からの集中砲火は回避されたと思いたい。慎一郎自身は蕎麦を好きでも嫌いでもない。
「帰り運転してみる?」
「いいんですか、うわー渋いお宅ですね」
「まだ新しいんだよ」
慎一郎は千晶の友人と右手の玄関ではなく、左手の竹垣へ足を向けた。残りの三人も続く。
「いいねー、俺もこういう家に住みたい」
「ねー。場所もいいよね、静かだし。ここなら水害の心配もないし」
慎一郎を除いてこの家にくるのは皆初めて、こじんまりとした古きよき日本家屋を懐かしむ。
「そっち?」
「ああ、いつもこっちから」
「ちょっと、それ。子供が真似するからやめてちょうだい」
千晶が留め石をまたいでいく慎一郎をとがめる。ラスカルズがいたら『外じゃちゃんとやってる』と千晶をなだめていただろう。(※進入禁止の意、関守り石)
「いいんだよ。ほら、爺さんも呼んでる」
「おお、来たな。ちょうどいい柿をもいでくれ」
「失礼しまーっす」
「ッっす。ご相伴」
弘樹と千晶は顔を見合わせたのち、breaking all the rules、つびなだーさい、と声をかけあって進んだ。
二人が遅れたのはジャンク屋に寄って車のCDを全部入れ替えておいたから。誠仁が気づくのは後日。
0
あなたにおすすめの小説

【R18】純粋無垢なプリンセスは、婚礼した冷徹と噂される美麗国王に三日三晩の初夜で蕩かされるほど溺愛される
奏音 美都
恋愛
数々の困難を乗り越えて、ようやく誓約の儀を交わしたグレートブルタン国のプリンセスであるルチアとシュタート王国、国王のクロード。
けれど、それぞれの執務に追われ、誓約の儀から二ヶ月経っても夫婦の時間を過ごせずにいた。
そんなある日、ルチアの元にクロードから別邸への招待状が届けられる。そこで三日三晩の甘い蕩かされるような初夜を過ごしながら、クロードの過去を知ることになる。
2人の出会いを描いた作品はこちら
「純粋無垢なプリンセスを野盗から助け出したのは、冷徹と噂される美麗国王でした」https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/443443630
2人の誓約の儀を描いた作品はこちら
「純粋無垢なプリンセスは、冷徹と噂される美麗国王と誓約の儀を結ぶ」
https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/183445041

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

人狼な幼妻は夫が変態で困り果てている
井中かわず
恋愛
古い魔法契約によって強制的に結ばれたマリアとシュヤンの14歳年の離れた夫婦。それでも、シュヤンはマリアを愛していた。
それはもう深く愛していた。
変質的、偏執的、なんとも形容しがたいほどの狂気の愛情を注ぐシュヤン。異常さを感じながらも、なんだかんだでシュヤンが好きなマリア。
これもひとつの夫婦愛の形…なのかもしれない。
全3章、1日1章更新、完結済
※特に物語と言う物語はありません
※オチもありません
※ただひたすら時系列に沿って変態したりイチャイチャしたりする話が続きます。
※主人公の1人(夫)が気持ち悪いです。

橘若頭と怖がり姫
真木
恋愛
八歳の希乃は、母を救うために極道・橘家の門を叩き、「大人になったら自分のすべてを差し出す」と約束する。
その言葉を受け取った橘家の若頭・司は、希乃を保護し、慈しみ、外界から遠ざけて育ててきた。
高校生になった希乃は、虚弱体質で寝込んでばかり。思いつめて、今まで養ってもらったお金を返そうと夜の街に向かうが、そこに司が現れて……。

俺様上司に今宵も激しく求められる。
美凪ましろ
恋愛
鉄面皮。無表情。一ミリも笑わない男。
蒔田一臣、あたしのひとつうえの上司。
ことあるごとに厳しくあたしを指導する、目の上のたんこぶみたいな男――だったはずが。
「おまえの顔、えっろい」
神様仏様どうしてあたしはこの男に今宵も激しく愛しこまれているのでしょう。
――2000年代初頭、IT系企業で懸命に働く新卒女子×厳しめの俺様男子との恋物語。
**2026.01.02start~2026.01.17end**
◆エブリスタ様にも掲載。人気沸騰中です!
https://estar.jp/novels/26513389

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

元恋人と、今日から同僚です
紗和木 りん
恋愛
女性向けライフスタイル誌・編集部で働く結城真帆(29)。
仕事一筋で生きてきた彼女の前に、ある日突然、五年前に別れた元恋人が現れた。
「今日から、この部署に配属になった」
そう告げたのは、穏やかで理性的な朝倉。
かつて、将来や価値観のすれ違いから別れた相手だ。
仕事として割り切ろうと距離を取る真帆だったが、過去の別れが誤解と説明不足によるものだったことが少しずつ見えてくる。
恋愛から逃げてきた女と、想いを言葉にできなかった男。
仕事も感情も投げ出さず、逃げずに選び直した先にあるのは「やり直し」ではなく……。
元恋人と同僚になった二人。
仕事から始まる新しい恋の物語。
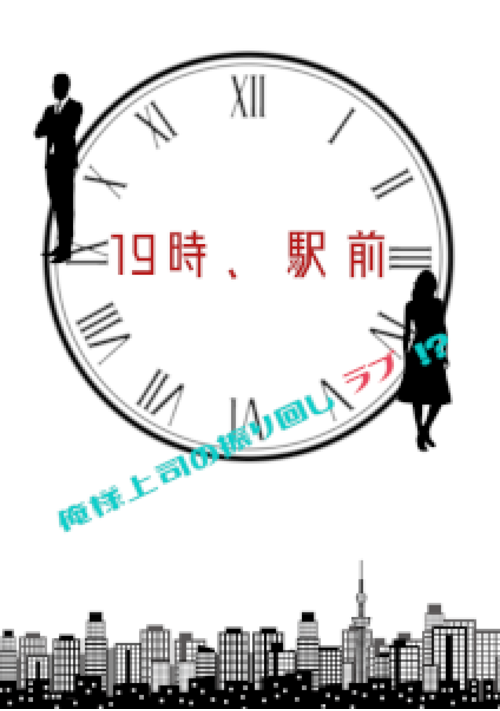
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















