3 / 80
1巻
1-3
しおりを挟む
――ようこそ、マスター。こちらは【リントヴルム市管理局】です。ご命令を入力してください。現在、市内の貯蔵魔力が不足しているため、機能が大幅に制限されております。
女性の澄んだ声と共に先ほどの石から光が出て、空中に不思議な映像が投影された。
【リントヴルム市運営状況】
管理人:レヴィン・エクエス
人口:3
都市ランク:F
実行可能なコマンド:【建造】【補修】【回収】
「うおっ、なんだ!?」
映像には、この都市の運営状況とやらが表示されていた。
一般的に魔力を用いて作動する道具を【魔導具】と呼ぶが、この石に使われている技術は、俺が知る魔導具よりずっと複雑そうだ。
「これを使えば、都市の管理ができるってことか? 便利な魔導具だな」
人口が3となっているのは、俺とエルフィ、そしてリントヴルムを指しているに違いない。
この都市ランクというのは、現在の都市の充実度を表しているのだろうか。あたりはすっかり瓦礫の山となっているし、先ほどリントヴルム自身も力が衰えていると言っていたからな。竜大陸を開拓していけば、ランクが上がっていくのかもしれない。
「もしかして、【建造】を選んだら家が建てられるのか?」
試しに、俺が「【建造】」と口にすると……
――現在【建造】できるものは以下の通りです。
【民家:小】【畑:小】
機能が制限されているからか、選択肢はかなり少ない。
だが、家自体は問題なく作れるようだ。ここ数日は、寝る場所にさえ困る有様だったし、雨風を凌げる家が手に入るだけでも大助かりだ。
俺は早速【民家:小】を選択する。
すると目の前に、家を象った蒼白い光の像が現れた。
「おっ、なんか出てきた。こうして建てる場所を選ぶんだな」
実体を持たない光の塊のようだが、俺が視線を動かすと、それに連動して光の家が動く。
エルフィが解説する。
「建てる場所を決めると、都市の魔力を消費してその映像の通りに家が建造される。そういう仕組み」
なるほど。原理はさっぱりだが、直感的な操作で建てる場所が決められるのはなかなか便利だ。
「エルフィはどこに建てたいんだ?」
あたりは瓦礫だらけで【建造】に適した場所は少ないみたいだが、俺はエルフィに希望を尋ねた。
「うーん、折角のママと私の新居。景色のいいところに大きい家を建てたい」
「って言ってもなあ……」
今作れるのは【民家:小】だ。
それに、景色のいい場所と言われても、瓦礫を撤去して都市を復興しないと難しいだろう。
「よし、ひとまず神樹の側に建てよう。ある程度都市を復興したら、また別のところに引っ越せばいいだろう」
俺は神樹の前に視線を動かし【建造】を実行した。近くには水場と、それなりに広い緑地もあるので、利便性も高いはずだ。
コマンドを実行すると、蒼い光がゆっくりと実体を伴い、丸太を積み重ねたログハウスへ変化していった。
「おお! 一体、どんな技術で作ってるんだ?」
もともと、都市にあったらしい金属製の建物と比べたら原始的な家だが、それでも立派なものだ。
しかし、魔法は数あれど、こうして家を一瞬で作るなど聞いたことがない。
古代の技術というのはとんでもないな。
「これがママと私の家……」
エルフィも目を輝かせながら、出来上がった家に見入っている。
【民家:小】とは言っていたが、二人で住むには十分な広さだ。
早速、俺たちは室内に入る。
「へぇ……居間に二人分の個室、ダイニングも完備かぁ……あれ? 俺の実家よりも広くないか?」
エクエス家には居間とダイニングルームの区別なんてなかったし、個室なんていう贅沢なものも当然なかった。一家五人が寝るための狭い寝室があるだけだ。
領地の経営が軌道に乗ったら、もっと広い家に住もうなんて話をよくしたが、まさかこんな形で念願の大きな家を手にするとは思いもよらなかった。
「キッチンもうちのより広くて、調理器具や石窯まである。これで生活には困らないな」
家を見て回り、これからの生活を想像するだけでにんまりとしてしまう。
「見て見て、ママ。ベッドふかふか」
「ああ、そうだな。俺の寝てた硬いベッドよりも上質だ」
布団の中には羽毛がぎっしりと詰まっており、カバーに丁寧な刺繍が施されている。
俺がこれまで使っていた木の板に藁を敷いただけのベッドよりも明らかに豪華で、今度は少し悲しくなってきた。
「どうしたの、ママ? 複雑そうな顔している。嫌だった?」
心配そうにエルフィが顔を覗き込んできた。そんなに深刻な話ではないので、俺は慌てて事情を明かす。
「実家よりも豪華だったから面食らっただけだよ。前はここよりも狭い場所に住んでいたから」
「嫌じゃないならよかった……でも、もっと大きくて綺麗な家が用意できればよかったのに。ママは酷い目に遭ったんだから、幸せになってほしい」
……なんて親思いな娘なのだろう。
最近は人の優しさに触れるどころか、理不尽な暴力に晒されるばかりだったので、エルフィの気遣いが身に染みる。
「気にしないでくれ。俺には十分すぎるほど立派な家だしな!」
実際、普通に暮らすにはかなり快適な家だ。
広さは十分だし、生活に必要な家具もある程度揃っている。
国を追われて一時はどうなることかと思ったが、こうして安心して過ごせる場所を手に入れられて本当によかった。
「ちなみに、もっと大きい家を作るには都市の魔力が足りてない。毎日、住人の魔力を少しずつもらっていく仕組みだから、もっと住む人を増やせればいいんだけど」
「住人から魔力を……税金代わりってことか」
そういう仕組みだとすると、俺とエルフィ、リントヴルムの三人しかいない現状では最低限の機能しか使えないのも当然だ。そうなると、今度はここに住んでくれる人を探す必要がある。
移住者の心当たりはなくもない。故郷のルミール村は、土地が痩せていて貧しい村だ。
この都市に移住できたら、みんなもっと快適に暮らせるかもしれない。
ぐぅ……
俺が今後のことを考えていると、大きな腹の音が鳴った。俺じゃないとなると……
「……ママ、お腹空いた」
我が娘は食べ盛りらしい。とはいえ、とっくに昼飯の時間は過ぎている頃だ。エルフィにつられて俺も空腹感を覚えてきた。
「食料はここで調達できるのか?」
「農業すればできるようになる。昔は町の外で野菜や動物を育てていた」
「でも、すぐに用意するとなると難しいよな」
【建造】で畑が作れても、すぐに収穫できるわけじゃない。地上で食料を確保する必要がある。
「って、よくよく考えたら、どうやって地上に戻ればいいんだ? 今はもう雲の上だし、エルフィも地上まで飛ぶのはキツくないか?」
「問題なし。何せ私は神竜族。ママを連れて地上まで飛ぶなんて余裕なのだ」
エルフィがVサインを見せて得意げにする。
さすが神竜族。飛行能力も並々ならぬものらしい。
「よし。それなら一度、地上に降ろしてもらえるか? 適当な村で食料を手に入れよう」
「任せて」
こうして、俺たちは再び地上へと降り立つのであった。
◆ ◆ ◆
俺たちがやってきたのは国境付近のシーリン村。
祖国エルウィン王国ではなく、隣国クローニア王国にある村だ。
たまたまリントヴルムがクローニアの上空を飛んでいたので、今回はシーリン村を選んだ。ここは敵国だが、いざとなったら空の上に逃げればいいわけだしな。
人目に付かないよう村の近くにこっそりと降り、そこから歩いてシーリンへ入った。
「これが持つ者と持たざる者の差か……」
大勢の人でごった返す市場を見て、俺はため息をつく。
我が故郷のルミール村もエルウィン側の国境付近に位置しているが、同じ国境付近の村であるシーリンの発展具合は段違いだった。
このあたりは肥沃な土壌が広がっているため農業が盛んで、ワインの名産地だ。おまけに、近くには金鉱山まであるため、牧歌的な雰囲気のルミール村よりもずっと賑やかだ。
うちの村もせめてもう少し土地が豊かであれば、どうにかなったのだろうけど……
「父さんたち、元気でやってるかなあ」
エルウィンのことはどうでもいいが、村のことは気がかりだった。
俺が聖獣を授からなかったせいで、国王から何か嫌がらせを受けていないだろうか?
同じ村出身のアリアが騎士団で活躍している以上、滅多なことにはなっていないはずだが心配だ。
「アリアも今頃どうしてるんだろうな」
彼女はもともと、戦いに向いた性格ではない。むしろ、おとなしくて引っ込み思案なタイプだったから、ひょっとしたら騎士団で苦労しているかもしれない。
「ママ……? なんだか悩んでるみたいだけど、大丈夫?」
俺の服の裾を引っ張り、エルフィが心配そうな表情を向けてきた。
「悪いな。急に国を追い出されたから、心残りがいろいろとあるんだ」
「アリアって、もしかしてママの恋人?」
「こ、恋人ってわけじゃない。大切な家族だよ」
そう。俺とアリアはそういった関係ではない。
だから、俺がアーガスとアリアの関係に口を出す筋合いはない。ないのだが……
――このワシ、国王ドルカスの名において、《聖獣使い》アーガス・アレス・アルベリヒと《神聖騎士》アリア・レムスの婚姻を認めよう。
ドルカスの宣言が頭をよぎる。
客観的に考えれば、アーガスは地位も実力もあり、アリアにふさわしい。
それは俺だって分かっている。彼女の幸せを考えれば、俺は祝福するべきだ。
だけど、どうしても割り切れない想いがあるのだ。
その時、どこからか呼び込みの声が聞こえてきた。
「おや、元気なさそうだね。サービスしてあげるから、うちで何か買っていかないかい?」
俺とエルフィが周囲を見回すと、屋台の中から背の高い褐色の肌の女性がこっちに手を振っていた。
店に並んでいる品を見るに、どうやら食料品店のようだ。
ちょうど食べ物を買いに来ていた俺たちは、彼女の陽気な声に導かれるように店へ向かう。
「やあやあ、お兄さん。私の名はメルセデス。メルセデス・アンソロだ。大陸中を旅しながら行商をしていてね。今はクローニアを中心に商売をしているんだ」
声の主……メルセデスさんは若く颯爽とした雰囲気の人で、爽やかな笑みを浮かべていた。
「お兄さん、旅人かい? 随分と軽装だね」
「いろいろとワケアリでして……食料を調達するためにシーリンに寄ったんです」
「ふーん。そっちで隠れてるのは、妹さんかい?」
気付いたら、エルフィが俺の背に隠れていた。
もしかして人見知りする性格なのだろうか。
俺はエルフィの頭を撫でながら、メルセデスさんに答える。
「そんなところです。お腹を空かせているので、美味しいものを食べさせてあげたいんです」
「なるほど、なるほど。そういうことならタイミングがよかった。カリン! ちょうどお客さんが来たみたいだよ」
「はい、はーい」
メルセデスさんが呼びかけると、透き通るような声と共に、浅黄色の髪をした落ち着いた雰囲気の女性がやってきた。その手にいっぱいの肉を抱えている。
「どうも、カリンと申します。ちょうど、搬入をしていたところでして。お肉をお求めですか?」
「食品全般を見たいらしいよ。妹さんがお腹を空かせてるから、美味しいものを食べさせたいんだってさ」
「まあ、仲がいいんですね。私にも弟のような幼馴染がいるから、お気持ちはよく分かります!」
「またまた、幼馴染ってだけじゃないだろう? あんな大英雄様の婚約者だなんて、羨ましいよ」
メルセデスさんがからかうように言って、カリンさんの肩を肘で突く。
「わ、私たち、まだそういう関係じゃ」
「まだ……ね。ということは、いずれはそういう関係になるつもりはあると」
「もう、メルセデス!」
カリンさんが顔を赤らめてメルセデスさんを責めた。
なんというか、平和な光景だなあ。
俺が二人のやり取りに和んでいると、カリンさんが話を切り替える。
「それよりも商売ですよ。お客さん、運がよかったですね。今は食料を手に入れるのが大変なんですよ」
ここは国境に近い場所ではあるものの、人口が多く交易もそれなりに行われているはず。
食料の入手が難しいなんて話は聞いたことがなかったが……
俺が首を傾げると、メルセデスさんが事情を説明する。
「まあ、突然の出来事だったしね。なんたってエルウィンが急に侵攻してきたんだから」
「えっ!?」
エルウィンがクローニアに侵攻?
以前から対立していた両国だが、ここ数年は小康状態だった。いつの間に事態が動いたのか。
カリンさんが頷く。
「商売にも影響出ていますし、何よりも村の農業は大打撃です」
農業に打撃……? 戦いが始まれば影響はあるだろうけど、今この村自体が攻められている様子はない。
何か別の事情があるのだろうか。
メルセデスさんが声を潜めて言う。
「ここだけの話だけど、エルウィンの兵士たちがこの近くの湖や川に毒を撒いたんだよ」
「なんですって?」
ここは農業が盛んな村だ。それを壊滅させれば、確かにクローニア王国に効率的に打撃を与えられるだろう。しかし、だからといって毒を流すなんて……
少し前まで王都にいたが、初めて聞く話だ。国民にさえ知らされず、侵攻が始まっていたとは。
俺は祖国の所業に内心で頭を抱える。
「そういうわけで、食料確保も大変な状況でね。私も村の支援のために、ここで営業してるのさ。ここでの売り上げは全額、村の復興に使うつもりだから景気よく頼むよ」
「そういうことでしたら」
幸い、俺はいくらか金貨を隠し持っていた。一人なら金貨一枚で一週間は食べていけることを思えば、当分の食費はまかなえる金額だ。
毒を流されては農業などまともにできないだろうし、同じ農村の出身として、せめて買って支援をしよう。
俺は保存の利く食品を中心に、およそ一ヶ月分の食料を買い漁る。
「お買い上げありがとうございます。こんなに買ってくれて、本当に助かります」
カリンさんが一礼した。
サービスで用意してくれた荷車に、ぎっしりと食材を積む。
さすがに多いかと心配したが、エルフィの力なら容易く運べるとのことだった。
「村の作物は完全にダメになって、毒で倒れた人もいるんだ。これからどうなるんだろうね」
心配そうに言うメルセデスさんに、俺は尋ねる。
「戦いはクローニアが優勢なんですか?」
エルウィン軍が毒を撒くという強硬手段に出たのは、追い詰められたからだろう。
ところが、メルセデスさんは首を横に振る。
「それが、クローニアの劣勢なんだ。敵の指揮官がたいそう優秀なお人らしくてね。闇夜に乗じた奇襲で、国境付近の砦があっという間に三つ落とされちまった。今は城に籠もって、防衛戦の真っ最中さ」
国境の樹海を抜けた先には、クローニアが築いた砦群があり、仮にそこを突破したとしても、そのさらに奥には堅牢な城壁を誇るマーレイ城がある。
クローニアの国境軍は精強で知られ、エルウィンからの侵攻はいつも砦で阻まれていたのだが、今回は違うらしい。
それにしても優秀な指揮官か……もしかしてアリアのことだろうか。
彼女の授かった天職、《神聖騎士》は、味方の指揮において絶大な効果を発揮する。
その力を活かせば、どんな戦場でも的確な作戦を打ち立て、味方を鼓舞し、戦いを有利に進めることができる。今回のエルウィンの勝利には、アリアの活躍があるかもしれない。
「まあ、マーレイ城にはエリス様っていう恐ろしく強い騎士様がいらっしゃるから、滅多なことはないと思うけどね」
エリス……名前からして女性騎士か?
しかし、クローニアにとっては頼もしい存在であろう人の名を出したメルセデスさんの顔色は優れない。
「このエリス様がまだ若いのにかわいそうなお人でね……いくら騎士だからって、国のために命を削って戦うことはないだろうに……」
「命を削る、ですか」
俺は彼女に話の続きを促す。
「そうさ。あの方の授かった《暗黒騎士》って天職は、凄まじい力を発揮できる代償に、寿命を奪うんだ」
「……詳しく聞かせていただいてもいいですか?」
他人事ながら聞き捨てならない内容だ。
俺自身も天職に振り回された人間として、興味を惹かれる。
俺はメルセデスさんに、その《暗黒騎士》について詳しく尋ねることにした。
◆ ◆ ◆
レヴィンがシーリン村を訪れる十日ほど前。
「エリス。お前の能力にも天職にも、私は欠片も期待していない」
クローニア王国北西にあるマーレイ城、その一室で私――エリス・ルベリアは、かつての父の言葉を反芻していた。
「お前はただ我がルベリア子爵家のために、良き女であり、良き婚姻を結べばそれでいいのだ」
父は私に何も期待していなかった。
何を学ぼうと何を為そうと、父の心が揺らぐことは一度もなかった。
クローニアの貴族家に生まれた私には、政略の駒としての生き方しかないのだ。
私は父に認められようと、良き駒であろうとした。必死に作法を、教養を身に付けた。
貴族子女にふさわしい立ち居振る舞いを心がけ、身だしなみにも気を遣った。
「なんということをしてくれた……この愚か者がっ!」
それは、父が初めて私に向けた強い感情であった。
「数ある天職の中から、よりにもよってそんなものを授かるとは……これではお前の女としての価値が下がるではないか!」
神授の儀が執り行われた日、私の天職を知った父は、人目をはばからずに私の頬を叩いた。
私が授かった《暗黒騎士》は、最高ランクの天職、S級天職の一つだ。
《暗黒騎士》は、持つ者に卓越した戦闘力をもたらす代わりに、呪いをかける。強力ではあるが、とても女神から授けられたとは思えない代物だ。
――どうして、実の父ですら私を認めてくれないんだろう。
父に認められたいがために努力をした。最上級の天職を手にしたのに、私は見限られてしまった。
私はこのまま誰にも認められず、無意味な人生を過ごすのだろうか。
毎日、そんなことばかり考えていた。
父は、「せめて国の役に立て」と言って、私にエルウィンとの国境を警備するガストン公爵家に仕えるよう命じた。
それから、私は剣を振るい続けた。人々を脅かす野盗や魔獣を斬り伏せるのが私の仕事だ。
そうして戦い続けるうちに、私はクローニア王国最強の一人と呼ばれるようになった。
人々から感謝されるのはとても嬉しい。だけど、私は不安だった。
力を使うごとに、私の寿命は削られている。これまでの戦いで、どれほどの寿命を失ったのか。
私の命はいつまでもつのか。十年後か、五年後か、来年? それとも……
こんな日々から抜け出したい。戦いの、死の恐怖がない暮らしを送りたいと願いながら、私は今日も命じられた任務をこなしている。
自室を出た私は今後の戦略について打ち合わせをするため、マーレイ城の司令室で待機していた。
今回の敵は隣国、エルウィン王国。敵は小康状態を破り、突如としてクローニアに侵攻してきた。
狙いはこの城の近くにある金鉱山だ。
これまでは国境沿いの砦を用いて撃退していたものの、ついに防衛線が破られた。
敵は、マーレイ城の間近にまで進軍してきているらしい。
「ご、ご報告いたします。城門前にエルウィン王国軍が現れました。数は一名」
慌てた様子で一人の兵士が司令室にやってきた。
「……は?」
兵の報告に、丸々と肥え脂ぎった騎士――ユリアン閣下がぽかんとした表情を浮かべる。
「報告は正確にせよ。たった一人で城を攻める間抜けなどいるものか!」
「それが、相手は白銀の巨大な騎士盾を持った少女で……」
「な、何!? 我が軍の砦を一夜で落とした【白銀の悪魔】か?」
白銀の悪魔とは、今回の戦いでエルウィンを率いる少女の異名で、私と同様、S級天職を持つ人物だ。
地の利があり、数でも勝っていたクローニア軍を相手に、彼女は優位に立ち回ってみせた。
それだけにユリアン閣下も慌てている。
「はい……それと、もう一つ報告がございます。兵たちが一斉に体調不良を訴えているのです」
「なんだと? どうしてこんな時に……」
「どうやら、飲み水に毒が……ぅ……」
突如、報告に来た兵が苦しみ出し、床に倒れ込んだ。
「まさか、やつらは毒を流したというのか?」
閣下の顔が青ざめた。
私たちクローニア軍は、付近を流れるラングラン川から飲み水を汲み入れている。
水源に毒を流せば、兵たちは一斉に戦闘力を奪われ、マーレイ城の攻略は容易になるだろう。
しかし、そんなことをすれば、付近の村民にも深刻な被害が出る。
いくら戦いとはいえ、エルウィンの作戦はあまりにも卑劣だ。
「グッ……ゴフッ……私にも毒が回ってきたか……」
しばらくして、閣下までが膝を折った。
私は慌てて二人の容体を確かめる。
どうやら致死性はないみたいだが、それでも苦痛は相当なものだろう。
兵士が必死の形相で訴える。
「か、閣下、恐らくは例の……白銀の悪魔の仕業かと……」
「分かっておるわ……あの小娘め、このような卑劣な作戦を……」
閣下は怒りに肩を震わせながら、私を見た。
「エリスよ……お前は無事だな? ならば、お前の出番だ」
私は《暗黒騎士》の能力で優れた戦闘力を得る代わりに、命を削る呪いを与えられている。
すでに呪いを身に受けているからか、それ以外の呪いや毒には強い耐性があった。
「このままでは敵に城門を破られる……だが、お前の力なら……白銀の悪魔を抑えられるはずだ」
私の《暗黒騎士》の力は、戦闘技能に特化したものだ。一対一の戦いであれば、S級天職持ちでも後れは取らないだろう。しかしそんな強敵を相手取れば、私の寿命は……
私は、閣下の命令に不安を隠せない。
「何、これが……最後の戦いだ。私とて、お前に死んでほしいわけではない……これを最後に、騎士の任を解こう。君のお父上、ルベリア卿にも……私から説明しようではないか」
「本当ですか? もう、戦わなくて済むんですか?」
ユリアン閣下の言葉に、私はわずかな希望を抱いた。
私に備わる天職は確かに強力だけれど、その代償は凄まじいものだ。
しかし、それでも父は私に騎士として戦い抜けと命じた。
私はそんな戦いの日々から解放される日を待ち望んでいた。
だから私は彼の約束を聞いて、肩の荷が下りたような心地がしていた。
ところが、続く閣下の話に、私の気持ちは一変する。
「うむ、もちろん嘘はつかん。これを機に君は引退し……私の伴侶となるのだ」
「……え?」
「ふ、ふふ……君は実に美しい……この私、ガストン公爵家の長子、ユリアンの伴侶にふさわしい。そうは思わんかね?」
「……っ。出撃します」
私は早々に会話を打ち切った。
たとえ、どれだけ足掻いて藻掻いても、私の人生は私のものではない。
こうして、誰かの都合で簡単に弄ばれる脆いものなのだ。
悔しさで唇を噛みしめると、私はその場をあとにした。
女性の澄んだ声と共に先ほどの石から光が出て、空中に不思議な映像が投影された。
【リントヴルム市運営状況】
管理人:レヴィン・エクエス
人口:3
都市ランク:F
実行可能なコマンド:【建造】【補修】【回収】
「うおっ、なんだ!?」
映像には、この都市の運営状況とやらが表示されていた。
一般的に魔力を用いて作動する道具を【魔導具】と呼ぶが、この石に使われている技術は、俺が知る魔導具よりずっと複雑そうだ。
「これを使えば、都市の管理ができるってことか? 便利な魔導具だな」
人口が3となっているのは、俺とエルフィ、そしてリントヴルムを指しているに違いない。
この都市ランクというのは、現在の都市の充実度を表しているのだろうか。あたりはすっかり瓦礫の山となっているし、先ほどリントヴルム自身も力が衰えていると言っていたからな。竜大陸を開拓していけば、ランクが上がっていくのかもしれない。
「もしかして、【建造】を選んだら家が建てられるのか?」
試しに、俺が「【建造】」と口にすると……
――現在【建造】できるものは以下の通りです。
【民家:小】【畑:小】
機能が制限されているからか、選択肢はかなり少ない。
だが、家自体は問題なく作れるようだ。ここ数日は、寝る場所にさえ困る有様だったし、雨風を凌げる家が手に入るだけでも大助かりだ。
俺は早速【民家:小】を選択する。
すると目の前に、家を象った蒼白い光の像が現れた。
「おっ、なんか出てきた。こうして建てる場所を選ぶんだな」
実体を持たない光の塊のようだが、俺が視線を動かすと、それに連動して光の家が動く。
エルフィが解説する。
「建てる場所を決めると、都市の魔力を消費してその映像の通りに家が建造される。そういう仕組み」
なるほど。原理はさっぱりだが、直感的な操作で建てる場所が決められるのはなかなか便利だ。
「エルフィはどこに建てたいんだ?」
あたりは瓦礫だらけで【建造】に適した場所は少ないみたいだが、俺はエルフィに希望を尋ねた。
「うーん、折角のママと私の新居。景色のいいところに大きい家を建てたい」
「って言ってもなあ……」
今作れるのは【民家:小】だ。
それに、景色のいい場所と言われても、瓦礫を撤去して都市を復興しないと難しいだろう。
「よし、ひとまず神樹の側に建てよう。ある程度都市を復興したら、また別のところに引っ越せばいいだろう」
俺は神樹の前に視線を動かし【建造】を実行した。近くには水場と、それなりに広い緑地もあるので、利便性も高いはずだ。
コマンドを実行すると、蒼い光がゆっくりと実体を伴い、丸太を積み重ねたログハウスへ変化していった。
「おお! 一体、どんな技術で作ってるんだ?」
もともと、都市にあったらしい金属製の建物と比べたら原始的な家だが、それでも立派なものだ。
しかし、魔法は数あれど、こうして家を一瞬で作るなど聞いたことがない。
古代の技術というのはとんでもないな。
「これがママと私の家……」
エルフィも目を輝かせながら、出来上がった家に見入っている。
【民家:小】とは言っていたが、二人で住むには十分な広さだ。
早速、俺たちは室内に入る。
「へぇ……居間に二人分の個室、ダイニングも完備かぁ……あれ? 俺の実家よりも広くないか?」
エクエス家には居間とダイニングルームの区別なんてなかったし、個室なんていう贅沢なものも当然なかった。一家五人が寝るための狭い寝室があるだけだ。
領地の経営が軌道に乗ったら、もっと広い家に住もうなんて話をよくしたが、まさかこんな形で念願の大きな家を手にするとは思いもよらなかった。
「キッチンもうちのより広くて、調理器具や石窯まである。これで生活には困らないな」
家を見て回り、これからの生活を想像するだけでにんまりとしてしまう。
「見て見て、ママ。ベッドふかふか」
「ああ、そうだな。俺の寝てた硬いベッドよりも上質だ」
布団の中には羽毛がぎっしりと詰まっており、カバーに丁寧な刺繍が施されている。
俺がこれまで使っていた木の板に藁を敷いただけのベッドよりも明らかに豪華で、今度は少し悲しくなってきた。
「どうしたの、ママ? 複雑そうな顔している。嫌だった?」
心配そうにエルフィが顔を覗き込んできた。そんなに深刻な話ではないので、俺は慌てて事情を明かす。
「実家よりも豪華だったから面食らっただけだよ。前はここよりも狭い場所に住んでいたから」
「嫌じゃないならよかった……でも、もっと大きくて綺麗な家が用意できればよかったのに。ママは酷い目に遭ったんだから、幸せになってほしい」
……なんて親思いな娘なのだろう。
最近は人の優しさに触れるどころか、理不尽な暴力に晒されるばかりだったので、エルフィの気遣いが身に染みる。
「気にしないでくれ。俺には十分すぎるほど立派な家だしな!」
実際、普通に暮らすにはかなり快適な家だ。
広さは十分だし、生活に必要な家具もある程度揃っている。
国を追われて一時はどうなることかと思ったが、こうして安心して過ごせる場所を手に入れられて本当によかった。
「ちなみに、もっと大きい家を作るには都市の魔力が足りてない。毎日、住人の魔力を少しずつもらっていく仕組みだから、もっと住む人を増やせればいいんだけど」
「住人から魔力を……税金代わりってことか」
そういう仕組みだとすると、俺とエルフィ、リントヴルムの三人しかいない現状では最低限の機能しか使えないのも当然だ。そうなると、今度はここに住んでくれる人を探す必要がある。
移住者の心当たりはなくもない。故郷のルミール村は、土地が痩せていて貧しい村だ。
この都市に移住できたら、みんなもっと快適に暮らせるかもしれない。
ぐぅ……
俺が今後のことを考えていると、大きな腹の音が鳴った。俺じゃないとなると……
「……ママ、お腹空いた」
我が娘は食べ盛りらしい。とはいえ、とっくに昼飯の時間は過ぎている頃だ。エルフィにつられて俺も空腹感を覚えてきた。
「食料はここで調達できるのか?」
「農業すればできるようになる。昔は町の外で野菜や動物を育てていた」
「でも、すぐに用意するとなると難しいよな」
【建造】で畑が作れても、すぐに収穫できるわけじゃない。地上で食料を確保する必要がある。
「って、よくよく考えたら、どうやって地上に戻ればいいんだ? 今はもう雲の上だし、エルフィも地上まで飛ぶのはキツくないか?」
「問題なし。何せ私は神竜族。ママを連れて地上まで飛ぶなんて余裕なのだ」
エルフィがVサインを見せて得意げにする。
さすが神竜族。飛行能力も並々ならぬものらしい。
「よし。それなら一度、地上に降ろしてもらえるか? 適当な村で食料を手に入れよう」
「任せて」
こうして、俺たちは再び地上へと降り立つのであった。
◆ ◆ ◆
俺たちがやってきたのは国境付近のシーリン村。
祖国エルウィン王国ではなく、隣国クローニア王国にある村だ。
たまたまリントヴルムがクローニアの上空を飛んでいたので、今回はシーリン村を選んだ。ここは敵国だが、いざとなったら空の上に逃げればいいわけだしな。
人目に付かないよう村の近くにこっそりと降り、そこから歩いてシーリンへ入った。
「これが持つ者と持たざる者の差か……」
大勢の人でごった返す市場を見て、俺はため息をつく。
我が故郷のルミール村もエルウィン側の国境付近に位置しているが、同じ国境付近の村であるシーリンの発展具合は段違いだった。
このあたりは肥沃な土壌が広がっているため農業が盛んで、ワインの名産地だ。おまけに、近くには金鉱山まであるため、牧歌的な雰囲気のルミール村よりもずっと賑やかだ。
うちの村もせめてもう少し土地が豊かであれば、どうにかなったのだろうけど……
「父さんたち、元気でやってるかなあ」
エルウィンのことはどうでもいいが、村のことは気がかりだった。
俺が聖獣を授からなかったせいで、国王から何か嫌がらせを受けていないだろうか?
同じ村出身のアリアが騎士団で活躍している以上、滅多なことにはなっていないはずだが心配だ。
「アリアも今頃どうしてるんだろうな」
彼女はもともと、戦いに向いた性格ではない。むしろ、おとなしくて引っ込み思案なタイプだったから、ひょっとしたら騎士団で苦労しているかもしれない。
「ママ……? なんだか悩んでるみたいだけど、大丈夫?」
俺の服の裾を引っ張り、エルフィが心配そうな表情を向けてきた。
「悪いな。急に国を追い出されたから、心残りがいろいろとあるんだ」
「アリアって、もしかしてママの恋人?」
「こ、恋人ってわけじゃない。大切な家族だよ」
そう。俺とアリアはそういった関係ではない。
だから、俺がアーガスとアリアの関係に口を出す筋合いはない。ないのだが……
――このワシ、国王ドルカスの名において、《聖獣使い》アーガス・アレス・アルベリヒと《神聖騎士》アリア・レムスの婚姻を認めよう。
ドルカスの宣言が頭をよぎる。
客観的に考えれば、アーガスは地位も実力もあり、アリアにふさわしい。
それは俺だって分かっている。彼女の幸せを考えれば、俺は祝福するべきだ。
だけど、どうしても割り切れない想いがあるのだ。
その時、どこからか呼び込みの声が聞こえてきた。
「おや、元気なさそうだね。サービスしてあげるから、うちで何か買っていかないかい?」
俺とエルフィが周囲を見回すと、屋台の中から背の高い褐色の肌の女性がこっちに手を振っていた。
店に並んでいる品を見るに、どうやら食料品店のようだ。
ちょうど食べ物を買いに来ていた俺たちは、彼女の陽気な声に導かれるように店へ向かう。
「やあやあ、お兄さん。私の名はメルセデス。メルセデス・アンソロだ。大陸中を旅しながら行商をしていてね。今はクローニアを中心に商売をしているんだ」
声の主……メルセデスさんは若く颯爽とした雰囲気の人で、爽やかな笑みを浮かべていた。
「お兄さん、旅人かい? 随分と軽装だね」
「いろいろとワケアリでして……食料を調達するためにシーリンに寄ったんです」
「ふーん。そっちで隠れてるのは、妹さんかい?」
気付いたら、エルフィが俺の背に隠れていた。
もしかして人見知りする性格なのだろうか。
俺はエルフィの頭を撫でながら、メルセデスさんに答える。
「そんなところです。お腹を空かせているので、美味しいものを食べさせてあげたいんです」
「なるほど、なるほど。そういうことならタイミングがよかった。カリン! ちょうどお客さんが来たみたいだよ」
「はい、はーい」
メルセデスさんが呼びかけると、透き通るような声と共に、浅黄色の髪をした落ち着いた雰囲気の女性がやってきた。その手にいっぱいの肉を抱えている。
「どうも、カリンと申します。ちょうど、搬入をしていたところでして。お肉をお求めですか?」
「食品全般を見たいらしいよ。妹さんがお腹を空かせてるから、美味しいものを食べさせたいんだってさ」
「まあ、仲がいいんですね。私にも弟のような幼馴染がいるから、お気持ちはよく分かります!」
「またまた、幼馴染ってだけじゃないだろう? あんな大英雄様の婚約者だなんて、羨ましいよ」
メルセデスさんがからかうように言って、カリンさんの肩を肘で突く。
「わ、私たち、まだそういう関係じゃ」
「まだ……ね。ということは、いずれはそういう関係になるつもりはあると」
「もう、メルセデス!」
カリンさんが顔を赤らめてメルセデスさんを責めた。
なんというか、平和な光景だなあ。
俺が二人のやり取りに和んでいると、カリンさんが話を切り替える。
「それよりも商売ですよ。お客さん、運がよかったですね。今は食料を手に入れるのが大変なんですよ」
ここは国境に近い場所ではあるものの、人口が多く交易もそれなりに行われているはず。
食料の入手が難しいなんて話は聞いたことがなかったが……
俺が首を傾げると、メルセデスさんが事情を説明する。
「まあ、突然の出来事だったしね。なんたってエルウィンが急に侵攻してきたんだから」
「えっ!?」
エルウィンがクローニアに侵攻?
以前から対立していた両国だが、ここ数年は小康状態だった。いつの間に事態が動いたのか。
カリンさんが頷く。
「商売にも影響出ていますし、何よりも村の農業は大打撃です」
農業に打撃……? 戦いが始まれば影響はあるだろうけど、今この村自体が攻められている様子はない。
何か別の事情があるのだろうか。
メルセデスさんが声を潜めて言う。
「ここだけの話だけど、エルウィンの兵士たちがこの近くの湖や川に毒を撒いたんだよ」
「なんですって?」
ここは農業が盛んな村だ。それを壊滅させれば、確かにクローニア王国に効率的に打撃を与えられるだろう。しかし、だからといって毒を流すなんて……
少し前まで王都にいたが、初めて聞く話だ。国民にさえ知らされず、侵攻が始まっていたとは。
俺は祖国の所業に内心で頭を抱える。
「そういうわけで、食料確保も大変な状況でね。私も村の支援のために、ここで営業してるのさ。ここでの売り上げは全額、村の復興に使うつもりだから景気よく頼むよ」
「そういうことでしたら」
幸い、俺はいくらか金貨を隠し持っていた。一人なら金貨一枚で一週間は食べていけることを思えば、当分の食費はまかなえる金額だ。
毒を流されては農業などまともにできないだろうし、同じ農村の出身として、せめて買って支援をしよう。
俺は保存の利く食品を中心に、およそ一ヶ月分の食料を買い漁る。
「お買い上げありがとうございます。こんなに買ってくれて、本当に助かります」
カリンさんが一礼した。
サービスで用意してくれた荷車に、ぎっしりと食材を積む。
さすがに多いかと心配したが、エルフィの力なら容易く運べるとのことだった。
「村の作物は完全にダメになって、毒で倒れた人もいるんだ。これからどうなるんだろうね」
心配そうに言うメルセデスさんに、俺は尋ねる。
「戦いはクローニアが優勢なんですか?」
エルウィン軍が毒を撒くという強硬手段に出たのは、追い詰められたからだろう。
ところが、メルセデスさんは首を横に振る。
「それが、クローニアの劣勢なんだ。敵の指揮官がたいそう優秀なお人らしくてね。闇夜に乗じた奇襲で、国境付近の砦があっという間に三つ落とされちまった。今は城に籠もって、防衛戦の真っ最中さ」
国境の樹海を抜けた先には、クローニアが築いた砦群があり、仮にそこを突破したとしても、そのさらに奥には堅牢な城壁を誇るマーレイ城がある。
クローニアの国境軍は精強で知られ、エルウィンからの侵攻はいつも砦で阻まれていたのだが、今回は違うらしい。
それにしても優秀な指揮官か……もしかしてアリアのことだろうか。
彼女の授かった天職、《神聖騎士》は、味方の指揮において絶大な効果を発揮する。
その力を活かせば、どんな戦場でも的確な作戦を打ち立て、味方を鼓舞し、戦いを有利に進めることができる。今回のエルウィンの勝利には、アリアの活躍があるかもしれない。
「まあ、マーレイ城にはエリス様っていう恐ろしく強い騎士様がいらっしゃるから、滅多なことはないと思うけどね」
エリス……名前からして女性騎士か?
しかし、クローニアにとっては頼もしい存在であろう人の名を出したメルセデスさんの顔色は優れない。
「このエリス様がまだ若いのにかわいそうなお人でね……いくら騎士だからって、国のために命を削って戦うことはないだろうに……」
「命を削る、ですか」
俺は彼女に話の続きを促す。
「そうさ。あの方の授かった《暗黒騎士》って天職は、凄まじい力を発揮できる代償に、寿命を奪うんだ」
「……詳しく聞かせていただいてもいいですか?」
他人事ながら聞き捨てならない内容だ。
俺自身も天職に振り回された人間として、興味を惹かれる。
俺はメルセデスさんに、その《暗黒騎士》について詳しく尋ねることにした。
◆ ◆ ◆
レヴィンがシーリン村を訪れる十日ほど前。
「エリス。お前の能力にも天職にも、私は欠片も期待していない」
クローニア王国北西にあるマーレイ城、その一室で私――エリス・ルベリアは、かつての父の言葉を反芻していた。
「お前はただ我がルベリア子爵家のために、良き女であり、良き婚姻を結べばそれでいいのだ」
父は私に何も期待していなかった。
何を学ぼうと何を為そうと、父の心が揺らぐことは一度もなかった。
クローニアの貴族家に生まれた私には、政略の駒としての生き方しかないのだ。
私は父に認められようと、良き駒であろうとした。必死に作法を、教養を身に付けた。
貴族子女にふさわしい立ち居振る舞いを心がけ、身だしなみにも気を遣った。
「なんということをしてくれた……この愚か者がっ!」
それは、父が初めて私に向けた強い感情であった。
「数ある天職の中から、よりにもよってそんなものを授かるとは……これではお前の女としての価値が下がるではないか!」
神授の儀が執り行われた日、私の天職を知った父は、人目をはばからずに私の頬を叩いた。
私が授かった《暗黒騎士》は、最高ランクの天職、S級天職の一つだ。
《暗黒騎士》は、持つ者に卓越した戦闘力をもたらす代わりに、呪いをかける。強力ではあるが、とても女神から授けられたとは思えない代物だ。
――どうして、実の父ですら私を認めてくれないんだろう。
父に認められたいがために努力をした。最上級の天職を手にしたのに、私は見限られてしまった。
私はこのまま誰にも認められず、無意味な人生を過ごすのだろうか。
毎日、そんなことばかり考えていた。
父は、「せめて国の役に立て」と言って、私にエルウィンとの国境を警備するガストン公爵家に仕えるよう命じた。
それから、私は剣を振るい続けた。人々を脅かす野盗や魔獣を斬り伏せるのが私の仕事だ。
そうして戦い続けるうちに、私はクローニア王国最強の一人と呼ばれるようになった。
人々から感謝されるのはとても嬉しい。だけど、私は不安だった。
力を使うごとに、私の寿命は削られている。これまでの戦いで、どれほどの寿命を失ったのか。
私の命はいつまでもつのか。十年後か、五年後か、来年? それとも……
こんな日々から抜け出したい。戦いの、死の恐怖がない暮らしを送りたいと願いながら、私は今日も命じられた任務をこなしている。
自室を出た私は今後の戦略について打ち合わせをするため、マーレイ城の司令室で待機していた。
今回の敵は隣国、エルウィン王国。敵は小康状態を破り、突如としてクローニアに侵攻してきた。
狙いはこの城の近くにある金鉱山だ。
これまでは国境沿いの砦を用いて撃退していたものの、ついに防衛線が破られた。
敵は、マーレイ城の間近にまで進軍してきているらしい。
「ご、ご報告いたします。城門前にエルウィン王国軍が現れました。数は一名」
慌てた様子で一人の兵士が司令室にやってきた。
「……は?」
兵の報告に、丸々と肥え脂ぎった騎士――ユリアン閣下がぽかんとした表情を浮かべる。
「報告は正確にせよ。たった一人で城を攻める間抜けなどいるものか!」
「それが、相手は白銀の巨大な騎士盾を持った少女で……」
「な、何!? 我が軍の砦を一夜で落とした【白銀の悪魔】か?」
白銀の悪魔とは、今回の戦いでエルウィンを率いる少女の異名で、私と同様、S級天職を持つ人物だ。
地の利があり、数でも勝っていたクローニア軍を相手に、彼女は優位に立ち回ってみせた。
それだけにユリアン閣下も慌てている。
「はい……それと、もう一つ報告がございます。兵たちが一斉に体調不良を訴えているのです」
「なんだと? どうしてこんな時に……」
「どうやら、飲み水に毒が……ぅ……」
突如、報告に来た兵が苦しみ出し、床に倒れ込んだ。
「まさか、やつらは毒を流したというのか?」
閣下の顔が青ざめた。
私たちクローニア軍は、付近を流れるラングラン川から飲み水を汲み入れている。
水源に毒を流せば、兵たちは一斉に戦闘力を奪われ、マーレイ城の攻略は容易になるだろう。
しかし、そんなことをすれば、付近の村民にも深刻な被害が出る。
いくら戦いとはいえ、エルウィンの作戦はあまりにも卑劣だ。
「グッ……ゴフッ……私にも毒が回ってきたか……」
しばらくして、閣下までが膝を折った。
私は慌てて二人の容体を確かめる。
どうやら致死性はないみたいだが、それでも苦痛は相当なものだろう。
兵士が必死の形相で訴える。
「か、閣下、恐らくは例の……白銀の悪魔の仕業かと……」
「分かっておるわ……あの小娘め、このような卑劣な作戦を……」
閣下は怒りに肩を震わせながら、私を見た。
「エリスよ……お前は無事だな? ならば、お前の出番だ」
私は《暗黒騎士》の能力で優れた戦闘力を得る代わりに、命を削る呪いを与えられている。
すでに呪いを身に受けているからか、それ以外の呪いや毒には強い耐性があった。
「このままでは敵に城門を破られる……だが、お前の力なら……白銀の悪魔を抑えられるはずだ」
私の《暗黒騎士》の力は、戦闘技能に特化したものだ。一対一の戦いであれば、S級天職持ちでも後れは取らないだろう。しかしそんな強敵を相手取れば、私の寿命は……
私は、閣下の命令に不安を隠せない。
「何、これが……最後の戦いだ。私とて、お前に死んでほしいわけではない……これを最後に、騎士の任を解こう。君のお父上、ルベリア卿にも……私から説明しようではないか」
「本当ですか? もう、戦わなくて済むんですか?」
ユリアン閣下の言葉に、私はわずかな希望を抱いた。
私に備わる天職は確かに強力だけれど、その代償は凄まじいものだ。
しかし、それでも父は私に騎士として戦い抜けと命じた。
私はそんな戦いの日々から解放される日を待ち望んでいた。
だから私は彼の約束を聞いて、肩の荷が下りたような心地がしていた。
ところが、続く閣下の話に、私の気持ちは一変する。
「うむ、もちろん嘘はつかん。これを機に君は引退し……私の伴侶となるのだ」
「……え?」
「ふ、ふふ……君は実に美しい……この私、ガストン公爵家の長子、ユリアンの伴侶にふさわしい。そうは思わんかね?」
「……っ。出撃します」
私は早々に会話を打ち切った。
たとえ、どれだけ足掻いて藻掻いても、私の人生は私のものではない。
こうして、誰かの都合で簡単に弄ばれる脆いものなのだ。
悔しさで唇を噛みしめると、私はその場をあとにした。
533
あなたにおすすめの小説

「お前は無能だ」と追放した勇者パーティ、俺が抜けた3秒後に全滅したらしい
夏見ナイ
ファンタジー
【荷物持ち】のアッシュは、勇者パーティで「無能」と罵られ、ダンジョン攻略の直前に追放されてしまう。だが彼がいなくなった3秒後、勇者パーティは罠と奇襲で一瞬にして全滅した。
彼らは知らなかったのだ。アッシュのスキル【運命肩代わり】が、パーティに降りかかる全ての不運や即死攻撃を、彼の些細なドジに変換して無効化していたことを。
そんなこととは露知らず、念願の自由を手にしたアッシュは辺境の村で穏やかなスローライフを開始。心優しいエルフやドワーフの仲間にも恵まれ、幸せな日々を送る。
しかし、勇者を失った王国に魔族と内通する宰相の陰謀が迫る。大切な居場所を守るため、無能と蔑まれた男は、その規格外の“幸運”で理不尽な運命に立ち向かう!

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。
カモミール
ファンタジー
勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。
だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、
ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。
国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。
そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。
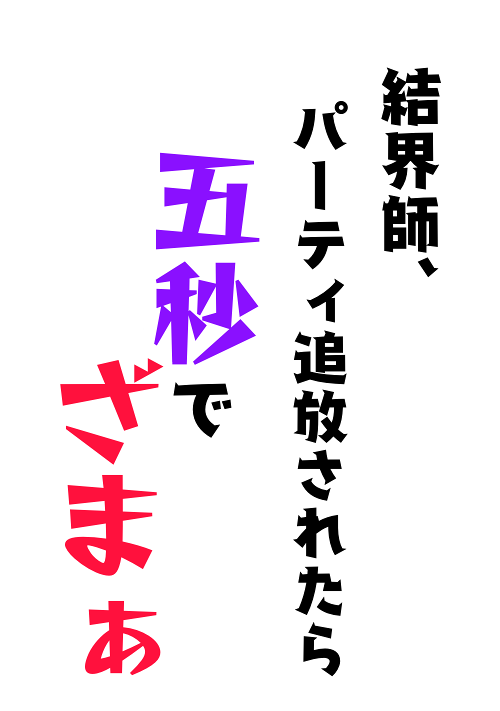
結界師、パーティ追放されたら五秒でざまぁ
七辻ゆゆ
ファンタジー
「こっちは上を目指してんだよ! 遊びじゃねえんだ!」
「ってわけでな、おまえとはここでお別れだ。ついてくんなよ、邪魔だから」
「ま、まってくださ……!」
「誰が待つかよバーーーーーカ!」
「そっちは危な……っあ」

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

友人(勇者)に恋人も幼馴染も取られたけど悔しくない。 だって俺は転生者だから。
石のやっさん
ファンタジー
パーティでお荷物扱いされていた魔法戦士のセレスは、とうとう勇者でありパーティーリーダーのリヒトにクビを宣告されてしまう。幼馴染も恋人も全部リヒトの物で、居場所がどこにもない状態だった。
だが、此の状態は彼にとっては『本当の幸せ』を掴む事に必要だった
何故なら、彼は『転生者』だから…
今度は違う切り口からのアプローチ。
追放の話しの一話は、前作とかなり似ていますが2話からは、かなり変わります。
こうご期待。

【本編45話にて完結】『追放された荷物持ちの俺を「必要だ」と言ってくれたのは、落ちこぼれヒーラーの彼女だけだった。』
ブヒ太郎
ファンタジー
「お前はもう用済みだ」――荷物持ちとして命懸けで尽くしてきた高ランクパーティから、ゼロスは無能の烙印を押され、なんの手切れ金もなく追放された。彼のスキルは【筋力強化(微)】。誰もが最弱と嘲笑う、あまりにも地味な能力。仲間たちは彼の本当の価値に気づくことなく、その存在をゴミのように切り捨てた。
全てを失い、絶望の淵をさまよう彼に手を差し伸べたのは、一人の不遇なヒーラー、アリシアだった。彼女もまた、治癒の力が弱いと誰からも相手にされず、教会からも冒険者仲間からも居場所を奪われ、孤独に耐えてきた。だからこそ、彼女だけはゼロスの瞳の奥に宿る、静かで、しかし折れない闘志の光を見抜いていたのだ。
「私と、パーティを組んでくれませんか?」
これは、社会の評価軸から外れた二人が出会い、互いの傷を癒しながらどん底から這い上がり、やがて世界を驚かせる伝説となるまでの物語。見捨てられた最強の荷物持ちによる、静かで、しかし痛快な逆襲劇が今、幕を開ける!

追放された私の代わりに入った女、三日で国を滅ぼしたらしいですよ?
タマ マコト
ファンタジー
王国直属の宮廷魔導師・セレス・アルトレイン。
白銀の髪に琥珀の瞳を持つ、稀代の天才。
しかし、その才能はあまりに“美しすぎた”。
王妃リディアの嫉妬。
王太子レオンの盲信。
そして、セレスを庇うはずだった上官の沈黙。
「あなたの魔法は冷たい。心がこもっていないわ」
そう言われ、セレスは**『無能』の烙印**を押され、王国から追放される。
彼女はただ一言だけ残した。
「――この国の炎は、三日で尽きるでしょう。」
誰もそれを脅しとは受け取らなかった。
だがそれは、彼女が未来を見通す“預言魔法”の言葉だったのだ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















