19 / 61
明け易し夏 ミツキの疑惑
重なる肌と火照る身体 身を焦がすほど熱く震える夜に
しおりを挟む
潮が満ちると映し出される深い夏色は、海と空の境界線の向こうまでも続いていて、囁《ささや》くように弾ける波の泡が、映し出された水面のミツキをかき消していく。ペリエを注いだグラスの中の余韻《よいん》のような、耳触りの良い音で引いていく波が、再び彼女をぼんやりと浮かび上がらせた。まるでウユニ湖の境界線のない空のように。
僕の手を引いて微笑むミツキは、白いワンピースの長い裾をもう片方の手で持って、そのつま先は砂の中に消えていく。足の指の隙間が崩れていって、えぐり取られた浜辺に足跡が残された。
「海に来たの久しぶり」
ミツキはそう言って、風に舞う白い砂から顔を背ける。
夏休みに入ってからは毎日何もすることがなく、部屋で宿題をするか、客がいないフォトスタジオで一人、ストレッチと筋トレ、そしてダンスをする日々によほどストレスを抱えていたのだろう。海に行くことを提案した時のミツキの喜びようは、学校で過ごす無口でクールなミツキとは別の人間、別の人種、別の人格のようで、とても歓喜していた。
僕の家族は全員、今頃ハワイで休暇を楽しんでいる。僕とミツキも誘われたのだが、無論ミツキは断った。特に、ミツキは日本人の多いオアフ島では絶対に目立つだろう。それよりも、この茨城の田舎の海の方がよほど楽しめるはずだ。特にこの県北地域は人がまばらなのだから。
園部三和子は実のところ、この田舎リゾートの地に立つ歴史ある温泉旅館オーナーの一人娘なのである。紫陽花の森でのお礼に、といただいた宿泊券を消化しなければいけない義務が生じたために、家族がいないタイミングで使おうと密かに計画をしたのである。
「僕も、こんなに綺麗な海ははじめてかも」
「わたしは、一昨年以来かな」
波打ち際の天女のような少女は、反射する光を全身で受け止めていて、比喩などではなく白いワンピースとともに輝いていた。小気味好い音で切るシャッターの向こう側で振り返るミツキは、やはり僕だけに見せる笑顔を惜しみなく注いでくれて、僕はレンズ越しに再び恋をする。
「ねえ、シュン君。お部屋に温泉ついているんだよね?」
「うん。結構良い部屋用意してくれたみたい」
一緒に入ろっか。というミツキの言葉に僕は、思わずバスタオル一枚のミツキを想像してしまい、動けずに腰のあたりまで波を被ってしまった。いや、実際に同じ部屋に泊まるという事実を、旅館に着いてから知った時点で、僕はどぎまぎしていて正気を失いかけている。いつ発狂してミツキに食らい付いてもおかしくない。そう、僕はゾンビになりかけている。
砂浜から少し歩いて、坂を上る。切り立った崖の上に建つ温泉旅館は、よくミステリードラマの犯人が、罪を告白するシーンで使われるくらい景観が良かった。なんといっても、この温泉は海を一望できる露天風呂が売りであり、日の出を温泉に入りながら拝むことができる温泉宿ベスト一〇に入っているくらい有名であった。
旅館に戻りロビーで鍵を受け取って部屋に入ると、畳の部屋と、ベッドが二つ並んでいる洋室が隣り合わせになっていて、二人で使うにはあまりにも広すぎた。また、テラスには大きな桶にたっぷりと赤茶色のお湯が張られていて、やはり海を臨むことができる。
「すごいね~~~~!!」
「ほんとすごい!! 地元にこんな場所があったなんて!」
ミツキはテラスに出ると、両手を上げて伸びをしながら気持ちよさそうに瞳を閉じた。心地よい潮風が彼女の髪をなびいていき、僕はその後ろ姿がたまらなく可愛くて。思わず背中を抱き締める。後ろ髪が僕の頬を撫でると、ミツキは振り向いて瞳を再び閉じた。柔らかいミツキの唇を奪うと、僕の右肺と左肺の中心がたまらずに震える。君をもう少しだけ僕だけのものにさせて。アイドルに戻る前に。
「シュン君。温泉に入ってみたいの」
「うん。露天風呂にでもいく? それとも部屋の?」
「露天風呂に行ってみない?」
「うん。そうだね」
外廊下を渡って、離れになっている建物に入ると、そこでミツキとはお別れ。少しだけ寂しかった。だが、僕よりもミツキのほうが重症である。その表情はもはや今生の別れ。繋いでいた手を離す瞬間もミツキの指は僕の指先を求めていて、列車で戦地に向かう恋人の兵士を追いかける幼気《いたいけ》な少女そのもの。ああ、僕の帰りを待っていて。必ずここに、この場所に戻るから。とはいえ、きっと待つのは僕の方なのだけれども。
「シュン君。なるべく早く戻るね。待っててね。先に帰らないで……」
「いや、そんな涙目で言う台詞なの? 大丈夫だよ。絶対にここで待っているから」
待ち合わせ場所は自販機が置いてあるちょっとしたカフェテラス。自販機にはコーヒー牛乳からアイスクリームまで揃っている、湯上りで瀕死の戦士のオアシスのような場所だ。なによりも、女子の帰還を待つ男子にとって、この場所は心の拠り所であろう。それもそのはず。このカフェテラスがなければ、数少ないマッサージチェアを泥仕合《どろじあい》をして奪い合わなければいけないのだから。
予想通り、僕の方が先に帰還してしまった。未だに任を解くことを許されないのだろうか、ミツキ一等兵が帰る気配もなく、ただ僕は彼女の無事を待つ。
きっと、潮騒《しおさい》に思いを馳せているのだろう。夕陽に照らされる水面は微かに柿色に染まっていて、瞳を閉じると心に虚空が浮かび上がる。その情景は何もない大海原に漂《ただよ》う、行く当てのない木片のような自分と、雲一つない朱色に染まる空だ。どこに流されているのか、何のために生を与えられたのか。その答えが出ない脳の中をほとばしる、さざ波の音だけが響く世界。だから、海は思いにふけってしまうのだろう。ミツキが僕と同じ感性ならば、だけれども。
コーヒー牛乳を片手に、丸テーブルに座って廊下を行き交う人視線を注ぐ。
浴衣を着た美少女を、通り過ぎる人々が唖然《あぜん》として視線で追う。アップヘアにした栗色の髪の毛と、その僅《わず》か下に見えるうなじが、さらに人の目をくぎ付けにする。
恐らく、いや絶対にすっぴんなのだろうけど、確実に花神楽美月《はなかぐらみつき》なのだから、もはや人々を救う術はない。みんな魂を抜かれてしまって、もぬけの殻のような表情はゾンビを通り過ごして地縛霊のよう。ミツキを見ることに固執して、仕舞《しまい》に彼氏は彼女に怒られる始末。このままだと阿鼻叫喚《あびきょうかん》になりかねないために、僕はミツキを救い出して椅子に座らせた。廊下の方から顔を背けて、僕と向き合わせる。ミツキにコーヒー牛乳を手渡すと、おいしそうに飲み干した。
「おいし~~。染みるね!」
「温泉のあとっていったら、コーヒー牛乳かフルーツ牛乳だよね!」
「明日の朝はフルーツ牛乳にしよう!」
朝日を見ながら入ることも計画のうちであるために、ミツキはスマホのアラームをこの旅館に着く前から五つもセットしていた。しかも朝四時から五分おきに。スヌーズという機能があることを知らないらしい。
渡り廊下を戻ると、エレベーターの前のにぎやかな空間に視線が行く。温泉旅館、特有のゲーセンだ。先ほどのミツキにもぬけの殻にされた彼氏と、それに業を煮やした彼女がクレーンゲームをしていた。ああ、まずい。ここは、見なかったことにして通り過ぎよう。だが、そうはいかないのが、うちの姫様だ。
「シュン君。ゲームセンターに行ってみたいの」
「言うと思った。温泉旅館といえばゲーセンだもんね」
きっと、ミツキはすっぴんだから、自分が花神楽美月だとは思われまい、なんて思っているに違いない。甘すぎる。すっぴんでもナチュラルメイクをしているような肌だし、エクステをしていない睫毛《まつげ》でも十分に長い。あとどれだけの人を地縛霊に変えちゃうの。怖いよ。
クレーンゲームの中に閉じ込められた地方限定の猫キャラ。キャティちゃんを所望する姫のために二百円を投下する。持ち上がり、出口付近で墜落して脱出失敗。もう一回救出を試みると、キャティが縦穴に真っ逆さまに落ちていく。印籠《いんろう》を持ったキャティちゃんをミツキに手渡すと、とても喜んだ。
「これ、シュン君からのはじめてのプレゼントだね」
「あ……。もっとマシなものをあげればよかった」
「え。可愛いからこれで良かったよ?」
「クレーンゲームの景品が初プレゼントとか。なんかごめん」
いいの、すごく嬉しいから、と言ってミツキは僕の右腕に自分の左腕を絡めてきてゲーセンの奥に進んでいく。右手で抱いたキャティちゃんも笑顔で良かった。ミツキの幸せそうな笑顔に、僕も思わず頬が綻《ほころ》ぶ。
部屋に戻ると食事が準備されていて、海鮮を中心とした料理はとても一人では食べきれる量ではなかった。なぜ田舎はこうも料理の量が多いのか。蕎麦屋にしかり、この旅館にしかり。しかも、あん肝とか白子とか、内容もマニアックすぎる。
しかし、ミツキはお構いなしに珍味を味わって食レポのような感想を僕に伝えると、食べるように勧めてくる。以前、旅番組に出ていた花神楽美月の食する姿が、演技ではないことが明白になった。ちなみに、志桜里は不味いと生放送で口走ってから、食レポはさせてもらえなくなったらしい。阿呆《あほう》だ。
さて、問題の入眠について、だ。ベッドは二つある。ミツキはベッドに入ると部屋を暗くすることを拒んだ。夜が怖い、と。
それについて、僕はまだ聞いていない。なぜ夜が怖いのか。暗闇が怖いのではなく、夜が怖いとミツキは言う。だが、ミツキがなにかトラウマを抱えているのなら、あえてそれを掘り起こす必要もないし、『ミツキは夜が怖い』ということを理解していれば済む話なのだから、騒ぎ立てる必要もない。そう思いながら、電球を点けたままミツキの入ったベッドの隣のベッドに潜り込んだ。
「おやすみ。ミツキ」
「ちょっとぉ。シュン君っていじわる」
「え? 僕なんかした?」
「そうじゃなくて、このままじゃ眠れない」
「……なんで?」
ミツキはベッドから抜け出して、僕のベッドに忍び込んでくる。タオルケットの海を泳いで海面から顔を出すと、僕の鼻先五センチメートルの前で、愛らしい瞳を僕の視界にフェードインしてくる。ベッドサイドのスイッチを押して、電球の明かりを消すと、僕に抱き着いてきた。
「夜は怖いんでしょ。大丈夫なの?」
「シュン君が一緒に寝てくれるなら。多分」
しかし、ミツキは震えていた。まるで怯える子猫のように小刻みに震える姿は、僕にとってもいたたまれずに、ミツキを優しく抱きしめるほかなかった。そんなに怯えないで。なにがあったのか知らないけれど、僕が守ってあげるから。
「電気点けようか?」
だが、いつかのミツキのように、僕の腕の中でかぶりを振る。
ねえシュン君。いいよ。シュン君なら。シュン君ならわたしの全部あげてもいいの。少しだけ怖いけど、シュン君ならきっと大丈夫。だって、シュン君はきっと私の最初で最後の人だから。
重ねた唇が少しだけ震えていて、ミツキの潤んだ瞳が僕を求めている。ミツキの感触が僕の理性を完全に脳内から消し去って、心臓から溢《あふ》れる激流が勢いを落とすことなく全身を駆け巡る。ミツキは微かに呟く。
————シュン君。わたしのこと好き?
好きに決まっている、と肺の底から湧き上がる熱い吐息とともに吐き出した台詞が、ミツキに溶けていった。僕と彼女、二人の両手に指を絡ませて強く握る。
僕の殻を抜け出した魂がミツキの魂に絡みついて、やがて一つになる。それは、愛を育むなどという簡単な言葉で済ませるほど単純ではない。火照る身体を抱き締めて重なる体温と満たされない唇が、ミツキをさらに求める。
シュン君お願い。このままわたしを……。シュン君大好き。シュン君。止めないで。シュン君大好き。シュン君。
————シュン君。愛している。
◇◆◇
まだ怖いの?
そう訊いた僕の言葉に、少し考えて、ベッドから起き上がったミツキはバスタオルを身体に巻いて窓を開けた。月に照らされた美しい肢体《したい》が浮かび上がると同時に、影法師が僕の足元まで伸びる。青い光に満ちた部屋の中は、少しだけ神秘的だった。風を感じたミツキの素肌はとても白く、まるで硝子細工《がらすざいく》のよう。
怖いけど、シュン君と一緒なら平気。
再び僕の元に歩み寄るミツキは、僕の頬にキスをして微笑みながら言う。
シュン君。これでもう結婚するしかないね、と。
僕の手を引いて微笑むミツキは、白いワンピースの長い裾をもう片方の手で持って、そのつま先は砂の中に消えていく。足の指の隙間が崩れていって、えぐり取られた浜辺に足跡が残された。
「海に来たの久しぶり」
ミツキはそう言って、風に舞う白い砂から顔を背ける。
夏休みに入ってからは毎日何もすることがなく、部屋で宿題をするか、客がいないフォトスタジオで一人、ストレッチと筋トレ、そしてダンスをする日々によほどストレスを抱えていたのだろう。海に行くことを提案した時のミツキの喜びようは、学校で過ごす無口でクールなミツキとは別の人間、別の人種、別の人格のようで、とても歓喜していた。
僕の家族は全員、今頃ハワイで休暇を楽しんでいる。僕とミツキも誘われたのだが、無論ミツキは断った。特に、ミツキは日本人の多いオアフ島では絶対に目立つだろう。それよりも、この茨城の田舎の海の方がよほど楽しめるはずだ。特にこの県北地域は人がまばらなのだから。
園部三和子は実のところ、この田舎リゾートの地に立つ歴史ある温泉旅館オーナーの一人娘なのである。紫陽花の森でのお礼に、といただいた宿泊券を消化しなければいけない義務が生じたために、家族がいないタイミングで使おうと密かに計画をしたのである。
「僕も、こんなに綺麗な海ははじめてかも」
「わたしは、一昨年以来かな」
波打ち際の天女のような少女は、反射する光を全身で受け止めていて、比喩などではなく白いワンピースとともに輝いていた。小気味好い音で切るシャッターの向こう側で振り返るミツキは、やはり僕だけに見せる笑顔を惜しみなく注いでくれて、僕はレンズ越しに再び恋をする。
「ねえ、シュン君。お部屋に温泉ついているんだよね?」
「うん。結構良い部屋用意してくれたみたい」
一緒に入ろっか。というミツキの言葉に僕は、思わずバスタオル一枚のミツキを想像してしまい、動けずに腰のあたりまで波を被ってしまった。いや、実際に同じ部屋に泊まるという事実を、旅館に着いてから知った時点で、僕はどぎまぎしていて正気を失いかけている。いつ発狂してミツキに食らい付いてもおかしくない。そう、僕はゾンビになりかけている。
砂浜から少し歩いて、坂を上る。切り立った崖の上に建つ温泉旅館は、よくミステリードラマの犯人が、罪を告白するシーンで使われるくらい景観が良かった。なんといっても、この温泉は海を一望できる露天風呂が売りであり、日の出を温泉に入りながら拝むことができる温泉宿ベスト一〇に入っているくらい有名であった。
旅館に戻りロビーで鍵を受け取って部屋に入ると、畳の部屋と、ベッドが二つ並んでいる洋室が隣り合わせになっていて、二人で使うにはあまりにも広すぎた。また、テラスには大きな桶にたっぷりと赤茶色のお湯が張られていて、やはり海を臨むことができる。
「すごいね~~~~!!」
「ほんとすごい!! 地元にこんな場所があったなんて!」
ミツキはテラスに出ると、両手を上げて伸びをしながら気持ちよさそうに瞳を閉じた。心地よい潮風が彼女の髪をなびいていき、僕はその後ろ姿がたまらなく可愛くて。思わず背中を抱き締める。後ろ髪が僕の頬を撫でると、ミツキは振り向いて瞳を再び閉じた。柔らかいミツキの唇を奪うと、僕の右肺と左肺の中心がたまらずに震える。君をもう少しだけ僕だけのものにさせて。アイドルに戻る前に。
「シュン君。温泉に入ってみたいの」
「うん。露天風呂にでもいく? それとも部屋の?」
「露天風呂に行ってみない?」
「うん。そうだね」
外廊下を渡って、離れになっている建物に入ると、そこでミツキとはお別れ。少しだけ寂しかった。だが、僕よりもミツキのほうが重症である。その表情はもはや今生の別れ。繋いでいた手を離す瞬間もミツキの指は僕の指先を求めていて、列車で戦地に向かう恋人の兵士を追いかける幼気《いたいけ》な少女そのもの。ああ、僕の帰りを待っていて。必ずここに、この場所に戻るから。とはいえ、きっと待つのは僕の方なのだけれども。
「シュン君。なるべく早く戻るね。待っててね。先に帰らないで……」
「いや、そんな涙目で言う台詞なの? 大丈夫だよ。絶対にここで待っているから」
待ち合わせ場所は自販機が置いてあるちょっとしたカフェテラス。自販機にはコーヒー牛乳からアイスクリームまで揃っている、湯上りで瀕死の戦士のオアシスのような場所だ。なによりも、女子の帰還を待つ男子にとって、この場所は心の拠り所であろう。それもそのはず。このカフェテラスがなければ、数少ないマッサージチェアを泥仕合《どろじあい》をして奪い合わなければいけないのだから。
予想通り、僕の方が先に帰還してしまった。未だに任を解くことを許されないのだろうか、ミツキ一等兵が帰る気配もなく、ただ僕は彼女の無事を待つ。
きっと、潮騒《しおさい》に思いを馳せているのだろう。夕陽に照らされる水面は微かに柿色に染まっていて、瞳を閉じると心に虚空が浮かび上がる。その情景は何もない大海原に漂《ただよ》う、行く当てのない木片のような自分と、雲一つない朱色に染まる空だ。どこに流されているのか、何のために生を与えられたのか。その答えが出ない脳の中をほとばしる、さざ波の音だけが響く世界。だから、海は思いにふけってしまうのだろう。ミツキが僕と同じ感性ならば、だけれども。
コーヒー牛乳を片手に、丸テーブルに座って廊下を行き交う人視線を注ぐ。
浴衣を着た美少女を、通り過ぎる人々が唖然《あぜん》として視線で追う。アップヘアにした栗色の髪の毛と、その僅《わず》か下に見えるうなじが、さらに人の目をくぎ付けにする。
恐らく、いや絶対にすっぴんなのだろうけど、確実に花神楽美月《はなかぐらみつき》なのだから、もはや人々を救う術はない。みんな魂を抜かれてしまって、もぬけの殻のような表情はゾンビを通り過ごして地縛霊のよう。ミツキを見ることに固執して、仕舞《しまい》に彼氏は彼女に怒られる始末。このままだと阿鼻叫喚《あびきょうかん》になりかねないために、僕はミツキを救い出して椅子に座らせた。廊下の方から顔を背けて、僕と向き合わせる。ミツキにコーヒー牛乳を手渡すと、おいしそうに飲み干した。
「おいし~~。染みるね!」
「温泉のあとっていったら、コーヒー牛乳かフルーツ牛乳だよね!」
「明日の朝はフルーツ牛乳にしよう!」
朝日を見ながら入ることも計画のうちであるために、ミツキはスマホのアラームをこの旅館に着く前から五つもセットしていた。しかも朝四時から五分おきに。スヌーズという機能があることを知らないらしい。
渡り廊下を戻ると、エレベーターの前のにぎやかな空間に視線が行く。温泉旅館、特有のゲーセンだ。先ほどのミツキにもぬけの殻にされた彼氏と、それに業を煮やした彼女がクレーンゲームをしていた。ああ、まずい。ここは、見なかったことにして通り過ぎよう。だが、そうはいかないのが、うちの姫様だ。
「シュン君。ゲームセンターに行ってみたいの」
「言うと思った。温泉旅館といえばゲーセンだもんね」
きっと、ミツキはすっぴんだから、自分が花神楽美月だとは思われまい、なんて思っているに違いない。甘すぎる。すっぴんでもナチュラルメイクをしているような肌だし、エクステをしていない睫毛《まつげ》でも十分に長い。あとどれだけの人を地縛霊に変えちゃうの。怖いよ。
クレーンゲームの中に閉じ込められた地方限定の猫キャラ。キャティちゃんを所望する姫のために二百円を投下する。持ち上がり、出口付近で墜落して脱出失敗。もう一回救出を試みると、キャティが縦穴に真っ逆さまに落ちていく。印籠《いんろう》を持ったキャティちゃんをミツキに手渡すと、とても喜んだ。
「これ、シュン君からのはじめてのプレゼントだね」
「あ……。もっとマシなものをあげればよかった」
「え。可愛いからこれで良かったよ?」
「クレーンゲームの景品が初プレゼントとか。なんかごめん」
いいの、すごく嬉しいから、と言ってミツキは僕の右腕に自分の左腕を絡めてきてゲーセンの奥に進んでいく。右手で抱いたキャティちゃんも笑顔で良かった。ミツキの幸せそうな笑顔に、僕も思わず頬が綻《ほころ》ぶ。
部屋に戻ると食事が準備されていて、海鮮を中心とした料理はとても一人では食べきれる量ではなかった。なぜ田舎はこうも料理の量が多いのか。蕎麦屋にしかり、この旅館にしかり。しかも、あん肝とか白子とか、内容もマニアックすぎる。
しかし、ミツキはお構いなしに珍味を味わって食レポのような感想を僕に伝えると、食べるように勧めてくる。以前、旅番組に出ていた花神楽美月の食する姿が、演技ではないことが明白になった。ちなみに、志桜里は不味いと生放送で口走ってから、食レポはさせてもらえなくなったらしい。阿呆《あほう》だ。
さて、問題の入眠について、だ。ベッドは二つある。ミツキはベッドに入ると部屋を暗くすることを拒んだ。夜が怖い、と。
それについて、僕はまだ聞いていない。なぜ夜が怖いのか。暗闇が怖いのではなく、夜が怖いとミツキは言う。だが、ミツキがなにかトラウマを抱えているのなら、あえてそれを掘り起こす必要もないし、『ミツキは夜が怖い』ということを理解していれば済む話なのだから、騒ぎ立てる必要もない。そう思いながら、電球を点けたままミツキの入ったベッドの隣のベッドに潜り込んだ。
「おやすみ。ミツキ」
「ちょっとぉ。シュン君っていじわる」
「え? 僕なんかした?」
「そうじゃなくて、このままじゃ眠れない」
「……なんで?」
ミツキはベッドから抜け出して、僕のベッドに忍び込んでくる。タオルケットの海を泳いで海面から顔を出すと、僕の鼻先五センチメートルの前で、愛らしい瞳を僕の視界にフェードインしてくる。ベッドサイドのスイッチを押して、電球の明かりを消すと、僕に抱き着いてきた。
「夜は怖いんでしょ。大丈夫なの?」
「シュン君が一緒に寝てくれるなら。多分」
しかし、ミツキは震えていた。まるで怯える子猫のように小刻みに震える姿は、僕にとってもいたたまれずに、ミツキを優しく抱きしめるほかなかった。そんなに怯えないで。なにがあったのか知らないけれど、僕が守ってあげるから。
「電気点けようか?」
だが、いつかのミツキのように、僕の腕の中でかぶりを振る。
ねえシュン君。いいよ。シュン君なら。シュン君ならわたしの全部あげてもいいの。少しだけ怖いけど、シュン君ならきっと大丈夫。だって、シュン君はきっと私の最初で最後の人だから。
重ねた唇が少しだけ震えていて、ミツキの潤んだ瞳が僕を求めている。ミツキの感触が僕の理性を完全に脳内から消し去って、心臓から溢《あふ》れる激流が勢いを落とすことなく全身を駆け巡る。ミツキは微かに呟く。
————シュン君。わたしのこと好き?
好きに決まっている、と肺の底から湧き上がる熱い吐息とともに吐き出した台詞が、ミツキに溶けていった。僕と彼女、二人の両手に指を絡ませて強く握る。
僕の殻を抜け出した魂がミツキの魂に絡みついて、やがて一つになる。それは、愛を育むなどという簡単な言葉で済ませるほど単純ではない。火照る身体を抱き締めて重なる体温と満たされない唇が、ミツキをさらに求める。
シュン君お願い。このままわたしを……。シュン君大好き。シュン君。止めないで。シュン君大好き。シュン君。
————シュン君。愛している。
◇◆◇
まだ怖いの?
そう訊いた僕の言葉に、少し考えて、ベッドから起き上がったミツキはバスタオルを身体に巻いて窓を開けた。月に照らされた美しい肢体《したい》が浮かび上がると同時に、影法師が僕の足元まで伸びる。青い光に満ちた部屋の中は、少しだけ神秘的だった。風を感じたミツキの素肌はとても白く、まるで硝子細工《がらすざいく》のよう。
怖いけど、シュン君と一緒なら平気。
再び僕の元に歩み寄るミツキは、僕の頬にキスをして微笑みながら言う。
シュン君。これでもう結婚するしかないね、と。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

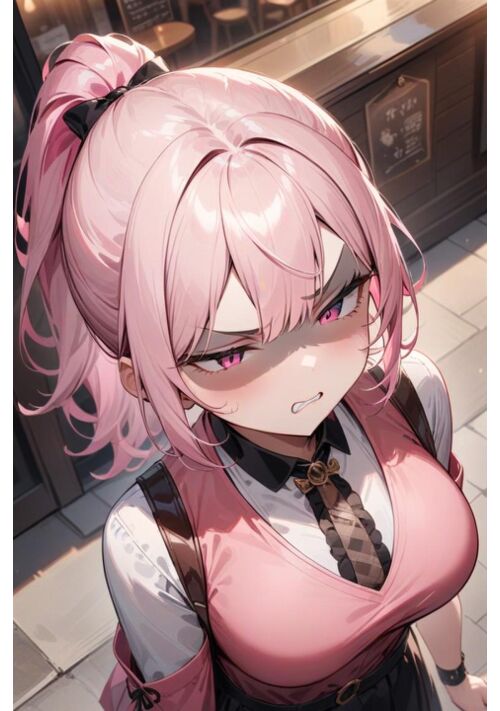
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















