25 / 61
明け易し夏 ミツキの疑惑
儚き追憶と甘い口づけ
しおりを挟む
面白くなってきましたね、なんて他人事のように話す怜《れん》さんは、かき氷で緑色になった舌を僕に見せながら呟《つぶや》く。この人はゾンビではなく、ただの吸血鬼だ。プラチナブロンドの髪と整った顔立ちは、まるでヴァンパイアのようで、きっと今宵も誰かの生き血を啜《すす》るに違いない。なんて想像してしまうのだが、実際のところ二次元をこよなく愛するアニメオタクなのだから、世の中なにが真実なのか分からなくなってくる。
ステージ上で火花を散らす美女たちが、一斉に敵意をむき出しにするのが、うちの姫。牡丹《ぼたん》の大正美人は、まるで城下に繰り出したお姫様で、僕の守るべき人。なのに、僕はゾンビに阻《はば》まれて進むことができずに、すでに諦めている。ナイト、いや御目見《おめみえ》といったところか、どちらにしてもすでに失格であろう。怜さんは、朱莉《あかり》が勝つと信じて疑わない。
浴衣を着た男女のペアの司会で進める浴衣美人コンテストは、只《ただ》ならぬ熱気に包まれていた。現在進行形で世間を騒がす花神楽美月《はなかぐらみつき》が、変装もせずにステージ上でもじもじする姿を一目見ようと血みどろの戦いを繰り広げているのは、ステージ階下の一般市民だ。一斉にスマホで集中砲火されたミツキは、もはや逃げ場などあるはずもなく、ただ俯《うつむ》いていた。
「ああ。これで明日のつぶやきランキング上位に、花神楽美月のしょんぼり浴衣姿じわる、が食い込んできそうだよね。もうみんなミツキちゃんを弄《いじ》りたくて仕方ないみたいだし」
怜さんが言うように、花神楽美月はなにかと弄られる。例の不倫事件からずっとその兆候が続いていて、僕の名前が出たことで更に酷くなっていた。
しかし、そこで黙っていないのがミツキだ。人前から姿を消さずに、逆に印象を変えろ、というのが姉さん——倉山咲菜《くらやまさな》の入れ知恵を真に受けた。お客さんと一体となって笑い合えることができれば、きっとSNSを変えることができる。そんなこと言っても、まさか、お盆縁日から実践することになるなんて。この浴衣美女コンテストは、完全に計算外である。やってくれたな朱莉のやつ。
「まずは、エントリーナンバー一番、唐沢ミナミさんです。自己紹介をお願いします」
司会の女性の声が町中のスピーカーから響き渡り、まるで防災無線のように音が割れていた。音量の調整が上手くいっていないのだろう。すごく不快である。
「唐沢ミナミです。一八歳です」
「得意なこととか、趣味とかあれば教えてください」
「バレーボールをずっとやっていました。趣味は、読書です」
はい、ありがとうございます、と司会の女性がステージ上で仕切ると、唐沢さんはステージの奥に戻っていく。横一列に並んだ浴衣美人たちは、緊張した面持ちで自分の出番を待っていて、なんだか処刑を待つ死刑囚のようだ。しかし、一人だけ緊張もせずに、やたらとやる気を出している少女がいる。しかも、名前を呼ばれると、頭脳明晰《ずのうめいせき》な小学生のようにはきはきとした言葉で返事をして、手を上げて前に出る姿はもはや、選挙に出馬するベテラン議員のようだ。
「野々村朱莉。十七歳です!! 好きな食べ物は肉。得意な事はダンス……いや、手料理ですッ!!」
「げ、元気ですね。他になにか会場の皆さんに伝えたいことはありますか?」
「はいッ!! 絶対にミツキちゃんに勝って、シュンを貰い受けますから!! 応援よろしくお願いしますッ!!」
「な、なに言ってんだあいつ。本気で僕を殺しにかかってきたな」
「さすが、妹。堂々としていて優勝間違いなしだね」
太ももに額がつくのではないかと思うほど、深くお辞儀をした朱莉は、顔を上げると僕の瞳を射抜くように見ては不敵に笑う。どこからその自信が来るのか、と逆に応援したくなるから不思議だ。
そして、いよいよ来てしまったミツキの出番。司会者に促されて、ステージの前方に立つと、深呼吸をして俯きながらしばらく黙り込む。まるで泣いているのか、と思えるほど肩で息をするものだから、ステージ前の今にも暴れそうなゾンビたちも息を呑んで見守る他ない。中には、がんばれ、と檄《げき》を飛ばす者まで現れる次第。これはいよいよ、花神楽美月も民衆の勢いに負けたのか、と誰もが思ったときだった。
顔を上げたミツキは完全に花神楽美月の顔になっていて、細めた瞳がステージ下の右から左、左から右に視線を投げかける。薄桃色の唇が僅《わず》かに開くと、艶《あで》やかに上唇を舐めた。花神楽美月の癖である。
「みんな……今日はありがとぉぉぉぉぉぉ!!!」
とんでもない笑顔を振りまきながら、司会者から奪い取ったマイクで叫ぶと、一斉にゾンビたちが餌に食らい付いた。檻に投げ込まれた生肉を一斉に貪《むさぼ》りつくす猛獣たちは、花神楽美月の声に完全に魅了されたようで、かわいい、とか、大好き、という言葉で愛を叫び始める。
てめえら、今日はぶっ飛んでいこうぜ、と再び叫ぶと、熱狂の渦がステージの周りを包み込んで、身動きが取れないくらいに混み始めた。
そうか。姿を見せない花神楽美月のことはいくらでも誹謗中傷で殺せるけれども、実際本人を目の前にして、しかも自分がその一部だと実感したとき、人は、共感という感情を覚えるのか。ライブの一体感、とはよく言ったものだ。花神楽美月と一つになった会場は、もはや彼女の顎《あご》一つでどうにでもなる状況だろう。一言で民衆の心を掴むなんて。まるでマスケット銃を持ちながらフランス国旗を振るう、自由の女神のようだ。マスケット銃で撃ち殺された人は数知れず。撃たれたゾンビは、ミツキの手足となって働く。スマホで撮った写真に言葉を添えてツイートする。花神楽美月最高ッ!! っと。
「わたしの得意なこと……みんな知ってるよね!! 教えて!!」
マイクをステージ下に向けたミツキに浴びせられる言葉は、ダンスと歌。しかし、中には花プリの狂信者であるプリズマーと思われるものが紛れていた。その証拠に、殺し文句、という謎の檄《げき》が飛んだのだから、意味が分からない。しかし、その言葉にいち早く反応した花神楽美月は、少しだけ身体を斜めに向けて唇に人差し指を当てて——静かにと告げるジェスチャー——僅かに呟く。
「瞳に恋する二秒前。君はすで落ちている」
花神楽美月の決め台詞である。正直意味が分からないのだが、なぜかプリズマーはそれで満足して倒れこむ。ますます意味が分からない。だが、花神楽美月と空気を共有しているゾンビたちは、実際に、恋する数秒前に落ちたらしい。司会者が時計を気にしつつ、マイクを取り返しにかかると、ようやく花神楽美月はステージ後ろに戻る。朱莉をはじめとした美女たちの視線も気にすることなく、スイッチの入ったミツキは堂々としていて格の違いを見せつけた。それはステージ下から見ても明らかだ。
「花神楽美月ってやっぱりすごいんだね。シュン君の将来はいかにも大変そうだ」
「はは……。いや、大丈夫ですよ……多分」
全員の紹介が終わったところで記念撮影になる。その場でプリントアウトされた写真は、本部のとなりのテントに貼りだされて、お客さんが自由に投票をする。花火の始まる九時直前に再びステージ上に召集されて大々的に発表される。その後は表彰式という運びだ。ミツキは謹慎中とはいえ現役アイドルなのに写真なんて撮られて大丈夫なのか、と心配になったのだが、スイッチの入った本人は写真にも気合が入っていて、すでに吹っ切れている。明日が怖い。絶対にマネージャー高梨に怒られる。その矛先は僕にも飛んでくる気がする。
ステージから降りたミツキは花神楽美月の仮面が取れていて、僕に微笑みかける姿は、やはり天使のようだった。ステージ上でのクールな台詞と雰囲気、そして目つきからは想像もできないほど愛くるしい眼差しは僕だけのもの。僕が再び恋に落ちるまでに二秒もかかるはずがない。お待たせ、と言って、遠慮がちに僕の小指に人差し指を絡めてくるミツキは微かに口開く。
シュン君の瞳なら恋するのに一秒も掛からないね、と。それはミツキだけだよ、なんて僕の口が言うけれど、胸は張り裂けそうだった。
僕とミツキの二人だけの時間————だと思っていたのに、すぐに囲まれてしまう。当たり前だ。ミツキは慌てて指を離すが、すでに遅し。サインください、までは良かったのだけれど、写真を一緒に撮ってください、はさすがに拒否したかった。中には、本当に付き合っていたのですね、なんて核心を突いてくる強者だっているくらいだ。しかし、僕の予想していた反応とは大分違うものだった。
「二人が付き合っているなら、応援します!」
「浴衣美女コンテスト最高でした。まじで応援してます」
「倉美月春夜さんとお似合いだと思います。地元の誇りです」
本当にかっこよかった。想像と違って、すごい良い子じゃん。がんばって美月ちゃん。応援しているから。倉美月くんと本当お似合い。羨ましい。必ず復帰してくださいね。
————絶対に負けないで。
一人一人の言葉が零《こぼ》れたワインのように心に染みて、その微かな香りが自分の中の呼吸を止めそうな魂に共鳴すると、僅かに震えていた。まさか、激励《げきれい》を貰えると思っていなかったのだろう。ミツキは本当に嬉しそうで、涙ぐんでいた。それを見たお客さんも、彼女の境遇を想像したのだろうか、もらい泣きをする人まで現れる。大変だったね、なんて。
賛否あるネットの情報はどれも、当たっているようで外れている。要はどれが真実か分からない。ミツキを見たこともない人は、悪い噂を信じてやまないのに、こうして目の前で喋り出すミツキを見た人は、花神楽美月は嵌《は》められた、という噂を信じ始める。素のミツキは優しくて、素直で、心からかわいいと思える性格なのだから、誰もがそうなるのは当然だとして。それにしても勝手なものだ。
人をかき分けて、なんとか辿り着いた綿菓子の出店前。いつか約束した、イベントがあれば買ってあげるという言葉を遂行できるのだから、やっと肩の荷が下りるというもの。綿菓子屋のおじさんは、僕に綿菓子を手渡すと、こっちにおいで、と手招きをする。テントの裏にある扉を開いて中に入れてくれるおじさんは、ここは安全だよ、と言って前歯が欠けた笑顔を僕とミツキに投げかけた。
中は喫茶店になっていて、少し前に妻が亡くなってしまい泣く泣く閉店したのだという。それでも、毎日掃除を怠《おこた》っていないようで、とても清潔感があった。観葉植物が至る所に置いてあって、アンティークのドーベルマンが陶器の置物となって店内を見張っていた。
バーカウンターに二人肩を並べて腰かけると、ミツキは嬉しそうに綿菓子にかぶりついた。口の周りについた雪のような綿菓子を指摘するとミツキは、シュン君とって、と甘えてくる。仕方ない、なんて言ってみたけれど、それは嘘。可愛くて可愛くて、どう表現をしたらいいのか分からないほど。とにかく抱きしめたかった。
「やっと二人きりになれたね。家に帰るまで無理かな、なんて思ってた」
「いや、正直、朱莉にはやられたって思ったけど、結果オーライになってびっくりしたよね」
「でも、負けたら朱莉ちゃんにシュン君取られちゃう。どうしよう」
そんなこと言って、僕の左腕に右腕を絡みつけてくるミツキは確信犯だ。だって、僕の気持ちはすべてがミツキに向いているのだから、朱莉に取られるはずがない。そんなこと当たり前だ。
「負けないと思うけど。でも負けたら、朱莉のところに行くしかないよね」
「もう意地悪。そうやってすぐにいじめるんだから。でも、朱莉ちゃん、少し可哀そうかな」
「うん。朱莉にはやく幸せになってもらいたいんだけど、なんとかならないかな」
シュン君を取っちゃって少し悪いと思っているんだ、と呟くミツキは、朱莉のことも好きだと話す。いつでも前向きで友達想いの朱莉は、きっとミツキのことなど恨んではいない。だからこそ、心が痛いのだと思う。むしろ罵《ののし》り合って大喧嘩するくらいの相手なら、すっきりするのかもしれないけれど。朱莉に早く僕なんかよりも、ずっと素敵で朱莉想いの人が現れますように。
「でも、朱莉ちゃんに悪いとは思っていても、自分の気持ちに嘘はつけない。シュン君がいない日々なんて考えられないもん」
「うん。もちろん。僕だって、それは同じだし。ミツキがいたからこそ、毎日自分を呪っていた自分の殻から出て来れたようなものなんだ。だから、ありがとうを言いたいよ」
美味しそうに食べるミツキの綿菓子を、僕も一口貰って食べる。口の中で凝縮する甘味が切なく舌の上をほとばしっていく。おいしいでしょ、と言って、ミツキは僕の口に綿菓子を優しく詰め込んだ。少しだけミツキの指に触れた唇が、その感じたぬくもりのいつまでも消えない残り香に、なんだか切ない気持ちになった。
「綿菓子って雪みたいだよね。口の中ですぐになくなっちゃう雪。お母さんが死んじゃう少し前に一緒に行ったお祭りで綿菓子を買ったの。お母さんと二人で食べた綿菓子がすごく甘くて、切なくて。でも、お母さんはわたしに、雪だって積もればなかなか融《と》けないのよって言って。口についた綿菓子を取ってくれたんだ。シュン君みたいに」
積もった雪は融けない、か。どういう想いでお母さんが言ったのかは分からないけれど。でも、ミツキのお母さんは優しい人だったのだろうと思う。
「だから、綿菓子とシュン君は外せないっていうか、なんだろう。つまり大好きってこと」
「うん。じゃあ、ミツキの誕生日は綿菓子でいっぱいにして、ミツキに雪を降らせてあげるよ」
「ほんと!? 三月が楽しみ」
綿菓子を食べ終わるころには、摺《す》り硝子《がらす》の向こう側の派手な世界を見て、雑踏《ざっとう》をしきりに気にする耳を無視しながら、僕とミツキは唇を重ねていた。
甘く、少しだけ切ない香りを楽しみながら。二度目のキスは完全にミツキの色に染まっていて、ストロベリーの香りを嗅《か》ぎたくて抱き締めていた。
ミツキの紅潮した頬は、まるで初恋の人を見る穢《けが》れなき少女のようで、三度目のキスで、再び僕の心を奪っていく。何度目の初恋だろう、か。
「シュン君。もっとして」
「ミツキ。唇なくなっちゃうよ?」
今度はミツキが僕を抱き締めると、再びキスをした。永遠のように感じたキスは、何度目のファーストキスだったのだろう。キスをするたびに恋に落ちる僕。
僕の首の後ろに手を回したミツキは、耳元で優しく囁《ささや》く。
————ずっと一緒にいて。キスをして。
気付くと、浴衣美人コンテストの結果発表の時間になっていた。
ステージ上で火花を散らす美女たちが、一斉に敵意をむき出しにするのが、うちの姫。牡丹《ぼたん》の大正美人は、まるで城下に繰り出したお姫様で、僕の守るべき人。なのに、僕はゾンビに阻《はば》まれて進むことができずに、すでに諦めている。ナイト、いや御目見《おめみえ》といったところか、どちらにしてもすでに失格であろう。怜さんは、朱莉《あかり》が勝つと信じて疑わない。
浴衣を着た男女のペアの司会で進める浴衣美人コンテストは、只《ただ》ならぬ熱気に包まれていた。現在進行形で世間を騒がす花神楽美月《はなかぐらみつき》が、変装もせずにステージ上でもじもじする姿を一目見ようと血みどろの戦いを繰り広げているのは、ステージ階下の一般市民だ。一斉にスマホで集中砲火されたミツキは、もはや逃げ場などあるはずもなく、ただ俯《うつむ》いていた。
「ああ。これで明日のつぶやきランキング上位に、花神楽美月のしょんぼり浴衣姿じわる、が食い込んできそうだよね。もうみんなミツキちゃんを弄《いじ》りたくて仕方ないみたいだし」
怜さんが言うように、花神楽美月はなにかと弄られる。例の不倫事件からずっとその兆候が続いていて、僕の名前が出たことで更に酷くなっていた。
しかし、そこで黙っていないのがミツキだ。人前から姿を消さずに、逆に印象を変えろ、というのが姉さん——倉山咲菜《くらやまさな》の入れ知恵を真に受けた。お客さんと一体となって笑い合えることができれば、きっとSNSを変えることができる。そんなこと言っても、まさか、お盆縁日から実践することになるなんて。この浴衣美女コンテストは、完全に計算外である。やってくれたな朱莉のやつ。
「まずは、エントリーナンバー一番、唐沢ミナミさんです。自己紹介をお願いします」
司会の女性の声が町中のスピーカーから響き渡り、まるで防災無線のように音が割れていた。音量の調整が上手くいっていないのだろう。すごく不快である。
「唐沢ミナミです。一八歳です」
「得意なこととか、趣味とかあれば教えてください」
「バレーボールをずっとやっていました。趣味は、読書です」
はい、ありがとうございます、と司会の女性がステージ上で仕切ると、唐沢さんはステージの奥に戻っていく。横一列に並んだ浴衣美人たちは、緊張した面持ちで自分の出番を待っていて、なんだか処刑を待つ死刑囚のようだ。しかし、一人だけ緊張もせずに、やたらとやる気を出している少女がいる。しかも、名前を呼ばれると、頭脳明晰《ずのうめいせき》な小学生のようにはきはきとした言葉で返事をして、手を上げて前に出る姿はもはや、選挙に出馬するベテラン議員のようだ。
「野々村朱莉。十七歳です!! 好きな食べ物は肉。得意な事はダンス……いや、手料理ですッ!!」
「げ、元気ですね。他になにか会場の皆さんに伝えたいことはありますか?」
「はいッ!! 絶対にミツキちゃんに勝って、シュンを貰い受けますから!! 応援よろしくお願いしますッ!!」
「な、なに言ってんだあいつ。本気で僕を殺しにかかってきたな」
「さすが、妹。堂々としていて優勝間違いなしだね」
太ももに額がつくのではないかと思うほど、深くお辞儀をした朱莉は、顔を上げると僕の瞳を射抜くように見ては不敵に笑う。どこからその自信が来るのか、と逆に応援したくなるから不思議だ。
そして、いよいよ来てしまったミツキの出番。司会者に促されて、ステージの前方に立つと、深呼吸をして俯きながらしばらく黙り込む。まるで泣いているのか、と思えるほど肩で息をするものだから、ステージ前の今にも暴れそうなゾンビたちも息を呑んで見守る他ない。中には、がんばれ、と檄《げき》を飛ばす者まで現れる次第。これはいよいよ、花神楽美月も民衆の勢いに負けたのか、と誰もが思ったときだった。
顔を上げたミツキは完全に花神楽美月の顔になっていて、細めた瞳がステージ下の右から左、左から右に視線を投げかける。薄桃色の唇が僅《わず》かに開くと、艶《あで》やかに上唇を舐めた。花神楽美月の癖である。
「みんな……今日はありがとぉぉぉぉぉぉ!!!」
とんでもない笑顔を振りまきながら、司会者から奪い取ったマイクで叫ぶと、一斉にゾンビたちが餌に食らい付いた。檻に投げ込まれた生肉を一斉に貪《むさぼ》りつくす猛獣たちは、花神楽美月の声に完全に魅了されたようで、かわいい、とか、大好き、という言葉で愛を叫び始める。
てめえら、今日はぶっ飛んでいこうぜ、と再び叫ぶと、熱狂の渦がステージの周りを包み込んで、身動きが取れないくらいに混み始めた。
そうか。姿を見せない花神楽美月のことはいくらでも誹謗中傷で殺せるけれども、実際本人を目の前にして、しかも自分がその一部だと実感したとき、人は、共感という感情を覚えるのか。ライブの一体感、とはよく言ったものだ。花神楽美月と一つになった会場は、もはや彼女の顎《あご》一つでどうにでもなる状況だろう。一言で民衆の心を掴むなんて。まるでマスケット銃を持ちながらフランス国旗を振るう、自由の女神のようだ。マスケット銃で撃ち殺された人は数知れず。撃たれたゾンビは、ミツキの手足となって働く。スマホで撮った写真に言葉を添えてツイートする。花神楽美月最高ッ!! っと。
「わたしの得意なこと……みんな知ってるよね!! 教えて!!」
マイクをステージ下に向けたミツキに浴びせられる言葉は、ダンスと歌。しかし、中には花プリの狂信者であるプリズマーと思われるものが紛れていた。その証拠に、殺し文句、という謎の檄《げき》が飛んだのだから、意味が分からない。しかし、その言葉にいち早く反応した花神楽美月は、少しだけ身体を斜めに向けて唇に人差し指を当てて——静かにと告げるジェスチャー——僅かに呟く。
「瞳に恋する二秒前。君はすで落ちている」
花神楽美月の決め台詞である。正直意味が分からないのだが、なぜかプリズマーはそれで満足して倒れこむ。ますます意味が分からない。だが、花神楽美月と空気を共有しているゾンビたちは、実際に、恋する数秒前に落ちたらしい。司会者が時計を気にしつつ、マイクを取り返しにかかると、ようやく花神楽美月はステージ後ろに戻る。朱莉をはじめとした美女たちの視線も気にすることなく、スイッチの入ったミツキは堂々としていて格の違いを見せつけた。それはステージ下から見ても明らかだ。
「花神楽美月ってやっぱりすごいんだね。シュン君の将来はいかにも大変そうだ」
「はは……。いや、大丈夫ですよ……多分」
全員の紹介が終わったところで記念撮影になる。その場でプリントアウトされた写真は、本部のとなりのテントに貼りだされて、お客さんが自由に投票をする。花火の始まる九時直前に再びステージ上に召集されて大々的に発表される。その後は表彰式という運びだ。ミツキは謹慎中とはいえ現役アイドルなのに写真なんて撮られて大丈夫なのか、と心配になったのだが、スイッチの入った本人は写真にも気合が入っていて、すでに吹っ切れている。明日が怖い。絶対にマネージャー高梨に怒られる。その矛先は僕にも飛んでくる気がする。
ステージから降りたミツキは花神楽美月の仮面が取れていて、僕に微笑みかける姿は、やはり天使のようだった。ステージ上でのクールな台詞と雰囲気、そして目つきからは想像もできないほど愛くるしい眼差しは僕だけのもの。僕が再び恋に落ちるまでに二秒もかかるはずがない。お待たせ、と言って、遠慮がちに僕の小指に人差し指を絡めてくるミツキは微かに口開く。
シュン君の瞳なら恋するのに一秒も掛からないね、と。それはミツキだけだよ、なんて僕の口が言うけれど、胸は張り裂けそうだった。
僕とミツキの二人だけの時間————だと思っていたのに、すぐに囲まれてしまう。当たり前だ。ミツキは慌てて指を離すが、すでに遅し。サインください、までは良かったのだけれど、写真を一緒に撮ってください、はさすがに拒否したかった。中には、本当に付き合っていたのですね、なんて核心を突いてくる強者だっているくらいだ。しかし、僕の予想していた反応とは大分違うものだった。
「二人が付き合っているなら、応援します!」
「浴衣美女コンテスト最高でした。まじで応援してます」
「倉美月春夜さんとお似合いだと思います。地元の誇りです」
本当にかっこよかった。想像と違って、すごい良い子じゃん。がんばって美月ちゃん。応援しているから。倉美月くんと本当お似合い。羨ましい。必ず復帰してくださいね。
————絶対に負けないで。
一人一人の言葉が零《こぼ》れたワインのように心に染みて、その微かな香りが自分の中の呼吸を止めそうな魂に共鳴すると、僅かに震えていた。まさか、激励《げきれい》を貰えると思っていなかったのだろう。ミツキは本当に嬉しそうで、涙ぐんでいた。それを見たお客さんも、彼女の境遇を想像したのだろうか、もらい泣きをする人まで現れる。大変だったね、なんて。
賛否あるネットの情報はどれも、当たっているようで外れている。要はどれが真実か分からない。ミツキを見たこともない人は、悪い噂を信じてやまないのに、こうして目の前で喋り出すミツキを見た人は、花神楽美月は嵌《は》められた、という噂を信じ始める。素のミツキは優しくて、素直で、心からかわいいと思える性格なのだから、誰もがそうなるのは当然だとして。それにしても勝手なものだ。
人をかき分けて、なんとか辿り着いた綿菓子の出店前。いつか約束した、イベントがあれば買ってあげるという言葉を遂行できるのだから、やっと肩の荷が下りるというもの。綿菓子屋のおじさんは、僕に綿菓子を手渡すと、こっちにおいで、と手招きをする。テントの裏にある扉を開いて中に入れてくれるおじさんは、ここは安全だよ、と言って前歯が欠けた笑顔を僕とミツキに投げかけた。
中は喫茶店になっていて、少し前に妻が亡くなってしまい泣く泣く閉店したのだという。それでも、毎日掃除を怠《おこた》っていないようで、とても清潔感があった。観葉植物が至る所に置いてあって、アンティークのドーベルマンが陶器の置物となって店内を見張っていた。
バーカウンターに二人肩を並べて腰かけると、ミツキは嬉しそうに綿菓子にかぶりついた。口の周りについた雪のような綿菓子を指摘するとミツキは、シュン君とって、と甘えてくる。仕方ない、なんて言ってみたけれど、それは嘘。可愛くて可愛くて、どう表現をしたらいいのか分からないほど。とにかく抱きしめたかった。
「やっと二人きりになれたね。家に帰るまで無理かな、なんて思ってた」
「いや、正直、朱莉にはやられたって思ったけど、結果オーライになってびっくりしたよね」
「でも、負けたら朱莉ちゃんにシュン君取られちゃう。どうしよう」
そんなこと言って、僕の左腕に右腕を絡みつけてくるミツキは確信犯だ。だって、僕の気持ちはすべてがミツキに向いているのだから、朱莉に取られるはずがない。そんなこと当たり前だ。
「負けないと思うけど。でも負けたら、朱莉のところに行くしかないよね」
「もう意地悪。そうやってすぐにいじめるんだから。でも、朱莉ちゃん、少し可哀そうかな」
「うん。朱莉にはやく幸せになってもらいたいんだけど、なんとかならないかな」
シュン君を取っちゃって少し悪いと思っているんだ、と呟くミツキは、朱莉のことも好きだと話す。いつでも前向きで友達想いの朱莉は、きっとミツキのことなど恨んではいない。だからこそ、心が痛いのだと思う。むしろ罵《ののし》り合って大喧嘩するくらいの相手なら、すっきりするのかもしれないけれど。朱莉に早く僕なんかよりも、ずっと素敵で朱莉想いの人が現れますように。
「でも、朱莉ちゃんに悪いとは思っていても、自分の気持ちに嘘はつけない。シュン君がいない日々なんて考えられないもん」
「うん。もちろん。僕だって、それは同じだし。ミツキがいたからこそ、毎日自分を呪っていた自分の殻から出て来れたようなものなんだ。だから、ありがとうを言いたいよ」
美味しそうに食べるミツキの綿菓子を、僕も一口貰って食べる。口の中で凝縮する甘味が切なく舌の上をほとばしっていく。おいしいでしょ、と言って、ミツキは僕の口に綿菓子を優しく詰め込んだ。少しだけミツキの指に触れた唇が、その感じたぬくもりのいつまでも消えない残り香に、なんだか切ない気持ちになった。
「綿菓子って雪みたいだよね。口の中ですぐになくなっちゃう雪。お母さんが死んじゃう少し前に一緒に行ったお祭りで綿菓子を買ったの。お母さんと二人で食べた綿菓子がすごく甘くて、切なくて。でも、お母さんはわたしに、雪だって積もればなかなか融《と》けないのよって言って。口についた綿菓子を取ってくれたんだ。シュン君みたいに」
積もった雪は融けない、か。どういう想いでお母さんが言ったのかは分からないけれど。でも、ミツキのお母さんは優しい人だったのだろうと思う。
「だから、綿菓子とシュン君は外せないっていうか、なんだろう。つまり大好きってこと」
「うん。じゃあ、ミツキの誕生日は綿菓子でいっぱいにして、ミツキに雪を降らせてあげるよ」
「ほんと!? 三月が楽しみ」
綿菓子を食べ終わるころには、摺《す》り硝子《がらす》の向こう側の派手な世界を見て、雑踏《ざっとう》をしきりに気にする耳を無視しながら、僕とミツキは唇を重ねていた。
甘く、少しだけ切ない香りを楽しみながら。二度目のキスは完全にミツキの色に染まっていて、ストロベリーの香りを嗅《か》ぎたくて抱き締めていた。
ミツキの紅潮した頬は、まるで初恋の人を見る穢《けが》れなき少女のようで、三度目のキスで、再び僕の心を奪っていく。何度目の初恋だろう、か。
「シュン君。もっとして」
「ミツキ。唇なくなっちゃうよ?」
今度はミツキが僕を抱き締めると、再びキスをした。永遠のように感じたキスは、何度目のファーストキスだったのだろう。キスをするたびに恋に落ちる僕。
僕の首の後ろに手を回したミツキは、耳元で優しく囁《ささや》く。
————ずっと一緒にいて。キスをして。
気付くと、浴衣美人コンテストの結果発表の時間になっていた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

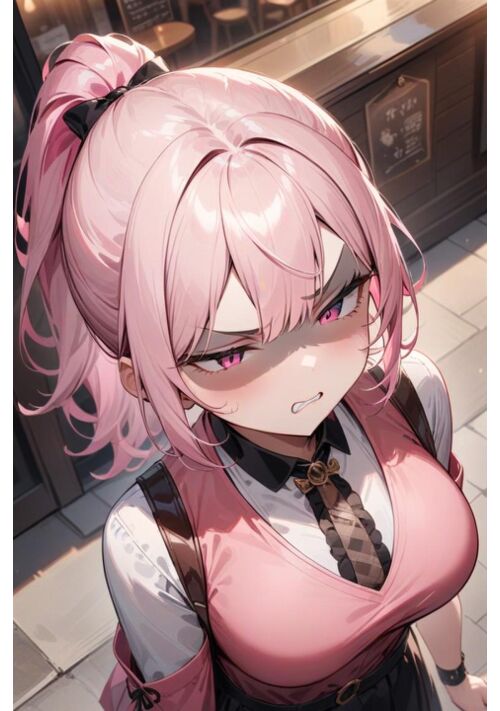
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















