24 / 61
明け易し夏 ミツキの疑惑
逆襲の野々村朱莉
しおりを挟む
離れから出てきたミツキの、淡い桃色の牡丹《ぼたん》で彩られた召し物が大正ロマンを奏でていて、小さく纏《まと》められた栗色の髪から咲いた木槿《むくげ》が、桜のように色づく。仄《ほのか》かに染まった頬の薄桃色のチークが僅《わず》かに持ち上がると、思わず抱きしめたくなった。浴衣を着たミツキは本当に綺麗で、僕のか弱い心臓を静かにノックする。
「シュン君。どうかな? 自分で着てみたんだけど、おかしくない?」
俯き加減で僕を見る上目遣いのミツキは、悪戯を半分、甘えを半分、僕の瞳を呑み込んでいく。きっと、浴衣を着た自分を褒めて欲しいのだろう。僕は真顔でじっと見つめる。あまりにも可愛すぎて、ついつい意地悪をしたくなってしまう。
「どうかな。うーん」
まじまじとミツキの眉間に視線を向けて、そのまま鼻を通り、唇、顎、首筋、襟にゆっくりと移していく。腰から脚、つま先に落ちていく頃には、ミツキは頬を膨らませていた。
「もう。知らないッ!! シュン君の意地悪……」
だけど、僕もすでに限界を通り過ぎていた。朱色の中に浮かぶ淡紅色《たんこうしょく》のシャボン玉のようなネイルカラーの指先を手に取って、僕は優しく、傷つけないように触れてから握るとミツキを見て言う。本当に綺麗だね、と。
「可愛くて、触れたら消えちゃうんじゃないかってくらいに、儚《はかな》いというか、可憐というか」
纏まらない言葉の欠片が宙を舞っていく。しかし、ミツキの拾い集める僕のばらばらになった破片が形を成していくように、一つになって彼女に染みていく。まるで、雫が落ちる水面のように波紋を広げてミツキの表情が明るく満ちていった。
「うん。シュン君ありがとう。行こう」
触れたままの手を握り返して、僕の手のひらを包んだミツキの暖かい手は、やがて指と指を絡めていき、僕の心まで引っ張っていった。
僕たちの住む町の商店街と神社が中心となって行われるお盆縁日は、とにかく派手で、毎年道路を封鎖して出店合戦が繰り広げられる。道路の真ん中に作られたステージ上で行われる浴衣美女コンテストや、盆踊りをパレードのように流しで行う、盆踊りコンテストも有名で賞品が家電とあって、大盛り上がりを見せていた。
「バレないかな?」
「バレる……と思う。でも、もう今更だよ。SNSで知らない人いないし。それに変装しないで行きたいっていったのはミツキじゃん。なにをしたって無駄な気がするんだけど」
「うん……そうだね。でもシュン君は迷惑じゃないの?」
「ミツキが大丈夫なら、僕は全く気にしないよ。それよりも、なんで変装しなかったの?」
「浴衣……せっかくの浴衣をいただいて、着たんだから、素のままの自分でって。分かるかな。この気持ち」
「————うん。なんとなく。でも、危険じゃない?」
「その時はシュン君が守ってくれるんでしょ? それにアスカさんの言っていたこともあるし。ちょっと戦ってみようかなって」
お盆縁日は薄暗い夕方から始まって、夜九時の花火で終了となる。昼間とはまた顔の見え方が違うんじゃないか、という期待は簡単に裏切られた。どこを歩いても明るい。それもそのはずで、数十メートルの等間隔で電柱に固定された投光器が道を照らしている、防犯対策もばっちりというわけだ。しかも、思った以上に人の出が多く、田舎のどこから湧いて出て来たのか、と思うほど活気があった。
「お、春夜!!」
ああ、見つかった、と顔を背けるも、すでに僕の視界に入ってくる見知れた顔の男。彼女と手を繋いで歩くサッカー部のエース。その名も涼森新之助。そして、紺色をベースに、黒っぽい紅葉が描かれた浴衣の少女は園部三和子だ。うなじを見せた妖艶な姿は、まるで和風魔女。呪術師とも取れるけれど、とても綺麗だった。なんて口に出して言えるはずもない。ミツキが拗《す》ねるから。
「新之助か。びっくりさせないでよ」
「お前、社会一般を敵に回したな。そのうちスナイパーに撃ち殺されるぞ」
「涼森君、こんばんは。シュン君を撃ち殺すの?」
真面目な顔をして怖いことを言うミツキに、新之助はそうだよ、なんて吹き込むものだから、たちが悪い。しかも、園部三和子まで、一回撃ち殺したほうが良いのかも、なんて言うのだから僕がどう見られているのかが想像つくというものだ。どうせ僕は、ミツキを独り占めしたカス男ですよ。ネットではクソミツキとかって言われているみたいだし。ええ、気にしないですけどね。
「ところで、新之助はステージ前でなにしてんの?」
「新之助くんが、納豆カレー大食い大会に出るって聞かないのよ。出場者にうちの高校の野球部の佐々木君と、ラグビー部の鈴木君、それに、レスリング部の相川君の名前があるから、サッカー部は誰も出ないのか、って」
「大食い大会ですか? シュン君は出ちゃだめだよ!?」
「出ないよ!! ミツキは僕のことなんだと思っているの……」
「お前ら。いいか。大食い大会で優勝したら、旅行券一〇万円分だぞ。俺は絶対に取る。そして、二人でハワイ旅行に行くんだ」
行けねえよ、とツッコミを入れようとした僕の代わりに、園部三和子が、ハワイ旅行なんて夢みたい、なんて真面目に言い放つ。僕とミツキは呆気に取られてただ笑うしかなかった。苦笑という種類のやつ。それにしても、納豆カレーというチョイスはいかがなものなのか。街の名物ではあるのだけれども。
ステージに上がった新之助は、ガチガチに緊張をしていて、まるで冷凍庫で一人裸で凍える類人猿のようだ。司会がマイクを向けて意気込みを聞いても、頑張りしゃす、と意味の分からないガッツを見せる新之助は、すでに気持ちで負けている。
いざ、男の真剣勝負が始まると、ラグビー部の鈴木が大皿の納豆カレーをものの三〇秒で平らげて二皿目。ほかのメンツも鈴木には遠く及ばずに、皆同じようなペースで熾烈《しれつ》な二位争いをしている。
やがて、ラグビー部の鈴木が五皿目で音《ね》を上げる頃には、他のメンツは三皿目で顔面蒼白であった。どう見ても、新之助に勝ち目はない。むしろ、よくここまで食べられたな。納豆カレーを。
「新之助くんは、納豆がだめなのに。よくここまで……」
隣でとんでもない真実を告げる園部三和子に、ミツキは奇声のような声で驚き、ありえない、と新之助の胸中を察したようだった。きっと、吐き出したいに違いない、と。
予想通り負けてしまった新之助は、顔色の悪い河童《かっぱ》のような表情で園部三和子とともに、雑踏に消えていった。記念品としてもらったこの街の名物のレトルト納豆カレーを食べる日が来るのか、少し気にはなったのだけれども、明日にはどうせ忘れているから気にしないことにした。
「シュン君もなにかチャレンジしてみたら? あ、運動系以外ね」
「そういえば、浴衣コンテストっていうのがあるんだけど、朱莉《あかり》が出るみたいだよ」
「え? 朱莉ちゃんが?」
「うん。応援する?」
「うん! 朱莉ちゃんが出るなら、応援しなきゃ」
やがてステージ前に現れた朱莉は、僕とミツキを見て深く嘆息する。リア充どもが、業火で焼きつくされるがいい、と呪いの言葉を吐いてステージ脇に待機した。朱莉は、僕とミツキの記事を知っているのだろうけど、それに追求することはなかった。
水色の金魚が描かれた可愛らしい浴衣と青いダリアの髪飾りは、朱莉の印象とは少し違っていたのだけれど、可憐な少女を演じる朱莉はいつも以上に愛らしかった。
「やあ、シュン君。ちょっと訊きたいことあるんだけど。いいかな?」
「怜《れん》さん。別にいいですけど」
ミツキに少しだけ、怜さんと話してくるね、と告げると、ミツキは行ってらっしゃい、と微笑んだ。すぐに戻るから。
封鎖された道路の路肩に二人座り込んで、怜さんは僕に買ってくれたお茶を手渡してくれた。
「ミツキちゃんと付き合っているって本当かい?」
「……はい」
「ふぅ。うん。分かった。朱莉はね、シュン君のために毎日毎日、筋トレしたり、ダイエットのために食事を考えたりと、そこまではいいんだけどね」
「そんなことしていたんですか。あいつ」
「うん。最近は、自分の性格に難があるんじゃないかって悩み始めてね。もっと可愛くなりたい。ミツキちゃんみたいになりたい、なんて言い出す始末なんだ。どう思う?」
朱莉は向上心が強い子だ。ダンスを見ていてもそうだし、勉学で言えば、テストで毎回学年一〇位以内は固い。それに、負けず嫌いなのだ。そんな朱莉が悩み始めたという性格には、勝ち負けなどあるのだろうか。そこを悩んでしまうと、あまり良い結果にならない気がする。自分の性格なんて、偽るという方法でしか変えようがないと思うのだが。それに、僕は今のままの朱莉のほうが好きだ。なんて、言える立場ではないのだけれども。
「朱莉は……すごく良い子だと思います。僕が転校してきたばかりのころ、彼女だけが僕と対等に接してくれたんです」
「へえ。その話聞かせてくれる?」
「はい。昼休みになると、僕は教室にいるのが辛くて、校庭の大きな樹の下で毎日お昼を食べていたんです……」
木々が色づく秋めいた風が気持ちよかったある日、いつものように弁当を開くと、姉さん特製の黄色い猫型ロボットが僕に嗤《わら》いかけていて。
一人で溜息を吐いていたら、後ろから変な弁当ね、って女の子が声を掛けて来たんです。背中まである長い髪の毛がとても綺麗で。何気なく僕の隣に座って、こう呟いたんです。
倉美月春夜《くらみつきしゅんや》くんだよね。あたしダンスやっているんだけど、君に勝ちたい、って。
みんな僕のことを、触ったら壊れてしまう薄いワイングラスみたいに扱うのに、朱莉だけは僕に気を使うことはなかったんです。次の日も、また次の日も現れて。次第に、僕のことをシュン、なんて勝手に呼ぶようになって。
シュンはさ、ダンスはもうできないんでしょ。ならあたしがその夢引き継ぐよ。ごめん、勝手かもしれないけれど、あたし、本当にシュンのダンス好きだったんだ。だから、シュンから認めてもらえるようになるくらいがんばるから。
なんて勝手な奴だと思ったんですけれど、それでも、話しているうちになんだか憎めない奴だな、って思ってきて。
銀杏の黄色い欠片が降りしきる、深い紅玉色《ルビーカラー》の空に落ちてしまいそうな秋の夕暮れに、朱莉は突然、僕に言ったんです。
————シュンはあたしと同じだね、と。
意味が分からなかったです。何を言っているのか。
学校前の坂で、僕の前に現れた朱莉は別人のように髪が短くなっていて。それで、僕がどうしたの、と訊いたら朱莉は、シュンにフラれる前に髪を切っておこうと思って、なんて言うんですよ。それから朱莉は今まで以上に僕にフレンドリーに話しかけてくるようになりました。まるで、旧知の親友のように。
「ふぅん。朱莉らしいね」
「なんで髪を切ったのか、未だに分からないんです」
「それはね、シュン君」
少し風が吹いた。夏の夜の煌めく宵の明星が揺れていて、通り過ぎる子供の七色に光るおもちゃと、甘い香りの綿菓子が鼻先をかすめていく。出店のちょうちんが怪しく光り、怜さんの鼻と頬を照らす。微笑んでいた顔が一瞬、真顔になった気がした。だけど、すぐに微笑む怜さんは、やはり優しい双眸《そうぼう》で僕を見る。
「君とは初めから付き合うことはできない、と知っていたからだよ」
「な、なんで……ですか?」
「当時の君は、好きな子がいたんじゃないのかな?」
「……正直、分かりません。でも、その子のことばかり考えていたのは確かです。少し距離が遠くなってしまって。余計想いを巡らせていたのかもしれません」
朱莉の好きなアイドルは鳥山志桜里《とりやましおり》だった。朱莉が好きなのはきっと僕だった。どんな気持ちで朱莉は僕を見ていたのだろう。どんな気持ちで鳥山志桜里を好きでいたのだろう。朱莉は僕と鳥山志桜里の関係を当時は知らなかったのだけれども、それでも、当時の状況を考えると、僕の心はかき乱される。
そう。僕と志桜里が知り合いだったと知ったネイキッドオータムカフェのあの日、朱莉は怒ることも泣くこともしなかった。普通なら僕に何かしらの不満を言うのに。なんでもない、普段の朱莉を装ったのだから、今考えると、朱莉には悪いことをしたかもしれない。
そうか。今、朱莉が想っていることがなんとなく分かった。
シュンはあたしと同じだね————きっと恋をしているんでしょう?
なんて言いたかったのかな。
「朱莉は可愛くないなんて言ったら、罰が当たると思います。本当に出来た子で。でも、僕は朱莉には応えられそうにありません。怜さんごめんなさい」
「謝ることじゃないよ。ただ、兄として妹が心配なだけで。恋愛ばかりはお互いの気持ちだからね。仕方ないよ。ただ、朱莉に告白されたら、きっぱり断ってくれるよね」
「はい。それはもう……」
「うん。ならよかった。弄《もてあそぶ》ぶようなことをしたら……なんてね。君は大丈夫そうだ。朱莉はきっと、もっともっと綺麗になるよ」
「そうですね。僕も朱莉には幸せになってもらいたいです」
ミツキの元に戻ると、彼女はステージ上の朱莉に手を振っていた。だが、朱莉はステージから降りてきてミツキの腕を引くと、再びステージ上に戻る。ミツキを連れて。乱入する形で参加となった浴衣コンテストは花神楽美月《はなかぐらみつき》の参加により、人がごった返して、まるでいつかの桜祭りのよう。
「なにしてんだ、朱莉!?」
「これは勝負なの。一世一代の勝負。ミツキちゃんには悪いけど、今日こそ勝つ!!」
「ちょ、ちょっと朱莉ちゃん、さすがに」
しかし、ミツキの抵抗空しく、ステージ階下のゾンビたちはミツキを引きずり降ろして食らいたいのか、激しく手を伸ばしてミツキを狙っている。
「あたしが勝ったら、シュンは貰うからッ!!」
「あ、はい、え? えぇ!? 朱莉ちゃ……」
それで浴衣コンテストの開催です~~~~!!!
呑気な司会の台詞に、ゾンビたちは誰からも勝利を収めていないのにも関わらず、勝鬨《かちどき》の声を上げていた。
「シュン君。どうかな? 自分で着てみたんだけど、おかしくない?」
俯き加減で僕を見る上目遣いのミツキは、悪戯を半分、甘えを半分、僕の瞳を呑み込んでいく。きっと、浴衣を着た自分を褒めて欲しいのだろう。僕は真顔でじっと見つめる。あまりにも可愛すぎて、ついつい意地悪をしたくなってしまう。
「どうかな。うーん」
まじまじとミツキの眉間に視線を向けて、そのまま鼻を通り、唇、顎、首筋、襟にゆっくりと移していく。腰から脚、つま先に落ちていく頃には、ミツキは頬を膨らませていた。
「もう。知らないッ!! シュン君の意地悪……」
だけど、僕もすでに限界を通り過ぎていた。朱色の中に浮かぶ淡紅色《たんこうしょく》のシャボン玉のようなネイルカラーの指先を手に取って、僕は優しく、傷つけないように触れてから握るとミツキを見て言う。本当に綺麗だね、と。
「可愛くて、触れたら消えちゃうんじゃないかってくらいに、儚《はかな》いというか、可憐というか」
纏まらない言葉の欠片が宙を舞っていく。しかし、ミツキの拾い集める僕のばらばらになった破片が形を成していくように、一つになって彼女に染みていく。まるで、雫が落ちる水面のように波紋を広げてミツキの表情が明るく満ちていった。
「うん。シュン君ありがとう。行こう」
触れたままの手を握り返して、僕の手のひらを包んだミツキの暖かい手は、やがて指と指を絡めていき、僕の心まで引っ張っていった。
僕たちの住む町の商店街と神社が中心となって行われるお盆縁日は、とにかく派手で、毎年道路を封鎖して出店合戦が繰り広げられる。道路の真ん中に作られたステージ上で行われる浴衣美女コンテストや、盆踊りをパレードのように流しで行う、盆踊りコンテストも有名で賞品が家電とあって、大盛り上がりを見せていた。
「バレないかな?」
「バレる……と思う。でも、もう今更だよ。SNSで知らない人いないし。それに変装しないで行きたいっていったのはミツキじゃん。なにをしたって無駄な気がするんだけど」
「うん……そうだね。でもシュン君は迷惑じゃないの?」
「ミツキが大丈夫なら、僕は全く気にしないよ。それよりも、なんで変装しなかったの?」
「浴衣……せっかくの浴衣をいただいて、着たんだから、素のままの自分でって。分かるかな。この気持ち」
「————うん。なんとなく。でも、危険じゃない?」
「その時はシュン君が守ってくれるんでしょ? それにアスカさんの言っていたこともあるし。ちょっと戦ってみようかなって」
お盆縁日は薄暗い夕方から始まって、夜九時の花火で終了となる。昼間とはまた顔の見え方が違うんじゃないか、という期待は簡単に裏切られた。どこを歩いても明るい。それもそのはずで、数十メートルの等間隔で電柱に固定された投光器が道を照らしている、防犯対策もばっちりというわけだ。しかも、思った以上に人の出が多く、田舎のどこから湧いて出て来たのか、と思うほど活気があった。
「お、春夜!!」
ああ、見つかった、と顔を背けるも、すでに僕の視界に入ってくる見知れた顔の男。彼女と手を繋いで歩くサッカー部のエース。その名も涼森新之助。そして、紺色をベースに、黒っぽい紅葉が描かれた浴衣の少女は園部三和子だ。うなじを見せた妖艶な姿は、まるで和風魔女。呪術師とも取れるけれど、とても綺麗だった。なんて口に出して言えるはずもない。ミツキが拗《す》ねるから。
「新之助か。びっくりさせないでよ」
「お前、社会一般を敵に回したな。そのうちスナイパーに撃ち殺されるぞ」
「涼森君、こんばんは。シュン君を撃ち殺すの?」
真面目な顔をして怖いことを言うミツキに、新之助はそうだよ、なんて吹き込むものだから、たちが悪い。しかも、園部三和子まで、一回撃ち殺したほうが良いのかも、なんて言うのだから僕がどう見られているのかが想像つくというものだ。どうせ僕は、ミツキを独り占めしたカス男ですよ。ネットではクソミツキとかって言われているみたいだし。ええ、気にしないですけどね。
「ところで、新之助はステージ前でなにしてんの?」
「新之助くんが、納豆カレー大食い大会に出るって聞かないのよ。出場者にうちの高校の野球部の佐々木君と、ラグビー部の鈴木君、それに、レスリング部の相川君の名前があるから、サッカー部は誰も出ないのか、って」
「大食い大会ですか? シュン君は出ちゃだめだよ!?」
「出ないよ!! ミツキは僕のことなんだと思っているの……」
「お前ら。いいか。大食い大会で優勝したら、旅行券一〇万円分だぞ。俺は絶対に取る。そして、二人でハワイ旅行に行くんだ」
行けねえよ、とツッコミを入れようとした僕の代わりに、園部三和子が、ハワイ旅行なんて夢みたい、なんて真面目に言い放つ。僕とミツキは呆気に取られてただ笑うしかなかった。苦笑という種類のやつ。それにしても、納豆カレーというチョイスはいかがなものなのか。街の名物ではあるのだけれども。
ステージに上がった新之助は、ガチガチに緊張をしていて、まるで冷凍庫で一人裸で凍える類人猿のようだ。司会がマイクを向けて意気込みを聞いても、頑張りしゃす、と意味の分からないガッツを見せる新之助は、すでに気持ちで負けている。
いざ、男の真剣勝負が始まると、ラグビー部の鈴木が大皿の納豆カレーをものの三〇秒で平らげて二皿目。ほかのメンツも鈴木には遠く及ばずに、皆同じようなペースで熾烈《しれつ》な二位争いをしている。
やがて、ラグビー部の鈴木が五皿目で音《ね》を上げる頃には、他のメンツは三皿目で顔面蒼白であった。どう見ても、新之助に勝ち目はない。むしろ、よくここまで食べられたな。納豆カレーを。
「新之助くんは、納豆がだめなのに。よくここまで……」
隣でとんでもない真実を告げる園部三和子に、ミツキは奇声のような声で驚き、ありえない、と新之助の胸中を察したようだった。きっと、吐き出したいに違いない、と。
予想通り負けてしまった新之助は、顔色の悪い河童《かっぱ》のような表情で園部三和子とともに、雑踏に消えていった。記念品としてもらったこの街の名物のレトルト納豆カレーを食べる日が来るのか、少し気にはなったのだけれども、明日にはどうせ忘れているから気にしないことにした。
「シュン君もなにかチャレンジしてみたら? あ、運動系以外ね」
「そういえば、浴衣コンテストっていうのがあるんだけど、朱莉《あかり》が出るみたいだよ」
「え? 朱莉ちゃんが?」
「うん。応援する?」
「うん! 朱莉ちゃんが出るなら、応援しなきゃ」
やがてステージ前に現れた朱莉は、僕とミツキを見て深く嘆息する。リア充どもが、業火で焼きつくされるがいい、と呪いの言葉を吐いてステージ脇に待機した。朱莉は、僕とミツキの記事を知っているのだろうけど、それに追求することはなかった。
水色の金魚が描かれた可愛らしい浴衣と青いダリアの髪飾りは、朱莉の印象とは少し違っていたのだけれど、可憐な少女を演じる朱莉はいつも以上に愛らしかった。
「やあ、シュン君。ちょっと訊きたいことあるんだけど。いいかな?」
「怜《れん》さん。別にいいですけど」
ミツキに少しだけ、怜さんと話してくるね、と告げると、ミツキは行ってらっしゃい、と微笑んだ。すぐに戻るから。
封鎖された道路の路肩に二人座り込んで、怜さんは僕に買ってくれたお茶を手渡してくれた。
「ミツキちゃんと付き合っているって本当かい?」
「……はい」
「ふぅ。うん。分かった。朱莉はね、シュン君のために毎日毎日、筋トレしたり、ダイエットのために食事を考えたりと、そこまではいいんだけどね」
「そんなことしていたんですか。あいつ」
「うん。最近は、自分の性格に難があるんじゃないかって悩み始めてね。もっと可愛くなりたい。ミツキちゃんみたいになりたい、なんて言い出す始末なんだ。どう思う?」
朱莉は向上心が強い子だ。ダンスを見ていてもそうだし、勉学で言えば、テストで毎回学年一〇位以内は固い。それに、負けず嫌いなのだ。そんな朱莉が悩み始めたという性格には、勝ち負けなどあるのだろうか。そこを悩んでしまうと、あまり良い結果にならない気がする。自分の性格なんて、偽るという方法でしか変えようがないと思うのだが。それに、僕は今のままの朱莉のほうが好きだ。なんて、言える立場ではないのだけれども。
「朱莉は……すごく良い子だと思います。僕が転校してきたばかりのころ、彼女だけが僕と対等に接してくれたんです」
「へえ。その話聞かせてくれる?」
「はい。昼休みになると、僕は教室にいるのが辛くて、校庭の大きな樹の下で毎日お昼を食べていたんです……」
木々が色づく秋めいた風が気持ちよかったある日、いつものように弁当を開くと、姉さん特製の黄色い猫型ロボットが僕に嗤《わら》いかけていて。
一人で溜息を吐いていたら、後ろから変な弁当ね、って女の子が声を掛けて来たんです。背中まである長い髪の毛がとても綺麗で。何気なく僕の隣に座って、こう呟いたんです。
倉美月春夜《くらみつきしゅんや》くんだよね。あたしダンスやっているんだけど、君に勝ちたい、って。
みんな僕のことを、触ったら壊れてしまう薄いワイングラスみたいに扱うのに、朱莉だけは僕に気を使うことはなかったんです。次の日も、また次の日も現れて。次第に、僕のことをシュン、なんて勝手に呼ぶようになって。
シュンはさ、ダンスはもうできないんでしょ。ならあたしがその夢引き継ぐよ。ごめん、勝手かもしれないけれど、あたし、本当にシュンのダンス好きだったんだ。だから、シュンから認めてもらえるようになるくらいがんばるから。
なんて勝手な奴だと思ったんですけれど、それでも、話しているうちになんだか憎めない奴だな、って思ってきて。
銀杏の黄色い欠片が降りしきる、深い紅玉色《ルビーカラー》の空に落ちてしまいそうな秋の夕暮れに、朱莉は突然、僕に言ったんです。
————シュンはあたしと同じだね、と。
意味が分からなかったです。何を言っているのか。
学校前の坂で、僕の前に現れた朱莉は別人のように髪が短くなっていて。それで、僕がどうしたの、と訊いたら朱莉は、シュンにフラれる前に髪を切っておこうと思って、なんて言うんですよ。それから朱莉は今まで以上に僕にフレンドリーに話しかけてくるようになりました。まるで、旧知の親友のように。
「ふぅん。朱莉らしいね」
「なんで髪を切ったのか、未だに分からないんです」
「それはね、シュン君」
少し風が吹いた。夏の夜の煌めく宵の明星が揺れていて、通り過ぎる子供の七色に光るおもちゃと、甘い香りの綿菓子が鼻先をかすめていく。出店のちょうちんが怪しく光り、怜さんの鼻と頬を照らす。微笑んでいた顔が一瞬、真顔になった気がした。だけど、すぐに微笑む怜さんは、やはり優しい双眸《そうぼう》で僕を見る。
「君とは初めから付き合うことはできない、と知っていたからだよ」
「な、なんで……ですか?」
「当時の君は、好きな子がいたんじゃないのかな?」
「……正直、分かりません。でも、その子のことばかり考えていたのは確かです。少し距離が遠くなってしまって。余計想いを巡らせていたのかもしれません」
朱莉の好きなアイドルは鳥山志桜里《とりやましおり》だった。朱莉が好きなのはきっと僕だった。どんな気持ちで朱莉は僕を見ていたのだろう。どんな気持ちで鳥山志桜里を好きでいたのだろう。朱莉は僕と鳥山志桜里の関係を当時は知らなかったのだけれども、それでも、当時の状況を考えると、僕の心はかき乱される。
そう。僕と志桜里が知り合いだったと知ったネイキッドオータムカフェのあの日、朱莉は怒ることも泣くこともしなかった。普通なら僕に何かしらの不満を言うのに。なんでもない、普段の朱莉を装ったのだから、今考えると、朱莉には悪いことをしたかもしれない。
そうか。今、朱莉が想っていることがなんとなく分かった。
シュンはあたしと同じだね————きっと恋をしているんでしょう?
なんて言いたかったのかな。
「朱莉は可愛くないなんて言ったら、罰が当たると思います。本当に出来た子で。でも、僕は朱莉には応えられそうにありません。怜さんごめんなさい」
「謝ることじゃないよ。ただ、兄として妹が心配なだけで。恋愛ばかりはお互いの気持ちだからね。仕方ないよ。ただ、朱莉に告白されたら、きっぱり断ってくれるよね」
「はい。それはもう……」
「うん。ならよかった。弄《もてあそぶ》ぶようなことをしたら……なんてね。君は大丈夫そうだ。朱莉はきっと、もっともっと綺麗になるよ」
「そうですね。僕も朱莉には幸せになってもらいたいです」
ミツキの元に戻ると、彼女はステージ上の朱莉に手を振っていた。だが、朱莉はステージから降りてきてミツキの腕を引くと、再びステージ上に戻る。ミツキを連れて。乱入する形で参加となった浴衣コンテストは花神楽美月《はなかぐらみつき》の参加により、人がごった返して、まるでいつかの桜祭りのよう。
「なにしてんだ、朱莉!?」
「これは勝負なの。一世一代の勝負。ミツキちゃんには悪いけど、今日こそ勝つ!!」
「ちょ、ちょっと朱莉ちゃん、さすがに」
しかし、ミツキの抵抗空しく、ステージ階下のゾンビたちはミツキを引きずり降ろして食らいたいのか、激しく手を伸ばしてミツキを狙っている。
「あたしが勝ったら、シュンは貰うからッ!!」
「あ、はい、え? えぇ!? 朱莉ちゃ……」
それで浴衣コンテストの開催です~~~~!!!
呑気な司会の台詞に、ゾンビたちは誰からも勝利を収めていないのにも関わらず、勝鬨《かちどき》の声を上げていた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

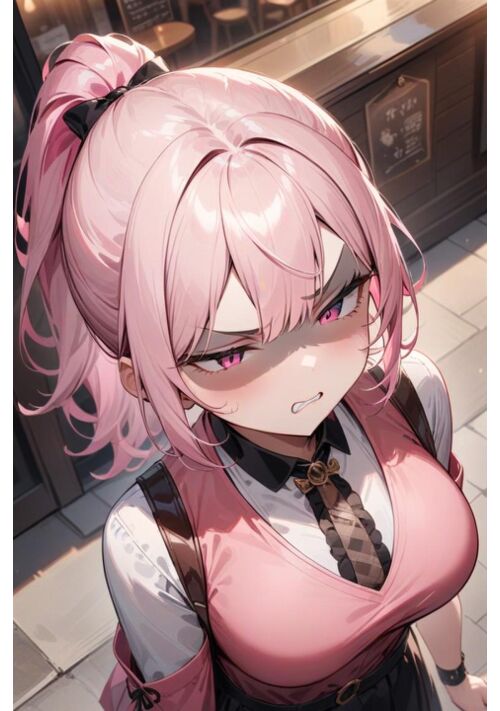
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















