28 / 61
明け易し夏 ミツキの疑惑
幕間 星も見えぬ空 心の荒む激動の一夜
しおりを挟む
くそ野郎を問いただしたい。
こんなことを鳥山志桜里《とりやましおり》に頼むのは、少しばかり、いやかなり虫のいい話だった。
白木坂慶介《しらきざかけいすけ》という男は、花鳥風月プリズムZの風見碧唯《かざみあおい》と繋がりがあるという情報を教えてくれたのも志桜里だ。だが、志桜里の意図が見えない。なぜ、今さら僕なんかに協力してくれるのだろうか。
新宿駅東口の改札を抜けた志桜里が、手を振りながらこちらに向かってくる。相変わらず、全く変装などしていない。むしろ、僕の顔が知り渡っているのに、それはないだろうと思う。ドッド柄のシャツに藤黄《とうおう》のプリーツスカートは、志桜里らしくないコーデで、どことなく大人になったような気がする。僕を見るなり少しだけ微笑む志桜里は、積年の想いを互いに重ねて来た遠距離の久方ぶりの恋人のよう。
「やほー。シュンは元気……じゃないね。シュン、ちゃんとご飯食べてるの?」
「うん。大丈夫だよ」
嘘を吐いた。実際、食欲があまりなく、毎食高カロリーのゼリーで済ませているのだから、それを志桜里が知れば激高するのは間違いない。だから、僕は嘘を吐く。心配かけたくないから。
「志桜里、今日はごめん。忙しいんでしょ。僕のこと殴りたいと思っているのは分かってる。終わったら、好きにしていいから」
「ちょっと、シュン。水臭いわよ。シュンのためなら一肌脱ぐのが私でしょ。それに、シュンがミツキと付き合っていたって、最終的に私のところに来てくれればそれでいいんだから」
心が広いようで、狭い。それが志桜里だ。そして、設定した目標にたどり着くまでにはどんな方法を使っても、突き抜ける。まるで弓から放たれた矢だ。的を得るためには、勢いを止めることができない矢。そんな志桜里と知り合って、一四年になる。出会った瞬間のことなど覚えていないけれど。気付いたらそこにいた、なんて。
僕はなぜ志桜里を好きにならなかったのだろう。いや、好きだけど、ミツキを想う気持ちとは別のものだ。もし、志桜里を選んでいたら、こんなに苦しい思いをすることはなかったのかもしれない。
「……ごめん。勝手だけど、約束はできない」
「そうやって、真面目なところも変わらないね」
「毎日、メッセージくれてありがとう。志桜里には話しておかなきゃいけないことがあるんだ。今日、終わったら話すよ」
なぜだろう。ミツキには話せないことが志桜里には話せる。そうか。志桜里は僕の親友なんだ。気兼ねなく、気遣うこともなく、すべてを許せる——委ねられる存在。僕は、そんな親友に甘えようとしているわけではない。ただ、知っていて欲しい。僕のことを。
熱帯夜の絡みつく湿度に蒸し焼きにされた身体を、ギンギンに冷えた水を喉に突っ込んで冷やしていく。一気に飲み干したペットボトルをコンビニのごみ箱に投げ捨てた。
歌舞伎町の一角にあるクラブに入っていく志桜里の背を追いかけて、僕も防音扉の先に吸い込まれていく。九〇年代のダーク・エレクトロが赤いレーザービームを彩っていて、凍てつく魔女の放つ氷の魔法のように冷えたクーラーが、僕の頭を締め付ける。
無機質。
周りの景色にも、音楽にも、踊り狂う人にもなんの感情も沸かない。ただ、ミツキの残り香を追う自分は、そのストロベリーの感触だけを頼りに進んでいく。きっかけは、白木坂慶介だ。そいつを見つけて話を聞き、場合によってはぶん殴る。もうどうなっても構わない。
僕を煽《あお》る様にうねるシンセサイザーが、耳障りだ。そんなことを考えていると、急激に最新の流行に切り替わっていく。しかし、ダーク・エレクトロから切り替えた先がエレクトロスウィングというハウス調のジャズなんて。DJの顔が見てみたい。
ストロボのような白い閃光がなんども志桜里の背を浮かび上がらせる。部屋の一角のテーブルに座り込む男女。一人は、風見碧唯。背中まである長い金髪を一本に束ねていて、虚《うつ》ろな瞳で志桜里を見ている。もう一人は、ブラウンのツーブロックの髪にピアスを開けたやんちゃなアイドル、白木坂慶介だ。
「碧唯《あおい》、ちょっとあんたの彼氏の顔借りていい?」
「……まさか、倉美月春夜!? なんでこんなところに!?」
「あ、あんたが……まさか」
「そのまさかだよ。白木坂慶介さん。シュンは、ちょっと……今、やばいよ」
僕をみんなで襲撃に来た魔王のように扱う。意味が分からない。まだ何も話していないのに。僕はできるだけ穏便《おんびん》に話を進めたい、と思っているのに。しかし、風見碧唯は無表情で僕を冷たく一瞥すると、すぐに視線を逸らした。白木坂慶介の僕を見る目は、まるで恐怖に怯えた子犬のよう。見かけによらず、臆病なのかもしれない。
「白木坂……さん、訊《き》いていいかな。ミツ……花神楽美月とはどういう関係?」
僕の一言で、その場が凍り付く。それもそのはず。白木坂慶介の彼女である風見碧唯が目の前にいるのだから、答えようがないのかもしれない。でも、僕は絶対に追求を止めない。ミツキに触れただけでも許せない。許すことなどできるはずがない。
「あ、ああ。それは……気の迷いというか」
白木坂慶介の言葉に、風見碧唯は何の反応もしない。むしろ、少し僕を睨んでいるかのようにも見える。まるで、僕のほうが悪いことをしているような表情に、僕は睨み返した。てめえの彼氏くらい、ちゃんと見張っておけよ、と言いたい。僕は怒っている。風見碧唯、お前にもだ。
「気の迷いで、ミツキに触れた、と?」
握り拳が震えるくらい力を入れていて、脳を満たす熱い血流が急激に脈打ちはじめる。顔が熱い。肺から漏れる吐息は灼熱を帯びていて、僕は思わずため息を吐く。Cut capersのSay whatがアレンジされて流れる軽快なラップが、僕の心拍数とシンクロしていて、流れる汗を手の甲で拭った。レーザービームの閃光が白木坂慶介の蒼白の顔を撫でていき、僕の顔を焦がしていく頃には目元は焼け落ちていて、鼻からは炎が漏れる。口からはどす黒いヘドロが零れ落ちていたのだと思う。
「ち、違う。そうじゃなくて、なんていうか。花神楽が……」
「はっきり言えよ……」
「だから、俺は……」
「ふざけんなッ!! てめえ、なんのつもりで!!!!!!」
気が付くと、テーブルに足を掛けていて、白木坂慶介の胸倉《むなぐら》を掴《つか》んでいた。グラスが何事か、と錯乱《さくらん》したように中身をぶちまけていて、辺りを桃色の液体が侵食していく。緑と青、それにピンクのオーロラエフェクトがアメーバのように広がる壁に後頭部を当てる白木坂慶介は、気色悪い色に染め上げられていて、思わずバーナーで焼きたくなった。振り上げた拳を志桜里が両手で必死に握って、それ以上拳が進まないようにせき止めている。
「シュン、ちょっと!! だめだって!!!」
「志桜里離せッ!! 僕は、こいつを殴らなくちゃ気が済まない!!」
「ま、待てって!! 誤解だ。誤解。本当に」
もはや、何も考えられない。こみ上げた怒りが全身を毒していて、脳を巡る思考よりも行動の方が数百倍速い。激流のように駆け巡る血液が、心臓を激しく震えさせる。分かっている。こんなに興奮したら命取りなことくらい。でも、止められない。こいつを殴らなくては、僕は収まらない。こいつを今すぐ、殺してやりたい。志桜里を思いきり振り解いて、再び拳を上げて振り下ろす。
拳が白木坂慶介の頬に当たる前に、待って、と、風見碧唯が口を開いた。僕は、その声の大きさに、拳を止める。風見碧唯を瞳孔の僅《わず》か斜めの一部に収めると、こちらを睨む彼女が肩で息をしていた。
「いい迷惑ね。ミツキよ。ミツキと取引したの。抱き合っている写真を撮って欲しいって。それで慶介にお願いしたのよ。慶介ならもうそういうチャラいキャラで世間一般が通っているから」
「ミツキが取引!? まさか碧唯、あんた!?」
「仕方ないでしょ。ミツキに知られちゃったんだから。あの子、あんな顔と言動で、とんでもない切れ者なのよ。凄《すご》まれたら、従うしかないじゃん」
「……分かった。まあいい。それより、シュン、どうするの?」
ミツキは何を取引したのだろうか。今の話の脈からは、僕の知らないミツキを垣間見た気がする。でも、それでもミツキを追わなくてはいけない。僕は決意したのだから。だから、それをミツキに言わなくちゃならない。
「ミツキの居場所を教えて欲しい。今のことは謝る。悪かったよ。ごめん」
「……俺は知らない。本当だ。それに、あれっきり一度も会っていないし、あれ以上のことは何もしていない。誓う。だから、俺も悪かった。あんたの気持ち、少し分かるから」
「……この場所に行ってみたら」
風見碧唯がナプキンに書いた住所は、少し滲んでいたけれど、今はそれが宝の地図のように輝いて見えた。丁寧にお礼を言って、そして、謝って。ぐちゃぐちゃの心を整理できないまま、クラブを後にする。
「私、シュンのキレたところ見るの初めてだったかも。怒ることはあってもね。シュンをあんなにキレさせるなんて、ミツキのこと許せないわぁ」
「ごめん。志桜里が止めてくれなかったら、僕は今頃、警察のお世話になっていたかも」
風見碧唯の書いたメモの指す場所は、虎ノ門にある高級ホテルであった。広大な中庭には滝が流れていて、カヌーで滝下りなんて遊びをしたら楽しいだろう。また、セキュリティもしっかりしていて、僕一人では入ることができなかったかもしれない。
豪華なシャンデリアが煌《きら》めくロビーまでは誰でも入ることができる。しかし、その先、エレベーターホールにはカードキーが必要であって、必ず宿泊者でなければ入ることができない。しかも、ミツキがいるであろう階は、さらに部屋のカードキーが必要で侵入不可能である。
だが、志桜里が自分の名前と身分証をロビーで見せると、すぐにカードキーが差し出された。なぜなら、その階層は彼女たちの事務所が借り上げているからだ。
「シュン、私、すごく損な役回りをしている気がするんだけど」
「うん。ごめん。埋め合わせは必ずする。なにがいい?」
「キスして。それですべて流すから」
「…………それは」
エレベーターの扉が開き、静謐《せいひつ》な空間と背後で僕のシャツを摘《つ》まむ志桜里に息が詰まりそうになった。キスなんて本気で言っていたのだろうか。真っ直ぐな志桜里のことだから、きっと本気なのだろうけど。でも、今までそんなこと言われたことがない。真っ直ぐなのと積極的なのは別のような気がする。いったい、志桜里にどんな心境の変化があったのだろう。
メモの通りに書かれた部屋の前に立って、瞳を閉じる。ゆっくりと息を吐いて、瞼を開くと同時にインターホンを押し込んだ。この先の世界はきっと異空間になっていて、僕を受け入れてくれるか、それとも拒絶して押し戻されてしまうのか。どちらにしても、相当な覚悟が必要であって。僕は、自分の暴れる心臓を言い聞かせることなど不可能であった。熱く漏れる吐息の音と滴る汗を見たのか、志桜里が、シュン、大丈夫よ、と背後から優しく呟く。
分厚い扉の向こうの音を聞くことはできない。ただ、開くのを待つばかり。
開いた扉から顔を出したのは、真っ赤に目を腫《は》らした兎のような少女。ぼさぼさになった髪の毛と未だにしゃくりあげている肩と鼻。啜《すす》りすぎたのか洟《はな》をかみすぎたのか、真っ赤になった鼻が可哀そうで、思わず抱きしめたくなる。酷く打ちひしがれていて、僕の視線が彼女の瞳孔を捉える頃には、ミツキは涙をぼろぼろと流していた。
「シュン……くん?」
「ちょっと、シュン、どいて」
扉を強引に開いて、ミツキの肘を力強く掴んで部屋の中まで引っ張っていった志桜里は、平手をミツキに浴びせる。ぱちんという音が響いた時には、ミツキは倒れて腰を床につけていた。何が起こったのか分からないミツキは、茫然と志桜里を見上げて呟く。なんで、と。
「シュンを、シュンをこんな風にさせたミツキが憎い。あんたのせいで、シュンは白木坂慶介をさっき、殴り殺しそうになったのよ! もし、シュンになにかあったら、私は絶対にミツキを許さないからッ!!」
少し大げさすぎる気もするが、真に受けたミツキは地面に腰を落としたまま、口をパクパクとさせていた。ミツキは、もしかして激高する志桜里を見るのが初めてなのかもしれない。僕は何度も見ているけど。それに、僕に視線を浴びせるミツキの表情は、泣きじゃくる子供そのもの。いや、ミツキが悪いのではなくて、すべて僕のせいなのだけれど。
「志桜里、もういいから。僕は大丈夫だから」
「良くないッ!! シュンはね、あんたを一番に考えて、それで悩んで、苦しんで。あんたが本当にシュンを好きなんだったら、しっかりと受け止めなさいよッ! ばっかじゃないの」
「し……おり……ちゃん、ごめん。でも、わたしがいるとシュン君は……」
「それで、あんな記事を捏造《ねつぞう》したの? シュンに嫌われれば、自分から離れると? シュンいったいなにがあったの?」
しばらく静寂が空間を支配した。痛いほどの張りつめた沈黙が、僕の喉に侵入してきたころには張り裂けそうな心臓が脈打って、目頭が熱くなる。乾いた舌がぎこちなく動き、言葉を放つことを諦めた声帯がゼンマイの切れたオルゴールのように音を漏らす。
言ってしまえば、僕は消えてなくなってしまうかもしれない。生きているのに死んだように扱われる。それは嫌だ。
「このままだと。二年。二年なんだ」
二人とも意味が分からなかったようで、口を開いたまま固まっている。何が二年なの、と。二年という七三〇日は長いようで短い。
だから、僕には時間がない。
こんなことを鳥山志桜里《とりやましおり》に頼むのは、少しばかり、いやかなり虫のいい話だった。
白木坂慶介《しらきざかけいすけ》という男は、花鳥風月プリズムZの風見碧唯《かざみあおい》と繋がりがあるという情報を教えてくれたのも志桜里だ。だが、志桜里の意図が見えない。なぜ、今さら僕なんかに協力してくれるのだろうか。
新宿駅東口の改札を抜けた志桜里が、手を振りながらこちらに向かってくる。相変わらず、全く変装などしていない。むしろ、僕の顔が知り渡っているのに、それはないだろうと思う。ドッド柄のシャツに藤黄《とうおう》のプリーツスカートは、志桜里らしくないコーデで、どことなく大人になったような気がする。僕を見るなり少しだけ微笑む志桜里は、積年の想いを互いに重ねて来た遠距離の久方ぶりの恋人のよう。
「やほー。シュンは元気……じゃないね。シュン、ちゃんとご飯食べてるの?」
「うん。大丈夫だよ」
嘘を吐いた。実際、食欲があまりなく、毎食高カロリーのゼリーで済ませているのだから、それを志桜里が知れば激高するのは間違いない。だから、僕は嘘を吐く。心配かけたくないから。
「志桜里、今日はごめん。忙しいんでしょ。僕のこと殴りたいと思っているのは分かってる。終わったら、好きにしていいから」
「ちょっと、シュン。水臭いわよ。シュンのためなら一肌脱ぐのが私でしょ。それに、シュンがミツキと付き合っていたって、最終的に私のところに来てくれればそれでいいんだから」
心が広いようで、狭い。それが志桜里だ。そして、設定した目標にたどり着くまでにはどんな方法を使っても、突き抜ける。まるで弓から放たれた矢だ。的を得るためには、勢いを止めることができない矢。そんな志桜里と知り合って、一四年になる。出会った瞬間のことなど覚えていないけれど。気付いたらそこにいた、なんて。
僕はなぜ志桜里を好きにならなかったのだろう。いや、好きだけど、ミツキを想う気持ちとは別のものだ。もし、志桜里を選んでいたら、こんなに苦しい思いをすることはなかったのかもしれない。
「……ごめん。勝手だけど、約束はできない」
「そうやって、真面目なところも変わらないね」
「毎日、メッセージくれてありがとう。志桜里には話しておかなきゃいけないことがあるんだ。今日、終わったら話すよ」
なぜだろう。ミツキには話せないことが志桜里には話せる。そうか。志桜里は僕の親友なんだ。気兼ねなく、気遣うこともなく、すべてを許せる——委ねられる存在。僕は、そんな親友に甘えようとしているわけではない。ただ、知っていて欲しい。僕のことを。
熱帯夜の絡みつく湿度に蒸し焼きにされた身体を、ギンギンに冷えた水を喉に突っ込んで冷やしていく。一気に飲み干したペットボトルをコンビニのごみ箱に投げ捨てた。
歌舞伎町の一角にあるクラブに入っていく志桜里の背を追いかけて、僕も防音扉の先に吸い込まれていく。九〇年代のダーク・エレクトロが赤いレーザービームを彩っていて、凍てつく魔女の放つ氷の魔法のように冷えたクーラーが、僕の頭を締め付ける。
無機質。
周りの景色にも、音楽にも、踊り狂う人にもなんの感情も沸かない。ただ、ミツキの残り香を追う自分は、そのストロベリーの感触だけを頼りに進んでいく。きっかけは、白木坂慶介だ。そいつを見つけて話を聞き、場合によってはぶん殴る。もうどうなっても構わない。
僕を煽《あお》る様にうねるシンセサイザーが、耳障りだ。そんなことを考えていると、急激に最新の流行に切り替わっていく。しかし、ダーク・エレクトロから切り替えた先がエレクトロスウィングというハウス調のジャズなんて。DJの顔が見てみたい。
ストロボのような白い閃光がなんども志桜里の背を浮かび上がらせる。部屋の一角のテーブルに座り込む男女。一人は、風見碧唯。背中まである長い金髪を一本に束ねていて、虚《うつ》ろな瞳で志桜里を見ている。もう一人は、ブラウンのツーブロックの髪にピアスを開けたやんちゃなアイドル、白木坂慶介だ。
「碧唯《あおい》、ちょっとあんたの彼氏の顔借りていい?」
「……まさか、倉美月春夜!? なんでこんなところに!?」
「あ、あんたが……まさか」
「そのまさかだよ。白木坂慶介さん。シュンは、ちょっと……今、やばいよ」
僕をみんなで襲撃に来た魔王のように扱う。意味が分からない。まだ何も話していないのに。僕はできるだけ穏便《おんびん》に話を進めたい、と思っているのに。しかし、風見碧唯は無表情で僕を冷たく一瞥すると、すぐに視線を逸らした。白木坂慶介の僕を見る目は、まるで恐怖に怯えた子犬のよう。見かけによらず、臆病なのかもしれない。
「白木坂……さん、訊《き》いていいかな。ミツ……花神楽美月とはどういう関係?」
僕の一言で、その場が凍り付く。それもそのはず。白木坂慶介の彼女である風見碧唯が目の前にいるのだから、答えようがないのかもしれない。でも、僕は絶対に追求を止めない。ミツキに触れただけでも許せない。許すことなどできるはずがない。
「あ、ああ。それは……気の迷いというか」
白木坂慶介の言葉に、風見碧唯は何の反応もしない。むしろ、少し僕を睨んでいるかのようにも見える。まるで、僕のほうが悪いことをしているような表情に、僕は睨み返した。てめえの彼氏くらい、ちゃんと見張っておけよ、と言いたい。僕は怒っている。風見碧唯、お前にもだ。
「気の迷いで、ミツキに触れた、と?」
握り拳が震えるくらい力を入れていて、脳を満たす熱い血流が急激に脈打ちはじめる。顔が熱い。肺から漏れる吐息は灼熱を帯びていて、僕は思わずため息を吐く。Cut capersのSay whatがアレンジされて流れる軽快なラップが、僕の心拍数とシンクロしていて、流れる汗を手の甲で拭った。レーザービームの閃光が白木坂慶介の蒼白の顔を撫でていき、僕の顔を焦がしていく頃には目元は焼け落ちていて、鼻からは炎が漏れる。口からはどす黒いヘドロが零れ落ちていたのだと思う。
「ち、違う。そうじゃなくて、なんていうか。花神楽が……」
「はっきり言えよ……」
「だから、俺は……」
「ふざけんなッ!! てめえ、なんのつもりで!!!!!!」
気が付くと、テーブルに足を掛けていて、白木坂慶介の胸倉《むなぐら》を掴《つか》んでいた。グラスが何事か、と錯乱《さくらん》したように中身をぶちまけていて、辺りを桃色の液体が侵食していく。緑と青、それにピンクのオーロラエフェクトがアメーバのように広がる壁に後頭部を当てる白木坂慶介は、気色悪い色に染め上げられていて、思わずバーナーで焼きたくなった。振り上げた拳を志桜里が両手で必死に握って、それ以上拳が進まないようにせき止めている。
「シュン、ちょっと!! だめだって!!!」
「志桜里離せッ!! 僕は、こいつを殴らなくちゃ気が済まない!!」
「ま、待てって!! 誤解だ。誤解。本当に」
もはや、何も考えられない。こみ上げた怒りが全身を毒していて、脳を巡る思考よりも行動の方が数百倍速い。激流のように駆け巡る血液が、心臓を激しく震えさせる。分かっている。こんなに興奮したら命取りなことくらい。でも、止められない。こいつを殴らなくては、僕は収まらない。こいつを今すぐ、殺してやりたい。志桜里を思いきり振り解いて、再び拳を上げて振り下ろす。
拳が白木坂慶介の頬に当たる前に、待って、と、風見碧唯が口を開いた。僕は、その声の大きさに、拳を止める。風見碧唯を瞳孔の僅《わず》か斜めの一部に収めると、こちらを睨む彼女が肩で息をしていた。
「いい迷惑ね。ミツキよ。ミツキと取引したの。抱き合っている写真を撮って欲しいって。それで慶介にお願いしたのよ。慶介ならもうそういうチャラいキャラで世間一般が通っているから」
「ミツキが取引!? まさか碧唯、あんた!?」
「仕方ないでしょ。ミツキに知られちゃったんだから。あの子、あんな顔と言動で、とんでもない切れ者なのよ。凄《すご》まれたら、従うしかないじゃん」
「……分かった。まあいい。それより、シュン、どうするの?」
ミツキは何を取引したのだろうか。今の話の脈からは、僕の知らないミツキを垣間見た気がする。でも、それでもミツキを追わなくてはいけない。僕は決意したのだから。だから、それをミツキに言わなくちゃならない。
「ミツキの居場所を教えて欲しい。今のことは謝る。悪かったよ。ごめん」
「……俺は知らない。本当だ。それに、あれっきり一度も会っていないし、あれ以上のことは何もしていない。誓う。だから、俺も悪かった。あんたの気持ち、少し分かるから」
「……この場所に行ってみたら」
風見碧唯がナプキンに書いた住所は、少し滲んでいたけれど、今はそれが宝の地図のように輝いて見えた。丁寧にお礼を言って、そして、謝って。ぐちゃぐちゃの心を整理できないまま、クラブを後にする。
「私、シュンのキレたところ見るの初めてだったかも。怒ることはあってもね。シュンをあんなにキレさせるなんて、ミツキのこと許せないわぁ」
「ごめん。志桜里が止めてくれなかったら、僕は今頃、警察のお世話になっていたかも」
風見碧唯の書いたメモの指す場所は、虎ノ門にある高級ホテルであった。広大な中庭には滝が流れていて、カヌーで滝下りなんて遊びをしたら楽しいだろう。また、セキュリティもしっかりしていて、僕一人では入ることができなかったかもしれない。
豪華なシャンデリアが煌《きら》めくロビーまでは誰でも入ることができる。しかし、その先、エレベーターホールにはカードキーが必要であって、必ず宿泊者でなければ入ることができない。しかも、ミツキがいるであろう階は、さらに部屋のカードキーが必要で侵入不可能である。
だが、志桜里が自分の名前と身分証をロビーで見せると、すぐにカードキーが差し出された。なぜなら、その階層は彼女たちの事務所が借り上げているからだ。
「シュン、私、すごく損な役回りをしている気がするんだけど」
「うん。ごめん。埋め合わせは必ずする。なにがいい?」
「キスして。それですべて流すから」
「…………それは」
エレベーターの扉が開き、静謐《せいひつ》な空間と背後で僕のシャツを摘《つ》まむ志桜里に息が詰まりそうになった。キスなんて本気で言っていたのだろうか。真っ直ぐな志桜里のことだから、きっと本気なのだろうけど。でも、今までそんなこと言われたことがない。真っ直ぐなのと積極的なのは別のような気がする。いったい、志桜里にどんな心境の変化があったのだろう。
メモの通りに書かれた部屋の前に立って、瞳を閉じる。ゆっくりと息を吐いて、瞼を開くと同時にインターホンを押し込んだ。この先の世界はきっと異空間になっていて、僕を受け入れてくれるか、それとも拒絶して押し戻されてしまうのか。どちらにしても、相当な覚悟が必要であって。僕は、自分の暴れる心臓を言い聞かせることなど不可能であった。熱く漏れる吐息の音と滴る汗を見たのか、志桜里が、シュン、大丈夫よ、と背後から優しく呟く。
分厚い扉の向こうの音を聞くことはできない。ただ、開くのを待つばかり。
開いた扉から顔を出したのは、真っ赤に目を腫《は》らした兎のような少女。ぼさぼさになった髪の毛と未だにしゃくりあげている肩と鼻。啜《すす》りすぎたのか洟《はな》をかみすぎたのか、真っ赤になった鼻が可哀そうで、思わず抱きしめたくなる。酷く打ちひしがれていて、僕の視線が彼女の瞳孔を捉える頃には、ミツキは涙をぼろぼろと流していた。
「シュン……くん?」
「ちょっと、シュン、どいて」
扉を強引に開いて、ミツキの肘を力強く掴んで部屋の中まで引っ張っていった志桜里は、平手をミツキに浴びせる。ぱちんという音が響いた時には、ミツキは倒れて腰を床につけていた。何が起こったのか分からないミツキは、茫然と志桜里を見上げて呟く。なんで、と。
「シュンを、シュンをこんな風にさせたミツキが憎い。あんたのせいで、シュンは白木坂慶介をさっき、殴り殺しそうになったのよ! もし、シュンになにかあったら、私は絶対にミツキを許さないからッ!!」
少し大げさすぎる気もするが、真に受けたミツキは地面に腰を落としたまま、口をパクパクとさせていた。ミツキは、もしかして激高する志桜里を見るのが初めてなのかもしれない。僕は何度も見ているけど。それに、僕に視線を浴びせるミツキの表情は、泣きじゃくる子供そのもの。いや、ミツキが悪いのではなくて、すべて僕のせいなのだけれど。
「志桜里、もういいから。僕は大丈夫だから」
「良くないッ!! シュンはね、あんたを一番に考えて、それで悩んで、苦しんで。あんたが本当にシュンを好きなんだったら、しっかりと受け止めなさいよッ! ばっかじゃないの」
「し……おり……ちゃん、ごめん。でも、わたしがいるとシュン君は……」
「それで、あんな記事を捏造《ねつぞう》したの? シュンに嫌われれば、自分から離れると? シュンいったいなにがあったの?」
しばらく静寂が空間を支配した。痛いほどの張りつめた沈黙が、僕の喉に侵入してきたころには張り裂けそうな心臓が脈打って、目頭が熱くなる。乾いた舌がぎこちなく動き、言葉を放つことを諦めた声帯がゼンマイの切れたオルゴールのように音を漏らす。
言ってしまえば、僕は消えてなくなってしまうかもしれない。生きているのに死んだように扱われる。それは嫌だ。
「このままだと。二年。二年なんだ」
二人とも意味が分からなかったようで、口を開いたまま固まっている。何が二年なの、と。二年という七三〇日は長いようで短い。
だから、僕には時間がない。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

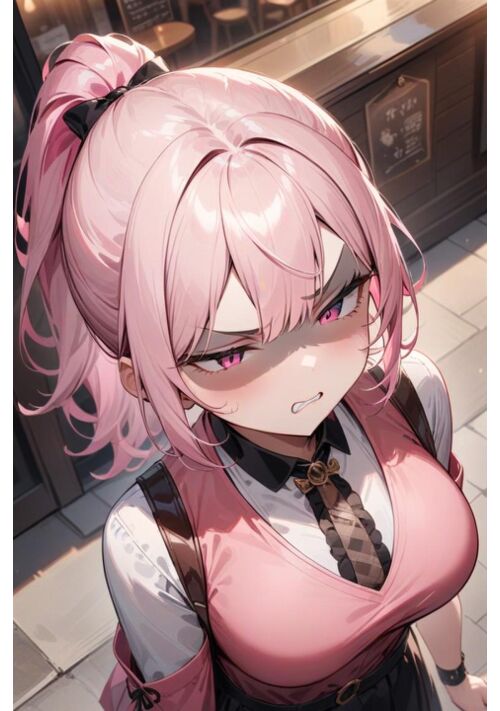
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















