33 / 61
龍淵に潜む秋・ミツキの求婚
ミツキと朱莉の仲直り
しおりを挟む
海に面した国営公園は、春にはネモフィラが幻想的に咲き誇る丘で有名になった経緯がある。紛れもない絶景スポットであり、秋にはコキアという真っ赤な真ん丸の植物が丘一面を支配していて、麓《ふもと》にはコスモス畑が広がっていた。コスモス畑と道を挟んで反対側には蕎麦《そば》の白い小さく可憐な花が一面に植えられている。
うわあ、すごい、と感嘆するミツキは、スマホを両手に持って写真を撮ることにご執心のようだ。確かに、これは圧巻である。
真っ白なアクリルの絵の具にアクアマリンのような海色を数滴落として、乱雑に混ぜたような空色に魔女が息を吹きかけたような雲が囁《ささや》いていて、風の音が随分と優しく聞こえた。
だけど、隣で僕に冷たい視線をくれる朱莉《あかり》は、そんな風の音を打ち消して僕にケチをつけてくる。なぜ、この場所を選んだのか。朱莉の頭蓋骨をこじ開けて、中身を見たくなった。いったい何を企んでいるのか。まさか、ミツキをどこかの崖から突き落とそうとしているのか。それとも、ミステリードラマのように崖の上でミツキから罪を訊《き》き出そうとしているのか。どちらにしても、気を緩めることができない。
「すごい。ねえ、シュン君、あの丘登ってみようよ」
まさに偶然の賜物であって、貴重な時間。丸一日のオフ。それを朱莉の計画に潰されるなんて、酷すぎる。なんて言った僕を諭すように、ミツキはかぶりを振ってコスモスを見ることに賛成したのだから、その気持ちを朱莉にも汲《く》み取って欲しい。おそらく無理だけど。
「うん。行こう。ほら、朱莉も行くよ」
「分かっているでござる。シュン、言っておくけど、ミツキちゃんにちゃんとあたしがお灸を据えるから。手伝ってよ」
「なんで僕が。というか、ミツキは潔白だって。本当にしつこいやつだな」
眉間に寄せた皺《しわ》の気迫で僕を圧倒しようとする朱莉は、笑顔で振り返って手を振るミツキにぎこちない笑みを浮かべながら、手を振り返した。
倉美月春夜《くらみつきしゅんや》がいる。なんていう声はもう気にしないことにした。もうなんとでも言えばいいよ。ミツキがアイドルを引退する来年には、どうでも良くなっているんだから。
変装したミツキは、なぜか正体がバレない。やはり人間の認識なんてそんなものなのだろう。ただ、僕がいることでバレないとも限らないのだけれども。
丘を登るにつれて、風が吹き荒ぶ。海風は猛烈に潮の薫りを運んできて、中腹に設置された鐘を鳴らすカップルたちが顔をしかめていた。まるで愛を祝福するような教会の音色のように響き渡る音が、朱莉の逆鱗《げきりん》に触れたようで。とにかく、愚痴がすごい。いい加減に彼氏を作りなよ、と言うと、白目を剥《む》くんじゃないかと思えるほど僕を睨《にら》んでくる。
「ねえ、みんなで鳴らそうよ。朱莉ちゃんも一緒に」
「あ、ああ。だってさ。朱莉もそろそろ普通に楽しみなよ」
屈託のない笑顔のミツキは、後ろ歩きをしながら僕と朱莉の手をそれぞれ引き始める。冷たくなったミツキの手を温めてあげたいのだけれども、朱莉がいるから難しい。ああ、もどかしい。
なぜこの鐘を鳴らしたいのか、なにかジンクスでもあるのか、と調べても何も出てこない。きっと、そこに鐘があるから鳴らす、というのが大勢の見解のようだった。それに、インストグラムに投稿でもするのだろう、と思われる。
「ねえ。ミツキちゃん。なんでミツキちゃんは————」
「え? なんて?」
近くで聞けば、空気と風を割ってしまうように鳴り響くけたたましい音に、朱莉の声は呑み込まれてしまった。その眼差しからは、悲しみが見て取れる。ミツキも気付いたようで、笑顔が消えていた————いや、素に戻ったと言ったほうが正確かもしれない。ミツキは、無理して笑顔を作っていたのだ。それに気づかなかった僕も朱莉も、同罪だ。
「ごめん……ね。朱莉ちゃん。わたし、確かに約束破っちゃったよね」
「ミツキ、それは違————」
「違わないの。朱莉ちゃんにしてみれば、わたしがシュン君を傷つけたことは事実なんだから。そこにどんな理由があっても、朱莉ちゃんの気持ちを踏みにじったことになると思うの。だから、今日————」
今度はミツキの声がかき消される。だから今日……もしかして。
「ミツキちゃん。あたしはね、シュンの彼氏でも何でもないからさ。だからこそ言えることってあると思うの。友達として。それとも、異性の友達からの忠告はだめ?」
かぶりを振るミツキは、朱莉の瞳を真っ直ぐに見て呟く。そんなことないよ、と。
「シュンはね、ミツキちゃんと出会う前のシュンとは別人のようになっちゃってね。ミツキちゃんのことを守ろう、とか。ミツキちゃんのためなら、とか。ミツキちゃんのために必死すぎて、周りが見えていない、というか。だから、忠告したかったの」
伏し目がちに僕を見る朱莉は少しだけ微笑を浮かべる。その意味を推《お》し量ることはできないのだけれども、僕をそんな風に思っていたなんて思いもよらなかった。
「朱莉ちゃん。ごめん。わたしがシュン君を駄目にしちゃっているってこと?」
「違うの。そうじゃなくて。シュンを取り巻く環境が変わっているの。ミツキちゃんと出会う前のシュンを悪く言う人は一人もいなかったのに。今では、歩くたびに陰口を叩かれていて。シュンはなんとも思っていないフリをしているけど。だれでも、そんな風になっちゃったら、いつか参っちゃうよ」
「いや、僕はそんなの全然————」
「それもミツキちゃん、あなたの浮気が原因なの。これは間違いないと思う。それを心配した女子がシュンを慰めるのが一番の原因。シュンは馬鹿真面目にミツキちゃんの浮気を全否定するから。側から見れば、単なるバカップルなの。あたしもこの前までそう思ってた」
「————ごめんなさい」
「だから、浮気をしていないというのは信じるとしても、今後、そういう思わせぶりなことはやめた方がいいと思う。どんな理由があったのか知らないけれど、シュンを苦しめていることに気付いて。芸能界だもの、きっとあたし達の知らないところで、色々とあるんでしょ。でも、シュンはミツキちゃんを守ろうとしているのに、ミツキちゃんはシュンを全然守ろうとしていないどころか、理解すらしていない。さすがに、あたしも見ていられないよ」
「朱莉。もういい。それ以上言うな。これは僕とミツキの問題なんだ。だから、僕が強くいられれば、何の問題もない。大したことない」
なんでミツキちゃんはシュンのことを見ようとしないの。
ぽつりと呟いた朱莉の言葉に、ミツキは完全に意気消沈してしまったように俯きながら唇を噛んでいた。違う、ミツキは僕を守ろうとか、そういうことじゃなくて。必死に未来に向かって進んでいるだけなのに。そこに、余裕がないだけなのに。
「ごめんね。シュン君。知らなかった。学校にあまり行っていなかったから、なんていうのは言い訳だけど。朱莉ちゃんに教えてもらわなかったら、わたし、何も知らずに……」
顔を両手で塞ぎ、泣き始めるミツキを朱莉は嘆息しながらただ見ていた。その視線に批判や嫉妬、悪意はなかったように見える。ただ、朱莉はそれを言うためにわざわざこんな公園に連れてきたのだろうか。
いつの間にか、花神楽美月《はなかぐらみつき》のエキスが抜けてしまったミツキは、もう花山充希《はなやまみつき》になってしまったのだろうか。朱莉の前でも泣くミツキは、きっと、今まで仮面を被っていたのだろう。強くなんてない。強い人間なんていない。ミツキだって普通の人間なのだ。
「ほら、順番来たよ。鐘鳴らすんでしょ。もう。泣いている場合じゃないよ」
「朱莉が泣かしたんだろ。いいか。僕は全く気にしていない。嫌われようが、陰口を叩かれようが、どうでもいい」
「あたしが見ていられないの。ミツキちゃんに心を掴まれたまま、気付いたら孤独になっちゃうシュンなんて、シュンじゃないでしょ。ミツキちゃんがいればそれだけで生きていけるの? 違うでしょ。ミツキちゃん以外すべて敵で、それで高校生活が上手くいくと思ってるの? いつか、自殺しちゃうんじゃないか、なんて思って、眠れなくなるのも嫌なの。この気持ちわかる? 分からないでしょ? ミツキちゃんしか見えていないんだから。もうサイテー」
一人は泣いていて、もう一人は泣き出しそうなのか、不機嫌なのか分からない表情。そして、僕は疲れ果てている表情。そんな写真を列の後ろの人に撮ってもらって。周りの人はみな怪訝《けげん》そうな表情をしていて、正直、学校生活よりもこっちのほうが恥ずかしかった。
ただ、三人で鳴らした鐘はどこまでも響いていくような気がして、空高く飛び立つ鳥のように空を駆け抜けていく。この音色は心の奥底で何回も反響していた。朱莉の言いたいことはよく分かったけれど、僕はミツキだけを見ていて何か悪いことでもあるのか、と反論したかったけれど、それはやめておいた。
泣いたらすっきりした、なんていうミツキは、蕎麦の花が咲き誇る前の古民家のベンチに座って茫然《ぼうぜん》とコキアの丘を眺めていた。僕はその隣でミツキの手を握る。冷たくなった手がなんだか、可哀想で。それでいて、愛おしくて。
「ねえ、シュン君。朱莉ちゃんの言うとおりだね。わたし、全然シュン君を見ていなかったんだと思う。自分のことばっかりで。すべてわたしの責任なのに」
「陰口を叩かれるくらいどうってことないんだ。慣れてるから。でもね、そんな僕を気遣ってくれる人がいるってことは、やっぱりその気持ちも大切にしなくちゃいけないのかな、なんて思うよ」
「うん。朱莉ちゃんのことも大切にしてあげて。あんなにシュン君を想ってくれるんだもん。妬いちゃうくらい素敵。本当にシュン君のことが好きなんだね」
「ねえ、ミツキ。今日って本当はオフなんかじゃなかったんでしょ。無理やり休んだんでしょ」
「————シュン君には隠し事できないなぁ。うん。だって、朱莉ちゃんが、シュン君のことで話があるって言ってきたら、断れないでしょ」
やがてお手洗いから戻ってきた朱莉は、遊園地に行きたいと言い出し公園内を移動した。
公園よりも家族連れが多く、喧騒《けんそう》に包まれた秋の空気が、屋台の香ばしい香りを運んでくる。スキップをする子供が転んだ後に、すぐ後ろの父親が抱きかかえて泣きじゃくる子供をあやしていた。みんなそれぞれの生き方があって、みんなそれぞれ、なにかしらを抱えているのかと思うと、少しだけ感傷的になる。僕もそういう社会の一部であって、朱莉の言いたいことが少しだけ理解できた。
観覧車の前で朱莉は、ミツキちゃん借りるね、と言って二人で行ってしまった。朱莉はもしかして、あの密室で二人きりになるために、わざわざここまで来たのか。ミツキになにを話すつもりなのか、少し不安になる。まさか殴り合いの喧嘩をしようとは思っていないとは思うのだけれども。
しかし、スマホに入ったメッセージを見て僕は思わずうな垂れた。ミツキからだ。
ごめん、朱莉ちゃんに話すね。シュン君には悪いけど、朱莉ちゃんに隠し通すのは難しいし、シュン君の口からより、わたしから言った方がシュン君は気持ちが楽でしょ。それに後から知らされてなかった、っていうのは可哀そう。ごめんなさい。勝手なことを今からします。
僕が言えなかったのが一番の原因なのか。観覧車から降りてくる朱莉を見るのが辛い。きっと、泣いて僕に掴みかかるか、もしくは、怒りながら、なんで言わないのよ、啖呵《たんか》を切るか、のどちらかだ。憂鬱だ。
だけど、観覧車を降りて来た朱莉はそのどちらでもない。茫然としていて、なにも話さない、反応しない、ただ僕を見ているだけだった。ミツキは僕を見ながら朱莉の後ろでゆっくりとかぶりを振って、瞳を閉じた。
「朱莉……どうしたの。ほら、怒って掴みかかってきたり、グミを食べさせてきたり、なんかしてよ。無反応なのは怖いよ」
「ねえ、シュン。初めて会った日覚えてる?」
「う、うん。銀杏の木の下で」
「あの日思ったの。倉美月春夜が近くにいるだけであたしは満足だって。付き合いたいとかそういうことじゃなくて、この人と友達になりたいって。でも、そうは言っても、あわよくば付き合えたらいいな、なんて夢みたいなこと思ってたの」
「朱莉……」
「きっとシュンには好きな人がいて、あたしなんて眼中にないだろうから、髪を切って一人でフラれてしまえば、友達になるのも簡単かな、なんて自己解決しちゃったくらいにしてさ。そうしている内に、なんだか本当にいて当たり前の生活になっちゃって。シュンと毎朝、坂でふざけ合って。たまに遊んでみたりして。すごく楽しかった。でも……でも」
「朱莉ちゃん……」
いなくなっちゃうなんて。ひどい。ごめん。今日はほんとうにごめん。知らなかったの。シュンのこと知らなかったのはあたし。何も知らないで、本当にごめん。
「朱莉、僕はまだ死んでいないよ。死ぬ気もない。だから顔を上げてよ」
ジェットコースターに揺さぶられた人々の悲鳴が、可愛らしいBGMを全否定して、子供たちのはしゃぐ声が、目まぐるしく虚空を満たしていく。みんな何かしら抱えて生きている。それでも、ここでは笑って、楽しんで。幸せな時間を過ごして。なのに、なのに、朱莉はなんで泣いているの。そんなのって悲しいよ。
「じゅん……あだじ。あたし、絶対にシュンを。シュンを守る。ミツキちゃんがいないときはあたしが守るから」
どんな話をしたのか、とミツキに視線を送るが、ミツキは朱莉からもらい泣きをする始末。これはいよいよ、僕が二股をかけて泣かしている図、という見方が粗方《あらかた》の予想のようだ。道行く人は、ひそひそと僕を見ながら通り過ぎていく。全然、僕を守っていないじゃないか。酷いよ。朱莉。ちぐはぐだ。
「朱莉ちゃ~~ん。ありがとう。本当にありがと~~~」
そして、観覧車の乗り場前で二人抱き合う姿は、異様な光景である。やはり、僕は蚊帳《かや》の外で、僕の意思なんて関係ないままブリキのおもちゃは動き出すんだろう。シュン君のためだから。シュンのことはあたしが引き受けた、なんて言って。
結局、二人が泣き止んだころには、すっかり仲直りをしていて、日が暮れるまで遊んで帰った。その間、僕は一人、ベンチの上でニューチューブを見ていたのだ。身体のことがあって、ほぼすべてのアトラクションが乗れないから。
でも、仲良く遊ぶ二人を見ていてすごく幸せな気分になったのだから、来てよかった。
うわあ、すごい、と感嘆するミツキは、スマホを両手に持って写真を撮ることにご執心のようだ。確かに、これは圧巻である。
真っ白なアクリルの絵の具にアクアマリンのような海色を数滴落として、乱雑に混ぜたような空色に魔女が息を吹きかけたような雲が囁《ささや》いていて、風の音が随分と優しく聞こえた。
だけど、隣で僕に冷たい視線をくれる朱莉《あかり》は、そんな風の音を打ち消して僕にケチをつけてくる。なぜ、この場所を選んだのか。朱莉の頭蓋骨をこじ開けて、中身を見たくなった。いったい何を企んでいるのか。まさか、ミツキをどこかの崖から突き落とそうとしているのか。それとも、ミステリードラマのように崖の上でミツキから罪を訊《き》き出そうとしているのか。どちらにしても、気を緩めることができない。
「すごい。ねえ、シュン君、あの丘登ってみようよ」
まさに偶然の賜物であって、貴重な時間。丸一日のオフ。それを朱莉の計画に潰されるなんて、酷すぎる。なんて言った僕を諭すように、ミツキはかぶりを振ってコスモスを見ることに賛成したのだから、その気持ちを朱莉にも汲《く》み取って欲しい。おそらく無理だけど。
「うん。行こう。ほら、朱莉も行くよ」
「分かっているでござる。シュン、言っておくけど、ミツキちゃんにちゃんとあたしがお灸を据えるから。手伝ってよ」
「なんで僕が。というか、ミツキは潔白だって。本当にしつこいやつだな」
眉間に寄せた皺《しわ》の気迫で僕を圧倒しようとする朱莉は、笑顔で振り返って手を振るミツキにぎこちない笑みを浮かべながら、手を振り返した。
倉美月春夜《くらみつきしゅんや》がいる。なんていう声はもう気にしないことにした。もうなんとでも言えばいいよ。ミツキがアイドルを引退する来年には、どうでも良くなっているんだから。
変装したミツキは、なぜか正体がバレない。やはり人間の認識なんてそんなものなのだろう。ただ、僕がいることでバレないとも限らないのだけれども。
丘を登るにつれて、風が吹き荒ぶ。海風は猛烈に潮の薫りを運んできて、中腹に設置された鐘を鳴らすカップルたちが顔をしかめていた。まるで愛を祝福するような教会の音色のように響き渡る音が、朱莉の逆鱗《げきりん》に触れたようで。とにかく、愚痴がすごい。いい加減に彼氏を作りなよ、と言うと、白目を剥《む》くんじゃないかと思えるほど僕を睨《にら》んでくる。
「ねえ、みんなで鳴らそうよ。朱莉ちゃんも一緒に」
「あ、ああ。だってさ。朱莉もそろそろ普通に楽しみなよ」
屈託のない笑顔のミツキは、後ろ歩きをしながら僕と朱莉の手をそれぞれ引き始める。冷たくなったミツキの手を温めてあげたいのだけれども、朱莉がいるから難しい。ああ、もどかしい。
なぜこの鐘を鳴らしたいのか、なにかジンクスでもあるのか、と調べても何も出てこない。きっと、そこに鐘があるから鳴らす、というのが大勢の見解のようだった。それに、インストグラムに投稿でもするのだろう、と思われる。
「ねえ。ミツキちゃん。なんでミツキちゃんは————」
「え? なんて?」
近くで聞けば、空気と風を割ってしまうように鳴り響くけたたましい音に、朱莉の声は呑み込まれてしまった。その眼差しからは、悲しみが見て取れる。ミツキも気付いたようで、笑顔が消えていた————いや、素に戻ったと言ったほうが正確かもしれない。ミツキは、無理して笑顔を作っていたのだ。それに気づかなかった僕も朱莉も、同罪だ。
「ごめん……ね。朱莉ちゃん。わたし、確かに約束破っちゃったよね」
「ミツキ、それは違————」
「違わないの。朱莉ちゃんにしてみれば、わたしがシュン君を傷つけたことは事実なんだから。そこにどんな理由があっても、朱莉ちゃんの気持ちを踏みにじったことになると思うの。だから、今日————」
今度はミツキの声がかき消される。だから今日……もしかして。
「ミツキちゃん。あたしはね、シュンの彼氏でも何でもないからさ。だからこそ言えることってあると思うの。友達として。それとも、異性の友達からの忠告はだめ?」
かぶりを振るミツキは、朱莉の瞳を真っ直ぐに見て呟く。そんなことないよ、と。
「シュンはね、ミツキちゃんと出会う前のシュンとは別人のようになっちゃってね。ミツキちゃんのことを守ろう、とか。ミツキちゃんのためなら、とか。ミツキちゃんのために必死すぎて、周りが見えていない、というか。だから、忠告したかったの」
伏し目がちに僕を見る朱莉は少しだけ微笑を浮かべる。その意味を推《お》し量ることはできないのだけれども、僕をそんな風に思っていたなんて思いもよらなかった。
「朱莉ちゃん。ごめん。わたしがシュン君を駄目にしちゃっているってこと?」
「違うの。そうじゃなくて。シュンを取り巻く環境が変わっているの。ミツキちゃんと出会う前のシュンを悪く言う人は一人もいなかったのに。今では、歩くたびに陰口を叩かれていて。シュンはなんとも思っていないフリをしているけど。だれでも、そんな風になっちゃったら、いつか参っちゃうよ」
「いや、僕はそんなの全然————」
「それもミツキちゃん、あなたの浮気が原因なの。これは間違いないと思う。それを心配した女子がシュンを慰めるのが一番の原因。シュンは馬鹿真面目にミツキちゃんの浮気を全否定するから。側から見れば、単なるバカップルなの。あたしもこの前までそう思ってた」
「————ごめんなさい」
「だから、浮気をしていないというのは信じるとしても、今後、そういう思わせぶりなことはやめた方がいいと思う。どんな理由があったのか知らないけれど、シュンを苦しめていることに気付いて。芸能界だもの、きっとあたし達の知らないところで、色々とあるんでしょ。でも、シュンはミツキちゃんを守ろうとしているのに、ミツキちゃんはシュンを全然守ろうとしていないどころか、理解すらしていない。さすがに、あたしも見ていられないよ」
「朱莉。もういい。それ以上言うな。これは僕とミツキの問題なんだ。だから、僕が強くいられれば、何の問題もない。大したことない」
なんでミツキちゃんはシュンのことを見ようとしないの。
ぽつりと呟いた朱莉の言葉に、ミツキは完全に意気消沈してしまったように俯きながら唇を噛んでいた。違う、ミツキは僕を守ろうとか、そういうことじゃなくて。必死に未来に向かって進んでいるだけなのに。そこに、余裕がないだけなのに。
「ごめんね。シュン君。知らなかった。学校にあまり行っていなかったから、なんていうのは言い訳だけど。朱莉ちゃんに教えてもらわなかったら、わたし、何も知らずに……」
顔を両手で塞ぎ、泣き始めるミツキを朱莉は嘆息しながらただ見ていた。その視線に批判や嫉妬、悪意はなかったように見える。ただ、朱莉はそれを言うためにわざわざこんな公園に連れてきたのだろうか。
いつの間にか、花神楽美月《はなかぐらみつき》のエキスが抜けてしまったミツキは、もう花山充希《はなやまみつき》になってしまったのだろうか。朱莉の前でも泣くミツキは、きっと、今まで仮面を被っていたのだろう。強くなんてない。強い人間なんていない。ミツキだって普通の人間なのだ。
「ほら、順番来たよ。鐘鳴らすんでしょ。もう。泣いている場合じゃないよ」
「朱莉が泣かしたんだろ。いいか。僕は全く気にしていない。嫌われようが、陰口を叩かれようが、どうでもいい」
「あたしが見ていられないの。ミツキちゃんに心を掴まれたまま、気付いたら孤独になっちゃうシュンなんて、シュンじゃないでしょ。ミツキちゃんがいればそれだけで生きていけるの? 違うでしょ。ミツキちゃん以外すべて敵で、それで高校生活が上手くいくと思ってるの? いつか、自殺しちゃうんじゃないか、なんて思って、眠れなくなるのも嫌なの。この気持ちわかる? 分からないでしょ? ミツキちゃんしか見えていないんだから。もうサイテー」
一人は泣いていて、もう一人は泣き出しそうなのか、不機嫌なのか分からない表情。そして、僕は疲れ果てている表情。そんな写真を列の後ろの人に撮ってもらって。周りの人はみな怪訝《けげん》そうな表情をしていて、正直、学校生活よりもこっちのほうが恥ずかしかった。
ただ、三人で鳴らした鐘はどこまでも響いていくような気がして、空高く飛び立つ鳥のように空を駆け抜けていく。この音色は心の奥底で何回も反響していた。朱莉の言いたいことはよく分かったけれど、僕はミツキだけを見ていて何か悪いことでもあるのか、と反論したかったけれど、それはやめておいた。
泣いたらすっきりした、なんていうミツキは、蕎麦の花が咲き誇る前の古民家のベンチに座って茫然《ぼうぜん》とコキアの丘を眺めていた。僕はその隣でミツキの手を握る。冷たくなった手がなんだか、可哀想で。それでいて、愛おしくて。
「ねえ、シュン君。朱莉ちゃんの言うとおりだね。わたし、全然シュン君を見ていなかったんだと思う。自分のことばっかりで。すべてわたしの責任なのに」
「陰口を叩かれるくらいどうってことないんだ。慣れてるから。でもね、そんな僕を気遣ってくれる人がいるってことは、やっぱりその気持ちも大切にしなくちゃいけないのかな、なんて思うよ」
「うん。朱莉ちゃんのことも大切にしてあげて。あんなにシュン君を想ってくれるんだもん。妬いちゃうくらい素敵。本当にシュン君のことが好きなんだね」
「ねえ、ミツキ。今日って本当はオフなんかじゃなかったんでしょ。無理やり休んだんでしょ」
「————シュン君には隠し事できないなぁ。うん。だって、朱莉ちゃんが、シュン君のことで話があるって言ってきたら、断れないでしょ」
やがてお手洗いから戻ってきた朱莉は、遊園地に行きたいと言い出し公園内を移動した。
公園よりも家族連れが多く、喧騒《けんそう》に包まれた秋の空気が、屋台の香ばしい香りを運んでくる。スキップをする子供が転んだ後に、すぐ後ろの父親が抱きかかえて泣きじゃくる子供をあやしていた。みんなそれぞれの生き方があって、みんなそれぞれ、なにかしらを抱えているのかと思うと、少しだけ感傷的になる。僕もそういう社会の一部であって、朱莉の言いたいことが少しだけ理解できた。
観覧車の前で朱莉は、ミツキちゃん借りるね、と言って二人で行ってしまった。朱莉はもしかして、あの密室で二人きりになるために、わざわざここまで来たのか。ミツキになにを話すつもりなのか、少し不安になる。まさか殴り合いの喧嘩をしようとは思っていないとは思うのだけれども。
しかし、スマホに入ったメッセージを見て僕は思わずうな垂れた。ミツキからだ。
ごめん、朱莉ちゃんに話すね。シュン君には悪いけど、朱莉ちゃんに隠し通すのは難しいし、シュン君の口からより、わたしから言った方がシュン君は気持ちが楽でしょ。それに後から知らされてなかった、っていうのは可哀そう。ごめんなさい。勝手なことを今からします。
僕が言えなかったのが一番の原因なのか。観覧車から降りてくる朱莉を見るのが辛い。きっと、泣いて僕に掴みかかるか、もしくは、怒りながら、なんで言わないのよ、啖呵《たんか》を切るか、のどちらかだ。憂鬱だ。
だけど、観覧車を降りて来た朱莉はそのどちらでもない。茫然としていて、なにも話さない、反応しない、ただ僕を見ているだけだった。ミツキは僕を見ながら朱莉の後ろでゆっくりとかぶりを振って、瞳を閉じた。
「朱莉……どうしたの。ほら、怒って掴みかかってきたり、グミを食べさせてきたり、なんかしてよ。無反応なのは怖いよ」
「ねえ、シュン。初めて会った日覚えてる?」
「う、うん。銀杏の木の下で」
「あの日思ったの。倉美月春夜が近くにいるだけであたしは満足だって。付き合いたいとかそういうことじゃなくて、この人と友達になりたいって。でも、そうは言っても、あわよくば付き合えたらいいな、なんて夢みたいなこと思ってたの」
「朱莉……」
「きっとシュンには好きな人がいて、あたしなんて眼中にないだろうから、髪を切って一人でフラれてしまえば、友達になるのも簡単かな、なんて自己解決しちゃったくらいにしてさ。そうしている内に、なんだか本当にいて当たり前の生活になっちゃって。シュンと毎朝、坂でふざけ合って。たまに遊んでみたりして。すごく楽しかった。でも……でも」
「朱莉ちゃん……」
いなくなっちゃうなんて。ひどい。ごめん。今日はほんとうにごめん。知らなかったの。シュンのこと知らなかったのはあたし。何も知らないで、本当にごめん。
「朱莉、僕はまだ死んでいないよ。死ぬ気もない。だから顔を上げてよ」
ジェットコースターに揺さぶられた人々の悲鳴が、可愛らしいBGMを全否定して、子供たちのはしゃぐ声が、目まぐるしく虚空を満たしていく。みんな何かしら抱えて生きている。それでも、ここでは笑って、楽しんで。幸せな時間を過ごして。なのに、なのに、朱莉はなんで泣いているの。そんなのって悲しいよ。
「じゅん……あだじ。あたし、絶対にシュンを。シュンを守る。ミツキちゃんがいないときはあたしが守るから」
どんな話をしたのか、とミツキに視線を送るが、ミツキは朱莉からもらい泣きをする始末。これはいよいよ、僕が二股をかけて泣かしている図、という見方が粗方《あらかた》の予想のようだ。道行く人は、ひそひそと僕を見ながら通り過ぎていく。全然、僕を守っていないじゃないか。酷いよ。朱莉。ちぐはぐだ。
「朱莉ちゃ~~ん。ありがとう。本当にありがと~~~」
そして、観覧車の乗り場前で二人抱き合う姿は、異様な光景である。やはり、僕は蚊帳《かや》の外で、僕の意思なんて関係ないままブリキのおもちゃは動き出すんだろう。シュン君のためだから。シュンのことはあたしが引き受けた、なんて言って。
結局、二人が泣き止んだころには、すっかり仲直りをしていて、日が暮れるまで遊んで帰った。その間、僕は一人、ベンチの上でニューチューブを見ていたのだ。身体のことがあって、ほぼすべてのアトラクションが乗れないから。
でも、仲良く遊ぶ二人を見ていてすごく幸せな気分になったのだから、来てよかった。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

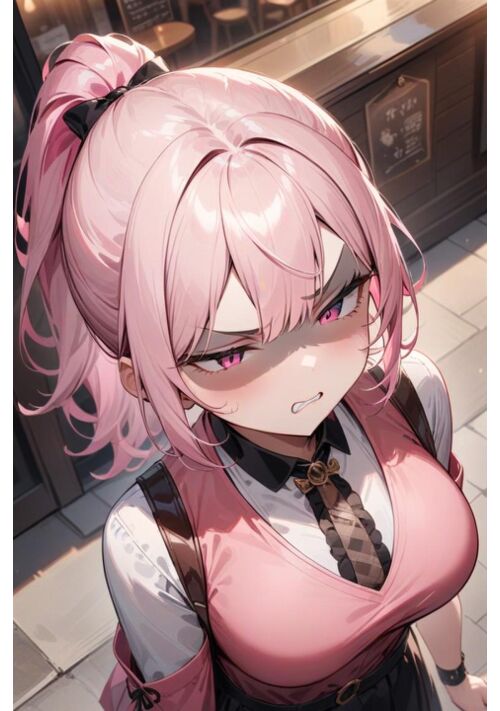
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















