46 / 61
霜夜の冬・ミツキの雪
シュン君が————うときは……わたしも。
しおりを挟む
珍しくミツキが風邪を引いた。学校を休むくらいなのだから、相当苦しいはず。風邪を引けば命取りの僕を思ってのことなのだろう。近づかないで、と昨晩、僕のことをミツキはけん制した。学校から帰るなり、僕はマスクをしてミツキの寝ている離れの引き戸を開く。
生憎《あいにく》、今日も姉さんと父さんはいない。当たり前のように母さんもいない。つまり、ミツキの看病をする人は僕しかいない。
「ミツキ~~~ゼリー買ってきたよ。上がるよ~~~!!」
きっと寝ているに違いない。上がりまちを踏みしめて歩く廊下は、ミツキの甘い香りに包まれていた。右側の引き戸を開くと整然とした部屋にベッドと机。手前には冷蔵庫とその向かいの棚に電気ポッドが置いてある。
こぢんまりとしたミツキの部屋は清潔感があって、とても居心地が良さそう。ベッドの上の盛り上がった布団がミツキなのだろう。確かに気温は低いけれども、あんなに布団に潜り込むのは、やはり発熱による悪寒が酷いのだろうか。
入るよ、と言ってベッドの横に立ち、布団を捲《まく》し上げてミツキを窺《うかが》う。寄せた眉間の皺《しわ》がその辛さを物語っている。頭痛が酷いのか、あるいは倦怠感《けんたいかん》で動けないのか。どちらにせよ、気の毒に思い、母屋から持ってきた冷えピタをそのおでこに貼る。すると、ゆっくりと瞼を開いたミツキは、跳び起きて言う。ダメじゃないシュン君、と。
「手洗いうがいするから、大丈夫だよ。こう見えて、風邪はここ五年くらい引いたことないし。それよりも、ほら、横になって」
もう、と頬を膨らませるミツキの肩まで布団を掛けて、コンビニ袋から取り出したゼリー飲料をベッドボードに置く。ふと、ベッドの向かいの机に視線を向けると、僕は思わず息を呑んでしまった。積み重なる心臓病に関する本の山。治療法や病気との付き合い方、それに食事法まで。あとは、ネットからプリントアウトした文献《ぶんけん》が束になって置いてある。どれもびっしりと付箋《ふせん》が張られていて、幾重にも蛍光マーカーで線が引かれていた。
「ミツキ……ありがとう」
「……え?」
「だって、こんなに本とかさ」
「ああ……それは、ごほっ」
咳き込むミツキの背中を摩《さす》って、僕は顔を背けた。決して咳をするミツキから顔を逸らしたわけではなく、溢れそうな涙を必死にこらえるために。昨日の行為でミツキが風邪を引くきっかけとなったのは確かなのだが、それだけではなく、僕のために割いてくれた勉強の時間がきっとミツキの体力を奪ったに違いない。だから、決めた。
「ミツキが治るまで、僕が看病するから」
「それは……だめ。シュン君にうつしちゃったら大変だもの」
たまには僕にも看病させてよ、と言って袋から取り出したヨーグルトを冷蔵庫に入れる。冷蔵庫の中の大部分を天然水のペットボトルが占拠していて、食べるものが一つもないことが気がかりだ。
「ねえ、食欲はあるの?」
「あまり……ないかも」
赤らめた顔はきっと発熱をしており、潤んだ瞳は悲しみを帯びているわけではないことが明らかだ。寒かったのか、エアコンの温める部屋の気温が二五度を超えていて、思わずパーカーの腕をまくる。しかし、こんな乾燥した部屋では、とても具合が良くなるとは思えない。
「ねえ、少し寒いかもしれないけれど、換気するね」
「うん」
開いた窓から流れ込む冷風は、まるで神聖さを帯びているように清らかで、ミツキが、うぅ寒い、と布団を口元まで被る反面、僕は気持ちが良かった。ミツキの首筋と腕に鳥肌が広がり、冷えピタを貼った額が汗で滲《にじ》み、その前髪は少し濡れている。辛いのかな。どうしたら楽になるだろう。
「食欲がなくても、少し食べられない? ゼリーなら食べられるんじゃないかな」
ベッドボードに置いたゼリーを手に取り、キャップを捻《ひね》り手渡すとミツキは上体を起こして口をつける。うん、おいしい、と口にして視線を落とした。風邪を引いているのだから元気はないのは当然としても、精神的にも落ち込んでいるみたい。きっと、僕のことを考えている。
「迷惑かけちゃってごめんなさい。あとは寝ているから、ね。シュン君、うつったら大変。だから————」
「心細いでしょ。それに、今日は月も出ない新月。ってことは、ミツキは電気を点けて寝るしかないけど、それじゃあ、熟睡できないよ」
「だめだめだめ。絶対にダメ」
「僕が発作を起こした日は、必ずミツキが僕に寄り添ってくれたでしょ。あれがどれほど心強いか。だから、今日は僕がミツキに寄り添うよ」
吸い込むゼリーに頬を膨らませるミツキは、眉間に皺を寄せてじっと僕を見つめる。むぅ、と声を漏らす顔の可愛いこと。思わず頭を撫で撫でして、後ろに回り込んだ僕はミツキの肩を抱き締めた。うつっちゃうよ、なんて声はこの際無視をして。
「でも……」
「じゃあ、ミツキのことが心配すぎて僕が死んじゃってもいいの?」
どれだけ心配性なんだよ、なんて自嘲《じちょう》する。しかし、ミツキの身体もそうだけど、暗い夜に怯《おび》えるミツキの方がどちらかと言えば心配だ。未だに癒えない心の傷は、僕が傍《そば》にいなければ広がってしまうのではないか、と。
「うぅ……シュン君が死んじゃうのは絶対に嫌。だけど、風邪うつっちゃったら……」
「その時はミツキに看病してもらうよ。はいヨーグルトね」
自分で食べられるのに、と言うミツキの口にヨーグルトを乗せたスプーンを運んで食べさせる。可愛い小鳥に餌付けをしているみたいで、なぜか嬉しい、と僕が言うとシュン君に懐《なつ》いていて可愛いでしょ、なんて。つい抱きしめたくなる。
★☆☆
時間が経つにつれて、ようやくミツキの悪寒が止んだ深夜〇時過ぎ、ミツキは目を覚ますと、その夜の暗さに混乱して声を漏らす。もうやめてぇ、と。夢幻《ゆめまぼろし》と現実の狭間で喘ぐ悲哀《ひあい》の少女。
椅子に腰かけて微睡《まどろ》む僕は、その声に反応して立ち上がり、大丈夫だよ、と声を掛けながらその手を握る。暗い夜に怯えるミツキには僕が絶対に必要で、まるで自分が特効薬みたい。だからこそ、一緒にいてあげないと。
「助けてシュン君……!!」
「大丈夫だから。ミツキ、僕はここにいるから」
ようやく落ち着きを取り戻したミツキは、怖い夢を見たの、と言って起こした上体を僕のお腹に押し付けてくる。その胸の鼓動は未だに収まる気配はなさそう。肩で息をするミツキの頭をゆっくり優しく撫でると、顔を上げて呟く。ごめんね、と。
「こんな時間に起きちゃったね。大丈夫?」
「……うん。大丈夫」
ミツキの身体から熱感は感じられない。熱が下がったのだろうか。測った体温は三六度八分。下がった熱に安堵の息を漏らした僕は、ミツキから離れて冷蔵庫のペットボトルを彼女に手渡す。
「シュン君。怖い夢を見たの。本当に怖かったよぉ」
潤んだ瞳に映る間接照明の橙《だいだい》が揺らめいて、唇が僅《わず》かに震えていた。未だ止まらない手の震えが、彼女の心の傷を連想させる。僕を抱きしめ返すミツキの小刻みに揺れる身体を力強く押さえると、安心したのか彼女は、ありがとうシュン君、と漏らす。
「ミツキのことは絶対に僕が守るからッ!!」
自分でも驚くほどに強い声色で、振動した空気が再び静寂を取り戻すまでに時間は掛からなかったけれど、その余韻はミツキの周囲をぐるぐると巡る。僕が怒っていると勘違いしたようで、はっ、と見上げた視線を僕から外そうとはしなかった。
「シュン君……?」
「ごめん。違うんだ。ミツキの身の安全が本当に心配で」
明らかに失言だった。今日に限ってそんなことを言ってしまうなんて。僕が花山健逸《はなやまけんいつ》と話をしたことがバレてしまうことだけは避けたい。
「ねえ。シュン君は何か知ってるの?」
「いや、違う。暗い夜にトラウマを抱いているミツキが心配って意味で」
「ねえシュン君。何を知っているの。ねえ」
シュン君、誰に訊《き》いたの?
「え?」
「わたしの事件は放っておいてくれていいの」
「何の話をしてるの?」
「————志桜里《しおり》ちゃんに聞いたの?」
新井木遥香《あらいぎはるか》は、確かに志桜里と碧唯《あおい》に聞きに行けと言っていた。だけど、まさかミツキから志桜里の名前が出るなんて思ってもみなかった。
「何も聞いていないよ? ねえ、ミツキ、いった——」
「シュン君は嘘を吐《つ》いてるよね。シュン君の嘘はすぐに分かるって言っているでしょ」
ベッドから立ち上がり、後ずさりする僕に詰め寄るミツキの表情は怒っているわけでも、悲しいわけでもなさそう。怪訝《けげん》。そう怪訝そうな表情。僕に対する疑いの目。この事件の真相を知ることがそんなに罪深いことなの。なぜ?
「ねえ、教えて。いったいミツキは何に巻き込まれているの?」
花山健逸に対する脅迫は、ミツキを人質にとった犯人のもの。それは、やはりミツキの拉致事件が関係しているのだろうか。だけど、ミツキの様子を見ていると、まるで————。まるで事件の全貌を知っているみたい。
「シュン君には関係ないの。ねえ、お願い。首を突っ込まないで、ね」
「それはできない。ある人から頼まれたから。ミツキをよろしく、って」
「————誰に?」
「僕のほかにもミツキを守りたいって人がいるんだ。今は明かせない。だけど、必ずいつか会わせるから」
俯いたミツキは握っていた拳を緩めて、顔を覆った。今にも嗚咽《おえつ》を上げそうな様子に、僕はゆっくりと近づき、ミツキの肩をそっと抱きしめる。いったいミツキを苦しめる原因は何なのか。やはり行こう。志桜里に直接訊かないと分からない。癪《しゃく》に障るけれど、新井木遥香の言う通りに。
「ミツキ、近々、僕は志桜里に会ってくる。はじめはミツキに隠して行こうと思ってたんだけど、やっぱり嘘は吐きたくない。だから、ミツキに告げて堂々と行くことにする」
「——やめ……て」
消え入るような言葉は、まるで暗闇に溶けていく淡い光のよう。微かな声色に帯びる悲しみ、或《ある》いは嘆きのような色彩はきっと無色で、僕の耳元を掠《かす》めていく。
「お願い。やめて」
「ねえ、ミツキ教えてよ。なんでそんなに僕を拒絶するの。僕はミツキの力になりたいだけなんだよ」
ゆっくりと息を吐いたミツキは、瞳を閉じて眉根を寄せると悲痛な表情で唇を噛んだ。力む鼻筋と頬の筋肉が再び緩むとき、ミツキは口を開く。違うの、と。
「シュン君を巻き込みたくないの。それに、これはもう終わった話。だから蒸し返さないで。取り返しがつかないことになっちゃうかもしれない。シュン君が巻き込まれちゃったら、わたしは……わたしはどうしたら」
「終わっていない……もし、僕が思っていることが事実だとしたら、終わった話ではないと思う。だから、ミツキが心配なんだ」
「————シュン君!?」
「犯人は誰とは断言できないけれど、僕なりに道筋ができた。ミツキノミコトの写真でミツキを復帰させようとした会社。そして、僕に三億円なんて大金をチラつかせて引っ張り出した会社。偶然にも同じ会社。なぜミツキに敢えて復帰して欲しいのか」
「…………シュン君。だめ。絶対にだめだよ」
————ミツキを再び……。
ぼんやりと見えてきた悪意のある思惑は、きっとミツキが引退しない限り続く。それどころか、引退させない気なのかもしれない。
「だから、ミツキ。僕と一緒に志桜里に会ってくれないか」
新井木遥香がどう関係しているのかは分からないけれど、話がややこしくなろうが、ミツキに隠し事はもうしたくない。秘密は花山健逸の件だけで十分だ。僕は嘘つきじゃない。吐きたくもない嘘をこれ以上増やしたくない。自分の意思とは無関係のところで吐かなければならない嘘は、ストレス以外の何物でもない。
「————分かった。でも約束して。話を聞くだけ、ね?」
「うん。分かった。でも、もしミツキに——」
「その先は言わないで。わたしは大丈夫。シュン君は自分のことだけ考えてくれれば大丈夫だから」
☆★☆
シュン君がもっと臆病だったら良かったのに、と言ったミツキは横たわるベッドで僕の方を見て嘆息する。いや、僕は臆病なのだけれども。
顎の下まで布団を掛けて、もう寝よう、とミツキの髪を梳《す》いた勇気のない僕は、自分の震える手を必死に抑えた。自分の病気のこともあるけれど、虎視眈々《こしたんたん》と狙う敵に対して何をすべきなのかが見えてこない。
「シュン君……手を握ってくれないかな」
「え。もちろんいいけど」
ベッドと掛布団の隙間から手を出すミツキの右手を握り、その上から左手で優しく包み込む。微かに感じるミツキの体温はすでに平熱で、汗ばんだパジャマは交換した方が良さそうなのだけれど。
「こうして握ってくれるだけでも幸せ。治ったら添い寝してね」
「————同じ空間にいたら、もう罹《かか》っているよねきっと」
握った手をザイルのようにして、ベッドを登頂していく。ミツキのベッドに潜り込んだ僕は、左手をミツキの首の下に潜り込ませると、自分の方に引き寄せる。風邪うつっちゃうよ、なんて言うミツキの唇にキスをして。そして、感じるミツキの体温が僕の心に火を灯《とも》す。
やはり、この子がいるおかげで僕は生を全うできる。もし、この子が僕の腕の中にいなければ、きっと僕は諦めて死んでいたかもしれない。死の呪縛は今も僕の心身を蝕《むしば》む。だけど、ミツキのお陰で黒ずむ精神は辛うじてせき止められていて、こうして傍にいるミツキの触れる肌が、僕の奥深くを温めてくれる。
「シュン君……お願い。わたしを連れて行って」
「どこに?」
………いなくならないで。いなくなるときは、わたしもシュン君の巡る世界に……。
弱気のミツキの瞳は少しだけ潤んでいて、僕を見つめる視線はとても弱々しく。僕を抱き締めるミツキは耳元で囁《ささや》く。
シュン君がもしも————ときは、わたしも————うから。
否定できない自分の弱さに辟易《へきえき》しながらも、僕は無言でミツキの髪を梳いた。
生憎《あいにく》、今日も姉さんと父さんはいない。当たり前のように母さんもいない。つまり、ミツキの看病をする人は僕しかいない。
「ミツキ~~~ゼリー買ってきたよ。上がるよ~~~!!」
きっと寝ているに違いない。上がりまちを踏みしめて歩く廊下は、ミツキの甘い香りに包まれていた。右側の引き戸を開くと整然とした部屋にベッドと机。手前には冷蔵庫とその向かいの棚に電気ポッドが置いてある。
こぢんまりとしたミツキの部屋は清潔感があって、とても居心地が良さそう。ベッドの上の盛り上がった布団がミツキなのだろう。確かに気温は低いけれども、あんなに布団に潜り込むのは、やはり発熱による悪寒が酷いのだろうか。
入るよ、と言ってベッドの横に立ち、布団を捲《まく》し上げてミツキを窺《うかが》う。寄せた眉間の皺《しわ》がその辛さを物語っている。頭痛が酷いのか、あるいは倦怠感《けんたいかん》で動けないのか。どちらにせよ、気の毒に思い、母屋から持ってきた冷えピタをそのおでこに貼る。すると、ゆっくりと瞼を開いたミツキは、跳び起きて言う。ダメじゃないシュン君、と。
「手洗いうがいするから、大丈夫だよ。こう見えて、風邪はここ五年くらい引いたことないし。それよりも、ほら、横になって」
もう、と頬を膨らませるミツキの肩まで布団を掛けて、コンビニ袋から取り出したゼリー飲料をベッドボードに置く。ふと、ベッドの向かいの机に視線を向けると、僕は思わず息を呑んでしまった。積み重なる心臓病に関する本の山。治療法や病気との付き合い方、それに食事法まで。あとは、ネットからプリントアウトした文献《ぶんけん》が束になって置いてある。どれもびっしりと付箋《ふせん》が張られていて、幾重にも蛍光マーカーで線が引かれていた。
「ミツキ……ありがとう」
「……え?」
「だって、こんなに本とかさ」
「ああ……それは、ごほっ」
咳き込むミツキの背中を摩《さす》って、僕は顔を背けた。決して咳をするミツキから顔を逸らしたわけではなく、溢れそうな涙を必死にこらえるために。昨日の行為でミツキが風邪を引くきっかけとなったのは確かなのだが、それだけではなく、僕のために割いてくれた勉強の時間がきっとミツキの体力を奪ったに違いない。だから、決めた。
「ミツキが治るまで、僕が看病するから」
「それは……だめ。シュン君にうつしちゃったら大変だもの」
たまには僕にも看病させてよ、と言って袋から取り出したヨーグルトを冷蔵庫に入れる。冷蔵庫の中の大部分を天然水のペットボトルが占拠していて、食べるものが一つもないことが気がかりだ。
「ねえ、食欲はあるの?」
「あまり……ないかも」
赤らめた顔はきっと発熱をしており、潤んだ瞳は悲しみを帯びているわけではないことが明らかだ。寒かったのか、エアコンの温める部屋の気温が二五度を超えていて、思わずパーカーの腕をまくる。しかし、こんな乾燥した部屋では、とても具合が良くなるとは思えない。
「ねえ、少し寒いかもしれないけれど、換気するね」
「うん」
開いた窓から流れ込む冷風は、まるで神聖さを帯びているように清らかで、ミツキが、うぅ寒い、と布団を口元まで被る反面、僕は気持ちが良かった。ミツキの首筋と腕に鳥肌が広がり、冷えピタを貼った額が汗で滲《にじ》み、その前髪は少し濡れている。辛いのかな。どうしたら楽になるだろう。
「食欲がなくても、少し食べられない? ゼリーなら食べられるんじゃないかな」
ベッドボードに置いたゼリーを手に取り、キャップを捻《ひね》り手渡すとミツキは上体を起こして口をつける。うん、おいしい、と口にして視線を落とした。風邪を引いているのだから元気はないのは当然としても、精神的にも落ち込んでいるみたい。きっと、僕のことを考えている。
「迷惑かけちゃってごめんなさい。あとは寝ているから、ね。シュン君、うつったら大変。だから————」
「心細いでしょ。それに、今日は月も出ない新月。ってことは、ミツキは電気を点けて寝るしかないけど、それじゃあ、熟睡できないよ」
「だめだめだめ。絶対にダメ」
「僕が発作を起こした日は、必ずミツキが僕に寄り添ってくれたでしょ。あれがどれほど心強いか。だから、今日は僕がミツキに寄り添うよ」
吸い込むゼリーに頬を膨らませるミツキは、眉間に皺を寄せてじっと僕を見つめる。むぅ、と声を漏らす顔の可愛いこと。思わず頭を撫で撫でして、後ろに回り込んだ僕はミツキの肩を抱き締めた。うつっちゃうよ、なんて声はこの際無視をして。
「でも……」
「じゃあ、ミツキのことが心配すぎて僕が死んじゃってもいいの?」
どれだけ心配性なんだよ、なんて自嘲《じちょう》する。しかし、ミツキの身体もそうだけど、暗い夜に怯《おび》えるミツキの方がどちらかと言えば心配だ。未だに癒えない心の傷は、僕が傍《そば》にいなければ広がってしまうのではないか、と。
「うぅ……シュン君が死んじゃうのは絶対に嫌。だけど、風邪うつっちゃったら……」
「その時はミツキに看病してもらうよ。はいヨーグルトね」
自分で食べられるのに、と言うミツキの口にヨーグルトを乗せたスプーンを運んで食べさせる。可愛い小鳥に餌付けをしているみたいで、なぜか嬉しい、と僕が言うとシュン君に懐《なつ》いていて可愛いでしょ、なんて。つい抱きしめたくなる。
★☆☆
時間が経つにつれて、ようやくミツキの悪寒が止んだ深夜〇時過ぎ、ミツキは目を覚ますと、その夜の暗さに混乱して声を漏らす。もうやめてぇ、と。夢幻《ゆめまぼろし》と現実の狭間で喘ぐ悲哀《ひあい》の少女。
椅子に腰かけて微睡《まどろ》む僕は、その声に反応して立ち上がり、大丈夫だよ、と声を掛けながらその手を握る。暗い夜に怯えるミツキには僕が絶対に必要で、まるで自分が特効薬みたい。だからこそ、一緒にいてあげないと。
「助けてシュン君……!!」
「大丈夫だから。ミツキ、僕はここにいるから」
ようやく落ち着きを取り戻したミツキは、怖い夢を見たの、と言って起こした上体を僕のお腹に押し付けてくる。その胸の鼓動は未だに収まる気配はなさそう。肩で息をするミツキの頭をゆっくり優しく撫でると、顔を上げて呟く。ごめんね、と。
「こんな時間に起きちゃったね。大丈夫?」
「……うん。大丈夫」
ミツキの身体から熱感は感じられない。熱が下がったのだろうか。測った体温は三六度八分。下がった熱に安堵の息を漏らした僕は、ミツキから離れて冷蔵庫のペットボトルを彼女に手渡す。
「シュン君。怖い夢を見たの。本当に怖かったよぉ」
潤んだ瞳に映る間接照明の橙《だいだい》が揺らめいて、唇が僅《わず》かに震えていた。未だ止まらない手の震えが、彼女の心の傷を連想させる。僕を抱きしめ返すミツキの小刻みに揺れる身体を力強く押さえると、安心したのか彼女は、ありがとうシュン君、と漏らす。
「ミツキのことは絶対に僕が守るからッ!!」
自分でも驚くほどに強い声色で、振動した空気が再び静寂を取り戻すまでに時間は掛からなかったけれど、その余韻はミツキの周囲をぐるぐると巡る。僕が怒っていると勘違いしたようで、はっ、と見上げた視線を僕から外そうとはしなかった。
「シュン君……?」
「ごめん。違うんだ。ミツキの身の安全が本当に心配で」
明らかに失言だった。今日に限ってそんなことを言ってしまうなんて。僕が花山健逸《はなやまけんいつ》と話をしたことがバレてしまうことだけは避けたい。
「ねえ。シュン君は何か知ってるの?」
「いや、違う。暗い夜にトラウマを抱いているミツキが心配って意味で」
「ねえシュン君。何を知っているの。ねえ」
シュン君、誰に訊《き》いたの?
「え?」
「わたしの事件は放っておいてくれていいの」
「何の話をしてるの?」
「————志桜里《しおり》ちゃんに聞いたの?」
新井木遥香《あらいぎはるか》は、確かに志桜里と碧唯《あおい》に聞きに行けと言っていた。だけど、まさかミツキから志桜里の名前が出るなんて思ってもみなかった。
「何も聞いていないよ? ねえ、ミツキ、いった——」
「シュン君は嘘を吐《つ》いてるよね。シュン君の嘘はすぐに分かるって言っているでしょ」
ベッドから立ち上がり、後ずさりする僕に詰め寄るミツキの表情は怒っているわけでも、悲しいわけでもなさそう。怪訝《けげん》。そう怪訝そうな表情。僕に対する疑いの目。この事件の真相を知ることがそんなに罪深いことなの。なぜ?
「ねえ、教えて。いったいミツキは何に巻き込まれているの?」
花山健逸に対する脅迫は、ミツキを人質にとった犯人のもの。それは、やはりミツキの拉致事件が関係しているのだろうか。だけど、ミツキの様子を見ていると、まるで————。まるで事件の全貌を知っているみたい。
「シュン君には関係ないの。ねえ、お願い。首を突っ込まないで、ね」
「それはできない。ある人から頼まれたから。ミツキをよろしく、って」
「————誰に?」
「僕のほかにもミツキを守りたいって人がいるんだ。今は明かせない。だけど、必ずいつか会わせるから」
俯いたミツキは握っていた拳を緩めて、顔を覆った。今にも嗚咽《おえつ》を上げそうな様子に、僕はゆっくりと近づき、ミツキの肩をそっと抱きしめる。いったいミツキを苦しめる原因は何なのか。やはり行こう。志桜里に直接訊かないと分からない。癪《しゃく》に障るけれど、新井木遥香の言う通りに。
「ミツキ、近々、僕は志桜里に会ってくる。はじめはミツキに隠して行こうと思ってたんだけど、やっぱり嘘は吐きたくない。だから、ミツキに告げて堂々と行くことにする」
「——やめ……て」
消え入るような言葉は、まるで暗闇に溶けていく淡い光のよう。微かな声色に帯びる悲しみ、或《ある》いは嘆きのような色彩はきっと無色で、僕の耳元を掠《かす》めていく。
「お願い。やめて」
「ねえ、ミツキ教えてよ。なんでそんなに僕を拒絶するの。僕はミツキの力になりたいだけなんだよ」
ゆっくりと息を吐いたミツキは、瞳を閉じて眉根を寄せると悲痛な表情で唇を噛んだ。力む鼻筋と頬の筋肉が再び緩むとき、ミツキは口を開く。違うの、と。
「シュン君を巻き込みたくないの。それに、これはもう終わった話。だから蒸し返さないで。取り返しがつかないことになっちゃうかもしれない。シュン君が巻き込まれちゃったら、わたしは……わたしはどうしたら」
「終わっていない……もし、僕が思っていることが事実だとしたら、終わった話ではないと思う。だから、ミツキが心配なんだ」
「————シュン君!?」
「犯人は誰とは断言できないけれど、僕なりに道筋ができた。ミツキノミコトの写真でミツキを復帰させようとした会社。そして、僕に三億円なんて大金をチラつかせて引っ張り出した会社。偶然にも同じ会社。なぜミツキに敢えて復帰して欲しいのか」
「…………シュン君。だめ。絶対にだめだよ」
————ミツキを再び……。
ぼんやりと見えてきた悪意のある思惑は、きっとミツキが引退しない限り続く。それどころか、引退させない気なのかもしれない。
「だから、ミツキ。僕と一緒に志桜里に会ってくれないか」
新井木遥香がどう関係しているのかは分からないけれど、話がややこしくなろうが、ミツキに隠し事はもうしたくない。秘密は花山健逸の件だけで十分だ。僕は嘘つきじゃない。吐きたくもない嘘をこれ以上増やしたくない。自分の意思とは無関係のところで吐かなければならない嘘は、ストレス以外の何物でもない。
「————分かった。でも約束して。話を聞くだけ、ね?」
「うん。分かった。でも、もしミツキに——」
「その先は言わないで。わたしは大丈夫。シュン君は自分のことだけ考えてくれれば大丈夫だから」
☆★☆
シュン君がもっと臆病だったら良かったのに、と言ったミツキは横たわるベッドで僕の方を見て嘆息する。いや、僕は臆病なのだけれども。
顎の下まで布団を掛けて、もう寝よう、とミツキの髪を梳《す》いた勇気のない僕は、自分の震える手を必死に抑えた。自分の病気のこともあるけれど、虎視眈々《こしたんたん》と狙う敵に対して何をすべきなのかが見えてこない。
「シュン君……手を握ってくれないかな」
「え。もちろんいいけど」
ベッドと掛布団の隙間から手を出すミツキの右手を握り、その上から左手で優しく包み込む。微かに感じるミツキの体温はすでに平熱で、汗ばんだパジャマは交換した方が良さそうなのだけれど。
「こうして握ってくれるだけでも幸せ。治ったら添い寝してね」
「————同じ空間にいたら、もう罹《かか》っているよねきっと」
握った手をザイルのようにして、ベッドを登頂していく。ミツキのベッドに潜り込んだ僕は、左手をミツキの首の下に潜り込ませると、自分の方に引き寄せる。風邪うつっちゃうよ、なんて言うミツキの唇にキスをして。そして、感じるミツキの体温が僕の心に火を灯《とも》す。
やはり、この子がいるおかげで僕は生を全うできる。もし、この子が僕の腕の中にいなければ、きっと僕は諦めて死んでいたかもしれない。死の呪縛は今も僕の心身を蝕《むしば》む。だけど、ミツキのお陰で黒ずむ精神は辛うじてせき止められていて、こうして傍にいるミツキの触れる肌が、僕の奥深くを温めてくれる。
「シュン君……お願い。わたしを連れて行って」
「どこに?」
………いなくならないで。いなくなるときは、わたしもシュン君の巡る世界に……。
弱気のミツキの瞳は少しだけ潤んでいて、僕を見つめる視線はとても弱々しく。僕を抱き締めるミツキは耳元で囁《ささや》く。
シュン君がもしも————ときは、わたしも————うから。
否定できない自分の弱さに辟易《へきえき》しながらも、僕は無言でミツキの髪を梳いた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

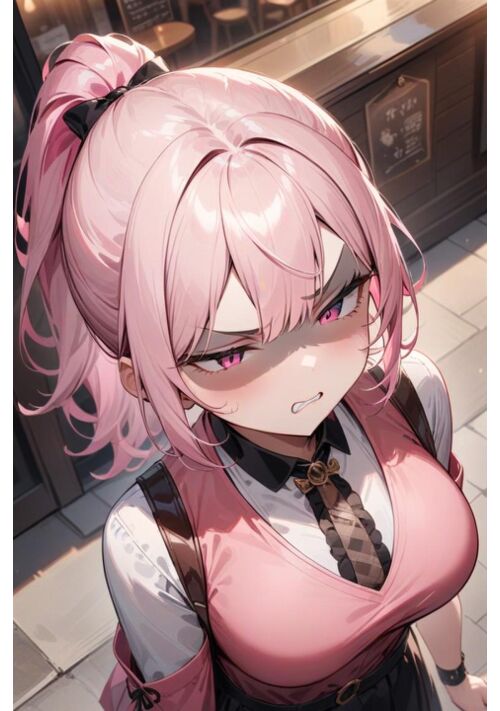
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















