45 / 61
霜夜の冬・ミツキの雪
重なる肌を温め合う甘い吐息の溢れる日
しおりを挟む
この辺は極寒の地ではないにしても、その日は一輪の花びらが舞い降りるように、雪が地面に溶け込んだ。儚《はかな》く散る白い結晶を手のひらで掴むと、吐き出す白い息が虚空《こくう》を染め上げる。だけど、すぐにまた虚無《きょむ》が無色に色づく。
学校から帰ると誰もいない居間の床に座り込み、僕は外を眺めていた。まだ一二月だと言うのに、骨を包む外側の肉が凍り付くのではないかというくらいに寒い。それもそのはずで、数年に一度の寒波が訪れていたのだから、冬将軍も凍えます、という上手いことを言った、したり顔のお天気おじさんもテレビの中で手を摩《さす》っていた。
ただいま、と玄関の引き戸を開けるミツキも鼻の頭を赤くしながら、エアコンの下で手を摩る。耳が冷たいの、なんて言いながらマフラーを外すと、ミツキは手洗いうがいをするために洗面所に小走りで向かっていった。
「ねえ、シュン君、今日もみんなお仕事で東京なの?」
「そうみたい。姉さんと母さんはともかく、父さんはジャケ写だって。どこかの歌手の」
「じゃあ、今日も二人きり?」
「そうなるね」
夕飯はお鍋にしようか、なんて話しているとますます雪が降ってくる。冷蔵庫の中身を見れば、買いだめをした食材がたんまりあって、姉さんの通販生活に抜け目がないことがよく分かった。姉さんに料理を習っているミツキは、最近では難しい料理を時短で作ることに凝り始めている。僕にはさっぱり理屈が分からないけれど、ミツキの料理はとてもおいしかった。
「窓、曇っちゃったね」
「外が寒いんだよ」
ミツキの人差し指で描く窓に生息した未知の生物は、まるでアニメの宇宙人。これはなに、と訊《き》くと、熊さんと答えるミツキの絵心が限りなくゼロに近いことは知っている。修学旅行のスケッチでも明らかだ。しかし、本人は自分が下手だと認識していないどころか、芸術性だけは僕に負けていないと自負する。いやいや、熊には到底見えない。
「ミツキ……それのどこが熊なの……?」
「酷い!! どう見ても熊さんでしょ」
頬を膨らませるミツキの再び描く熊は、どう見ても目が狂喜乱舞《きょうきらんぶ》しているクリーチャー。もう見るに堪《たえ》えない。
「ねえ、ミツキ。雪すごい綺麗だね。ちょっとだけ外出てみない?」
「……寒いの嫌い。だけど、シュン君が温めてくれるなら」
裸になった庭の木々たちを彩る白い雪たちが、凛《りん》とした空気の中でとめどなく溢れていた。毛糸の帽子が良く似合うミツキは、傘を差して空を仰《あお》ぐ。毛糸のマフラーが首を三周したころには口元まで隠れていて、キスできないね、なんて僕が言うと顎の下にそれを追いやった。淡い桃色の唇が、雪のように白い肌から浮き出るように色づき、思わず僕はキスをした。冷たい感触だけど、唇の内側の温もりが気持ち良い。
「ねえ、シュン君。キスしたいなら中に入ろうよ。寒くて凍えちゃう」
「しもやけになりそうだね。でも、雪ってすごく好き」
「綿菓子みたいだけど、雪は嫌い~。だって、寒いんだもん」
積もったら雪だるま作ろう、と約束をして玄関の引き戸を引いた。外気との温度差により手足がジンジンと鳴り響き、コートやマフラー、手袋を脱いで薄着になった僕たちは肩を寄せ合って外を眺める。この窓から眺める庭は、とても風情があって好きだった。それはミツキも同じようで、春夏秋冬どこを切り取っても美しい、と見つめる双眸《そうぼう》の先を庭から僕に移してまたキスをする。と言っても、僕がミツキの頭を寄せて視線を奪ったのだけれども。
重ねる唇が互いを奪い合い、それでも足りない僕の欲望がミツキを押し倒す。後頭部に置いた手の甲が床に当たって少し痛い。
「ここじゃだめ。だって床が痛いもの」
「そうだね」
ミツキの軽い体躯《たいく》を抱えて自室のベッドに優しく横たわらせると、その愛らしい瞳が僕を見つめる。彼女の吐息が桃色に染まる。
「シュン君……いいよ? 激しく求められるのも好きだから」
「せっかく温めてあげてるのに」
互いに脱いだ服をベッドの下に投げ捨てて、うつ伏せになったミツキの背中を弄《もてあそ》ぶ。
「ミツキ、愛してる……普段は言えないけど、いつも想っているよ」
「……嬉しい。シュン君。毎日雪が降ればいいのになぁ……あ。うぅん」
本当だよ、と言った僕の首筋を這うミツキの唇に思わず呻《うめ》いた。もう理性なんてそこには存在しない。あるのはミツキを求めるもう一人の僕の自我だけだった。
狂うように咲き乱れるミツキの指が僕の背中に食い込む。もし、ずっと一つのまま、このままミツキと朽ち果てるなら。それなら世界が明日失われても構わない。僕を構成する原子がミツキの原子と交じり合って、溶けあって、融合して、再び生まれ変われるならミツキと一つになりたい。
————それでも足りないなんて、僕は欲張りだ。
★☆☆
ふと目を覚ますと、日の落ちた窓の向こう側が黒いベルベットのように揺らめいていて、時計の針が八時を指している。痺《しび》れた僕の腕を枕にするミツキは、可愛い寝息を立てていて、布団を首まで掛けてあげた。起き上がった僕の身体はとても冷えていて、思わず身震いをする。急いで服を着ると、いなくなった僕に気付いたミツキが目を覚ます。
「あれ、寝ちゃってた……今何時?」
「八時みたい。どうりでお腹も空くよね」
そうだよね、ごめん、と言って服を着るミツキは少し顔色が悪い気がした。身体が冷えて風邪でも引いてしまったのだろうか。だけど、そんな素振りも見せずにいつもの元気なミツキだった。
「いや、謝ることではない気がするんだけど」
「だって、ご飯作るつもりだったのに……」
下着を身に着けたミツキの腕を引き、ベッドに寝そべった僕はその華奢《きゃしゃ》な身体を受け止める。きゃぁ、と声を上げるミツキを優しく抱きしめてキスをした。
「ちょっと、シュン君!?」
「ごめん。でも、離れたらなぜか急に恋しくなっちゃって」
「離れたって……ほんの一メートルじゃない」
「だって、寒いでしょ」
「……うん」
二度と離したくない。このままずっと。このままミツキと抱きしめ合っていたい。そう言った僕に、うん、とだけ答えてしばらく僕の肩越しに向こうを見ていたミツキは、突然、静かに笑い始める。
「どうしたの?」
「だって、シュン君、お腹空いてるんでしょ」
「まあ、うん」
「食欲より、わたしへの性欲のほうが勝ってるってこと?」
「……そう言われると、なんか僕が飢えた人みたいで嫌だ」
「ふふ。可笑しいね。でもすごく嬉しいの」
わたしは、食欲もあるけど、シュン君のほうを食べたいかな、なんて言って、僕の唇をかぶっと食べたミツキは、愛くるしい眼差しで僕を眺める。いたずら心いっぱいで、僕の頬を食べて、次に耳たぶ、そして、首筋を食べた。そのお返しに僕はミツキの二の腕を食べると、その柔らかい感触が気持ち良くてついその胸を求めた。柔らかく豊満な感触に思わず漏らした吐息がミツキの嬌声と相成《あいな》って、また彼女の温もりが欲しくなる。
「もう。シュン君は仕方のない子だなぁ」
「ミツキの方こそ。ねえ、ミツキ」
「うん?」
「このまま時間が止まればいいのにね」
肌を重ねれば重ねるほど、少し先の未来が頭をよぎる。幸せな時間を考えれば考えるほど、死の呪縛が僕を苦しめる。ミツキをこのままずっと抱きしめられたら。
「シュン君、また暗いこと考えているんでしょ」
「————うん。ごめん」
僕を抱き締めるミツキは耳元で囁《ささや》く。大丈夫だよ。わたしはずっとシュン君を抱き締めていてあげるから。だから、なにも心配しないで。
「年が明けて少ししたら、ミツキと離れ離れにならなくちゃいけないなんて」
でも、それは僕よりもミツキの方が深刻だったのかもしれない。眉尻を下げるミツキは、表情を見せまいと僕の胸に顔を埋めた。彼女の気も知らないで、僕はなんで弱音なんかを吐いたのだろう。ごめんね。ミツキ。
「シュン君は絶対に帰ってくるよね?」
「うん。絶対に」
「それなら、離れていても平気。帰ってきた時にまた嬉しさ倍増じゃない」
「でも、それでもミツキと離れたくない。辛いよ。辛いんだよ。怖い。すごく」
かぶりを振ったミツキは、上体を起こして僕の頭を抱き締める。大丈夫だから、わたしはいつも近くにいるからって。
「ごめん。波のように押し寄せるんだ。嬉しいことや楽しいこと、ミツキを愛おしいと思うことが強ければ強いほど、その反動のように恐怖とか悲しみが押し寄せてきて。あまりの大きさに押しつぶされそうになって」
しかし、ミツキはそんな僕を抱きしめ、そして、受け止めてくれる。優しく包み込むように抱擁するその腕の中は、まるで揺りかごのよう。とても居心地が良くて、つい甘えてしまう。
今度はわたしが優しく抱きしめて、シュン君にキスしてあげる。わたしが辛いときに、いつもシュン君がしてくれるように。
学校から帰ると誰もいない居間の床に座り込み、僕は外を眺めていた。まだ一二月だと言うのに、骨を包む外側の肉が凍り付くのではないかというくらいに寒い。それもそのはずで、数年に一度の寒波が訪れていたのだから、冬将軍も凍えます、という上手いことを言った、したり顔のお天気おじさんもテレビの中で手を摩《さす》っていた。
ただいま、と玄関の引き戸を開けるミツキも鼻の頭を赤くしながら、エアコンの下で手を摩る。耳が冷たいの、なんて言いながらマフラーを外すと、ミツキは手洗いうがいをするために洗面所に小走りで向かっていった。
「ねえ、シュン君、今日もみんなお仕事で東京なの?」
「そうみたい。姉さんと母さんはともかく、父さんはジャケ写だって。どこかの歌手の」
「じゃあ、今日も二人きり?」
「そうなるね」
夕飯はお鍋にしようか、なんて話しているとますます雪が降ってくる。冷蔵庫の中身を見れば、買いだめをした食材がたんまりあって、姉さんの通販生活に抜け目がないことがよく分かった。姉さんに料理を習っているミツキは、最近では難しい料理を時短で作ることに凝り始めている。僕にはさっぱり理屈が分からないけれど、ミツキの料理はとてもおいしかった。
「窓、曇っちゃったね」
「外が寒いんだよ」
ミツキの人差し指で描く窓に生息した未知の生物は、まるでアニメの宇宙人。これはなに、と訊《き》くと、熊さんと答えるミツキの絵心が限りなくゼロに近いことは知っている。修学旅行のスケッチでも明らかだ。しかし、本人は自分が下手だと認識していないどころか、芸術性だけは僕に負けていないと自負する。いやいや、熊には到底見えない。
「ミツキ……それのどこが熊なの……?」
「酷い!! どう見ても熊さんでしょ」
頬を膨らませるミツキの再び描く熊は、どう見ても目が狂喜乱舞《きょうきらんぶ》しているクリーチャー。もう見るに堪《たえ》えない。
「ねえ、ミツキ。雪すごい綺麗だね。ちょっとだけ外出てみない?」
「……寒いの嫌い。だけど、シュン君が温めてくれるなら」
裸になった庭の木々たちを彩る白い雪たちが、凛《りん》とした空気の中でとめどなく溢れていた。毛糸の帽子が良く似合うミツキは、傘を差して空を仰《あお》ぐ。毛糸のマフラーが首を三周したころには口元まで隠れていて、キスできないね、なんて僕が言うと顎の下にそれを追いやった。淡い桃色の唇が、雪のように白い肌から浮き出るように色づき、思わず僕はキスをした。冷たい感触だけど、唇の内側の温もりが気持ち良い。
「ねえ、シュン君。キスしたいなら中に入ろうよ。寒くて凍えちゃう」
「しもやけになりそうだね。でも、雪ってすごく好き」
「綿菓子みたいだけど、雪は嫌い~。だって、寒いんだもん」
積もったら雪だるま作ろう、と約束をして玄関の引き戸を引いた。外気との温度差により手足がジンジンと鳴り響き、コートやマフラー、手袋を脱いで薄着になった僕たちは肩を寄せ合って外を眺める。この窓から眺める庭は、とても風情があって好きだった。それはミツキも同じようで、春夏秋冬どこを切り取っても美しい、と見つめる双眸《そうぼう》の先を庭から僕に移してまたキスをする。と言っても、僕がミツキの頭を寄せて視線を奪ったのだけれども。
重ねる唇が互いを奪い合い、それでも足りない僕の欲望がミツキを押し倒す。後頭部に置いた手の甲が床に当たって少し痛い。
「ここじゃだめ。だって床が痛いもの」
「そうだね」
ミツキの軽い体躯《たいく》を抱えて自室のベッドに優しく横たわらせると、その愛らしい瞳が僕を見つめる。彼女の吐息が桃色に染まる。
「シュン君……いいよ? 激しく求められるのも好きだから」
「せっかく温めてあげてるのに」
互いに脱いだ服をベッドの下に投げ捨てて、うつ伏せになったミツキの背中を弄《もてあそ》ぶ。
「ミツキ、愛してる……普段は言えないけど、いつも想っているよ」
「……嬉しい。シュン君。毎日雪が降ればいいのになぁ……あ。うぅん」
本当だよ、と言った僕の首筋を這うミツキの唇に思わず呻《うめ》いた。もう理性なんてそこには存在しない。あるのはミツキを求めるもう一人の僕の自我だけだった。
狂うように咲き乱れるミツキの指が僕の背中に食い込む。もし、ずっと一つのまま、このままミツキと朽ち果てるなら。それなら世界が明日失われても構わない。僕を構成する原子がミツキの原子と交じり合って、溶けあって、融合して、再び生まれ変われるならミツキと一つになりたい。
————それでも足りないなんて、僕は欲張りだ。
★☆☆
ふと目を覚ますと、日の落ちた窓の向こう側が黒いベルベットのように揺らめいていて、時計の針が八時を指している。痺《しび》れた僕の腕を枕にするミツキは、可愛い寝息を立てていて、布団を首まで掛けてあげた。起き上がった僕の身体はとても冷えていて、思わず身震いをする。急いで服を着ると、いなくなった僕に気付いたミツキが目を覚ます。
「あれ、寝ちゃってた……今何時?」
「八時みたい。どうりでお腹も空くよね」
そうだよね、ごめん、と言って服を着るミツキは少し顔色が悪い気がした。身体が冷えて風邪でも引いてしまったのだろうか。だけど、そんな素振りも見せずにいつもの元気なミツキだった。
「いや、謝ることではない気がするんだけど」
「だって、ご飯作るつもりだったのに……」
下着を身に着けたミツキの腕を引き、ベッドに寝そべった僕はその華奢《きゃしゃ》な身体を受け止める。きゃぁ、と声を上げるミツキを優しく抱きしめてキスをした。
「ちょっと、シュン君!?」
「ごめん。でも、離れたらなぜか急に恋しくなっちゃって」
「離れたって……ほんの一メートルじゃない」
「だって、寒いでしょ」
「……うん」
二度と離したくない。このままずっと。このままミツキと抱きしめ合っていたい。そう言った僕に、うん、とだけ答えてしばらく僕の肩越しに向こうを見ていたミツキは、突然、静かに笑い始める。
「どうしたの?」
「だって、シュン君、お腹空いてるんでしょ」
「まあ、うん」
「食欲より、わたしへの性欲のほうが勝ってるってこと?」
「……そう言われると、なんか僕が飢えた人みたいで嫌だ」
「ふふ。可笑しいね。でもすごく嬉しいの」
わたしは、食欲もあるけど、シュン君のほうを食べたいかな、なんて言って、僕の唇をかぶっと食べたミツキは、愛くるしい眼差しで僕を眺める。いたずら心いっぱいで、僕の頬を食べて、次に耳たぶ、そして、首筋を食べた。そのお返しに僕はミツキの二の腕を食べると、その柔らかい感触が気持ち良くてついその胸を求めた。柔らかく豊満な感触に思わず漏らした吐息がミツキの嬌声と相成《あいな》って、また彼女の温もりが欲しくなる。
「もう。シュン君は仕方のない子だなぁ」
「ミツキの方こそ。ねえ、ミツキ」
「うん?」
「このまま時間が止まればいいのにね」
肌を重ねれば重ねるほど、少し先の未来が頭をよぎる。幸せな時間を考えれば考えるほど、死の呪縛が僕を苦しめる。ミツキをこのままずっと抱きしめられたら。
「シュン君、また暗いこと考えているんでしょ」
「————うん。ごめん」
僕を抱き締めるミツキは耳元で囁《ささや》く。大丈夫だよ。わたしはずっとシュン君を抱き締めていてあげるから。だから、なにも心配しないで。
「年が明けて少ししたら、ミツキと離れ離れにならなくちゃいけないなんて」
でも、それは僕よりもミツキの方が深刻だったのかもしれない。眉尻を下げるミツキは、表情を見せまいと僕の胸に顔を埋めた。彼女の気も知らないで、僕はなんで弱音なんかを吐いたのだろう。ごめんね。ミツキ。
「シュン君は絶対に帰ってくるよね?」
「うん。絶対に」
「それなら、離れていても平気。帰ってきた時にまた嬉しさ倍増じゃない」
「でも、それでもミツキと離れたくない。辛いよ。辛いんだよ。怖い。すごく」
かぶりを振ったミツキは、上体を起こして僕の頭を抱き締める。大丈夫だから、わたしはいつも近くにいるからって。
「ごめん。波のように押し寄せるんだ。嬉しいことや楽しいこと、ミツキを愛おしいと思うことが強ければ強いほど、その反動のように恐怖とか悲しみが押し寄せてきて。あまりの大きさに押しつぶされそうになって」
しかし、ミツキはそんな僕を抱きしめ、そして、受け止めてくれる。優しく包み込むように抱擁するその腕の中は、まるで揺りかごのよう。とても居心地が良くて、つい甘えてしまう。
今度はわたしが優しく抱きしめて、シュン君にキスしてあげる。わたしが辛いときに、いつもシュン君がしてくれるように。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

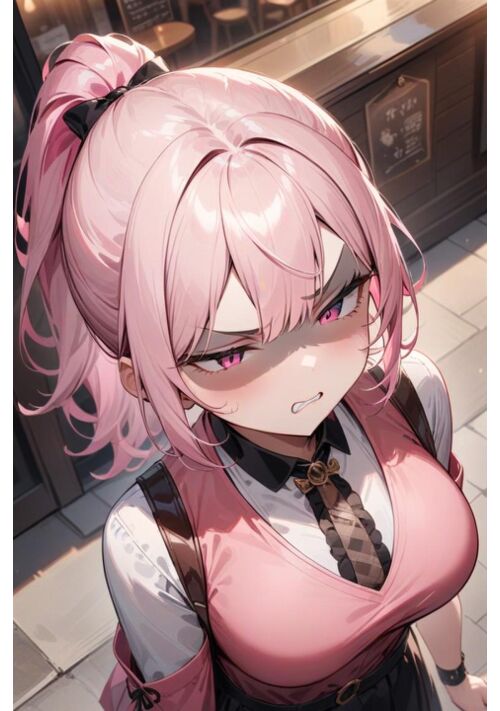
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















