59 / 61
巡る季節に告ぐ言葉・三月の雪
巡る季節に告ぐ言葉・三月の雪
しおりを挟む
風が華やぐ香《かぐわ》しき季節は、彩る草木に感ず芽吹《めぶ》く春。君と出会った季節に、僕は決心を固めた。この日をどれほど待ち望んだことか。庭の桜と梅が薫りて萌《も》ゆ朝に、ミツキを誘う。出かけたい。まだ、三月だというのに桜が咲いた。しかも満開。これは茨城北部ではありえないこと。
車に乗っていくの、と訊《き》いたミツキの言葉にかぶりを振って、僕はバスでいきたいと申し出る。訝しむミツキの額にキスをして、いいからいいから、と告げる朝八時。霞《かすみ》がかった空の色は水色に溶け出した群青色《ぐんじょういろ》。しかし、西の山に掛かる不気味な雲が、季節外れの雪を降らすと聞く。でも、今は囲炉裏《いろり》のような仄《ほの》かに感じる優しい陽気。桜の薫り短し命育むこの季節、この時に、僕は君に告げる。
もはや変装などいらないミツキは、裾の広がった辛子色の膝丈スカートに藍色のスプリングニット、それにデニムのライダースを着て、なんだかお姉さんになったな、と見惚れてしまった。
「シュン君、行こう。それでどこにいくの?」
「うん、すぐそこだよ。ミツキもよく知っているところ」
そうなんだ、と言って待つバス停のベンチは朝露《あさつゆ》で濡れていた。座らずに立ちながらバスを待っていると、ミツキは言う。ねえ、お花見に行きたいね。少し胸がちくり。
ようやくやってきたバスに乗り込んで、二人掛けの席に座ると僕の手を握るミツキは窓の外に視線をやって、桜が随分咲いたね、なんて。巡る季節に僕の手を引いてくれた君に、捧ぐ言葉はもう何度も僕の脳内を巡って、言葉を練り上げた喉奥の燃ゆる魂が、今かとその時を待っている。
ここで降りるよ、と言ってミツキに自分の腕を掴むように差し出すと、ありがとう、と絡みつけてきた腕がなんとなく震えていた——気がした。まさか、寒いのミツキ。
「ねえ、シュン君……ここって、衛星アンテナのあの公園だよね?」
「うん。お花見したいでしょ」
「……うん。でも、珍しいね。こんな朝から」
「今日は、雪の予報なんだよ。だから、晴れているうちに、ね」
春という慶福《けいふく》を全身で受け止めながら進む公園は、桜の香る幻想的な季節。家族連れやカップルがそれぞれの愛を囁《ささや》き、微笑み合う温かい空間は、まさに桜一色。華やぐ春色の花弁が地面まで彩り、空の青さと相成って、ポラロイドのような濃淡《のうたん》で描かれている。
公園の奥まで歩くと、目当ての場所にたどり着く。ミツキの呼吸が微かに変わる。僅かに荒くなった息遣いに、大丈夫だよ、落ち着いて。気付いているのかもしれない。
いや、僕の精神のほうが尋常じゃないのだけれども。手汗が滲《にじ》む感覚と、つま先から駆け上る血流が心臓を過ぎた辺りで沸点に達する僕の身体は、まるで煮えたぎる溶岩のよう。固まって動かなくなる四肢の関節が、ギスギスと音を立てる。ああ、こんな気持ちだったのかな。ミツキが僕に想いを伝えた時は。
「ミツキ。君がここで僕に想いを伝えた日のことは、今でも鮮明に覚えているよ」
「……シュン君」
「でも、恋人も今日で終わり」
「え————どういうこと?」
やはり意地悪したくなってしまう。ミツキの困り顔が見たくて。それに、何回も無いのだから。こうやって想いを真面目に伝えることなんて。
「だから、恋人は今日まで。ミツキ、色々とあったけど、本当に楽しかった。毎日、ミツキの顔を見るのが楽しくて、すこし切なくて」
「なんで……そういうこと言うの……本気で言っているの?」
「本気だよ。本気だからここに来たんだよ。ミツキ。昨日までの関係にさようならしよう」
「————ひどい」
泣きそうな顔のミツキを見て、少しやりすぎたかな、と、いつも反省してしまう。でも、この後に見せる表情が忘れられないくらいに好き。雪原から顔を出す水仙《スイセン》のような笑顔。だけど、春のように芽吹く僕の感情は、もうこれ以上抑えきれない。
「誕生日おめでとうミツキ。僕と結婚しよう。今日からは、恋人以上夫婦未満の関係。ね」
ジャケットの内ポケットから取り出したリングケースには、ダイヤの指輪。そっと取り出して、ミツキの左手の薬指に恐る恐る嵌《は》める。桜色のネイルが彩る長く美しい指に煌めく、朝露《あさつゆ》に反射して輝く光のようなダイヤモンドのハレーションに息を呑んだ。
「シュン君……」
今にも泣きそうな顔から、笑顔を咲かせるはずのミツキの瞳から落ちる雫。まさか。
本当に泣いてしまった。あれ、予想外の展開。ぼろぼろと流す涙は、まるで別れを告げられた恋人そのもの。しゃくりあげる泣き顔のミツキは、指輪に視線を落として、そのまま赤い瞳のままで、向日葵のような明るい笑顔など見せる気配はない。なんで、なんで泣き止まないの。お別れなんてしないから、泣き止んでよ。でも、ダイヤモンドに零れて砕ける涙の雫がミルククラウンのよう。その輝きが僕の心を打った。ミツキ、本当に愛している。
降りしきる桜の花びらが光に透ける様相はまるで雪。時間が止まった僕とミツキの周りに香《かぐわ》しき風が吹いて、頬を撫でるその花びらがくすぐったい。同時に鼻の上に感じる冷たい水滴。空を仰げば舞い散る雪の結晶。そうか、もう雪が。
手のひらを空に向ける。その冷たい感触に混じる、桜の花びらがひらひらと手のひらに舞い降りる。
花びらと雪の幻想的な光景に、ミツキも顔を上げて呟く。綺麗。
————三月《みつき》の雪が湿っぽいことに気付いた。
ようやく泣き止んだミツキを優しく抱きしめる。そして耳元で囁く言葉。君に告げる言葉。
好きだよミツキ。出会ったころよりもずっとずっと。
愛している。今までも。これからもずっとずっと。
★☆☆
しばらく沈黙した時間、僕たちは無言で抱き合った。舞い降りる雪と舞い散る桜の花びらが幻想的な時間を演出して、まるで奇跡の上に成り立つ舞台。そう、奇跡の上に僕たちは成り立つ。
巡り合わせ。出会いと命。時間と境遇。その一つ一つが僕たちを互いに引き合わせている。三月に咲く桜。暖かい日に降り積もる雪。そして、君の誕生日。
「ミツキ。それでどうなの。結婚してくれるの?」
「————どうしようかな」
「え。まさかここで断られるとか、もう死刑宣告なんだけど」
「だって、シュン君がいつも意地悪するんだもん。だから、焦らしちゃう」
「ええ。だって。ミツキの困り顔が見たいから」
「ほらぁ。そうやって。もう。じゃあ、キスして。今までで一番気持ちを込めて」
うん、と言って瞳を閉じる。抱きしめるその華奢《きゃしゃ》な身体を優しく引き寄せて、重ねた唇から感じるミツキの僅かな震えは、瞳を開けば気付く涙。顔を離して訊く。なんで泣いているの。
「やっと、ここまで来たんだなって。シュン君が倒れちゃった時は、はじめ諦めていたんだ。こんなこと言ったらシュン君に悪いけど、もう駄目なのかなって。それでも、最期までちゃんと見届けようって。そんな諦めの境地だったの。でもね、志桜里ちゃんに殴られた時、あんたが本当にシュンを好きなんだったら、しっかりと受け止めなさいよって言われて気付いたの。シュン君が絶望したときはわたしが支えなくちゃって。わたしがシュン君の手を引かないとって。だから」
こうしてシュン君と結婚できる日が来るなんて、本当に奇跡なんだなって。
「うん。今度は、僕がミツキを支えるよ。ミツキが絶望した時には、僕がその矢面に立ち、僕がミツキを守る。絶対」
「もう、何回も守ってもらっているよ。うん、シュン君。結婚しよう。大好き。これからもずっとずっと」
再び抱き寄せてキスをする。ミツキ一生大事に、大切にするから。
☆★☆
父さん、母さん、姉さん、話があります。
「ミツキと結婚させてください。まだ年齢は若いし、社会人になればきっと分からないことだらけだと思うけど、お互い支え合って生きていくって決めたから」
父さんも母さんも、姉さんも何も言わなかった。ただ、頷いて、話を聞くだけ。真剣な眼差しの母さんは、立ち上がって、居間の窓から外を眺める。雪は止んだみたいね、と。午後の日差しが照り付ける庭の桜と梅は雪化粧が施されて、融《と》けた雪がオパールの輝きのように光る。正座した僕とミツキは互いに手を床に着いて、頭を下げた。
「春夜、ミツキちゃんは良い子よ。でもね、結婚は楽しいことばかりじゃないの。時に辛いことや悲しいことを経験して、成長していくものなのよ。だからゴールインだなんて、思わないこと」
振り返った母さんの頬には一筋の涙が。その理由は、きっとミツキと同じ。僕が無事にこうして生きて、結婚なんて言葉を口にする日が来たことが嬉しいのだと思う。だって、ミツキちゃんありがとう、と呟いたから。
「ミツキちゃんがいたから、春夜はがんばれた。あなたのお陰。むしろ、春夜をこれからもよろしくお願いします。あなたなら、なにも心配いらないわ」
母さんの言葉に、はい、と裏返った声で返事をしたミツキは口を堅く結びながら笑っていた。姉さんが立ち上がり、はい、話は終わり、とミツキの頭を撫でて、お茶を入れ始める。
「良かった。シュン君みたいに意地悪されるのかと思った」
ミツキはそう言って、お茶を啜《すす》る。明らかに我が家族に慣れ切ったミツキは、少しいたずら心を見せるようになっていた。その言葉に反応した姉さんが凄む。シュン、あんたミツキちゃんに何したの、と。延々と姉さんと母さんに説教されながら飲んだお茶は少し渋かった。
★★★
翌日の早朝、急に鳴り響くスマホの着信に驚き跳び起きた。隣に寝ていたミツキもその着信の画面にくぎ付けになる。病院からの着信。きっと志桜里《しおり》だ。志桜里になにかあったんだ。
————鳥山《とりやま》さんが急変しました。急いで来てください。
急いで準備をして向かう病院は、まだ薄闇の中、月が煌々と照らすバイパスを走り抜けて二〇分。姉さんの運転する車で向かう車内は、僕とミツキ、それに母さんが無言で空気を重くしていた。
志桜里との思い出がメリーゴーランドのように回る脳内で、彼女はいつも僕に笑顔をくれた。ポカリを一緒に飲んだダンススタジオ。二人走った渋谷道玄坂。幾度となく僕を励ましてくれた志桜里。病室から眺めたテレビの中の志桜里は不愛想だったけど、その収録のあとに訪れた彼女は微笑んでいた。僕の前では、いつも笑顔。そして、僕にくれた優しさ。
なんで、なんでこうなっちゃうんだ。
「シュン君……」
力を入れすぎて白くなった僕の拳を両手で包み込むミツキは、なにも言わなかったけど、眉間に寄せた皺からして感情を抑えているよう。はち切れんばかりの感情を抑えて、僕もゆっくりと息を吐く。その熱さで、気道が焦げるような想い。
病院に着いて、急いで向かった集中治療室の前で医者に言われる二度目の言葉。会ってあげてください。
————恐らく今夜を越えることはできません。
扉を開けてベッドに横たわる志桜里に駆けつける。モニターや点滴、それに酸素マスクをつけた志桜里は静かに寝息を立てていて、瞳を開けることはなかった。その手を握り、思わず叫んでしまった。彼女の名前を。何度も。その手を強く握って。
「志桜里ちゃん、わたし、わだし、まだ伝えていないこと、いっぱいあるのに。どうして、どうしてこんなに早く」
「待ってよ、志桜里。話したいんだ、目を開けろよ」
シュン……ミツキ……。
微かに開いた瞳が僕と、その隣のミツキを見る。弱々しい視線が泳ぐ僕とミツキの顔は、泪《なみだ》と洟《はな》でぐちゃぐちゃに。それを見て、僅かに笑った志桜里がなんとか声を振り絞る。
ミツキ……シュンをお願い。
シュン……ミツキをお願い。
「志桜里、良く聞いて。僕は志桜里と一緒に歩んだ十数年、とても楽しかった。志桜里がいたからこそ、今の僕がいるんだ。だから、だ……から……ありがとう。僕の命を拾ってくれたのは志桜里だよ」
泣かないの……男で……しょ……シュン。
————志桜里ありがとう。
本当……楽しかった。ありがとう。
文字通り、息を引き取った。余命一九年の短い彼女の命は、儚く、それでいて美しく。彼女の名前通り、桜のように。笑顔のまま。
————さようなら、志桜里。また会おう、ね。
これが、僕の————君に告げる言葉。
☆☆☆
通夜式と葬儀は近親者のみで、と言ったが、実際は倉美月家《くらみつきけ》とミツキだけの簡単なものだった。でも、志桜里の好きな苺をいっぱいお供えして、彼女との思い出の写真をいっぱい飾ってあげて。僕とミツキ、そして志桜里で撮ったクリスマスの写真は大きく引き伸ばして。こんな笑顔の志桜里は見たことない、と姉さんも言っていた。なかなか笑わない氷の女王は、湿っぽい雪解けのように最後は笑顔で。
三月《みつき》の雪のように。
車に乗っていくの、と訊《き》いたミツキの言葉にかぶりを振って、僕はバスでいきたいと申し出る。訝しむミツキの額にキスをして、いいからいいから、と告げる朝八時。霞《かすみ》がかった空の色は水色に溶け出した群青色《ぐんじょういろ》。しかし、西の山に掛かる不気味な雲が、季節外れの雪を降らすと聞く。でも、今は囲炉裏《いろり》のような仄《ほの》かに感じる優しい陽気。桜の薫り短し命育むこの季節、この時に、僕は君に告げる。
もはや変装などいらないミツキは、裾の広がった辛子色の膝丈スカートに藍色のスプリングニット、それにデニムのライダースを着て、なんだかお姉さんになったな、と見惚れてしまった。
「シュン君、行こう。それでどこにいくの?」
「うん、すぐそこだよ。ミツキもよく知っているところ」
そうなんだ、と言って待つバス停のベンチは朝露《あさつゆ》で濡れていた。座らずに立ちながらバスを待っていると、ミツキは言う。ねえ、お花見に行きたいね。少し胸がちくり。
ようやくやってきたバスに乗り込んで、二人掛けの席に座ると僕の手を握るミツキは窓の外に視線をやって、桜が随分咲いたね、なんて。巡る季節に僕の手を引いてくれた君に、捧ぐ言葉はもう何度も僕の脳内を巡って、言葉を練り上げた喉奥の燃ゆる魂が、今かとその時を待っている。
ここで降りるよ、と言ってミツキに自分の腕を掴むように差し出すと、ありがとう、と絡みつけてきた腕がなんとなく震えていた——気がした。まさか、寒いのミツキ。
「ねえ、シュン君……ここって、衛星アンテナのあの公園だよね?」
「うん。お花見したいでしょ」
「……うん。でも、珍しいね。こんな朝から」
「今日は、雪の予報なんだよ。だから、晴れているうちに、ね」
春という慶福《けいふく》を全身で受け止めながら進む公園は、桜の香る幻想的な季節。家族連れやカップルがそれぞれの愛を囁《ささや》き、微笑み合う温かい空間は、まさに桜一色。華やぐ春色の花弁が地面まで彩り、空の青さと相成って、ポラロイドのような濃淡《のうたん》で描かれている。
公園の奥まで歩くと、目当ての場所にたどり着く。ミツキの呼吸が微かに変わる。僅かに荒くなった息遣いに、大丈夫だよ、落ち着いて。気付いているのかもしれない。
いや、僕の精神のほうが尋常じゃないのだけれども。手汗が滲《にじ》む感覚と、つま先から駆け上る血流が心臓を過ぎた辺りで沸点に達する僕の身体は、まるで煮えたぎる溶岩のよう。固まって動かなくなる四肢の関節が、ギスギスと音を立てる。ああ、こんな気持ちだったのかな。ミツキが僕に想いを伝えた時は。
「ミツキ。君がここで僕に想いを伝えた日のことは、今でも鮮明に覚えているよ」
「……シュン君」
「でも、恋人も今日で終わり」
「え————どういうこと?」
やはり意地悪したくなってしまう。ミツキの困り顔が見たくて。それに、何回も無いのだから。こうやって想いを真面目に伝えることなんて。
「だから、恋人は今日まで。ミツキ、色々とあったけど、本当に楽しかった。毎日、ミツキの顔を見るのが楽しくて、すこし切なくて」
「なんで……そういうこと言うの……本気で言っているの?」
「本気だよ。本気だからここに来たんだよ。ミツキ。昨日までの関係にさようならしよう」
「————ひどい」
泣きそうな顔のミツキを見て、少しやりすぎたかな、と、いつも反省してしまう。でも、この後に見せる表情が忘れられないくらいに好き。雪原から顔を出す水仙《スイセン》のような笑顔。だけど、春のように芽吹く僕の感情は、もうこれ以上抑えきれない。
「誕生日おめでとうミツキ。僕と結婚しよう。今日からは、恋人以上夫婦未満の関係。ね」
ジャケットの内ポケットから取り出したリングケースには、ダイヤの指輪。そっと取り出して、ミツキの左手の薬指に恐る恐る嵌《は》める。桜色のネイルが彩る長く美しい指に煌めく、朝露《あさつゆ》に反射して輝く光のようなダイヤモンドのハレーションに息を呑んだ。
「シュン君……」
今にも泣きそうな顔から、笑顔を咲かせるはずのミツキの瞳から落ちる雫。まさか。
本当に泣いてしまった。あれ、予想外の展開。ぼろぼろと流す涙は、まるで別れを告げられた恋人そのもの。しゃくりあげる泣き顔のミツキは、指輪に視線を落として、そのまま赤い瞳のままで、向日葵のような明るい笑顔など見せる気配はない。なんで、なんで泣き止まないの。お別れなんてしないから、泣き止んでよ。でも、ダイヤモンドに零れて砕ける涙の雫がミルククラウンのよう。その輝きが僕の心を打った。ミツキ、本当に愛している。
降りしきる桜の花びらが光に透ける様相はまるで雪。時間が止まった僕とミツキの周りに香《かぐわ》しき風が吹いて、頬を撫でるその花びらがくすぐったい。同時に鼻の上に感じる冷たい水滴。空を仰げば舞い散る雪の結晶。そうか、もう雪が。
手のひらを空に向ける。その冷たい感触に混じる、桜の花びらがひらひらと手のひらに舞い降りる。
花びらと雪の幻想的な光景に、ミツキも顔を上げて呟く。綺麗。
————三月《みつき》の雪が湿っぽいことに気付いた。
ようやく泣き止んだミツキを優しく抱きしめる。そして耳元で囁く言葉。君に告げる言葉。
好きだよミツキ。出会ったころよりもずっとずっと。
愛している。今までも。これからもずっとずっと。
★☆☆
しばらく沈黙した時間、僕たちは無言で抱き合った。舞い降りる雪と舞い散る桜の花びらが幻想的な時間を演出して、まるで奇跡の上に成り立つ舞台。そう、奇跡の上に僕たちは成り立つ。
巡り合わせ。出会いと命。時間と境遇。その一つ一つが僕たちを互いに引き合わせている。三月に咲く桜。暖かい日に降り積もる雪。そして、君の誕生日。
「ミツキ。それでどうなの。結婚してくれるの?」
「————どうしようかな」
「え。まさかここで断られるとか、もう死刑宣告なんだけど」
「だって、シュン君がいつも意地悪するんだもん。だから、焦らしちゃう」
「ええ。だって。ミツキの困り顔が見たいから」
「ほらぁ。そうやって。もう。じゃあ、キスして。今までで一番気持ちを込めて」
うん、と言って瞳を閉じる。抱きしめるその華奢《きゃしゃ》な身体を優しく引き寄せて、重ねた唇から感じるミツキの僅かな震えは、瞳を開けば気付く涙。顔を離して訊く。なんで泣いているの。
「やっと、ここまで来たんだなって。シュン君が倒れちゃった時は、はじめ諦めていたんだ。こんなこと言ったらシュン君に悪いけど、もう駄目なのかなって。それでも、最期までちゃんと見届けようって。そんな諦めの境地だったの。でもね、志桜里ちゃんに殴られた時、あんたが本当にシュンを好きなんだったら、しっかりと受け止めなさいよって言われて気付いたの。シュン君が絶望したときはわたしが支えなくちゃって。わたしがシュン君の手を引かないとって。だから」
こうしてシュン君と結婚できる日が来るなんて、本当に奇跡なんだなって。
「うん。今度は、僕がミツキを支えるよ。ミツキが絶望した時には、僕がその矢面に立ち、僕がミツキを守る。絶対」
「もう、何回も守ってもらっているよ。うん、シュン君。結婚しよう。大好き。これからもずっとずっと」
再び抱き寄せてキスをする。ミツキ一生大事に、大切にするから。
☆★☆
父さん、母さん、姉さん、話があります。
「ミツキと結婚させてください。まだ年齢は若いし、社会人になればきっと分からないことだらけだと思うけど、お互い支え合って生きていくって決めたから」
父さんも母さんも、姉さんも何も言わなかった。ただ、頷いて、話を聞くだけ。真剣な眼差しの母さんは、立ち上がって、居間の窓から外を眺める。雪は止んだみたいね、と。午後の日差しが照り付ける庭の桜と梅は雪化粧が施されて、融《と》けた雪がオパールの輝きのように光る。正座した僕とミツキは互いに手を床に着いて、頭を下げた。
「春夜、ミツキちゃんは良い子よ。でもね、結婚は楽しいことばかりじゃないの。時に辛いことや悲しいことを経験して、成長していくものなのよ。だからゴールインだなんて、思わないこと」
振り返った母さんの頬には一筋の涙が。その理由は、きっとミツキと同じ。僕が無事にこうして生きて、結婚なんて言葉を口にする日が来たことが嬉しいのだと思う。だって、ミツキちゃんありがとう、と呟いたから。
「ミツキちゃんがいたから、春夜はがんばれた。あなたのお陰。むしろ、春夜をこれからもよろしくお願いします。あなたなら、なにも心配いらないわ」
母さんの言葉に、はい、と裏返った声で返事をしたミツキは口を堅く結びながら笑っていた。姉さんが立ち上がり、はい、話は終わり、とミツキの頭を撫でて、お茶を入れ始める。
「良かった。シュン君みたいに意地悪されるのかと思った」
ミツキはそう言って、お茶を啜《すす》る。明らかに我が家族に慣れ切ったミツキは、少しいたずら心を見せるようになっていた。その言葉に反応した姉さんが凄む。シュン、あんたミツキちゃんに何したの、と。延々と姉さんと母さんに説教されながら飲んだお茶は少し渋かった。
★★★
翌日の早朝、急に鳴り響くスマホの着信に驚き跳び起きた。隣に寝ていたミツキもその着信の画面にくぎ付けになる。病院からの着信。きっと志桜里《しおり》だ。志桜里になにかあったんだ。
————鳥山《とりやま》さんが急変しました。急いで来てください。
急いで準備をして向かう病院は、まだ薄闇の中、月が煌々と照らすバイパスを走り抜けて二〇分。姉さんの運転する車で向かう車内は、僕とミツキ、それに母さんが無言で空気を重くしていた。
志桜里との思い出がメリーゴーランドのように回る脳内で、彼女はいつも僕に笑顔をくれた。ポカリを一緒に飲んだダンススタジオ。二人走った渋谷道玄坂。幾度となく僕を励ましてくれた志桜里。病室から眺めたテレビの中の志桜里は不愛想だったけど、その収録のあとに訪れた彼女は微笑んでいた。僕の前では、いつも笑顔。そして、僕にくれた優しさ。
なんで、なんでこうなっちゃうんだ。
「シュン君……」
力を入れすぎて白くなった僕の拳を両手で包み込むミツキは、なにも言わなかったけど、眉間に寄せた皺からして感情を抑えているよう。はち切れんばかりの感情を抑えて、僕もゆっくりと息を吐く。その熱さで、気道が焦げるような想い。
病院に着いて、急いで向かった集中治療室の前で医者に言われる二度目の言葉。会ってあげてください。
————恐らく今夜を越えることはできません。
扉を開けてベッドに横たわる志桜里に駆けつける。モニターや点滴、それに酸素マスクをつけた志桜里は静かに寝息を立てていて、瞳を開けることはなかった。その手を握り、思わず叫んでしまった。彼女の名前を。何度も。その手を強く握って。
「志桜里ちゃん、わたし、わだし、まだ伝えていないこと、いっぱいあるのに。どうして、どうしてこんなに早く」
「待ってよ、志桜里。話したいんだ、目を開けろよ」
シュン……ミツキ……。
微かに開いた瞳が僕と、その隣のミツキを見る。弱々しい視線が泳ぐ僕とミツキの顔は、泪《なみだ》と洟《はな》でぐちゃぐちゃに。それを見て、僅かに笑った志桜里がなんとか声を振り絞る。
ミツキ……シュンをお願い。
シュン……ミツキをお願い。
「志桜里、良く聞いて。僕は志桜里と一緒に歩んだ十数年、とても楽しかった。志桜里がいたからこそ、今の僕がいるんだ。だから、だ……から……ありがとう。僕の命を拾ってくれたのは志桜里だよ」
泣かないの……男で……しょ……シュン。
————志桜里ありがとう。
本当……楽しかった。ありがとう。
文字通り、息を引き取った。余命一九年の短い彼女の命は、儚く、それでいて美しく。彼女の名前通り、桜のように。笑顔のまま。
————さようなら、志桜里。また会おう、ね。
これが、僕の————君に告げる言葉。
☆☆☆
通夜式と葬儀は近親者のみで、と言ったが、実際は倉美月家《くらみつきけ》とミツキだけの簡単なものだった。でも、志桜里の好きな苺をいっぱいお供えして、彼女との思い出の写真をいっぱい飾ってあげて。僕とミツキ、そして志桜里で撮ったクリスマスの写真は大きく引き伸ばして。こんな笑顔の志桜里は見たことない、と姉さんも言っていた。なかなか笑わない氷の女王は、湿っぽい雪解けのように最後は笑顔で。
三月《みつき》の雪のように。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

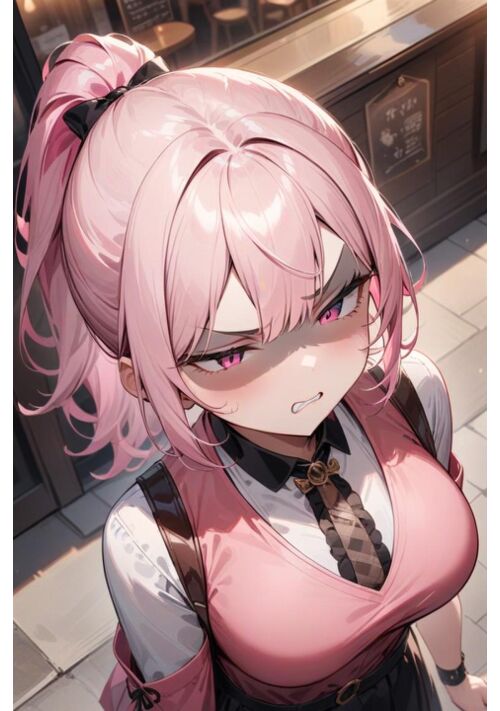
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















