76 / 119
僕ではない誰かへの言葉
3
しおりを挟む
僕は氷雨と、ふたりきり。
何も言わずに並んで、川面の煌めきを眺めていた。
「何話すんでしょうね」
遠くを見る時の声で言う氷雨は、対岸の人影を眺めていた。
僕は目を細める。
「さあ、僕らにはわからないことさ」
いくら目つきを悪くしても、彼らにピントが合うことはない。
若と芽衣花や、対岸の彼らもそう。人生が他人と交わりきることはない。
だから僕は、最初に立てた予想と真逆の選択を取るようにしている。
氷雨の言おうとしていることだって、同じことだ。
「君の伝えたいことって?」
「じゃあ、ここで問題」
ジャジャーンと優しい口調で言って、氷雨が目を閉じる。
「アタシが伝えたいことがある相手って、よぎセンでしょーか」
「一応聞くけど、ヒントは?」
「ないっス」
「だよな」
僕はフッと笑う。無理にそうしたから、吐いた息は自嘲げに聞こえる。
「違う。僕じゃない」
答えは、もうわかっていた。
氷雨はゆっくりと目を開けると、イジワルな顔で笑いかけてくる。
「せーかいです」
その言葉を聞いて、落胆がなかったといえば嘘になる。
けれど僕の心は、不思議なほどに凪いでいた。
氷雨は僕の額に人差し指を当てて、柔らかく微笑む。
「でも、半分不正解です」
「答えは一つじゃないのか」
「そりゃそっスよ。最終的に答えが一つになるのは、ガッコーの数学だけで通じるおままごとです」
氷雨の指先が、額からゆったりと流れ落ちてくる。
「ちゃんとあるっスよ。よぎセンにも、伝えたいこと」
やがて彼女の指先が鼻で止まると、ときおり見せる少年みたいな笑顔で笑いかけてきた。
「でも、それは一番最後っス」
アタシ、デザートは最後に取っとくタイプなんで。
止まった指先が、鼻先をツンと弾く。
微かに僕は仰け反って、それから形のいい鼻をつまみ返す。
氷雨は大げさに手を振って降参して見せた。
「何やってんの、アンタら。もう」
そこに若と芽衣花が戻ってくる。
晴れた空のように笑う芽衣花の後ろには、顔を背けた若がいて。二人から漂う春みたいに透き通った青臭さに、僕らは自然と笑顔になる。
持っていた飴をあげて「おめでとう」と言ったり、強がる若に冷やかしを入れて、些細な小突き合いに発展したり。
最終的には、川辺の水切りで判定を決めた。
そこで僕は、人生で初めて若に勝利した。
絵に描いたような、取り留めもない日常があった。青春なんてものが現実に存在するのなら、今がそうだと言ってもいい。
「よぎセン、アタシね。今まで生きてきた中で、今が一番フツーで──いっちばん楽しいです」
そう言った彼女に、僕は上手く笑えていただろうか?
ひりついた喉と痛むほどに痙攣する口角を、川辺の風が隠してくれる。
すぐにでも抱き締めてしまいたい。そんなことを思ったのは、氷雨が初めてだった。
「氷雨」
僕は改めて、その綺麗な名前を呼ぶ。
これから伝える言葉が不純であることは、とっくに理解していた。
「僕は君に寄り添っていたいと思うんだ。だから、聞いてほしい」
恥ずかしくて、みっともない告白の言葉だった。
けれどその告白は「愛してる」を伝える前に、消えてしまった。
氷雨の人差し指が、僕の唇に添えられる。
「ダメっスよ、よぎセン。そこから先は、言わせないっス」
代わりに、頬に小さなキスが触れた。
この瞬間だけは、愛結晶のことを完全に忘れていられた。自分が怪物であることも、この病を僕以外の人間が保有している可能性も。
ただ、屈託なく笑う氷雨の顔がひたすら瞼の裏に焼き付いていた。
それが二〇一四年の七月二十日までに、僕らが経験した夏の出来事だ。
七月の終わりには終業式があって、夏休みが始まった。
八月一日までは大雨が続いて、僕らは久しぶりに一人の夜を過ごした。
その間、氷雨からは何の連絡もなかった。
氷雨が言葉を伝えられないのは、きっと最初から分かっていた。けれど僕は、それでいいと思っていた。
伝えるために勇気が必要な言葉なら、僕の前くらいでは臆病でいい。いつか恐怖や悲しみに波のような隙間が出来たなら、その時にでも伝えてくれればいい。
誰かに伝えた言葉が、せめて一つでも氷雨自身の幸福に繋がることを、僕は祈っていた。
氷雨茉宵の全裸写真が拡散されたのは、八月六日のことだ。
何も言わずに並んで、川面の煌めきを眺めていた。
「何話すんでしょうね」
遠くを見る時の声で言う氷雨は、対岸の人影を眺めていた。
僕は目を細める。
「さあ、僕らにはわからないことさ」
いくら目つきを悪くしても、彼らにピントが合うことはない。
若と芽衣花や、対岸の彼らもそう。人生が他人と交わりきることはない。
だから僕は、最初に立てた予想と真逆の選択を取るようにしている。
氷雨の言おうとしていることだって、同じことだ。
「君の伝えたいことって?」
「じゃあ、ここで問題」
ジャジャーンと優しい口調で言って、氷雨が目を閉じる。
「アタシが伝えたいことがある相手って、よぎセンでしょーか」
「一応聞くけど、ヒントは?」
「ないっス」
「だよな」
僕はフッと笑う。無理にそうしたから、吐いた息は自嘲げに聞こえる。
「違う。僕じゃない」
答えは、もうわかっていた。
氷雨はゆっくりと目を開けると、イジワルな顔で笑いかけてくる。
「せーかいです」
その言葉を聞いて、落胆がなかったといえば嘘になる。
けれど僕の心は、不思議なほどに凪いでいた。
氷雨は僕の額に人差し指を当てて、柔らかく微笑む。
「でも、半分不正解です」
「答えは一つじゃないのか」
「そりゃそっスよ。最終的に答えが一つになるのは、ガッコーの数学だけで通じるおままごとです」
氷雨の指先が、額からゆったりと流れ落ちてくる。
「ちゃんとあるっスよ。よぎセンにも、伝えたいこと」
やがて彼女の指先が鼻で止まると、ときおり見せる少年みたいな笑顔で笑いかけてきた。
「でも、それは一番最後っス」
アタシ、デザートは最後に取っとくタイプなんで。
止まった指先が、鼻先をツンと弾く。
微かに僕は仰け反って、それから形のいい鼻をつまみ返す。
氷雨は大げさに手を振って降参して見せた。
「何やってんの、アンタら。もう」
そこに若と芽衣花が戻ってくる。
晴れた空のように笑う芽衣花の後ろには、顔を背けた若がいて。二人から漂う春みたいに透き通った青臭さに、僕らは自然と笑顔になる。
持っていた飴をあげて「おめでとう」と言ったり、強がる若に冷やかしを入れて、些細な小突き合いに発展したり。
最終的には、川辺の水切りで判定を決めた。
そこで僕は、人生で初めて若に勝利した。
絵に描いたような、取り留めもない日常があった。青春なんてものが現実に存在するのなら、今がそうだと言ってもいい。
「よぎセン、アタシね。今まで生きてきた中で、今が一番フツーで──いっちばん楽しいです」
そう言った彼女に、僕は上手く笑えていただろうか?
ひりついた喉と痛むほどに痙攣する口角を、川辺の風が隠してくれる。
すぐにでも抱き締めてしまいたい。そんなことを思ったのは、氷雨が初めてだった。
「氷雨」
僕は改めて、その綺麗な名前を呼ぶ。
これから伝える言葉が不純であることは、とっくに理解していた。
「僕は君に寄り添っていたいと思うんだ。だから、聞いてほしい」
恥ずかしくて、みっともない告白の言葉だった。
けれどその告白は「愛してる」を伝える前に、消えてしまった。
氷雨の人差し指が、僕の唇に添えられる。
「ダメっスよ、よぎセン。そこから先は、言わせないっス」
代わりに、頬に小さなキスが触れた。
この瞬間だけは、愛結晶のことを完全に忘れていられた。自分が怪物であることも、この病を僕以外の人間が保有している可能性も。
ただ、屈託なく笑う氷雨の顔がひたすら瞼の裏に焼き付いていた。
それが二〇一四年の七月二十日までに、僕らが経験した夏の出来事だ。
七月の終わりには終業式があって、夏休みが始まった。
八月一日までは大雨が続いて、僕らは久しぶりに一人の夜を過ごした。
その間、氷雨からは何の連絡もなかった。
氷雨が言葉を伝えられないのは、きっと最初から分かっていた。けれど僕は、それでいいと思っていた。
伝えるために勇気が必要な言葉なら、僕の前くらいでは臆病でいい。いつか恐怖や悲しみに波のような隙間が出来たなら、その時にでも伝えてくれればいい。
誰かに伝えた言葉が、せめて一つでも氷雨自身の幸福に繋がることを、僕は祈っていた。
氷雨茉宵の全裸写真が拡散されたのは、八月六日のことだ。
2
あなたにおすすめの小説

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。

スルドの声(嚶鳴2) terceira homenagem
桜のはなびら
現代文学
何かを諦めて。
代わりに得たもの。
色部誉にとってそれは、『サンバ』という音楽で使用する打楽器、『スルド』だった。
大学進学を機に入ったサンバチーム『ソール・エ・エストレーラ』で、入会早々に大きな企画を成功させた誉。
かつて、心血を注ぎ、寝食を忘れて取り組んでいたバレエの世界では、一度たりとも届くことのなかった栄光。
どれだけの人に支えられていても。
コンクールの舞台上ではひとり。
ひとりで戦い、他者を押し退け、限られた席に座る。
そのような世界には適性のなかった誉は、サンバの世界で知ることになる。
誉は多くの人に支えられていることを。
多くの人が、誉のやろうとしている企画を助けに来てくれた。
成功を収めた企画の発起人という栄誉を手に入れた誉。
誉の周りには、新たに人が集まってくる。
それは、誉の世界を広げるはずだ。
広がる世界が、良いか悪いかはともかくとして。

元おっさんの幼馴染育成計画
みずがめ
恋愛
独身貴族のおっさんが逆行転生してしまった。結婚願望がなかったわけじゃない、むしろ強く思っていた。今度こそ人並みのささやかな夢を叶えるために彼女を作るのだ。
だけど結婚どころか彼女すらできたことのないような日陰ものの自分にそんなことができるのだろうか? 軟派なことをできる自信がない。ならば幼馴染の女の子を作ってそのままゴールインすればいい。という考えのもと始まる元おっさんの幼馴染育成計画。
※この作品は小説家になろうにも掲載しています。
※【挿絵あり】の話にはいただいたイラストを載せています。表紙はチャーコさんが依頼して、まるぶち銀河さんに描いていただきました。

はじまりの朝
さくら乃
BL
子どもの頃は仲が良かった幼なじみ。
ある出来事をきっかけに離れてしまう。
中学は別の学校へ、そして、高校で再会するが、あの頃の彼とはいろいろ違いすぎて……。
これから始まる恋物語の、それは、“はじまりの朝”。
✳『番外編〜はじまりの裏側で』
『はじまりの朝』はナナ目線。しかし、その裏側では他キャラもいろいろ思っているはず。そんな彼ら目線のエピソード。

結婚相手は、初恋相手~一途な恋の手ほどき~
馬村 はくあ
ライト文芸
「久しぶりだね、ちとせちゃん」
入社した会社の社長に
息子と結婚するように言われて
「ま、なぶくん……」
指示された家で出迎えてくれたのは
ずっとずっと好きだった初恋相手だった。
◌⑅◌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◌⑅◌
ちょっぴり照れ屋な新人保険師
鈴野 ちとせ -Chitose Suzuno-
×
俺様なイケメン副社長
遊佐 学 -Manabu Yusa-
◌⑅◌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◌⑅◌
「これからよろくね、ちとせ」
ずっと人生を諦めてたちとせにとって
これは好きな人と幸せになれる
大大大チャンス到来!
「結婚したい人ができたら、いつでも離婚してあげるから」
この先には幸せな未来しかないと思っていたのに。
「感謝してるよ、ちとせのおかげで俺の将来も安泰だ」
自分の立場しか考えてなくて
いつだってそこに愛はないんだと
覚悟して臨んだ結婚生活
「お前の頭にあいつがいるのが、ムカつく」
「あいつと仲良くするのはやめろ」
「違わねぇんだよ。俺のことだけ見てろよ」
好きじゃないって言うくせに
いつだって、強引で、惑わせてくる。
「かわいい、ちとせ」
溺れる日はすぐそこかもしれない
◌⑅◌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◌⑅◌
俺様なイケメン副社長と
そんな彼がずっとすきなウブな女の子
愛が本物になる日は……

27歳女子が婚活してみたけど何か質問ある?
藍沢咲良
恋愛
一色唯(Ishiki Yui )、最近ちょっと苛々しがちの27歳。
結婚適齢期だなんて言葉、誰が作った?彼氏がいなきゃ寂しい女確定なの?
もう、みんな、うるさい!
私は私。好きに生きさせてよね。
この世のしがらみというものは、20代後半女子であっても放っておいてはくれないものだ。
彼氏なんていなくても。結婚なんてしてなくても。楽しければいいじゃない。仕事が楽しくて趣味も充実してればそれで私の人生は満足だった。
私の人生に彩りをくれる、その人。
その人に、私はどうやら巡り合わないといけないらしい。
⭐︎素敵な表紙は仲良しの漫画家さんに描いて頂きました。著作権保護の為、無断転載はご遠慮ください。
⭐︎この作品はエブリスタでも投稿しています。
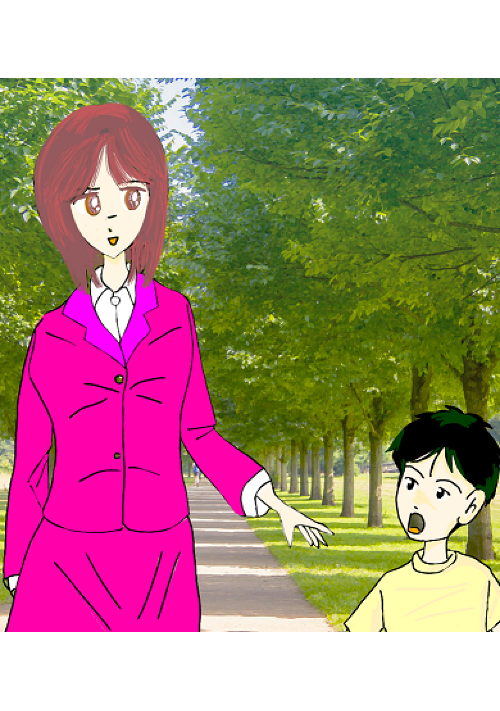
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

【完結】イケメンが邪魔して本命に告白できません
竹柏凪紗
青春
高校の入学式、芸能コースに通うアイドルでイケメンの如月風磨が普通科で目立たない最上碧衣の教室にやってきた。女子たちがキャーキャー騒ぐなか、風磨は碧衣の肩を抱き寄せ「お前、今日から俺の女な」と宣言する。その真意とウソつきたちによって複雑になっていく2人の結末とは──
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















