12 / 122
第一章
11
しおりを挟む
「ちょっと、あんたっ!」
誰かが誰かを呼び止めている、それにしても、何と品のない事でしょう。
「ちょっと、何無視しているのよっ!」
ガシリと腕を掴まれ、私は硬直する。
「えっ?」
「えっ、じゃないわよ、どういう事よ。」
「……。」
私は彼女を見て冷めた目で見る。
「……。」
「何とか言いなさいよ、この悪役令嬢の癖に。」
「……。」
確実に突き刺さる視線に私の腕を掴む彼女は分かっていないのか、私を睨めつけている。
私は口元に手を当て、嘆息する。
「何よ、言いたい事があるならはっきりと言いなさいよ。」
「貴女分かっておりませんの?」
「はぁ?」
「わたくしの身分と貴女との身分の違いに。」
「ここは学校で平等だって言っているのに、何を言っているのよ。」
まるで私の方が間違っているというように鼻で笑っている彼女に私は痛み出す頭を押さえたかった。
確かにこの学校は平等だと掲げている。
しかし、相応の常識や品を守らなくてもいいとは言ってはいない。
なのに、この少女は何を穿き間違っているのか、そんな事をのたまっている。
「非常識。」
ポツリと私の吐き出した言葉に彼女はそれを拾い上げる。
「貴女の方がよっぽど非常識じゃないっ!」
「……。」
私はどうすればいいのかと頭を悩ませる。
きっと彼女に貴族としてのルールを教えてもきっと納得はしてくれない、でも、説明しなければいけないだろう。
「わたくしのどこが非常識というのでしょうか?」
「わたしが呼びかけているのに何で無視するんですか、人としてあり得ないでしょう。」
「……貴女ごときの身分に何故わたくしが堪えなければなりませんの?」
「はぁ?身分出すなんてずるいですね~。」
「……。」
私は思わず嘆息する。
「何ですか?」
苛立ちを隠そうとしない彼女に私は意を決する。
「身分は大切ですわよ。」
「ここは学校よ。」
「ええ、確かにここは学校です、ですが、小さな社交場ですわ。」
「何ですかそれ。」
「わたくしたちはいずれ社交場にでますわよね。」
「決まっているじゃない。」
胸を張る彼女にこのままで彼女は大丈夫なのかと、私は不安になる。
「でしたら、貴族でも爵位というものがあるのはご存知ですよね。」
「馬鹿にしないでよね。」
「……。」
ギロリと睨む彼女に私は苦笑する。
「貴女の家の爵位は?」
「男爵よ。」
「そうですよね。それでしたら、わたくし家はご存知かしら?」
「確か、公爵でしょ。」
「……。」
何故ここまで知っているのに、そのような態度でいられるのか不思議です、周りなんて青を通り過ぎて白色の顔色になっている人が続出しているのに。
「でしたら分かりません?」
「何がよ。」
「わたくしの家の方が爵位が上なのですよ。」
「だったら何よ、親の爵位じゃない。」
「……。」
私は頭を恥もなく抱えたくなる。
「ええ、確かに親の爵位でもありますわよ。」
「だったら、何でわたしがあんたなんかにへりくだらなくちゃならないのよ。」
彼女の言葉に周りがざわめき、そして、私はとうとう溜息を吐いた。
「何なのよ。」
「分かっておりませんのね。」
「だから何なのよ。」
「わたくしはいいましたよね?ここは小さな社交場だと、わたくしは公爵令嬢ですのよ、そして、貴女は男爵令嬢。」
「だからそれが何なのよ。」
「それが、わたくしたちの今の身分。」
「……。」
「その身分相応の態度というものがあります、同じ公爵家の者でしたら失礼に当たらなくとも、それ以下の者だと無礼に当たるものがあります。」
私の目の端に彼の人の色が見えた。
「それを貴女は理解しておりませんのね。」
「意味わかんないんだけど。」
「……初等部からやり直したらいかがですか?」
もう私は投げやりになり、そんな事を呟いた、その時、周りの者たちは同意するように何度も頷いている。
「ひ、酷い…。」
まるで悲劇のヒロインのようにショックを受ける彼女は傍から見れば喜劇のヒロインにしか見えませんね。
ああ、とうとうあの方が一歩踏み出したわ。
誰かが誰かを呼び止めている、それにしても、何と品のない事でしょう。
「ちょっと、何無視しているのよっ!」
ガシリと腕を掴まれ、私は硬直する。
「えっ?」
「えっ、じゃないわよ、どういう事よ。」
「……。」
私は彼女を見て冷めた目で見る。
「……。」
「何とか言いなさいよ、この悪役令嬢の癖に。」
「……。」
確実に突き刺さる視線に私の腕を掴む彼女は分かっていないのか、私を睨めつけている。
私は口元に手を当て、嘆息する。
「何よ、言いたい事があるならはっきりと言いなさいよ。」
「貴女分かっておりませんの?」
「はぁ?」
「わたくしの身分と貴女との身分の違いに。」
「ここは学校で平等だって言っているのに、何を言っているのよ。」
まるで私の方が間違っているというように鼻で笑っている彼女に私は痛み出す頭を押さえたかった。
確かにこの学校は平等だと掲げている。
しかし、相応の常識や品を守らなくてもいいとは言ってはいない。
なのに、この少女は何を穿き間違っているのか、そんな事をのたまっている。
「非常識。」
ポツリと私の吐き出した言葉に彼女はそれを拾い上げる。
「貴女の方がよっぽど非常識じゃないっ!」
「……。」
私はどうすればいいのかと頭を悩ませる。
きっと彼女に貴族としてのルールを教えてもきっと納得はしてくれない、でも、説明しなければいけないだろう。
「わたくしのどこが非常識というのでしょうか?」
「わたしが呼びかけているのに何で無視するんですか、人としてあり得ないでしょう。」
「……貴女ごときの身分に何故わたくしが堪えなければなりませんの?」
「はぁ?身分出すなんてずるいですね~。」
「……。」
私は思わず嘆息する。
「何ですか?」
苛立ちを隠そうとしない彼女に私は意を決する。
「身分は大切ですわよ。」
「ここは学校よ。」
「ええ、確かにここは学校です、ですが、小さな社交場ですわ。」
「何ですかそれ。」
「わたくしたちはいずれ社交場にでますわよね。」
「決まっているじゃない。」
胸を張る彼女にこのままで彼女は大丈夫なのかと、私は不安になる。
「でしたら、貴族でも爵位というものがあるのはご存知ですよね。」
「馬鹿にしないでよね。」
「……。」
ギロリと睨む彼女に私は苦笑する。
「貴女の家の爵位は?」
「男爵よ。」
「そうですよね。それでしたら、わたくし家はご存知かしら?」
「確か、公爵でしょ。」
「……。」
何故ここまで知っているのに、そのような態度でいられるのか不思議です、周りなんて青を通り過ぎて白色の顔色になっている人が続出しているのに。
「でしたら分かりません?」
「何がよ。」
「わたくしの家の方が爵位が上なのですよ。」
「だったら何よ、親の爵位じゃない。」
「……。」
私は頭を恥もなく抱えたくなる。
「ええ、確かに親の爵位でもありますわよ。」
「だったら、何でわたしがあんたなんかにへりくだらなくちゃならないのよ。」
彼女の言葉に周りがざわめき、そして、私はとうとう溜息を吐いた。
「何なのよ。」
「分かっておりませんのね。」
「だから何なのよ。」
「わたくしはいいましたよね?ここは小さな社交場だと、わたくしは公爵令嬢ですのよ、そして、貴女は男爵令嬢。」
「だからそれが何なのよ。」
「それが、わたくしたちの今の身分。」
「……。」
「その身分相応の態度というものがあります、同じ公爵家の者でしたら失礼に当たらなくとも、それ以下の者だと無礼に当たるものがあります。」
私の目の端に彼の人の色が見えた。
「それを貴女は理解しておりませんのね。」
「意味わかんないんだけど。」
「……初等部からやり直したらいかがですか?」
もう私は投げやりになり、そんな事を呟いた、その時、周りの者たちは同意するように何度も頷いている。
「ひ、酷い…。」
まるで悲劇のヒロインのようにショックを受ける彼女は傍から見れば喜劇のヒロインにしか見えませんね。
ああ、とうとうあの方が一歩踏み出したわ。
10
あなたにおすすめの小説

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m
✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。
【あらすじ】
神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!
そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!
事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!
カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

世の中は意外と魔術で何とかなる
ものまねの実
ファンタジー
新しい人生が唐突に始まった男が一人。目覚めた場所は人のいない森の中の廃村。生きるのに精一杯で、大層な目標もない。しかしある日の出会いから物語は動き出す。
神様の土下座・謝罪もない、スキル特典もレベル制もない、転生トラックもそれほど走ってない。突然の転生に戸惑うも、前世での経験があるおかげで図太く生きられる。生きるのに『隠してたけど実は最強』も『パーティから追放されたから復讐する』とかの設定も必要ない。人はただ明日を目指して歩くだけで十分なんだ。
『王道とは歩むものではなく、その隣にある少しずれた道を歩くためのガイドにするくらいが丁度いい』
平凡な生き方をしているつもりが、結局騒ぎを起こしてしまう男の冒険譚。困ったときの魔術頼み!大丈夫、俺上手に魔術使えますから。※主人公は結構ズルをします。正々堂々がお好きな方はご注意ください。

白いもふもふ好きの僕が転生したらフェンリルになっていた!!
ろき
ファンタジー
ブラック企業で消耗する社畜・白瀬陸空(しらせりくう)の唯一の癒し。それは「白いもふもふ」だった。 ある日、白い子犬を助けて命を落とした彼は、異世界で目を覚ます。
ふと水面を覗き込むと、そこに映っていたのは―― 伝説の神獣【フェンリル】になった自分自身!?
「どうせ転生するなら、テイマーになって、もふもふパラダイスを作りたかった!」 「なんで俺自身がもふもふの神獣になってるんだよ!」
理想と真逆の姿に絶望する陸空。 だが、彼には規格外の魔力と、前世の異常なまでの「もふもふへの執着」が変化した、とある謎のスキルが備わっていた。
これは、最強の神獣になってしまった男が、ただひたすらに「もふもふ」を愛でようとした結果、周囲の人間(とくにエルフ)に崇拝され、勘違いが勘違いを呼んで国を動かしてしまう、予測不能な異世界もふもふライフ!
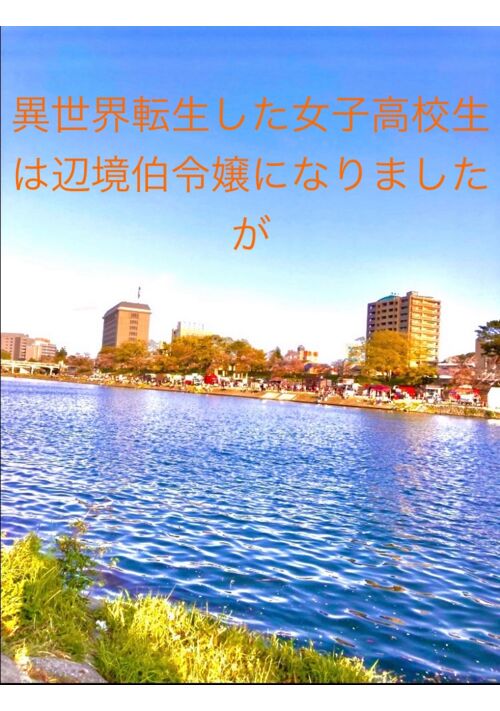
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

悪徳領主の息子に転生しました
アルト
ファンタジー
悪徳領主。その息子として現代っ子であった一人の青年が転生を果たす。
領民からは嫌われ、私腹を肥やす為にと過分過ぎる税を搾り取った結果、家の外に出た瞬間にその息子である『ナガレ』が領民にデカイ石を投げつけられ、意識不明の重体に。
そんな折に転生を果たすという不遇っぷり。
「ちょ、ま、死亡フラグ立ち過ぎだろおおおおお?!」
こんな状態ではいつ死ぬか分かったもんじゃない。
一刻も早い改善を……!と四苦八苦するも、転生前の人格からは末期過ぎる口調だけは受け継いでる始末。
これなんて無理ゲー??

転生したみたいなので異世界生活を楽しみます
さっちさん
ファンタジー
又々、題名変更しました。
内容がどんどんかけ離れていくので…
沢山のコメントありがとうございます。対応出来なくてすいません。
誤字脱字申し訳ございません。気がついたら直していきます。
感傷的表現は無しでお願いしたいと思います😢
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ありきたりな転生ものの予定です。
主人公は30代後半で病死した、天涯孤独の女性が幼女になって冒険する。
一応、転生特典でスキルは貰ったけど、大丈夫か。私。
まっ、なんとかなるっしょ。

まったく知らない世界に転生したようです
吉川 箱
ファンタジー
おっとりヲタク男子二十五歳成人。チート能力なし?
まったく知らない世界に転生したようです。
何のヒントもないこの世界で、破滅フラグや地雷を踏まずに生き残れるか?!
頼れるのは己のみ、みたいです……?
※BLですがBがLな話は出て来ません。全年齢です。
私自身は全年齢の主人公ハーレムものBLだと思って書いてるけど、全く健全なファンタジー小説だとも言い張れるように書いております。つまり健全なお嬢さんの癖を歪めて火のないところへ煙を感じてほしい。
111話までは毎日更新。
それ以降は毎週金曜日20時に更新します。
カクヨムの方が文字数が多く、更新も先です。

異世界転生旅日記〜生活魔法は無限大!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
農家の四男に転生したルイ。
そんなルイは、五歳の高熱を出した闘病中に、前世の記憶を思い出し、ステータスを見れることに気付き、自分の能力を自覚した。
農家の四男には未来はないと、家族に隠れて金策を開始する。
十歳の時に行われたスキル鑑定の儀で、スキル【生活魔法 Lv.∞】と【鑑定 Lv.3】を授かったが、親父に「家の役には立たない」と、家を追い出される。
家を追い出されるきっかけとなった【生活魔法】だが、転生あるある?の思わぬ展開を迎えることになる。
ルイの安寧の地を求めた旅が、今始まる!
見切り発車。不定期更新。
カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















