8 / 39
十五週目
しおりを挟む
ひとつきもかかった、というかひと月で始まったと言うべきか。
気がつけば、街がクリスマスになってしばらく経つ。
セールが今週で終わる、という基準からいうと明後日がクリスマスらしい。
だいたいこの時期の畑中純一は実家に帰ってしまうので、クリスマスという印象が街に出ると、帰省のチケットを準備するか、という感覚だったが、今年はそうもいかなかった。
そろそろふたつきになるが、裁判はジリジリと進んでいるのか進んでいないのか。あまり純一の生活には支障がなさそうだった。
結局、年内には純一は二度だけ裁判所に出かけて行って、身分照会を受けたあと、三時間ほどづつ日本語とも思えない言葉のやりとりを水本先生の隣で黙って聞いていただけだった。
水本先生に言わせるとそういうモノらしいのだが、さすがに年明けにはペースが上がるだろうという見通しも立ってきたらしい。
最初の数回は顔見せと資料の受け渡しみたいなモノらしい。勤め人的には、ソロソロ仕事なんかしている場合じゃないよ、という事実上の猶予期間であるということで、ソレまでに弁護士なりを決めるための作業期間であるという水本先生の解説だ。
実際のところ、水本先生は女の子たちの件でほとんど連日通っていて、久しぶりに気合を入れて裁判所に通っている、ということだった。すでに裁判は始まっていて、公式には誰も認めないが、証拠も状況も明らかなときは足繁く通ってみせてプレッシャーを掛けるのが一番安上がりで確実というコトらしい。
「気合と確信のあるところにヒトは説得されるモノだからね。出物が揃っているところでは体を動かした方がいいんだ。
――ああ、そうそう、この間の資料のまとめ、なかなかいい出来だった。特に指示がなくてアレなら、ウチでちょっとしごいてやれば、代書関係はすぐ身につく。
――最近の学生は法律関係の論理性をナメている奴らが多くて、法学部出身の勘とかセンスの悪い奴らが増えているのはどうにかならないのかね。ツボを売るのや女を口説くのと同じ方法で法律も動いていると勘違いしている奴らが多すぎる。理系文系ってのはアレだけど、いっそ理系の学生を引っこ抜いて法律教えた方が早いような気がするよ。
――万が一就職浪人してしまったらウチの事務所来なさい。資格はともかく仕事の仕方は教えてあげられるから」
裁判はまだ始まっていないも同然で、純一にとって面白いことはなにもなく、水本弁護士のテカテカと張りのある頭と、その先生に妙に買われたモノだという印象しかなかった。
どうせ、学生は冬休みなので、裁判所に行くのは純一にとってどうということもなかったが、警察からは事情の確認をおこなうことになるかもしれないから、あまり遠出はしないでくれと言われている。お陰で時間はあるが実家に引き篭る気にもなれず、正月だというのに都会で過ごすことになりそうだった。かと行って遊びに行く先も絞られる。誰もそうは言わないが、事件の構造的にサークルの誰かが絡んでいた可能性は高く、休みに大学に行く気もしない。
とはいえアパートに引き篭るのも純一の性に合わない。気がつけば街を一周りしてみて阿吽魔法探偵事務所でお茶を飲んでいた。大学に通う用がなくなってから、純一はほとんど毎日来ている。
苦学生という程でもない生活を親の仕送りでやっている身としては、遊ぶ金くらいは自分で稼ぐが正解だけれども、今年は大学が楽しかったので純一はあまり遊びもせずバイトもしなかった。その割に乾いた感じがしないのは、喫茶店がわりにしている居心地良いスペースを確保したからだろうと思う。
特に用があるわけでもなく訪れた純一に、夜月はコーヒーを入れてくれたままデスクに戻って一言三言話しただけで居眠りを始めた。夜月の居眠りは最近珍しくもないが、コーヒーを入れてくれて、しかし自分は飲まないで寝ている、っていうのはどうなんだろう。
と純一が思っていると、モソリと夜月が動き受話器をとり、「はい、こちら阿吽魔法探偵事務所です」と言った。チラリと純一を見たような気がする。どうやら駅からこの事務所への道順を説明しているようだ。
と、未登録の電話番号から呼び出しがあった。
「――もしもし、畑中くん?お久しぶり。今電話大丈夫?」
聞き覚えのある声だった。だが思い出せない。
出先だけれど、イイよ。と純一が答えると、
「突然だけど、あさって暇?パーティーやるんだけど来て欲しいんだ」と名乗りもしないで続けられた。
どうやら、親しい人物からの電話らしいが、誰だか全然思い出せない。先方も外らしく雑踏の音がする。場所を聞くと駅の傍の小洒落たレストランで、店自体に興味があったのもあって了解した。
「少し多めに紅茶を入れてください」
来客があるのか珍しく夜月が純一にそんな指示を出した。
事務所の扉がノックされたのは、ティーバックを取り出しているときだった。
扉をあけて挨拶をしたのは、聞き覚えのある若い女の声だった。ひとりひとりの識別はつかないが、挨拶の声で分かった。カップソーサを準備して出て行くと事件の時の子たちが四人が揃ってきていた。一人が挨拶の手に絡げた携帯電話を開いて閉じてみせた。彼女が電話の主らしい。滝沢さんだったか。
四人は裁判所に行った帰りがけだった。全員近場の駅だったので、揃っていた帰りがけにクリスマスパーティーでもしないかという話になったらしい。ここに寄ったのはそのお誘いと、水本先生を紹介したことに対する夜月へのお礼を述べるためだった。たまたま一緒にいた赤木先生も誘ったらしいが、年末で忙しい時期だからということで断られそうだ。山下さんの名前は出なかったが、卒論のピッチを上げるために冬休みも帰省しないで研究室に泊り込みの男だけのクリスマスをすることに決めている彼らは、雪と雨を降らさなければそれだけでサンタを信じる、とまで言い切っていたので、純一も口には出さなかった。女の子たちは事務所のガランとした感じと妙に良い作りのメイプルのデスク、奥のカーテンの間仕切りに興味深々だったが、比較的無難な話題を選んで帰ることを告げた。
夜月は、駅まで送って用がなければ帰っても良い、といって純一を送り出した。
女性のグループに男一人で混ざるのは、よほど気心が知れているか、よほど慣れているかしないとムリだ。名前もろくに認識できないような間柄ではおざなりに付き合うしかない。そんな感じが面白いのか、女の子たちはあからさまに純一を観察している。
「畑中くん、つきあってる彼女いないでしょ」
背の高いショートヘアの娘が脇から尋ねた。
「いません」
「お、ノーコメント、とか言うかと思ってたら正直に答えた」
名前は知らないけど、事件の現場でバールを純一から奪った娘が言った。
そんなので逃げられるような雰囲気でもないから、あっさり答えた。
「欲しくないの?」
ストレートな質問だ。
「欲しいけど、作る時間と方法が思いつかなかった」
バール娘がニヤリと笑った。
「四点お試しセットがあるんだけど、どうかな」
「あー、なんか、読めた。私たちと付き合わないとか言うんだ。なんか化粧品のサンプルみたいだな」
笑っている顔と困っている顔と半々くらいだったのを見て、純一は対応を間違えたことを悟る。
「……ええ、と、流れがつかめないんだけど、結構マジだった?」
「少なくとも私はマジ」
バール娘が言った。
「うひょーハーレムだぁーとか笑って流されるよりはマシだったかな」
室内犬のような髪型の小柄な娘が評した。
「ひょっとして中古は嫌だとか言う宗派のヒト?なら仕方ないけど」
バールの君が少し心配そうに言った。
「あのなぁ、そんな男がフォーシーズンスポーツサークルなんてナンパなサークルに居る訳ないだろ」
「でも、マトモに出てきてないじゃん。夏合宿楽しみにしてたのに」
ボソリと滝沢が言った。
「あのなぁ、滝沢」
「ブブー。滝川紫です」
「やっぱりなぁ。オカシイと思ったのよね。警察で滝沢さんってドコにいるかとか聞かれるし」
「ユカリ、優先権剥奪。ついでに畑中くん減点」
滝沢だと思っていた滝川のフルネームが分かった。彼女が答える前に一気にツッコミが入る。
「仕方ない。自己紹介タイムをここらで改めて設けますか。どうせ、名前も分からないままじゃ付き合うってのもアレだしね」
連絡先の交換というか、女の子たちの名前の勉強会のようなものを駅の中のドーナツ屋でおこなう事になった。
佐々木未来、川上光、滝川紫、遠藤慶子。純一は密かにバールを受け取った順番で純一は覚えた。彼女らは川上を除くと三年生で川上も一回浪人しているから同い年らしい。学部はバラバラだけどサークルが縁で買い物や旅行で何度かいっしょしているとかで、シフトも揃えたらしい。
佐々木は仕切り屋でどこでも一人いると楽なタイプ。細い川上を奥の席に詰めて、その隣に純一を座らせ、滝川で蓋をする。自分は斜め向かいで全員を目の届く位置においた。
川上は滝川が純一を気にしているのを気がついて純一を観察していた時期があるらしい。細く締まった体はなにかスポーツをマトモにやっていたようだ。学部が一緒で、講義もかぶっているモノがあったらしいが、知らなかった。
やたらと複雑な髪型をしている少し小柄な遠藤はなんというか、目のやり場に困るプロポーションの持ち主だった。ソレは全員わかっているらしく、正面に遠藤を置いて少し困った純一を意地悪く観察している。
滝川は名前を正しく覚えていなかったことがよほど気に触ったのか、「わたし、滝川紫は――」という言い方を少し繰り返していた。このメンバーの中では普通であることが却って目立つから、もう覚えた、と思う。もちろん純一にそんな自信はない。
で、しばらくすると、さっきの会話の説明に戻った。
全員が純一を別の件で知っていたらしい。去年までいた女王様とアダ名されていた女子学生が酒に酔ったままスキー場で派手に転んだのを背負っておりてきた。言われてみれば、去年の春スキー合宿のときに見知ったトドの醜態を見かねてそんなこともした。で、サークルの男を一回り喰ったはずの女王様が、酔った自分を背負っておりてきた感心な男性がサークルの男しかも喰ったことがない男、という事実を知りチャンスを狙ったが結局喰い損なった。という本人にしてみれば、えーそんな事言われても、という事件だった。しかもこの話には続いがあって、当時一年生だった女子学生がたまたま帰りに並んで座ることになり、純一が童貞でないことを証言してしまったことで、女王様はそうとうに荒れくるっていたらしい。ということで、純一は幻のヌシのような扱いを受けていた。本人はどうでも良いところで株が上がっていたようだ。
畑中純一が適切な対応を普通に選択できる間の良い独り者で、四人は男薬が欲しいところだった。わざわざ新しい出会いを探すのも今は少し億劫だし、リハビリ替わりに付き合ってくれるとだいぶウレシイ。純一の好みは知らないけれど、四人もいればアタリは含まれているかもしれない。
どうも良く分からないが、男薬とかリハビリとかいうニュアンスを考えると、四人は意外と真剣に自身に不安を感じているような気もする。
「気分はわかるけど、四人というか、二人でもムリでないかなぁ。俺には。あんまり甲斐性ないし」
プッ、と笑われた。ええと、と純一は思い見回してしまう。
「ゴメン。ごめんなさい。からかったわけでなくて、真剣に考えてくれることが予想以上に嬉しくて、つい」
「夜中に突然電話掛けても良いですか」
遠藤の言葉を受けて川上が言った。川上の言葉はあまりに静かで真剣だった。彼女らが求めているモノがなんだか純一にも分かるような気がした。
「本気で四人とって言うなら、SNSとIRCのチャンネルも教えとくよ。電話はもちろん良いけど、寝てたらゴメン」
携帯のメールでキーを送る。
「ちなみに、故郷においてきた彼女とかはホントにいないの」
滝川が心配そうに言った。
「そんなのがいたら、あんなサークルに籍をおいたりしないよ。俺のこと、どういう風にみてたのさ」
「優良物件ってヤツね。良い勘しているわ、ヒカリ」
「恋愛に興味がないというより、メンドくさがりだと思ったから、コッチから押せばいけると思った。畑中くん、ゴメンね。計算高くて」
川上がチョット済まなさそうに言ったのは、たぶん弁解というよりは釘をさすための言葉だったのだと純一は思う。
「よろしくお願いします」
遠藤が胸を邪魔そうに頭を下げた。つられて全員頭を下げる。そんな感じで解散になった。
翌日、夜中に川上から映画を見に行こうと純一は誘われて、映画を見たあとくらいから所在確認メールが届き始め、近くを車で買物していた佐々木が最後に合流して全員集まっていた。駅そばのショッピングアーケードと郊外型のショッピングモールは微妙な対決関係にあって、間にあった商店はスッカリ整理されてしまったが、言うほど悪いことばかりでもなく、学生にとっては緩やかなたまり場だった。川上はモールと大学の間くらいのところに住んでいて、モールが出している巡回バスのコースが近いのでモール派らしい。どうやら佐々木も車で動くことが多いのでモール派らしい。純一はバイクで移動することもあるのでどちらも使うが、バイクだと買い物には不便なのでアーケード利用が自然に多くなる。食品専門店の規模と性質がアーケードとモールの一番の違いか。
滝川と遠藤は恐ろしいことにほとんど外食で済ませてしまうと言っていた。
ソレはどうなのよ、ということで、佐々木先生のお料理教室が急遽、畑中邸で催されることになった。
純一はどういうことかあまり気にしていなかったが、どちらかと言うと純一の趣味素行調査みたいな雰囲気で、台所やらゴミ箱やら風呂場やらトイレやらにチェックが入っていた。お叱りの言葉も幾つかあったが、どうやら概ね合格ということのようで安心した。寝室件勉強部屋は四人とも無言でチェックを入れて評価は下されなかったのが純一には却って不気味だった。いっそタンスやらベット下をチェックされた方がまだマシなくらい四人とも黙って部屋を観察していた。
メインは鳥のひき肉でツクネを作った以外はあまり難しいことはせずに、季節のお野菜を中心に洗う千切る煮る。鍋モノという、あまり料理という気のしない料理を皆でつつくことになった。料理をしない滝川と遠藤も包丁を使えないというほど酷いモノでもなく、単にひとり分を作ったり残ったものを保存できない、というところがネックで料理から遠ざかっていたらしい。一品披露ということで、二人が作ったコンニャクの染み炊きと玉子焼きは普通に美味しいと言える味だった。純一の出した豆腐のトマトソース炊きはホールトマトの缶詰と豆腐をあわせて中華鍋で炊いただけのものだが、なかなかの好評だった。
なりゆきで酒が入ったので、夏掛けやら予備の布団を出して少し強めに暖房を効かせて四人を泊めることにした。風呂の使い方を教えて、入りたくなったら勝手に使ってくれ、と言って純一は寝室に引っ込んだ。
翌朝、卵と牛乳でフレンチトーストを焼いている匂いで目が覚めた。
半分勢いで四人泊めたことを思い出した。付き合っていることになっているから、まぁいいだろう、で泊めたわけだが、女の子を雑魚寝にさせて自分ひとりでベットというのはチコっと気にはなっていた。ソレはソレとしてまぁ要するに、まぁいいだろう。考えてもどうにもならない。
「おはよう」
ダイニングキッチンに遠藤以外の三人の姿を見つけ、シャワーの音がするということは洗面所は使えるらしい。脱ぎ散らされた服と下着を横目に声を掛けて歯を磨く。磨りガラスの向こうで慌てたような声が挨拶を返してきたが、すでに歯ブラシを突っ込んでいる口では返事できない。お椀のようなブラジャーのカップはちょっとしたインパクトだったけど、世の中にはそういうモノもあるという程度のこと。その場は無視したが朝食を終えて、四人がそれぞれ着替えなどのために解散したとき、純一のテンションは急降下した。大変そうだという想像と理解がいきなり降ってきた。
妙に慣れない空気が残っている気がして換気扇を回したまま、部屋を出る。しばらくうろうろして結局、阿吽魔法探偵事務所に足を向けてしまった。ここのところのパターンと化した、デスクチェアーにもたれかかりキャビネットをフットレストにした夜月の居眠り姿を無視して、ヤカンを火にかけカーテンの奥からアフリカ特集の写真雑誌を引っ張り出し眺めながらキッチンに向かう。キッチンのトースターの脇には衛星軌道の宇宙写真特集号と大型ネコ科特集号が読みさしになっていた。いつの間にかスプレー行為をしていたらしいことに気がつき、お茶とまとめてソファーに持っていく。居眠りをしている夜月のデスクに紅茶を一注しして、雑誌を眺めているとしばらくして夜月がモソモソと動き出した。
「なんか機嫌悪そうですね」
頭をカキカキ夜月が言った。
「――酒臭くて女くさい割にはナニもなかった感じが原因ですか」
ヒドく無神経な批評が純一に突き刺さる。
「……結論だけ言われると、まぁそうですけど」
雑誌を眺めながらそう言うのが精一杯。
「いいですねぇ。健全な青春の悩みな感じがします。やることやるまでの距離を獲得するまでが男にとっての恋愛の楽しさで、そこから先は単なるスポーツ競技みたいなモノですから。――はぁふぅらやましひ」
ウラヤマシイを欠伸とともに吐かれるとここまでひどくムカつくものであるか、と頭を掻きかきカーテンの奥に消えた夜月を純一は睨みつける。苦情を嗤い却下するようにシャワー音が聞こえた。クリスマスナンバーの暢気な鼻歌が漏れてくるのがまたムカつく。
夜月がカーテンの向うから出てきた時にはダークスーツになっていた。赤と緑のストライプのネクタイはたぶんクリスマスを意識したものなのだろう。
そこにデスクの電話が鳴った。大仰に溜息をつき、ツーコールで電話に出る夜月。
「はい。こちら――。あーうん。ハイハイ。そうですが。はい営業しております。ハイハイ。それではお待ちしております」
妙に丁寧に電話を切ると、デスクの引き出しから鏡を取り出してネクタイを少し直す。
「畑中くん、ドタキャンであいすみませんが、これからちょっとメンドくさいお客様が来るようです。お嬢さん方には申し訳ありませんが欠席するとお伝え下さい。会費は少ないですが、コレでキャンセル料ということでお願いいたします」
夜月は鏡と一緒に取り出していた茶封筒を純一に差し出す。中を覗くと五万円入っていた。ビックリする純一に背を向けて肩を回す夜月は妙な気合に満ちている。
「お客様と鉢合わせすると面倒くさいので、今日明日は来ないでください。で、できるだけ早く出かけてくださるとお客様と鉢合わせしないですむので安心です。時間中途半端ですけど、駅前の喫茶店ででも時間潰してください。すみません」
夜月はどうやら余程お客に逢わせたくないらしい。
言われた通りにビルを出て信号待ちをしている時に、読みかけの雑誌を借りてこようと思いついた。
クルリと方向転換して事務所に戻ると呆れたような悲しい顔をした夜月と戸口で対面した。
「なんですか?」
「雑誌を借りようと思って」
夜月は応接セットを一瞥し机の上の雑誌をまとめて自分で取って純一に押し付けた。
「コレですね。あーうん。マズイな。仕方ない。階段で五階まで登ってからエレベータで降りてください。で、出口から出たら左に進んで少なくとも信号二つ真っすぐ行ってください。コレは重要。絶対ちゃんと守ってください。いいですね。絶対ですよ」
夜月はそう言うと純一を押し出し、階段を指し扉を閉めた。純一は狐につままれたような感じがしたが、夜月の様子から言うことをきいておくことにした。
階段で五階まで登ると専門図書翻訳会社と、ビデオ個室がある。エレベーターは上に向かっていた。下の呼び出しを押す。
エレベータが三階で停った。
五階についたときゴンドラには誰も乗っていなかった。
下りの三階は素通り。
一階に着いたとき、あからさまに暴力的な男が二人、こちらを見た。階段の前にももう一人いたので三人か。
男たちは小脇にまとめて抱えた雑誌に眼をやると一人が鼻で笑った。ちょっとムッとしたが、関わりになりたいわけではないので、ビルを出る。黒塗りのセダン。なんだか分からないが、状況的にはソレで十分なので、左に折れて直進。振り向くのはヤバそうだったので路々の窓や鏡で車の様子を見ていると、車から一人降りてこちらを追っている様子。
走った方がいいのか、いけないのか。走ると後ろの様子をみる余裕はなくなる。
男はまだ走っていない。意図があって追っているというほどハッキリしていない、のだと思う。
一つ目の信号は青だった。信号変われ、と念じたのは白バイに追われたとき以来だ。右側をミニパトが通過していく。当然のように純一は無視されている。少しは空気読んで役に立てよ、と純一はそんな理不尽な考えに自分で嗤った。
そういうときは不思議に信号は変ったことがない気がする。男は自動車も点滅信号も無視してまっすぐ来る。
二つ目の信号は赤だった。変わらないのは分かっている気がするが、それでも純一は、こんどこそ信号よ変われ変われと念じて立ち止まっていた。これだけ念じているのにオマエは変われないのか。
後ろから来る男の姿はアチコチに見えているが、どれも近づいているのは間違いない。途中で自販機も公衆電話もコンビニもいくつか通過しているから、ちょっとお使いというワケでないのは分かっている。だが、森永のホワイトチョコレートソーダなら駅地下で見かけたからそっちにいってくれ。
と、男の歩みが急に遅くなった。まさかホワイトチョコレートソーダが欲しかったのではあるまい。
後ろで自転車のブレーキ音がして、つい反射で振り向いてしまった。目の前に自転車に乗った警官。ぶつかったかと思ったらしく、ゴメン、と警官は言った。もう一台、信号を渡ってきた。
お巡りさん二人は奇遇を感じたのか、挨拶をして信号待ちで雑談を始めた。明らかに男は狼狽した動きをみせる。
信号が青くなったら走るべきかどうするべきか、純一は悩んでいた。男との間合いを考えると、警官の自転車が見えているギリギリまでは走らない方がいい、と思っていた。だが、ソレはその間に男が追いかけるのに飽きて走ってきたときにはマージンがなくなることも意味している。追ってきている男の仕事は、顔を確認して因縁をつけて時間を稼ぎ、応援を呼ぶこと。多分殴られ上手な男だろうと思う。車で待機している連中がいることを考えれば、事務所の一階を張っていた連中を考えれば、車は三台以上いることになる。車が動いたら数十秒で囲まれる。捕まるならせめてどこかの建物内にして欲しい。
信号が青くなった。二台の自転車が力強く漕ぎ出された。
「市民会館はどう行けばいいですか」
老人の声がした。
自転車の警官は気勢を削がれて苦笑していたが、純一は内心で拳を握った。二人の警官は肩を竦めると一人が申し送りをして老人に道の説明をはじめ、もう一人が先行することにした。
先行した警官が純一を追い抜いて曲がった道を、純一が追って曲がったとき、追跡していた男はかなりの本気で走っていた。だが壁に映った顔が識別できるとしたら、ソレはヤクザをやっているような人間の視力とは言えない距離だった。
角を曲がった途端、純一は走り出し、手近なビルに飛び込むとエレベータを呼び出し、幾つかのフロアのスイッチを押すと裏口から出た。念のため、銀行の入っているビルを一つ通過して尾行を確認した。マいたらしい。
タクシーを拾って駅の反対側に降ろしてもらって、駅地下の紅茶専門店でプレゼント包装の紅茶セットと薔薇の花を模したクッキーを四つづつ買うと、紙袋に雑誌をしまい喫茶コーナーで心底グッタリした。
――斎さん、ソレはメンドくさいお客様でした。
なんだか分からないが、警察でないならヤクザくらいしか候補のなさそうな動きはナンナンダと聞くのもうんざり。純一はそんな気分だった。
そんな感じで、夕食会にご招待いただいたときには、純一は疲労と緊張でスゴいことになっていた。
コレ以上ないダメなローテンションに欠席も少し考えた純一が嫌々ながらレストランをくぐったのは数分前。
ダークブラウンのバギーパンツとフリースのタートルネックにモスグリーンのハーフコートは、純一には似合っており、ノータイで許されるところならどこでも問題ないファッションだったが、お嬢様方の気合の入り方は謝恩会か披露宴かという勢いだった。あまりの衝撃にテンションがたたき落とされ急上昇したのを、感じざるを得なかった。女が着飾っているのを観るのは男としては幸せなんだろうと思う。いや、間違いない。疲労と幸福感でいい感じに頭が麻痺しているのを純一は楽しんでいた。
「会が始まる前に良いお知らせと悪いお知らせがあります。
悪いお知らせは斎さんがお仕事でお客様を迎えているということです。
良いお知らせは斎さんから皆さんへのささやかなお詫びとプレゼントして、幾分多めのキャンセル料を畑中純一さんにおあずけくださったということです。たぶん私たちの分の支払いは純一くんが旦那の甲斐性をみせてくれるでしょう。
今年は色々ありましたが、まだ僅かに残っています。残りを楽しみ、来年はさらに楽しみましょう。では私たちの旦那様予定者、畑中純一さんに乾杯をお願いいたします」
「メリークリスマス」
純一には本気だかどうだかよく分からない佐々木の幹事挨拶を受けて、夕食会は始まった。
純一はヒドくいい気分だった。酒も入っていたしで、ついうっかりみんなに訊いてしまった。
「確認しておきたいんだけど、君たちの求める付き合っている彼氏の機能って何?」
「男友達」
「セフレ」
「セフレの線はいいや。俺あんまりソッチのこと良くわかんないし、食事時にする話でもない気がする。必要になったら相談しよう。男友達って何すれば良いの」
「サイフ」
「アシ」
「別荘」
「ボディーガード」
「旅行の連れ」
「相談相手」
「苦情窓口」
「スパム先」
「ガイド」
「コック」
「家庭教師」
「執事」
「掃除屋さん」
「運転代行」
「修理屋さん」
「電気屋さん」
「荷物持ち」
「飼い主」
「ペット」
「湯たんぽ」
「布団」
「抱き枕」
「お父さん」
「お兄ちゃん」
「弟」
「おもちゃ」
「褒めて」
「撫でて」
「チューして」
「ハグして」
「抱っこさせて」
「舐めたい」
「噛み付かせて」
「腕枕して」
「膝枕させて」
「日向ぼっこしよう」
「腕組もう」
「手を繋ぐ」
四人もいるとすごい勢いで出てくる。
「なんだか、二十四時間営業では追いつかないような気がしますが、皆さんいかがお考えでしょう」
なんだか白い目の集中砲火を食らう。
「敗北主義的発言ね」
「悲観的っていうか全然前提が間違っているわね」
「真面目に言ってるのかどうなのかもアヤシイわね」
「意外と手間のかかるダメな子なのかしら」
純一は両手を上げて発言を撤回する。
「サイフはかなり薄いけれど他は全部できます。だけど脊髄反射でできるほど馴染んでいないから、ポーリングは安定してできないよ」
「脊髄反射でできるのは一流ホストかラブラブ新婚さんだけです。だけど、純一くんにはそこを目指して欲しいと思います」
遠藤が笑って口にしたが目は結構真剣だった。
「サイフは、全部出せと言っているわけでなく、ちょっと調整してくれるだけでいい」
「自分が使うのより少し多めに準備してくれればいいの。使うか使わないかとかでなくてね。苦しいようなら後で返すし」
川上が言ったのを滝川が補足した。
「まぁ甲斐性の働かせどころなんぞは観察と想像で見極めないと、いくらあっても追いつかないというのは時間や金と一緒だ。力はあるがダメな男を良い旦那にするのは女の甲斐性よね。ヒカリの意見によると、優良ダメ男物件としてはかなり有望だという。私もソレには賛成。少し鍛えればいい感じになる」
佐々木が真面目に言っているらしいことは疑う必要がなかった。その佐々木がアイコンタクトを飛ばした。
「あーん」
遠藤がローストチキンをフォークに刺して口元に突き出す。純一はギョッとしたが、求められているところは理解したので素直に口にした。
「ウレシイ?」
遠藤が訊いた。
「とても恥ずかしいがウレシイ」
咀嚼する時間だけ考えて純一はそう言った。
「ギコチナイけどこんなもんじゃない?」
滝川が反対側で言った。
「私は結構満足かも初々しい感じがカワイイ」
「ふーん。じゃぁ、私もアーン」
遠藤の言葉に羨ましくなったのか、滝川もフォークを差し出した。仕方ないのでパクっと銜える。
「美味しい?」
その様子を見ていた他のテーブルから笑いが漏れているのが純一の目に入った。
「笑われているのがすごく恥ずかしい」
「だめだなぁ。君は私たちの男なんだから他のテーブルなんて気にする必要はないのだよ。ご主人様」
佐々木が笑って言った。
「じゃあ、私も、アーン」
テーブルの向こう側から川上が参戦してきた。
「どう?」
「美味しい。今度はウチでやろう」
ザッっと女の子の目が集まった。
「……ウン」
川上が少しためらってうなづいた。
「オー訓練の成果が早くも」
「ミキちゃんもやってみないの?」
遠藤の言葉に、すでに皿の上を片付けてしまっていた佐々木は川上が皿を寄せた鶏肉を断り、バケットを小さくちぎり皿にまだたくさん残っていたソースを指が汚れるのも構わずたっぷりつけて、身を乗り出して差し出した。
「アーン」
斜向かいの位置なので、純一も身を乗り出す事になるが、微妙に届かない。純一がパンだけを銜えようとした瞬間ほんの僅か指が伸び、佐々木の指が口に飛び込んだ。純一は歯に当たった爪の感触に慌ててパンを銜えて身を引いた。
「美味しい?」
見守っていた全員が見ている中で、佐々木は指にまだ残っているソースを舐めとりながら言った。
「あー結構なお点前で」
爪の先でひっかかれた口の中を舐めながら純一は答えた。
「ミキちゃん、ソレはずるい」
佐々木は滝川の糾弾を平然と受け、あらかた舐めとった指を気を利かせたウェイターの持ってきたフィンガーボールですすぐ。
「もう私の皿の肉がなかったんだから、しょうがないじゃないか」
「食べ物であんまり遊ぶなよ。それに俺は次の皿が欲しい」
ムキになって怒ってまでやることじゃないので、純一は口を挟んだ。
「ソレと佐々木、爪で口の中切った。痛いよ」
「あ、ごめんなさい。唇の裏に当たっちゃってたか。お詫びに下の名前で呼ぶことを許可します。ミキと呼び捨てでいいわよ」
「それはありがとう」
「ミキ」
少し怪訝な顔をする純一に佐々木がくりかえす。
「リピータフタミー、ミキ」
「ミキ」
「次のセンテンスに進みましょう。愛しているよ、ミキ」
コースの配膳がデザートがブュッシュ・ド・ノエルに変わるのも無視して佐々木は言った。
「リピータフタミー、愛しているよ、ミキ」
まるで英会話の教材かナニかのような言葉。しかしその目は笑っていない。
「愛しているよ、ミキ」
気休めにしても本気にしても求められている役割がハッキリしているからか、純一は本気で素直に口に出した。
「うれしいわ、純一さん。私も愛している」
仮りそめでも何でも、そう言われるのはうれしい。佐々木の目が潤んでいるような気も少しした。すでにワインも四本目になっているので、酔っているのは間違いない。そういう理由かもしれないが、そこはまぁいい。すでに純一の幸福感のカウンターは振りきれていた。
勢いのまま、純一は川上に向き直る。
「ヒカリ」
「は、ハい」
「愛しているよ、ヒカリ」
「あ、ありがとう。純一さん」
ツッコミの厳しい川上が意外にもナニも言わずに、ケーキに向かって逃げるようにフォークを進めた。
なんだか分からないが、楽しい。理由は感じているのだが、ソレがこんなにも嬉しいモノだとは思わなかった。
「名前を間違えていて済まなかった。滝川さん。できれば許して欲しい。ユカリ」
「うん。あんまり話してなかったし。しょうがないもの」
「愛しているよ。ユカリ」
「ウレシイ。今度はちゃんと全部覚えていてくれたのね」
「君が結婚するまで忘れません。タキガワユカリさん」
「結婚しても名前は変わらないから覚えてて。純一さん」
「もちろんだよ。ユカリ」
名前を繰り返す度に目が潤んできた滝川は純一の腕の中に顔をうずめた。鼻をグシグシやっている。ナプキンが固くて、上手くいかないらしい。ポケットから和手ぬぐいを引っ張り出して純一は滝川に渡す。
滝川が落ち着いたところで、すでにデザートを終えていた遠藤に向き直った。
「ケイコ」
「なんですか、純一さん」
「愛しているよ、ケイコ」
「私も愛しています。純一さん」
遠藤は純一の両手を包みこむと、鼻先にこすりつけ指先を舐め口づけした。振り払わなくても自由に動く指先で口元や鼻先を軽くなぞったり叩いたりしていると嬉しそうな顔をする。
「ケーちゃん、純一くんはまだケーキ食べてないよ」
佐々木の声に抱え込んでいた手に甘噛みすると、遠藤はようやく開放した。
「順番最後で良かった。スッカリ堪能しちゃった。ありがとう。純一さん」
「これも彼氏の役割だろ、ケイコ。名前を呼び捨てにするよりは気分的に楽だからいいさ」
「そんな風に割り切られると悲しいけど、私にはとても大事なことなの。――嫉妬した?ミーちゃん」
「うん。結構キタ。でも、愛しているから大丈夫」
佐々木は素で返した。
「ケーキ美味しい。チョコクリームがふわふわでベタベタもたもたしてなくて、ケーキと丁度いい甘さ」
「多分、砂糖の代わりに水飴とキャラメルを使って、炭酸ガスでホイップしているの」
川上が説明を入れた。
「へーそんな機械があるんだ」
「泡だて器を電気じゃなくて、ボンベの炭酸ガスの圧力で回転させながら吹き込んでふんわり仕上げるの。便利だけど、ソーダマシン用の使い捨てボンベで差し替え利かないから毎日使うつもりか業務用でないとちょっと買いにくい道具」
「でもみんなで大きいところに引っ越すなら買ってもいいかも。玉子焼きとか楽そうだし、他にも使えるんでしょ」
滝川が思いついたように言った。
「引越し?大きいところって?」
「みんなでルームシェアしようかって話があるの」
聞きとがめた純一に遠藤が説明をする。
「裁判することになったでしょ。全員親元離れて一人だから、嫌がらせとかあると一人だとさすがに不安だし、危ないし」
遠藤がコーヒーのお代りを受けながら言った。
「嫌がらせ?」ってのは初耳だ。
「なんか偉い人の息子だかなんだかが混じっているらしくって、赤木先生ができれば、家や人の少ない学校の傍よりは街中に引っ越した方が安全なんだけどって。実際に街頭とか少ないトコもあるからちょっと怖いところもあるし。ウチに赤木先生が来たときにそんな話が出たの」
遠藤の家がどこだか分からないが、モールと学校の間という辺りは確かにあまり人が多く歩くような道ではない。
「一応訊いておくけど、ソレで俺を四人の彼氏ということにしようとしたとか?」
怒っているというよりは、なりゆきの確認が必要だろうという気分だったのだが、女の子たちは明らかに危惧するところが多かったようだ。佐々木さえ一瞬ひるんだ。
「違う。そこは大丈夫。――」
川上が力強く保証した。
「――事件のあと、私たちは四人で会うことが多くなっていた。自然に助けてくれた人の話になってたの。去年とかは合宿にも来てたけど今年は全然だねって話になって、でも彼女いないみたいって話になって、勿体無いよねって。良い人なのに気がつかれないのはもったいないし、誰かに取られちゃうくらいなら欲しいし、って話になって。でも向こうにも好みがあるだろうし、あっさり振られるかも、でも順番が回ってこないうちに誰かがくっついたらムカつくし、って話で。じゃぁミンナで付き合ってみてダメならダメってことで、クリスマスで彼女いないなら捕まるだろうし誘ってみた。だから彼氏になって欲しいという話と、ルームシェアとかボディーガードとかの話は全然関係ない。ミンナ純粋に畑中純一を欲しいと思った。だけ」
「ルームシェアとかの話は、ちょっと前に向こうの弁護士らしい人から手紙が来ててさ。要するに向こうの弁護を引き受けますって内容らしいんだけど、水本先生に連絡したら赤木先生が飛んできてくれたの。全員の家を回って危ないところ色々指摘して、できれば引越しって話になってさ。水本先生が幾つか不動産屋さんをあたって大きめの部屋を調べてくれて、四人の家賃や光熱費を合計したら結構大きめのマンションを割安で借りられることが分かったの」
滝川の説明を聞くと、結構本気らしい。
「私は帰らずこっちで就職することにしているし、月々少し安いくらいの支払いで新築マンションも買えることが分かったから、卒業後もこの関係を続けるならマンション買っちゃうかと、私は思っている。もちろん離婚ってか破談が決まった段階で、転売して売却益を分割するつもり。ちなみに、借りる予定の部屋はどれも風呂トイレ台所を除いて六部屋以上あるから、君がいつ泊まっても大丈夫だし、専用のプレイルームが欲しいといいだしても大丈夫」
「でもあっさり振られるかもしれないし、コッチがあっさり見限るかもしれないから、引越しとルームシェアの話はジュンジュン抜きで進める。あと、プレイルームより大きなお風呂場が欲しい。ユニットバスはイヤ」
プレイルームとかサラッと流した佐々木よりも、受けた川上の言葉に驚く。
「ジュンジュン?」
「ジュンジュンか。ジュンチーとかでくるかと思ったが、どう思う、ケーちゃん、ユカリン。ピカリンの提案は」
「意外とそういうの好きね。ミーちゃん」
「この歳でもこういう呼び名が自然に使える関係は結構面白い。まぁ、初対面で言われたら間違いなく殺すが」
「ところで、ミーちゃん」
「なぁに、純一さん、愛しているわ」
ジュンジュンなりなんなりで返ってくるかと思ったら、ちょっと重い。
「俺も愛しているよ。って、ミーちゃんって言うなってこと?」
「なんか私の愛を疑われたような気がしたから、必死で弁解しているの」
デザートも終わり、空いた机の上で腕を仰ぎ芝居がかってみせる佐々木。
「疑ったというよりは、なにが起こっているのかという興味だな。愛あればこその無邪気な質問だよ、ハニー」
純一は付きあうことにした。
「良かった、ウレシイわ。愛しているのは間違いないもの。ソレでところで、なにが聞きたかったの?ダーリン」
「愛する素敵な皆さんに心ばかりのプレゼントなぞ用意してきたんだが、このタイミングでお渡ししても良いだろうか」
「もちろんよ、ダーリン。でもところで、この後お家におじゃまして良かったら皆で伺おうかと思っているのだけど、よろしくて?」
「あ、ひょっとして、ウチ帰って渡した方が良い?」
一瞬にして素に帰ってしまった純一を四人は笑った。
「そしたら一旦お開きにしましょう」
パラパラと女の子が席を立つタイミングでチェックを頼み、支払った。夜月に預かった金額に純一の会費予算を足して数百円余る。という絶妙な金額だった。
「良い夜を」そんな声に送り出され、連れ立って街を歩く。
すぐに左右を遠藤と川上とに挟まれる。しばらく滝川はうろうろと三人の周りを廻っていたが、純一を少しかがませると後ろに飛びついた。
「悪いがさすがにもう無理だ」
純一は佐々木に笑ってみせる。
「そうでもないわ」
そういうと佐々木は川上の腰に伸ばしていた純一の右手に左手の指を絡める。
「ほらね。このくらい軽い軽い」
佐々木は元気よく引っ張り出した。
佐々木の車のトランクから荷物を下ろす間も四人は純一にぶら下がり続け、酔っ払ったんだか疲れたんだか分からない状態で純一のマンションに帰ってきた。駐車場からマンションまで五人ともなんだかよく分からないが大笑いをしていた。一階のロビーを抜けエレベーターを待つ間こそ、笑いをこらえていたが、エレベーターに乗った途端にまた笑い転げた。
着飾ったままの姿で荷物を抱えて、しかも純一に張り付いている姿を近所の親子連れに発見され子どもがお父さんに、あれやって―、と言い出し、ノリの良いお父さんがお母さんと子供を抱えてクルクル回りだしたことがキッカケだった。
体力のありそうな、実際に高校国体に水泳で県代表になったこともある川上が先頭になって両手の指を純一と絡げてそこに佐々木と滝川を内向きに座らせて、背中に遠藤をぶら下げてナニかの祭りのダシのような格好で歩いていた。佐々木と滝川が荷物をまとめて持っているが結構大きい。だんだん、ヒールが辛くなってきたという川上をかばうため、最後の一区間は二人を肩に乗せて両腕を踏ん張るような姿勢で川上の肩に手を回して歩いていた。カップルがコッチを指さしたのを純一も見た。落ちる―と言う頭の後ろの嬉しそうな遠藤の悲鳴は全員の笑いを誘い。駐車場からの百メートルあまりの道のりをひとかたまり大笑いしながら純一は歩いた。
「そうは見えないけどすっごい体力よね」
「やらせといてナニ言ってるんだか」
自分だけぶら下がっていない。と不満を述べた川上をエレベータの中でお姫様抱っこにして、じゃぁ私が後ろと佐々木が張り付き。もう疲れたから良いや。と遠藤と滝川がおざなりに腕を絡め、身を寄せた。なんだよ、全然終わらないのか。でまた笑った。
右側にぶら下がった滝川にズボンのポケットから鍵を探らせて、玄関に入ったところでようやく両手が自由に動くようになったので、川上を抱えたままヒールを脱がして下ろしてやった。靴擦れでストッキングが破けていた。
「ソレはなんだか素敵なサービス」遠藤が羨ましそうに言って写真をとった。私たちもやれ―と言う声に答えてあまり広くもないマンションの玄関で、お姫様抱っこでヒールを脱がして記念に写真撮影までするというサービスをおこなった純一はかなりの疲労困憊で、リビングに帰ってきた。
寝室を女の子の着替えに提供すると、ヤカンにお湯を沸かし、紅茶の準備をする。ラジオをクリスマスしか合わせないFENにするとクリスマスナンバーが流れ出した。リビングでうつ伏せになって伸びをした。薄物のワンピースなのか寝間着なのか判断に困るモノを着た遠藤が最初に出てきた。
「お疲れ」そう言って、とすんと純一の背の上に座る。
「ハッピーメリークリスマス」
「あー、ハッピーメリークリスマス」
遠藤はクリスマスソングの鼻歌に合わせて肩を揺すっているらしく、背に載っている尻の重心が変わる。純一はひらめいた。
「ケイコちゃん。お願いがあるんだけど」
「なぁに、純一さん」
「俺の肩胛骨の間に膝をついて正座してくれる?」
「マッサージ?」
「そそ」
背中の上で鼻歌歌いながら、もぞもぞしている遠藤をおいて三人が出てこない。
ヤカンが湯の沸いた音を出す。
「ケイコちゃん、ヤカン止めて、ポットの脇にあるティーバッグ全部入れて、お湯入れてすぐにタイマー回してくれるかな」
遠藤は鼻歌を歌ったまま、肩の筋肉をなぞっていた手を伏せたままの鎖骨に進める。
「ケーちゃん?聞こえてますか」
純一がひねって向けた顔に遠藤は鼻歌のまま口を近づけた。
「私とセックスしたくない?」
冗談ではなさそうな探るような目で遠藤がいった。
「いま?紅茶入れてプレゼント交換した後ならいいよ。でも他の三人を追い返すのはヤダな。ミキちゃん酒入っているし、飲酒検問ありそうだしね」
「そんなコト言う口は――」チュプっという音とともに遠藤が純一の上唇に吸い付いた。
唇が吸い込まれた隙間に遠藤の舌が入り込む。
純一は唇を吸われたまま、上半身を入れ替え起こす。遠藤は振り落とさるのかと慌てたが純一の腕が腰と膝を抱えているのを知り、より積極的に唇を重ね舌を差し入れる。あまり重くない遠藤の体とはいえ、普段と違う息苦しさに開いたり閉じたりする純一の唇を探検するように遠藤は舌を進める。ヤカンの音を気にしながら純一はバランスと下半身の力で膝を起こし立ち上がる。遠藤の膝を割り、腰骨にひっかけて、唇と舌をからませたまま沸き立つヤカンからポットに湯を注ぎ、ポットからカップに注ぎ、ポットに茶葉をいれ改めて湯を注ぎタイマーを回す。ナニをやっているのか大体のところを察した遠藤はイタズラを明らかに楽しんでいる表情で豊かな胸を擦りつけ蠢かせつつ、困った顔の純一を観察しながら長い長いキスを楽しんでいた。
タイマーが鳴ったところで純一が遠藤を支えていた腕を離すと、ズルズルと木登りに失敗した猫のように唇から離れていく。
「はい、時間切れです」
首に手を回したままムッツリしている遠藤に、茶葉を取り出しながら純一は言った。温めていたカップとポットをトレーに載せて、遠藤を無視してリビングに向かった。
途中寝室をガラリと開ける。部屋着に着替えた三人が気まずそうに立っていた。
「今のはどういう意味かどなたかの解説を希望しますが、まずはお茶にしよう」
ラジオは厚木は晴天快晴でホワイトクリスマスにはならなかったけど、サンタを探すには絶好の日和なので空を見張って探してみようぜ、とかそんな感じのMCが入っていた。話題は米軍のサンタクロース関連体制のバカ話らしい。
「純一くんとセックスしたかったのは本当なの。別にからかう意味があったわけでもないし、反応を覗くとかそんな感じの話でもないの。強いていえば本当にヒドく発情したというだけ」
この二日で十分ヒドく驚いて、この上なんの冗談かと思っただけで特に今更怒ったわけでもない。濡れた猫のような有様になってしまった遠藤に逆に同情してしまって純一は一生懸命に言葉を探した。
「しょうがない。コッチおいで」
ちょっと離れて座っていた遠藤を膝を叩いて招き、あぐらに肩を沈めさせて膝枕をしてやる。
「たいしたモノでもないけど、プレゼントは配っておきたかったから……俺の紙袋ってどこだっけ」
「まっててー」
川上が立ち上がって戻ってきたときには紙袋は一つではなかった。雑誌が入ったままの紙袋を純一に差し出し残りをそれぞれ配る。
「さて、それでは彼女不在期間二十周年記念にして、なんと四人も彼女ができることになった華やかなクリスマスを記念して、可愛い美人の俺の彼女のみなさんにささやかなプレゼントをたっぷりの愛、カッコ計量不能カッコ閉じ、とともに差し上げたいと思います。ビスケットは結構薄くてもろいから壊れる前に食べた方がいいよ」
堅焼きにしたクレープ生地の焼き菓子をジャムと飴のスプレーで支えた白とオレンジのバラは、空気の乾いている冬場の季節物で小さく軽いくせに、一緒に買った紅茶セットより高い。
クリスマスのナンバーが少し遅れてラジオから聞こえてきた。
「食品成分表には規格がないから成分表示には書いてないけど、畑中純一の愛ってのが含まれてるから湿気ってガッカリしないうちに早めに食べてね」
「彼女不在期間満了を記念して、純一さんにはペアのマグカップをお送りします。愛人の皆さんにはです」
滝川がそう言う。取り出してみると黒字と白地の入れ替わっただまし絵のペアカップの片一方は他の三人と同じ柄だった。
「ほほう。愛人の私たちは揃い柄か。そうかー、純一の愛人専用カップか。噂の愛人の滝沢用を用意するとはなかなかの心がけだ。私たちはココにおいていけばいいのも気が利いている。かわいそうにユカリンの分はなさそうだが」
「アレがあたしのよ!」
「でもアレはジュンジュンへのプレゼントでしょ」
「わざわざ愛人とか言わなきゃいいのに。これがユカリンの分なんだね。分かったから、あとで皆の分洗って棚に入れておいて」
川上がつっこんだところで、純一は話を切ることにする。
「私はピクニックバスケット。ココの家、まえ来たとき揃いの食器とか全然なかったから、ウチでも全然使っていないヤツを持ってきた。六人用だから噂の滝沢さんが現れても大丈夫よ」
「これか。目の前で邪魔くさかったヤツは」
「落として割れたらどうしようかと思ってた。でもこれで最低限食器は揃ったでしょ。コレはご主人様への貢物で、女の子用には伸びる手袋の手首が長いヤツ色違いの二枚セット。寝るときにしておくと冷えなくて結構いい」
川上が袋の名前を確認しながら、一つづつ配り始めた。
「私はお箸。と箸袋。私のはコレ。螺鈿で魚の細工が入っている。皆柄違いだから自分の覚えておいて」
純一のは梨地になっていた。箸袋は大根とカブとナスにキュウリの染め抜き。
純一の膝の脇でうずくまっていた遠藤がモソリと起き上がった。
「私はバイト先で前のキャンペーンの残りでドンブリ大小でたくさん貰ってきた。あとレンゲ。みんな用にはおザブね」
ドンブリ大小といってもいかにもオマケ商品らしく全体に小さく大きな小鉢くらいの大きさの飯丼と、ラーメン屋でコレが出てきたら怒るだろうなと言うような大きさの大きめの茶碗だった。だが、電子レンジで使えます、の文字はとても心強い。
紙袋から食器を取出し包装をたたんで紙袋に戻すと、遠藤は再び純一の膝の上に頭を載せる。
「みんな食器ってなんだかなぁ。こないだの晩ご飯が余程ショックだったと見える」
「食器が少なくてステンのボールを鍋の鉢にするのまでは仕方ないとして、パイレックスのタンブラーグラスまで出てくるようだと少しね。でも、コレなら明日はお米のご飯炊けるじゃないか」
「三合炊きだけど足りるかな」
「足りなかったら電子レンジで芋ふかしてもいいし。一昨日の残ってるでしょ」
「愛人じゃない滝川紫さん、てつだって」
川上が立ち上がって、そこらに開陳された食器類を集めだした。
「なにを」
「洗って片付けるの。食器を」
「ピカリン、ユカリン頼む。洗っといて」
「頼まれました。ジュンジュン」
純一が言うと、川上が立ち上がってぴしっと敬礼してみせる。
「ユカリンわかったよ。あとでジュンジュンの膝貸して。見てたらなんか羨ましくなってきた」
立ち上がった川上の持っているお盆に食器を少し足して立ち上がる滝川。
二人が立ち上がったのを見ながら遠藤は純一の指を音を立ててしゃぶっていた。
「ミキ、風呂、先に使っていいよ。洗うものあるなら洗濯機も使っていいし」
「そしたらお先にそうします。――おーい、ピカリン、ユカリン洗濯物出して。洗っちゃう」
「ケー、洗い物、はいいか」
「ある」
遠藤はモソモソと丸まるとスカートの下からブラジャーとパンツを取り出して佐々木に渡した。さすがに佐々木も苦笑する。
「立ってる?」
佐々木はどちらということなく訊いた。
「ヤナ会話だな、おい。少し恥じらえ」
「発情した雌にとって気に入った雄の生殖能力は最重要事項よ」
「私たちのために避妊はして欲しいな」
臆面も無く言った遠藤に苦笑しながら佐々木が注文をつけた。
「出来婚しなくても認知してくれれば産んぢゃうよ?」
「まぁ、私もそのつもり。旦那様が心配そうな顔しているから責任とってくださるようだし、大丈夫かな。――じゃぁ、ごゆっくり」
ごゆっくり、と言う方が反対な気がする。空いている手で三つ編みを巻き込みシニヨンに結ったおくれ毛を撫でてやると、遠藤はアスファルトの上の芋虫のようにモソモソとうねり始めた。そのうちツヤツヤに濡れた純一の指を重たく歪んだ胸に押し当てる。
「約束」
そう言って胸の上で動いていない純一の手の甲をつねった。純一は人差し指中指薬指で小さな三角形を作り乳首を探り、その周りをクルクルと指先で円を描いてやる。クともフともつかない吐息を漏らしながら気分を出している顔の髪の生え際をなぞってやる。
変な話だが、犬か猫を撫でているような気がしてきて次第に勃起が治まってきた。代わりに純一から逃げ出した淫気に当てられたかのように遠藤の腰と膝の動きが早くなる。衣擦れに合わせて純一も指の動きを早くする。突然遠藤の頭が激しく動き、額の生え際を撫でていた指が位置を失い半眼のまぶたを叩く。遠藤は達した。息が急速に整ってゆき、膝が崩れる。くすぐっていた指を落ち着け、手のひらで撫でてやる。
台所の二人がコッチを見ていた。
「終わった?」
「お、おつかれ。ありがとう」
「意外と早かったね」
台所とリビングで微妙に噛みあっていない。
「気にせずヤっても良かったのに」
「俺は気にするんだよ。犯罪被害者と分かっている相手に、交際申込まれて三日目でハメるってのは、余程事情が分かっていないと俺の価値観では無責任だというんだよ。ホストじゃないんだ。まずは説明しろ」
「説明はしにくい。多分できない。私たちはケーちゃんのホントのことはよく分かってないし、ケーちゃんは多分色々ツラいから」
純一の言葉に川上が言った。
「純一くんはオナニーするときの理由を説明できる?」
なんだろう。考えた事ない。溜まったから?生理現象?
「――そんな感じ」
「まぁ、アレだ。私たちの場合は、不幸な体験を類似の幸福な体験でオーバーライトして抹消しようという防衛反射。とか臨床的には説明されそうだけどね。正直、同種の体験をした者としては、自分の体験を言語化して誰かに説明するなど、ご主人様の命令でも嫌だね。あの時のことを思い出すと殺して欲しいくらいさ」
タオルで髪を巻いたパジャマ姿で佐々木が風呂場から戻ってきた。
「――肉体的に健全な男性としての反応と、社会的に健全な男性としての反応がせめぎ合って、抑制的な行動を選択させたという状況は分かる。でもね、さらに肉体の反応と精神の反応が全くズレていると、快楽に逃げることも苦痛を認めることもできない状態になるんだ。あの三十分足らずの出来事は絶望と無力いう意味を知る酷いものだったよ。そして貴方はごくあっさりと私に復讐の機会を眩しくも下された。まぁ多分だから彼女はキミを求めて、私はあなたを必要と感じているんだろうと思う」
佐々木はそう言って、頭のタオルを少し叩いて解いた。肘の辺りまで落ちてきた前髪を掻き上げる。
「……ベッド借りていい?」
川上が佐々木を避けるようにして寝室の戸口に立ち入った。
「あとで布団出しに行くけど、いいよ。風呂は?」
「朝借りる」
川上は寝室に消えた。純一と川上のやりとりを無視して佐々木が純一の前に歩み寄り、膝を突き合わせるような距離で膝立ちになる。薄着になってパジャマ姿だと、かなり着痩せする印象だったことが分かる。ユサリと量感を持った胸と温かい女の体臭が見えない圧迫を加え、反射で純一の手のひらが固くなり、遠藤が身じろぐ。
佐々木は目の高さの胸元のボタンを外してパジャマの前をくつろげ、形の良い張りのある乳房をさらけ出す。そして遠藤の頭に置いていた手を自分の左胸に掬うように置く。
「慶子に一番を譲るっていう約束があるから我慢もできるけど、本当はすぐにもヤリたい。ヤッて欲しい。愛というよりきっと恋だけどそういうのもちょっとオカシイ」
胸で腕を押し込むように佐々木はにじり寄る。
「ダメっ」
佐々木の後ろに立った滝川が引き戻す。佐々木はバランスを崩し正座になった。
「なになに?」
「ミーちゃん、その膝は私の」
滝川は半泣きだった。
「その膝は私のなの。食器洗いしたら膝枕してくれることになってたの。お風呂はいる前に聞いていたでしょ。洗い物を片付けている間、クチャクチャ聞こえてきたりエッチな匂いがしてヤだったの。でもみんなとの約束だったから、ソレはガマンしたの。でも私も約束したの。だからソレは私のなの!」
大きな声に寝ていた遠藤が目を覚ました。胸の上の純一の腕を軽くタップして、お風呂借りるね、と浴室に消えた。
「ユカリ、おいで」
遠藤のいたのと反対側の腿を叩いて純一は滝川を促す。ちょっとしゃくりあげながら滝川は純一の示した膝枕に腹に顔を向けて頭をおろす。
「ミキ、毛布をあるだけ持ってきて、場所は」
「大丈夫。わかる。シーツと枕もね」
とりあえず宥めて落ち着ける。
ヤレヤレ。
純一の思うところを正直に述べれば、その一言に尽きた。
覚悟していたとはいえ、正解なしの択一を危うく躱したのかどうなのか。却って見事にハマったのかも。
少なくともコレはフワフワポワポワするような展開でも、男はセックスだけしていれば事足りるような展開でもない。
そう理解していたはずだった。だけど、まだ油断していた。そう気がついたのは日が変わり夜半もいい加減過ぎていた頃。純一は寝床に群れなした辺りを思い出してみる。
眠りについた時点で磔刑じみていた。だがそこまでは、油断と感じるほどのコトではない。
今日はナザレのイエスの誕生日で磔刑にあったのは春分の日だろう。そう苦情申し立てたのもまるで無視された。洒落というかじゃれ合いの範疇だと純一は思う。洒落というかじゃれ合いの範疇だったと純一は思う。
佐々木はチャンと痛くないようにしておくからとマットレスを二枚横に並べ、上に毛布とシーツで少し厚みを作り、ダブルベッドサイズにした。確かに痛くはない。嘘はついていない。
滝川と佐々木に腕枕をすることになった辺りを、純一は思い出していた。
「土曜日になったね」滝川がいった。
「ナザレのイエス。お誕生日おめでとう。」
すでに両腕を滝川と佐々木に腕枕に提供して、磔刑に処せられている純一が言った。。
「メシアの誕生だ。すると私が東方の賢者?マギ?」
風呂上りの遠藤が聞こえていたらしく言った。
「東はそっちだ。マギが起きていたら一緒に寝ようって言ってみてくれるかな。導きの天使さん」
佐々木の言葉で、遠藤が寝室に消え、出てくると台所に足を向けた。
理由はすぐに分かった。川上が密かにもってきたシャンパンボトルを寝室から持って現れると、さっき来たばかりのワイングラスにちょっと残っていたチーズとナイフをトレーに乗せて遠藤が持ってきた。
「なんだかイキナリ煮上がってたから、悲しく持って帰るトコだった」
「ゴメンゴメン。なんか楽しすぎて、ヘンになってた」
ボトルを純一に差し出しながらの川上の苦情に佐々木が答えた。
家主の純一がシャンパンのボトルを受け取り開けると空気が少し清浄に戻った。
「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む人はわたしにとどまり、わたしもその人のうちにとどまる」
純一は自分の知っている数少ないキリストの言葉の中で一番好きなモノを口にしながらグラスにシャンパンを注ぐ。
「はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちの内に命はない」
小さくなりすぎて乾いた固いチーズを切りながら、どちらが先に来るべきか知らない言葉を唱える。
と、ナイフがチーズの固いところで流れて左手の指を切った。よく切れるナイフなので、痛みはそれほどだがチーズが少し汚れた。「あー、これは立派なホスティアだ。痛まないうちに食べきらないとだ」
切った指を浮かせて残りも切り分ける。次第に指の血の雫が溜まってきたが、雫が崩れる前に切り終わった。
純一が口に含もうとした指を、スッと佐々木が引き寄せる。
「ミーちゃん。反省してなさそう」
その手を更に川上が留める。
「ヒカリ、わかったよ。ごめんなさい」
佐々木が手を離す。川上が両手で純一の手を唇に導く。
「次は私」
川上が含んでいた指をはなすと、佐々木が手を伸ばそうとした瞬間に滝川が純一の方に手を掛けて引いた。マットレスの分傾いた純一は希望に応えるためとバランスを取るために滝川の方に左手を差し出す。
「ミキちゃんは最後だね」
遠藤の確認の言葉に佐々木は鼻を鳴らして応える。
遠藤は滝川が純一の指を開放すると、皿を指さしながら目を瞑り口を開けて舌を伸ばした。チーズを舌に載せろ、というサインらしい。舌先を手招くように変形させてみせる。
純一がチーズを舌の上に差し出してやると、器用に舌先をくぼませて指先を包みこみ、チーズごと口に銜えた。唇だけでなく歯まで使われて固定され指先のチーズを舐め取られていく。
周囲からは手を使わずに新たな展開をみせた遠藤の機転に感嘆の声が上がった。
佐々木も遠藤を真似て舌を伸ばす。純一は舌の上にチーズを落とした。佐々木はちょっとムッとしてグラスのシャンパンを口に含むと純一の首をたぐり寄せた。
「おとなしく聖体をお受けなさい」
純一は佐々木の鼻を摘む。しばらく佐々木はジタジタしていたが、口の中のものを飲み込んだ。
「いけず」
佐々木が思いのほか可愛かったので、鼻にやっていた指で唇をなぞると、噛み付かれた。
そんな感じの聖体拝領ごっこを楽しんでシャンパンを開けて、全員で寝ることになった。
純一は改めて寝床で磔刑に処された。今度は左腕の佐々木との体の間に遠藤が入り込んで胸の上に頭を載せた。ゆるく結った髪がマフラーのようだった。
部屋の明かりを消してくれた川上が純一の枕を抜き、首の下に腕をさしいれると純一の頭をかかえるようにして寝た。
さすがにしばらく女たちを警戒して寝付けなかったが、意外と疲れているコトを感した途端に眠りに落ちた。
純一は油断していた。
警戒が足りなかった。
状況の理解が不足していた。
だからレイプをさける努力を怠った。
結果として純一はレイプされた。
気がつけば、街がクリスマスになってしばらく経つ。
セールが今週で終わる、という基準からいうと明後日がクリスマスらしい。
だいたいこの時期の畑中純一は実家に帰ってしまうので、クリスマスという印象が街に出ると、帰省のチケットを準備するか、という感覚だったが、今年はそうもいかなかった。
そろそろふたつきになるが、裁判はジリジリと進んでいるのか進んでいないのか。あまり純一の生活には支障がなさそうだった。
結局、年内には純一は二度だけ裁判所に出かけて行って、身分照会を受けたあと、三時間ほどづつ日本語とも思えない言葉のやりとりを水本先生の隣で黙って聞いていただけだった。
水本先生に言わせるとそういうモノらしいのだが、さすがに年明けにはペースが上がるだろうという見通しも立ってきたらしい。
最初の数回は顔見せと資料の受け渡しみたいなモノらしい。勤め人的には、ソロソロ仕事なんかしている場合じゃないよ、という事実上の猶予期間であるということで、ソレまでに弁護士なりを決めるための作業期間であるという水本先生の解説だ。
実際のところ、水本先生は女の子たちの件でほとんど連日通っていて、久しぶりに気合を入れて裁判所に通っている、ということだった。すでに裁判は始まっていて、公式には誰も認めないが、証拠も状況も明らかなときは足繁く通ってみせてプレッシャーを掛けるのが一番安上がりで確実というコトらしい。
「気合と確信のあるところにヒトは説得されるモノだからね。出物が揃っているところでは体を動かした方がいいんだ。
――ああ、そうそう、この間の資料のまとめ、なかなかいい出来だった。特に指示がなくてアレなら、ウチでちょっとしごいてやれば、代書関係はすぐ身につく。
――最近の学生は法律関係の論理性をナメている奴らが多くて、法学部出身の勘とかセンスの悪い奴らが増えているのはどうにかならないのかね。ツボを売るのや女を口説くのと同じ方法で法律も動いていると勘違いしている奴らが多すぎる。理系文系ってのはアレだけど、いっそ理系の学生を引っこ抜いて法律教えた方が早いような気がするよ。
――万が一就職浪人してしまったらウチの事務所来なさい。資格はともかく仕事の仕方は教えてあげられるから」
裁判はまだ始まっていないも同然で、純一にとって面白いことはなにもなく、水本弁護士のテカテカと張りのある頭と、その先生に妙に買われたモノだという印象しかなかった。
どうせ、学生は冬休みなので、裁判所に行くのは純一にとってどうということもなかったが、警察からは事情の確認をおこなうことになるかもしれないから、あまり遠出はしないでくれと言われている。お陰で時間はあるが実家に引き篭る気にもなれず、正月だというのに都会で過ごすことになりそうだった。かと行って遊びに行く先も絞られる。誰もそうは言わないが、事件の構造的にサークルの誰かが絡んでいた可能性は高く、休みに大学に行く気もしない。
とはいえアパートに引き篭るのも純一の性に合わない。気がつけば街を一周りしてみて阿吽魔法探偵事務所でお茶を飲んでいた。大学に通う用がなくなってから、純一はほとんど毎日来ている。
苦学生という程でもない生活を親の仕送りでやっている身としては、遊ぶ金くらいは自分で稼ぐが正解だけれども、今年は大学が楽しかったので純一はあまり遊びもせずバイトもしなかった。その割に乾いた感じがしないのは、喫茶店がわりにしている居心地良いスペースを確保したからだろうと思う。
特に用があるわけでもなく訪れた純一に、夜月はコーヒーを入れてくれたままデスクに戻って一言三言話しただけで居眠りを始めた。夜月の居眠りは最近珍しくもないが、コーヒーを入れてくれて、しかし自分は飲まないで寝ている、っていうのはどうなんだろう。
と純一が思っていると、モソリと夜月が動き受話器をとり、「はい、こちら阿吽魔法探偵事務所です」と言った。チラリと純一を見たような気がする。どうやら駅からこの事務所への道順を説明しているようだ。
と、未登録の電話番号から呼び出しがあった。
「――もしもし、畑中くん?お久しぶり。今電話大丈夫?」
聞き覚えのある声だった。だが思い出せない。
出先だけれど、イイよ。と純一が答えると、
「突然だけど、あさって暇?パーティーやるんだけど来て欲しいんだ」と名乗りもしないで続けられた。
どうやら、親しい人物からの電話らしいが、誰だか全然思い出せない。先方も外らしく雑踏の音がする。場所を聞くと駅の傍の小洒落たレストランで、店自体に興味があったのもあって了解した。
「少し多めに紅茶を入れてください」
来客があるのか珍しく夜月が純一にそんな指示を出した。
事務所の扉がノックされたのは、ティーバックを取り出しているときだった。
扉をあけて挨拶をしたのは、聞き覚えのある若い女の声だった。ひとりひとりの識別はつかないが、挨拶の声で分かった。カップソーサを準備して出て行くと事件の時の子たちが四人が揃ってきていた。一人が挨拶の手に絡げた携帯電話を開いて閉じてみせた。彼女が電話の主らしい。滝沢さんだったか。
四人は裁判所に行った帰りがけだった。全員近場の駅だったので、揃っていた帰りがけにクリスマスパーティーでもしないかという話になったらしい。ここに寄ったのはそのお誘いと、水本先生を紹介したことに対する夜月へのお礼を述べるためだった。たまたま一緒にいた赤木先生も誘ったらしいが、年末で忙しい時期だからということで断られそうだ。山下さんの名前は出なかったが、卒論のピッチを上げるために冬休みも帰省しないで研究室に泊り込みの男だけのクリスマスをすることに決めている彼らは、雪と雨を降らさなければそれだけでサンタを信じる、とまで言い切っていたので、純一も口には出さなかった。女の子たちは事務所のガランとした感じと妙に良い作りのメイプルのデスク、奥のカーテンの間仕切りに興味深々だったが、比較的無難な話題を選んで帰ることを告げた。
夜月は、駅まで送って用がなければ帰っても良い、といって純一を送り出した。
女性のグループに男一人で混ざるのは、よほど気心が知れているか、よほど慣れているかしないとムリだ。名前もろくに認識できないような間柄ではおざなりに付き合うしかない。そんな感じが面白いのか、女の子たちはあからさまに純一を観察している。
「畑中くん、つきあってる彼女いないでしょ」
背の高いショートヘアの娘が脇から尋ねた。
「いません」
「お、ノーコメント、とか言うかと思ってたら正直に答えた」
名前は知らないけど、事件の現場でバールを純一から奪った娘が言った。
そんなので逃げられるような雰囲気でもないから、あっさり答えた。
「欲しくないの?」
ストレートな質問だ。
「欲しいけど、作る時間と方法が思いつかなかった」
バール娘がニヤリと笑った。
「四点お試しセットがあるんだけど、どうかな」
「あー、なんか、読めた。私たちと付き合わないとか言うんだ。なんか化粧品のサンプルみたいだな」
笑っている顔と困っている顔と半々くらいだったのを見て、純一は対応を間違えたことを悟る。
「……ええ、と、流れがつかめないんだけど、結構マジだった?」
「少なくとも私はマジ」
バール娘が言った。
「うひょーハーレムだぁーとか笑って流されるよりはマシだったかな」
室内犬のような髪型の小柄な娘が評した。
「ひょっとして中古は嫌だとか言う宗派のヒト?なら仕方ないけど」
バールの君が少し心配そうに言った。
「あのなぁ、そんな男がフォーシーズンスポーツサークルなんてナンパなサークルに居る訳ないだろ」
「でも、マトモに出てきてないじゃん。夏合宿楽しみにしてたのに」
ボソリと滝沢が言った。
「あのなぁ、滝沢」
「ブブー。滝川紫です」
「やっぱりなぁ。オカシイと思ったのよね。警察で滝沢さんってドコにいるかとか聞かれるし」
「ユカリ、優先権剥奪。ついでに畑中くん減点」
滝沢だと思っていた滝川のフルネームが分かった。彼女が答える前に一気にツッコミが入る。
「仕方ない。自己紹介タイムをここらで改めて設けますか。どうせ、名前も分からないままじゃ付き合うってのもアレだしね」
連絡先の交換というか、女の子たちの名前の勉強会のようなものを駅の中のドーナツ屋でおこなう事になった。
佐々木未来、川上光、滝川紫、遠藤慶子。純一は密かにバールを受け取った順番で純一は覚えた。彼女らは川上を除くと三年生で川上も一回浪人しているから同い年らしい。学部はバラバラだけどサークルが縁で買い物や旅行で何度かいっしょしているとかで、シフトも揃えたらしい。
佐々木は仕切り屋でどこでも一人いると楽なタイプ。細い川上を奥の席に詰めて、その隣に純一を座らせ、滝川で蓋をする。自分は斜め向かいで全員を目の届く位置においた。
川上は滝川が純一を気にしているのを気がついて純一を観察していた時期があるらしい。細く締まった体はなにかスポーツをマトモにやっていたようだ。学部が一緒で、講義もかぶっているモノがあったらしいが、知らなかった。
やたらと複雑な髪型をしている少し小柄な遠藤はなんというか、目のやり場に困るプロポーションの持ち主だった。ソレは全員わかっているらしく、正面に遠藤を置いて少し困った純一を意地悪く観察している。
滝川は名前を正しく覚えていなかったことがよほど気に触ったのか、「わたし、滝川紫は――」という言い方を少し繰り返していた。このメンバーの中では普通であることが却って目立つから、もう覚えた、と思う。もちろん純一にそんな自信はない。
で、しばらくすると、さっきの会話の説明に戻った。
全員が純一を別の件で知っていたらしい。去年までいた女王様とアダ名されていた女子学生が酒に酔ったままスキー場で派手に転んだのを背負っておりてきた。言われてみれば、去年の春スキー合宿のときに見知ったトドの醜態を見かねてそんなこともした。で、サークルの男を一回り喰ったはずの女王様が、酔った自分を背負っておりてきた感心な男性がサークルの男しかも喰ったことがない男、という事実を知りチャンスを狙ったが結局喰い損なった。という本人にしてみれば、えーそんな事言われても、という事件だった。しかもこの話には続いがあって、当時一年生だった女子学生がたまたま帰りに並んで座ることになり、純一が童貞でないことを証言してしまったことで、女王様はそうとうに荒れくるっていたらしい。ということで、純一は幻のヌシのような扱いを受けていた。本人はどうでも良いところで株が上がっていたようだ。
畑中純一が適切な対応を普通に選択できる間の良い独り者で、四人は男薬が欲しいところだった。わざわざ新しい出会いを探すのも今は少し億劫だし、リハビリ替わりに付き合ってくれるとだいぶウレシイ。純一の好みは知らないけれど、四人もいればアタリは含まれているかもしれない。
どうも良く分からないが、男薬とかリハビリとかいうニュアンスを考えると、四人は意外と真剣に自身に不安を感じているような気もする。
「気分はわかるけど、四人というか、二人でもムリでないかなぁ。俺には。あんまり甲斐性ないし」
プッ、と笑われた。ええと、と純一は思い見回してしまう。
「ゴメン。ごめんなさい。からかったわけでなくて、真剣に考えてくれることが予想以上に嬉しくて、つい」
「夜中に突然電話掛けても良いですか」
遠藤の言葉を受けて川上が言った。川上の言葉はあまりに静かで真剣だった。彼女らが求めているモノがなんだか純一にも分かるような気がした。
「本気で四人とって言うなら、SNSとIRCのチャンネルも教えとくよ。電話はもちろん良いけど、寝てたらゴメン」
携帯のメールでキーを送る。
「ちなみに、故郷においてきた彼女とかはホントにいないの」
滝川が心配そうに言った。
「そんなのがいたら、あんなサークルに籍をおいたりしないよ。俺のこと、どういう風にみてたのさ」
「優良物件ってヤツね。良い勘しているわ、ヒカリ」
「恋愛に興味がないというより、メンドくさがりだと思ったから、コッチから押せばいけると思った。畑中くん、ゴメンね。計算高くて」
川上がチョット済まなさそうに言ったのは、たぶん弁解というよりは釘をさすための言葉だったのだと純一は思う。
「よろしくお願いします」
遠藤が胸を邪魔そうに頭を下げた。つられて全員頭を下げる。そんな感じで解散になった。
翌日、夜中に川上から映画を見に行こうと純一は誘われて、映画を見たあとくらいから所在確認メールが届き始め、近くを車で買物していた佐々木が最後に合流して全員集まっていた。駅そばのショッピングアーケードと郊外型のショッピングモールは微妙な対決関係にあって、間にあった商店はスッカリ整理されてしまったが、言うほど悪いことばかりでもなく、学生にとっては緩やかなたまり場だった。川上はモールと大学の間くらいのところに住んでいて、モールが出している巡回バスのコースが近いのでモール派らしい。どうやら佐々木も車で動くことが多いのでモール派らしい。純一はバイクで移動することもあるのでどちらも使うが、バイクだと買い物には不便なのでアーケード利用が自然に多くなる。食品専門店の規模と性質がアーケードとモールの一番の違いか。
滝川と遠藤は恐ろしいことにほとんど外食で済ませてしまうと言っていた。
ソレはどうなのよ、ということで、佐々木先生のお料理教室が急遽、畑中邸で催されることになった。
純一はどういうことかあまり気にしていなかったが、どちらかと言うと純一の趣味素行調査みたいな雰囲気で、台所やらゴミ箱やら風呂場やらトイレやらにチェックが入っていた。お叱りの言葉も幾つかあったが、どうやら概ね合格ということのようで安心した。寝室件勉強部屋は四人とも無言でチェックを入れて評価は下されなかったのが純一には却って不気味だった。いっそタンスやらベット下をチェックされた方がまだマシなくらい四人とも黙って部屋を観察していた。
メインは鳥のひき肉でツクネを作った以外はあまり難しいことはせずに、季節のお野菜を中心に洗う千切る煮る。鍋モノという、あまり料理という気のしない料理を皆でつつくことになった。料理をしない滝川と遠藤も包丁を使えないというほど酷いモノでもなく、単にひとり分を作ったり残ったものを保存できない、というところがネックで料理から遠ざかっていたらしい。一品披露ということで、二人が作ったコンニャクの染み炊きと玉子焼きは普通に美味しいと言える味だった。純一の出した豆腐のトマトソース炊きはホールトマトの缶詰と豆腐をあわせて中華鍋で炊いただけのものだが、なかなかの好評だった。
なりゆきで酒が入ったので、夏掛けやら予備の布団を出して少し強めに暖房を効かせて四人を泊めることにした。風呂の使い方を教えて、入りたくなったら勝手に使ってくれ、と言って純一は寝室に引っ込んだ。
翌朝、卵と牛乳でフレンチトーストを焼いている匂いで目が覚めた。
半分勢いで四人泊めたことを思い出した。付き合っていることになっているから、まぁいいだろう、で泊めたわけだが、女の子を雑魚寝にさせて自分ひとりでベットというのはチコっと気にはなっていた。ソレはソレとしてまぁ要するに、まぁいいだろう。考えてもどうにもならない。
「おはよう」
ダイニングキッチンに遠藤以外の三人の姿を見つけ、シャワーの音がするということは洗面所は使えるらしい。脱ぎ散らされた服と下着を横目に声を掛けて歯を磨く。磨りガラスの向こうで慌てたような声が挨拶を返してきたが、すでに歯ブラシを突っ込んでいる口では返事できない。お椀のようなブラジャーのカップはちょっとしたインパクトだったけど、世の中にはそういうモノもあるという程度のこと。その場は無視したが朝食を終えて、四人がそれぞれ着替えなどのために解散したとき、純一のテンションは急降下した。大変そうだという想像と理解がいきなり降ってきた。
妙に慣れない空気が残っている気がして換気扇を回したまま、部屋を出る。しばらくうろうろして結局、阿吽魔法探偵事務所に足を向けてしまった。ここのところのパターンと化した、デスクチェアーにもたれかかりキャビネットをフットレストにした夜月の居眠り姿を無視して、ヤカンを火にかけカーテンの奥からアフリカ特集の写真雑誌を引っ張り出し眺めながらキッチンに向かう。キッチンのトースターの脇には衛星軌道の宇宙写真特集号と大型ネコ科特集号が読みさしになっていた。いつの間にかスプレー行為をしていたらしいことに気がつき、お茶とまとめてソファーに持っていく。居眠りをしている夜月のデスクに紅茶を一注しして、雑誌を眺めているとしばらくして夜月がモソモソと動き出した。
「なんか機嫌悪そうですね」
頭をカキカキ夜月が言った。
「――酒臭くて女くさい割にはナニもなかった感じが原因ですか」
ヒドく無神経な批評が純一に突き刺さる。
「……結論だけ言われると、まぁそうですけど」
雑誌を眺めながらそう言うのが精一杯。
「いいですねぇ。健全な青春の悩みな感じがします。やることやるまでの距離を獲得するまでが男にとっての恋愛の楽しさで、そこから先は単なるスポーツ競技みたいなモノですから。――はぁふぅらやましひ」
ウラヤマシイを欠伸とともに吐かれるとここまでひどくムカつくものであるか、と頭を掻きかきカーテンの奥に消えた夜月を純一は睨みつける。苦情を嗤い却下するようにシャワー音が聞こえた。クリスマスナンバーの暢気な鼻歌が漏れてくるのがまたムカつく。
夜月がカーテンの向うから出てきた時にはダークスーツになっていた。赤と緑のストライプのネクタイはたぶんクリスマスを意識したものなのだろう。
そこにデスクの電話が鳴った。大仰に溜息をつき、ツーコールで電話に出る夜月。
「はい。こちら――。あーうん。ハイハイ。そうですが。はい営業しております。ハイハイ。それではお待ちしております」
妙に丁寧に電話を切ると、デスクの引き出しから鏡を取り出してネクタイを少し直す。
「畑中くん、ドタキャンであいすみませんが、これからちょっとメンドくさいお客様が来るようです。お嬢さん方には申し訳ありませんが欠席するとお伝え下さい。会費は少ないですが、コレでキャンセル料ということでお願いいたします」
夜月は鏡と一緒に取り出していた茶封筒を純一に差し出す。中を覗くと五万円入っていた。ビックリする純一に背を向けて肩を回す夜月は妙な気合に満ちている。
「お客様と鉢合わせすると面倒くさいので、今日明日は来ないでください。で、できるだけ早く出かけてくださるとお客様と鉢合わせしないですむので安心です。時間中途半端ですけど、駅前の喫茶店ででも時間潰してください。すみません」
夜月はどうやら余程お客に逢わせたくないらしい。
言われた通りにビルを出て信号待ちをしている時に、読みかけの雑誌を借りてこようと思いついた。
クルリと方向転換して事務所に戻ると呆れたような悲しい顔をした夜月と戸口で対面した。
「なんですか?」
「雑誌を借りようと思って」
夜月は応接セットを一瞥し机の上の雑誌をまとめて自分で取って純一に押し付けた。
「コレですね。あーうん。マズイな。仕方ない。階段で五階まで登ってからエレベータで降りてください。で、出口から出たら左に進んで少なくとも信号二つ真っすぐ行ってください。コレは重要。絶対ちゃんと守ってください。いいですね。絶対ですよ」
夜月はそう言うと純一を押し出し、階段を指し扉を閉めた。純一は狐につままれたような感じがしたが、夜月の様子から言うことをきいておくことにした。
階段で五階まで登ると専門図書翻訳会社と、ビデオ個室がある。エレベーターは上に向かっていた。下の呼び出しを押す。
エレベータが三階で停った。
五階についたときゴンドラには誰も乗っていなかった。
下りの三階は素通り。
一階に着いたとき、あからさまに暴力的な男が二人、こちらを見た。階段の前にももう一人いたので三人か。
男たちは小脇にまとめて抱えた雑誌に眼をやると一人が鼻で笑った。ちょっとムッとしたが、関わりになりたいわけではないので、ビルを出る。黒塗りのセダン。なんだか分からないが、状況的にはソレで十分なので、左に折れて直進。振り向くのはヤバそうだったので路々の窓や鏡で車の様子を見ていると、車から一人降りてこちらを追っている様子。
走った方がいいのか、いけないのか。走ると後ろの様子をみる余裕はなくなる。
男はまだ走っていない。意図があって追っているというほどハッキリしていない、のだと思う。
一つ目の信号は青だった。信号変われ、と念じたのは白バイに追われたとき以来だ。右側をミニパトが通過していく。当然のように純一は無視されている。少しは空気読んで役に立てよ、と純一はそんな理不尽な考えに自分で嗤った。
そういうときは不思議に信号は変ったことがない気がする。男は自動車も点滅信号も無視してまっすぐ来る。
二つ目の信号は赤だった。変わらないのは分かっている気がするが、それでも純一は、こんどこそ信号よ変われ変われと念じて立ち止まっていた。これだけ念じているのにオマエは変われないのか。
後ろから来る男の姿はアチコチに見えているが、どれも近づいているのは間違いない。途中で自販機も公衆電話もコンビニもいくつか通過しているから、ちょっとお使いというワケでないのは分かっている。だが、森永のホワイトチョコレートソーダなら駅地下で見かけたからそっちにいってくれ。
と、男の歩みが急に遅くなった。まさかホワイトチョコレートソーダが欲しかったのではあるまい。
後ろで自転車のブレーキ音がして、つい反射で振り向いてしまった。目の前に自転車に乗った警官。ぶつかったかと思ったらしく、ゴメン、と警官は言った。もう一台、信号を渡ってきた。
お巡りさん二人は奇遇を感じたのか、挨拶をして信号待ちで雑談を始めた。明らかに男は狼狽した動きをみせる。
信号が青くなったら走るべきかどうするべきか、純一は悩んでいた。男との間合いを考えると、警官の自転車が見えているギリギリまでは走らない方がいい、と思っていた。だが、ソレはその間に男が追いかけるのに飽きて走ってきたときにはマージンがなくなることも意味している。追ってきている男の仕事は、顔を確認して因縁をつけて時間を稼ぎ、応援を呼ぶこと。多分殴られ上手な男だろうと思う。車で待機している連中がいることを考えれば、事務所の一階を張っていた連中を考えれば、車は三台以上いることになる。車が動いたら数十秒で囲まれる。捕まるならせめてどこかの建物内にして欲しい。
信号が青くなった。二台の自転車が力強く漕ぎ出された。
「市民会館はどう行けばいいですか」
老人の声がした。
自転車の警官は気勢を削がれて苦笑していたが、純一は内心で拳を握った。二人の警官は肩を竦めると一人が申し送りをして老人に道の説明をはじめ、もう一人が先行することにした。
先行した警官が純一を追い抜いて曲がった道を、純一が追って曲がったとき、追跡していた男はかなりの本気で走っていた。だが壁に映った顔が識別できるとしたら、ソレはヤクザをやっているような人間の視力とは言えない距離だった。
角を曲がった途端、純一は走り出し、手近なビルに飛び込むとエレベータを呼び出し、幾つかのフロアのスイッチを押すと裏口から出た。念のため、銀行の入っているビルを一つ通過して尾行を確認した。マいたらしい。
タクシーを拾って駅の反対側に降ろしてもらって、駅地下の紅茶専門店でプレゼント包装の紅茶セットと薔薇の花を模したクッキーを四つづつ買うと、紙袋に雑誌をしまい喫茶コーナーで心底グッタリした。
――斎さん、ソレはメンドくさいお客様でした。
なんだか分からないが、警察でないならヤクザくらいしか候補のなさそうな動きはナンナンダと聞くのもうんざり。純一はそんな気分だった。
そんな感じで、夕食会にご招待いただいたときには、純一は疲労と緊張でスゴいことになっていた。
コレ以上ないダメなローテンションに欠席も少し考えた純一が嫌々ながらレストランをくぐったのは数分前。
ダークブラウンのバギーパンツとフリースのタートルネックにモスグリーンのハーフコートは、純一には似合っており、ノータイで許されるところならどこでも問題ないファッションだったが、お嬢様方の気合の入り方は謝恩会か披露宴かという勢いだった。あまりの衝撃にテンションがたたき落とされ急上昇したのを、感じざるを得なかった。女が着飾っているのを観るのは男としては幸せなんだろうと思う。いや、間違いない。疲労と幸福感でいい感じに頭が麻痺しているのを純一は楽しんでいた。
「会が始まる前に良いお知らせと悪いお知らせがあります。
悪いお知らせは斎さんがお仕事でお客様を迎えているということです。
良いお知らせは斎さんから皆さんへのささやかなお詫びとプレゼントして、幾分多めのキャンセル料を畑中純一さんにおあずけくださったということです。たぶん私たちの分の支払いは純一くんが旦那の甲斐性をみせてくれるでしょう。
今年は色々ありましたが、まだ僅かに残っています。残りを楽しみ、来年はさらに楽しみましょう。では私たちの旦那様予定者、畑中純一さんに乾杯をお願いいたします」
「メリークリスマス」
純一には本気だかどうだかよく分からない佐々木の幹事挨拶を受けて、夕食会は始まった。
純一はヒドくいい気分だった。酒も入っていたしで、ついうっかりみんなに訊いてしまった。
「確認しておきたいんだけど、君たちの求める付き合っている彼氏の機能って何?」
「男友達」
「セフレ」
「セフレの線はいいや。俺あんまりソッチのこと良くわかんないし、食事時にする話でもない気がする。必要になったら相談しよう。男友達って何すれば良いの」
「サイフ」
「アシ」
「別荘」
「ボディーガード」
「旅行の連れ」
「相談相手」
「苦情窓口」
「スパム先」
「ガイド」
「コック」
「家庭教師」
「執事」
「掃除屋さん」
「運転代行」
「修理屋さん」
「電気屋さん」
「荷物持ち」
「飼い主」
「ペット」
「湯たんぽ」
「布団」
「抱き枕」
「お父さん」
「お兄ちゃん」
「弟」
「おもちゃ」
「褒めて」
「撫でて」
「チューして」
「ハグして」
「抱っこさせて」
「舐めたい」
「噛み付かせて」
「腕枕して」
「膝枕させて」
「日向ぼっこしよう」
「腕組もう」
「手を繋ぐ」
四人もいるとすごい勢いで出てくる。
「なんだか、二十四時間営業では追いつかないような気がしますが、皆さんいかがお考えでしょう」
なんだか白い目の集中砲火を食らう。
「敗北主義的発言ね」
「悲観的っていうか全然前提が間違っているわね」
「真面目に言ってるのかどうなのかもアヤシイわね」
「意外と手間のかかるダメな子なのかしら」
純一は両手を上げて発言を撤回する。
「サイフはかなり薄いけれど他は全部できます。だけど脊髄反射でできるほど馴染んでいないから、ポーリングは安定してできないよ」
「脊髄反射でできるのは一流ホストかラブラブ新婚さんだけです。だけど、純一くんにはそこを目指して欲しいと思います」
遠藤が笑って口にしたが目は結構真剣だった。
「サイフは、全部出せと言っているわけでなく、ちょっと調整してくれるだけでいい」
「自分が使うのより少し多めに準備してくれればいいの。使うか使わないかとかでなくてね。苦しいようなら後で返すし」
川上が言ったのを滝川が補足した。
「まぁ甲斐性の働かせどころなんぞは観察と想像で見極めないと、いくらあっても追いつかないというのは時間や金と一緒だ。力はあるがダメな男を良い旦那にするのは女の甲斐性よね。ヒカリの意見によると、優良ダメ男物件としてはかなり有望だという。私もソレには賛成。少し鍛えればいい感じになる」
佐々木が真面目に言っているらしいことは疑う必要がなかった。その佐々木がアイコンタクトを飛ばした。
「あーん」
遠藤がローストチキンをフォークに刺して口元に突き出す。純一はギョッとしたが、求められているところは理解したので素直に口にした。
「ウレシイ?」
遠藤が訊いた。
「とても恥ずかしいがウレシイ」
咀嚼する時間だけ考えて純一はそう言った。
「ギコチナイけどこんなもんじゃない?」
滝川が反対側で言った。
「私は結構満足かも初々しい感じがカワイイ」
「ふーん。じゃぁ、私もアーン」
遠藤の言葉に羨ましくなったのか、滝川もフォークを差し出した。仕方ないのでパクっと銜える。
「美味しい?」
その様子を見ていた他のテーブルから笑いが漏れているのが純一の目に入った。
「笑われているのがすごく恥ずかしい」
「だめだなぁ。君は私たちの男なんだから他のテーブルなんて気にする必要はないのだよ。ご主人様」
佐々木が笑って言った。
「じゃあ、私も、アーン」
テーブルの向こう側から川上が参戦してきた。
「どう?」
「美味しい。今度はウチでやろう」
ザッっと女の子の目が集まった。
「……ウン」
川上が少しためらってうなづいた。
「オー訓練の成果が早くも」
「ミキちゃんもやってみないの?」
遠藤の言葉に、すでに皿の上を片付けてしまっていた佐々木は川上が皿を寄せた鶏肉を断り、バケットを小さくちぎり皿にまだたくさん残っていたソースを指が汚れるのも構わずたっぷりつけて、身を乗り出して差し出した。
「アーン」
斜向かいの位置なので、純一も身を乗り出す事になるが、微妙に届かない。純一がパンだけを銜えようとした瞬間ほんの僅か指が伸び、佐々木の指が口に飛び込んだ。純一は歯に当たった爪の感触に慌ててパンを銜えて身を引いた。
「美味しい?」
見守っていた全員が見ている中で、佐々木は指にまだ残っているソースを舐めとりながら言った。
「あー結構なお点前で」
爪の先でひっかかれた口の中を舐めながら純一は答えた。
「ミキちゃん、ソレはずるい」
佐々木は滝川の糾弾を平然と受け、あらかた舐めとった指を気を利かせたウェイターの持ってきたフィンガーボールですすぐ。
「もう私の皿の肉がなかったんだから、しょうがないじゃないか」
「食べ物であんまり遊ぶなよ。それに俺は次の皿が欲しい」
ムキになって怒ってまでやることじゃないので、純一は口を挟んだ。
「ソレと佐々木、爪で口の中切った。痛いよ」
「あ、ごめんなさい。唇の裏に当たっちゃってたか。お詫びに下の名前で呼ぶことを許可します。ミキと呼び捨てでいいわよ」
「それはありがとう」
「ミキ」
少し怪訝な顔をする純一に佐々木がくりかえす。
「リピータフタミー、ミキ」
「ミキ」
「次のセンテンスに進みましょう。愛しているよ、ミキ」
コースの配膳がデザートがブュッシュ・ド・ノエルに変わるのも無視して佐々木は言った。
「リピータフタミー、愛しているよ、ミキ」
まるで英会話の教材かナニかのような言葉。しかしその目は笑っていない。
「愛しているよ、ミキ」
気休めにしても本気にしても求められている役割がハッキリしているからか、純一は本気で素直に口に出した。
「うれしいわ、純一さん。私も愛している」
仮りそめでも何でも、そう言われるのはうれしい。佐々木の目が潤んでいるような気も少しした。すでにワインも四本目になっているので、酔っているのは間違いない。そういう理由かもしれないが、そこはまぁいい。すでに純一の幸福感のカウンターは振りきれていた。
勢いのまま、純一は川上に向き直る。
「ヒカリ」
「は、ハい」
「愛しているよ、ヒカリ」
「あ、ありがとう。純一さん」
ツッコミの厳しい川上が意外にもナニも言わずに、ケーキに向かって逃げるようにフォークを進めた。
なんだか分からないが、楽しい。理由は感じているのだが、ソレがこんなにも嬉しいモノだとは思わなかった。
「名前を間違えていて済まなかった。滝川さん。できれば許して欲しい。ユカリ」
「うん。あんまり話してなかったし。しょうがないもの」
「愛しているよ。ユカリ」
「ウレシイ。今度はちゃんと全部覚えていてくれたのね」
「君が結婚するまで忘れません。タキガワユカリさん」
「結婚しても名前は変わらないから覚えてて。純一さん」
「もちろんだよ。ユカリ」
名前を繰り返す度に目が潤んできた滝川は純一の腕の中に顔をうずめた。鼻をグシグシやっている。ナプキンが固くて、上手くいかないらしい。ポケットから和手ぬぐいを引っ張り出して純一は滝川に渡す。
滝川が落ち着いたところで、すでにデザートを終えていた遠藤に向き直った。
「ケイコ」
「なんですか、純一さん」
「愛しているよ、ケイコ」
「私も愛しています。純一さん」
遠藤は純一の両手を包みこむと、鼻先にこすりつけ指先を舐め口づけした。振り払わなくても自由に動く指先で口元や鼻先を軽くなぞったり叩いたりしていると嬉しそうな顔をする。
「ケーちゃん、純一くんはまだケーキ食べてないよ」
佐々木の声に抱え込んでいた手に甘噛みすると、遠藤はようやく開放した。
「順番最後で良かった。スッカリ堪能しちゃった。ありがとう。純一さん」
「これも彼氏の役割だろ、ケイコ。名前を呼び捨てにするよりは気分的に楽だからいいさ」
「そんな風に割り切られると悲しいけど、私にはとても大事なことなの。――嫉妬した?ミーちゃん」
「うん。結構キタ。でも、愛しているから大丈夫」
佐々木は素で返した。
「ケーキ美味しい。チョコクリームがふわふわでベタベタもたもたしてなくて、ケーキと丁度いい甘さ」
「多分、砂糖の代わりに水飴とキャラメルを使って、炭酸ガスでホイップしているの」
川上が説明を入れた。
「へーそんな機械があるんだ」
「泡だて器を電気じゃなくて、ボンベの炭酸ガスの圧力で回転させながら吹き込んでふんわり仕上げるの。便利だけど、ソーダマシン用の使い捨てボンベで差し替え利かないから毎日使うつもりか業務用でないとちょっと買いにくい道具」
「でもみんなで大きいところに引っ越すなら買ってもいいかも。玉子焼きとか楽そうだし、他にも使えるんでしょ」
滝川が思いついたように言った。
「引越し?大きいところって?」
「みんなでルームシェアしようかって話があるの」
聞きとがめた純一に遠藤が説明をする。
「裁判することになったでしょ。全員親元離れて一人だから、嫌がらせとかあると一人だとさすがに不安だし、危ないし」
遠藤がコーヒーのお代りを受けながら言った。
「嫌がらせ?」ってのは初耳だ。
「なんか偉い人の息子だかなんだかが混じっているらしくって、赤木先生ができれば、家や人の少ない学校の傍よりは街中に引っ越した方が安全なんだけどって。実際に街頭とか少ないトコもあるからちょっと怖いところもあるし。ウチに赤木先生が来たときにそんな話が出たの」
遠藤の家がどこだか分からないが、モールと学校の間という辺りは確かにあまり人が多く歩くような道ではない。
「一応訊いておくけど、ソレで俺を四人の彼氏ということにしようとしたとか?」
怒っているというよりは、なりゆきの確認が必要だろうという気分だったのだが、女の子たちは明らかに危惧するところが多かったようだ。佐々木さえ一瞬ひるんだ。
「違う。そこは大丈夫。――」
川上が力強く保証した。
「――事件のあと、私たちは四人で会うことが多くなっていた。自然に助けてくれた人の話になってたの。去年とかは合宿にも来てたけど今年は全然だねって話になって、でも彼女いないみたいって話になって、勿体無いよねって。良い人なのに気がつかれないのはもったいないし、誰かに取られちゃうくらいなら欲しいし、って話になって。でも向こうにも好みがあるだろうし、あっさり振られるかも、でも順番が回ってこないうちに誰かがくっついたらムカつくし、って話で。じゃぁミンナで付き合ってみてダメならダメってことで、クリスマスで彼女いないなら捕まるだろうし誘ってみた。だから彼氏になって欲しいという話と、ルームシェアとかボディーガードとかの話は全然関係ない。ミンナ純粋に畑中純一を欲しいと思った。だけ」
「ルームシェアとかの話は、ちょっと前に向こうの弁護士らしい人から手紙が来ててさ。要するに向こうの弁護を引き受けますって内容らしいんだけど、水本先生に連絡したら赤木先生が飛んできてくれたの。全員の家を回って危ないところ色々指摘して、できれば引越しって話になってさ。水本先生が幾つか不動産屋さんをあたって大きめの部屋を調べてくれて、四人の家賃や光熱費を合計したら結構大きめのマンションを割安で借りられることが分かったの」
滝川の説明を聞くと、結構本気らしい。
「私は帰らずこっちで就職することにしているし、月々少し安いくらいの支払いで新築マンションも買えることが分かったから、卒業後もこの関係を続けるならマンション買っちゃうかと、私は思っている。もちろん離婚ってか破談が決まった段階で、転売して売却益を分割するつもり。ちなみに、借りる予定の部屋はどれも風呂トイレ台所を除いて六部屋以上あるから、君がいつ泊まっても大丈夫だし、専用のプレイルームが欲しいといいだしても大丈夫」
「でもあっさり振られるかもしれないし、コッチがあっさり見限るかもしれないから、引越しとルームシェアの話はジュンジュン抜きで進める。あと、プレイルームより大きなお風呂場が欲しい。ユニットバスはイヤ」
プレイルームとかサラッと流した佐々木よりも、受けた川上の言葉に驚く。
「ジュンジュン?」
「ジュンジュンか。ジュンチーとかでくるかと思ったが、どう思う、ケーちゃん、ユカリン。ピカリンの提案は」
「意外とそういうの好きね。ミーちゃん」
「この歳でもこういう呼び名が自然に使える関係は結構面白い。まぁ、初対面で言われたら間違いなく殺すが」
「ところで、ミーちゃん」
「なぁに、純一さん、愛しているわ」
ジュンジュンなりなんなりで返ってくるかと思ったら、ちょっと重い。
「俺も愛しているよ。って、ミーちゃんって言うなってこと?」
「なんか私の愛を疑われたような気がしたから、必死で弁解しているの」
デザートも終わり、空いた机の上で腕を仰ぎ芝居がかってみせる佐々木。
「疑ったというよりは、なにが起こっているのかという興味だな。愛あればこその無邪気な質問だよ、ハニー」
純一は付きあうことにした。
「良かった、ウレシイわ。愛しているのは間違いないもの。ソレでところで、なにが聞きたかったの?ダーリン」
「愛する素敵な皆さんに心ばかりのプレゼントなぞ用意してきたんだが、このタイミングでお渡ししても良いだろうか」
「もちろんよ、ダーリン。でもところで、この後お家におじゃまして良かったら皆で伺おうかと思っているのだけど、よろしくて?」
「あ、ひょっとして、ウチ帰って渡した方が良い?」
一瞬にして素に帰ってしまった純一を四人は笑った。
「そしたら一旦お開きにしましょう」
パラパラと女の子が席を立つタイミングでチェックを頼み、支払った。夜月に預かった金額に純一の会費予算を足して数百円余る。という絶妙な金額だった。
「良い夜を」そんな声に送り出され、連れ立って街を歩く。
すぐに左右を遠藤と川上とに挟まれる。しばらく滝川はうろうろと三人の周りを廻っていたが、純一を少しかがませると後ろに飛びついた。
「悪いがさすがにもう無理だ」
純一は佐々木に笑ってみせる。
「そうでもないわ」
そういうと佐々木は川上の腰に伸ばしていた純一の右手に左手の指を絡める。
「ほらね。このくらい軽い軽い」
佐々木は元気よく引っ張り出した。
佐々木の車のトランクから荷物を下ろす間も四人は純一にぶら下がり続け、酔っ払ったんだか疲れたんだか分からない状態で純一のマンションに帰ってきた。駐車場からマンションまで五人ともなんだかよく分からないが大笑いをしていた。一階のロビーを抜けエレベーターを待つ間こそ、笑いをこらえていたが、エレベーターに乗った途端にまた笑い転げた。
着飾ったままの姿で荷物を抱えて、しかも純一に張り付いている姿を近所の親子連れに発見され子どもがお父さんに、あれやって―、と言い出し、ノリの良いお父さんがお母さんと子供を抱えてクルクル回りだしたことがキッカケだった。
体力のありそうな、実際に高校国体に水泳で県代表になったこともある川上が先頭になって両手の指を純一と絡げてそこに佐々木と滝川を内向きに座らせて、背中に遠藤をぶら下げてナニかの祭りのダシのような格好で歩いていた。佐々木と滝川が荷物をまとめて持っているが結構大きい。だんだん、ヒールが辛くなってきたという川上をかばうため、最後の一区間は二人を肩に乗せて両腕を踏ん張るような姿勢で川上の肩に手を回して歩いていた。カップルがコッチを指さしたのを純一も見た。落ちる―と言う頭の後ろの嬉しそうな遠藤の悲鳴は全員の笑いを誘い。駐車場からの百メートルあまりの道のりをひとかたまり大笑いしながら純一は歩いた。
「そうは見えないけどすっごい体力よね」
「やらせといてナニ言ってるんだか」
自分だけぶら下がっていない。と不満を述べた川上をエレベータの中でお姫様抱っこにして、じゃぁ私が後ろと佐々木が張り付き。もう疲れたから良いや。と遠藤と滝川がおざなりに腕を絡め、身を寄せた。なんだよ、全然終わらないのか。でまた笑った。
右側にぶら下がった滝川にズボンのポケットから鍵を探らせて、玄関に入ったところでようやく両手が自由に動くようになったので、川上を抱えたままヒールを脱がして下ろしてやった。靴擦れでストッキングが破けていた。
「ソレはなんだか素敵なサービス」遠藤が羨ましそうに言って写真をとった。私たちもやれ―と言う声に答えてあまり広くもないマンションの玄関で、お姫様抱っこでヒールを脱がして記念に写真撮影までするというサービスをおこなった純一はかなりの疲労困憊で、リビングに帰ってきた。
寝室を女の子の着替えに提供すると、ヤカンにお湯を沸かし、紅茶の準備をする。ラジオをクリスマスしか合わせないFENにするとクリスマスナンバーが流れ出した。リビングでうつ伏せになって伸びをした。薄物のワンピースなのか寝間着なのか判断に困るモノを着た遠藤が最初に出てきた。
「お疲れ」そう言って、とすんと純一の背の上に座る。
「ハッピーメリークリスマス」
「あー、ハッピーメリークリスマス」
遠藤はクリスマスソングの鼻歌に合わせて肩を揺すっているらしく、背に載っている尻の重心が変わる。純一はひらめいた。
「ケイコちゃん。お願いがあるんだけど」
「なぁに、純一さん」
「俺の肩胛骨の間に膝をついて正座してくれる?」
「マッサージ?」
「そそ」
背中の上で鼻歌歌いながら、もぞもぞしている遠藤をおいて三人が出てこない。
ヤカンが湯の沸いた音を出す。
「ケイコちゃん、ヤカン止めて、ポットの脇にあるティーバッグ全部入れて、お湯入れてすぐにタイマー回してくれるかな」
遠藤は鼻歌を歌ったまま、肩の筋肉をなぞっていた手を伏せたままの鎖骨に進める。
「ケーちゃん?聞こえてますか」
純一がひねって向けた顔に遠藤は鼻歌のまま口を近づけた。
「私とセックスしたくない?」
冗談ではなさそうな探るような目で遠藤がいった。
「いま?紅茶入れてプレゼント交換した後ならいいよ。でも他の三人を追い返すのはヤダな。ミキちゃん酒入っているし、飲酒検問ありそうだしね」
「そんなコト言う口は――」チュプっという音とともに遠藤が純一の上唇に吸い付いた。
唇が吸い込まれた隙間に遠藤の舌が入り込む。
純一は唇を吸われたまま、上半身を入れ替え起こす。遠藤は振り落とさるのかと慌てたが純一の腕が腰と膝を抱えているのを知り、より積極的に唇を重ね舌を差し入れる。あまり重くない遠藤の体とはいえ、普段と違う息苦しさに開いたり閉じたりする純一の唇を探検するように遠藤は舌を進める。ヤカンの音を気にしながら純一はバランスと下半身の力で膝を起こし立ち上がる。遠藤の膝を割り、腰骨にひっかけて、唇と舌をからませたまま沸き立つヤカンからポットに湯を注ぎ、ポットからカップに注ぎ、ポットに茶葉をいれ改めて湯を注ぎタイマーを回す。ナニをやっているのか大体のところを察した遠藤はイタズラを明らかに楽しんでいる表情で豊かな胸を擦りつけ蠢かせつつ、困った顔の純一を観察しながら長い長いキスを楽しんでいた。
タイマーが鳴ったところで純一が遠藤を支えていた腕を離すと、ズルズルと木登りに失敗した猫のように唇から離れていく。
「はい、時間切れです」
首に手を回したままムッツリしている遠藤に、茶葉を取り出しながら純一は言った。温めていたカップとポットをトレーに載せて、遠藤を無視してリビングに向かった。
途中寝室をガラリと開ける。部屋着に着替えた三人が気まずそうに立っていた。
「今のはどういう意味かどなたかの解説を希望しますが、まずはお茶にしよう」
ラジオは厚木は晴天快晴でホワイトクリスマスにはならなかったけど、サンタを探すには絶好の日和なので空を見張って探してみようぜ、とかそんな感じのMCが入っていた。話題は米軍のサンタクロース関連体制のバカ話らしい。
「純一くんとセックスしたかったのは本当なの。別にからかう意味があったわけでもないし、反応を覗くとかそんな感じの話でもないの。強いていえば本当にヒドく発情したというだけ」
この二日で十分ヒドく驚いて、この上なんの冗談かと思っただけで特に今更怒ったわけでもない。濡れた猫のような有様になってしまった遠藤に逆に同情してしまって純一は一生懸命に言葉を探した。
「しょうがない。コッチおいで」
ちょっと離れて座っていた遠藤を膝を叩いて招き、あぐらに肩を沈めさせて膝枕をしてやる。
「たいしたモノでもないけど、プレゼントは配っておきたかったから……俺の紙袋ってどこだっけ」
「まっててー」
川上が立ち上がって戻ってきたときには紙袋は一つではなかった。雑誌が入ったままの紙袋を純一に差し出し残りをそれぞれ配る。
「さて、それでは彼女不在期間二十周年記念にして、なんと四人も彼女ができることになった華やかなクリスマスを記念して、可愛い美人の俺の彼女のみなさんにささやかなプレゼントをたっぷりの愛、カッコ計量不能カッコ閉じ、とともに差し上げたいと思います。ビスケットは結構薄くてもろいから壊れる前に食べた方がいいよ」
堅焼きにしたクレープ生地の焼き菓子をジャムと飴のスプレーで支えた白とオレンジのバラは、空気の乾いている冬場の季節物で小さく軽いくせに、一緒に買った紅茶セットより高い。
クリスマスのナンバーが少し遅れてラジオから聞こえてきた。
「食品成分表には規格がないから成分表示には書いてないけど、畑中純一の愛ってのが含まれてるから湿気ってガッカリしないうちに早めに食べてね」
「彼女不在期間満了を記念して、純一さんにはペアのマグカップをお送りします。愛人の皆さんにはです」
滝川がそう言う。取り出してみると黒字と白地の入れ替わっただまし絵のペアカップの片一方は他の三人と同じ柄だった。
「ほほう。愛人の私たちは揃い柄か。そうかー、純一の愛人専用カップか。噂の愛人の滝沢用を用意するとはなかなかの心がけだ。私たちはココにおいていけばいいのも気が利いている。かわいそうにユカリンの分はなさそうだが」
「アレがあたしのよ!」
「でもアレはジュンジュンへのプレゼントでしょ」
「わざわざ愛人とか言わなきゃいいのに。これがユカリンの分なんだね。分かったから、あとで皆の分洗って棚に入れておいて」
川上がつっこんだところで、純一は話を切ることにする。
「私はピクニックバスケット。ココの家、まえ来たとき揃いの食器とか全然なかったから、ウチでも全然使っていないヤツを持ってきた。六人用だから噂の滝沢さんが現れても大丈夫よ」
「これか。目の前で邪魔くさかったヤツは」
「落として割れたらどうしようかと思ってた。でもこれで最低限食器は揃ったでしょ。コレはご主人様への貢物で、女の子用には伸びる手袋の手首が長いヤツ色違いの二枚セット。寝るときにしておくと冷えなくて結構いい」
川上が袋の名前を確認しながら、一つづつ配り始めた。
「私はお箸。と箸袋。私のはコレ。螺鈿で魚の細工が入っている。皆柄違いだから自分の覚えておいて」
純一のは梨地になっていた。箸袋は大根とカブとナスにキュウリの染め抜き。
純一の膝の脇でうずくまっていた遠藤がモソリと起き上がった。
「私はバイト先で前のキャンペーンの残りでドンブリ大小でたくさん貰ってきた。あとレンゲ。みんな用にはおザブね」
ドンブリ大小といってもいかにもオマケ商品らしく全体に小さく大きな小鉢くらいの大きさの飯丼と、ラーメン屋でコレが出てきたら怒るだろうなと言うような大きさの大きめの茶碗だった。だが、電子レンジで使えます、の文字はとても心強い。
紙袋から食器を取出し包装をたたんで紙袋に戻すと、遠藤は再び純一の膝の上に頭を載せる。
「みんな食器ってなんだかなぁ。こないだの晩ご飯が余程ショックだったと見える」
「食器が少なくてステンのボールを鍋の鉢にするのまでは仕方ないとして、パイレックスのタンブラーグラスまで出てくるようだと少しね。でも、コレなら明日はお米のご飯炊けるじゃないか」
「三合炊きだけど足りるかな」
「足りなかったら電子レンジで芋ふかしてもいいし。一昨日の残ってるでしょ」
「愛人じゃない滝川紫さん、てつだって」
川上が立ち上がって、そこらに開陳された食器類を集めだした。
「なにを」
「洗って片付けるの。食器を」
「ピカリン、ユカリン頼む。洗っといて」
「頼まれました。ジュンジュン」
純一が言うと、川上が立ち上がってぴしっと敬礼してみせる。
「ユカリンわかったよ。あとでジュンジュンの膝貸して。見てたらなんか羨ましくなってきた」
立ち上がった川上の持っているお盆に食器を少し足して立ち上がる滝川。
二人が立ち上がったのを見ながら遠藤は純一の指を音を立ててしゃぶっていた。
「ミキ、風呂、先に使っていいよ。洗うものあるなら洗濯機も使っていいし」
「そしたらお先にそうします。――おーい、ピカリン、ユカリン洗濯物出して。洗っちゃう」
「ケー、洗い物、はいいか」
「ある」
遠藤はモソモソと丸まるとスカートの下からブラジャーとパンツを取り出して佐々木に渡した。さすがに佐々木も苦笑する。
「立ってる?」
佐々木はどちらということなく訊いた。
「ヤナ会話だな、おい。少し恥じらえ」
「発情した雌にとって気に入った雄の生殖能力は最重要事項よ」
「私たちのために避妊はして欲しいな」
臆面も無く言った遠藤に苦笑しながら佐々木が注文をつけた。
「出来婚しなくても認知してくれれば産んぢゃうよ?」
「まぁ、私もそのつもり。旦那様が心配そうな顔しているから責任とってくださるようだし、大丈夫かな。――じゃぁ、ごゆっくり」
ごゆっくり、と言う方が反対な気がする。空いている手で三つ編みを巻き込みシニヨンに結ったおくれ毛を撫でてやると、遠藤はアスファルトの上の芋虫のようにモソモソとうねり始めた。そのうちツヤツヤに濡れた純一の指を重たく歪んだ胸に押し当てる。
「約束」
そう言って胸の上で動いていない純一の手の甲をつねった。純一は人差し指中指薬指で小さな三角形を作り乳首を探り、その周りをクルクルと指先で円を描いてやる。クともフともつかない吐息を漏らしながら気分を出している顔の髪の生え際をなぞってやる。
変な話だが、犬か猫を撫でているような気がしてきて次第に勃起が治まってきた。代わりに純一から逃げ出した淫気に当てられたかのように遠藤の腰と膝の動きが早くなる。衣擦れに合わせて純一も指の動きを早くする。突然遠藤の頭が激しく動き、額の生え際を撫でていた指が位置を失い半眼のまぶたを叩く。遠藤は達した。息が急速に整ってゆき、膝が崩れる。くすぐっていた指を落ち着け、手のひらで撫でてやる。
台所の二人がコッチを見ていた。
「終わった?」
「お、おつかれ。ありがとう」
「意外と早かったね」
台所とリビングで微妙に噛みあっていない。
「気にせずヤっても良かったのに」
「俺は気にするんだよ。犯罪被害者と分かっている相手に、交際申込まれて三日目でハメるってのは、余程事情が分かっていないと俺の価値観では無責任だというんだよ。ホストじゃないんだ。まずは説明しろ」
「説明はしにくい。多分できない。私たちはケーちゃんのホントのことはよく分かってないし、ケーちゃんは多分色々ツラいから」
純一の言葉に川上が言った。
「純一くんはオナニーするときの理由を説明できる?」
なんだろう。考えた事ない。溜まったから?生理現象?
「――そんな感じ」
「まぁ、アレだ。私たちの場合は、不幸な体験を類似の幸福な体験でオーバーライトして抹消しようという防衛反射。とか臨床的には説明されそうだけどね。正直、同種の体験をした者としては、自分の体験を言語化して誰かに説明するなど、ご主人様の命令でも嫌だね。あの時のことを思い出すと殺して欲しいくらいさ」
タオルで髪を巻いたパジャマ姿で佐々木が風呂場から戻ってきた。
「――肉体的に健全な男性としての反応と、社会的に健全な男性としての反応がせめぎ合って、抑制的な行動を選択させたという状況は分かる。でもね、さらに肉体の反応と精神の反応が全くズレていると、快楽に逃げることも苦痛を認めることもできない状態になるんだ。あの三十分足らずの出来事は絶望と無力いう意味を知る酷いものだったよ。そして貴方はごくあっさりと私に復讐の機会を眩しくも下された。まぁ多分だから彼女はキミを求めて、私はあなたを必要と感じているんだろうと思う」
佐々木はそう言って、頭のタオルを少し叩いて解いた。肘の辺りまで落ちてきた前髪を掻き上げる。
「……ベッド借りていい?」
川上が佐々木を避けるようにして寝室の戸口に立ち入った。
「あとで布団出しに行くけど、いいよ。風呂は?」
「朝借りる」
川上は寝室に消えた。純一と川上のやりとりを無視して佐々木が純一の前に歩み寄り、膝を突き合わせるような距離で膝立ちになる。薄着になってパジャマ姿だと、かなり着痩せする印象だったことが分かる。ユサリと量感を持った胸と温かい女の体臭が見えない圧迫を加え、反射で純一の手のひらが固くなり、遠藤が身じろぐ。
佐々木は目の高さの胸元のボタンを外してパジャマの前をくつろげ、形の良い張りのある乳房をさらけ出す。そして遠藤の頭に置いていた手を自分の左胸に掬うように置く。
「慶子に一番を譲るっていう約束があるから我慢もできるけど、本当はすぐにもヤリたい。ヤッて欲しい。愛というよりきっと恋だけどそういうのもちょっとオカシイ」
胸で腕を押し込むように佐々木はにじり寄る。
「ダメっ」
佐々木の後ろに立った滝川が引き戻す。佐々木はバランスを崩し正座になった。
「なになに?」
「ミーちゃん、その膝は私の」
滝川は半泣きだった。
「その膝は私のなの。食器洗いしたら膝枕してくれることになってたの。お風呂はいる前に聞いていたでしょ。洗い物を片付けている間、クチャクチャ聞こえてきたりエッチな匂いがしてヤだったの。でもみんなとの約束だったから、ソレはガマンしたの。でも私も約束したの。だからソレは私のなの!」
大きな声に寝ていた遠藤が目を覚ました。胸の上の純一の腕を軽くタップして、お風呂借りるね、と浴室に消えた。
「ユカリ、おいで」
遠藤のいたのと反対側の腿を叩いて純一は滝川を促す。ちょっとしゃくりあげながら滝川は純一の示した膝枕に腹に顔を向けて頭をおろす。
「ミキ、毛布をあるだけ持ってきて、場所は」
「大丈夫。わかる。シーツと枕もね」
とりあえず宥めて落ち着ける。
ヤレヤレ。
純一の思うところを正直に述べれば、その一言に尽きた。
覚悟していたとはいえ、正解なしの択一を危うく躱したのかどうなのか。却って見事にハマったのかも。
少なくともコレはフワフワポワポワするような展開でも、男はセックスだけしていれば事足りるような展開でもない。
そう理解していたはずだった。だけど、まだ油断していた。そう気がついたのは日が変わり夜半もいい加減過ぎていた頃。純一は寝床に群れなした辺りを思い出してみる。
眠りについた時点で磔刑じみていた。だがそこまでは、油断と感じるほどのコトではない。
今日はナザレのイエスの誕生日で磔刑にあったのは春分の日だろう。そう苦情申し立てたのもまるで無視された。洒落というかじゃれ合いの範疇だと純一は思う。洒落というかじゃれ合いの範疇だったと純一は思う。
佐々木はチャンと痛くないようにしておくからとマットレスを二枚横に並べ、上に毛布とシーツで少し厚みを作り、ダブルベッドサイズにした。確かに痛くはない。嘘はついていない。
滝川と佐々木に腕枕をすることになった辺りを、純一は思い出していた。
「土曜日になったね」滝川がいった。
「ナザレのイエス。お誕生日おめでとう。」
すでに両腕を滝川と佐々木に腕枕に提供して、磔刑に処せられている純一が言った。。
「メシアの誕生だ。すると私が東方の賢者?マギ?」
風呂上りの遠藤が聞こえていたらしく言った。
「東はそっちだ。マギが起きていたら一緒に寝ようって言ってみてくれるかな。導きの天使さん」
佐々木の言葉で、遠藤が寝室に消え、出てくると台所に足を向けた。
理由はすぐに分かった。川上が密かにもってきたシャンパンボトルを寝室から持って現れると、さっき来たばかりのワイングラスにちょっと残っていたチーズとナイフをトレーに乗せて遠藤が持ってきた。
「なんだかイキナリ煮上がってたから、悲しく持って帰るトコだった」
「ゴメンゴメン。なんか楽しすぎて、ヘンになってた」
ボトルを純一に差し出しながらの川上の苦情に佐々木が答えた。
家主の純一がシャンパンのボトルを受け取り開けると空気が少し清浄に戻った。
「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む人はわたしにとどまり、わたしもその人のうちにとどまる」
純一は自分の知っている数少ないキリストの言葉の中で一番好きなモノを口にしながらグラスにシャンパンを注ぐ。
「はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちの内に命はない」
小さくなりすぎて乾いた固いチーズを切りながら、どちらが先に来るべきか知らない言葉を唱える。
と、ナイフがチーズの固いところで流れて左手の指を切った。よく切れるナイフなので、痛みはそれほどだがチーズが少し汚れた。「あー、これは立派なホスティアだ。痛まないうちに食べきらないとだ」
切った指を浮かせて残りも切り分ける。次第に指の血の雫が溜まってきたが、雫が崩れる前に切り終わった。
純一が口に含もうとした指を、スッと佐々木が引き寄せる。
「ミーちゃん。反省してなさそう」
その手を更に川上が留める。
「ヒカリ、わかったよ。ごめんなさい」
佐々木が手を離す。川上が両手で純一の手を唇に導く。
「次は私」
川上が含んでいた指をはなすと、佐々木が手を伸ばそうとした瞬間に滝川が純一の方に手を掛けて引いた。マットレスの分傾いた純一は希望に応えるためとバランスを取るために滝川の方に左手を差し出す。
「ミキちゃんは最後だね」
遠藤の確認の言葉に佐々木は鼻を鳴らして応える。
遠藤は滝川が純一の指を開放すると、皿を指さしながら目を瞑り口を開けて舌を伸ばした。チーズを舌に載せろ、というサインらしい。舌先を手招くように変形させてみせる。
純一がチーズを舌の上に差し出してやると、器用に舌先をくぼませて指先を包みこみ、チーズごと口に銜えた。唇だけでなく歯まで使われて固定され指先のチーズを舐め取られていく。
周囲からは手を使わずに新たな展開をみせた遠藤の機転に感嘆の声が上がった。
佐々木も遠藤を真似て舌を伸ばす。純一は舌の上にチーズを落とした。佐々木はちょっとムッとしてグラスのシャンパンを口に含むと純一の首をたぐり寄せた。
「おとなしく聖体をお受けなさい」
純一は佐々木の鼻を摘む。しばらく佐々木はジタジタしていたが、口の中のものを飲み込んだ。
「いけず」
佐々木が思いのほか可愛かったので、鼻にやっていた指で唇をなぞると、噛み付かれた。
そんな感じの聖体拝領ごっこを楽しんでシャンパンを開けて、全員で寝ることになった。
純一は改めて寝床で磔刑に処された。今度は左腕の佐々木との体の間に遠藤が入り込んで胸の上に頭を載せた。ゆるく結った髪がマフラーのようだった。
部屋の明かりを消してくれた川上が純一の枕を抜き、首の下に腕をさしいれると純一の頭をかかえるようにして寝た。
さすがにしばらく女たちを警戒して寝付けなかったが、意外と疲れているコトを感した途端に眠りに落ちた。
純一は油断していた。
警戒が足りなかった。
状況の理解が不足していた。
だからレイプをさける努力を怠った。
結果として純一はレイプされた。
0
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
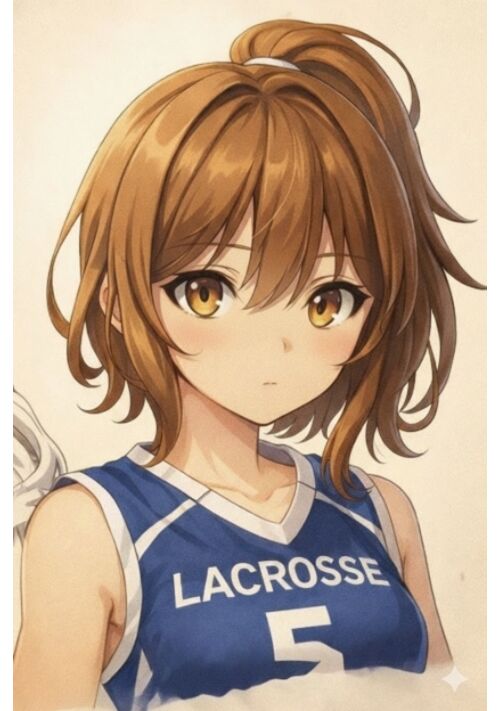
私の守護霊さん『ラクロス編』
Masa&G
キャラ文芸
本作は、本編『私の守護霊さん』の番外編です。
本編では描ききれなかった「ラクロス編」を、単独でも読める形でお届けします。番外編だけでも内容はわかりますが、本編を先に読んでいただくと、より物語に入り込みやすくなると思います。
「絶対にレギュラーを取って、東京代表に行きたい――」
そんな想いを胸に、宮司彩音は日々ラクロスの練習に明け暮れている。
同じポジションには、絶対的エースアタッカー・梶原真夏。埋まらない実力差に折れそうになる彩音のそばには、今日も無言の相棒・守護霊さんがいた。
守護霊さんの全力バックアップのもと、彩音の“レギュラー奪取&東京代表への挑戦”が始まる──。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~
Mio
ファンタジー
妻から手紙が来た。
妻が死んで18年目の今日。
息子の誕生日。
「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」
息子は…17年前に死んだ。
手紙はもう一通あった。
俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。
------------------------------

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















