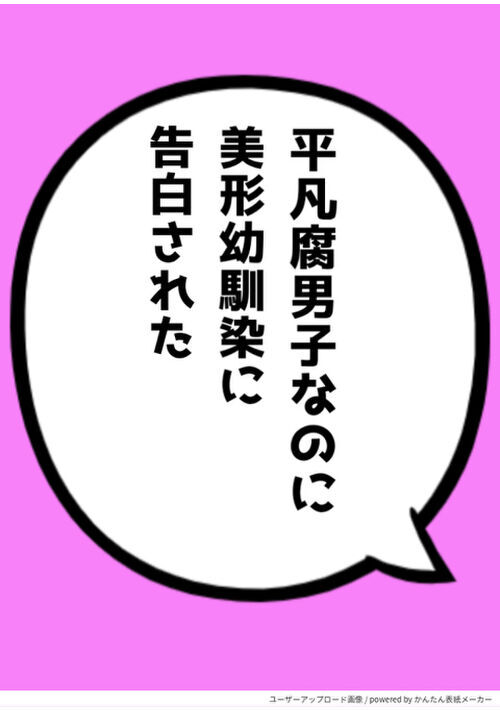2 / 5
確かに、片桐とは同中です。けどマジでそれだけ
しおりを挟む我が母校の体育館は、去年の改修で、アリーナもかくやと言う広さと清潔感を誇っている。
故にバスケやバレーの地区大会の会場になる事も多く、今日のような日は、会場準備から何からに駆り出される羽目になる。
加えて一年ともくれば、求められる働きぶりは、馬車馬もかくやと言うほどだ。
こちらです。あなたは?あ、〇〇高校……では、こちらを使って頂いて……。と言った具合に、続々と到着する参加校の方々を控室まで案内する。
「こら、右成!」
武道場の鍵が、つるりと滑り落ちる。かしゃーん!と音を立てたそれを、他校の先輩が拾ってくれる。
「ありがとうございます」と鍵を受け取り、今度こそ扉を開けて。
怒号が聞こえた方を振り返ると、右成が他校の部員に噛み付いているところだった。
比喩とかではなく、物理的に噛み付いている。
それだけでも奇怪な光景ではあるが、さらに異質なのは、噛み付かれた方が右成によく似た顔をしているという点。いや、似ているというよりかは、全く同じ顔面だ。
噛みついているのは右成だし、齧られている方も右成。
「ちょうど良かった藤白!ちょっとこいつ捕獲して!」
頬に引っ掻き傷をこさえた先輩が、必死の形相で助けを求めてくる。
噛みついている方──右成aを慌てて取り押さえ、どうにか右成bから引き剥がそうとする。
「み、右成、やめろ。正気に戻れ」
「ガルルルル」
だめだ人語を忘れてる。今にも野生に帰りそうな右成aに喰われながら、右成bは「元気だねぇ」と他人事みたいに笑う。あんたそれで良いのか。
ベリ!と、ジタバタする右成aを、ようやっと引き剥がす。
「何があったかは知らないけど、まず謝れよ」
「…………」
「暴力はだめだ」
心を込めて諭せば、少しだけ肩を震わせて抵抗を止めた。それでも頑なに謝罪をしないので、代わりに「すみません」と俺が頭を下げる。
「ああ、いやいや。大丈夫です。お気になさらず」
右成bは、ゆったりした所作で首を振った。側頭部からピュウピュウ血が噴き出ている。
傷害、暴行、出場停止、部活動停止。
あまりに景気の良い出血大サービスに、一瞬でそんな言葉が脳内を駆け抜ける。
「ただの兄弟喧嘩なんで」
「は、」
目を剥く。確かにこいつ──右成aは、他校の兄弟に対抗するためにここに来たと言っていたが。
「右成朝陽。夕陽の双子の兄です。よろしく」
「よろしくお願いします……?」
「もしかしてきみ、侑希くん?」
「ど、何処かでお会いしましたか……」
「いや、夕陽がお世話になってるみたいだから」
穏やかな笑みのまま、右成b……朝陽さんが右成にアイコンタクトを取る。
釣られるように右成を見ると、先刻とは違って、何処か狼狽えるように視線を彷徨わせていた。
「恥ずかしがるなよぉ。……こいつ、バレー馬鹿でしょう?」
「バ……まあ、熱意は常々感じてます」
「だから、温度差って言うの?そう言うので、チームの奴らとの衝突も多かったから、1人で上手くやれてるか心配だったんだけど」
────良かったね、夕陽。
俺と右成の相貌を交互に見比べて、さらに笑みを深める。
普段はサルみてぇな右成しか見てないので目立たないが、こうして普通に笑えば、中々に優しげな面差しをしている。同じ遺伝子でも、印象は全く違う。
黙ってニコニコしていれば、右成ももっと友達が増えるのではないかと思った。
憐れみの視線を向けると、何処か青い顔をした右成と目が合う。いつもはこういう時、必ずこっちを睨んでいるのに。
何やら尋常じゃない様子に、思わず息を呑んだ。
「朝陽、他の一年はもう準備して体育館行ってるけど……何?おまえ負傷してるの?」
冷ややかな声音だった。
右成、と、口に出し掛けたチームメイトの名を飲み込んで、声の飛んできた方を振り返る。
他チームの選手だった。
恐らく年上であろうその人は、朝陽くんを咎めながら、目を細めた。
背も高く、体格にも恵まれている。整えられた指先からは、意識の高さが窺える。
妙にオーラがある人だと思った。
「ごめん、アオイくん。すぐ行く」
「…………敬語も使えないの?」
「すみません、アオイくん先輩」
あんたそれで良いのか。威圧的な先輩も、あなたそれで良いのか。
モヤモヤとさせられるやりとりが、目の前で一往復。朝陽くんはベンチコートを翻して、体育館へと向かった『アオイくん』の後を追う。
「またね」と。
一度振り返り、唇だけを動かす。涼しげに目を細めて、今度こそ体育館へと向かって行った。
「……おまえ、大丈夫?」
その背を見送って、未だ隣で立ち尽くしている同期へと視線を向ける。
先輩にぶたれた時だって喧しかったコイツが、ここまで静かになるのは、ある意味大事件だ。
「…………ないのに」
「は?」
強張った表情で、何かをボソボソ呟く。
本当大丈夫か、お前。顔色ヤバいぞ。
「俺、お前のこと、アイツには一言も話してないのに」
「ええ……」
「つか学校の事以前に、口きいてない」
思わず声が出る。
アンチ兄なのは前々から知っていたが、家で口すら利いていないとは。
「ご家族に話したりしたんじゃないの、俺のこと。それなら直接話さなくても、フツーに伝わるでしょ」
「でも名前……お前の名前までは、家族にも教えてねぇよ」
「……………」
「……………」
2人して顔を見合わせる。右成にこんな顔をさせるのは、後にも先にもあの兄だけなのだろうと思った。
し、心配性なんデショ……。なんて呟くと、思い切り足を踏まれる。コイツマジで暴力マン。
「……カカンショー?ってやつなんだよ、あいつ」
「はぁ……」
「さっきだって、『お前もウチの学校来ればよかったのに』とか何とか、舐めやがって」
「引き抜きか?それは困る」
「困……当然、本気じゃないんだろうけど」
少しだけむず痒そうにしながら、顔を伏せる。
しかし、そうか。あの怒りっぷりにも納得が行くと思った。
右成は基本、自分自身が舐められるのも大嫌いだが、自分の意志や決断を否定されるのはもっと嫌いだ。『そのチームを捨ててここに来るべきだった』と言うのは、右成にとっての最大限の侮辱なのだろう。自身はチームメイトに傲岸に振る舞うくせに、とんだジャイアニズムだと思う。
「俺のこと、何もできないガキだと思ってんだ。年も変わんねぇのに」
「………………」
「……なんだお前、怖……キショいよ……」
無言で背中を叩くと、本気で怯えられる。
どんな暴言よりも、何だか胸にキた気がする。
「右成!藤白!」
前触れもなく名前を呼ばれて、肩を揺らす。振り返れば、右成も梅干しみたいな顔のまま、同じ方を向いた。
こーくんだ。
頬が緩みそうになるけど、どうにかして引き締める。ベンチコートを着たまま、こーくんはこいこいと手招きした。
「ユニフォーム組はアップするから、体育館上がってこい」
「あ、でも案内が……」
「良い良い。こっちは俺らやっとくから、行ってこい」
口籠る右成に、他の先輩達が手を振る。俺たちは先刻の騒動のせいでほぼ仕事をしていなかったので、戦力的にも大きな損失にはならないだろう。
礼をして、こーくんの元へと小走りで急ぐ。
後ろから追ってくる右成の足音に、訳もなく耳を澄ませた。
***
コートに立っていると、よく人の心が折れる音が聞こえてくる。相手からも味方からも、満遍なく。
けれど此方の声は届かずに、徐々に呼吸の仕方すら忘れて息苦しさは増していく。
この空気のコートは、密閉された水槽みたいだと常々思う。
またサービスエースだ。
何本目だ?
いつもはギャラリーの声なんて聞こえないのに、今日だけはやけにはっきり聞こえた。
願わくば、隣のコイツには聞こえていない事を祈るが。
「……右成」
小さく声をかける。
ガラスみたいな目が、きろ、とこっちを向いた。良かった。俺の声は聞こえるみたいだ。
地区大会決勝。
下馬表通り危なげなく勝ち進んだ俺たちを待ち受けたのは、因縁の名門私立校である。
昔ながらの強豪で、絶対的エースを軸に、高い能力水準の選手を揃えた穴の無い構成。
特に今年は、u15にも選ばれたセッターと、その候補と呼び声の高い新一年スパイカーを新戦力として迎えたと言う。
そしてその天才セッターが、今朝会った『アオイくん』で、新一年スパイカーが、『右成朝陽』その人であった。
淡々と、綻びの無いトス回しに、こちらの守備は掻き乱される。
そして特に、右成朝陽のサーブは、守備の未熟な俺たちにとって、大きな脅威となった。
高い打点から繰り出されるジャンプサーブは、その威力もさることながら、同世代では類を見ない精度のコントロールを誇っていた。
的確に、そして執拗に相手の急所を抉る事に長けているのだ。
まず一本目は、俺に飛んできた。
経験の浅い一年生で、崩れやすいと踏んでのことだろう。こーくんとのレセプション練習が役に立ち、何とか上げることができた。
そして2本目は、右成だった。3本目も、4本目も右成だった。
右成が対応しきれなかったわけではない。けれど砲弾みたいなサーブを幾度と無く受れば、当然ミスも数本は出てくる。
一度対応された時点でエースやその他にターゲットを変えるのが定石である分、その選択はあまりにも不自然に思えたが。
……ネット越しに見える、右成と全く同じ顔をした青年。
表情は穏やかでありながら、双眸だけは、滾るような興奮に活き活きと色付いている。
それを見て、ああと納得する。彼にとって、きっと合理性だとか定石だとかは、どうでも良いのだと。
その感情の名前すらわからないが、彼はただ、楽しくて仕方が無いのだ。
誰かの心を折る事が──否、片割れの心を折ることが、楽しくて仕方が無い。自分こそが片割れを叩き潰し、矜持も、自尊も、何もかもを蹂躙してやるのだと。
きっと何度レシーブを上げようと、彼はこの先ずっと、右成を狙い続けるのだろう。
真っ直ぐに右成だけを見つめる視線は、そんな、偏執的で陰惨な愉楽すら思わせた。
「負けるな」
気付けば、そんな言葉が転がり出ていた。
先輩や、こーくん、右成が少しだけ驚いたような表情をする。俺も自分に驚いている。やや於いて、俺は存外苛ついているのだと自覚する。ここでは上手い奴が正義で、実際に彼は結果を残している。それでも、右成朝陽の、合理性を完全に無視した自慰めいたプレーは、好きになれないと思った。
「多分先生は、タイムも交代させる気もない。一本、俺たちが自力で切るしかない」
「………ああ」
「上に上げるだけで良い」
「…………」
「俺が決めるから」
一点決めて、あの悪趣味なサーブを切る。
セッター……こーくんへと視線を向ければ、小さく頷いてくれた。
「舐めやがって」
「上げてから言え」
「俺は上げた」
「全部あげてから言え」
小言を言い合いながら、ホイッスルを聞く。
風船でも叩き潰したみたいな破裂音の後に、風圧を伴ってボールが飛んでくる。
相変わらず右成狙いなのは変わらない。
「……ぎっ、」
ほぼ右膝を崩すような体勢で反応。
完璧とは言えないが、2段トスに繋げられないボールでも無い。こーくんが落下地点に走る間に、俺を含めたスパイカーが助走距離を取る。
ライトバックから右利きライトへの2段トスは、難易度も高い。定石通りならレフト一択だが、こーくんなら、ライトでも俺に上げてくるだろう。
「俺が決める」と言い、その言動に少しでも合理性があるならば、スパイカーの意志を尊重する。
頼もしく居て、どこまでも無慈悲だ。
己の言動の責任を果たせと。身体全体を使ってセットアップされたトスが、そう凄んでいるみたいだ。
角度を付け、ほぼネットに並行な位置からの助走。
集まってくるブロッカーの隙間から、相手のコートを確認する。
ブロック3枚。完成も早い。
踏み込み、バックスイング。筋繊維の収縮、膨張。
空中姿勢を保ったまま、胸を開き弓のように反る。
自分でもよく飛べているのがわかる。
体幹トレーニングと、腹筋、背筋、ロードワーク。
その全ての集大成がこれだった。
僅かな差ではあるが、滞空時間の長さは、空中線での勝敗に直結する。
ブロッカーが、最高到達点に登って、そして落ちる。
その瞬間に、腰を回転させる。
完全にブロックの上から振り下ろされた手が、思い切りボールを叩き落とす。
鋭角なコースには確認通り人はおらず、少しの静寂を埋めるように、ホイッスルの音が響いた。
「飛ぶねぇ」
「空中で待ってたね」
「完全にブロックの上から打ったな、今」
「いっつもそれやれよ」
先輩達が、ハイタッチを求めに来る。こーくんは頭を撫でてくれた。
こーくんの信頼に報いれたと言う実感に、スパイカーで本当に良かったと思った。
「…………ナイスキー」
どこか不満げに唇を尖らせる右成。「どういたしまして」と薄く笑うと、目を見開き、歯痒そうに歯軋りをした。良かった、いつも通りだ。
ボールを受け取り、サーブを打つべくエンドラインへと下がる。
何処か残念そうに笑う右成朝陽に、薄寒さを感じた。
***
3セットまでも連れ込んだ試合は、結局終始相手の優勢で終わり、俺たちは負けた。けれども地区予選は通過しているので、県大会に上がれば、また彼らと戦う事になるだろう。
悔し泣きする右成を宥めながら、ストレッチ。
「レセプションの練習付き合ってやるから」と言えば、鼻声で「ごぼごぼごぼ」と帰ってくる。お前は何に溺れてるんだ。
「おまえ゛くっさい……」
「は、」
クンクンと自分の袖を匂う。
自分では分からないが、きっとこいつだって同じ匂いだ。とは言え匂いは気になるので、バッグからシーブリーズを探し出して、首やら胸やらに塗っておく。
ついでに汗だらけのユニフォームを脱いで、練習着に着替えた。
「ほら、お前もいい加減着替えろって」
「絶ッッ対、クソ朝陽よりうまくなる」
「そうしてくれ。ほら、バンザイしろバンザイ。脱がしてやるから」
「おまえよりも上手くなるるるる」
「わかったから、あーもう、風邪ひくぞ」
ぐずぐずと泣きながらも、大人しくバンザイする右成。甥っ子にするみたいにユニフォームを脱がせる。右成のバッグから勝手に引っ張り出した練習着を着せて、シーブリーズを顔面にぶちまけた。
「ぶ!」
「おまえクッサ。自分がフローラルに包まれるとわかるけど」
「びびび死、死ぬ!死ぬ死ぬ死ぬ……ん、」
右成の目が、キョトと瞬く。
泣きやんだかと思えば、じっと俺の手元を凝視して。
「お前、それ変えた?」
『それ』と言うのは、シーブリーズのボトルである。ガサツなように見えて、変に目敏かったりする。
「前は黄色のやつだったよな。色ウルセーってずっと思ってたから」
「変えた……というかこれは────、」
「ゆーうき」
鼻にかかったようなテノールが、俺の言葉を遮る。
ほぼ同時に肩に添えられた重みに、目を見開いた。
誰だ、と言いたいところだけど、出会い頭に下痢ツボを押してくるようなヤツは、あいつしかいない。
「片桐」
「やっほ」
肩を軽く叩いて、隣に腰を下ろしてくる。
鼻梁のスッと通った横顔に、長くて白い首、真っ黒なサラサラヘアー。
練習着を着ている分、普段よりも体格の豊かさが目立つ。
「お疲れ様、凄かったねぇ」
「見てたの?」
「丁度、休憩中にやってたからね」
「練習に集中しなよ」
「俺だけじゃないもん。チームの連中も見てたし、あと、結構クラスの奴とかも。『ウチのガッコ、こんな強かったの~!?』って」
グーにした両手を顎先にくっつけて、キショい声を出す。
ぶに、と頬を掴めば、へらへらと笑いながら両手を掴まれる。鼻を掠めた甘い匂いに、やんわりと手を下ろして距離を取った。
「なに、何で逃げるのさ」
「汗臭いからおれ」
「ええ?部活生なんて皆同じようなモンでしょ。俺も大して変わらないよ」
朗らかに笑いながら、同じだけ距離を詰めてくる片桐。
さすが片桐だ。余裕も思いやりも、どこかの誰かさんとは違う。
「…………片桐、秀司くん……?」
気配が消えていると思ったら、右成は片桐の登場にすっかり目を回していた。
「きみは、」
俺の視線を追うようにして、片桐が右成へと目を向ける。
その笑みは人当たり良く、初めて出会った時の彼を思い起こさせる。よそ行き用である。
「こいつは右成。同期」
「ああ、右成くん。……彼が?よく侑希から名前聞くからかなぁ。初めて会った気しないや。よろしく」
「よ、よろしく……」
気圧されるみたいに、差し出された片桐の手を取る右成。こんなしおらしい右成は中々見る事が出来ないので、少しだけ愉快だ。
小さく笑うと、片桐と右成の4つの目玉が、皿みたいにまん丸になった。
なんだその目。言いたい事があるなら言ったらどうなんだ。
「お前、一生笑わない方が良いよ……」
「は?」
「笑顔キモい……」
反射的に右成の胸ぐらを掴む。
そのままアンチクショウの口にシーブリーズを突っ込もうとして、片桐に止められる。
「これだけはやめて」なんて言葉に、少しだけ冷静になって、肩パンに切り替えた。
「痛ーーーッ!」
「マッスルばいばいしろ」
「マ……、もしかして肉離れのことマッスルバイバイって呼んでんの?」
何がおかしいんだ貴様。
その大きく開いた口に突っ込んでやろうと、拳を握りしめて。
「仲良いんだねぇ、2人」
目を見開く。
依然ニコニコと微笑んだまま、片桐がゆっくりと立ち上がった。幾分か冷静になった頭で、俺は拳を開いてパーにして、右成は間抜けに口を開けた。
どこまでも穏やかな声音ではあれど、その声には、背筋が伸びるような、妙な緊張感が伴っていたから。
「か、片桐?」
「そろそろ休憩終わるから、俺行くよ」
「ああ……」
「遅れたらドヤされちゃう。じゃあ、またね。侑希、右成クン」
待合室から出て行く片桐の背に、ふりふりと手を振る。
扉のところで、「あ、そうそう」と立ち止まるので、顎を引いて手を下ろした。
「それ、大事に使ってよね」
それ、と。目線で示されたのは、シーブリーズである。黄色のボトルに、青色のキャップ。
頷けば、満足げに微笑んで、今度こそ待合室から出て行く。
「…………それって何だよ」
扉が閉まってしばらく経って、右成が半目で尋ねてくる。意味もなくパキ、とキャップを開閉して、少しだけ考える。
「ただの制汗剤」
「ウソつけよ。何、片桐クンにもらったわけ?」
「キャップだけな」
「は?」
先程答えようとしたのだが、片桐自身に遮られたのだった。
あの、片桐の誕生日の夜。
何を思ったのか、アイツは俺の制汗剤の蓋をせびった。どんな陰湿な嫌がらせだと拒否すれば、『じゃあ俺の蓋あげるから』と、謎の譲歩を受けたのだ。
それは結果的に交換でしかないし、アイツの意図も分からない。けれど何も知らないうちに丸め込まれて、俺のシーブリーズは青キャップ黄ボトルのキメラへと変貌してしまった。
「まあ、キャップがプレゼントってのは流石に酷いから、後でちゃんとハンドクリームあげたけど。アイツ意識高いくせに手はカッサカサで────、」
「……それさぁ」
一連の経緯を聞いた後、右成は何処かゲッソリとした表情で俺を睨んだ。
「………………」
「………………」
「なんだよ」
「………………」
「なんか言えよ」
痺れを切らして詰め寄っても、口元をむず痒そうに動かすだけで答えようとしない。
互いに、胡乱な目で見つめ合って。
「…………いや、何でもない」
「はぁ…?」
先に視線を逸らしたのは、意外にも右成の方だった。こう言った睨み合いの時、此奴は意地でも先に目を逸らさない。
そんならしくない反応に毒気を抜かれると共に不安になる。
なんだ、こいつ。敗北は人を変えるのか?
「……何でもねぇって言ってるでしょ。ほら、行くぞ。そろそろ片付け始まるだろ」
「何だお前」
立ち上がり、誤魔化すように控え室から出て行く右成。先刻までガキみたいに泣いてた奴が、よく言った物である。
シーブリーズを鞄に放り込んで、俺もまた、右成の後を追うように立ち上がった。
[newpage]
「片桐くんと仲良いの?」
「右成くんって休みの日何してるの?」
俺は限界だった。ただでさえ持て余していた質問が、もう一人分増えたのだから。
我が校で執り行われたあの大会は、成績も相まって、この学校のギャラリーをある程度集めたらしい。そこで目にした一年レギュラー右成の活躍に、ファンが生まれ、追っかけが増え。
試合やら学校やらで、右成について呼び止められる事が最早当たり前となってきていた。
試しにあれのどこが良いのかを聞けば、「えー、スポーツしてるところカッコ良いし!」「一年でレギュラーでしょ?すごいじゃん」「ちょっと近付き難いと思ってたけど、藤白君と話してるの見てると、割と気さくなのかなって」「つかフツーに超イケメン。背高いし」エトセトラエトセトラ……。
右成の普段の姿を知っている人間からすれば、血迷うな、考え直せと小一時間説得したくなるような案件だ。しかし俺には、そんな余裕もリソースも親切心もない。
「我慢ならん」
「は?」
「何でお前みたいなのにアプローチしたがるんだ」
こんな、叩いても叩いても響かなそうな奴に。
そんな思いが爆発したのは、トイレに行くまでに3度呼び止められ、とうとう漏らしそうになった昼休みだった。
「え、なに。俺がモテるって話?僻んでるの?」
「もうそれで良いよ。とにかく、『藤白くんに俺の事は聞かないで』ってプラカード下げて生活するとかして」
「いやだ!」
ボールをレシーブしながら、元気よく拒否される。
頭が痛い。こちらはバレーに集中したいのに、とんだ役損である。
「もうお前、彼女の1人や2人作れよ……」
そしてあの、健気な女の子たちを黙らせてくれ。
そう呻くと、右成がまた「いやだ!」と声を張り上げる。
そうだこいつもまた、バレー馬鹿なのだ。
クラスのマドンナとボールが並んでいたら間違いなく後者を選ぶし、正直選手以外の人類の区別がついているのかすら怪しい。
「失礼だろ!」
「え、今名も知れぬ女子を慮ったの?そんな倫理観がお前に……?」
「バレーに失礼だろうが!」
「そっちか……」
知ってたけど、半目になる。人でなしっぷりは健在である。
「兎に角どうにかして。今日の昼練、遅れたのもそのせいなんだからな」
「マジか。深刻な問題じゃん」
「さっきからずっとそう言ってるよ、馬鹿。そもそも、何で俺のところに皆来るんだ。勘弁して……」
「それはお前が一番俺に近しいからでしょ」
「は……?」
今、俄には信じ難いニュアンスの言葉が出なかったか。近し……何?右成が今そう言った?
目を剥けば、「じゃあさ」と朴訥とした口振りでボールをトスしてくる。
「お前の作戦、パクらせてよ」
「はぁ?俺の作戦?」
「うん」
ちょっと理解が及ばなくて、混乱するうちに、あられも無い方向にボールが飛んでいく。
それも難なくレシーブする右成の成長ぶりに、目頭が熱くなった。
「お前のシーブリーズ」
「おお」
「キャップ、片桐クンと交換したって言ってたじゃん」
「言ったねぇ」
「あれ、カップルがするやつだから」
「はい?」
俺はボールを落とした。
素っ頓狂な声は、紛れもなく俺の口から出た物だ。てんてん……とボールが小さくバウンドして、やがて完全に沈黙する。
「カッ……誰と誰が何だって?」
「やっぱ知らずにやってたのかよ。ツっこんで良いものか測りかねてたけど」
間延びしたような、呆れたような声で指摘される。
カップルが、何?
シーブリーズの蓋を交換するのが?秘境とかの儀式みたいなもの?
どんな意味と意図があるのだとか、今時の恋愛って、何て小癪なんだとか。そんな感想は隅に置いて、要点だけを吟味する。
片桐と俺は付き合っていたという事だろうか。
馬鹿野郎そんな事実も記憶あるはずがない。
だが、事実として俺たちはキャップを交換した。
それは片桐が、俺のキャップが欲しいと言ったからだ。買ったばかりだったので、当然キャップをぶん取られるのは困ると断った。すると譲歩として、交換することになった。
これはまあ、事故だろう。事故。ぜんぜん事故の範囲内だ。
最初の提案をしてきた片桐の真意こそ謎だが、多分カスタマイズしたかったとか、適当な理由な気がする。大概気分屋なのだ、アイツは。
問題はそれがなぜ、『作戦』やら『女の子避け』やらに繋がるのかどうかだが。
「『藤白くんってフリーかなぁ』『でも、シーブリーズのキャップ、誰かと交換してるらしいよ!』『アーン、ほなフリーとちゃうか』」
「どうしたんだ急に。大丈夫か」
猫撫で声の一人芝居に、ゾワゾワと腕に鳥肌が立つのを感じる。吐き気を催しながらも気遣ったのに、右成は不服ですと言う顔でボールを投げつけてくる。
「だからお前、彼女いると思われてるよって話」
「俺が?」
「そうだよ。バレーが原因で俺が目付けられるなら、お前も目付けられるってわかるだろ」
「いや……」
「でも恋のおまじないする相手が居るなら、諦めなきゃねって。ここまでがワンセット」
『シーブリーズのキャップ交換』を、『恋のおまじない』と言い換えるのが絶妙にキモい。
「でも、俺はいまだに片桐の事聞かれるけど。キャップ交換したのに」
「片桐クンは……、あれはもう、何か異次元だろ。特例。フツーは、彼女いるって分かってる相手を狙ったりしねぇわ」
今にも鼻をほじり出しそうな同期。
その言わんとする事が、今ようやく分かってきた気がする。俺に対する言い分の真偽は置いておくとしても、右成のその作戦は確かに効果的だと感じたからだ。
「お前が誰かとキャップを交換すれば?」
「話が早くて助かるよぉ、藤白くん」
「じゃあ俺のと交換するか」
「はぁ?」
今度は右成が素っ頓狂な声を上げる番だった。
それだけじゃ飽き足らず、せっかく拾ったボールをまた落とす。町一番の阿呆でも目撃したような表情だった。
「何だその顔」
「片桐クンはどうすんのさ」
「え?何でそこで片桐が出てくんの」
「いやいやいや、逆に何でそこで片桐クンを無視できるの?お前実はすごい馬鹿だろ」
『馬鹿』と。こいつにだけは言われたくないランキングが存在するなら、それは3位以内には入る言葉だろう。
このキャップは既に俺の物だし、できるなら、今すぐにでも手を打って被害を最小限に留めたい。
「アイツは俺のキャップが欲しいって言ったんだ」
「だから?」
「交換は成り行き」
「それで?」
「ならアイツはアイツ自身のキャップがどうなろうと、どうでも良いだろ。普通に考えて」
「あー、なるほどね」
その声には、何処か言葉通りの得心と、妙な諦観が滲んでいるように思えた。阿呆を見る顔をやめたので、ボールをぶつけるのもやめにしてやる。
振り返って、自分のシーブリーズボトルを差し出せば、右成は眉を顰める。
ぐる、と何かを逡巡するように視線を彷徨わせて、「まぁ、良いか」と息を吐いた。
「ほらよ」
ピンク色のキャップを投げ渡されて、俺も同じように、青のキャップを投げ返す。
新しくカスタマイズされたピンクキャップ黄ボトルの制汗剤は、頭が痛くなるようなカラーリングをしていた。
***
シーブリーズを使い切る頃。対策が若干の効果を発揮しながらも、右成ファンはそれを上回る勢いで増加していた。
試合どころか、練習試合、普段の練習にまで押し寄せるようになったギャラリーを見れば、驚くほどの事でも無いだろう。
「お前、すごいな……」
「今頃?俺は最初から超絶イケメンでモテモテだっただろうが」
「……?」
「本気で分からないって顔するなよ。お前、あれだな。大概人に興味ねぇな」
「いやいや、体格とかコンディションだとか人一倍見てるし」
「ほれ見ろ」
因みに、なにが「ほれ見ろ」なのかは全く分からない。右成田からのパスを受けて、トスを上げる。
右成は確か少し高めで余裕のあるボールが好きなので、気持ち高めに上げてやる。
約一年前。「お前はセッターになれ」と、先生に言われ、「俺はスパイカーです」と暴れ回って反抗したあの日から。何だかんだこーくんに丸め込まれ、みっちりセッターのアレソレを叩き込まれてきた結果、かなり様になってきた気がする。
「あっ、」
ボキ!と、枝でも手折るような音を響かせたスパイク。ボールが元気よく体育館の外へと転がり出て行く。右成はボールを追っかける習性があるため、俺が「行けよ」という間も無くそれを追ってくれる。
1人体育館に取り残されたので、籠からもう一つボールを取り出して、ポーンと高く投げる。ボールが落ちてくる間に身体の方向を半回転させて、また、ポーンと高くオーバーして。
「あの、藤白くん」
少しだけ高い声に、ぴたとボールをキャッチする。振り向けば、そこには見覚えのない女の子が居た。華奢で、肩も足も腕も細くて、全体的にすぐ折れてしまいそうだと思った。
「……きみは?」
「私は、あの。5組の湯田って言います」
「湯田さん。どうしたの?」
「えっと、」
もじ、と足を擦り合わせながら、うろうろと視線を彷徨わせる。
その要領を得ない立ち振る舞いには、既視感しか無かった。内心ゲッソリとしながら、「片桐と右成、どっち?」と開きかけた口を、思い切り閉じる。
「……藤白くんは、お付き合いしてる人とかいるの?」
予想外にも、それは俺に対する質問だったからだ。
「お、俺ぇ?」
「?うん」
自分でも聞いたことないような声を上げた自覚はあるが、湯田さんは気にしていないみたいだ。
ここで何で、なんて聞くのも、少し感じが悪い気もするし。
こちらをじいと見つめてくる真っ黒で大きな目に気圧されてしまって、結局、「いないよ」と素直に答えた。
「そ、そうなんだ!」
先刻までの緊張からは一転、湯田さんは、心底嬉しそうに表情を綻ばせる。何だか単純に、愛らしいなと思った。
「私、前偶然藤白くんが部活してるところ見て」
「うん」
「すごく、カッコ良いなって。何より、バレーボール好きなんだなって」
「うん。大好き」
「……っ、」
何故かここにきて頬を赤らめる湯田さん。
その反応の真意は分からないが、他人から見ても楽しそうに見えるのなら、それはとても誇らしく、喜ぶべきことに思えた。
先を促すように首を傾げると、赤い顔を伏せて、何かを決心したみたいにまた顔を上げた。
「あの、これからも藤白くんがバレーしてるところ、見にきても良いかな」
「たぶん、大丈夫だと思う。今も結構人来るし、練習の妨げにならない程度なら……」
目を丸くする湯田さん。俺は何か間違えただろうか。女バレ以外の女子とあまり話す機会がない分、こういうのには慣れていない。狼狽を隠すように後頭部を掻けば、湯田さんは、耐えられないと言ったふうに笑った。
本当にわからない。
「ふふ。藤白くん、意外と天然なんだね」
「……そうかな?」
「私ね、藤白くんが好き」
「あ、ありがとう」
「彼女になりたいなって思う」
ここに来て漸く、湯田さんの言葉の意味を理解する。
彼女は、俺に特別な好意を寄せてくれているのだ。……その、友愛だとか尊敬だとかとは違う、もっと、俺が知らない類の好意。
どうして良いのか分からなくて、目を剥く事しかできなくて。
「……正直そういうのよく分からなくて。きっと、きみのこと大切にできないと思うよ。おれは、その、」
「私はね、バレーボールが好きな藤白くんが好き」
「っ、」
「だから、私は1番じゃなくても良いよ。藤白くんにとっての1番が、バレーだって知ってるから」
はにかみながら、上目遣いで俺の表情を伺う。いじらしくて、健気だと思う。その懸命さに応えたいとも思う。
けれど俺は、なにも分からない。だってきみのこと何も知らないし、自分のことだってよく分かってない。
戸惑うみたいに視線を彷徨わせたら、柔らかい感触に、ぎゅっと両手を包まれる。
「っ、……?、?」
「じゃあ、連絡先だけでも交換してほしいな。少しずつでも、私のこと知ってほしい」
「でも、スマホ今教室にあって」
「だと思って、LINEのIDメモしてきたの。これだけでも受け取って?」
細くて、柔らかくて、真っ白な指。
サンゴみたいにポッキリと折れてしまうんじゃないかって、手を握られている方は気が気じゃない。
少しの恥じらいと強引さを以て握らされた紙切れは、酷く重く感じられる。
湯田さんを見て、メモを見て。また、湯田さんを見る。湯田さんは、ゆったりと目元を撓ませて、「待ってる」と笑った。
「…………」
「じゃあ、私行くね。練習の邪魔しちゃってごめん」
プリーツスカートを揺らして、逃げるみたいに体育館から出て行く。暫く立ち尽くして、メモ用紙を、練習着のポケットへと突っ込んだ。
「…………隅に置けないねぇ」
「突っ立ってないで助けろよ」
「無茶言うなって」
背後からヒョッコリと顔を出した右成に、呪詛を吐いた。
とっくの昔に、ボールを回収して戻ってきていたらしい。息を顰めているつもりだったんだろうが、無駄にデカい図体がずっと視界の端でチラチラしてた。
「……こう言う時、お前はどうしてるの」
「俺ぇ?」
さっさと練習に戻ろうと促しながら、右成が間伸びした返事をする。俺よりもずっと、こう言う機会は多いだろう。
「部活に集中したいんだよねって、断る」
「傷付かないかな」
「さぁ、知らね。俺そう言うの割とどーでも良いタイプだから」
「人でなしめ……」
「は?お前にだけは言われたくねぇよ。けどそう言うの気になる人は、受け止めるしかないんじゃない?」
カラカラ笑いながら、こちらにボールを寄越してくる。
軽く強打を打って、右成が拾って。そのボールを、また右成へのトスにする。
「……っし」
床にボールを叩きつけ、着地する右成。
釈然としないままその様子を目で追ったら、涼しげな目と視線がかち合った。
「傷つけちゃったなぁ、悲しい思いをしてるんだろうなぁ、勇気を振り絞ったんだろうなぁって。そう言うの全部、受け止めて背負うしかないんじゃない。カワイソウ」
「…………」
「辛い?」
「おれは、人でなしじゃ、ないので……」
目を伏せると、ヌッと長い影に覆われる。
無遠慮に伸びた手が、俺のポケットを漁って、IDの書かれたメモを引っ張り出した。
「は?右成おまえ」
……何するんだ、と。続けようとした言葉は、発せられることなく腹へと戻って行く。
にぃ、と細められた目が、見たことのない酷薄さを帯びていたから。
背筋を駆け上がってくる薄寒さに、思わず息を呑んだ。
「ビリビリにしてやろうか、これ」
「何言って……」
「それで言えば良い。『人でなしにダメにされちゃったので、連絡できませんでした』って」
「…………」
「俺はね、藤白」
弧を描いていたはずの双眸が、思い切り見開かれる。鼻先が触れ合うような距離感で、妙に開いた瞳孔が、俺の視線を捕らえていた。
「他人が何しようとどーでも良い。俺のことどう言おうと、誰と乳くり合おうと、人殺そうと、心底どーでも良い」
「……悪かったって。どーでも良い話ふって」
「でもお前はダメだろ」
「は、」
その表情には、何だろう。いつかの──彼の片割れを彷彿とさせる何かがあった。
「色ボケで集中できません?恋の悩みで頭がいっぱいです?他の女の顔がチラ付きます?目の前に俺がいるのに?」
「許せるわけねぇよな?お前のトスもレシーブも、全部俺のためにあんのに。マトモぶってねぇでさっさと切り捨てろよ。それができねぇなら、他の奴にレギュラー明け渡せ」
───なんなら俺がころしてやろうか、その女。
そう言い切った男の相貌からは、表情の一切が抜け落ちていた。
おまえ、右成朝陽みたいだね。咄嗟に唇を引き結んで、そんな言葉を呑み込む。正反対に見えていたけれど、所詮、血は争えないと言う事だろうか。本人がああまでして嫌悪する片割れと、今の右成はよく似ている。
悪趣味で、陰惨で、悪辣で。
そしてどこか、まともじゃない。
「……返せよ」
右成の手からメモ用紙を毟り取る。
猛禽じみた目が、きろ、とその挙動を追った。そして、獲物を見定めて、見聞するみたいに、じいと俺を観察して。
「どうでも良いんだろ、いつも通りのプレーさえできれば」
その言葉に、漸く表情が動く。目を細め、俺の言葉の先を待っているようだった。
「できるの?」
「それ、俺に言ってるの?」
「あ?」
「俺より上手くなってから大口叩けって言ってんだよ、下手糞が。あんまイキんじゃねぇ」
顔を顰め、片眉を上げる。
数字は正直だ。守備成功率も、得点率も、ブロックの本数も。選手の技量、成果、貢献度全てを、詳らかに可視化してくれる。
俺がこいつよりもそれで劣っていたのなら、幾分か素直にその恫喝を受け入れる事はできたのだろうが。
分かってはいる。人を黙らせるために数字や事実を振り翳すのは、外道のする事だ。最も軽蔑されるべき蛮行。
けれど、しょうがないだろう。
お前みたいな生半可な人でなしが、1番癪に触るんだから。
バレーを理由に誰かを蔑ろにするのなら、誰をも黙らせる正当性と説得力が要る。
そうだろ?
「…………人でなしが」
右成は、今にも喉元に飛びかかってきそうな表情で唸る。けれども実際に飛びかかってくることも、反論してくる事もない。
バレーを主軸に置き、望んで殺伐とした価値観に生きる此奴こそ、それを1番肌で理解しているからだ。理解しているからこそ、俺を上回らない限り、俺に逆らう事ができない。此奴が今できる事は、黙って牙を研ぐ事だけだ。
やっと静かになった下手糞に、幾分か晴れやかな心でボールを投げる。
いつもよりピリついた空気感が、最高に気持ち良いと思った。
応援ありがとうございます!
10
お気に入りに追加
61
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる