あなたにおすすめの小説

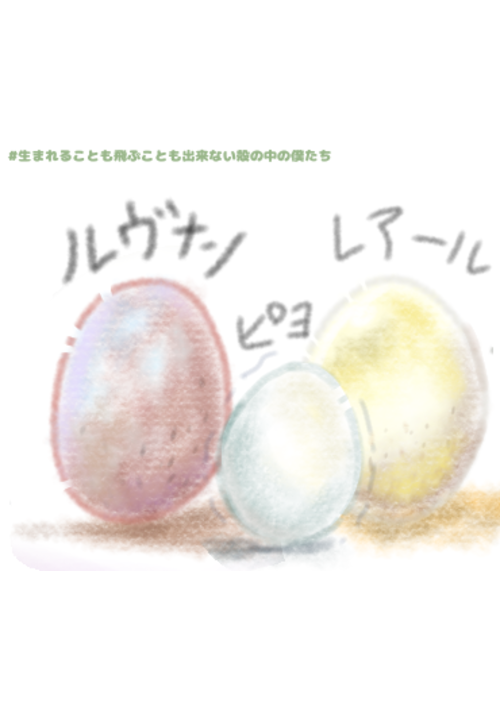
生まれることも飛ぶこともできない殻の中の僕たち
はるかず
児童書・童話
生まれることもできない卵の雛たち。
5匹の殻にこもる雛は、卵の中でそれぞれ悩みを抱えていた。
一歩生まれる勇気さえもてない悩み、美しくないかもしれない不安、現実の残酷さに打ちのめされた辛さ、頑張れば頑張るほど生まれることができない空回り、醜いことで傷つけ傷つけられる恐怖。
それぞれがそれぞれの悩みを卵の中で抱えながら、出会っていく。
彼らは世界の美しさを知ることができるのだろうか。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

アリアさんの幽閉教室
柚月しずく
児童書・童話
この学校には、ある噂が広まっていた。
「黒い手紙が届いたら、それはアリアさんからの招待状」
招かれた人は、夜の学校に閉じ込められて「恐怖の時間」を過ごすことになる……と。
招待状を受け取った人は、アリアさんから絶対に逃れられないらしい。
『恋の以心伝心ゲーム』
私たちならこんなの楽勝!
夜の学校に閉じ込められた杏樹と星七くん。
アリアさんによって開催されたのは以心伝心ゲーム。
心が通じ合っていれば簡単なはずなのに、なぜかうまくいかなくて……??
『呪いの人形』
この人形、何度捨てても戻ってくる
体調が悪くなった陽菜は、原因が突然現れた人形のせいではないかと疑いはじめる。
人形の存在が恐ろしくなって捨てることにするが、ソレはまた家に現れた。
陽菜にずっと付き纏う理由とは――。
『恐怖の鬼ごっこ』
アリアさんに招待されたのは、美亜、梨々花、優斗。小さい頃から一緒にいる幼馴染の3人。
突如アリアさんに捕まってはいけない鬼ごっこがはじまるが、美亜が置いて行かれてしまう。
仲良し3人組の幼馴染に一体何があったのか。生き残るのは一体誰――?
『招かれざる人』
新聞部の七緒は、アリアさんの記事を書こうと自ら夜の学校に忍び込む。
アリアさんが見つからず意気消沈する中、代わりに現れたのは同じ新聞部の萌香だった。
強がっていたが、夜の学校に一人でいるのが怖かった七緒はホッと安心する。
しかしそこで待ち受けていたのは、予想しない出来事だった――。
ゾクッと怖くて、ハラハラドキドキ。
最後には、ゾッとするどんでん返しがあなたを待っている。


童話絵本版 アリとキリギリス∞(インフィニティ)
カワカツ
絵本
その夜……僕は死んだ……
誰もいない野原のステージの上で……
アリの子「アントン」とキリギリスの「ギリィ」が奏でる 少し切ない ある野原の物語 ———
全16話+エピローグで紡ぐ「小さないのちの世界」を、どうぞお楽しみ下さい。
※高学年〜大人向き

【完結】またたく星空の下
mazecco
児童書・童話
【第15回絵本・児童書大賞 君とのきずな児童書賞 受賞作】
※こちらはweb版(改稿前)です※
※書籍版は『初恋×星空シンバル』と改題し、web版を大幅に改稿したものです※
◇◇◇冴えない中学一年生の女の子の、部活×恋愛の青春物語◇◇◇
主人公、海茅は、フルート志望で吹奏楽部に入部したのに、オーディションに落ちてパーカッションになってしまった。しかもコンクールでは地味なシンバルを担当することに。
クラスには馴染めないし、中学生活が全然楽しくない。
そんな中、海茅は一人の女性と一人の男の子と出会う。
シンバルと、絵が好きな男の子に恋に落ちる、小さなキュンとキュッが詰まった物語。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















