1 / 1
星の柩と最後の物語(ラスト・テイル)
しおりを挟む
第一章:崩れゆくインクの城
世界は「物語」でできている。それが比喩ではないことを、私は知っていた。空に浮かぶ太陽は太古の神が記した一行の修辞であり、大地は幾重にも重ねられた羊皮紙の層だ。だが今、そのインクは掠れ、世界は急速に「空白」へと還ろうとしていた。
私が住む空中図書館都市「ビブリオテカ」の最奥、賢人会議の間。重苦しい沈黙の中、羊皮紙が擦れる音だけが響いていた。
「エリアンよ。予言の時は来た」
ソーン長老がしわがれた声で告げた。円卓を囲むのは、冷ややかな視線を送る魔術師ベインと、不安げに髭を撫でる学者カエル。そして、彼らの中央で震えている幼い少女、盲目の予言者フィアだ。
「世界から色が失われている」フィアが虚空を見つめて呟く。「北の山脈はすでに『記述』を失い、ただの灰色の霧になったわ。物語が終わろうとしているの」
私は拳を握りしめた。「だから、私に行けと言うのですか。『原初のペン』を探しに」
「そうだ」ベインが冷たく言い放つ。「お前は稀代の『記述士』だ。現実を書き換える資格がある」
私の隣には、護衛として雇われた巨漢の騎士ガレスが控えていた。彼は剣の柄に手をかけ、不安げに天井を見上げている。「おい、記述士様。揺れてないか?」
その時だった。轟音と共に、図書館の巨大な書架が悲鳴を上げた。天井のフレスコ画――世界の創世記を描いた壮大な絵画――に、醜悪な亀裂が走る。亀裂の奥から滲み出してきたのは、黒でも白でもない、存在を否定するような「無」の色だった。
「モロスだ……! 『空白』が見つかった!」カエルが絶叫する。
崩落する瓦礫の中、銀髪の少女が音もなく私の前に降り立った。自動人形の司書、リラだ。彼女の琥珀色の義眼が回転し、焦点が私に合う。
「マスター・エリアン。逃走経路を算出。生存確率は3パーセント。急いで」
彼女が指差した先、出口である巨大な扉が、音を立てて「無」に侵食され始めていた。インクが水に溶けるように、扉の装飾がドロドロと崩れ落ちていく。
「走れ!」ガレスが叫び、私を突き飛ばした。
だが、私の視界の端で、逃げ遅れたソーン長老の体が「無」に触れた瞬間、彼は悲鳴さえ上げずに文字の羅列へと分解され、霧散してしまった。
第二章:エーテルの海、忘却の底へ
都市ビブリオテカは堕ちた。私たちはリラの導きで、都市の基部にある廃棄ダストシュートへと飛び込んだ。そこは、書き損じられた歴史や忘れられた伝承が沈殿する「エーテルの海」へと続いていた。
薄暗い紫色の霧が立ち込める荒野。ここが世界の最下層だ。私、リラ、ガレス、そして無理やり連れてこられた予言者フィアの四人は、頼りない足取りで進んでいた。
「……寒い」フィアがガレスの背中で震える。「ここには言葉がない。意味がないの」
「しっかりしろ」ガレスが剣で霧を払う。「俺たちが必ず守る」
リラが先頭を歩きながら、機械的な声で解説する。「ここは『校正の沼』。存在を許されなかった物語の墓場です。注意してください。彼らは、語られることを渇望しています」
その警告の直後、霧が凝縮し、人の形を成した。半透明の美しい女性――精霊セレーネだ。彼女はかつて英雄と呼ばれたが、歴史書から名前を消された亡霊だった。
「記述士さん」セレーネが哀しげに微笑み、私の頬に冷たい手を触れる。「貴方も消されに来たの? それとも、書き直しに来たの?」
「世界を救いに来た」私は答えた。「原初のペンはどこにある?」
セレーネは遠く、空中に浮かぶ逆さまの塔を指差した。「あそこ。『沈黙の塔』。でも気をつけて。あそこには彼がいる」
その時、地面――いや、古びた羊皮紙の地層が大きく揺れた。沼から無数の「黒い文字」が触手のように溢れ出し、私たちの足首を掴む。
「行け! ここは俺が食い止める!」
ガレスが剣を抜き、文字の触手を斬り裂く。だが、切った端から文字は増殖し、ガレスの鎧に『死』『終わり』『絶望』という単語を刻み込んでいく。
「ガレス!」
私が手を伸ばした瞬間、ガレスの足元の地面が裂けた。彼はニカッと笑い、親指を立てる。 「いい物語を書けよ、先生」
彼は文字の奔流に飲み込まれ、その存在自体が「段落の終わり」を示す記号へと変換されて消滅した。私たちは悲鳴を上げるフィアを引きずり、逆さまの塔へと走るしかなかった。
目の前で橋が崩れ落ち、対岸の塔への道が絶たれる。リラが私の腕を掴んだ。「跳びます。私を信じて」
第三章:物語の捕食者
逆さまの塔の内部は、重力が歪んでいた。階段は天井へと続き、窓の外には星々が下に見える。 私たちは、塔の中腹にある広大なアーカイブにたどり着いた。そこには、世界を侵食していたあの「無」が、玉座のように鎮座していた。
影そのものである男、モロスがそこにいた。彼は手に一冊の本を持っていた。表紙には何も書かれていない。
「ようこそ、エリアン」モロスの声は、耳ではなく脳髄に直接響くようだった。「無駄な足掻きだ。物語は終わるためにある。なぜ、それを引き伸ばそうとする?」
「終わらせるためじゃない。続けるためだ!」私が叫ぶ。
「続き?」モロスは嘲笑った。「見ろ、お前の連れているその人形を」
モロスが指を鳴らすと、リラの胸部装甲が強制的に展開された。そこには心臓の代わりに、光り輝く複雑な歯車と、一本の青白い巻物が埋め込まれていた。
「リラ……それは?」
リラは表情を変えずに言った。「私は司書ではありません。私は『原初のペン』の鞘(さや)です。そして、ペンを使うためのインクは、私の記憶中枢(メモリー)そのものです」
衝撃が私を貫く。世界を救う力を手に入れるには、リラという存在、彼女が私と過ごした全ての時間を消費しなければならないということか。
「残酷だろう?」モロスが影を伸ばし、フィアを捕らえようとする。「少女の予言も、騎士の犠牲も、すべては徒労だ。さあ、その人形を砕いてペンを取れ。それとも、ここで全員『空白』になるか?」
フィアが悲鳴を上げる。モロスの影が彼女の視力を、聴力を、そして存在を塗りつぶそうとしていた。
「選べ、記述士!」
私は懐剣を抜き、リラへと向けた。リラは静かに目を閉じ、受け入れるように胸を突き出す。 「マスター、世界のために」
私は叫び声を上げ、剣を振り下ろした――
第四章:犠牲と代償の天秤
金属音。 私の剣はリラの胸ではなく、彼女の足元の床――制御術式が刻まれた要石を貫いていた。
「なっ……!?」モロスが初めて動揺を見せた。
「私は記述士だ!」私は叫ぶ。「物語の結末は、私が決める! 犠牲の上に成り立つハッピーエンドなど、私が推敲(リライト)してやる!」
要石が砕け、塔の重力制御が崩壊する。空間がねじれ、モロスの影が物理的な実体を保てずに霧散し始めた。 「愚かな……! 秩序を壊せば、インクの海に溺れるぞ!」
「構わない!」
崩壊する塔の中、私はリラの手を引き、フィアを背負って最上階(重力的に言えば最下層)の「著者の間」へと走った。 だが、モロスの影は執拗だった。ドロドロとした暗黒が津波のように押し寄せる。
「マスター、計算外です。しかし……」リラが初めて、人間のように微笑んだ。「悪くありません」
最奥の扉。そこには『原初の語り部』が待つ空間があるはずだ。だが、扉を開くには時間がかかる。迫りくるモロスの影。
「私が止めます」 リラが足を止めた。
「ダメだ! 一緒に行くんだ!」
「いいえ。貴方は『書く』人、私は『守る』モノ。役割が違います」 リラは琥珀の瞳を輝かせ、体内のエーテル炉を暴走させた。全身が白熱し、神々しい光を放つ。 「行ってください、エリアン。そして、私を忘れない物語を書いて」
彼女は扉の前に立ち塞がり、迫りくる無限の闇へと両手を広げた。 「さようなら」
私はフィアと共に扉の中へと転がり込んだ。背後で凄まじい閃光が走り、そして重厚な扉が音を立てて閉ざされた。 扉の向こうから、リラが砕け散る音と、モロスの断末魔が聞こえた気がした。そして、完全な静寂が訪れた。
目の前には、ただ一つの机と、古びた羽ペン。 そして、その奥に佇む、顔のない人影。
第五章:白紙の上の最初の一行
顔のない人影――**原初の語り部(ファースト・オーサー)**は、静かに言った。声は、若いようでもあり、老いているようでもあった。
「よく来たね、記述士。そして、予言の子よ」
部屋は真っ白だった。壁も床もなく、ただ無限の白紙が広がっている。 「リラは……死んだのか?」私の声は震えていた。
「彼女は物語の一部になった」語り部は淡々と答える。「古い物語は閉じられた。モロスという『空白』もまた、次のページをめくるために必要な機能だったのだよ」
語り部は机上の羽ペンを私に差し出した。 「世界は寿命を迎えた。修復は不可能だ。だが、君には『次』を書く権利がある。どんな世界にする? 魔法が満ちる世界か? 機械の理性が支配する世界か? それとも……」
私はペンを受け取った。その重みは、リラの命の重みだ。ガレスの、ソーン長老の、消えていったすべての人々の重みだ。 隣でフィアが、見えない目で私を見つめている。「エリアン、貴方が望む世界を」
私は震える手で、インク壺にペンを浸した。 完全な理想郷を作ることもできた。悲しみのない世界を。 だが、私は思い出す。ガレスの最期の笑顔を。リラの計算外の微笑みを。喪失の痛みこそが、私たちが生きた証だった。
「完璧な世界はいらない」
私は羊皮紙にペンを走らせた。 新しい世界。そこにはやはり夜があり、別れがあり、死があるだろう。しかし、星を見上げる者がいて、過去を語り継ぐ図書館がある世界だ。
インクが紙に染み込むと同時に、白い部屋が色づき始めた。青い空、緑の大地、そして風の匂い。 私の体も、フィアの体も、光の粒子となって解けていく。私たちは新しい物語の登場人物へと再構成されていくのだ。
意識が消える直前、私は最後の一文を記した。 それは、かつて私を守ってくれた、ある自動人形の瞳の色についての描写だった。
――そして、新しい朝が来る。 私は目覚める。枕元には古びた一冊の本。 タイトルは『星の柩と最後の物語』。 著者の名前は消えて読めないが、表紙には琥珀色の石が一つ、優しく埋め込まれていた。
世界は「物語」でできている。それが比喩ではないことを、私は知っていた。空に浮かぶ太陽は太古の神が記した一行の修辞であり、大地は幾重にも重ねられた羊皮紙の層だ。だが今、そのインクは掠れ、世界は急速に「空白」へと還ろうとしていた。
私が住む空中図書館都市「ビブリオテカ」の最奥、賢人会議の間。重苦しい沈黙の中、羊皮紙が擦れる音だけが響いていた。
「エリアンよ。予言の時は来た」
ソーン長老がしわがれた声で告げた。円卓を囲むのは、冷ややかな視線を送る魔術師ベインと、不安げに髭を撫でる学者カエル。そして、彼らの中央で震えている幼い少女、盲目の予言者フィアだ。
「世界から色が失われている」フィアが虚空を見つめて呟く。「北の山脈はすでに『記述』を失い、ただの灰色の霧になったわ。物語が終わろうとしているの」
私は拳を握りしめた。「だから、私に行けと言うのですか。『原初のペン』を探しに」
「そうだ」ベインが冷たく言い放つ。「お前は稀代の『記述士』だ。現実を書き換える資格がある」
私の隣には、護衛として雇われた巨漢の騎士ガレスが控えていた。彼は剣の柄に手をかけ、不安げに天井を見上げている。「おい、記述士様。揺れてないか?」
その時だった。轟音と共に、図書館の巨大な書架が悲鳴を上げた。天井のフレスコ画――世界の創世記を描いた壮大な絵画――に、醜悪な亀裂が走る。亀裂の奥から滲み出してきたのは、黒でも白でもない、存在を否定するような「無」の色だった。
「モロスだ……! 『空白』が見つかった!」カエルが絶叫する。
崩落する瓦礫の中、銀髪の少女が音もなく私の前に降り立った。自動人形の司書、リラだ。彼女の琥珀色の義眼が回転し、焦点が私に合う。
「マスター・エリアン。逃走経路を算出。生存確率は3パーセント。急いで」
彼女が指差した先、出口である巨大な扉が、音を立てて「無」に侵食され始めていた。インクが水に溶けるように、扉の装飾がドロドロと崩れ落ちていく。
「走れ!」ガレスが叫び、私を突き飛ばした。
だが、私の視界の端で、逃げ遅れたソーン長老の体が「無」に触れた瞬間、彼は悲鳴さえ上げずに文字の羅列へと分解され、霧散してしまった。
第二章:エーテルの海、忘却の底へ
都市ビブリオテカは堕ちた。私たちはリラの導きで、都市の基部にある廃棄ダストシュートへと飛び込んだ。そこは、書き損じられた歴史や忘れられた伝承が沈殿する「エーテルの海」へと続いていた。
薄暗い紫色の霧が立ち込める荒野。ここが世界の最下層だ。私、リラ、ガレス、そして無理やり連れてこられた予言者フィアの四人は、頼りない足取りで進んでいた。
「……寒い」フィアがガレスの背中で震える。「ここには言葉がない。意味がないの」
「しっかりしろ」ガレスが剣で霧を払う。「俺たちが必ず守る」
リラが先頭を歩きながら、機械的な声で解説する。「ここは『校正の沼』。存在を許されなかった物語の墓場です。注意してください。彼らは、語られることを渇望しています」
その警告の直後、霧が凝縮し、人の形を成した。半透明の美しい女性――精霊セレーネだ。彼女はかつて英雄と呼ばれたが、歴史書から名前を消された亡霊だった。
「記述士さん」セレーネが哀しげに微笑み、私の頬に冷たい手を触れる。「貴方も消されに来たの? それとも、書き直しに来たの?」
「世界を救いに来た」私は答えた。「原初のペンはどこにある?」
セレーネは遠く、空中に浮かぶ逆さまの塔を指差した。「あそこ。『沈黙の塔』。でも気をつけて。あそこには彼がいる」
その時、地面――いや、古びた羊皮紙の地層が大きく揺れた。沼から無数の「黒い文字」が触手のように溢れ出し、私たちの足首を掴む。
「行け! ここは俺が食い止める!」
ガレスが剣を抜き、文字の触手を斬り裂く。だが、切った端から文字は増殖し、ガレスの鎧に『死』『終わり』『絶望』という単語を刻み込んでいく。
「ガレス!」
私が手を伸ばした瞬間、ガレスの足元の地面が裂けた。彼はニカッと笑い、親指を立てる。 「いい物語を書けよ、先生」
彼は文字の奔流に飲み込まれ、その存在自体が「段落の終わり」を示す記号へと変換されて消滅した。私たちは悲鳴を上げるフィアを引きずり、逆さまの塔へと走るしかなかった。
目の前で橋が崩れ落ち、対岸の塔への道が絶たれる。リラが私の腕を掴んだ。「跳びます。私を信じて」
第三章:物語の捕食者
逆さまの塔の内部は、重力が歪んでいた。階段は天井へと続き、窓の外には星々が下に見える。 私たちは、塔の中腹にある広大なアーカイブにたどり着いた。そこには、世界を侵食していたあの「無」が、玉座のように鎮座していた。
影そのものである男、モロスがそこにいた。彼は手に一冊の本を持っていた。表紙には何も書かれていない。
「ようこそ、エリアン」モロスの声は、耳ではなく脳髄に直接響くようだった。「無駄な足掻きだ。物語は終わるためにある。なぜ、それを引き伸ばそうとする?」
「終わらせるためじゃない。続けるためだ!」私が叫ぶ。
「続き?」モロスは嘲笑った。「見ろ、お前の連れているその人形を」
モロスが指を鳴らすと、リラの胸部装甲が強制的に展開された。そこには心臓の代わりに、光り輝く複雑な歯車と、一本の青白い巻物が埋め込まれていた。
「リラ……それは?」
リラは表情を変えずに言った。「私は司書ではありません。私は『原初のペン』の鞘(さや)です。そして、ペンを使うためのインクは、私の記憶中枢(メモリー)そのものです」
衝撃が私を貫く。世界を救う力を手に入れるには、リラという存在、彼女が私と過ごした全ての時間を消費しなければならないということか。
「残酷だろう?」モロスが影を伸ばし、フィアを捕らえようとする。「少女の予言も、騎士の犠牲も、すべては徒労だ。さあ、その人形を砕いてペンを取れ。それとも、ここで全員『空白』になるか?」
フィアが悲鳴を上げる。モロスの影が彼女の視力を、聴力を、そして存在を塗りつぶそうとしていた。
「選べ、記述士!」
私は懐剣を抜き、リラへと向けた。リラは静かに目を閉じ、受け入れるように胸を突き出す。 「マスター、世界のために」
私は叫び声を上げ、剣を振り下ろした――
第四章:犠牲と代償の天秤
金属音。 私の剣はリラの胸ではなく、彼女の足元の床――制御術式が刻まれた要石を貫いていた。
「なっ……!?」モロスが初めて動揺を見せた。
「私は記述士だ!」私は叫ぶ。「物語の結末は、私が決める! 犠牲の上に成り立つハッピーエンドなど、私が推敲(リライト)してやる!」
要石が砕け、塔の重力制御が崩壊する。空間がねじれ、モロスの影が物理的な実体を保てずに霧散し始めた。 「愚かな……! 秩序を壊せば、インクの海に溺れるぞ!」
「構わない!」
崩壊する塔の中、私はリラの手を引き、フィアを背負って最上階(重力的に言えば最下層)の「著者の間」へと走った。 だが、モロスの影は執拗だった。ドロドロとした暗黒が津波のように押し寄せる。
「マスター、計算外です。しかし……」リラが初めて、人間のように微笑んだ。「悪くありません」
最奥の扉。そこには『原初の語り部』が待つ空間があるはずだ。だが、扉を開くには時間がかかる。迫りくるモロスの影。
「私が止めます」 リラが足を止めた。
「ダメだ! 一緒に行くんだ!」
「いいえ。貴方は『書く』人、私は『守る』モノ。役割が違います」 リラは琥珀の瞳を輝かせ、体内のエーテル炉を暴走させた。全身が白熱し、神々しい光を放つ。 「行ってください、エリアン。そして、私を忘れない物語を書いて」
彼女は扉の前に立ち塞がり、迫りくる無限の闇へと両手を広げた。 「さようなら」
私はフィアと共に扉の中へと転がり込んだ。背後で凄まじい閃光が走り、そして重厚な扉が音を立てて閉ざされた。 扉の向こうから、リラが砕け散る音と、モロスの断末魔が聞こえた気がした。そして、完全な静寂が訪れた。
目の前には、ただ一つの机と、古びた羽ペン。 そして、その奥に佇む、顔のない人影。
第五章:白紙の上の最初の一行
顔のない人影――**原初の語り部(ファースト・オーサー)**は、静かに言った。声は、若いようでもあり、老いているようでもあった。
「よく来たね、記述士。そして、予言の子よ」
部屋は真っ白だった。壁も床もなく、ただ無限の白紙が広がっている。 「リラは……死んだのか?」私の声は震えていた。
「彼女は物語の一部になった」語り部は淡々と答える。「古い物語は閉じられた。モロスという『空白』もまた、次のページをめくるために必要な機能だったのだよ」
語り部は机上の羽ペンを私に差し出した。 「世界は寿命を迎えた。修復は不可能だ。だが、君には『次』を書く権利がある。どんな世界にする? 魔法が満ちる世界か? 機械の理性が支配する世界か? それとも……」
私はペンを受け取った。その重みは、リラの命の重みだ。ガレスの、ソーン長老の、消えていったすべての人々の重みだ。 隣でフィアが、見えない目で私を見つめている。「エリアン、貴方が望む世界を」
私は震える手で、インク壺にペンを浸した。 完全な理想郷を作ることもできた。悲しみのない世界を。 だが、私は思い出す。ガレスの最期の笑顔を。リラの計算外の微笑みを。喪失の痛みこそが、私たちが生きた証だった。
「完璧な世界はいらない」
私は羊皮紙にペンを走らせた。 新しい世界。そこにはやはり夜があり、別れがあり、死があるだろう。しかし、星を見上げる者がいて、過去を語り継ぐ図書館がある世界だ。
インクが紙に染み込むと同時に、白い部屋が色づき始めた。青い空、緑の大地、そして風の匂い。 私の体も、フィアの体も、光の粒子となって解けていく。私たちは新しい物語の登場人物へと再構成されていくのだ。
意識が消える直前、私は最後の一文を記した。 それは、かつて私を守ってくれた、ある自動人形の瞳の色についての描写だった。
――そして、新しい朝が来る。 私は目覚める。枕元には古びた一冊の本。 タイトルは『星の柩と最後の物語』。 著者の名前は消えて読めないが、表紙には琥珀色の石が一つ、優しく埋め込まれていた。
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します
namisan
ファンタジー
バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。
マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。
その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。
「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。
しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。
「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」
公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。
前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。
これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。


元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。
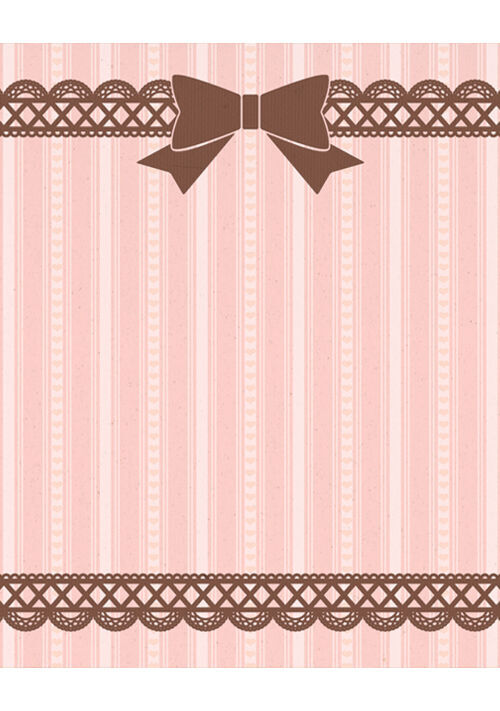
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

それは思い出せない思い出
あんど もあ
ファンタジー
俺には、食べた事の無いケーキの記憶がある。
丸くて白くて赤いのが載ってて、切ると三角になる、甘いケーキ。自分であのケーキを作れるようになろうとケーキ屋で働くことにした俺は、無意識に周りの人を幸せにしていく。

新緑の光と約束~精霊の愛し子と守護者~
依羽
ファンタジー
「……うちに来るかい?」
森で拾われた赤ん坊は、ルカと名付けられ、家族に愛されて育った。
だが8歳のある日、重傷の兄を救うため、ルカから緑の光が――
「ルカは精霊の愛し子。お前は守護者だ」
それは、偶然の出会い、のはずだった。
だけど、結ばれていた"運命"。
精霊の愛し子である愛くるしい弟と、守護者であり弟を溺愛する兄の、温かな家族の物語。
他の投稿サイト様でも公開しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















