9 / 25
本編
第九話 白花の勇者(1)
しおりを挟む
軍都から王都へは六時間ほどの距離である。
休みなく馬を走らせたゼファーの率いる隊列は、朝焼けの中、王都の門をくぐった。
空に、明けの明星が輝いていた。
王都の大通り。城へ続くその道は、ひどい有様だった。
道端には帰る家を失ったのであろう民が、傷を抱えて朝焼けの中、断続的なうめき声と、荒んだ視線で王の隊列を測るように見ていた。
「陛下…どうか、ご許可を」
クロードが騎馬から降りて、ゼファーを見上げた。その眼差しは、真にゼファーの許しを待っているというよりは、許しを得ることを、確信している目つきだった。
ゼファーは頷いた。クロードの手は、すでに癒炎剣へと触れている。
「民よ、聞け!これより癒焔剣アレストの使い手がゆく。傷を負った者は白い炎を恐れるな!その焔は癒す力、当代ユーノヴェルト辺境伯クロードの慈悲である!」
ゼファーの声は強く、それこそ雷のように響き渡った。顔を伏せていたいくらかの民が、顔を上げた。
とん、とクロードは荒れた道の上で、歩を進める。
そしてその腰の帯剣を、抜いた。
「どうぞどなたもお近くへ!みな等しく我が主君の民、同じ王に拝す者!身分も職も隔たりなく、私の力が及ぶ限り、その傷を癒すと誓いましょう!」
地面を撫でるように振るったアレストの剣先から、ふわりと白い花弁のように癒炎が立ち上がる。
ゆっくりと、クロードは歩を進める。ほとんどただ剣を振るだけの剣舞は、癒炎を送り出す風の具現化のようであった。
「…お、おお…!!」
触れた怪我人の、感嘆の声が上がる。
「ほんとだ!本当に、治ったぞ…!!」
「この辺りにいるのは軽症者のようだな。体を動かせぬ重症者はどっちだ」
騎馬より降りて尋ねたゼファーに、怪我を負っていた男は、恐縮して視線を下に落とした。
「へ、へぇ…教会の方に皆運ばれていきました…!」
「そうか。クロード、聞こえたか」
「はい。向かいます」
剣舞を続けながら、クロードは頷いた。
「治癒術師と弓騎士隊はクロードと共に教会へ向かい、治療と救助に当たれ。槍騎士隊と魔術師は私と共に王城へ。王都騎士と連携を取り、周辺の魔物を掃討する」
ゼファーは再び愛馬に跨った。王都は広く、王城へと向かうには、城下町よりさらに奥へ進む必要がある。
「ご武運を」
「ああ、お前も」
短く言葉を交わし、二人の神剣使いはそれぞれの戦場へと向かうこととなった。
シアンが教会の扉を開いた時、その中は血の匂いとうめき声で溢れていた。老いも若きも、男も女も関係なく、痛みと苦しみでうめき、そして泣き喚く者すらいた。
「ああ……軍都の治癒術師隊ですか……」
「と、弓騎士隊だ。助っ人が来たっていうのに、ずいぶんと浮かない顔だな」
司祭服を血で汚した男が、覇気なく言うのに、シアンは常の短気を抑えた声で問いかけた。
「もう掛けられる分の治癒術は掛けました。これ以上は魔力負荷に耐えられません。…あとは患者本人の体力次第です」
男の他にも司祭服を来た者たちは、ぐったりと項垂れている。相当に厳しい状況だったことが伺い知れた。
「シアン副隊長。司祭殿の言う通りかと。やれることはやっていただいたようです」
「ならこっちで俺たちが出来ることはないか。坊ちゃん、任せていいな」
「はい」
「よ、よしたまえ、本当に魔力負荷の限界なんだ。これ以上治癒魔法を掛ければ、細胞が耐えられずに壊死する」
「心配すんな。坊ちゃんの炎は……奇跡ってやつだ」
クロードが、再びアレストを抜いた。
剣舞で白炎を振るう姿を、朝日を通したステンドグラスの光が照らしている。
そうするとまるで、本当に奇跡のようだった。クロード自身が燃えて、人を癒す炎と化しているような、そんな錯覚を覚えるほど。
「な……な、あれ、は……」
白炎が空中で分かたれて、花びらのように舞う。その光は、吸い込まれるように傷に寄り添い、幾人もの傷を治していった。
「……な?奇跡、だろ」
「もしや、あれは……っ、もう一本の、神剣、なのですか……っ!」
司祭はすぐに、アレストのことを思い至ったようだった。あるいは、いまここにアレストの使い手が現れてくれればと、願っていたのかもしれない。
「そうらしいぞ。それじゃ、弓騎士隊は手分けして救助活動に移るとするかな。コンビ組んで、治癒術師と行動しろ。魔力負荷限界に達しても重症の人間は教会に運び込む。坊ちゃん!いいか?」
「はい。お願いします」
手早く段取りを決めたシアンに、クロードは剣舞を止めぬまま、微笑で頷いた。
救助活動は日が高くなっても続いた。
何せ広い王都である。怪我人を受け入れていた教会も一つだけでなく、クロードは動かせぬ重傷者がいると聞けば、何度も場所を変えて治療に走った。
その距離は王都城下町をぐるりと一周。時間は太陽が一番高く昇る頃である。
シアンは弓騎士隊と治癒術師たちに順番で昼食と休憩を取らせた。もちろんクロードにも。
そうして、クロードと交代でシアンが最後に休憩をとった頃には、もう夕暮れが迫っていた。
クロードがいまだ運び込まれてくる怪我人の治療を治癒術師たちと進めていた、その時である。
空を、一筋の雷が走った。
「きゃっ!?」
「こ、こんな時に雷まで…!!」
「雨も降ってないってのに……!」
教会に集まった人々の表情が恐怖に染まる。それほどの、威圧感。だがその稲光を、クロードはよく知っていた。
「……陛下」
いくつもの雷光が走る。それが落ちるのが王都城下町の外側だと言うことに気づき、内部の安全を確保した上での掃討なのだろう、とクロードは見当をつけた。
「あれは、陛下の迅雷剣ハルファドです。外に余程の大物がいたのかもしれません」
クロードは手を止めて、動揺する人々に告げる。そのこめかみを、汗が伝ってぽたり、と落ちた。
「だ、大丈夫なのですか……!?」
「信じてお待ちしましょう。陛下は僕より余程、神剣の扱いに慣れていらっしゃいます」
クロードが微笑めば、途端安堵の空気が流れる。この奇跡のような癒しの炎を使う使い手が言うならば、とその目が物語っていた。
「坊ちゃん、休憩交代だ。」
「シアン殿。まだお休みにならなくていいのですか」
シアンのとった休憩は、他の隊員より遥かに少なかった。というのに、その顔に疲れはなく、不敵に笑う余裕さえあった。
「あの冷血将軍に連れ回された経験なら、今回が始めてじゃないんでね。強行軍は慣れてる」
「ですが……」
「夜に備えてろ。次にもう一波あったら、あんたには死ぬほど働いてもらうことになるんだからな」
「わかりました。重傷の方がいらっしゃいましたら、叩き起こしてください」
「おう。容赦なく叩き起こすから安心してろ」
シアンの遠慮のない言葉に、クロードは安心してアレストを剣に収めた。
白い炎がふわりと舞い散って、クロードは息を吐きだす。ど、と急に体に疲労がのしかかって、膝が笑う。
「おーい、肩貸そうか坊ちゃん」
「いえ、大丈夫です、これぐらいで弱音は言えませんから」
クロードがきっぱりと断れば、シアンもそれ以上は何も言わず、傷に残った負傷者に、消毒や包帯を施すための作業に移っていった。
ぱた、ぱたた、とクロードのこめかみから汗が止めどなく溢れる。それは木の床に吸い込まれてすぐに乾く。クロードは、厚意で借りることのできた教会の司祭の私室に滑り込み、そのまま体を倒した。体が、鉛のように重い。途中からは自分に対しても癒炎の力を振るって疲労を誤魔化していたが、それも限界はある。
ほとんど一日中、アレストを振るっていた。だが、お陰で実践での振るい方の感覚も掴み始めていた。クロードは疲労でぼんやりとする頭で、充足感を感じつつ、窓の外を走る、青雷を見上げた。
「……きれいだ」
ほとんど無意識で呟いて、クロードは目を閉じた。
ゼファーの体の周りを、青白い雷光が覆っていた。
ハルファドを本気で振るう時には、雷光の鎧を纏うのが常だった。誰のサポートも期待は出来ない。特に、ユリウスやロベルトという規格外の能力を持つ猛者がいないこの場において。
相対する大型の魔物は、この日ゼファーが何度となく撃破してきた種であった。
一つ目の異形の巨人。それは過去にも何度か討伐したことのあるゼファーだったが、奇妙だ、と感じていた。本来ならば、このように群れを成す魔物ではない。
剣術のみで、手足の自由を奪い、鋼鉄の心の臓に向けては、ハルファドの雷撃を。
轟音と共に雷撃を叩き込んで、ゼファーは一息ついた。
その頭上に、翼持つ魔物が舞う。面倒な。ゼファーがハルファドにバチリと稲光を纏わせる。
だがその光が放たれる前に、一筋の光がその魔物を貫く。若葉色のその光に思いあたりがあり、ゼファーはハルファドの雷撃を、短い感覚で七回、鳴らした。
ほとんど音だけのそれは、昔からの合図であった。
迅雷剣ハルファドを、納刀する。戦場の終わりのその合図である。
「ほんっとめちゃくちゃだぜ、神剣ってやつは」
「シアン。クロードはどうした」
「いま少し休ませてますよ。負傷者も落ち着いて来たんでね。治癒術師で回してます」
しばらくもせずに現れたシアンは、その弓の弦に光を灯していた。ロベルトのものより黄色みがかった緑のその光は、シアンの眼の色とよく似ている。
「ならばいい。今ので近くに見える大型は全て倒した。一度王都に戻る」
「じゃあ王城の門番に伝えてきましょうか」
「いらん。魑魅魍魎の巣では休まるものも休まらぬ」
「ハハ。じゃあ、あの坊ちゃんのベッドにでも入ります?」
ふざけて言ったシアンに、ゼファーは嫌な顔をする。元よりシアンが口の減らない男であるのは知っているものの、クロードをも巻き込んだ軽口に、ゼファーは酷く腹立たしいものを覚えて、返す言葉にことさら冷たさが乗ることとなった。
「妙な邪推をするな」
「邪推じゃねえだろ。気付いてんだろ、あんた」
おそらく、時間だけで言えば、軍都で一番クロードと共にいたのはシアンだ。だから、クロードの変化に一番に気付くとすればシアンであるのは想像に難くなく、ゼファーは否定の反論を失った。
「抱いちまえよ。満更でもないくせに、あんたらしくもない」
「立場や状況を考えろ。そもそも成年もしていない子どもを相手にするか」
「あんたがそんなこと気にするようになったとはね。言い寄ってくるバカ全部食って、道化野郎が青筋立ててキレてたの知ってんだぞ、こっちは」
「ユリウスのあれは怒ったふりだ。金や体目当ての相手ならば何人いようが気に留めてないぞ、あれは」
シアンは肩を竦めた。ゼファーのユリウス評を信じているのかいないのか、ただそこの事情はどうでもいいと言わんばかりに。
「じゃあ坊ちゃんは?」
「しつこいぞ」
「しつこくするね。あんた絶対、あの坊ちゃんを逃がしたら後悔するぜ」
ふざけた声色を消したシアンの目を、ゼファーはじっと見返した。この目が、ずっとロベルトを追っているのを知っている。
「……だとしても、今ではない、だろう」
「は、ずりぃ年上って感じ」
「私も扱いかねている。お前もあまり追求するな」
ゼファーは思ったままを告げた。クロードの好意については、それこそシアンの言う通り満更でもない。
だが、肉体的な接触ともなると、今までのクロードとの関係がそこに集約してしまうのが、惜しいと思っていた。
だから、その感情の名を知らぬ王は、ただただ心地良いクロードの好意を受け取って、その暖かさに心を揺らすだけに留めていた。
「いやもうそこまで行ってんなら、抱ける時に抱いとけよ」
「手を出せば、クロードにとっての私が、好意に胡座をかいて未成年に手を出した男になるのだが?一生消せぬぞ、それは」
「……あ?」
肉体的な接触をすることに抵抗はないし、クロードも否を言わないであろう、という確信がゼファーにはある。
だが、十年後、二十年後。聡明を深めているだろうクロードの姿は想像に容易く、その彼が、そのような乱れた行いに眉を顰めるのまで、目に見えるようだった。
「いや、あんた、それは……それはさあ……いや、悪ィ、マジですんません、そんな純な感じとは思わなくて……」
「ぐちゃぐちゃ言うなら最初から口出しをするな」
散々好き勝手言ったシアンが急にもごもごと口ごもるので、ゼファーは鬱陶しそうに言い放った。実際かなり鬱陶しかったので。
「いやそれは自分の過去の行いを振り返ってくれねぇかな」
「やかましい。お前こそロベルトとのことをいい加減どうにかしろ」
「……ッス、それはマジで、はい……」
痛い所を突かれて、シアンは黙った。王から見れば、シアンの方こそはっきりさせるべき頃合いだと思っていた。
何せ、それこそゼファーですら成人する前からのことなので。
シアンからクロードの滞在する場所を聞き、ゼファーは一直線にその教会へと向かった。もはやからかう気力もないのか、シアンは王を送り出して、自身は教会の外側に見張りに立った。
静かに礼拝堂の扉を開けば、月の光が差す。
微かに聞こえたのは、低く甘い歌声だった。
アレストを腕に抱いたクロードが、目を伏せて子守唄を歌っていた。癒炎の白い炎が花弁のように舞い、その顔を柔らかに照らしている。
ゼファーは息を呑んだ。まるで見知らぬ異国の宗教画のような風景であった。
一歩、ゼファーが歩を進めると、青い瞳が開いてクロードが微笑んだ。
「…陛下。ご無事で」
「ああ。…まだ治療が必要な者がいたか」
「命に関わる方はどうにか終えました。これは沈痛と導眠のために」
「そこまでコントロール出来るようになったか」
「実践が何よりの教師とも言いますから」
クロードの顔に、疲労が滲んでいる。だが、充足感もある表情だった。得られるものも大きかったか、とゼファーは読み取って、そのクロードの隣に腰を下ろす。祭壇前の段差に、この国でも高位の家格の二人が並んだ。
長椅子に座って眠る怪我人たちは、どれも穏やかな寝顔であった。
「戦況はいかがでしたか」
「軍都の精鋭を以てすれば大したことはなかった。…が、妙な気配はあったな。群れを作らぬ大型の魔物が隊列を組んでいた」
「それは……」
「本当に、魔竜の件と関係があるやもしれん」
魔竜復活の前から、魔物が凶暴化するという記録は救世主伝説の一節にも組み込まれている。それを鎮めたのが救世主の力であったというのも。
だが今、この国に救世主はいない。ならば、持ちうる戦力で戦うしか術はなかった。
「まあ、なにはともあれ状況が収まってからだな。明日正午までに新たな襲撃がなければ、大臣たちを招集する。来れるな、クロード」
「はい」
クロードの顔に、僅かに緊張が走った。
今までのクロードの来歴からして、他の貴族との交流が希薄なのは歴然としている。
それが突然、戦局だけでなく政局をも変えうる神剣の使い手として、国政の中心に立つのだ。緊張するなという方が無理で、だが慌てふためかないのは、クロードの思慮深さの表れだった。
「少し休む、肩を貸せ」
「陛下、このようなところでなくとも………」
「私にとって、お前の隣より安全な場所がこの王都にはないのでな」
かっ、とクロードの頬が紅潮した。少年らしい純朴な反応に気をよくして、ゼファーは喉を鳴らして笑った。
「僕の肩などでよければ、いくらでも。おやすみなさいませ、陛下」
「ああ、おやすみ」
白い炎の端を見ながら、ゼファーは目を閉じた。
再び、低く甘い歌声が掠れて響く。
目を開けば、子どもたちが団子のように目の前に群がっていて、ゼファーは声を掛けようか迷った。自分が、それほど子どもに好かれる方ではない自覚があったので。
だが、子どもたちはヒソヒソと内緒話をしながら、そこから離れる気配はない。仕方なしに、ゼファーは声を掛けることにした。
「……何か、クロードに用か?」
「きゃっ」
驚きの声が上がるのは、想定通り。隣の体温がぬるく、まだ眠りの中にあるのをわかっていたので、用事があるのならばそちらだろう、と見当を付けて問うた。
「ええと、あの」
子どもたちの中でも年長の方だろう少女が、震えながら声を上げた。ゼファーは急いて問い返しはせずに、黙って続きを待つ。
そのゼファーに、ずい、と野花のブーケが差し出される。
「白いお花の勇者さまに、どうぞ!」
ゼファーの手に押し付けるようにしてそれを預けると、少女は周りの子どもたちと共に駆け出して行った。
色とりどりの野花はどれも子どもの高い体温でくたりとしおれかけている。だが、この状況下で子どもが出来る返礼として最大のものであろう、とゼファーはクロードの奮闘に思いを馳せた。
「白いお花の勇者様、か」
アレストの癒炎がそう見えたのだろう。あの白光だけを見れば、あの神剣が、恐ろしい破壊の力をも秘めているとは思いもよらぬことだろう。
ゼファーは、野花のブーケから一本、白い花を抜き出した。それを、まだ眠りの中にある、クロードの赤毛に差し込んだ。
クロードは、それに気づかずに眠っている。だからゼファーも、今一度眠りについたのだった。
王都王城。
その荘厳たる美麗な宮殿に入った途端、クロードが顔を顰めたので、シアンは笑い出すのを堪える羽目になった。
城下町の惨状とは比べものにならぬほど安寧に守られたそこは、傷の一つもなければ、怪我人の一人もおらず、ここだけが重点的に守られていたのだと分かる。
王宮には貴族たちが避難してきており、そこここで様々なざわめきがあった。
興味関心、が一番強いだろう。ゼファーは戴冠からほとんどを軍都で過ごした。故に、主だった官職についた者以外は王の姿を見たことをない者も多い。
ざわめきの中に、侮りの視線をいくつか感じて、シアンは呆れた。この場にいる誰も彼もが、ゼファーを野蛮な将軍と、次代を担う女王が君臨するまでの繋ぎの王としか見ていない。
もし本当にそうであれば、この聡明な少年が付き従うはずもなかったはずだ。険しい顔をしたクロードを横目で眺めながら、シアンは護衛として表情も気配もなるべく消して、二人の貴人に付き従った。
そこに、軽やかな足取りで歩み寄る少女がいた。少女の髪は、王と同じ紺碧だった。
「叔父上」
「セシリア、無事だったか」
皇太女セシリア。ゼファーの姪であり、先王の娘である。金色の瞳が、王と良く似ていた。
シアンは何度か会ったことがあるが、その頃のお転婆は身を潜め、年頃の姫君らしい淑やかさで挨拶をする少女に、月日の流れを感じた。確か今年で十五だったか。シアンは胸中で指折り数える。
「騎士たちの尽力です。叔父上、この度は救助要請に拙速を以て応えて頂き、感謝致します」
「苦労をさせたな。私が軍都の方にばかり、精鋭の兵を連れて行ったばかりに」
王の皮肉に、姫君は曖昧な笑みだけを返した。
クロードには伝えなかったことだが、王都の騎士はそのほとんどが貴族の子女の名誉職と化しており、統制が取れているとは言えぬ有様であった。そのことを姫君もわかっているのだろう。
そのため、主な戦力と言えば王都騎士団よりも教会所属の聖堂騎士であった、そのため、防戦一方になったというのが、王とシアンの共通の見解であった。
本来ならば、守りに特化した聖堂騎士と、攻めに長けた王都騎士団の両輪を以て魔物の襲撃に反撃するのが理想である。だがこの状況では、聖堂騎士たちは奮闘した方とも言えた。
「それより叔父上、こちらの方をご紹介して頂いても?ーー…兵たちの話によれば癒炎剣アレストを、お持ちだとか」
姫君がよく通る声でそう告げれば、周囲にざわめきが広がる。癒炎剣アレスト。二千年の間、使い手が現れなかった神剣。その使い手が現れた。
その影響を分かっていて、セシリアは言ったのだろう。周囲のざわめきを気にすることもなく、クロードに微笑みかけた。
「耳が早いな。クロード、姪のセシリアだ。名ぐらいはお前の領地にも届いているかと思うが」
「はい」
クロードは微笑んで、膝を折って拝礼した。シアンは引いた。まるで演劇のような完璧な所作にすぎて、いっそ茶番めいていたからだ。
「初めてお目にかかります、セシリア皇太女殿下。ユーノヴェルト辺境伯クロードと申します。国王陛下のお赦しを頂き、癒炎剣アレストを帯剣させて頂いております」
わずかに掠れたクロードの声が、涼やかに姫君に告げる。過不足ない挨拶に、セシリアは満足げに頷き、完璧な淑女の笑みを見せた。
「……アレストをお抜きになるまで、ご苦労があったことと思います。この度の件におきましても、叔父をお支え頂き、礼を申し上げます。どうぞお立ちください」
「はい」
クロードが背を正し、若い二人は並び立った。冗談のように、完璧な姫君と騎士の物語の、絵画の如き二人だった。
ざわめきは色を変える。
まあ焦るわな。シアンは白けた。癒炎剣アレストを振るって王都の民を救った勇者。それだけで姫君の相手に足る勇名である。つまり王都在住の貴族たちの駆け引きの外から現れた、埒外の候補者となりうる。
ただ、当の本人といえば隣の巨漢に夢中なわけだが。
「叔父上、これから今後に関わる重要な話をなさるとお伺いしました。私も同席してよろしいでしょうか」
「……覚悟があるのならばな」
「覚悟ならば、叔父上に皇太子としてご指名を頂いた頃より」
金の瞳と金の瞳が互いを映す。
「ならば良い。不安があれば姉上たちを頼れ」
「叔母上たちもお呼びになっていたのですか。それは……」
「ここでは観客が多すぎる。時間まで待て」
「はい。失礼を。それでは、後ほど。……クロード様も」
にこ、と姫君は笑い、背を向けた。ピンと伸びた背筋が、王のものとよく似ていた。
「……坊ちゃん、これから苦労するぞ」
「はい?」
「ちょっとイケメンの自覚した方がいいぜ」
からかい混じりのシアンの言葉に、クロードはまるで何も気付いていない顔だった。
それが余計に面白くて、シアンは声を押し殺して笑った。
休みなく馬を走らせたゼファーの率いる隊列は、朝焼けの中、王都の門をくぐった。
空に、明けの明星が輝いていた。
王都の大通り。城へ続くその道は、ひどい有様だった。
道端には帰る家を失ったのであろう民が、傷を抱えて朝焼けの中、断続的なうめき声と、荒んだ視線で王の隊列を測るように見ていた。
「陛下…どうか、ご許可を」
クロードが騎馬から降りて、ゼファーを見上げた。その眼差しは、真にゼファーの許しを待っているというよりは、許しを得ることを、確信している目つきだった。
ゼファーは頷いた。クロードの手は、すでに癒炎剣へと触れている。
「民よ、聞け!これより癒焔剣アレストの使い手がゆく。傷を負った者は白い炎を恐れるな!その焔は癒す力、当代ユーノヴェルト辺境伯クロードの慈悲である!」
ゼファーの声は強く、それこそ雷のように響き渡った。顔を伏せていたいくらかの民が、顔を上げた。
とん、とクロードは荒れた道の上で、歩を進める。
そしてその腰の帯剣を、抜いた。
「どうぞどなたもお近くへ!みな等しく我が主君の民、同じ王に拝す者!身分も職も隔たりなく、私の力が及ぶ限り、その傷を癒すと誓いましょう!」
地面を撫でるように振るったアレストの剣先から、ふわりと白い花弁のように癒炎が立ち上がる。
ゆっくりと、クロードは歩を進める。ほとんどただ剣を振るだけの剣舞は、癒炎を送り出す風の具現化のようであった。
「…お、おお…!!」
触れた怪我人の、感嘆の声が上がる。
「ほんとだ!本当に、治ったぞ…!!」
「この辺りにいるのは軽症者のようだな。体を動かせぬ重症者はどっちだ」
騎馬より降りて尋ねたゼファーに、怪我を負っていた男は、恐縮して視線を下に落とした。
「へ、へぇ…教会の方に皆運ばれていきました…!」
「そうか。クロード、聞こえたか」
「はい。向かいます」
剣舞を続けながら、クロードは頷いた。
「治癒術師と弓騎士隊はクロードと共に教会へ向かい、治療と救助に当たれ。槍騎士隊と魔術師は私と共に王城へ。王都騎士と連携を取り、周辺の魔物を掃討する」
ゼファーは再び愛馬に跨った。王都は広く、王城へと向かうには、城下町よりさらに奥へ進む必要がある。
「ご武運を」
「ああ、お前も」
短く言葉を交わし、二人の神剣使いはそれぞれの戦場へと向かうこととなった。
シアンが教会の扉を開いた時、その中は血の匂いとうめき声で溢れていた。老いも若きも、男も女も関係なく、痛みと苦しみでうめき、そして泣き喚く者すらいた。
「ああ……軍都の治癒術師隊ですか……」
「と、弓騎士隊だ。助っ人が来たっていうのに、ずいぶんと浮かない顔だな」
司祭服を血で汚した男が、覇気なく言うのに、シアンは常の短気を抑えた声で問いかけた。
「もう掛けられる分の治癒術は掛けました。これ以上は魔力負荷に耐えられません。…あとは患者本人の体力次第です」
男の他にも司祭服を来た者たちは、ぐったりと項垂れている。相当に厳しい状況だったことが伺い知れた。
「シアン副隊長。司祭殿の言う通りかと。やれることはやっていただいたようです」
「ならこっちで俺たちが出来ることはないか。坊ちゃん、任せていいな」
「はい」
「よ、よしたまえ、本当に魔力負荷の限界なんだ。これ以上治癒魔法を掛ければ、細胞が耐えられずに壊死する」
「心配すんな。坊ちゃんの炎は……奇跡ってやつだ」
クロードが、再びアレストを抜いた。
剣舞で白炎を振るう姿を、朝日を通したステンドグラスの光が照らしている。
そうするとまるで、本当に奇跡のようだった。クロード自身が燃えて、人を癒す炎と化しているような、そんな錯覚を覚えるほど。
「な……な、あれ、は……」
白炎が空中で分かたれて、花びらのように舞う。その光は、吸い込まれるように傷に寄り添い、幾人もの傷を治していった。
「……な?奇跡、だろ」
「もしや、あれは……っ、もう一本の、神剣、なのですか……っ!」
司祭はすぐに、アレストのことを思い至ったようだった。あるいは、いまここにアレストの使い手が現れてくれればと、願っていたのかもしれない。
「そうらしいぞ。それじゃ、弓騎士隊は手分けして救助活動に移るとするかな。コンビ組んで、治癒術師と行動しろ。魔力負荷限界に達しても重症の人間は教会に運び込む。坊ちゃん!いいか?」
「はい。お願いします」
手早く段取りを決めたシアンに、クロードは剣舞を止めぬまま、微笑で頷いた。
救助活動は日が高くなっても続いた。
何せ広い王都である。怪我人を受け入れていた教会も一つだけでなく、クロードは動かせぬ重傷者がいると聞けば、何度も場所を変えて治療に走った。
その距離は王都城下町をぐるりと一周。時間は太陽が一番高く昇る頃である。
シアンは弓騎士隊と治癒術師たちに順番で昼食と休憩を取らせた。もちろんクロードにも。
そうして、クロードと交代でシアンが最後に休憩をとった頃には、もう夕暮れが迫っていた。
クロードがいまだ運び込まれてくる怪我人の治療を治癒術師たちと進めていた、その時である。
空を、一筋の雷が走った。
「きゃっ!?」
「こ、こんな時に雷まで…!!」
「雨も降ってないってのに……!」
教会に集まった人々の表情が恐怖に染まる。それほどの、威圧感。だがその稲光を、クロードはよく知っていた。
「……陛下」
いくつもの雷光が走る。それが落ちるのが王都城下町の外側だと言うことに気づき、内部の安全を確保した上での掃討なのだろう、とクロードは見当をつけた。
「あれは、陛下の迅雷剣ハルファドです。外に余程の大物がいたのかもしれません」
クロードは手を止めて、動揺する人々に告げる。そのこめかみを、汗が伝ってぽたり、と落ちた。
「だ、大丈夫なのですか……!?」
「信じてお待ちしましょう。陛下は僕より余程、神剣の扱いに慣れていらっしゃいます」
クロードが微笑めば、途端安堵の空気が流れる。この奇跡のような癒しの炎を使う使い手が言うならば、とその目が物語っていた。
「坊ちゃん、休憩交代だ。」
「シアン殿。まだお休みにならなくていいのですか」
シアンのとった休憩は、他の隊員より遥かに少なかった。というのに、その顔に疲れはなく、不敵に笑う余裕さえあった。
「あの冷血将軍に連れ回された経験なら、今回が始めてじゃないんでね。強行軍は慣れてる」
「ですが……」
「夜に備えてろ。次にもう一波あったら、あんたには死ぬほど働いてもらうことになるんだからな」
「わかりました。重傷の方がいらっしゃいましたら、叩き起こしてください」
「おう。容赦なく叩き起こすから安心してろ」
シアンの遠慮のない言葉に、クロードは安心してアレストを剣に収めた。
白い炎がふわりと舞い散って、クロードは息を吐きだす。ど、と急に体に疲労がのしかかって、膝が笑う。
「おーい、肩貸そうか坊ちゃん」
「いえ、大丈夫です、これぐらいで弱音は言えませんから」
クロードがきっぱりと断れば、シアンもそれ以上は何も言わず、傷に残った負傷者に、消毒や包帯を施すための作業に移っていった。
ぱた、ぱたた、とクロードのこめかみから汗が止めどなく溢れる。それは木の床に吸い込まれてすぐに乾く。クロードは、厚意で借りることのできた教会の司祭の私室に滑り込み、そのまま体を倒した。体が、鉛のように重い。途中からは自分に対しても癒炎の力を振るって疲労を誤魔化していたが、それも限界はある。
ほとんど一日中、アレストを振るっていた。だが、お陰で実践での振るい方の感覚も掴み始めていた。クロードは疲労でぼんやりとする頭で、充足感を感じつつ、窓の外を走る、青雷を見上げた。
「……きれいだ」
ほとんど無意識で呟いて、クロードは目を閉じた。
ゼファーの体の周りを、青白い雷光が覆っていた。
ハルファドを本気で振るう時には、雷光の鎧を纏うのが常だった。誰のサポートも期待は出来ない。特に、ユリウスやロベルトという規格外の能力を持つ猛者がいないこの場において。
相対する大型の魔物は、この日ゼファーが何度となく撃破してきた種であった。
一つ目の異形の巨人。それは過去にも何度か討伐したことのあるゼファーだったが、奇妙だ、と感じていた。本来ならば、このように群れを成す魔物ではない。
剣術のみで、手足の自由を奪い、鋼鉄の心の臓に向けては、ハルファドの雷撃を。
轟音と共に雷撃を叩き込んで、ゼファーは一息ついた。
その頭上に、翼持つ魔物が舞う。面倒な。ゼファーがハルファドにバチリと稲光を纏わせる。
だがその光が放たれる前に、一筋の光がその魔物を貫く。若葉色のその光に思いあたりがあり、ゼファーはハルファドの雷撃を、短い感覚で七回、鳴らした。
ほとんど音だけのそれは、昔からの合図であった。
迅雷剣ハルファドを、納刀する。戦場の終わりのその合図である。
「ほんっとめちゃくちゃだぜ、神剣ってやつは」
「シアン。クロードはどうした」
「いま少し休ませてますよ。負傷者も落ち着いて来たんでね。治癒術師で回してます」
しばらくもせずに現れたシアンは、その弓の弦に光を灯していた。ロベルトのものより黄色みがかった緑のその光は、シアンの眼の色とよく似ている。
「ならばいい。今ので近くに見える大型は全て倒した。一度王都に戻る」
「じゃあ王城の門番に伝えてきましょうか」
「いらん。魑魅魍魎の巣では休まるものも休まらぬ」
「ハハ。じゃあ、あの坊ちゃんのベッドにでも入ります?」
ふざけて言ったシアンに、ゼファーは嫌な顔をする。元よりシアンが口の減らない男であるのは知っているものの、クロードをも巻き込んだ軽口に、ゼファーは酷く腹立たしいものを覚えて、返す言葉にことさら冷たさが乗ることとなった。
「妙な邪推をするな」
「邪推じゃねえだろ。気付いてんだろ、あんた」
おそらく、時間だけで言えば、軍都で一番クロードと共にいたのはシアンだ。だから、クロードの変化に一番に気付くとすればシアンであるのは想像に難くなく、ゼファーは否定の反論を失った。
「抱いちまえよ。満更でもないくせに、あんたらしくもない」
「立場や状況を考えろ。そもそも成年もしていない子どもを相手にするか」
「あんたがそんなこと気にするようになったとはね。言い寄ってくるバカ全部食って、道化野郎が青筋立ててキレてたの知ってんだぞ、こっちは」
「ユリウスのあれは怒ったふりだ。金や体目当ての相手ならば何人いようが気に留めてないぞ、あれは」
シアンは肩を竦めた。ゼファーのユリウス評を信じているのかいないのか、ただそこの事情はどうでもいいと言わんばかりに。
「じゃあ坊ちゃんは?」
「しつこいぞ」
「しつこくするね。あんた絶対、あの坊ちゃんを逃がしたら後悔するぜ」
ふざけた声色を消したシアンの目を、ゼファーはじっと見返した。この目が、ずっとロベルトを追っているのを知っている。
「……だとしても、今ではない、だろう」
「は、ずりぃ年上って感じ」
「私も扱いかねている。お前もあまり追求するな」
ゼファーは思ったままを告げた。クロードの好意については、それこそシアンの言う通り満更でもない。
だが、肉体的な接触ともなると、今までのクロードとの関係がそこに集約してしまうのが、惜しいと思っていた。
だから、その感情の名を知らぬ王は、ただただ心地良いクロードの好意を受け取って、その暖かさに心を揺らすだけに留めていた。
「いやもうそこまで行ってんなら、抱ける時に抱いとけよ」
「手を出せば、クロードにとっての私が、好意に胡座をかいて未成年に手を出した男になるのだが?一生消せぬぞ、それは」
「……あ?」
肉体的な接触をすることに抵抗はないし、クロードも否を言わないであろう、という確信がゼファーにはある。
だが、十年後、二十年後。聡明を深めているだろうクロードの姿は想像に容易く、その彼が、そのような乱れた行いに眉を顰めるのまで、目に見えるようだった。
「いや、あんた、それは……それはさあ……いや、悪ィ、マジですんません、そんな純な感じとは思わなくて……」
「ぐちゃぐちゃ言うなら最初から口出しをするな」
散々好き勝手言ったシアンが急にもごもごと口ごもるので、ゼファーは鬱陶しそうに言い放った。実際かなり鬱陶しかったので。
「いやそれは自分の過去の行いを振り返ってくれねぇかな」
「やかましい。お前こそロベルトとのことをいい加減どうにかしろ」
「……ッス、それはマジで、はい……」
痛い所を突かれて、シアンは黙った。王から見れば、シアンの方こそはっきりさせるべき頃合いだと思っていた。
何せ、それこそゼファーですら成人する前からのことなので。
シアンからクロードの滞在する場所を聞き、ゼファーは一直線にその教会へと向かった。もはやからかう気力もないのか、シアンは王を送り出して、自身は教会の外側に見張りに立った。
静かに礼拝堂の扉を開けば、月の光が差す。
微かに聞こえたのは、低く甘い歌声だった。
アレストを腕に抱いたクロードが、目を伏せて子守唄を歌っていた。癒炎の白い炎が花弁のように舞い、その顔を柔らかに照らしている。
ゼファーは息を呑んだ。まるで見知らぬ異国の宗教画のような風景であった。
一歩、ゼファーが歩を進めると、青い瞳が開いてクロードが微笑んだ。
「…陛下。ご無事で」
「ああ。…まだ治療が必要な者がいたか」
「命に関わる方はどうにか終えました。これは沈痛と導眠のために」
「そこまでコントロール出来るようになったか」
「実践が何よりの教師とも言いますから」
クロードの顔に、疲労が滲んでいる。だが、充足感もある表情だった。得られるものも大きかったか、とゼファーは読み取って、そのクロードの隣に腰を下ろす。祭壇前の段差に、この国でも高位の家格の二人が並んだ。
長椅子に座って眠る怪我人たちは、どれも穏やかな寝顔であった。
「戦況はいかがでしたか」
「軍都の精鋭を以てすれば大したことはなかった。…が、妙な気配はあったな。群れを作らぬ大型の魔物が隊列を組んでいた」
「それは……」
「本当に、魔竜の件と関係があるやもしれん」
魔竜復活の前から、魔物が凶暴化するという記録は救世主伝説の一節にも組み込まれている。それを鎮めたのが救世主の力であったというのも。
だが今、この国に救世主はいない。ならば、持ちうる戦力で戦うしか術はなかった。
「まあ、なにはともあれ状況が収まってからだな。明日正午までに新たな襲撃がなければ、大臣たちを招集する。来れるな、クロード」
「はい」
クロードの顔に、僅かに緊張が走った。
今までのクロードの来歴からして、他の貴族との交流が希薄なのは歴然としている。
それが突然、戦局だけでなく政局をも変えうる神剣の使い手として、国政の中心に立つのだ。緊張するなという方が無理で、だが慌てふためかないのは、クロードの思慮深さの表れだった。
「少し休む、肩を貸せ」
「陛下、このようなところでなくとも………」
「私にとって、お前の隣より安全な場所がこの王都にはないのでな」
かっ、とクロードの頬が紅潮した。少年らしい純朴な反応に気をよくして、ゼファーは喉を鳴らして笑った。
「僕の肩などでよければ、いくらでも。おやすみなさいませ、陛下」
「ああ、おやすみ」
白い炎の端を見ながら、ゼファーは目を閉じた。
再び、低く甘い歌声が掠れて響く。
目を開けば、子どもたちが団子のように目の前に群がっていて、ゼファーは声を掛けようか迷った。自分が、それほど子どもに好かれる方ではない自覚があったので。
だが、子どもたちはヒソヒソと内緒話をしながら、そこから離れる気配はない。仕方なしに、ゼファーは声を掛けることにした。
「……何か、クロードに用か?」
「きゃっ」
驚きの声が上がるのは、想定通り。隣の体温がぬるく、まだ眠りの中にあるのをわかっていたので、用事があるのならばそちらだろう、と見当を付けて問うた。
「ええと、あの」
子どもたちの中でも年長の方だろう少女が、震えながら声を上げた。ゼファーは急いて問い返しはせずに、黙って続きを待つ。
そのゼファーに、ずい、と野花のブーケが差し出される。
「白いお花の勇者さまに、どうぞ!」
ゼファーの手に押し付けるようにしてそれを預けると、少女は周りの子どもたちと共に駆け出して行った。
色とりどりの野花はどれも子どもの高い体温でくたりとしおれかけている。だが、この状況下で子どもが出来る返礼として最大のものであろう、とゼファーはクロードの奮闘に思いを馳せた。
「白いお花の勇者様、か」
アレストの癒炎がそう見えたのだろう。あの白光だけを見れば、あの神剣が、恐ろしい破壊の力をも秘めているとは思いもよらぬことだろう。
ゼファーは、野花のブーケから一本、白い花を抜き出した。それを、まだ眠りの中にある、クロードの赤毛に差し込んだ。
クロードは、それに気づかずに眠っている。だからゼファーも、今一度眠りについたのだった。
王都王城。
その荘厳たる美麗な宮殿に入った途端、クロードが顔を顰めたので、シアンは笑い出すのを堪える羽目になった。
城下町の惨状とは比べものにならぬほど安寧に守られたそこは、傷の一つもなければ、怪我人の一人もおらず、ここだけが重点的に守られていたのだと分かる。
王宮には貴族たちが避難してきており、そこここで様々なざわめきがあった。
興味関心、が一番強いだろう。ゼファーは戴冠からほとんどを軍都で過ごした。故に、主だった官職についた者以外は王の姿を見たことをない者も多い。
ざわめきの中に、侮りの視線をいくつか感じて、シアンは呆れた。この場にいる誰も彼もが、ゼファーを野蛮な将軍と、次代を担う女王が君臨するまでの繋ぎの王としか見ていない。
もし本当にそうであれば、この聡明な少年が付き従うはずもなかったはずだ。険しい顔をしたクロードを横目で眺めながら、シアンは護衛として表情も気配もなるべく消して、二人の貴人に付き従った。
そこに、軽やかな足取りで歩み寄る少女がいた。少女の髪は、王と同じ紺碧だった。
「叔父上」
「セシリア、無事だったか」
皇太女セシリア。ゼファーの姪であり、先王の娘である。金色の瞳が、王と良く似ていた。
シアンは何度か会ったことがあるが、その頃のお転婆は身を潜め、年頃の姫君らしい淑やかさで挨拶をする少女に、月日の流れを感じた。確か今年で十五だったか。シアンは胸中で指折り数える。
「騎士たちの尽力です。叔父上、この度は救助要請に拙速を以て応えて頂き、感謝致します」
「苦労をさせたな。私が軍都の方にばかり、精鋭の兵を連れて行ったばかりに」
王の皮肉に、姫君は曖昧な笑みだけを返した。
クロードには伝えなかったことだが、王都の騎士はそのほとんどが貴族の子女の名誉職と化しており、統制が取れているとは言えぬ有様であった。そのことを姫君もわかっているのだろう。
そのため、主な戦力と言えば王都騎士団よりも教会所属の聖堂騎士であった、そのため、防戦一方になったというのが、王とシアンの共通の見解であった。
本来ならば、守りに特化した聖堂騎士と、攻めに長けた王都騎士団の両輪を以て魔物の襲撃に反撃するのが理想である。だがこの状況では、聖堂騎士たちは奮闘した方とも言えた。
「それより叔父上、こちらの方をご紹介して頂いても?ーー…兵たちの話によれば癒炎剣アレストを、お持ちだとか」
姫君がよく通る声でそう告げれば、周囲にざわめきが広がる。癒炎剣アレスト。二千年の間、使い手が現れなかった神剣。その使い手が現れた。
その影響を分かっていて、セシリアは言ったのだろう。周囲のざわめきを気にすることもなく、クロードに微笑みかけた。
「耳が早いな。クロード、姪のセシリアだ。名ぐらいはお前の領地にも届いているかと思うが」
「はい」
クロードは微笑んで、膝を折って拝礼した。シアンは引いた。まるで演劇のような完璧な所作にすぎて、いっそ茶番めいていたからだ。
「初めてお目にかかります、セシリア皇太女殿下。ユーノヴェルト辺境伯クロードと申します。国王陛下のお赦しを頂き、癒炎剣アレストを帯剣させて頂いております」
わずかに掠れたクロードの声が、涼やかに姫君に告げる。過不足ない挨拶に、セシリアは満足げに頷き、完璧な淑女の笑みを見せた。
「……アレストをお抜きになるまで、ご苦労があったことと思います。この度の件におきましても、叔父をお支え頂き、礼を申し上げます。どうぞお立ちください」
「はい」
クロードが背を正し、若い二人は並び立った。冗談のように、完璧な姫君と騎士の物語の、絵画の如き二人だった。
ざわめきは色を変える。
まあ焦るわな。シアンは白けた。癒炎剣アレストを振るって王都の民を救った勇者。それだけで姫君の相手に足る勇名である。つまり王都在住の貴族たちの駆け引きの外から現れた、埒外の候補者となりうる。
ただ、当の本人といえば隣の巨漢に夢中なわけだが。
「叔父上、これから今後に関わる重要な話をなさるとお伺いしました。私も同席してよろしいでしょうか」
「……覚悟があるのならばな」
「覚悟ならば、叔父上に皇太子としてご指名を頂いた頃より」
金の瞳と金の瞳が互いを映す。
「ならば良い。不安があれば姉上たちを頼れ」
「叔母上たちもお呼びになっていたのですか。それは……」
「ここでは観客が多すぎる。時間まで待て」
「はい。失礼を。それでは、後ほど。……クロード様も」
にこ、と姫君は笑い、背を向けた。ピンと伸びた背筋が、王のものとよく似ていた。
「……坊ちゃん、これから苦労するぞ」
「はい?」
「ちょっとイケメンの自覚した方がいいぜ」
からかい混じりのシアンの言葉に、クロードはまるで何も気付いていない顔だった。
それが余計に面白くて、シアンは声を押し殺して笑った。
0
あなたにおすすめの小説

旦那様と僕
三冬月マヨ
BL
旦那様と奉公人(の、つもり)の、のんびりとした話。
縁側で日向ぼっこしながらお茶を飲む感じで、のほほんとして頂けたら幸いです。
本編完結済。
『向日葵の庭で』は、残酷と云うか、覚悟が必要かな? と思いまして注意喚起の為『※』を付けています。

猫カフェの溺愛契約〜獣人の甘い約束〜
なの
BL
人見知りの悠月――ゆづきにとって、叔父が営む保護猫カフェ「ニャンコの隠れ家」だけが心の居場所だった。
そんな悠月には昔から猫の言葉がわかる――という特殊な能力があった。
しかし経営難で閉店の危機に……
愛する猫たちとの別れが迫る中、運命を変える男が現れた。
猫のような美しい瞳を持つ謎の客・玲音――れお。
彼が差し出したのは「店を救う代わりに、お前と契約したい」という甘い誘惑。
契約のはずが、いつしか年の差を超えた溺愛に包まれて――
甘々すぎる生活に、だんだんと心が溶けていく悠月。
だけど玲音には秘密があった。
満月の夜に現れる獣の姿。猫たちだけが知る彼の正体、そして命をかけた契約の真実
「君を守るためなら、俺は何でもする」
これは愛なのか契約だけなのか……
すべてを賭けた禁断の恋の行方は?
猫たちが見守る小さなカフェで紡がれる、奇跡のハッピーエンド。

雪解けを待つ森で ―スヴェル森の鎮魂歌(レクイエム)―
なの
BL
百年に一度、森の魔物へ生贄を捧げる村。
その年の供物に選ばれたのは、誰にも必要とされなかった孤児のアシェルだった。
死を覚悟して踏み入れた森の奥で、彼は古の守護者である獣人・ヴァルと出会う。
かつて人に裏切られ、心を閉ざしたヴァル。
そして、孤独だったアシェル。
凍てつく森での暮らしは、二人の運命を少しずつ溶かしていく。
だが、古い呪いは再び動き出し、燃え盛る炎が森と二人を飲み込もうとしていた。
生贄の少年と孤独な獣が紡ぐ、絶望の果てにある再生と愛のファンタジー

地味メガネだと思ってた同僚が、眼鏡を外したら国宝級でした~無愛想な美人と、チャラ営業のすれ違い恋愛
中岡 始
BL
誰にも気づかれたくない。
誰の心にも触れたくない。
無表情と無関心を盾に、オフィスの隅で静かに生きる天王寺悠(てんのうじ・ゆう)。
その存在に、誰も興味を持たなかった――彼を除いて。
明るく人懐こい営業マン・梅田隼人(うめだ・はやと)は、
偶然見た「眼鏡を外した天王寺」の姿に、衝撃を受ける。
無機質な顔の奥に隠れていたのは、
誰よりも美しく、誰よりも脆い、ひとりの青年だった。
気づいてしまったから、もう目を逸らせない。
知りたくなったから、もう引き返せない。
すれ違いと無関心、
優しさと孤独、
微かな笑顔と、隠された心。
これは、
触れれば壊れそうな彼に、
それでも手を伸ばしてしまった、
不器用な男たちの恋のはなし。

虐げられている魔術師少年、悪魔召喚に成功したところ国家転覆にも成功する
あかのゆりこ
BL
主人公のグレン・クランストンは天才魔術師だ。ある日、失われた魔術の復活に成功し、悪魔を召喚する。その悪魔は愛と性の悪魔「ドーヴィ」と名乗り、グレンに契約の代償としてまさかの「口づけ」を提示してきた。
領民を守るため、王家に囚われた姉を救うため、グレンは致し方なく自分の唇(もちろん未使用)を差し出すことになる。
***
王家に虐げられて不遇な立場のトラウマ持ち不幸属性主人公がスパダリ系悪魔に溺愛されて幸せになるコメディの皮を被ったそこそこシリアスなお話です。
・ハピエン
・CP左右固定(リバありません)
・三角関係及び当て馬キャラなし(相手違いありません)
です。
べろちゅーすらないキスだけの健全ピュアピュアなお付き合いをお楽しみください。
***
2024.10.18 第二章開幕にあたり、第一章の2話~3話の間に加筆を行いました。小数点付きの話が追加分ですが、別に読まなくても問題はありません。
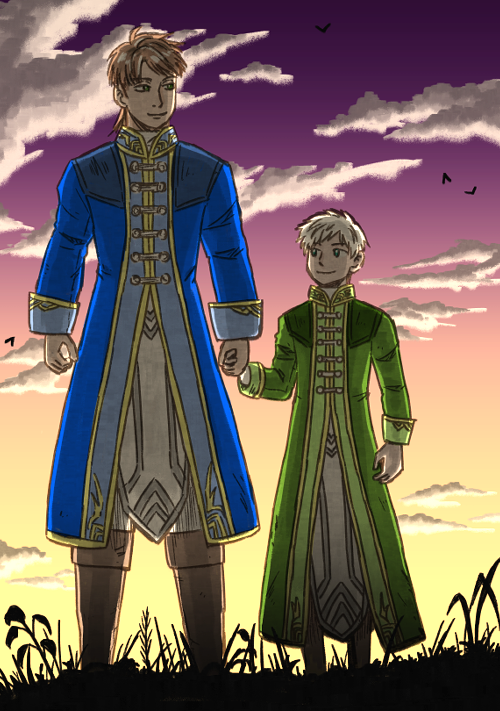
天涯孤独になった少年は、元軍人の優しいオジサンと幸せに生きる
ir(いる)
BL
※2025/11 プロローグを追加しました
ファンタジー。最愛の父を亡くした後、恋人(不倫相手)と再婚したい母に騙されて捨てられた12歳の少年。30歳の元軍人の男性との出会いで傷付いた心を癒してもらい、恋(主人公からの片思い)をする物語。
※序盤は主人公が悲しむシーンが多いです。
※主人公と相手が出会うまで、少しかかります(28話)
※BL的展開になるまでに、結構かかる予定です。主人公が恋心を自覚するようでしないのは51話くらい?
※女性は普通に登場しますが、他に明確な相手がいたり、恋愛目線で主人公たちを見ていない人ばかりです。
※同性愛者もいますが、異性愛が主流の世界です。なので主人公は、男なのに男を好きになる自分はおかしいのでは?と悩みます。
※主人公のお相手は、保護者として主人公を温かく見守り、支えたいと思っています。

人気作家は売り専男子を抱き枕として独占したい
白妙スイ@1/9新刊発売
BL
八架 深都は好奇心から売り専のバイトをしている大学生。
ある日、不眠症の小説家・秋木 晴士から指名が入る。
秋木の家で深都はもこもこの部屋着を着せられて、抱きもせず添い寝させられる。
戸惑った深都だったが、秋木は気に入ったと何度も指名してくるようになって……。
●八架 深都(はちか みと)
20歳、大学2年生
好奇心旺盛な性格
●秋木 晴士(あきぎ せいじ)
26歳、小説家
重度の不眠症らしいが……?
※性的描写が含まれます
完結いたしました!

【完結】社畜の俺が一途な犬系イケメン大学生に告白された話
日向汐
BL
「好きです」
「…手離せよ」
「いやだ、」
じっと見つめてくる眼力に気圧される。
ただでさえ16時間勤務の後なんだ。勘弁してくれ──。
・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:
純真天然イケメン大学生(21)× 気怠げ社畜お兄さん(26)
閉店間際のスーパーでの出会いから始まる、
一途でほんわか甘いラブストーリー🥐☕️💕
・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:
📚 **全5話/9月20日(土)完結!** ✨
短期でサクッと読める完結作です♡
ぜひぜひ
ゆるりとお楽しみください☻*
・───────────・
🧸更新のお知らせや、2人の“舞台裏”の小話🫧
❥❥❥ https://x.com/ushio_hinata_2?s=21
・───────────・
応援していただけると励みになります💪( ¨̮ 💪)
なにとぞ、よしなに♡
・───────────・
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















