30 / 55
ずるい 2
しおりを挟む~白崎side~
小鳥遊と一緒に戻った教室で、お姫様に従者が出来たとか勝手に盛り上がられ。
「はいはい、好きなように言っててよ」
急に自分を囲むように騒がられても、そういったことにまだ不慣れな僕は塩対応をするので精一杯だ。
もうちょっと愛想よくした方がいいんだってわかってるけど、まだそれを自然に出来るまでにはなっていない。
前髪を切ったのが、三年前。それからも、なるべく目が見えている程度の前髪にするようにしている。
今回の学校祭での距離の詰め方は、自分自身の予想をとっくに超えてしまっていて、僕自身の戸惑いが大きい。
その中で他のクラスメイトより、ほんのすこしだけ…距離が近くなっただろう小鳥遊。
何がキッカケなのかを明かしてもらえていないけど、僕のことが好きだと告白されたばかりだ。
告白されたとはいえ、僕の中には黒木咲良という二個上の先輩という存在が不動であって……。
「あれ? 衣装脱いできたのに、メイクそのままで戻ってきたの? …ねぇ、誰かメイク落としてあげてー」
「あ、ホントだ。可愛いままだね、白崎くん。…このままでもよさそうだけど、しなれていない人だとメイクしっぱなしは気持ち悪いかな?」
「気持ち悪いとかじゃないけど、なんだか落ち着かないっていうか…目立って、嫌だ」
ムスッとしながら愚痴のように呟けば、前髪を上げるヘアバンドを手渡される。
「目立つの嫌だとは聞いていたけど、そこまで顔に出るくらい嫌だったの?」
僕は自分を囲むうちの一人に向けて、コクンとうなずいて見せる。
「…のに、あんなにがんばってくれたんだね」
「まあ、クラスの出し物だし、協力はしなきゃと思ったし。正直、本当に嫌だったけど…背中押してくれた人いたから…やってみようかな、と」
「そうなんだ」
その話題になって、あの時の廊下での会話を思い出す。
「学校のイベントなんだから、バカバカしいことをやって楽しんだ方が勝ちみたいなもんだって…さ。ま、今思えば、あんな白雪姫…バカバカしすぎる。……楽しかったけど」
顔をひんやりしたシートで拭いてもらいながら、あの会話の後に頭を撫でてもらったなとか思い出していたら、背後でなにか騒いでる声がした。
ふと振り向いてみると、黒木先輩が教室の入り口にいてこっちをみて微笑んでいて。
メイクを落としてもらっている僕は、一瞬ためらう。やってもらってるのに、立っていいの? とか、クラスメイトの前で先輩と話すとか、顔がゆるみそうなのを堪えられる自信がない、とか。あれやこれやで。
でもためらっていたら、先輩はすぐにいなくなってしまうかもしれない。
「え? 先輩? ちょ…待ってください!」
オデコ丸出しの状態で立ち上がろうとした僕へ、先輩は手をヒラッと振って来なくてもいいよと伝えてくる。
あの手つきは、中学の時にも見たことがあるやつだ。
来なくていいと言われても、やっぱり行きたいのが本音なんだけど。
「これ、渡されたんだけど」
オロオロする僕の目の前に、折りたたまれたメモが差し出される。
確か衣装を担当してくれた子だったかな、この子。
指先でつまむようにして受け取れば、僕の名前がちゃんと書いてある。
嬉しい気持ちのままに顔を緩めたまま、メモを見て、先輩を見て。…を何度か繰り返すと、先輩がこれまで見たことがなかった笑顔を見せた。
すこしだけ、大人っぽい…ドキドキするような…そんな微笑みを浮かべている。
「じゃ、俺も戻るから」
の声に、コクコクとうなずき微笑み返す。
先輩はすぐに廊下を歩き出して、いなくなって。
両手の親指と人差し指でメモをはさむように持ち、すこしうつむきがちに白崎へと書かれたその文字を見下ろす。
チョコプリンを作った後に、先輩からも何度かメモ程度の紙で手紙みたいなのをもらったことがある。
メールでのやりとりは、すぐに返信がもらえるのがいい。
(でも、こうやって形に残るものの方が、僕は好きだ)
指先で先輩の文字で書かれた自分の名前をなぞると、自然と顔がほころぶ。
(あぁ、嬉しいな。がんばったら、こんなご褒美がもらえるだなんて)
そうやって自分の世界に入り込んでいた僕は、まわりの様子がさっきまでと少し違っていることに気づけていない。
(このメモは、後でこっそり見よう。みんなの前で開けるのは嫌だ)
メモをポケットにしまって、もう一度顔を上げて、スキンケアの続きをと思いだした僕。
(………え。なに? この空気)
顔を赤くしている人が半分と、僕と目を合わせない人がすこしと、遠巻きに僕を見ている人がすこし。
さっきまで一緒にいた小鳥遊は、衣装をハンガーに掛けながら遠巻きに僕を見ている中にいた。
「僕……何かした?」
何をどう聞けばいいのかわからなくなって、それだけを呟く。聞いた相手はメイク担当の子。
「あー…っと、いや…なにも?」
と、なぜか疑問形で返されてしまい、僕の疑問は消えるはずもなく。
「……あと、なにをどうすればいいのかだけ教えてくれる? 自分でやるよ。任せててごめんね」
疑問をそのままにしたくない気持ちはあるのに、その空気に耐えられなくて背中を向ける方を選んだ。
そうやって逃げようとするから、交友関係が拡がりそうで拡がらないんだってわかってるのにな。
「いや…その……やるよ? 遠慮しないでいいよ。もうちょっとで終わるし」
メイク担当の子がそう言ってくるけど、僕にはもう…無理だった。
「……ちょうだい? 他になにをやればいいの?」
「あ………。じゃ、あ…その……こっちを塗ってから、こっちを塗って。出来ればあまり強くこすらずに肌に手のひらで押さえるみたいにして吸収させるっていうか」
そういいながら、化粧品を手にしてやり方を身振り手振りも見せつつ、教えてくれる。
「…こう?」
僕がそう言えば、無言でうなずいた彼女。
ヘアバンドを外して、近くに置かれていた鏡へ近づいて前髪を整えた。
「はい、これ」
僕はヘアバンドを返して、教室を出ていこうとした時。
「白崎、俺も一緒に行く」
小鳥遊が窓のそばから駆け寄ってきて、僕を引き留める。
「トイレに行ってくるから、その間に休憩の順番わかるようにしといてくれる?」
バタバタしすぎてて、最終日の休憩時間をハッキリ知らない僕。
「あ、うん。いってらっしゃい」
困った顔をして僕を見送る委員長。
「うん」
廊下に出てすぐ、胸の奥の重さを吐くようにため息をつく。
「……なんなんだよ」
取り繕うとか考えられなくなって、思わず本音がこぼれた。
隣に小鳥遊っていうクラスメイトがいるのに。
自然と早足になって、僕はそのままの勢いで階段を下りていく。
「あれ? トイレは?」
小鳥遊がそう言って僕の腕を引いたけど、おかまいなしに階段を下りて二階へと急ぐ。
下りてすぐの場所を顔だけ左右に振って、探し物の姿を追う。
(…やっぱりもうない、か。誰か捨てちゃったか、落とし物として回収されたか。後者なら、同じものがあったら誰が飲んだかわからないモノだったら嫌だし。…学校祭本部に聞きに行くとか、ちょっとな)
先輩からもらったペットボトルは、先輩の熱騒動の時にこのあたりの廊下に置いてしまっていた。
先輩方との会話で動揺していなきゃ、ちゃんと回収して、大事に持ち帰ったはずのペットボトル。
「…あぁ、ついてない」
楽しかったはずの学校祭が、どんどん楽しくなくなっていく。
「探し物か? 俺も一緒に探すか?」
なんて、小鳥遊が聞いてきたけど、僕は首をゆるく振るだけ。
「…いいのか? 困ってんじゃねぇの?」
とか、改めて言葉にされてみると、ガッカリしている僕がいる。
「困ってるっていうか、ガッカリしてるだけ。……飲み物だったから、きっともうどこかに捨てられたかもしれない」
僕がそう返せば「なんだ、飲み物か」と小鳥遊が驚いている。
「ただの飲み物じゃないし」
ボソッとそう呟き、階段を上がって行く。
「行くよ、トイレ」
そう言いながら。
トイレに行って用を足して、手を洗ってハンカチで拭いて。
「悪いんだけど、そっち向いてて」
こそっとさっき受け取ったメモを開いて、中身を確かめる。
『第二音楽室に、19時半』
『一緒に見よう』
『黒木』
「…………はぁ…。死ぬかもしれない、僕」
心の中で呟いていたはずの声が、無意識で出ていたみたいだ。
「は? 死ぬ? 何が書かれて」
と小鳥遊が言ったと同時に、僕の手からメモを奪って開いた。
「あ゛ぁ゛???」
読んだ瞬間に低くてガラの悪い声を発して、僕を睨みつけてきたのがよくわからない。
「返して」
破れないように気をつけて、小鳥遊の手からメモを奪い返す。
ポケットに入れて、その上からそっと撫でる。
(さっきまで形容しがたい気持ちだったのに、先輩のメモひとつで簡単に元通り以上になれた)
その事実は、先輩が自分にとって特別な存在なんだと再確認させるには十分すぎて。
「花火、誘おうと思ってたのに」
小鳥遊がトイレのドアを押し開け、先に廊下へと出ていく。
「そうだったんだ。悪いけど、僕、先輩と見るから」
先輩に関してだけはハッキリと言葉に出来るみたいで、小鳥遊が顔を歪めてブツブツとなにかを言っていた。
「文句あるなら、こっち見て言ってよ」
ムッとしながらそう聞けば「文句じゃねぇわ」と小鳥遊。
「じゃあ、なに」
廊下を曲がって少し歩けば、3組まですぐだ。
「休憩。一緒に学校祭回ってくれよ。……それくらいいいだろ?」
そう言われて、先輩と一緒に回るのは無理そうだしなと考えて、休憩時間が一緒なのかどうかを知らない僕はこう返した。
「休憩が一緒ならね」
と。
小鳥遊が僕が先に申請していた休憩時間と全部時間が合うようにと、まったく同じ時間帯に申請していたのを知ったのは、その二年後。
「言質取ったからな、白崎」
「はいはい。一緒だったらいいね、休憩」
「…だな」
そんな会話をしてから、小鳥遊と二人で休憩時間を過ごし、閉会式では出し物の白雪姫が特別賞をもらって壇上へ。
王子役の子とこそっと話をして、役っぽいお辞儀をすることにして。
結構ノリがいい自分の一面を知って、楽しく過ごせるなら学校祭も悪くないななんて思ったり。
(でも、あのおかしな空気の時間だけは、今でも嫌な記憶ですぐに思い出せてしまう)
今は忘れていた方がいいことを、つい思い出してしまったりもした。
うちの学校は1年と2年はクラスがそのままで、3年になって進路に合わせたクラス分けになるとか聞いた。
来年もこのメンバーで学校祭をやるんだな。
……とかボンヤリしている間に、スマホで時間を見れば結構いい時間になっていた。
まわりももうすぐ花火が上がるってことで、そわそわしている人や、誰かを誘っている会話なんかも通り過ぎざまで聞こえてきた。
「なんで小鳥遊がついてきてるの」
先輩のメモ通りに第二音楽室へと向かうため、階段を下りていく僕。その少し後ろから、小鳥遊がくっついてくる。
「ほら…白雪姫だったから? お姫様を無事に送らないと」
よくわからない言い訳っぽいのを呟き、本当にずっとついてくる。
「ドレスもメイクもつけてないんだし、劇は終わったんだからさ。エスコートとかいらないよ」
スタスタと小鳥遊に構うことなく、早足で向かう。思ったよりも時間がギリギリだった。
「小鳥遊もどこか見やすいとこ行ってさ、花火見たら? 一緒に見る友達、僕よりはいるよね?」
自虐的なことを言いつつ、事実を告げる。
「……はあ。俺のことは気にしなくていいから、今だけはあの先輩に譲ってやるだけだからな」
「…ん? 何のこと?」
よくわからない話が出てきて、気になる僕は首をかしげてから聞いてみる。
「何を譲るの? あの先輩って、まさか黒木先輩? なにか譲ってあげたの? っていうか、面識あったっけ」
問いかけてみたけど、音楽室の前まで行っても答えてくれないままだ。
「スッキリしなくて、気持ち悪いんだけど」
睨みつけてから、ドアの取っ手に手をかけた。
「気にすんな。ホラ、すこし息が上がってる」
「…はぁ。こんなに急ぐハメになるなんて思ってなかったのに」
そう言ってからドアを開ければ、音楽室の中は暗くって。
廊下の明かりがドアを開けていくに従って、淡い色の線のように先輩の方へと伸びていくように見えた。
「せ……先輩っ。遅れてすみません」
先輩がいる場所は窓際で、遠くからアナウンスと歓声が聞こえていた。
先輩の表情が暗さでよく見えないやなんて思いながら、小鳥遊に「じゃあね」とだけ声をかける。
小鳥遊は「じゃあな」とだけ返して、僕に早く中に入れよと入るまで見送ってくれるみたいな感じで。
小さく手を振ろうと上げた手が、さっきまで窓際にいたはずの先輩に取られていて。
「え? 先輩?」
ビックリして思わず声をあげた僕を、先輩は一瞬で音楽室の中へと引きこんだ。
背後でドアが閉まって、真っ暗な中に二人になって。
走ってきたのと先輩に手を取られているという現実とに、心臓がドッドッドッドッと早鐘を打つ。
グッと手を引いたまま、先輩の気配が近づいた気がしたと思ったら、思ったよりも近かったのを知ってしまう。
「よそ見してんなよ」
と、囁かれたその声が、唇が耳に触れるほど近い場所で聞こえたから。
その声の直後に、花火の音がドォ…ンと聴こえてきた。
よそ見の意味がよくわからない。
(っていうよりも、先輩の声が近かった! 唇、絶対触れたよね? 僕の耳に。どうしよう。本気で死にそう。冗談じゃなく死ぬかもしれない。いや、死んでもいい)
混乱しつつも、先輩に引かれるがままに窓の方へと近づいていく。
「来ねぇつもりかと思った」
先輩はずっと手を離さない。僕の手首をギュッと握ったままなんだ。
「来るに決まってるじゃないですか。ちょっと…出るのが遅れちゃいましたけど」
「来るって信じてたけどな、俺は」
先輩、今どんな顔をしていますか? 顔が見たいのに、見られない。ここにいる理由が花火じゃなきゃ、この部屋に明かりをつけたいくらいだ。
「嬉しかったです。今年しか一緒に見られないって思っていたので」
時々花火のわずかな明かりで色づく、先輩の横顔。そっと盗み見て、トク…トク…と鳴る心音を確かめた。
胸の奥が痛くて苦しいのに、この心地よさ。そして、愛しくてたまらない気持ちでいっぱいになる。
「…あ。悪い。手、痛かったか?」
そう言ってから、先輩の手が離れてしまう。
「…あっ」
離れたくなかったし、むしろつなぎたいとすら思っていた。
「ん?」
思わずあげた声に返された声へ、僕は「いいえ」とだけ返す。
窓のサンにそっと手を置いて、花火を眺める。
赤、黄色、紫……青。キレイだ。
サンに置いていた僕の手に、サンのヒンヤリした温度とは真逆の温度が触れる。手の甲に先輩の手のひらが、ふに…と重なる。
手を重ねたまま僕の指の間に先輩の指が入り込み、そのまま軽くキュッと握られて。そしてそのタイミングで一歩分、先輩が僕へと近づいたのがわかった。
(え? え? なに? 何が起きてるの?)
今までにない先輩の行動の連続に、僕はどんどん花火どころじゃなくなってくる。
「キレイだな…花火」
なんてくっついてきた先輩の声に、心臓が今にも壊れそうな勢いで脈打ち、「は、はい」となんとか返事をした僕を…誰か褒めてほしい。
0
あなたにおすすめの小説

今日もBL営業カフェで働いています!?
卵丸
BL
ブラック企業の会社に嫌気がさして、退職した沢良宜 篤は給料が高い、男だけのカフェに面接を受けるが「腐男子ですか?」と聞かれて「腐男子ではない」と答えてしまい。改めて、説明文の「BLカフェ」と見てなかったので不採用と思っていたが次の日に採用通知が届き疑心暗鬼で初日バイトに向かうと、店長とBL営業をして腐女子のお客様を喜ばせて!?ノンケBL初心者のバイトと同性愛者の店長のノンケから始まるBLコメディ
※ 不定期更新です。
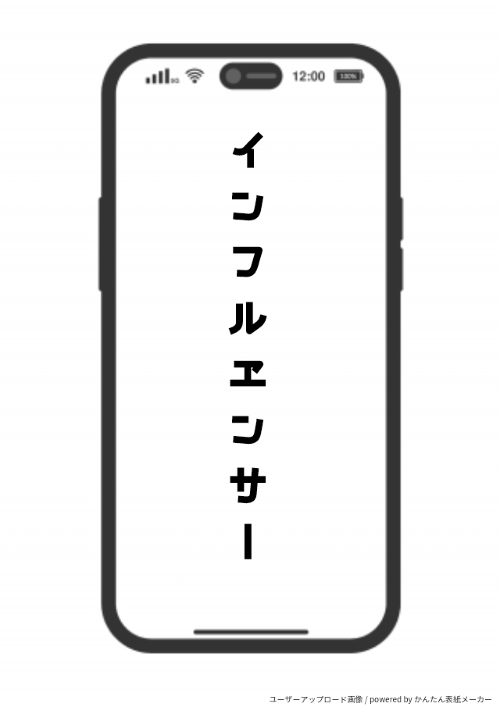
インフルエンサー
うた
BL
イケメン同級生の大衡は、なぜか俺にだけ異様なほど塩対応をする。修学旅行でも大衡と同じ班になってしまって憂鬱な俺だったが、大衡の正体がSNSフォロワー5万人超えの憧れのインフルエンサーだと気づいてしまい……。
※pixivにも投稿しています

【BL】捨てられたSubが甘やかされる話
橘スミレ
BL
渚は最低最悪なパートナーに追い出され行く宛もなく彷徨っていた。
もうダメだと倒れ込んだ時、オーナーと呼ばれる男に拾われた。
オーナーさんは理玖さんという名前で、優しくて暖かいDomだ。
ただ執着心がすごく強い。渚の全てを知って管理したがる。
特に食へのこだわりが強く、渚が食べるもの全てを知ろうとする。
でもその執着が捨てられた渚にとっては心地よく、気味が悪いほどの執着が欲しくなってしまう。
理玖さんの執着は日に日に重みを増していくが、渚はどこまでも幸福として受け入れてゆく。
そんな風な激重DomによってドロドロにされちゃうSubのお話です!
アルファポリス限定で連載中

白花の檻(はっかのおり)
AzureHaru
BL
その世界には、生まれながらに祝福を受けた者がいる。その祝福は人ならざるほどの美貌を与えられる。
その祝福によって、交わるはずのなかった2人の運命が交わり狂っていく。
この出会いは祝福か、或いは呪いか。
受け――リュシアン。
祝福を授かりながらも、決して傲慢ではなく、いつも穏やかに笑っている青年。
柔らかな白銀の髪、淡い光を湛えた瞳。人々が息を呑むほどの美しさを持つ。
攻め――アーヴィス。
リュシアンと同じく祝福を授かる。リュシアン以上に人の域を逸脱した容姿。
黒曜石のような瞳、彫刻のように整った顔立ち。
王国に名を轟かせる貴族であり、数々の功績を誇る英雄。


はじまりの朝
さくら乃
BL
子どもの頃は仲が良かった幼なじみ。
ある出来事をきっかけに離れてしまう。
中学は別の学校へ、そして、高校で再会するが、あの頃の彼とはいろいろ違いすぎて……。
これから始まる恋物語の、それは、“はじまりの朝”。
✳『番外編〜はじまりの裏側で』
『はじまりの朝』はナナ目線。しかし、その裏側では他キャラもいろいろ思っているはず。そんな彼ら目線のエピソード。


兄貴同士でキスしたら、何か問題でも?
perari
BL
挑戦として、イヤホンをつけたまま、相手の口の動きだけで会話を理解し、電話に答える――そんな遊びをしていた時のことだ。
その最中、俺の親友である理光が、なぜか俺の彼女に電話をかけた。
彼は俺のすぐそばに身を寄せ、薄い唇をわずかに結び、ひと言つぶやいた。
……その瞬間、俺の頭は真っ白になった。
口の動きで読み取った言葉は、間違いなくこうだった。
――「光希、俺はお前が好きだ。」
次の瞬間、電話の向こう側で彼女の怒りが炸裂したのだ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















