4 / 18
第一章「とある雪の日の邂逅」
02
しおりを挟む家につくなり、ユキさんは「疲れた!」と布団に倒れこんだ。
いつもより青白い顔をして、額の上に腕を置く彼の姿を見下ろす。
そんなことは初めてで、どうしていいかわからず立ち尽くした俺に、
「幽々子ちゃん、だっけ? 彼女、椅子に座らせてあげなさい」
と、指示をした。
声が上ずっている。苦しそうだ。
「僕なら大丈夫。久しぶりに箒ひとつで三人同時に飛行したからね。少し、疲れただけさ」
「……ン」
仕方なしに、俺は幽々子の腕を引いて部屋の中に連れ込んだ。
彼女は抵抗しなかった。
いまだぼんやりしているみたいで、部屋の中をぼうっと見渡している。
「座れだってよ。そのへん、てきとーに腰かけてくれ」
幽々子にそう告げると、彼女はふらふらと手近にあったソファに腰かけた。
奇しくもそれは、俺が応接用にと買えと言ったソファだった。
「空飛ぶ画家なんて、初めて見た……」
ぽつり。
そんな言葉に、思わず吹き出しそうになるのを必死にこらえる。
「インスタントでよければ、珈琲いれるけど」
「……飲む……」
「ん」
立ち上がって台所へ足を向けると、ちらりとユキさんが目に入った。
まだ倒れこんだままのユキさんは、その瞼を閉じている。
魔法で空を飛ぶ。
言葉では簡単に言えるが、もしかしたら、結構疲れることなのかもしれなかった。
だとしたら、どうしてそこまでして、ユキさんはあの場から逃げたかったのだろう?
(追ってくる、ていってたな)
あの場所には、一体何がいたのだろうか。
幽々子は一体、何に襲われていたのだろうか。
「……どうして、私が『危ない』ってわかったの?」
ヤカンにじゃばじゃばと水を出す。
その最中に、幽々子が口を開いたようだった。
問いかけに答えたのはユキさんだった。
「キミの背に『もや』が見えた。去っていく一瞬にね」
「もや……?」
「怪異が潜んでいるときに出る『症状』といえばいいのかな。とにかく、キミの命を奪おうとしているのがわかった」
ユキさんは淡々と答える。
その話に一ミリも信憑性はない。普通の人間なら「ワケがわからない」と激昂したっておかしくはない。
けれど幽々子はそうしなかった。
ただじ、と黙ってそれに聞き入っているようだった。
「一体どこであんなものに憑かれたんだい、キミ。長く生きている僕でさえ、あんなものを見るのは久しぶりだ」
「…………」
幽々子は答えなかった。
代わりにヤカンがぴーっと音を鳴らして叫んだ。
火を止めて、湯をコップに注ぐ。
ユキさんが落としても割れないように、ステンレス製、アウトドア用のものしかないがまあ幽々子だし、仕方ないだろう。
「ほい」
「あ、ありがとう」
「わあ。僕にもあるのかい? やった!」
ことん、とカップを置くとユキさんはベッドからずるずると降りてきた。
仕方なしにその体を抱き留めて、ソファのところまでもっていく。
軽い。いつもより、軽く感じる。
「インスタントだからな。味は期待するなよ」
保険のようにそんな言葉を吐いて、俺もユキさんの隣に座った。
ユキさんはコップを片手で持ち、ずるずると珈琲を啜っている。
幽々子も、こく、と一口珈琲をのんだ。
それから、ほっと安堵したような表情を見せて、瞼を伏せる。
「……阿久津。誰かのために珈琲いれるの、上手だね」
「あ?」
「優しい味がする。インスタントなのに、ヘンなの」
俺はハッとユキさんをみた。
けれどユキさんは珈琲に夢中で、とくにコメントはない。
「直希が淹れてくれるのと、似てる」
思わず目を丸くした俺に、幽々子は慌てて顔を赤くした。
「あ、ごめん。直希っていうのは、今の、こ、恋人の名前なんだけど」
……気を遣われているようだった。
別に俺は幽々子のことを引きずっていないし、今はとくに何とも思っていないのだが。
何しろ当時、どうやって付き合ったかとかどちらが告白したとか、そういうのも覚えていないくらいだ。
(って口にしたら怒るだろうし傷つけるよな。黙っておこ)
俺も珈琲に口をつける。
とくに変わった味はしない。いつも通りの、安いインスタントコーヒーだ。
「直希もね、よく珈琲いれてくれた。大学の講義が長かったときとか、バイトで遅かった日とか。そういうときの珈琲は、なんだか違う味がするんだ」
でも、と幽々子はつづけた。
「最近は……その。二人で住むために引っ越したんだけど、その……部屋が、おかしくて」
「部屋がおかしい?」
「そうなの。常に誰かに見られているような、常に私たち以外に誰かがいるような、そんな気がして、部屋にいるのがつらくて……」
「…………」
俺の頭には、二つ原因が浮かんだ。
一つは定番の超常現象。その部屋がいわゆる事故物件か何かで、何かが潜んでいるパターン。
もう一つも定番、『ストーカー』。
質の悪いストーカーがこいつを付け回していて、部屋の中にカメラとか仕込んでいるパターン。
あるいは、隣の部屋に住んでいて、どっかに穴が開いているとか。そんな感じ。
「部屋じゃないな」
しかしそんな俺の考えを、ユキさんは隣で否定した。
「アレはどちらかというと、キミを執拗に付け回しているようだ」
珈琲のカップがコトン、と軽い音で置かれる。
どうやら一気に飲んでしまったようだ。
「それも念入りにね。おそらく今日のようなこと、初めてじゃないだろう?」
幽々子はこくり、と頷いた。
「だろうね。隠れるのも相当うまい。初見では気づけなかった。でも、恐らく『根源』は部屋にあるんだろう。目的は明確にキミだが、あれは本体じゃなかった」
「魔法使いってのは、そんなことまでわかるもんなのか?」
「そりゃあ、まあ。キミたちよりはうんと長く生きているからね」
えへんと胸を張るユキさん。
ふーん、と納得する俺。
「え。……魔法使い?」
と、固まる幽々子。
そこでようやく、俺の発言が失言だったと気づく。
慌てて何か言おうとしたが、言葉が見つからない。
幽々子はふるふると震えて、それから。
「魔法使いー!?」
と、大きく叫びだした。大興奮である。
「箒で空を飛んでるからもしかしたらとは思ってたけど本当に!? やだ、すごい! 本物だ!」
サインください! と言いそうな勢いだ。
さすがのユキさんもその笑顔がひきつっている。
「わた、わたし、魔法使いにすっごく憧れてて! うわあ、感激だよう~!」
「おい、幽々子、落ち着け」
べし。と頭に手刀を落とす。
それでようやくのこと、幽々子は落ち着きを取り戻したようだった。
「あはは……、話を元に戻しても?」
「うう、はい……痛い……」
頭をさする幽々子に少し憐みの視線を向けながら、ユキさんは言った。
「キミさえよければ、その『家』にお邪魔させていただいても? 現場までいけば、どれが『根源』かわかるかもしれないし」
「それは、いいですけど……いいんですか? 私たち、お金とかそんなに持ってるわけでは……」
「僕は別にソレを生業とはしていないから、お金なんてとったりしないさ」
そういうと、ユキさんは片手を掲げてくい、と曲げた。
そこらに広げてあった画材道具たちがぞろぞろと一斉に動き出す。
まるで意思を持っているみたいだ。
彼らは揃って黒いヴィンテージ風のトランクに吸い込まれていった。
最後にイーゼルに掲げられたままのキャンバスが、のそのそと動き出す。
そうして彼も同様に、トランクの中へとすっぽり入っていった。
「おいで」
ユキさんが声をかけると、トランクはてこてこと歩くようにして左右に体を振った。
そうして、ユキさんの手元までくるとぴたりと止まった。
「……まさかそれ、持ってくのか?」
ていうか、今からいくのかよ。
そんな言葉を飲み込んだ俺に、ユキさんはトランクを差し出す。
「善は急げというだろう? 今回は特別に車だって貸し与えようじゃないか」
トランクを受け取った俺の手のひらに、続けて、ぽんっと鍵が出た。
車のカギだった。
今どきはもうあまりない、銀色に鈍く輝く鍵。
「待て。あんた、車なんて持ってるのか?」
「一応ね。昔買ったんだ。一九〇〇年代のキャデラックで、当時は大層人気があったんだ」
「それ動くのかよ……」
貰った鍵をじろりと見つめる。
そこで気づいた。一九〇〇年? キャデラック?
「左ハンドルじゃねえかその車! 無理無理、そんなもん運転したことないし!」
「大丈夫だよ、大体は一緒さ。仕組みが変わらないんだから、難しいことはない」
ユキさんに連れられて嫌々ながら外へ出る。
切り立った崖に作られた我が家は、なんていうか、改めてみると『家』という感じがない。
辺りも木々が生い茂る森だし、道だって舗装されたものじゃなく獣たちが踏みしめて作ったものだ。
ここから舗装された道に出るのに、徒歩だと一時間、車だと十五分くらいだろうか(ちなみに箒だと数分で通過する)。
彼がぽん、と地面を叩くと、ずるずる、と土の中からそれは現れた。
艶々のボディは確かに新品同様で、とてもじゃないがクラシックカーの質感じゃない。
まるで当時のまま、時を止められていたかのようだった。
「これさあ、売って、別の車を……」
「むっ。この車は凄いんだぞ。とあるギャングが愛用した車でね、銃弾をも防ぐ鋼鉄仕様なんだ」
「んなこといったって、運転できなきゃ意味ねえだろ……車検とかとってんのかよ」
「とってない!」
「だろうな。却下だ却下、いつも通り列車使おうぜ、列車」
さすがにため息をついた。
現代日本で車検をとらずに公道を走るなんて、法令違反もいいところだ。
「いやあ、危ないと思うよ? さっきみたいになるかもしれないし」
ドアの狂ったような開閉が脳裏に浮かぶ。
「私もあれは、ちょっと……」
幽々子も俺の後ろでそんなことを呟いた。
……確かにあれは、できればもう見たくはない。
だが。
だがしかし、だ。
かろうじて運転できたとしても、こんなクラシックカー、目立たないわけがないのだ。
どうせすぐにパトカーが寄ってきて、「お兄さん、車検とかちゃんととってる? 珍しい車だね」とフレンドリーに話しかけてくるに違いない。
そうじゃなくたって、こんな年代物の車、格好の客寄せ餌だ。
「わかったよ、じゃあこれはいつか海外に行ったときに乗ろうじゃないか」
「車検をとってからな」
「それじゃあ、えーと、これなんてどう?」
続いて出てきたのはカボチャの馬車だった。
ので、思い切りぶん殴って壊した。
「馬車もダメなのかい?」
「いろんな意味でダメだろ……いやわかんねえけど」
そこまで俺も詳しくはない。
ちなみに幽々子は少し目を輝かせてみていた。乗りたかったようだ。
「うーん、それじゃあ……」
どこぞの猫型ロボットが四次元ポケットを漁るときのような唸り声を出して、ユキさんは空を見上げた。
ほどなくして、「あ!」と声があがる。
今度は何を思いついたのだろう。できればこの案件は手短に済ませたい。
食材は冷蔵庫に放り投げたが、今日の夕飯はハンバーグの予定なのだ。仕込みがある。
「僕的にはあまり、使いたくはないのだけれどね……」
とんとん、とユキさんがつま先で地面を叩く。
すると次に地面から這い出てきたのは、真っ青なオーリスだ。
これまた新車である。
「これは前に絵を売ったとき、貰ったものでね。キミのいう車検も大丈夫のはずだよ」
「ちゃんとした車あるじゃんかよ! これを最初から出せよな!」
「だってこれ、鍵がね、ないんだよ。なんかボタンを押すとかで……」
「今の車はみんなスマートキーなんだよ! これが通常なんだよ!」
「ええ……ひくわ……」
「ひくな!」
かくして、俺は真新しいその運転席に乗り込んだ。
新車特有のシートを引っぺがす。
ユキさんは助手席に、幽々子は後部座席に乗り込んだ。
ブレーキペダルを踏み込んで、スタートボタンを押し込む。
「おお……すごい! 本当に鍵を入れなくてもエンジンがかかった!」
隣ではしゃぐユキさんに、シートベルトをかける。
背後をみると、幽々子はすでにシートベルトを着用していた。
ハンドルを握る。
車を運転するのは久しぶりだ。
ユキさんに出会う前にはたまに頼まれて運転をしていたから、一年ぶりくらいか。
「お。ナビもついてるじゃん」
タッチパネルに触れる。
これなら幽々子の家にもラクに着けそうだ。
「幽々子、住所」
「あ、うん」
たどたどしく住所を口にする幽々子にあわせて、ナビに住所をいれる。
うん、ばっちりだ。問題ない。
アクセルを踏み込む。車が動き出すと、ユキさんが俺を見て小首を傾げた。
「阿久津くん。ナビってなんだい?」
「まじか。マジでいってんのか、ユキさん」
ばきばきと枝が折れる音が車内に響く中、俺は言葉を失った。
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
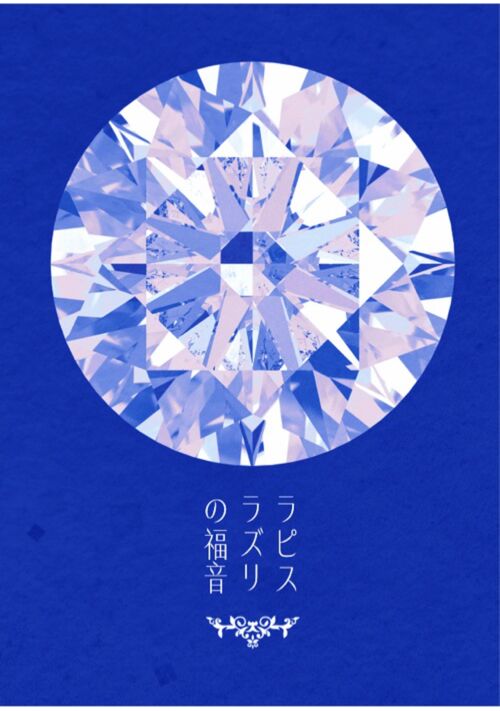
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















