5 / 18
第一章「とある雪の日の邂逅」
03
しおりを挟む山道を普通車で移動すること小一時間。
すっかり日が暮れた頃、ようやくのこと幽々子の家周辺までたどり着けた。
「あとはここを真っ直ぐいくだけ。突き当りにあるマンションがそうだよ」
後部座席で、幽々子は元気そうだ。
「……もっと何か起きるかと思ったけど、何もなかったな」
「何かって?」
「例えば、うーん、電車が突っ込んでくるとか、橋が落ちるとか」
「なんだいそれ。フィクションの定番だな」
俺の呟きに、ユキさんはケラケラと笑った。
どうやら少しは回復できたようだ。
ちなみに俺の方は、久しぶりの運転で結構疲れた。早く帰って寝たい。
「そういや一緒に住んでるっていうその恋人サンよ、大丈夫なのか?」
「ああ、直希はなんていうか、そういうの全然見えなくて。全くダメージなし。私一人怖がってる、みたいな」
「フーン」
難儀なモンだ。
俺がその立場なら、やるせなかったかもしれない。
何しろ怖いという『それ』がみえないのだ。どうしてやりようもない。
俺のそんな感情を感じ取ったのか、幽々子は慌てて首を横に振った。
「でも心配してくれてないってわけじゃないよ。信じてないってわけでもないし。前に私にお守り買ってきてくれたし」
「お守り?」
聞き返したのはユキさんだ。
「う、うん。数珠みたいなのとか、キーホルダーとか。どれもすぐに壊れてなくなっちゃったけど」
「ふうん……あ。阿久津くん、そこのパーキングに入れよう」
「ン」
幽々子の今の話に、ユキさんは何か引っかかりを覚えたみたいだった。
直希。ナオキ。なおき。
うん、全然心当たりがない。高校のやつではないのだろう。
あるいは、転校していった先で出来た恋人なのかもしれない。
ともすれば、その『プレゼントしたお守りがすぐ壊れる』という話のどこに問題があったのかわからない。
大体、お守りなんてのはそんなもんだろうに。
「さて、それじゃ行こう。トランクを忘れないで持ってくれ」
「はいはい」
車から降りる。そのやけに重たいトランクを担ぐ。
「ほんとに画材だけ入ってんの、これ」
「そうだよ。僕の画材は特注だからね」
「怪しい……」
やや遅れて、幽々子が下りてきた。
道の突き当りに、確かにマンションが見える。結構立派なもんだ。
俺と同い年のこいつが購入できるマンションとは思えないけど、やはり何かわけありなのではないだろうか。
幽々子は、マンションが近づいてくるたび、顔色を青ざめさせた。
ぎゅっと胸の前で両手を握りしめて、何かに怯えるようだった。
「つーか、突然訪ねて平気なのか? そのナオキとやら、怒るんじゃねえの」
マンションはまばらに電気がついていた。
たくさんある窓に灯る電気がまばらなことに、何か違和感はおぼえる。が、その程度だ。
よくいわれるような『嫌な感じ』とかはとくにわからない。
「それはないよ。直希は一週間の出張中で、今、ちょっと留守なの」
「ご都合主義だな」
修羅場になることだって考えてはいたのだが。一応。
「阿久津くんは、こういうの初めてだよね?」
「あ?」
ふいに、ユキさんが俺の腕を引いた。
「要するにお化けと対決することさ」
「お化けって、あんたな」
「いいかい。もし何に見えても、決して『僕』以外を頼ってはいけないよ。現場において、『僕』以上はない。そう心にとめておいて」
「……、……おう」
少し間が空いたのは、決して怖かったわけでも、戸惑ったわけでもない。
ただユキさんが、不思議な表情を浮かべたからだった。
まるで俺に祈るかのような、願うかのような、すがるかのような。そんな顔だ。
「それじゃ行こう。ぱっぱと片付けて帰ろうじゃないか」
すぐに表情は戻る。
いつものユキさんの顔だ。
マンションの入口はオートロック仕様だった。
幽々子がそれを解除して、俺たちも後に続く。
六階までエレベーターであがると、六〇六と書かれたドアプレートの前で幽々子は立ち止まった。
「うわ」
思わず声が出た。
ここまでくると、ようやくのこと俺にも何か感じ取れる。
黒いもや、というよりは、黒いどろどろした何か、質量をもったものだ。
油汚れのように悪質で、取りづらく、掃除のしづらい。そんな『汚れ』が思い浮かぶ。
「あ、開けます」
上ずった声で、幽々子が鍵を回す。
がちゃり。
やけに重たい音がした。
それから、ゆっくりとドアが開く。
「…………」
部屋の中は、暗くて何も見えない。
ただその暗闇の中に、何か、もっと、黒い塊があるような気がした。
「電気つけますね」
ぱち。
こちらは軽い音がして、室内の電気が灯った。
まるで四散するように、暗闇に紛れていた何かはその姿を隠してしまった。
「根源ってのは、藁人形とか、そういうもんなのか?」
「どうだろう。ケース・バイ・ケースだからね」
そういうと、ユキさんは室内に入っていった。
辺りをぶしつけにきょろきょろと見渡している。
「となりの部屋は?」
「空き部屋です。確か」
「ふうん……」
コンコン、とユキさんが壁を叩く。
音の響きを確認するような動作だった。
(にしても……)
部屋の中は、幽々子いわくの『ザ・女子』という感じだ。
全体的にピンクで、雑貨が多く、ベッドに彼氏の意見は反映されていないのか、こちらもピンクである。
なんだかいづらくて、視線を天井へそらす。
……そうして、後悔した。
「ユ、ユキさん、あ、あれ」
「うん?」
天井を指さす。
ユキさんも、俺と同じように上を見上げた。
「あらま」
そうして、そんな言葉を呟いた。
天井には、びっしりと、女の髪がひしめいていた。
そりゃもう、ところせまし、という感じだ。
天井のライト回りだけを避けるようにして蠢くそれらは、控えめにいっても気味が悪い。
「これはまた、ずいぶんと……」
「はーいお茶淹れたよ~って……なんで二人そろって上見てるの?」
遅れて、幽々子が台所からこちらに戻ってきたらしい。
そうして俺たちと同様、上を向いたのだろう。
「ひっ!」
と、喉をひきつらせたような悲鳴と共に、カップが床で割れる音がした。
「な、なに、なに、これえ……!」
今にも泣きそうな、幽々子の声がする。
それから、「うーん」と唸るユキさんの声。
俺はと言うと、それから目が離せなかった。
まるで生き物のように天井に張り付いてひしめき、蠢くそれが本当におぞましい。
「思った以上にでかいな……、とりあえずはこれを……」
「! ユキさん!」
天井に張り付いていたそれらが、一斉に動く。
その矛先はすぐにわかった。
ユキさんの体を抱き留めるようにして、床を転がる。
先ほどまでユキさんが立っていた場所には、髪の毛の柱が出来上がっていた。
「おや。助けてくれたのかい、阿久津くん」
ユキさんの危機管理能力も、ここまでくると大物感がある。
「では僕も、君の『主人』として相応しい動きをみせよう」
彼はそんなふうにのんびりと呟くと、片手を向けた。
──思わず、息をのむ。
その手にキラキラとした星の輝きみたいなものが集まっていく。
そうして、それは球体を象ると徐々に大きくなっていった。
「わん、つー、すりー!」
ぱちん、と指パッチンによく似た音が鳴る。
球体は弾かれたように飛び出して、その髪の柱にぶつかった。
途端に球体がはじけ飛ぶ。
中に詰め込まれたたくさんの温かな光が星のように散らばって、天井のそれらに張り付く。
「その光は命の輝き、生命の灯火。全てを焼き焦がすもの──『Sirius(シリウス)』!」
ユキさんの声にこたえるように、星たちは一斉に強い光を放った。
もう目の前は真っ白だ。何一つ見えやしない。
すぐ傍にあるユキさんだけは、かろうじてぼんやりと確認できた。
じゅ、という音がする。
言葉の通り、この強い光で『髪たち』を焼き尽くしているのかもしれない。
「……え」
目を凝らしていると、不意に。
その光の中から──母親が、歩いてきた。
俺の母親だ。そこにいるはずのない、母親だ。
思わず立ち上がろうした俺を、ユキさんの非力な腕が掴んで制した。
「ダメだ。アレはキミに見えてる誰かじゃない」
「で、も」
「僕を信じて。僕以外は、頼ってはならない」
はっとした。
そうだ。俺は、その言葉をかけられた。
ここに来る前に、ここに足を踏み入れる前に。
改めて、目の前に視線を戻す。
「──ッ!」
光の中にいたのは、母親などではなかった。
そこにあったのは、ただのバケモノだ。
髪の長い女。定番の白いワンピースに身を包んで、手と足を真っ赤に濡らした、気味の悪い女だ!
「阿久津くん、トランクをとってくれるかい」
「トランクっていったって、何も見えやしな……」
俺は言葉を失った。
すぐ足元に、あのトランクがある。
「ほら。これでいいか?」
ユキさんに差し出すと、トランクはひとりでに口を開けた。
それから、画材道具たちがわらわらと一人でに溢れ出てくる。
「キミは僕を『魔法使い』で『画家』だと信じてくれたけど、本当は少し違うんだ」
筆がひとりでに宙に浮く。
絵の具がパレットに飛び出して、イーゼルはひとりでに立ち上がった。
最後にキャンバスが、のそのそと歩いてきて、イーゼルの上によじ登る。
キャンバスがセットされると、筆はユキさんに握られることなく、べたべたと絵の具をキャンバスの上に載せ始めた。
「……うわ……」
思わず声が漏れた。
真っ白な光の中に立つ女は、筆によってキャンバスの中に描きこまれていく。
そうしてそれと同時に、そこに立つ女の姿は徐々に薄くなっていくのだ。
──まるで、キャンバスの中に閉じ込められていくかのようだ。
ユキさんは、少し申し訳なさそうに微笑んだ。
「キミにはずっと内緒にしていたかったのだけれど。……僕の本業は、『こういうもの』なのさ」
俺は、ここで初めて、ユキさんの作業風景をここ一年であまりみたことがないことに気が付いた。
最初の頃は居心地が悪くて町をうろついた。
だから絵を描いている姿なんてみなくても当然だと思ってた。
ここ一年の間で売れた絵はほんの数枚で、いつみたってキャンバスは白のまま。
そりゃそうだ。
こういう事象に立ち会う経験をしたのは今が初めてで、ユキさんが単独で行う姿も俺は見ていない。
かたん。
筆が落ちる。
光が止んで、色が戻ってくる。
天井にはもう髪が蠢いていたりしなかった。
どこかくすんでいた部屋の空気が、少しはマシになった気がした。
……そうして、キャンバスにはやつがいる。
あの薄気味悪い女が、閉じ込められている。
「さて」
ユキさんが指を弾くと、どこからともなく黒い布がキャンバスを覆った。
まるで梱包するかのようにキャンバスを包み込む。
そうして、トランクの中へとそれは放り込まれていった。
「これで完了だ。おそらくはもう安全だと思うけど」
「おわ、った、んだ」
幽々子は、放心状態だった。
呆然とこちらを見つめていて、心ここにあらず、といったようだ。
「さあ、帰ろうか、阿久津くん」
「あ、ああ」
すでに踵を返しているユキさんのあとを、慌てて追いかける。
重いトランクをひっつかむと、いくらか重さが増しているように思えた。
「ま、待って!」
幽々子が俺たちを呼び止める。
ユキさんが、「うん?」と振り返った。
つられて俺も振り返る。
幽々子は、涙目でこちらをみて、震えていた。
「あ、ありがとうございました!」
「いいえ。困ったときはお互いさまさ」
答えたのはユキさんだった。
彼が足を進めたので、俺もそれに続く。
幽々子の震えが少し気になったが、まあ、ユキさんが大丈夫というのだから大丈夫なのだろう。
マンションの階段を下りて、正面の出口から出る。
あのパーキングまで戻ってオーリスに乗り込むと、時刻が十九時を回っていることを知った。
「ユキさん、今日はこのへんで食べてかない?」
助手席に乗り込む彼に声をかける。
しかしユキさんは首を横に振った。
「それより先に、やることがあるだろう?」
「やること?」
絵の販売登録とか? と小首を傾げた俺に、ユキさんは言った。
「バルミューダだよ! 究極のトースターさ! 絵を描き上げたのだから、当然、買って帰る権利があるだろう?」
呆れてしまった。
こんなことがあったのに、よもやそこに意識があるとは。
どれだけ究極のトースターとやらを食べたいんだ、このひとは。
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
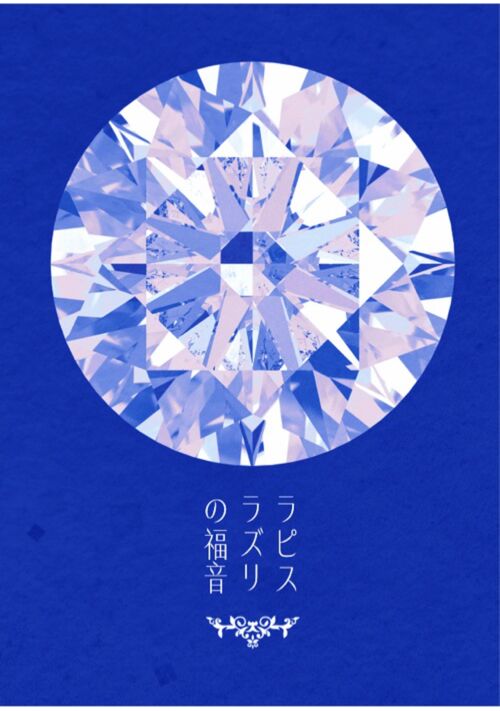
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















