6 / 18
第一章「とある雪の日の邂逅」
04
しおりを挟む「え? 結局、幽々子ちゃんのところにいたのは『何』だったのかって?」
バルミューダ(高級オーブントースターの名前である。カッコイイ)を担ぎ上げる俺を見上げて、ユキさんは振り返った。
その手はすでにドアノブを回している。
「ン。だって気になるだろ。……それがあんたの本業だっていうなら」
「うーん、でも僕、これからはただの『画家』として生きていこうと思ってたんだけどなあ」
切り立った崖の壁をそのまま生かして作られた我が家の前で車を止めると、オーリスはその車体をまた土の中に消していった。
正直勿体ない。今でこそあまり見かけないし、生産されているのかは不明だがそれでも前に見かけたときは四百万近くしていた。
それが、ずるずると土の中に還っていくのだから、土汚れがつかないって知ってたってどきどきする。
「幽々子ちゃんのことは本当に、見えてしまったしキミの知り合いだから助けただけさ」
ガチャり。
ドアノブが回って、ドアが開く。
ユキさんが入っていく後ろに、俺も続く。
「てことはなに、あんた、一年も俺を養うために慣れない絵を描いてたってこと?」
「う」
ぴたり。ユキさんが立ち止まる。
「……あ、あんまりそういうこと言わないでくれよ。照れるなあ」
わずかに振り返った耳が赤い。
珍しいことがあるもんだ。本当に照れているらしかった。
なんだか俺まで、顔が熱くなってきた。
「それにあんなことをして暮らしてたのはここ数百年くらいの間だけさ。もっと前は、普通に森の奥でひっそりと暮らしていたんだよ」
「待った。ずっと聞きたかったんだけど、あんた、何歳なわけ?」
「さあ? 生きてる年数が千を超えると、一体いつから生きてるのかわからなくなるものだよ」
トランクと、バルミューダを降ろす。
さて、このバルミューダをどこに置くかだが……。
「あっ。待った。キミ、今、古いオーブントースターを捨てようと思っただろう」
台所に置かれているオーブントースターを庇うように、ユキさんが立ちはだかった。
俺の視線の先をみたのだろう。
「ダメだぞ。これはキミが最初におススメしてくれた家電じゃないか!」
「だって置く場所ないだろ」
この家は手狭である。
ベッドは一つしかないし、台所だってそんなに広くない。
ソファだって二組しかないし、テーブルも一つだ。
どっか市内のマンションの方がはるかに広いだろう。
「じゃあ僕の倉庫にいれておこう。……ごめんね、また使うからね」
ユキさんは、そうやって古いオーブントースターを撫でた。
するとそれはまるで命でも得たように、ずるずると這って床へ降りると、ユキさんの群青色のコートの内側へと消えていった。
……この人、マジで四次元ポケットとか持ってるかもしれない。
「やれやれ……」
箱からそのシックな黒い本体を取り出す。
すっぽり空いたその隙間にセットすると、ユキさんが「おお!」と声を上げる。
「これで明日の朝は究極のトーストが食べれるわけだね」
「そうだな」
冷蔵庫を開ける。
結局飯は外食になった。
外食と言っても、ユキさんが外で食べるのを嫌がるからファーストフードを買ってきただけだが。
お手頃価格のハンバーガーセット。
気にしてないとはいってるけど、ユキさんはあまり外に出たがらないし、夏でもそのマントみたいなコートを離さない。
(隻腕って、何かと目をひくしな)
義手でもあればもう少し違うのかもしれないが。
いやでも、ユキさんなら高性能な義手くらい持っていそうだ。
「ほら、とっとと食って寝ようぜ」
「そうだね」
買ってきた包みを開ける。
ハンバーガー特有のあのいい匂いが室内に広がった。
「……さっきの質問だけれど、あれはね、『誰かの悪意』だよ」
「悪意?」
「そう。それも死んだひとのじゃない。生きている人間のものだ」
包みからハンバーガーを二つ、ポテトを二つ、飲み物を二つ取り出す。
どっちも同じものだ。チーズバーガーに目玉焼きが挟まったやつ。
飲み物もド定番のコーラだ。ユキさんはこれを飲んだことがないらしい。
「恐らく彼女は何か強い恨みをかったんだろうよ。その体を真っ二つか、あるいは潰してやりたいと思うほどにね」
「幽々子が、そんなに強い恨みを? 考えられねえな」
ばく、とかぶりつく。
俺の所作をみて、ユキさんもそれを真似た。
「……ん? でもそいつ、生きてるってことはまた起こるんじゃねえの?」
もぐもぐと咀嚼しながら眉間にしわを寄せると、ユキさんはそれをごくんと飲み込んで、頷いた。
「うん。そうだよ」
「いやそれ解決してねーじゃん!」
思わずソファから立ち上がってしまった。
幽々子の少し安堵した表情が思い浮かぶ。……同時に、わずかに震えが残る体も。
「とりあえずの脅威を拭っただけだからね。もう一度強いものを『送る』なんて素人ならしばらくは不可能だよ」
対して、ユキさんは素っ気ないもんだ。
ハンバーガーに夢中である。
それを食べ終わると、ポテトを一つ手に取って口に放り込んだ。
しょっぱい! と顔をしかめる様は完全に他人事だ。
「素人じゃなかったら?」
「え?」
「だから、相手が素人じゃなくて、なんかこう、呪いとか使える相手ならどうなんだよ」
ハンバーガーを一気に口へ放り込む。
ポテトには手をつけなかった。かわりにコーラで、口の中を流し込む。
返答次第では、幽々子の部屋にもう一度行く必要だってあるだろう。
「うーん、この国にはそれこそ魔法使いと同じくらい現存していないと思うけれど……そうだなあ」
ユキさんも、ポテトをコーラで流し込んで、ごくんと飲み込んだ。
うわ、しゅわしゅわしてる! と声が漏れる。
「もしそうだったなら、今晩にでも仕掛けてくるかもしれないね」
「!」
俺はその言葉をうけて、すかさずドアへと足を向けた。
突然の行動に見えたのか、ユキさんが慌ててソファから立ち上がる。
「ど、どこいくの?」
「幽々子んとこ。悪いユキさん、車もっかい貸して」
靴を履いて振り返ると、ユキさんは俯いてそこに立っていた。
「……あの子がまだ大事なの?」
「はあ?」
思わず呆れながら聞き返した。
なんでそうなるのかわからないし、何でそんなことをきくのかわからなかった。
「あのな。あいつにはちゃんと新しい相手がいただろ。今更俺がどうこう思うと思ってんのか?」
「だって、妙に気に掛けるじゃないか」
「そりゃ知り合いだからな。当然だろ」
「じゃあ、も、元カノじゃなかったとしても、彼女の家に向かうのかい?」
「知り合いが死んだら後味が悪いからな」
「ふうん……そういうものなのか……」
少し何か考えるふうにして、ユキさんも俺の隣に並んだ。
靴を履いて、トランクを手招きする。
「? あんたもくるのか」
「キミ一人じゃ対処なんて出来ないでしょう」
ユキさんは、トランクを開けると中から黒い布で包まれたキャンバスを取り出した。
それをコートの内側にしまい込んで、それから、真新しいキャンバスを取り出す。
ふとあの気味の悪い女が頭に思い浮かんでしまって、俺は頭を横に振った。
「さあ、行こうか」
少し前で、ユキさんがドアを開けてこちらに微笑みかけていた。
その微笑みが少し寂しそうで、俺は少し疑問に思いながら、そのあとを続いた。
***
──震えが止まらない。
あの真っ白な光の中にいた直希の手を取ってから、体の調子がおかしい。
(でも、あの不思議な画家さんは、もう大丈夫っていってたし)
気のせいかもしれない。
けれど、そうではないかもしれない。
嫌な感じはずうっと消えないのだ。この部屋からなのか、隣からなのか、はたまた、自分からなのか。
「う、うう、うう」
テレビは消した。
聞こえてくる音声に何か違う声がかぶって聞こえるからだ。
けれど音を消すと、周囲から聞こえてくる他人の生活音が違う音に聞こえてきて、それもまたストレスになる。
それならばと何も聞こえないようにイヤホンを耳にはめてみたけど、その無音もまた、嵐の前の静けさを思わせて嫌だった。
(直希さえ、帰ってきてくれれば)
少なくとも二人で笑いごとにできたし、怖さは半減したはずだ。
二人でそうやって生きてきたのだ。
この怪奇現象が度を越えておかしくなり命を狙うようになったのは直希の出張後からだ。
きっと直希さえ帰ってくれば、また、いつもみたいに。
少なく、収まってくれる、はずなのに。
こんこんっ
背筋が凍った。
ノック音だ。
イヤホンをしていても、それが『玄関のドア』を叩いていることがわかる。
(だって、だって、大丈夫だって)
心臓が止まってしまいそうなほど鼓動している。
激しい動悸に吐き気さえ催してきた。
必死にスマホで、直希にメッセージを送る。
もうメンヘラだとか妄想だとか何を言われてもいいと思った。
もしこれが、死ぬ間際の瞬間だというのなら。
──あなたに会えて、幸せだったと告白しておきたい。
「……幽々子? いないのか?」
「! 阿久津!」
ハッとした。
なんだ、と安堵した。
玄関にいたのは彼だったのだ。きっと何かあったに違いない。
そう思ってスマホから手を離し、玄関へ向かって、鍵を──
「開けるなッ!」
背後から怒鳴るような声がして、振り返る。
ベランダの窓を突き破って、阿久津がそこにいた。脇にはあの真っ白な髪の魔法使いを抱えて。
「ドアから離れなさい」
「え、あ、なん、で」
「いいから」
真っ白な髪の魔法使いが言う。
彼女は、じりじりと退いた。
ドアのノックが途端に激しくなる。まるで突き破ろうとしているかのようだった。
「もう大丈夫だなんて軽率な発言を撤回するよ」
「おう、そうしてくれ」
幽々子の隣を、二人がすたすたと歩いて行った。
阿久津の手には、あの重そうなトランクが再び握られている。
「でもそれで『釣った』ようなものだ。ふふ、そこはうまくいったね」
魔法使いは、片手をドアへとむける。
「来るよ、阿久津くん。幽々子ちゃんを守るよう意識を向けて」
「おう」
ノックの音が止む。
そうして、ひとりでにがちゃり、と鍵が回った。
ぎいい、と音が鳴って、ドアが開く。
幽々子はハッと口を押えた。鳴き声も嗚咽も一切を漏らさないようにだった。
「……うふふ、ふふ。みぃつけた」
少し子供っぽい声で、それは喋った。
真っ黒に塗りつぶされた、影のような小さな少女だった。
「せんせえにわるいことする、わるーいおんな」
「ひっ……」
少女は、じろり、と一つしかない目玉を幽々子に向ける。
目と目がばちっとあった。
たったそれだけで、体の自由はまるできかなくなってしまった。
「おっと」
その視線を、阿久津が阻む。
「……む」
少女は唇を尖らせて、阿久津を見た。
そのぎょろりとした目玉は化け物のようだ。
(うお、なんだ)
視線を合わせると、バチ、と電気が走るようだった。
しかしとくにそれ以外に異変はない。
「あなたきらい。もうだれかのものなのね、あなた」
「あ?」
「まがん、きかないんだわ。そんなのいや」
まがん。
マガン。
魔眼?
そこに思い至って、阿久津は少し顔をひきつらせた。
そんなものにお目にかかるのは初めてだ。
「そうだよ。彼は僕のものだ」
答えたのはやはり、魔法使いだった。
「キミは、僕と同じ絶滅危惧種──『魔女』だね?」
「うふふ」
彼女はその真っ黒な体でくすくすと笑うと、頷いた。
「ええ、ええ。そうよ、そのとおり」
ずず、と音がした。
彼女の足元、その真っ黒な影から、髪の毛のようなものがずるずると這い出てくる。
「りそうのわたしをえのなかにとじこめた『わるーいまほうつかいさん』はあなたね」
「ふふ」
魔法使いの足元からは、対照的にきらきらと星の輝きが漏れた。
そうしてその輝きは、阿久津と、幽々子の真下へ広がっていく。
阿久津は、じろ、とその真っ黒な少女を睨みつけた。
真っ黒な体の、真ん中。
胸のあたりに、真っ赤に塗りつぶされた心臓が見える。
それは色鮮やかで、どくどくと、脈を打っていた。
0
あなたにおすすめの小説

俺の婚約者は小さな王子さま?!
大和 柊霞
BL
「私の婚約者になってくれますか?」
そう言い放ったのはこの国の王子さま?!
同性婚の認められるパミュロン王国で次期国王候補の第1王子アルミスから婚約を求められたのは、公爵家三男のカイルア。公爵家でありながら、長男のように頭脳明晰でもなければ次男のように多才でもないカイルアは自由気ままに生きてかれこれ22年。
今の暮らしは性に合っているし、何不自由ない!人生は穏やかに過ごすべきだ!と思っていたのに、まさか10歳の王子に婚約を申し込まれてしまったのだ。
「年の差12歳なんてありえない!」
初めはそんな事を考えていたカイルアだったがアルミス王子と過ごすうちに少しづつ考えが変わっていき……。
頑張り屋のアルミス王子と、諦め系自由人のカイルアが織り成す救済BL

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
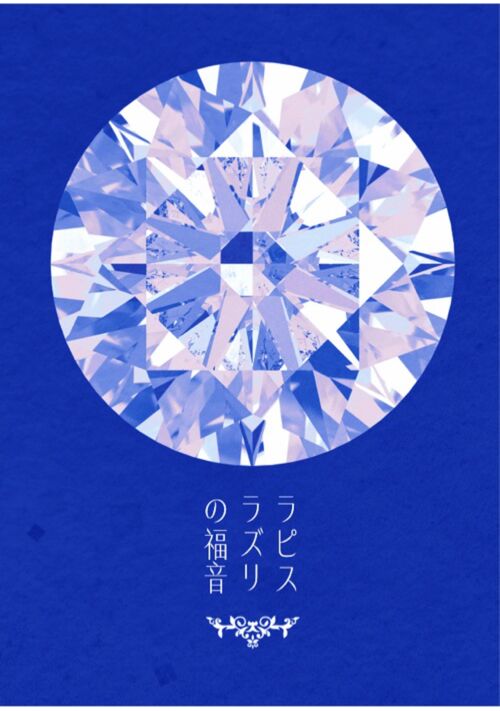
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

後宮に咲く美しき寵后
不来方しい
BL
フィリの故郷であるルロ国では、真っ白な肌に金色の髪を持つ人間は魔女の生まれ変わりだと伝えられていた。生まれた者は民衆の前で焚刑に処し、こうして人々の安心を得る一方、犠牲を当たり前のように受け入れている国だった。
フィリもまた雪のような肌と金髪を持って生まれ、来るべきときに備え、地下の部屋で閉じ込められて生活をしていた。第四王子として生まれても、処刑への道は免れられなかった。
そんなフィリの元に、縁談の話が舞い込んでくる。
縁談の相手はファルーハ王国の第三王子であるヴァシリス。顔も名前も知らない王子との結婚の話は、同性婚に偏見があるルロ国にとって、フィリはさらに肩身の狭い思いをする。
ファルーハ王国は砂漠地帯にある王国であり、雪国であるルロ国とは真逆だ。縁談などフィリ信じず、ついにそのときが来たと諦めの境地に至った。
情報がほとんどないファルーハ王国へ向かうと、国を上げて祝福する民衆に触れ、処刑場へ向かうものだとばかり思っていたフィリは困惑する。
狼狽するフィリの元へ現れたのは、浅黒い肌と黒髪、サファイア色の瞳を持つヴァシリスだった。彼はまだ成人にはあと二年早い子供であり、未成年と婚姻の儀を行うのかと不意を突かれた。
縁談の持ち込みから婚儀までが早く、しかも相手は未成年。そこには第二王子であるジャミルの思惑が隠されていて──。

カフェ・コン・レーチェ
こうらい ゆあ
BL
小さな喫茶店 音雫には、今日も静かなオルゴール調のの曲が流れている。
背が高すぎるせいか、いつも肩をすぼめている常連の彼が来てくれるのを、僕は密かに楽しみにしていた。
苦いブラックが苦手なのに、毎日変わらずブラックを頼む彼が気になる。
今日はいつもより温度を下げてみようかな?香りだけ甘いものは苦手かな?どうすれば、喜んでくれる?
「君の淹れる珈琲が一番美味しい」
苦手なくせに、いつも僕が淹れた珈琲を褒めてくれる彼。
照れ臭そうに顔を赤ながらも褒めてくれる彼ともっと仲良くなりたい。
そんな、ささやかな想いを込めて、今日も丁寧に豆を挽く。
甘く、切なく、でも愛しくてたまらない――
珈琲の香りに包まれた、静かで優しい記憶の物語。


隊長さんとボク
ばたかっぷ
BL
ボクの名前はエナ。
エドリアーリアナ国の守護神獣だけど、斑色の毛並みのボクはいつもひとりぼっち。
そんなボクの前に現れたのは優しい隊長さんだった――。
王候騎士団隊長さんが大好きな小動物が頑張る、なんちゃってファンタジーです。
きゅ~きゅ~鳴くもふもふな小動物とそのもふもふを愛でる隊長さんで構成されています。
えろ皆無らぶ成分も極小ですσ(^◇^;)本格ファンタジーをお求めの方は回れ右でお願いします~m(_ _)m
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















