4 / 5
第三章:顕になる溺愛
しおりを挟む
グレイホールド城での私の立場は、いつしか微妙な、しかし確実な変化を遂げていた。「客人」というよりも、むしろ城の「奥方」に近いような扱いを、周囲から受けるようになっていたのだ。それは、他ならぬライオス・グレイウォール辺境伯自身の、私に対する態度が原因であることは明らかだった。
彼の私への配慮は、日を追うごとに細やかさを増していった。私が執務室で書類仕事に没頭していると、いつの間にか侍女が温かいハーブティーと、私の好物であるドライフルーツを添えた焼き菓子を運んでくる。聞けば、「旦那様が、セレスティア様がお疲れではないかと気遣われて」とのこと。私が少しでも眉を顰めたり、ため息をついたりするのを見咎めようものなら、ライオス様は即座に「何か不都合でもあったか?誰がセレスティア嬢を不快にさせたのだ?」と、周囲の侍従たちに氷のように冷たい視線を送る。その剣幕は、彼らが震え上がるほどだった。
私が書庫で古い文献を調べていると知れば、翌日には王都の書店から最新の関連書籍が何冊も届いている。私が庭園の花々を愛でているのを見れば、珍しい品種の球根や種が遠方から取り寄せられ、庭師たちが嬉々としてそれらを植え始める。まるで、私の小さな願いや好みが、彼の絶対的な命令であるかのように、城全体が動いているかのようだった。
当初は戸惑いを隠せなかった家臣たちも、ライオス様の私への並々ならぬ執心ぶりと、私が実際に領地経営に多大な貢献をしている事実を目の当たりにするうちに、徐々にその態度を軟化させていった。むしろ、彼らは「セレスティア様のお気に召すように」と、先回りして私に便宜を図ろうとさえし始めた。
ある晩餐の席でのことだった。隣国の横柄な使者が、酒の勢いも手伝ってか、私に対して侮辱的な言葉を口にしたのだ。
「ほう、これが噂のヴァーミリオン公爵のご令嬢か。王太子殿下に捨てられ、辺境伯に拾われたとは…まことにお気の毒な境遇ですな。まぁ、女の価値など、所詮はその程度のものかもしれませぬが」
その言葉が発せられた瞬間、それまで和やかだった晩餐の空気が凍り付いた。ライオス様の顔から表情が消え、その灰色の瞳は絶対零度の氷のように冷たく光った。彼が静かにナイフを置く音が、やけに大きく響く。
「貴様…今、何と言った?」
彼の声は低く、地を這うようだったが、その奥には抑えきれない怒りの炎が燃え盛っているのがわかった。使者は、ライオス様のただならぬ雰囲気にようやく気づき、顔面蒼白になったが、もう遅い。
「我がグレイウォール辺境伯家が、最大の敬意を払ってお迎えしているセレスティア嬢を侮辱するとは…貴国は、我が領に戦を仕掛けたいと、そう解釈してよろしいか?」
それは脅しではなかった。本気の宣告だった。彼の背後には、いつでも牙を剥く準備ができている「北の狼」の影が見えるようだった。
「い、いえ、滅相もございません!酔った上での失言、どうかお許しを…!」
使者は震えながら床に額を擦り付けて謝罪し、その日のうちにほうほうの体で領地から逃げ帰っていった。
その夜、ライオス様は私の部屋を訪れた。彼は何も言わず、ただ暖炉の前に立つ私の肩を、後ろからそっと抱きしめた。
「すまなかった。あのような不快な思いをさせてしまった」
「いいえ…ライオス様。私は、大丈夫ですわ」
「君を傷つけるものは、それが何であろうと、私が全て排除する」彼の腕に力がこもる。「君は、ただ…ここにいて、笑っていてくれればいい。それだけで、私は…」
彼はそれ以上言葉を続けなかったが、その温もりと、私を見つめる熱のこもった瞳が、何よりも雄弁に彼の想いを物語っていた。それは、単なる庇護欲ではない。もっと深く、もっと個人的な、燃えるような独占欲と、そして紛れもない愛情だった。
この出来事は、城の内外に瞬く間に広まった。「辺境伯は、セレスティア嬢に完全に心を奪われている」「彼女を傷つける者は、たとえ隣国の使者であろうと容赦しない」と。
それは「溺愛」と呼ぶにふさわしいものだった。初めは、彼の過剰とも思える庇護に戸惑いを感じていた私も、いつしかその深い愛情に包まれることに、心地よさを感じ始めていた。彼の腕の中は、世界で一番安全で、温かい場所だと感じるようになっていた。
ある晴れた日、私はライオス様と共に馬で領地を巡っていた。雪解け水の流れる小川のほとりで休憩していた時、彼が不意に私の手を取った。
「セレスティア」
初めて、彼は私のことを「嬢」を付けずに呼んだ。その響きに、私の心臓が小さく跳ねる。
「私は…君なしでは、もう生きていけないのかもしれない」
彼の真剣な眼差しが、私を射抜く。
「君がここにいてくれるだけで、この雪原にも春が来たように感じる。君の笑顔は、どんな太陽よりも温かい」
それは、武骨で言葉数の少ない彼が、必死で紡ぎ出した愛の言葉だった。その不器用さが、かえって私の胸を強く打った。
私は、彼の手に自分の手を重ねた。
「ライオス様…私も、同じ気持ちですわ。あなたのそばにいられることが、今の私の何よりの幸せです」
彼の顔に、これまで見たこともないような柔らかな笑みが浮かんだ。それは、まるで厳冬を乗り越え、ようやく訪れた春の陽光のように、温かく、そして眩しかった。
もはや、私たちの間に遠慮や躊躇いはなかった。彼の愛情は、時に激しく、時に優しく、私を包み込む。そして私もまた、この不器用で、しかし誰よりも誠実な「北の狼」を、心の底から愛していることを自覚していた。かつて「氷の貴婦人」と呼ばれた私の心は、彼の熱い想いによって完全に溶かされ、そこには彼への深い愛情と信頼が、確かな温もりとなって息づいていた。
彼の私への配慮は、日を追うごとに細やかさを増していった。私が執務室で書類仕事に没頭していると、いつの間にか侍女が温かいハーブティーと、私の好物であるドライフルーツを添えた焼き菓子を運んでくる。聞けば、「旦那様が、セレスティア様がお疲れではないかと気遣われて」とのこと。私が少しでも眉を顰めたり、ため息をついたりするのを見咎めようものなら、ライオス様は即座に「何か不都合でもあったか?誰がセレスティア嬢を不快にさせたのだ?」と、周囲の侍従たちに氷のように冷たい視線を送る。その剣幕は、彼らが震え上がるほどだった。
私が書庫で古い文献を調べていると知れば、翌日には王都の書店から最新の関連書籍が何冊も届いている。私が庭園の花々を愛でているのを見れば、珍しい品種の球根や種が遠方から取り寄せられ、庭師たちが嬉々としてそれらを植え始める。まるで、私の小さな願いや好みが、彼の絶対的な命令であるかのように、城全体が動いているかのようだった。
当初は戸惑いを隠せなかった家臣たちも、ライオス様の私への並々ならぬ執心ぶりと、私が実際に領地経営に多大な貢献をしている事実を目の当たりにするうちに、徐々にその態度を軟化させていった。むしろ、彼らは「セレスティア様のお気に召すように」と、先回りして私に便宜を図ろうとさえし始めた。
ある晩餐の席でのことだった。隣国の横柄な使者が、酒の勢いも手伝ってか、私に対して侮辱的な言葉を口にしたのだ。
「ほう、これが噂のヴァーミリオン公爵のご令嬢か。王太子殿下に捨てられ、辺境伯に拾われたとは…まことにお気の毒な境遇ですな。まぁ、女の価値など、所詮はその程度のものかもしれませぬが」
その言葉が発せられた瞬間、それまで和やかだった晩餐の空気が凍り付いた。ライオス様の顔から表情が消え、その灰色の瞳は絶対零度の氷のように冷たく光った。彼が静かにナイフを置く音が、やけに大きく響く。
「貴様…今、何と言った?」
彼の声は低く、地を這うようだったが、その奥には抑えきれない怒りの炎が燃え盛っているのがわかった。使者は、ライオス様のただならぬ雰囲気にようやく気づき、顔面蒼白になったが、もう遅い。
「我がグレイウォール辺境伯家が、最大の敬意を払ってお迎えしているセレスティア嬢を侮辱するとは…貴国は、我が領に戦を仕掛けたいと、そう解釈してよろしいか?」
それは脅しではなかった。本気の宣告だった。彼の背後には、いつでも牙を剥く準備ができている「北の狼」の影が見えるようだった。
「い、いえ、滅相もございません!酔った上での失言、どうかお許しを…!」
使者は震えながら床に額を擦り付けて謝罪し、その日のうちにほうほうの体で領地から逃げ帰っていった。
その夜、ライオス様は私の部屋を訪れた。彼は何も言わず、ただ暖炉の前に立つ私の肩を、後ろからそっと抱きしめた。
「すまなかった。あのような不快な思いをさせてしまった」
「いいえ…ライオス様。私は、大丈夫ですわ」
「君を傷つけるものは、それが何であろうと、私が全て排除する」彼の腕に力がこもる。「君は、ただ…ここにいて、笑っていてくれればいい。それだけで、私は…」
彼はそれ以上言葉を続けなかったが、その温もりと、私を見つめる熱のこもった瞳が、何よりも雄弁に彼の想いを物語っていた。それは、単なる庇護欲ではない。もっと深く、もっと個人的な、燃えるような独占欲と、そして紛れもない愛情だった。
この出来事は、城の内外に瞬く間に広まった。「辺境伯は、セレスティア嬢に完全に心を奪われている」「彼女を傷つける者は、たとえ隣国の使者であろうと容赦しない」と。
それは「溺愛」と呼ぶにふさわしいものだった。初めは、彼の過剰とも思える庇護に戸惑いを感じていた私も、いつしかその深い愛情に包まれることに、心地よさを感じ始めていた。彼の腕の中は、世界で一番安全で、温かい場所だと感じるようになっていた。
ある晴れた日、私はライオス様と共に馬で領地を巡っていた。雪解け水の流れる小川のほとりで休憩していた時、彼が不意に私の手を取った。
「セレスティア」
初めて、彼は私のことを「嬢」を付けずに呼んだ。その響きに、私の心臓が小さく跳ねる。
「私は…君なしでは、もう生きていけないのかもしれない」
彼の真剣な眼差しが、私を射抜く。
「君がここにいてくれるだけで、この雪原にも春が来たように感じる。君の笑顔は、どんな太陽よりも温かい」
それは、武骨で言葉数の少ない彼が、必死で紡ぎ出した愛の言葉だった。その不器用さが、かえって私の胸を強く打った。
私は、彼の手に自分の手を重ねた。
「ライオス様…私も、同じ気持ちですわ。あなたのそばにいられることが、今の私の何よりの幸せです」
彼の顔に、これまで見たこともないような柔らかな笑みが浮かんだ。それは、まるで厳冬を乗り越え、ようやく訪れた春の陽光のように、温かく、そして眩しかった。
もはや、私たちの間に遠慮や躊躇いはなかった。彼の愛情は、時に激しく、時に優しく、私を包み込む。そして私もまた、この不器用で、しかし誰よりも誠実な「北の狼」を、心の底から愛していることを自覚していた。かつて「氷の貴婦人」と呼ばれた私の心は、彼の熱い想いによって完全に溶かされ、そこには彼への深い愛情と信頼が、確かな温もりとなって息づいていた。
0
あなたにおすすめの小説

地味な私では退屈だったのでしょう? 最強聖騎士団長の溺愛妃になったので、元婚約者はどうぞお好きに
reva
恋愛
「君と一緒にいると退屈だ」――そう言って、婚約者の伯爵令息カイル様は、私を捨てた。
選んだのは、華やかで社交的な公爵令嬢。
地味で無口な私には、誰も見向きもしない……そう思っていたのに。
失意のまま辺境へ向かった私が出会ったのは、偶然にも国中の騎士の頂点に立つ、最強の聖騎士団長でした。
「君は、僕にとってかけがえのない存在だ」
彼の優しさに触れ、私の世界は色づき始める。
そして、私は彼の正妃として王都へ……

あなたが「いらない」と言った私ですが、溺愛される妻になりました
reva
恋愛
「君みたいな女は、俺の隣にいる価値がない!」冷酷な元婚約者に突き放され、すべてを失った私。
けれど、旅の途中で出会った辺境伯エリオット様は、私の凍った心をゆっくりと溶かしてくれた。
彼の領地で、私は初めて「必要とされる」喜びを知り、やがて彼の妻として迎えられる。
一方、王都では元婚約者の不実が暴かれ、彼の破滅への道が始まる。
かつて私を軽んじた彼が、今、私に助けを求めてくるけれど、もう私の目に映るのはあなたじゃない。

婚約破棄ブームに乗ってみた結果、婚約者様が本性を現しました
ラム猫
恋愛
『最新のトレンドは、婚約破棄!
フィアンセに婚約破棄を提示して、相手の反応で本心を知ってみましょう。これにより、仲が深まったと答えたカップルは大勢います!
※結果がどうなろうと、我々は責任を負いません』
……という特設ページを親友から見せられたエレアノールは、なかなか距離の縮まらない婚約者が自分のことをどう思っているのかを知るためにも、この流行に乗ってみることにした。
彼が他の女性と仲良くしているところを目撃した今、彼と婚約破棄して身を引くのが正しいのかもしれないと、そう思いながら。
しかし実際に婚約破棄を提示してみると、彼は豹変して……!?
※『小説家になろう』様、『カクヨム』様にも投稿しています

寵愛の花嫁は毒を愛でる~いじわる義母の陰謀を華麗にスルーして、最愛の公爵様と幸せになります~
紅葉山参
恋愛
アエナは貧しい子爵家から、国の英雄と名高いルーカス公爵の元へと嫁いだ。彼との政略結婚は、彼の底なしの優しさと、情熱的な寵愛によって、アエナにとってかけがえのない幸福となった。しかし、その幸福を妬み、毎日のように粘着質ないじめを繰り返す者が一人、それは夫の継母であるユーカ夫人である。
「たかが子爵の娘が、公爵家の奥様面など」 ユーカ様はそう言って、私に次から次へと理不尽な嫌がらせを仕掛けてくる。大切な食器を隠したり、ルーカス様に嘘の告げ口をしたり、社交界で恥をかかせようとしたり。
だが、私は決して挫けない。愛する公爵様との穏やかな日々を守るため、そして何より、彼が大切な家族と信じているユーカ様を悲しませないためにも、私はこの毒を静かに受け流すことに決めたのだ。
誰も気づかないほど巧妙に、いじめを優雅にスルーするアエナ。公爵であるあなたに心配をかけまいと、彼女は今日も微笑みを絶やさない。しかし、毒は徐々に、確実に、その濃度を増していく。ついに義母は、アエナの命に関わるような、取り返しのつかない大罪に手を染めてしまう。
愛と策略、そして運命の結末。この溺愛系ヒロインが、華麗なるスルー術で、最愛の公爵様との未来を掴み取る、痛快でロマンティックな物語の幕開けです。
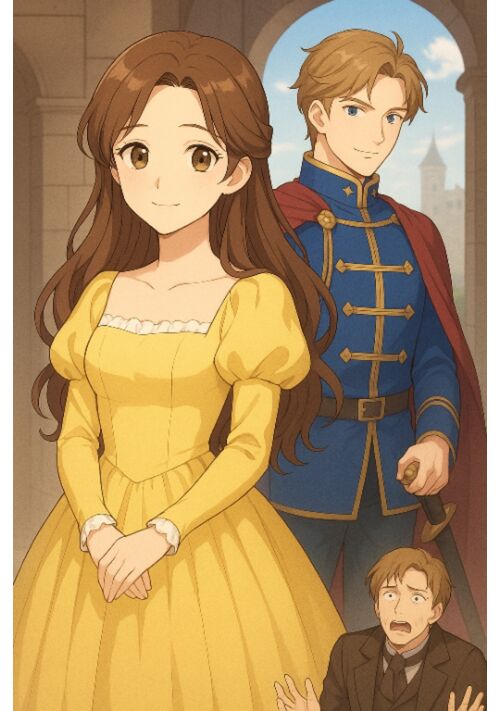
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
reva
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……

【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。
猫屋敷 むぎ
恋愛
没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――
私の願いは一瞬にして踏みにじられました。
母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、
婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。
「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」
まさか――あの優しい彼が?
そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。
子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。
でも、私には、味方など誰もいませんでした。
ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。
白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。
「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」
やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。
それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、
冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。
没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。
これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。
※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ
※わんこが繋ぐ恋物語です
※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

その言葉、今さらですか?あなたが落ちぶれても、もう助けてあげる理由はありません
reva
恋愛
「君は、地味すぎるんだ」――そう言って、辺境伯子息の婚約者はわたしを捨てた。
彼が選んだのは、華やかで社交界の華と謳われる侯爵令嬢。
絶望の淵にいたわたしは、道で倒れていた旅人を助ける。
彼の正体は、なんと隣国の皇帝だった。
「君の優しさに心を奪われた」優しく微笑む彼に求婚され、わたしは皇妃として新たな人生を歩み始める。
一方、元婚約者は選んだ姫に裏切られ、すべてを失う。
助けを乞う彼に、わたしは冷たく言い放つ。
「あなたを助ける義理はありません」。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















