46 / 81
和風の豪邸
しおりを挟む
4車線もある太い幹線道路を下り、郊外に向かったタクシーの車窓が広くなったような気がした。高いビルは鳴りを潜めて空が広い。
前を行く車の数が減り、後ろを走る車もいなくなった頃、妙に敷地の大きい住宅地を抜けた所でタクシーが止まった。
そこはやけに立派な純和風数寄屋門の前だ。
「ここは?」
「ここはって俺ん家に決まってるだろう」
「え?マンションとかアパートじゃ無いんですか?一軒家?」
「何でもいいだろ」と氷上は笑うが、鍵の掛かった引戸を開けると松の傘が迎えてくれる。その奥に建つのは焼杉の壁に幾重にも重なる瓦屋根、正面から見える窓はほぼ木の雨戸に塞がれているが、見る限りアルミサッシは一つもない。
しかも圧倒されるくらい大きかった。
「か、家族がいるんじゃ無いですか?」
髭を生やし、着物を来たお父さんと氷上と同じ目をした若いお母さんがいたら……
速攻で逃げる。
「何を慌ててるんだ」
「だって…何て挨拶すればいいかわかりません」
「家族はいない、俺1人だよ」
「え?ここに?……1人で?」
「前は兄貴がいたけど結婚して出ていったからな、ああ、床をよく見て歩かないと足の裏が黒くなるぞ」
土間で靴を脱いで玄関の式代を上がると廊下も畳だった。
足が汚れると言われたから床をよく見てみると、普段使用しているらしい生活の導線が見えるくらいの厚い埃が積もってる。
「こんな広い家に1人なんて寂しくは無いんですか?ってか怖いでしょう」
「慣れてるから寂しくも無いし怖くも無い、でも奥とか2階に行くと電器が切れてるから何かいるかもな、俺は風呂とトイレと台所の一部と寝る部屋にしか行かないんだ」
「ほら」と引き戸を開けて見せてくれた台所は広くて、何なら北見の部屋より広くて、成る程、1人なら冷蔵庫の前とシンクの前くらいだけで用は足りるだろうと思えた。
「台所だけで20畳くらいはありそうですね、びっくりした。氷上さんってお金持ちの息子だったんですね」
「金持ちだったのは爺さんかな、俺の両親は普通の公務員だよ」
今は?どこに?と聞きたかったがそれはやめた。台所の対面にあった部屋の雪見障子から数枚の写真が添えられた仏壇が見えたからだ。
床に道を開いている導線はそこには無い。
つまり、触れてはいけないのだと思った。
「おい、何してるこっちだ」
「……はい」
もう、口でしてもらうなんて忘れていた。
来い来いと振られる手に付いていくと、その部屋だけは洋室になっている。
ここも20畳くらいはあるのだろうか、のっぺりとした壁の天井近くにだけ横長の窓が並ぶだけで外の景色が見えるような窓は無い。
「暗いのに……暗く無いですね」
「電機は付くけどどうする?」
「いや、いらない…かな……」
部屋の灯りは点いていないのにほんのりと明るいのは月明かりが差し込んでいるからだ。ほぼ何も無い部屋はとても寂しく、寝散らかしたままのベッドが一つと、まるでスポットライトを浴びるように月明かりに照らされた美しいグランドピアノが一台鎮座している。
「アーティストのスタジオみたいですね」
「ほぼ弾かないけどな」
「弾いてくださいよ、前にジャズバーで聴いたOver the rainbowがいいです」
「あれはジャズ初心者の姫がいたから誰でも知ってる曲を選んだだけだ、俺はクラシックしか知らないし、残念ながらもう難しい曲は弾けないと思う」
「何でもいいんです、何か弾いてください」
ほぼ弾かないと氷上は言ったが、全く掃除をしていないらしい床の埃は正直だった。
ちゃんとピアノへの導線が出来ている。
「氷上さんは……やっぱりお金持ちの息子さんなんですね」
「だから普通だって」
「普通じゃ無いです」
屋敷と呼べる大きな家、鍵盤を滑る軽やかな指、趣味で齧ったのでは無い事を物語る立派なピアノ。部屋の隅で埃を被っている木の木馬。
端正に育てられた事を伺わせる片鱗はそこここに満ちている。
「何でこうなったかな」
思わず出てきた独り言に「何が?」と聞かれても微笑むしか出来ない。
「ほらピアノの前に座ってください」
「酔っているから無理」と氷上は笑うが、酒に強い上殆ど飲んでないし、前は酔ってても弾いた。細い背中をピアノの前まで押して2つあった椅子の一つに座らせた。
するとポンポンともう一つの椅子を叩いて座れと言う。
「俺は邪魔でしょう、立って見てます」
「いいから座れよ」
「そう言うなら……座りますけど……」
本音を言うとピアノを弾く氷上を少し離れた場所から見たかった。
しかし、いつかのジャスバーで見た笑ってない笑顔を浮かべる氷上に吸い寄せられ、椅子の端っこに腰を下ろして隣に並んでみた。
「ピアノって独特の匂いがするんですね」
「そうか?」
「はい」
「俺は慣れているからわからないな、それじゃあ……姫が何か弾いて」
「……が?……」
「ああ、何でもいい」
「いや、全くもって全然無理です、音楽のスキルは無いを通り越してマイナスです」
「指一本で鍵盤を押せば音は出るぞ」
「右脳さんってそう言う事をよく言いますよね」
下手でも何でも描きたいものを描いたらいい、思うままでいい?
よく無い。
芸術方面の要素が全く無いのにそんな事を言われても出来ない。大体描きたいものなんて無いし、必要最低限の需要に乗ると「これは何だ」と怒られてしまう。
一回見ただけで複雑なロゴをトレースしたり、知っている曲を何となく弾いたら音楽になるような人には決して分からないだろう。
「弾けって言っても無理ですよ」
「チューリップの歌は?」
「咲いた、咲いた♫ってやつですか?」
「うん、始まりはここ」
落ちた指からポーンと金属音が上がる。
そう言われればそれは「ド」の音だ。
ドレミ、ドレミ、ソミレド、レミレ……
音を追って鍵盤を押すと何となくチューリップの曲になる。
「ほら出来る」
「出来るけど…」
「もう一度」と言われ、チューリップの冒頭を繰り返した。するとそこに静かな和音が乗ってくる。
それは酷く地味で、酷く拙いセッションだったが氷上の伴奏が付くとそれなりに聞こえてくる。
慌てて間違えても関係無い。
「綺麗ですね」
美しいでも無く、良い曲でも無い。
ただ綺麗だった。
「俺……ピアノの音ってもんを始めて聞いたような気がします」
「そんな訳ないだろ」
「違うけどそうなんです」
鍵盤を叩けば音が出る。
それはそうなのだが、ピアノの音が出るって事とピアノが鳴るって事は全然違う。
音楽を紡ぐというのはこんなに単純な事だったのか。静かに、時には派手に、同じフレーズを繰り返し、調子に乗った素人がカエルの歌を混ぜるとそこに和音が追随する。
もう前髪が落ちているから目の表情は見えないが、やっぱり氷上は笑っていたと思う。
恐らく10分か15分くらいだったと思う。
今まで味わったことの無い感覚に胸が高鳴っていた。
ピアノの鍵盤にエンジ色のフェルトを被せて蓋を閉じると残念に思ったくらいだ。
それなのに氷上は「じゃあやる?」と仕事の続きを即すような軽さでベッドを指す。
「……変な人だけど、常識無いし、面倒だし、ウスバカゲロウだし、そのくせエロいしビッチだしヤリチンだけど…」
「突然何だよ」
「やらないです、今日は何もしたく無いです」
「じゃあ日本酒があるから飲む?」
「……そうですね」
「じゃあ」と出て来たのはキンキンに冷やした純米吟醸酒だった。キッチンまで取りに行くのかと思えば、ベッド横という思わぬ場所にあった床下収納から出て来たから笑えた。
2人で飲み交わしたのは、座り込んだのは窓から刺す月明かりが四角を描く床の上だ。
さっきまではピアノを照らしていた月灯りは、時間を追って動いたのだろう。
まるで被写体を追うスポットライトそのものに思えた。
「お酒…冷えてて美味しいですね」
「俺と飲むから旨いんだろ」
「否定出来ない所が悔しいです」
ガラスのお猪口は洗ってないんだろうなとは思うが注いでくれたからもうそれでいい。
上澄を舐めるとワインのようにフルーティな香りがする。
「ねえ氷上さん」
「え?する?」
「しないです、あの、手伝いますから……今度この家を少し掃除しませんか?」
「気が向いた時にするからいいよ、どうせすぐに元通りだ」
「気が向いた時って、これ2、3年は放置してるでしょう」
「してるかもな」
氷上が壁に近い隅の方に指を立てると年月を掛け、ゆっくりゆっくり降り積もった細かい埃がこんもりと盛れた。
真似をして指で手繰ってみると線が描ける。
ついでにドラえもんを描いてみると「何だそれは」と笑う氷上は……
月の目を持ち、青白い灯りがよく似合う人だった。
前を行く車の数が減り、後ろを走る車もいなくなった頃、妙に敷地の大きい住宅地を抜けた所でタクシーが止まった。
そこはやけに立派な純和風数寄屋門の前だ。
「ここは?」
「ここはって俺ん家に決まってるだろう」
「え?マンションとかアパートじゃ無いんですか?一軒家?」
「何でもいいだろ」と氷上は笑うが、鍵の掛かった引戸を開けると松の傘が迎えてくれる。その奥に建つのは焼杉の壁に幾重にも重なる瓦屋根、正面から見える窓はほぼ木の雨戸に塞がれているが、見る限りアルミサッシは一つもない。
しかも圧倒されるくらい大きかった。
「か、家族がいるんじゃ無いですか?」
髭を生やし、着物を来たお父さんと氷上と同じ目をした若いお母さんがいたら……
速攻で逃げる。
「何を慌ててるんだ」
「だって…何て挨拶すればいいかわかりません」
「家族はいない、俺1人だよ」
「え?ここに?……1人で?」
「前は兄貴がいたけど結婚して出ていったからな、ああ、床をよく見て歩かないと足の裏が黒くなるぞ」
土間で靴を脱いで玄関の式代を上がると廊下も畳だった。
足が汚れると言われたから床をよく見てみると、普段使用しているらしい生活の導線が見えるくらいの厚い埃が積もってる。
「こんな広い家に1人なんて寂しくは無いんですか?ってか怖いでしょう」
「慣れてるから寂しくも無いし怖くも無い、でも奥とか2階に行くと電器が切れてるから何かいるかもな、俺は風呂とトイレと台所の一部と寝る部屋にしか行かないんだ」
「ほら」と引き戸を開けて見せてくれた台所は広くて、何なら北見の部屋より広くて、成る程、1人なら冷蔵庫の前とシンクの前くらいだけで用は足りるだろうと思えた。
「台所だけで20畳くらいはありそうですね、びっくりした。氷上さんってお金持ちの息子だったんですね」
「金持ちだったのは爺さんかな、俺の両親は普通の公務員だよ」
今は?どこに?と聞きたかったがそれはやめた。台所の対面にあった部屋の雪見障子から数枚の写真が添えられた仏壇が見えたからだ。
床に道を開いている導線はそこには無い。
つまり、触れてはいけないのだと思った。
「おい、何してるこっちだ」
「……はい」
もう、口でしてもらうなんて忘れていた。
来い来いと振られる手に付いていくと、その部屋だけは洋室になっている。
ここも20畳くらいはあるのだろうか、のっぺりとした壁の天井近くにだけ横長の窓が並ぶだけで外の景色が見えるような窓は無い。
「暗いのに……暗く無いですね」
「電機は付くけどどうする?」
「いや、いらない…かな……」
部屋の灯りは点いていないのにほんのりと明るいのは月明かりが差し込んでいるからだ。ほぼ何も無い部屋はとても寂しく、寝散らかしたままのベッドが一つと、まるでスポットライトを浴びるように月明かりに照らされた美しいグランドピアノが一台鎮座している。
「アーティストのスタジオみたいですね」
「ほぼ弾かないけどな」
「弾いてくださいよ、前にジャズバーで聴いたOver the rainbowがいいです」
「あれはジャズ初心者の姫がいたから誰でも知ってる曲を選んだだけだ、俺はクラシックしか知らないし、残念ながらもう難しい曲は弾けないと思う」
「何でもいいんです、何か弾いてください」
ほぼ弾かないと氷上は言ったが、全く掃除をしていないらしい床の埃は正直だった。
ちゃんとピアノへの導線が出来ている。
「氷上さんは……やっぱりお金持ちの息子さんなんですね」
「だから普通だって」
「普通じゃ無いです」
屋敷と呼べる大きな家、鍵盤を滑る軽やかな指、趣味で齧ったのでは無い事を物語る立派なピアノ。部屋の隅で埃を被っている木の木馬。
端正に育てられた事を伺わせる片鱗はそこここに満ちている。
「何でこうなったかな」
思わず出てきた独り言に「何が?」と聞かれても微笑むしか出来ない。
「ほらピアノの前に座ってください」
「酔っているから無理」と氷上は笑うが、酒に強い上殆ど飲んでないし、前は酔ってても弾いた。細い背中をピアノの前まで押して2つあった椅子の一つに座らせた。
するとポンポンともう一つの椅子を叩いて座れと言う。
「俺は邪魔でしょう、立って見てます」
「いいから座れよ」
「そう言うなら……座りますけど……」
本音を言うとピアノを弾く氷上を少し離れた場所から見たかった。
しかし、いつかのジャスバーで見た笑ってない笑顔を浮かべる氷上に吸い寄せられ、椅子の端っこに腰を下ろして隣に並んでみた。
「ピアノって独特の匂いがするんですね」
「そうか?」
「はい」
「俺は慣れているからわからないな、それじゃあ……姫が何か弾いて」
「……が?……」
「ああ、何でもいい」
「いや、全くもって全然無理です、音楽のスキルは無いを通り越してマイナスです」
「指一本で鍵盤を押せば音は出るぞ」
「右脳さんってそう言う事をよく言いますよね」
下手でも何でも描きたいものを描いたらいい、思うままでいい?
よく無い。
芸術方面の要素が全く無いのにそんな事を言われても出来ない。大体描きたいものなんて無いし、必要最低限の需要に乗ると「これは何だ」と怒られてしまう。
一回見ただけで複雑なロゴをトレースしたり、知っている曲を何となく弾いたら音楽になるような人には決して分からないだろう。
「弾けって言っても無理ですよ」
「チューリップの歌は?」
「咲いた、咲いた♫ってやつですか?」
「うん、始まりはここ」
落ちた指からポーンと金属音が上がる。
そう言われればそれは「ド」の音だ。
ドレミ、ドレミ、ソミレド、レミレ……
音を追って鍵盤を押すと何となくチューリップの曲になる。
「ほら出来る」
「出来るけど…」
「もう一度」と言われ、チューリップの冒頭を繰り返した。するとそこに静かな和音が乗ってくる。
それは酷く地味で、酷く拙いセッションだったが氷上の伴奏が付くとそれなりに聞こえてくる。
慌てて間違えても関係無い。
「綺麗ですね」
美しいでも無く、良い曲でも無い。
ただ綺麗だった。
「俺……ピアノの音ってもんを始めて聞いたような気がします」
「そんな訳ないだろ」
「違うけどそうなんです」
鍵盤を叩けば音が出る。
それはそうなのだが、ピアノの音が出るって事とピアノが鳴るって事は全然違う。
音楽を紡ぐというのはこんなに単純な事だったのか。静かに、時には派手に、同じフレーズを繰り返し、調子に乗った素人がカエルの歌を混ぜるとそこに和音が追随する。
もう前髪が落ちているから目の表情は見えないが、やっぱり氷上は笑っていたと思う。
恐らく10分か15分くらいだったと思う。
今まで味わったことの無い感覚に胸が高鳴っていた。
ピアノの鍵盤にエンジ色のフェルトを被せて蓋を閉じると残念に思ったくらいだ。
それなのに氷上は「じゃあやる?」と仕事の続きを即すような軽さでベッドを指す。
「……変な人だけど、常識無いし、面倒だし、ウスバカゲロウだし、そのくせエロいしビッチだしヤリチンだけど…」
「突然何だよ」
「やらないです、今日は何もしたく無いです」
「じゃあ日本酒があるから飲む?」
「……そうですね」
「じゃあ」と出て来たのはキンキンに冷やした純米吟醸酒だった。キッチンまで取りに行くのかと思えば、ベッド横という思わぬ場所にあった床下収納から出て来たから笑えた。
2人で飲み交わしたのは、座り込んだのは窓から刺す月明かりが四角を描く床の上だ。
さっきまではピアノを照らしていた月灯りは、時間を追って動いたのだろう。
まるで被写体を追うスポットライトそのものに思えた。
「お酒…冷えてて美味しいですね」
「俺と飲むから旨いんだろ」
「否定出来ない所が悔しいです」
ガラスのお猪口は洗ってないんだろうなとは思うが注いでくれたからもうそれでいい。
上澄を舐めるとワインのようにフルーティな香りがする。
「ねえ氷上さん」
「え?する?」
「しないです、あの、手伝いますから……今度この家を少し掃除しませんか?」
「気が向いた時にするからいいよ、どうせすぐに元通りだ」
「気が向いた時って、これ2、3年は放置してるでしょう」
「してるかもな」
氷上が壁に近い隅の方に指を立てると年月を掛け、ゆっくりゆっくり降り積もった細かい埃がこんもりと盛れた。
真似をして指で手繰ってみると線が描ける。
ついでにドラえもんを描いてみると「何だそれは」と笑う氷上は……
月の目を持ち、青白い灯りがよく似合う人だった。
0
あなたにおすすめの小説

エリート上司に完全に落とされるまで
琴音
BL
大手食品会社営業の楠木 智也(26)はある日会社の上司一ノ瀬 和樹(34)に告白されて付き合うことになった。
彼は会社ではよくわかんない、掴みどころのない不思議な人だった。スペックは申し分なく有能。いつもニコニコしててチームの空気はいい。俺はそんな彼が分からなくて距離を置いていたんだ。まあ、俺は問題児と会社では思われてるから、変にみんなと仲良くなりたいとも思ってはいなかった。その事情は一ノ瀬は知っている。なのに告白してくるとはいい度胸だと思う。
そんな彼と俺は上手くやれるのか不安の中スタート。俺は彼との付き合いの中で苦悩し、愛されて溺れていったんだ。
社会人同士の年の差カップルのお話です。智也は優柔不断で行き当たりばったり。自分の心すらよくわかってない。そんな智也を和樹は溺愛する。自分の男の本能をくすぐる智也が愛しくて堪らなくて、自分を知って欲しいが先行し過ぎていた。結果智也が不安に思っていることを見落とし、智也去ってしまう結果に。この後和樹は智也を取り戻せるのか。


宵にまぎれて兎は回る
宇土為名
BL
高校3年の春、同級生の名取に告白した冬だったが名取にはあっさりと冗談だったことにされてしまう。それを否定することもなく卒業し手以来、冬は親友だった名取とは距離を置こうと一度も連絡を取らなかった。そして8年後、勤めている会社の取引先で転勤してきた名取と8年ぶりに再会を果たす。再会してすぐ名取は自身の結婚式に出席してくれと冬に頼んできた。はじめは断るつもりだった冬だが、名取の願いには弱く結局引き受けてしまう。そして式当日、幸せに溢れた雰囲気に疲れてしまった冬は式場の中庭で避難するように休憩した。いまだに思いを断ち切れていない自分の情けなさを反省していると、そこで別の式に出席している男と出会い…
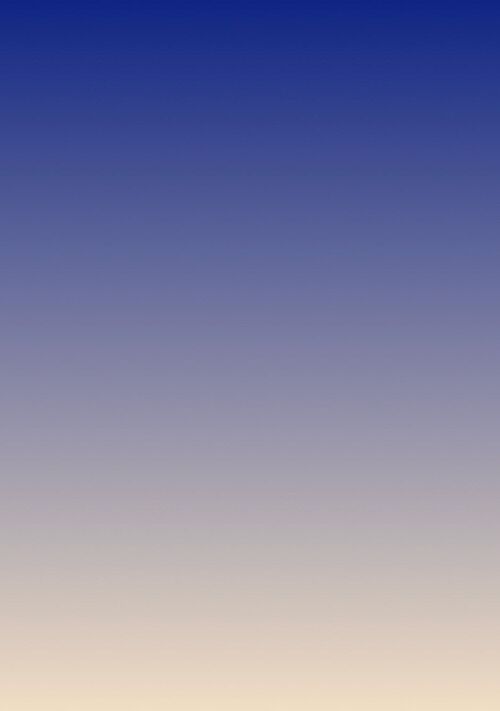
あの部屋でまだ待ってる
名雪
BL
アパートの一室。
どんなに遅くなっても、帰りを待つ習慣だけが残っている。
始まりは、ほんの気まぐれ。
終わる理由もないまま、十年が過ぎた。
与え続けることも、受け取るだけでいることも、いつしか当たり前になっていく。
――あの部屋で、まだ待ってる。

壁乳
リリーブルー
BL
ご来店ありがとうございます。ここは、壁越しに、触れ合える店。
最初は乳首から。指名を繰り返すと、徐々に、エリアが拡大していきます。
俺は後輩に「壁乳」に行こうと誘われた。
じれじれラブコメディー。
4年ぶりに続きを書きました!更新していくのでよろしくお願いします。
(挿絵byリリーブルー)

有能課長のあり得ない秘密
みなみ ゆうき
BL
地方の支社から本社の有能課長のプロジェクトチームに配属された男は、ある日ミーティングルームで課長のとんでもない姿を目撃してしまう。
しかもそれを見てしまったことが課長にバレて、何故か男のほうが弱味を握られたかのようにいいなりになるはめに……。

【R18+BL】空に月が輝く時
hosimure
BL
仕事が終わり、アパートへ戻ると、部屋の扉の前に誰かがいた。
そこにいたのは8年前、俺を最悪な形でフッた兄貴の親友だった。
告白した俺に、「大キライだ」と言っておいて、今更何の用なんだか…。
★BL小説&R18です。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















