22 / 166
第二十一話:冬の収穫と、雪解けの味
しおりを挟む
化学肥料という名の禁断の果実を得て、『陽だまりの家』の野菜たちは、もはや成長というよりも「進化」と呼ぶべき速度で、その生命力を爆発させていた。
あれから二週間。リーフ村は、すっかり深い雪に覆われた。屋根には分厚い雪が積もり、道は凍てつき、人々は暖炉の前から動くことも億劫になる、本格的な冬の到来だ。木々は葉を落とし、畑は白い沈黙に閉ざされている。生命の営みが、全て停止したかのような、静かで厳しい季節。
だが、俺の家の裏手にある、あの琥珀色に輝く家の中だけは、常春の楽園だった。
「……信じられん。本当に、実がなっている……」
その日、俺と一緒にハウスを訪れた父アルフレッドは、目の前の光景に、もはや驚きを通り越して、神の御業でも見るかのような、畏敬の念に満ちた声で呟いた。
無理もない。彼の目の前には、外の雪景色が嘘であるかのように、青々とした葉を茂らせた作物が、たわわに実をつけているのだから。
ぷっくりと赤く色づいたトマト。艶やかな紫色をしたナス。そして、地面には、ずんぐりとした大根が、その白い頭を誇らしげに覗かせている。霜が降りる季節に種を蒔き、雪が降る頃に収穫を迎える。この世界の農民が聞けば、誰もが正気を疑うであろう奇跡が、今、この『陽だまりの家』で、現実のものとなっていた。
「すごい……!ルークスお兄ちゃん、トマトさん、真っ赤だよ!」
俺の後ろからひょっこりと顔を出したリサが、目をキラキラさせて歓声を上げる。彼女は、ハウス建設の一番弟子として、今やこの楽園の共同管理人のようなポジションに収まっていた。
「ああ。もう食べ頃だ。今日は、この村の歴史が始まって以来、初めての『冬の収穫祭』にしよう」
俺は、誇らしげにそう宣言すると、籠を手に取り、一番大きく、そして見事に赤く熟したトマトを、そっと枝からもぎ取った。ずしり、と心地よい重みが、手のひらに伝わってくる。
それは、俺がこの世界で、自分の知識と努力で育て上げた、最初の果実だった。
◇
その日の昼食は、グルト家にとって、忘れられない特別な食卓となった。
テーブルの中央には、収穫したばかりの野菜たちが、宝石のように並べられている。朝露(ハウスの中なので結露だが)に濡れたままの、瑞々しいトマト。包丁を入れると、サクッと心地よい音がする、みずみずしい大根。そして、オリーブオイルの代用品として、森で採れるクルミから搾った油でこんがりと焼かれた、艶やかなナス。
調味料は、いつもの『精製された塩』と、自生のハーブだけ。だが、素材そのものが持つ圧倒的な生命力が、どんな高級な調味料にも勝る、最高の馳走となっていた。
「……いただきます」
父さんの、いつもより少しだけ厳かな声で、食事は始まった。
まず、俺は真っ赤なトマトを丸かじりした。口の中に、甘酸っぱい果汁が、じゅわっと溢れ出す。太陽の恵みをたっぷりと浴びた、濃厚な夏の味。外は雪景色だというのに、口の中だけは真夏の畑にいるかのようだ。
「……あまい……」
母さんが、薄切りにしたトマトを一枚口に運び、驚きに目を見開いている。
「果物みたいに甘いわ……!これが、本当に野菜なの……?」
「とまと、おいちい!」
マキナは、小さな口を果汁で真っ赤にしながら、夢中でトマトにかじりついていた。
そして、父さんは。
寡黙な父さんは、何も言わずに、ただ黙々と、一切れ、また一切れと、野菜を口に運んでいた。だが、その咀嚼する速度はいつもよりずっとゆっくりで、まるで一口一口、その味を全身で確かめるかのように、丁寧に、大切に味わっているのが分かった。
やがて、彼は全てを食べ終えると、ふう、と一つ、満足のため息をついた。そして、俺の目を真っ直ぐに見て、ただ一言、こう言った。
「……美味かった」
その、飾り気のない、しかし万感の思いが込められた一言は、どんな賛辞よりも深く、俺の胸に染み渡った。
前世で、俺はいつも一人だった。冷たいコンビニの弁当を、無機質なデスクで胃に流し込むだけの日々。そんな俺が、今、どうだ。
自分で育てた、採れたての野菜を。自分で料理して。大切な家族と、笑いながら囲んでいる。
(ああ……これだ)
これこそが、俺が心の底から渇望していた、「スローライフ」の本当の姿なんだ。ポイントでも、スキルでもない。この温かくて、かけがえのない笑顔こそが、俺が本当に手に入れたかった、最高の報酬だった。
込み上げてくる熱いものをこらえるように、俺は、少しだけ塩辛くなった大根のスープを、ゆっくりと、大切に飲み干したのだった。
◇
その日の午後、俺は収穫した野菜の一部を籠に詰め、村人たちへのおすそ分けに回ることにした。井戸やハウスの建設を手伝ってくれた、ささやかなお礼だ。
家を出ようとすると、ちょうど家の前で友達と遊んでいたリサが、ぱっとこちらに駆け寄ってきた。
「ルークスお兄ちゃん、お出かけ?」
「ああ。みんなに、この野菜を届けてこようと思ってね」
俺が籠の中身を見せると、リサは「わあ!」と目を輝かせた。彼女もまた、この奇跡の野菜が生まれるのを、誰よりも近くで見てきた功労者の一人だ。
俺は、籠の中から一番つやつやと輝いているトマトを一つ取り出すと、彼女の小さな手のひらに、そっと乗せてやった。
「これは、一番弟子への特別報酬だ。みんなに配る前に、まず味見してもらわないとな」
「え……!い、いの!?私が一番に!?」
リサは、宝物を受け取ったかのように、真っ赤なトマトを両手で大事そうに包み込んだ。そして、俺の顔とトマトを交互に見比べると、満面の笑みで大きく頷いた。
「うん!ありがとう、お師匠様!」
元気いっぱいの返事を聞いて、俺も思わず笑みがこぼれた。この純粋な喜びこそ、何よりの報酬だ。
「じゃあ、行ってくるよ」
「いってらっしゃい!」
弾むような声に見送られ、俺は最初のおすそ分け先である、マーサさんの家へと向かった。
「まあ!これは、あのハウスで採れたという……!」
俺が籠の中身を見せると、マーサさんは腰を抜かさんばかりに驚いていた。
「冬に、こんなに瑞々しい野菜が食べられるなんて……。夢のようですだよ、ルークス様」
涙ぐみながら感謝するマーサさんを皮切りに、俺が訪れた家々は、どこも熱狂的な歓迎で俺を迎えてくれた。人々は、冬の野菜をまるで奇跡の供物のように受け取り、俺に何度も、何度も頭を下げた。その度に、俺の脳内にはボーナスポイント獲得の通知が鳴り響いたが、もはやそんなことはどうでもよかった。彼らの純粋な笑顔が見られるだけで、俺の心は十分に満たされていた。
村中がお祭り騒ぎのような活気に包まれる中、俺は、最後の一軒へと向かっていた。
ゲルトの家だ。
あの日、彼が置いていったウサギへの、返礼のつもりだった。だが、家の前に立つと、さすがに少しだけ、足がすくむ。
俺が、意を決して扉を叩こうとした、その時だった。
「……何か用かよ」
背後から、ぶっきらぼうな声がした。振り返ると、そこには薪割りを終えて戻ってきたらしいゲルトが、訝しげな顔で立っていた。
「……これ、おすそ分けだ」
俺は、少しだけ気まずい沈黙の後、野菜の入った小さな袋を彼に差し出した。
ゲルトは、俺の手の中の袋と、俺の顔を、交互に見た。その瞳には、まだ戸惑いと警戒の色が浮かんでいる。
「……いらねえよ。施しは受けねえ」
彼は、そう言ってぷいと顔をそむけた。だが、その視線は、袋から覗く真っ赤なトマトに、一瞬だけ、釘付けになっていた。
「施しじゃない。これは、この前のウサギのお礼だ。すごく、美味しかったから」
俺の言葉に、ゲルトの肩が、びくりと震えた。彼は、何も言えずに、ただ俯いている。
気まずい沈黙が、雪のように冷たく、二人の間に降り積もる。
「……にいちゃん!」
その沈黙を破ったのは、ててて、と家の裏手から駆け寄ってきた、小さな救世主だった。マキナだ。彼女は、俺を見つけると、満面の笑みで抱きついてきた。
「マキナ、どうしたんだ?」
「あのね、フェンが、雪だるまさん作ったの!」
彼女が指さす先を見ると、そこにはフェンが鼻先で雪を転がして作ったらしい、いびつな形の雪玉がちょこんと置かれていた。
マキナは、ゲルトの存在に気づくと、不思議そうに首を傾げた。そして、俺が持っている野菜の袋に気づくと、無邪気にこう言った。
「あ!とまと!おにいちゃん、このおにいちゃんにも、あげるの?」
「……ああ、そうだよ」
「そっか!このとまと、すっごくあまくて、おいしいんだよ!おにいちゃんも、たべてみてね!」
マキナの、一点の曇りもない純粋な笑顔と、悪意のない言葉。それは、どんな説得よりも強く、ゲルトの固く凍てついた心を、ほんの少しだけ、溶かしたようだった。
ゲルトは、しばらくの間、マキナの屈託のない笑顔と、俺が差し出す袋を、呆然と見比べていた。やがて、彼は何かを諦めたように、ふう、と一つ、小さなため息をついた。
そして、俺から視線を逸らしたまま、小さな、蚊の鳴くような声で、ぽつりと呟いた。
「……どうも」
そう言って、彼は俺の手から、ひったくるように野菜の袋を奪うと、踵を返し、家の中へと駆け込んでしまった。
その背中は、まだ小さく、そして不器用だった。
だが、俺には分かった。彼が受け取ったのは、ただの野菜ではない。彼が、初めて他人からの「善意」を、素直に受け取った、記念すべき瞬間だったのだ。
俺は、その不器用な背中が見えなくなるまで、黙ってそれを見送った。
リーフ村の長い冬に、また一つ、温かい光が灯った。それは、まだとても小さく、か細い光だったが、やがて、凍てついた少年の心を完全に溶かすほどの、大きな希望の光になるのかもしれない。俺は、そんな予感を、胸に抱いていた。
【読者へのメッセージ】
第二十一話、お読みいただきありがとうございました!
ついに実現した、ルークスの夢「採れたて野菜の温かい食卓」。そして、ゲルトとの間に生まれた、雪解けの小さな兆し。この二つの「温かい」シーンに、ほっこりしていただけましたら幸いです。
「お父さんの一言に泣いた!」「一番弟子リサ、可愛い!」「ゲルト、頑張れ!」など、皆さんの感想が、次の物語を描くための何よりのエネルギーになります。下の評価(☆)やブックマークも、ぜひよろしくお願いいたします!
村に、そしてゲルトの心に、小さな変化が訪れました。この奇跡の野菜は、やて村の外の世界へと繋がっていきます。次回、新たな出会いの予感…?どうぞお楽しみに!
あれから二週間。リーフ村は、すっかり深い雪に覆われた。屋根には分厚い雪が積もり、道は凍てつき、人々は暖炉の前から動くことも億劫になる、本格的な冬の到来だ。木々は葉を落とし、畑は白い沈黙に閉ざされている。生命の営みが、全て停止したかのような、静かで厳しい季節。
だが、俺の家の裏手にある、あの琥珀色に輝く家の中だけは、常春の楽園だった。
「……信じられん。本当に、実がなっている……」
その日、俺と一緒にハウスを訪れた父アルフレッドは、目の前の光景に、もはや驚きを通り越して、神の御業でも見るかのような、畏敬の念に満ちた声で呟いた。
無理もない。彼の目の前には、外の雪景色が嘘であるかのように、青々とした葉を茂らせた作物が、たわわに実をつけているのだから。
ぷっくりと赤く色づいたトマト。艶やかな紫色をしたナス。そして、地面には、ずんぐりとした大根が、その白い頭を誇らしげに覗かせている。霜が降りる季節に種を蒔き、雪が降る頃に収穫を迎える。この世界の農民が聞けば、誰もが正気を疑うであろう奇跡が、今、この『陽だまりの家』で、現実のものとなっていた。
「すごい……!ルークスお兄ちゃん、トマトさん、真っ赤だよ!」
俺の後ろからひょっこりと顔を出したリサが、目をキラキラさせて歓声を上げる。彼女は、ハウス建設の一番弟子として、今やこの楽園の共同管理人のようなポジションに収まっていた。
「ああ。もう食べ頃だ。今日は、この村の歴史が始まって以来、初めての『冬の収穫祭』にしよう」
俺は、誇らしげにそう宣言すると、籠を手に取り、一番大きく、そして見事に赤く熟したトマトを、そっと枝からもぎ取った。ずしり、と心地よい重みが、手のひらに伝わってくる。
それは、俺がこの世界で、自分の知識と努力で育て上げた、最初の果実だった。
◇
その日の昼食は、グルト家にとって、忘れられない特別な食卓となった。
テーブルの中央には、収穫したばかりの野菜たちが、宝石のように並べられている。朝露(ハウスの中なので結露だが)に濡れたままの、瑞々しいトマト。包丁を入れると、サクッと心地よい音がする、みずみずしい大根。そして、オリーブオイルの代用品として、森で採れるクルミから搾った油でこんがりと焼かれた、艶やかなナス。
調味料は、いつもの『精製された塩』と、自生のハーブだけ。だが、素材そのものが持つ圧倒的な生命力が、どんな高級な調味料にも勝る、最高の馳走となっていた。
「……いただきます」
父さんの、いつもより少しだけ厳かな声で、食事は始まった。
まず、俺は真っ赤なトマトを丸かじりした。口の中に、甘酸っぱい果汁が、じゅわっと溢れ出す。太陽の恵みをたっぷりと浴びた、濃厚な夏の味。外は雪景色だというのに、口の中だけは真夏の畑にいるかのようだ。
「……あまい……」
母さんが、薄切りにしたトマトを一枚口に運び、驚きに目を見開いている。
「果物みたいに甘いわ……!これが、本当に野菜なの……?」
「とまと、おいちい!」
マキナは、小さな口を果汁で真っ赤にしながら、夢中でトマトにかじりついていた。
そして、父さんは。
寡黙な父さんは、何も言わずに、ただ黙々と、一切れ、また一切れと、野菜を口に運んでいた。だが、その咀嚼する速度はいつもよりずっとゆっくりで、まるで一口一口、その味を全身で確かめるかのように、丁寧に、大切に味わっているのが分かった。
やがて、彼は全てを食べ終えると、ふう、と一つ、満足のため息をついた。そして、俺の目を真っ直ぐに見て、ただ一言、こう言った。
「……美味かった」
その、飾り気のない、しかし万感の思いが込められた一言は、どんな賛辞よりも深く、俺の胸に染み渡った。
前世で、俺はいつも一人だった。冷たいコンビニの弁当を、無機質なデスクで胃に流し込むだけの日々。そんな俺が、今、どうだ。
自分で育てた、採れたての野菜を。自分で料理して。大切な家族と、笑いながら囲んでいる。
(ああ……これだ)
これこそが、俺が心の底から渇望していた、「スローライフ」の本当の姿なんだ。ポイントでも、スキルでもない。この温かくて、かけがえのない笑顔こそが、俺が本当に手に入れたかった、最高の報酬だった。
込み上げてくる熱いものをこらえるように、俺は、少しだけ塩辛くなった大根のスープを、ゆっくりと、大切に飲み干したのだった。
◇
その日の午後、俺は収穫した野菜の一部を籠に詰め、村人たちへのおすそ分けに回ることにした。井戸やハウスの建設を手伝ってくれた、ささやかなお礼だ。
家を出ようとすると、ちょうど家の前で友達と遊んでいたリサが、ぱっとこちらに駆け寄ってきた。
「ルークスお兄ちゃん、お出かけ?」
「ああ。みんなに、この野菜を届けてこようと思ってね」
俺が籠の中身を見せると、リサは「わあ!」と目を輝かせた。彼女もまた、この奇跡の野菜が生まれるのを、誰よりも近くで見てきた功労者の一人だ。
俺は、籠の中から一番つやつやと輝いているトマトを一つ取り出すと、彼女の小さな手のひらに、そっと乗せてやった。
「これは、一番弟子への特別報酬だ。みんなに配る前に、まず味見してもらわないとな」
「え……!い、いの!?私が一番に!?」
リサは、宝物を受け取ったかのように、真っ赤なトマトを両手で大事そうに包み込んだ。そして、俺の顔とトマトを交互に見比べると、満面の笑みで大きく頷いた。
「うん!ありがとう、お師匠様!」
元気いっぱいの返事を聞いて、俺も思わず笑みがこぼれた。この純粋な喜びこそ、何よりの報酬だ。
「じゃあ、行ってくるよ」
「いってらっしゃい!」
弾むような声に見送られ、俺は最初のおすそ分け先である、マーサさんの家へと向かった。
「まあ!これは、あのハウスで採れたという……!」
俺が籠の中身を見せると、マーサさんは腰を抜かさんばかりに驚いていた。
「冬に、こんなに瑞々しい野菜が食べられるなんて……。夢のようですだよ、ルークス様」
涙ぐみながら感謝するマーサさんを皮切りに、俺が訪れた家々は、どこも熱狂的な歓迎で俺を迎えてくれた。人々は、冬の野菜をまるで奇跡の供物のように受け取り、俺に何度も、何度も頭を下げた。その度に、俺の脳内にはボーナスポイント獲得の通知が鳴り響いたが、もはやそんなことはどうでもよかった。彼らの純粋な笑顔が見られるだけで、俺の心は十分に満たされていた。
村中がお祭り騒ぎのような活気に包まれる中、俺は、最後の一軒へと向かっていた。
ゲルトの家だ。
あの日、彼が置いていったウサギへの、返礼のつもりだった。だが、家の前に立つと、さすがに少しだけ、足がすくむ。
俺が、意を決して扉を叩こうとした、その時だった。
「……何か用かよ」
背後から、ぶっきらぼうな声がした。振り返ると、そこには薪割りを終えて戻ってきたらしいゲルトが、訝しげな顔で立っていた。
「……これ、おすそ分けだ」
俺は、少しだけ気まずい沈黙の後、野菜の入った小さな袋を彼に差し出した。
ゲルトは、俺の手の中の袋と、俺の顔を、交互に見た。その瞳には、まだ戸惑いと警戒の色が浮かんでいる。
「……いらねえよ。施しは受けねえ」
彼は、そう言ってぷいと顔をそむけた。だが、その視線は、袋から覗く真っ赤なトマトに、一瞬だけ、釘付けになっていた。
「施しじゃない。これは、この前のウサギのお礼だ。すごく、美味しかったから」
俺の言葉に、ゲルトの肩が、びくりと震えた。彼は、何も言えずに、ただ俯いている。
気まずい沈黙が、雪のように冷たく、二人の間に降り積もる。
「……にいちゃん!」
その沈黙を破ったのは、ててて、と家の裏手から駆け寄ってきた、小さな救世主だった。マキナだ。彼女は、俺を見つけると、満面の笑みで抱きついてきた。
「マキナ、どうしたんだ?」
「あのね、フェンが、雪だるまさん作ったの!」
彼女が指さす先を見ると、そこにはフェンが鼻先で雪を転がして作ったらしい、いびつな形の雪玉がちょこんと置かれていた。
マキナは、ゲルトの存在に気づくと、不思議そうに首を傾げた。そして、俺が持っている野菜の袋に気づくと、無邪気にこう言った。
「あ!とまと!おにいちゃん、このおにいちゃんにも、あげるの?」
「……ああ、そうだよ」
「そっか!このとまと、すっごくあまくて、おいしいんだよ!おにいちゃんも、たべてみてね!」
マキナの、一点の曇りもない純粋な笑顔と、悪意のない言葉。それは、どんな説得よりも強く、ゲルトの固く凍てついた心を、ほんの少しだけ、溶かしたようだった。
ゲルトは、しばらくの間、マキナの屈託のない笑顔と、俺が差し出す袋を、呆然と見比べていた。やがて、彼は何かを諦めたように、ふう、と一つ、小さなため息をついた。
そして、俺から視線を逸らしたまま、小さな、蚊の鳴くような声で、ぽつりと呟いた。
「……どうも」
そう言って、彼は俺の手から、ひったくるように野菜の袋を奪うと、踵を返し、家の中へと駆け込んでしまった。
その背中は、まだ小さく、そして不器用だった。
だが、俺には分かった。彼が受け取ったのは、ただの野菜ではない。彼が、初めて他人からの「善意」を、素直に受け取った、記念すべき瞬間だったのだ。
俺は、その不器用な背中が見えなくなるまで、黙ってそれを見送った。
リーフ村の長い冬に、また一つ、温かい光が灯った。それは、まだとても小さく、か細い光だったが、やがて、凍てついた少年の心を完全に溶かすほどの、大きな希望の光になるのかもしれない。俺は、そんな予感を、胸に抱いていた。
【読者へのメッセージ】
第二十一話、お読みいただきありがとうございました!
ついに実現した、ルークスの夢「採れたて野菜の温かい食卓」。そして、ゲルトとの間に生まれた、雪解けの小さな兆し。この二つの「温かい」シーンに、ほっこりしていただけましたら幸いです。
「お父さんの一言に泣いた!」「一番弟子リサ、可愛い!」「ゲルト、頑張れ!」など、皆さんの感想が、次の物語を描くための何よりのエネルギーになります。下の評価(☆)やブックマークも、ぜひよろしくお願いいたします!
村に、そしてゲルトの心に、小さな変化が訪れました。この奇跡の野菜は、やて村の外の世界へと繋がっていきます。次回、新たな出会いの予感…?どうぞお楽しみに!
183
あなたにおすすめの小説

元侯爵令嬢の異世界薬膳料理~転生先はみんな食事に興味が無い世界だったので、美味しいご飯で人の身も心も癒します~
向原 行人
ファンタジー
異世界へ転生して数日。十七歳の侯爵令嬢、アリスとして目覚めた私は、早くも限界を迎えていた。
というのも、この世界……みんな食事に興味が無くて、毎食パンとハムだけとか、ハムがチーズに変わるとか、せいぜいその程度だ。
料理というより、食材を並べているだけって感じがする。
元日本人の私としては温かいご飯がたべたいので、自分で食事を作るというと、「貴族が料理など下賤なことをするのは恥だ!」と、意味不明な怒られ方をした。
わかった……だったら、私は貴族を辞める!
家には兄が二人もいるし、姉だっているから問題無いでしょ。
宛てもなく屋敷を飛び出した私は、小さな村で更に酷い食事事情を目の当たりにする。
育ち盛りの子供たちや、身体を使う冒険者たちが、それだけしか食べないなんて……よし、美味しいご飯でみんなも私も幸せになろう!
医食同源! 大食いモフモフ聖獣に、胃袋を掴んでしまった騎士隊長と一緒に、異世界で美味しくて身体に良い食材探しだ!
※第○話:主人公視点
挿話○:タイトルに書かれたキャラの視点
となります。

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました
SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗
ファンタジー
不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。
不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。
14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!
ちかっぱ雪比呂
ファンタジー
40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。
しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。
おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。
漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。
この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

【土壌改良】で死の荒野がSランク農園に!食べただけでレベルアップする野菜で、世界最強ギルド設立
黒崎隼人
ファンタジー
「え? これ、ただのトマトですよ?」
「いいえ、それは食べただけで魔力が全回復する『神の果実』です!」
ブラック企業で働き詰めだった青年は、異世界の名門貴族の三男・ノアとして転生する。
しかし、授かったスキルは【土壌改良】という地味なもの。
「攻撃魔法も使えない役立たず」と罵られ、魔物すら寄り付かない死の荒野へ追放されてしまう。
だが、彼らは知らなかった。
ノアのスキルは、現代の農業知識と合わせることで、荒れ果てた土地を「Sランク食材」が溢れる楽園に変えるチート能力だったことを!
伝説の魔獣(もふもふ)をキュウリ一本で手懐け、行き倒れた天才エルフを極上スープで救い出し、気づけば荒野には巨大な「農業ギルド」が誕生していた。
これは、本人がただ美味しい野菜を作ってのんびり暮らしたいだけなのに、周囲からは「世界を救う大賢者」と崇められてしまう、無自覚・最強の農業ファンタジー!

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】
のびすけ。
ファンタジー
気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。
そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。
幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、
“とっておき”のチートで人生を再起動。
剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。
そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。
これは、理想を形にするために動き出した少年の、
少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。
【なろう掲載】

『急所』を突いてドロップ率100%。魔物から奪ったSSRスキルと最強装備で、俺だけが規格外の冒険者になる
仙道
ファンタジー
気がつくと、俺は森の中に立っていた。目の前には実体化した女神がいて、ここがステータスやスキルの存在する異世界だと告げてくる。女神は俺に特典として【鑑定】と、魔物の『ドロップ急所』が見える眼を与えて消えた。 この世界では、魔物は倒した際に稀にアイテムやスキルを落とす。俺の眼には、魔物の体に赤い光の点が見えた。そこを攻撃して倒せば、【鑑定】で表示されたレアアイテムが確実に手に入るのだ。 俺は実験のために、森でオークに襲われているエルフの少女を見つける。オークのドロップリストには『剛力の腕輪(攻撃力+500)』があった。俺はエルフを助けるというよりも、その腕輪が欲しくてオークの急所を剣で貫く。 オークは光となって消え、俺の手には強力な腕輪が残った。 腰を抜かしていたエルフの少女、リーナは俺の圧倒的な一撃と、伝説級の装備を平然と手に入れる姿を見て、俺に同行を申し出る。 俺は効率よく強くなるために、彼女を前衛の盾役として採用した。 こうして、欲しいドロップ品を狙って魔物を狩り続ける、俺の異世界冒険が始まる。
12/23 HOT男性向け1位
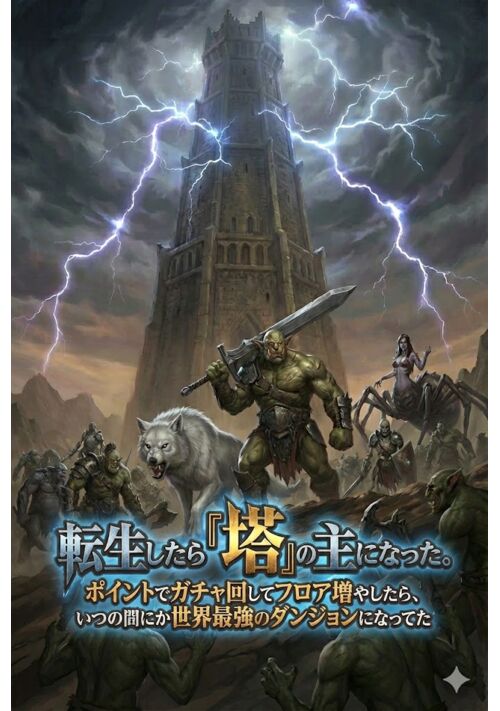
転生したら『塔』の主になった。ポイントでガチャ回してフロア増やしたら、いつの間にか世界最強のダンジョンになってた
季未
ファンタジー
【書き溜めがなくなるまで高頻度更新!♡٩( 'ω' )و】
気がつくとダンジョンコア(石)になっていた。
手持ちの資源はわずか。迫りくる野生の魔物やコアを狙う冒険者たち。 頼れるのは怪しげな「魔物ガチャ」だけ!?
傷ついた少女・リナを保護したことをきっかけにダンジョンは急速に進化を始める。
罠を張り巡らせた塔を建築し、資源を集め、強力な魔物をガチャで召喚!
人間と魔族、どこの勢力にも属さない独立した「最強のダンジョン」が今、産声を上げる!

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする
初
ファンタジー
ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。
リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。
これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















