9 / 11
第9話: スーパーの特売と、半額シールの呪縛
しおりを挟む
「雅人、準備はいい? 今日は近所のスーパー『ヤオヨロズ』のポイント5倍デー。さらに、土曜恒例の夕方タイムセールも重なる、一週間の家計を左右する聖戦の日なんだから」
鈴木花は、自室のリビングで気合を入れ直すように自らの頬を叩いた。手には戦術書(特売チラシ)と、聖遺物(ポイントカード)が握られている。
対する橘雅人は、いつもの群青色の羽織をパサリと翻し、神妙な面持ちで頷いた。
「うむ。生活の基盤となる『食』を司る場へ赴くのだ。心身を浄化し、万全の態勢で臨もう。花、君の戦い(節約)に、私の術が少しでも助けになれば幸いだ」
「術は使わなくていいからね。あと、変な目で見られないように、なるべく普通にしててよ?」
二人は連れ立って、夕暮れ時のスーパーへと足を踏み入れた。店内は、今か今かとタイムセールの開始を待つ主婦や家族連れでごった返し、独特の熱気が渦巻いている。
雅人は自動ドアを潜った瞬間、眉間に皺を寄せ、スッと片手を口元に当てた。
「……花、いけない。この空間、想像以上に気が乱れている。人々の『少しでも安く』『良いものを手に入れたい』という強烈な欲の念が、天井の蛍光灯に反射して火花を散らしているぞ」
「それはただの活気だよ、雅人。ほら、まずは野菜売り場!」
花は雅人の腕を強引に引き、青果コーナーへと向かった。
そこには、今日の目玉であるキャベツが一玉98円で山積みにされていた。花が吟味しようと手を伸ばした瞬間、雅人がその手を押さえた。
「待て、花。安易に触れてはならん。このキャベツの山……特に底に積み上げられたこの一玉を見てみろ。これは、上にある新鮮な個体たちから発せられる『圧迫の気』と、買い手にスルーされ続けたことによる『選ばれなかった者たちの悲哀』を一身に浴びている。このままでは、このキャベツは今夜、『不満の霊』を宿した苦い温野菜へと変貌してしまうだろう」
「雅人、それはただの見切り品なの! 葉っぱが少し萎れてるだけ! 外側の葉を剥いて、千切りにして油で炒めれば、甘みが出て最高に美味しくなるの。霊じゃなくて、主婦の知恵で浄化するから大丈夫!」
花は半ば強引にキャベツをカゴに放り込み、次なる目的地である精肉コーナーへと進んだ。
そこはまさに戦場だった。店員が黄色い「半額シール」の束を手に持ち、牛肉のパックに次々と貼り付けていく。主婦たちがその動きを虎視眈々と見つめ、パックが棚に置かれた瞬間に四方八方から手が伸びる。
「よし、雅人! あっちの和牛肩ロース、半額になったよ! 取って!」
花が指示を飛ばすが、雅人はパックを手に取ったまま、金縛りにあったように動かなくなった。
「花……この黄色い札は、危険だ。私には見える。この肉を一度手に取り、値段を見て溜息をつき、結局棚に戻した数多の者たちの『迷い』。そして、他人に取られたくないと願う者の『独占欲』が、強力な呪縛となって肉の繊維一本一本に絡みついている。このまま食せば、我々の胃腸には『節約の呪い』がかかり、心まで貧相な、ひもじい思いに支配されてしまうぞ」
雅人は真剣そのものの表情で、周囲の客に悟られないよう、指先で小さく九字を切り始めた。
「臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前……! 肉に宿りし執着の念よ、霧散せよ。この牛が本来持っていた広大な牧草地の記憶を呼び覚まし、清浄なるタンパク質へと還れ!」
「雅人、レジ袋の列が並んじゃうから! あと、イケメンが和牛のパックを拝んでると、新手の宗教勧誘かと思われて通報されるからやめて!」
花の必死の制止も虚しく、雅人の「お清め」は続いた。しかし不思議なことに、雅人が指を振った後、その肉のパックは夕日に照らされたかのように一瞬だけ艶やかに輝いた(ように花には見えた)。
「……ふぅ。これでよし。この肉は今、あらゆる主婦の情念から解き放たれ、ただの極上の和牛へと昇華された。花、これを今夜の『禊(みそぎ)』のメインディッシュにしよう」
「……お祓いのおかげか分かんないけど、確かに美味しそうに見えるね。じゃあ、次はお豆腐!」
次に二人が向かったのは、日配品コーナーだった。
そこには、パック詰めされたレジ袋用のビニールロールが設置されていた。花が指先を濡らし、袋を開けようと苦戦していると、雅人が怪訝そうな顔でロールを見つめた。
「花、そこにも敵がいる。あの透明な薄膜には、『静電気の霊』が群生している。袋が開かなくてイライラする者の焦燥感を糧にし、指先と膜の間に斥力を発生させる邪悪な存在だ。私の指先に宿る『放電の気』で一掃してやろう」
「それはただの乾燥! 指を湿らせれば済む話なの! 雅人がバチバチ火花を散らしたら、袋が溶けちゃうでしょ!」
花のツッコミが店内に響き渡る。
店員が「あのお客様、また……」という顔でこちらを見ている。花は恥ずかしさで顔を赤くしながら、カゴいっぱいの食材を持ってレジへと急いだ。
レジを済ませ、重い買い物袋を両手に下げてスーパーを後にする頃には、街はすっかり夜の帳に包まれていた。
帰り道、雅人は袋の重さを全く苦にする様子もなく、むしろどこか充足感に満ちた表情で夜空を見上げていた。
「花よ。スーパーという場所は、実に興味深いな。そこには人々の生きるためのエネルギー、すなわち『生への執着』がこれでもかと満ち溢れている。あの熱気、あの混乱。あれこそが、現代における最も原始的な祭事なのかもしれん」
「雅人がそう言うと、ただの買い出しがすごいイベントみたいに聞こえるね」
「うむ。特にあの『タイムセールのゴング』。あれは人々の闘争本能を呼び覚ます召喚儀式の合図のようだった。次は私も、あの最前線に混ざって、真の『選ばれし食材』を勝ち取ってみたいものだ」
「雅人が参加したら、多分、霊的に気合が入りすぎて、他のお客さんが威圧感で近寄れなくなっちゃうよ。それはそれで営業妨害だし」
二人は並んで歩きながら、今夜のメニューについて話し合った。
「さっきの和牛、せっかく雅人がお祓いしてくれたから、シンプルに塩胡椒で焼こうか。あ、でも雅人が持ってる『特別な塩』じゃなくて、普通の食卓塩でいいからね?」
「いや、花。あの肉には、私の実家から取り寄せた『ヒマラヤの陽気溢れる岩塩』が合う。肉に宿る大地の記憶と、高地の清浄なる気が共鳴し、口の中で多幸感の結界が……」
「また始まった……。分かった、分かったから。半分ずつ使おう」
家に着き、キッチンに食材を並べる。
雅人がお祓いをした(と言い張る)キャベツは、確かに瑞々しく、和牛のパックはどこか誇らしげに冷蔵庫へと収まっていった。
花は、ふと思った。
「結婚式」という、一生に一度の盛大な儀式。そこへ至る道はまだ遠く、雅人の実家との折り合いや、彼自身の陰陽師としての使命など、乗り越えなければならない壁はたくさんあるだろう。
けれど、こうしてスーパーで安い肉を買い、あーだこーだと霊的な文句を言い合いながら、一緒に晩ごはんを作る。この「小さな、代わり映えのしない日常の儀式」の積み重ねこそが、どんな強力な護符や結界よりも、二人の絆を強く、深く結びつけていくのだ。
「あ、雅人! 買ってきた卵、一つだけパックの中で『黄金のオーラ』を放ってる気がするんだけど!」
花がパックを開けると、そこには他よりも少し形の良い卵があった。
雅人は覗き込み、眼鏡の奥の目を細めた。
「ふむ。花、それはおそらく『双子の卵』だな。一つの殻の中に二つの魂が寄り添う吉兆だ。明日、二人で割ってみよう。それは、我々の前途に幸多からんことを示す神の啓示だ」
「……お祓いじゃなくて、珍しく普通に素敵なこと言ったね」
「うむ。君と日々を過ごすうちに、私の霊感も、君の放つ『生活感』という名の光に浄化されていくようだ」
雅人の大きな手が、花の頭を優しく撫でる。
その手からは、邪気を払う冷たい気ではなく、花を慈しむ温かな体温が伝わってきた。
「さあ、花。今夜の夕餉(ゆうげ)を始めよう。まずは、この半額シールの呪縛から解き放たれた肉を、最高の状態で供養(調理)するのだ」
「はいはい。じゃあ雅人は、キャベツの千切りをお願い。陰陽師の包丁捌き、期待してるよ」
「任せておけ。私の包丁は、食材の『細胞の未練』さえも断ち切る」
「細胞の未練は残しておいていいから、指切らないでね!」
キッチンに、トントントンと小気味よい包丁の音が響き渡る。
夕食の香りが広がる中、二人の賑やかな日常は、今夜も幸せな結界に包まれて更けていく。
鈴木花は、自室のリビングで気合を入れ直すように自らの頬を叩いた。手には戦術書(特売チラシ)と、聖遺物(ポイントカード)が握られている。
対する橘雅人は、いつもの群青色の羽織をパサリと翻し、神妙な面持ちで頷いた。
「うむ。生活の基盤となる『食』を司る場へ赴くのだ。心身を浄化し、万全の態勢で臨もう。花、君の戦い(節約)に、私の術が少しでも助けになれば幸いだ」
「術は使わなくていいからね。あと、変な目で見られないように、なるべく普通にしててよ?」
二人は連れ立って、夕暮れ時のスーパーへと足を踏み入れた。店内は、今か今かとタイムセールの開始を待つ主婦や家族連れでごった返し、独特の熱気が渦巻いている。
雅人は自動ドアを潜った瞬間、眉間に皺を寄せ、スッと片手を口元に当てた。
「……花、いけない。この空間、想像以上に気が乱れている。人々の『少しでも安く』『良いものを手に入れたい』という強烈な欲の念が、天井の蛍光灯に反射して火花を散らしているぞ」
「それはただの活気だよ、雅人。ほら、まずは野菜売り場!」
花は雅人の腕を強引に引き、青果コーナーへと向かった。
そこには、今日の目玉であるキャベツが一玉98円で山積みにされていた。花が吟味しようと手を伸ばした瞬間、雅人がその手を押さえた。
「待て、花。安易に触れてはならん。このキャベツの山……特に底に積み上げられたこの一玉を見てみろ。これは、上にある新鮮な個体たちから発せられる『圧迫の気』と、買い手にスルーされ続けたことによる『選ばれなかった者たちの悲哀』を一身に浴びている。このままでは、このキャベツは今夜、『不満の霊』を宿した苦い温野菜へと変貌してしまうだろう」
「雅人、それはただの見切り品なの! 葉っぱが少し萎れてるだけ! 外側の葉を剥いて、千切りにして油で炒めれば、甘みが出て最高に美味しくなるの。霊じゃなくて、主婦の知恵で浄化するから大丈夫!」
花は半ば強引にキャベツをカゴに放り込み、次なる目的地である精肉コーナーへと進んだ。
そこはまさに戦場だった。店員が黄色い「半額シール」の束を手に持ち、牛肉のパックに次々と貼り付けていく。主婦たちがその動きを虎視眈々と見つめ、パックが棚に置かれた瞬間に四方八方から手が伸びる。
「よし、雅人! あっちの和牛肩ロース、半額になったよ! 取って!」
花が指示を飛ばすが、雅人はパックを手に取ったまま、金縛りにあったように動かなくなった。
「花……この黄色い札は、危険だ。私には見える。この肉を一度手に取り、値段を見て溜息をつき、結局棚に戻した数多の者たちの『迷い』。そして、他人に取られたくないと願う者の『独占欲』が、強力な呪縛となって肉の繊維一本一本に絡みついている。このまま食せば、我々の胃腸には『節約の呪い』がかかり、心まで貧相な、ひもじい思いに支配されてしまうぞ」
雅人は真剣そのものの表情で、周囲の客に悟られないよう、指先で小さく九字を切り始めた。
「臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前……! 肉に宿りし執着の念よ、霧散せよ。この牛が本来持っていた広大な牧草地の記憶を呼び覚まし、清浄なるタンパク質へと還れ!」
「雅人、レジ袋の列が並んじゃうから! あと、イケメンが和牛のパックを拝んでると、新手の宗教勧誘かと思われて通報されるからやめて!」
花の必死の制止も虚しく、雅人の「お清め」は続いた。しかし不思議なことに、雅人が指を振った後、その肉のパックは夕日に照らされたかのように一瞬だけ艶やかに輝いた(ように花には見えた)。
「……ふぅ。これでよし。この肉は今、あらゆる主婦の情念から解き放たれ、ただの極上の和牛へと昇華された。花、これを今夜の『禊(みそぎ)』のメインディッシュにしよう」
「……お祓いのおかげか分かんないけど、確かに美味しそうに見えるね。じゃあ、次はお豆腐!」
次に二人が向かったのは、日配品コーナーだった。
そこには、パック詰めされたレジ袋用のビニールロールが設置されていた。花が指先を濡らし、袋を開けようと苦戦していると、雅人が怪訝そうな顔でロールを見つめた。
「花、そこにも敵がいる。あの透明な薄膜には、『静電気の霊』が群生している。袋が開かなくてイライラする者の焦燥感を糧にし、指先と膜の間に斥力を発生させる邪悪な存在だ。私の指先に宿る『放電の気』で一掃してやろう」
「それはただの乾燥! 指を湿らせれば済む話なの! 雅人がバチバチ火花を散らしたら、袋が溶けちゃうでしょ!」
花のツッコミが店内に響き渡る。
店員が「あのお客様、また……」という顔でこちらを見ている。花は恥ずかしさで顔を赤くしながら、カゴいっぱいの食材を持ってレジへと急いだ。
レジを済ませ、重い買い物袋を両手に下げてスーパーを後にする頃には、街はすっかり夜の帳に包まれていた。
帰り道、雅人は袋の重さを全く苦にする様子もなく、むしろどこか充足感に満ちた表情で夜空を見上げていた。
「花よ。スーパーという場所は、実に興味深いな。そこには人々の生きるためのエネルギー、すなわち『生への執着』がこれでもかと満ち溢れている。あの熱気、あの混乱。あれこそが、現代における最も原始的な祭事なのかもしれん」
「雅人がそう言うと、ただの買い出しがすごいイベントみたいに聞こえるね」
「うむ。特にあの『タイムセールのゴング』。あれは人々の闘争本能を呼び覚ます召喚儀式の合図のようだった。次は私も、あの最前線に混ざって、真の『選ばれし食材』を勝ち取ってみたいものだ」
「雅人が参加したら、多分、霊的に気合が入りすぎて、他のお客さんが威圧感で近寄れなくなっちゃうよ。それはそれで営業妨害だし」
二人は並んで歩きながら、今夜のメニューについて話し合った。
「さっきの和牛、せっかく雅人がお祓いしてくれたから、シンプルに塩胡椒で焼こうか。あ、でも雅人が持ってる『特別な塩』じゃなくて、普通の食卓塩でいいからね?」
「いや、花。あの肉には、私の実家から取り寄せた『ヒマラヤの陽気溢れる岩塩』が合う。肉に宿る大地の記憶と、高地の清浄なる気が共鳴し、口の中で多幸感の結界が……」
「また始まった……。分かった、分かったから。半分ずつ使おう」
家に着き、キッチンに食材を並べる。
雅人がお祓いをした(と言い張る)キャベツは、確かに瑞々しく、和牛のパックはどこか誇らしげに冷蔵庫へと収まっていった。
花は、ふと思った。
「結婚式」という、一生に一度の盛大な儀式。そこへ至る道はまだ遠く、雅人の実家との折り合いや、彼自身の陰陽師としての使命など、乗り越えなければならない壁はたくさんあるだろう。
けれど、こうしてスーパーで安い肉を買い、あーだこーだと霊的な文句を言い合いながら、一緒に晩ごはんを作る。この「小さな、代わり映えのしない日常の儀式」の積み重ねこそが、どんな強力な護符や結界よりも、二人の絆を強く、深く結びつけていくのだ。
「あ、雅人! 買ってきた卵、一つだけパックの中で『黄金のオーラ』を放ってる気がするんだけど!」
花がパックを開けると、そこには他よりも少し形の良い卵があった。
雅人は覗き込み、眼鏡の奥の目を細めた。
「ふむ。花、それはおそらく『双子の卵』だな。一つの殻の中に二つの魂が寄り添う吉兆だ。明日、二人で割ってみよう。それは、我々の前途に幸多からんことを示す神の啓示だ」
「……お祓いじゃなくて、珍しく普通に素敵なこと言ったね」
「うむ。君と日々を過ごすうちに、私の霊感も、君の放つ『生活感』という名の光に浄化されていくようだ」
雅人の大きな手が、花の頭を優しく撫でる。
その手からは、邪気を払う冷たい気ではなく、花を慈しむ温かな体温が伝わってきた。
「さあ、花。今夜の夕餉(ゆうげ)を始めよう。まずは、この半額シールの呪縛から解き放たれた肉を、最高の状態で供養(調理)するのだ」
「はいはい。じゃあ雅人は、キャベツの千切りをお願い。陰陽師の包丁捌き、期待してるよ」
「任せておけ。私の包丁は、食材の『細胞の未練』さえも断ち切る」
「細胞の未練は残しておいていいから、指切らないでね!」
キッチンに、トントントンと小気味よい包丁の音が響き渡る。
夕食の香りが広がる中、二人の賑やかな日常は、今夜も幸せな結界に包まれて更けていく。
0
あなたにおすすめの小説

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

「やはり鍛えることは、大切だな」
イチイ アキラ
恋愛
「こんなブスと結婚なんていやだ!」
その日、一つのお見合いがあった。
ヤロール伯爵家の三男、ライアンと。
クラレンス辺境伯家の跡取り娘、リューゼットの。
そして互いに挨拶を交わすその場にて。
ライアンが開幕早々、ぶちかましたのであった。
けれども……――。
「そうか。私も貴様のような生っ白くてか弱そうな、女みたいな顔の屑はごめんだ。気が合うな」

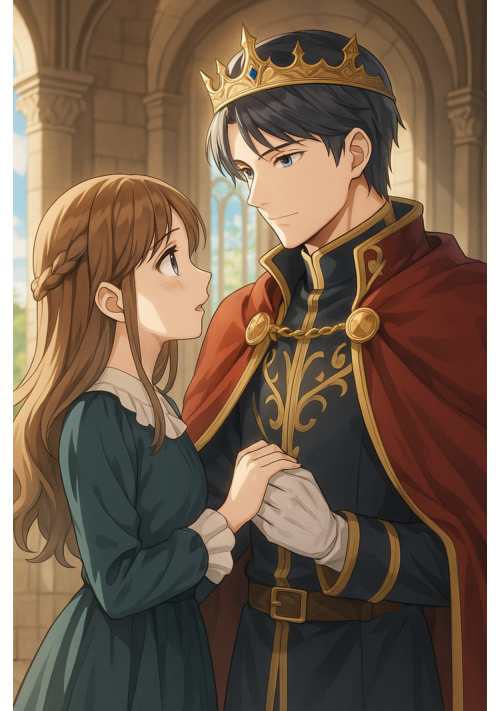
ご愁傷様です~「冴えない女」と捨てられた私が、王妃になりました~
有賀冬馬
恋愛
「地味な君とは釣り合わない」――私は、婚約者の騎士エルマーにそう告げられ、婚約破棄された。病弱で目立たない私は、美しい妹と比べられ、家族からも冷遇されてきた。
居場所を失い、ひっそり暮らしていたある日、市場で助けた老人が、なんとこの国の若き国王陛下で!?
彼と私は密かに逢瀬を重ねるように。
「愚かな男には一生かかっても分かるまい。私は、彼女のような女性を誇りに思う」妃選びの場で告げられた国王陛下の一言に、貴族社会は騒然。


いつか彼女を手に入れる日まで〜after story〜
月山 歩
恋愛
幼い頃から相思相愛の婚約者がいる私は、医師で侯爵の父が、令嬢に毒を盛ったと疑われて、捕らえられたことから、婚約者と結婚できないかもしれない危機に直面する。私はどうなってしまうの?
「いつかあなたを手に入れる日まで」のその後のお話です。単独でもわかる内容になっていますが、できればそちらから読んでいただけると、より理解していただけると思います。

退屈扱いされた私が、公爵様の教えで社交界を塗り替えるまで
有賀冬馬
恋愛
「お前は僕の隣に立つには足りない」――そう言い放たれた夜から、私の世界は壊れた。
辺境で侍女として働き始めた私は、公爵の教えで身だしなみも心も整えていく。
公爵は決して甘やかさない。だが、その公正さが私を変える力になった。
元婚約者の偽りは次々に暴かれ、私はもう泣かない。最後に私が選んだのは、自分を守ってくれた静かな人。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















