5 / 30
第1部 エド・ホード
第5話 十二歳式
しおりを挟む
「エドー、迎えにきたよ」
外から呼ばれて玄関に出ると、リテアがお祭りの衣装を着て立っていた。赤染のドレスに革のベルトを巻いて、頭には羽飾りをつけていた。うっすら引かれた口紅や、なめらかな肩やイヤリングも、何もかもが彼女を大人っぽく見せていた。僕は急に寂しくなった。自分だけがいつまでも大人になれないでいる気がした。
「緊張してる?」
リテアが僕に笑いかける。が、僕にはそれさえも、大人びた仕草に感じられた。リテアは自分がおかしいからではなく、僕のために笑ったのだ。それは以前の僕たちとはまったく違ってしまっていた。
「平気だよ」
と僕は言った。本当の気持ちを伝えられたらどれだけよかっただろうと思いながら。
「あらー、リテアちゃん、綺麗だねえ」
エレンおばさんも出てきて言った。
「リテアちゃんは、夏が終わったら街に出るの?」
「まだ決まったわけではないですけど」
リテアは少し困ったように言った。
「いいのよ。もう大人なんだから、自分のことは自分で決めないとね」
じゃあ、私もあとで行くからね、とエレンおばさんに送り出されて、僕たちは二人で成人の滝へ向かった。この村の子供は、数えで十二になる年に、崖から滝つぼに飛び込むことになっている。理由は誰も知らないけれど、昔からの決まりなのだそうだ。
「崖から飛べば、少しは気持ちが変わるのかな?」
僕は隣を歩くリテアに言った。
「変わるって?」
「なんだろう、ちょっとは大人になるっていうか……」
「どうだろうね」
リテアはまた例の大人びた笑みを浮かべた。
「ねえエド、どうなったとしても、わたしたちはずっと友達だよね?」
僕はとっさに言葉を返せなかった。
沈黙を埋めるように、リテアはまた小さく笑った。
滝のある崖の上には、すでに多くの大人たちが集まっていた。木のベンチや供物台には、焼き鳥や尾頭つきの魚など、ご馳走がところせましと並べてある。村のお年寄りたちが火を囲み、笛や太鼓の音を合わせていた。陽気でどこか妖しい演奏と、激しい水音が重なると、薄暗い火明かりのせいもあってか、途端に神聖な気分になった。
村にはうんと小さな子を除いて、子供は僕たち二人しかいない。僕もリテアも、成人の儀式を見るのはこれがはじめてのことだった。緊張でたいした会話もできないまま、ときどき顔を見合わせてはヘラヘラしていた。
十六夜の月が空に昇ると、いよいよ儀式がはじまった。僕たちはお酒を口に含み、順番に崖の際へ並んだ。笛が止み、太鼓の音が早くなる。鼓動までもが早くなって、目の前の奈落に息がつまった。
「森の神々よ、わたしはリテア・オルセン、この夏で晴れて成人となる」
リテアが右手を高くあげて宣言する。声が少しうわずっていた。
「わたしはこの秋に街へ出て、科学の発展のため勉強します。いつか魔法みたいな道具を両手いっぱいに抱えて、この村へ戻ってくることを誓います」
村の人たちが一斉に拍手をする。楽器の音が高らかに響いて、飛べー、とみんながはやしたてた。リテアは僕のほうを振り返って片目をつむると、そのまま背後に倒れるように身を投げた。わあっと歓声があがって、指笛と拍手が割れんばかりに響く。次は僕の番だった。
「僕の名前はエド・ホード。この夏で晴れて成人となる」
ここまでは練習通り。が、次の言葉が出てこなかった。重苦しい沈黙に、水音だけが響いている。大丈夫よ、とリテアのお母さんが、温かい声援を送ってくれた。エレンおばさんは不安そうにこちらを見ている。
「僕は……、僕は……」
水音だけが響いている。村の人たちの視線を矢のように感じた。
「僕は……、普通の大人になりたい」
笛の音は鳴らなかった。拍手も指笛もない。大人たちは明らかに戸惑っていた。僕のせいだ。僕が儀式を台無しにした。全身から冷や汗が出る。かと言って、自分がどんな大人になりたいのかもわからなかった。
僕は逃げるように身を投げた。それこそ自分を捨てるみたいに。
外から呼ばれて玄関に出ると、リテアがお祭りの衣装を着て立っていた。赤染のドレスに革のベルトを巻いて、頭には羽飾りをつけていた。うっすら引かれた口紅や、なめらかな肩やイヤリングも、何もかもが彼女を大人っぽく見せていた。僕は急に寂しくなった。自分だけがいつまでも大人になれないでいる気がした。
「緊張してる?」
リテアが僕に笑いかける。が、僕にはそれさえも、大人びた仕草に感じられた。リテアは自分がおかしいからではなく、僕のために笑ったのだ。それは以前の僕たちとはまったく違ってしまっていた。
「平気だよ」
と僕は言った。本当の気持ちを伝えられたらどれだけよかっただろうと思いながら。
「あらー、リテアちゃん、綺麗だねえ」
エレンおばさんも出てきて言った。
「リテアちゃんは、夏が終わったら街に出るの?」
「まだ決まったわけではないですけど」
リテアは少し困ったように言った。
「いいのよ。もう大人なんだから、自分のことは自分で決めないとね」
じゃあ、私もあとで行くからね、とエレンおばさんに送り出されて、僕たちは二人で成人の滝へ向かった。この村の子供は、数えで十二になる年に、崖から滝つぼに飛び込むことになっている。理由は誰も知らないけれど、昔からの決まりなのだそうだ。
「崖から飛べば、少しは気持ちが変わるのかな?」
僕は隣を歩くリテアに言った。
「変わるって?」
「なんだろう、ちょっとは大人になるっていうか……」
「どうだろうね」
リテアはまた例の大人びた笑みを浮かべた。
「ねえエド、どうなったとしても、わたしたちはずっと友達だよね?」
僕はとっさに言葉を返せなかった。
沈黙を埋めるように、リテアはまた小さく笑った。
滝のある崖の上には、すでに多くの大人たちが集まっていた。木のベンチや供物台には、焼き鳥や尾頭つきの魚など、ご馳走がところせましと並べてある。村のお年寄りたちが火を囲み、笛や太鼓の音を合わせていた。陽気でどこか妖しい演奏と、激しい水音が重なると、薄暗い火明かりのせいもあってか、途端に神聖な気分になった。
村にはうんと小さな子を除いて、子供は僕たち二人しかいない。僕もリテアも、成人の儀式を見るのはこれがはじめてのことだった。緊張でたいした会話もできないまま、ときどき顔を見合わせてはヘラヘラしていた。
十六夜の月が空に昇ると、いよいよ儀式がはじまった。僕たちはお酒を口に含み、順番に崖の際へ並んだ。笛が止み、太鼓の音が早くなる。鼓動までもが早くなって、目の前の奈落に息がつまった。
「森の神々よ、わたしはリテア・オルセン、この夏で晴れて成人となる」
リテアが右手を高くあげて宣言する。声が少しうわずっていた。
「わたしはこの秋に街へ出て、科学の発展のため勉強します。いつか魔法みたいな道具を両手いっぱいに抱えて、この村へ戻ってくることを誓います」
村の人たちが一斉に拍手をする。楽器の音が高らかに響いて、飛べー、とみんながはやしたてた。リテアは僕のほうを振り返って片目をつむると、そのまま背後に倒れるように身を投げた。わあっと歓声があがって、指笛と拍手が割れんばかりに響く。次は僕の番だった。
「僕の名前はエド・ホード。この夏で晴れて成人となる」
ここまでは練習通り。が、次の言葉が出てこなかった。重苦しい沈黙に、水音だけが響いている。大丈夫よ、とリテアのお母さんが、温かい声援を送ってくれた。エレンおばさんは不安そうにこちらを見ている。
「僕は……、僕は……」
水音だけが響いている。村の人たちの視線を矢のように感じた。
「僕は……、普通の大人になりたい」
笛の音は鳴らなかった。拍手も指笛もない。大人たちは明らかに戸惑っていた。僕のせいだ。僕が儀式を台無しにした。全身から冷や汗が出る。かと言って、自分がどんな大人になりたいのかもわからなかった。
僕は逃げるように身を投げた。それこそ自分を捨てるみたいに。
0
あなたにおすすめの小説

異世界帰りの勇者、今度は現代世界でスキル、魔法を使って、無双するスローライフを送ります!?〜ついでに世界も救います!?〜
沢田美
ファンタジー
かつて“異世界”で魔王を討伐し、八年にわたる冒険を終えた青年・ユキヒロ。
数々の死線を乗り越え、勇者として讃えられた彼が帰ってきたのは、元の日本――高校卒業すらしていない、現実世界だった。
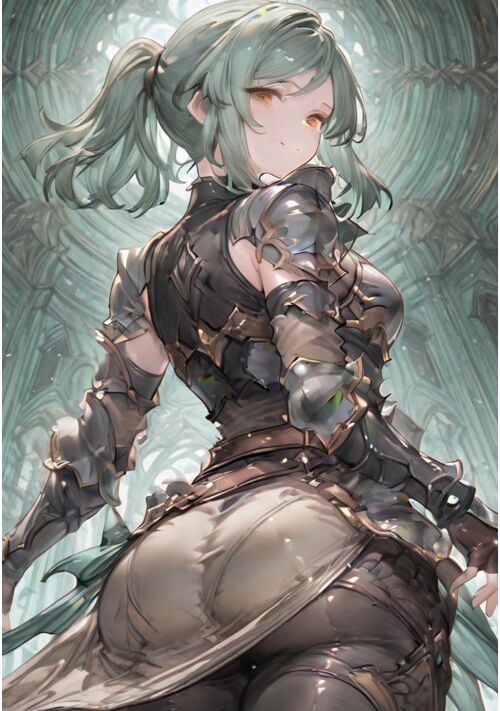
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

氷の精霊と忘れられた王国 〜追放された青年、消えた約束を探して〜
fuwamofu
ファンタジー
かつて「英雄」と讃えられた青年アレンは、仲間の裏切りによって王国を追放された。
雪原の果てで出会ったのは、心を閉ざした氷の精霊・リィナ。
絶望の底で交わした契約が、やがて滅びかけた王国の運命を変えていく――。
氷と炎、愛と憎しみ、真実と嘘が交錯する異世界再生ファンタジー。
彼はなぜ忘れられ、なぜ再び立ち上がるのか。
世界の記憶が凍りつく時、ひとつの約束だけが、彼らを導く。

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。


第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

転生社畜、転生先でも社畜ジョブ「書記」でブラック労働し、20年。前人未到のジョブレベルカンストからの大覚醒成り上がり!
nineyu
ファンタジー
男は絶望していた。
使い潰され、いびられ、社畜生活に疲れ、気がつけば死に場所を求めて樹海を歩いていた。
しかし、樹海の先は異世界で、転生の影響か体も若返っていた!
リスタートと思い、自由に暮らしたいと思うも、手に入れていたスキルは前世の影響らしく、気がつけば変わらない社畜生活に、、
そんな不幸な男の転機はそこから20年。
累計四十年の社畜ジョブが、遂に覚醒する!!

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜
KeyBow
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞
ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。
諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。
そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。
捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。
腕には、守るべきメイドの少女。
眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。
―――それは、ただの不運な落下のはずだった。
崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。
その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。
死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。
だが、その力の代償は、あまりにも大きい。
彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――
つまり平和で自堕落な生活そのものだった。
これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、
守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、
いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。
―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















