7 / 30
第1部 エド・ホード
第7話 呪い
しおりを挟む
夏の終わりに、リテアの学校の合格通知が届いた。今日の間に荷物をまとめて、リテアは三日後にはこの村を出ていくらしい。一度よそへ行ってしまえば、きっと二度と戻らないだろうことは、さすがの僕にもわかっていた。
これまでに外へ行った大人たちは、誰もが、必ず帰ってくる、と約束をしてこの村を去った。が、実際に帰った人はいない。たまに顔を見せに戻ることはあるけれど、またすぐに街へ戻ってしまうのだった。
通知から二日目の夜にお別れ会をして、村の人たちと大騒ぎをして朝まで歌った。出発前夜はゆっくり休めるように、とのことだったが、僕はもちろん、最後の夜はツリーハウスへ行った。最後くらいは、リテアと二人きりでいたいと思った。
ランプに火を灯して絨毯に座り、揺れる影を見ながらラジオを聞いた。しかし零時を過ぎても、リテアはやってこなかった。彼女の心は、すでにこの村を発ってしまったのだろう。やがてオイルが燃え尽きたのか、ランプの明かりは消えてしまった。自分の手のひらも見えない暗闇のなかで、僕は急激に胸が苦しくなるのを感じた。
森の声が聞こえていた。
窓を見ると、燃え立つような青白い火が、ガラスの表面を波打っていた。くらりくらりとひるがえり、その火が身を大きくするたび、僕の苦痛も大きくなった。火はゆっくり伸びてきて、胸のなかへ入ってくる。消えろ、と僕は強く念じた。消えろ、消えろ、消えろ。火はリテアの人形に燃え移り、やがて静かに同化すると、本人とうりふたつの姿になった。
表情こそ変わらないものの、弾力や肌触りや匂いさえ、本物と区別がつかなかった。森の声が頭にこだまし、胸が張り裂けそうなほど苦しくなる。消えろ、消えろ、と念じながら、僕はリテアの身体にしがみついた。火は僕の胸を焼き尽くし、森の声で囁いた。石を取れ。その一瞬、僕は間違いなくリテアといた。彼女は半袖の白い寝間着姿で、タオルケットにくるまり眠っていた。石を取れ、と声が言う。僕は心が割れそうになるのをこらえながら、無我夢中でリテアの首飾りに手を伸ばした。石を掴むと同時に涙があふれて、森の声も青白い火も消えてしまった。
次に気がついたとき、部屋にはすでに朝の光が差し込んでいた。眠っていたというよりは、気を失っていたんじゃないか、と思うほど短い間に感じられた。森を出て村へ帰ると、
「おお、エド、無事だったか」
「エレンが心配してるよ」
と近所の人たちに次々と声をかけられた。何か変だと思いながら家に帰ると、外で待っていたエレンおばさんが、目に大粒の涙を浮かべながら僕を抱きしめた。
「……エド、よかったわ、あなたは無事だったのね」
「ごめん、おばさん。何かあったの?」
「落ち着いて聞いてね」
エレンおばさんは僕の肩をつかんだまま、地面に両膝をついてこちらを見つめた。
「どうしたの?」
「リテアちゃんがね、亡くなったのよ」
「は?」
僕は急に視界がせまくなるように感じた。
「昨日の夜、家に強盗が入ったのよ。かわいそうに、ご両親は気づきもしなかったそうよ」
僕は言葉を失った。エレンおばさんは僕をまた強く抱きしめると、
「夕方から葬儀があるからね」
と涙声で言った。きちんとお別れをしないとね。
僕はエレンおばさんの腕を引きはがして、リテアの家に走っていった。エレンおばさんは僕を止めなかった。
リテアの家には、すでに多くの人が集まっていた。みんな黒い服を着て、申し合せたように浮かない顔をしている。レンガ造りの広いリビングに、花束で埋め尽くされた棺があった。リテアはそのなかで眠っていた。半袖の白い寝間着姿で、いつも身につけているはずの首飾りはしていなかった。
「やあエド、来てくれたんだね」
リテアのお父さんが、僕を見つけて声をかけてくれた。
おじさんのまぶたは赤くはれていて、僕はとっさになんて言っていいかわからなくなった。
「よかった、無事だったんだね。君にも何かあったんじゃないかって、みんな心配していたんだよ」
「リテアはどうしたんですか?」
「強盗に襲われたんだ。うちに忍び込んだはいいが、金目のものが見つからなかったんだろうね、娘の首飾りを盗っていったよ」
「……首飾り?」
僕は恐怖と罪悪感に気を失いそうになった。
「大丈夫かい?」
「……僕のせいなんです」
そう言うと、部屋中の人たちの視線が集まった。
「ちょっとこっちに」
おじさんは僕の手をつかむと、部屋の二階へ連れていった。
「いったいどういうことだい?」
「僕が首飾りを盗ったんです」
「首飾りを持っているのか?」
僕は首を横に振った。
「そうだろう。まだ誰にも伝えていないが、家の鍵はすべて閉まったままだった。もちろん娘の部屋も全部だよ。密室だったんだ。普通の人間が入れるわけない」
「僕は森に入りました。昨日も森にいたんです。それで……」
「娘を待ってくれていたんだね。昨日の夜は、私が早く眠るように注意したから……こんなことなら、行かせていればよかったよ」
「僕のせいなんです」
「でも森にいたんだろう? 大丈夫、エドのせいじゃない。君くらいの年頃の子は、身近に起こった不幸を、なんでも自分のせいみたいに思ってしまうものなんだ。もとはと言えば、私が首飾りなんてやらなければ」
「あの首飾りはなんなんですか?」
僕はふいと思い出して先を続けた。
「リテアはおじさんが、妖精王にもらったものだと話していました。あの首飾りには、何か不思議な力があるんですか?」
「馬鹿なことを言っちゃいけない。あれは出張の土産に買ったものだよ」
「リテアはたしか、魔法の本の話もしていました。森のどこかに幽霊たちの住む屋敷があって、死者の魂を呼び寄せてるって。そこに行けば、リテアとまた話せますか?」
おじさんはうつむいたまま首を横に振った。
「悪いけどみんなデタラメだよ」
「でも」
「でもたしかに森は危険だ。私も少しあまかった。もう森には入っちゃいけないよ」
おじさんはそう言うと、僕の頭をそっとなでた。
僕はまた一階に戻って、棺のなかのリテアを見つめた。頬が少しこけていて、あんなにやわらかそうだった肌は見る影もなかった。誰が首飾りを盗ったのだろう、と僕は思った。誰がリテアを殺したのだろう。
お前だ、と森の声が言った気がした。
これまでに外へ行った大人たちは、誰もが、必ず帰ってくる、と約束をしてこの村を去った。が、実際に帰った人はいない。たまに顔を見せに戻ることはあるけれど、またすぐに街へ戻ってしまうのだった。
通知から二日目の夜にお別れ会をして、村の人たちと大騒ぎをして朝まで歌った。出発前夜はゆっくり休めるように、とのことだったが、僕はもちろん、最後の夜はツリーハウスへ行った。最後くらいは、リテアと二人きりでいたいと思った。
ランプに火を灯して絨毯に座り、揺れる影を見ながらラジオを聞いた。しかし零時を過ぎても、リテアはやってこなかった。彼女の心は、すでにこの村を発ってしまったのだろう。やがてオイルが燃え尽きたのか、ランプの明かりは消えてしまった。自分の手のひらも見えない暗闇のなかで、僕は急激に胸が苦しくなるのを感じた。
森の声が聞こえていた。
窓を見ると、燃え立つような青白い火が、ガラスの表面を波打っていた。くらりくらりとひるがえり、その火が身を大きくするたび、僕の苦痛も大きくなった。火はゆっくり伸びてきて、胸のなかへ入ってくる。消えろ、と僕は強く念じた。消えろ、消えろ、消えろ。火はリテアの人形に燃え移り、やがて静かに同化すると、本人とうりふたつの姿になった。
表情こそ変わらないものの、弾力や肌触りや匂いさえ、本物と区別がつかなかった。森の声が頭にこだまし、胸が張り裂けそうなほど苦しくなる。消えろ、消えろ、と念じながら、僕はリテアの身体にしがみついた。火は僕の胸を焼き尽くし、森の声で囁いた。石を取れ。その一瞬、僕は間違いなくリテアといた。彼女は半袖の白い寝間着姿で、タオルケットにくるまり眠っていた。石を取れ、と声が言う。僕は心が割れそうになるのをこらえながら、無我夢中でリテアの首飾りに手を伸ばした。石を掴むと同時に涙があふれて、森の声も青白い火も消えてしまった。
次に気がついたとき、部屋にはすでに朝の光が差し込んでいた。眠っていたというよりは、気を失っていたんじゃないか、と思うほど短い間に感じられた。森を出て村へ帰ると、
「おお、エド、無事だったか」
「エレンが心配してるよ」
と近所の人たちに次々と声をかけられた。何か変だと思いながら家に帰ると、外で待っていたエレンおばさんが、目に大粒の涙を浮かべながら僕を抱きしめた。
「……エド、よかったわ、あなたは無事だったのね」
「ごめん、おばさん。何かあったの?」
「落ち着いて聞いてね」
エレンおばさんは僕の肩をつかんだまま、地面に両膝をついてこちらを見つめた。
「どうしたの?」
「リテアちゃんがね、亡くなったのよ」
「は?」
僕は急に視界がせまくなるように感じた。
「昨日の夜、家に強盗が入ったのよ。かわいそうに、ご両親は気づきもしなかったそうよ」
僕は言葉を失った。エレンおばさんは僕をまた強く抱きしめると、
「夕方から葬儀があるからね」
と涙声で言った。きちんとお別れをしないとね。
僕はエレンおばさんの腕を引きはがして、リテアの家に走っていった。エレンおばさんは僕を止めなかった。
リテアの家には、すでに多くの人が集まっていた。みんな黒い服を着て、申し合せたように浮かない顔をしている。レンガ造りの広いリビングに、花束で埋め尽くされた棺があった。リテアはそのなかで眠っていた。半袖の白い寝間着姿で、いつも身につけているはずの首飾りはしていなかった。
「やあエド、来てくれたんだね」
リテアのお父さんが、僕を見つけて声をかけてくれた。
おじさんのまぶたは赤くはれていて、僕はとっさになんて言っていいかわからなくなった。
「よかった、無事だったんだね。君にも何かあったんじゃないかって、みんな心配していたんだよ」
「リテアはどうしたんですか?」
「強盗に襲われたんだ。うちに忍び込んだはいいが、金目のものが見つからなかったんだろうね、娘の首飾りを盗っていったよ」
「……首飾り?」
僕は恐怖と罪悪感に気を失いそうになった。
「大丈夫かい?」
「……僕のせいなんです」
そう言うと、部屋中の人たちの視線が集まった。
「ちょっとこっちに」
おじさんは僕の手をつかむと、部屋の二階へ連れていった。
「いったいどういうことだい?」
「僕が首飾りを盗ったんです」
「首飾りを持っているのか?」
僕は首を横に振った。
「そうだろう。まだ誰にも伝えていないが、家の鍵はすべて閉まったままだった。もちろん娘の部屋も全部だよ。密室だったんだ。普通の人間が入れるわけない」
「僕は森に入りました。昨日も森にいたんです。それで……」
「娘を待ってくれていたんだね。昨日の夜は、私が早く眠るように注意したから……こんなことなら、行かせていればよかったよ」
「僕のせいなんです」
「でも森にいたんだろう? 大丈夫、エドのせいじゃない。君くらいの年頃の子は、身近に起こった不幸を、なんでも自分のせいみたいに思ってしまうものなんだ。もとはと言えば、私が首飾りなんてやらなければ」
「あの首飾りはなんなんですか?」
僕はふいと思い出して先を続けた。
「リテアはおじさんが、妖精王にもらったものだと話していました。あの首飾りには、何か不思議な力があるんですか?」
「馬鹿なことを言っちゃいけない。あれは出張の土産に買ったものだよ」
「リテアはたしか、魔法の本の話もしていました。森のどこかに幽霊たちの住む屋敷があって、死者の魂を呼び寄せてるって。そこに行けば、リテアとまた話せますか?」
おじさんはうつむいたまま首を横に振った。
「悪いけどみんなデタラメだよ」
「でも」
「でもたしかに森は危険だ。私も少しあまかった。もう森には入っちゃいけないよ」
おじさんはそう言うと、僕の頭をそっとなでた。
僕はまた一階に戻って、棺のなかのリテアを見つめた。頬が少しこけていて、あんなにやわらかそうだった肌は見る影もなかった。誰が首飾りを盗ったのだろう、と僕は思った。誰がリテアを殺したのだろう。
お前だ、と森の声が言った気がした。
0
あなたにおすすめの小説

異世界帰りの勇者、今度は現代世界でスキル、魔法を使って、無双するスローライフを送ります!?〜ついでに世界も救います!?〜
沢田美
ファンタジー
かつて“異世界”で魔王を討伐し、八年にわたる冒険を終えた青年・ユキヒロ。
数々の死線を乗り越え、勇者として讃えられた彼が帰ってきたのは、元の日本――高校卒業すらしていない、現実世界だった。
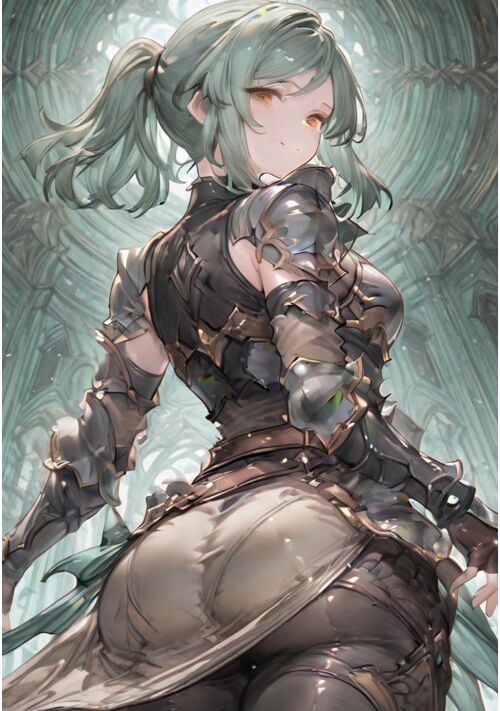
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

氷の精霊と忘れられた王国 〜追放された青年、消えた約束を探して〜
fuwamofu
ファンタジー
かつて「英雄」と讃えられた青年アレンは、仲間の裏切りによって王国を追放された。
雪原の果てで出会ったのは、心を閉ざした氷の精霊・リィナ。
絶望の底で交わした契約が、やがて滅びかけた王国の運命を変えていく――。
氷と炎、愛と憎しみ、真実と嘘が交錯する異世界再生ファンタジー。
彼はなぜ忘れられ、なぜ再び立ち上がるのか。
世界の記憶が凍りつく時、ひとつの約束だけが、彼らを導く。

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。


第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

転生社畜、転生先でも社畜ジョブ「書記」でブラック労働し、20年。前人未到のジョブレベルカンストからの大覚醒成り上がり!
nineyu
ファンタジー
男は絶望していた。
使い潰され、いびられ、社畜生活に疲れ、気がつけば死に場所を求めて樹海を歩いていた。
しかし、樹海の先は異世界で、転生の影響か体も若返っていた!
リスタートと思い、自由に暮らしたいと思うも、手に入れていたスキルは前世の影響らしく、気がつけば変わらない社畜生活に、、
そんな不幸な男の転機はそこから20年。
累計四十年の社畜ジョブが、遂に覚醒する!!

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜
KeyBow
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞
ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。
諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。
そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。
捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。
腕には、守るべきメイドの少女。
眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。
―――それは、ただの不運な落下のはずだった。
崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。
その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。
死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。
だが、その力の代償は、あまりにも大きい。
彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――
つまり平和で自堕落な生活そのものだった。
これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、
守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、
いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。
―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















