11 / 30
第1部 エド・ホード
第11話 堕天使の召喚
しおりを挟む
幽霊図書館から持ち帰った『堕天使の召喚』には、一柱の堕天使を召喚するための手順が、百近くも書かれてあった。召喚者の身だしなみや条件の項目にはじまり、儀式の前に済ませておく禊についてや、召喚に必要な供物の一覧、場所や暦や魔法円の書き方など、五百ページにもわたってびっしり書かれてあった。
読むだけでも大変だったけれど、僕はもう一度リテアと話せるならと、寝る間をおしんで四日間で読破した。体を清潔に保つことや、儀式に適した場所を探すこと、魔法円の書き方などは、それほど難しそうではなかった。いちばん苦労したのは、召喚に必要な供物を見つけることだった。純白のカエルに、甲羅の二つあるカメ、左右の目の色の違うネコに、角が四本ある羊の頭……。エルクとテリーの力を借りても、すべて見つけるのに一年近くかかってしまった。
すべての準備が整うと、僕は髪を短く切って、風呂に入って体の毛をそり、満月の浮かぶ小高い丘にやってきた。月の実をナイフで切って、きらきらと光る果汁を、森の泉で汲んできた水に搾り入れる。砂の地面に、その水で大小二つの魔法円を書き、自転車の車輪のように三角形で繋ぐ。最後に大きい魔法円に供物を置いたら、自分は小さいほうに立って本を開いた。
「天使が現れたら、僕らはもう手出しができないから」
エルクは真剣な顔で言った。
「天使は僕たち精霊より、何百倍も強力な権限を持っているから。いいかい? 絶対に小さな魔法円から出てはいけないよ。奴らはたしかに精霊より、自在に自然の法則を曲げられるけれど、自分の身体を持っていないのは同じなんだ」
「つまり?」
と首をかしげると、
「君の身体を奪おうとするってことさ」
テリーが不安げな顔で言った。「ねえ、エド、本当にやる気?」
「そのために準備してきたんじゃないか」
「やめるなら今だよ」
エルクまでもがそんなことを言う。
「はじめるよ」
僕は本に目を落とした。
エルクとテリーが闇に消え入る。
「私は歩む。主は泳ぐ。月が林檎と落ちてくる」
僕は意味のわからない呪文を、間違えないように読みあげていった。
「鏡は悪事を見逃さない。主を呼ぶのは誰だろう。そう訊く私は誰だろう」
魔法円が光を放ち、陽炎のように地上を波打つ。金星の明かりが、大きな魔法円に降り注ぎ、やがて完全に堕ちてきた。爆音がとどろき、あたりに砂煙が立ち込める。
「来たれ、デーモン」
最後にそう唱えて膝をついた。
砂煙に赤紫の光が映える。視界がはれると、一柱の堕天使が現れた。
――様子が変だ。
エルクの言いたいことは僕にもわかった。『堕天使の召喚』の挿絵には、牛のような顔をした、三対の翼を持つ堕天使の姿が描かれてあった。が、目の前に現れたその魔物は、赤い顔で角をはやしてはいるものの、それ以外はあまりに人間らしかった。
「久方ぶりの召喚だ。具象化の悦には慣れかけたものの、やはり大手を振って出られるのはいい。感謝するぞ、我が小さき召喚士よ。さあ、さっそく望みを聞こう」
赤い顔の魔物は流れるような口調で言った。
「あなたは四大天使の一柱ですか?」
「それが望みか?」
僕はあわてて首を横に振った。
「私が誰であろうと構わんだろう。そもそも魔物やら天使やらといったものは、お前ら人間どもの定めた分類に過ぎん」
「僕の望みは、リテアとまた話すことです」
「いかに天使といえども、死者を地上に蘇らせることはできない。お前はそれを理解したうえで、そいつとまた話したいと言っているんだな?」
そうです、と僕は頷いた。
「なら聞き入れよう。ではこちらに少しだけ、顔を近づけてくれるかな?」
言われるがまま、匂いを嗅ぐように鼻先を寄せると、
――ダメだエド!
頭のなかでエルクが叫んだ。僕はとっさに顔をひっこめた。もうすぐで小さな魔法円から、鼻を出すところだった。
「……ほう、奇特なガキだ、精霊の声が聞こえるのか」
赤い顔の魔物はそう言うと、おもむろに手のひらを上に向けた。
「これがなんだかわかるか?」
長い爪の赤い手から、何かがじわじわと浮かび出てくる。
柳の葉の形をした首飾り。緑の石のネックレス。
「それは……」
僕は言葉を失った。
「お前のおかげで手に入った。あの夜は世話になったな」
「……返せ」
僕は思わず手を伸ばした。
――やめろエド!
エルクの声にはっとする。が、遅かった。リテアの首飾りは、魔物の手のなかで形を変え、大きな槍の姿になった。鈍く光る一本槍。魔物の手から離れると、ものすごい速さで飛び込んできた。僕はとっさに手を引っ込めたが、指先が魔法円の内側に入る前に、槍に体もろとも押し出されてしまった。
「妖精王の鎧!」
僕はエルクの能力を使って、光のバリアを展開した。が、とても槍の勢いは殺せそうにない。魔法円から完全に引きずり出され、崖際へじりじりと追いつめられる。
――エド、もう限界だ。
エルクがそう呟いた刹那、光のバリアはガラスのように砕け散ってしまった。
「神の創りたもうた霊槍だぞ? 精霊ごときに止められるはずがない。さあ、グングニルの槍に続いて、その眼もこちらにいただこうか!」
槍が僕の胸に突き刺さる。途端に青白い火が噴きあげて、魂の割れる痛みがした。リテアを殺した。母親を殺した。父親はお前を憎んでいた。邪悪な声が頭を飛び交う。消えろ、消えろ、と念じるほど、青白い火は大きく燃えた。
――眼を使え。
消え入りそうな意識のなかで、森の声が聞こえた気がした。が、僕はすでに動けなかった。焼け切れそうなまぶたを開いて、誰かが僕の代わりに叫んだ。
「図に乗るなルキエル!」
その一瞬、槍はくるりとひるがえり、魔物のほうへ飛んでいった。魔物はすんでのところで避けようとしたが、それでも槍は、彼の脇腹に突き刺さった。
「馬鹿な……天使を規定しただと?」
赤紫の煙幕が、たちどころに丘を取り巻いていく。
「いたぞ! こっちだ!」
僕は駆けつけた誰かに担ぎあげられ、何かの乗り物にのせられた。
「……憶えていろ」
魔物が煙に呑まれていく。
僕の意識は急激に細くなっていった。
読むだけでも大変だったけれど、僕はもう一度リテアと話せるならと、寝る間をおしんで四日間で読破した。体を清潔に保つことや、儀式に適した場所を探すこと、魔法円の書き方などは、それほど難しそうではなかった。いちばん苦労したのは、召喚に必要な供物を見つけることだった。純白のカエルに、甲羅の二つあるカメ、左右の目の色の違うネコに、角が四本ある羊の頭……。エルクとテリーの力を借りても、すべて見つけるのに一年近くかかってしまった。
すべての準備が整うと、僕は髪を短く切って、風呂に入って体の毛をそり、満月の浮かぶ小高い丘にやってきた。月の実をナイフで切って、きらきらと光る果汁を、森の泉で汲んできた水に搾り入れる。砂の地面に、その水で大小二つの魔法円を書き、自転車の車輪のように三角形で繋ぐ。最後に大きい魔法円に供物を置いたら、自分は小さいほうに立って本を開いた。
「天使が現れたら、僕らはもう手出しができないから」
エルクは真剣な顔で言った。
「天使は僕たち精霊より、何百倍も強力な権限を持っているから。いいかい? 絶対に小さな魔法円から出てはいけないよ。奴らはたしかに精霊より、自在に自然の法則を曲げられるけれど、自分の身体を持っていないのは同じなんだ」
「つまり?」
と首をかしげると、
「君の身体を奪おうとするってことさ」
テリーが不安げな顔で言った。「ねえ、エド、本当にやる気?」
「そのために準備してきたんじゃないか」
「やめるなら今だよ」
エルクまでもがそんなことを言う。
「はじめるよ」
僕は本に目を落とした。
エルクとテリーが闇に消え入る。
「私は歩む。主は泳ぐ。月が林檎と落ちてくる」
僕は意味のわからない呪文を、間違えないように読みあげていった。
「鏡は悪事を見逃さない。主を呼ぶのは誰だろう。そう訊く私は誰だろう」
魔法円が光を放ち、陽炎のように地上を波打つ。金星の明かりが、大きな魔法円に降り注ぎ、やがて完全に堕ちてきた。爆音がとどろき、あたりに砂煙が立ち込める。
「来たれ、デーモン」
最後にそう唱えて膝をついた。
砂煙に赤紫の光が映える。視界がはれると、一柱の堕天使が現れた。
――様子が変だ。
エルクの言いたいことは僕にもわかった。『堕天使の召喚』の挿絵には、牛のような顔をした、三対の翼を持つ堕天使の姿が描かれてあった。が、目の前に現れたその魔物は、赤い顔で角をはやしてはいるものの、それ以外はあまりに人間らしかった。
「久方ぶりの召喚だ。具象化の悦には慣れかけたものの、やはり大手を振って出られるのはいい。感謝するぞ、我が小さき召喚士よ。さあ、さっそく望みを聞こう」
赤い顔の魔物は流れるような口調で言った。
「あなたは四大天使の一柱ですか?」
「それが望みか?」
僕はあわてて首を横に振った。
「私が誰であろうと構わんだろう。そもそも魔物やら天使やらといったものは、お前ら人間どもの定めた分類に過ぎん」
「僕の望みは、リテアとまた話すことです」
「いかに天使といえども、死者を地上に蘇らせることはできない。お前はそれを理解したうえで、そいつとまた話したいと言っているんだな?」
そうです、と僕は頷いた。
「なら聞き入れよう。ではこちらに少しだけ、顔を近づけてくれるかな?」
言われるがまま、匂いを嗅ぐように鼻先を寄せると、
――ダメだエド!
頭のなかでエルクが叫んだ。僕はとっさに顔をひっこめた。もうすぐで小さな魔法円から、鼻を出すところだった。
「……ほう、奇特なガキだ、精霊の声が聞こえるのか」
赤い顔の魔物はそう言うと、おもむろに手のひらを上に向けた。
「これがなんだかわかるか?」
長い爪の赤い手から、何かがじわじわと浮かび出てくる。
柳の葉の形をした首飾り。緑の石のネックレス。
「それは……」
僕は言葉を失った。
「お前のおかげで手に入った。あの夜は世話になったな」
「……返せ」
僕は思わず手を伸ばした。
――やめろエド!
エルクの声にはっとする。が、遅かった。リテアの首飾りは、魔物の手のなかで形を変え、大きな槍の姿になった。鈍く光る一本槍。魔物の手から離れると、ものすごい速さで飛び込んできた。僕はとっさに手を引っ込めたが、指先が魔法円の内側に入る前に、槍に体もろとも押し出されてしまった。
「妖精王の鎧!」
僕はエルクの能力を使って、光のバリアを展開した。が、とても槍の勢いは殺せそうにない。魔法円から完全に引きずり出され、崖際へじりじりと追いつめられる。
――エド、もう限界だ。
エルクがそう呟いた刹那、光のバリアはガラスのように砕け散ってしまった。
「神の創りたもうた霊槍だぞ? 精霊ごときに止められるはずがない。さあ、グングニルの槍に続いて、その眼もこちらにいただこうか!」
槍が僕の胸に突き刺さる。途端に青白い火が噴きあげて、魂の割れる痛みがした。リテアを殺した。母親を殺した。父親はお前を憎んでいた。邪悪な声が頭を飛び交う。消えろ、消えろ、と念じるほど、青白い火は大きく燃えた。
――眼を使え。
消え入りそうな意識のなかで、森の声が聞こえた気がした。が、僕はすでに動けなかった。焼け切れそうなまぶたを開いて、誰かが僕の代わりに叫んだ。
「図に乗るなルキエル!」
その一瞬、槍はくるりとひるがえり、魔物のほうへ飛んでいった。魔物はすんでのところで避けようとしたが、それでも槍は、彼の脇腹に突き刺さった。
「馬鹿な……天使を規定しただと?」
赤紫の煙幕が、たちどころに丘を取り巻いていく。
「いたぞ! こっちだ!」
僕は駆けつけた誰かに担ぎあげられ、何かの乗り物にのせられた。
「……憶えていろ」
魔物が煙に呑まれていく。
僕の意識は急激に細くなっていった。
0
あなたにおすすめの小説

異世界帰りの勇者、今度は現代世界でスキル、魔法を使って、無双するスローライフを送ります!?〜ついでに世界も救います!?〜
沢田美
ファンタジー
かつて“異世界”で魔王を討伐し、八年にわたる冒険を終えた青年・ユキヒロ。
数々の死線を乗り越え、勇者として讃えられた彼が帰ってきたのは、元の日本――高校卒業すらしていない、現実世界だった。
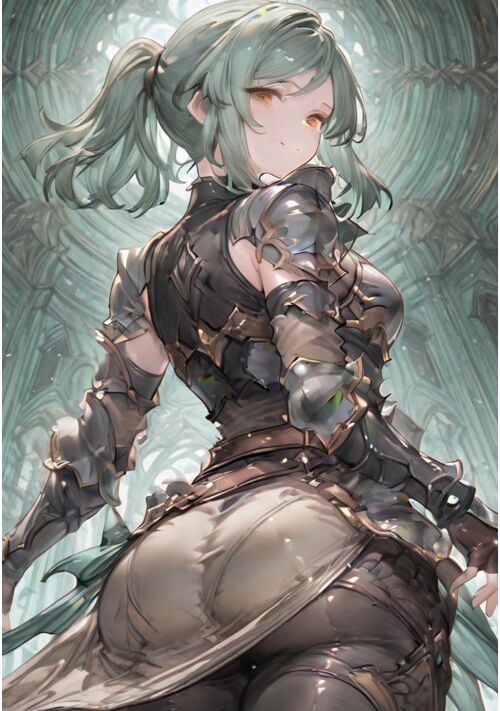
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

氷の精霊と忘れられた王国 〜追放された青年、消えた約束を探して〜
fuwamofu
ファンタジー
かつて「英雄」と讃えられた青年アレンは、仲間の裏切りによって王国を追放された。
雪原の果てで出会ったのは、心を閉ざした氷の精霊・リィナ。
絶望の底で交わした契約が、やがて滅びかけた王国の運命を変えていく――。
氷と炎、愛と憎しみ、真実と嘘が交錯する異世界再生ファンタジー。
彼はなぜ忘れられ、なぜ再び立ち上がるのか。
世界の記憶が凍りつく時、ひとつの約束だけが、彼らを導く。

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。


第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

転生社畜、転生先でも社畜ジョブ「書記」でブラック労働し、20年。前人未到のジョブレベルカンストからの大覚醒成り上がり!
nineyu
ファンタジー
男は絶望していた。
使い潰され、いびられ、社畜生活に疲れ、気がつけば死に場所を求めて樹海を歩いていた。
しかし、樹海の先は異世界で、転生の影響か体も若返っていた!
リスタートと思い、自由に暮らしたいと思うも、手に入れていたスキルは前世の影響らしく、気がつけば変わらない社畜生活に、、
そんな不幸な男の転機はそこから20年。
累計四十年の社畜ジョブが、遂に覚醒する!!

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜
KeyBow
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞
ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。
諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。
そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。
捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。
腕には、守るべきメイドの少女。
眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。
―――それは、ただの不運な落下のはずだった。
崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。
その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。
死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。
だが、その力の代償は、あまりにも大きい。
彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――
つまり平和で自堕落な生活そのものだった。
これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、
守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、
いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。
―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















