20 / 30
第1部 エド・ホード
第20話 最初の授業
しおりを挟む
本館はお城のような建物だった。こげ茶色の外壁に、緑青色のとんがり屋根。連なる尖塔や鐘楼の上には、制服にあしらわれているのと同じ紋章の旗がなびいていた。思った以上に巨大らしく、歩いても歩いても近づいてこない。
五分ほどしてようやく、跳ね橋のところまで来ることができた。深い堀には水が溜まっていて、お城のような講義棟が逆さまに映っていた。
アーチ状の入口からなかへ入ると、広いロビーに大きな二股階段が見えた。放射状に埋め込まれた敷石、星座図の描かれた吹き抜けの天井。暖炉の談話スペースには、色あせた地球儀や、すすけた甲冑が並んでいる。僕はカミラに案内されて、中央の階段をのぼっていった。最上階のいちばん奥で、カミラはふいと立ち止まった。
「ここが大司教室だよ」
「大司教?」
「ここは大学なんだけど、同時にアベカ派の教会でもあるの」
カミラは少し緊張した面持ちで扉を叩いた。
はい、と年老いた男性の声が聞こえて、そのすぐ後に扉が開いた。
「待っていましたよ。君がエド・ホード君か。若いころのお父さんにそっくりだ」
出てきたのは白髪の坊主のおじいさんだった。大柄で、たぶん身長は一八〇センチ以上ある。グレーのスーツ姿で、左耳には銀のリングが光っていた。
「私の名はオズ。この大学の校長をしています。遠い昔、君のお父さんは私のゼミ生でした」
オズ校長は手を出して、僕に握手を促した。両手で握り返すと、千年も前からある木に触ったような、静かで不思議な感じがした。
「お父さんの眼だね」
オズ校長は僕の顔を覗き込んで言った。
「父さんはどんな学生でしたか?」
と尋ねると、
「暗い子だったなあ」
顔をくしゃくしゃにして高笑いした。カミラも隣でくすくす笑って、後ろ手に僕の背中を叩いてきた。
「冗談だよ。たしかに暗かったが、それも君のお母さんに出会うまでだ」
「母さんのことも知ってるんですか?」
「まあ入ってくれ。贈答用の紅茶が山ほどあるんだ」
僕はカミラと一緒に部屋に入って、三人掛けの革張りのソファに座った。灰色の絨毯に、ローテーブル、葉巻の箱とガラスの灰皿。壁際の本棚には、藁で編まれた人形が敷き詰めてある。オズ校長は、自ら奥の給湯スペースで紅茶を入れると、クッキーを添えて机に出してくれた。自分は向かいの椅子に座る。
「最初の講義は、私がする決まりなんだ」
オズ校長は葉巻を一本、手に取ると、マッチもライターも使わずに、指を鳴らして火をつけてみせた。思わず声をあげて驚くと、
「新入生は反応がよくていいな」
「反応が鈍くてすみません」
カミラが皮肉っぽく言って笑いを取った。
「今からするのは、魔術使いの基本の基、〈ラフマ〉と〈アート〉についての話だ」
オズ校長は葉巻をくゆらせて、白い煙で〝RAHMA〟〝ĀT〟と宙に書いた。
「万物のもとになったラフマの神話については、監督生のラルフ君から聞いてるかな。神はラフマをもとに太陽を創り、海を創り、大地を創った。実は私たちの身体にも、微量ながらラフマが含まれている。それが〈アート〉だ。魔術者たちは太古の昔から、精霊たちにこのアートを分け与えることで、自然法則に背く術を培ってきた」
オズ校長は宙に浮いた文字を吹き消して、新たに〝アートの精製〟と書き記した。
「十八世紀のまだ初頭、ある高名な魔術者が、泉に漂うラフマを自らのアートとして使う術を編み出した。それを皮切りに研究は進み、海や森、果ては大地や大気にいたるまで、あらゆる場所からアートを精製する術が開発されていった。その技術や思想は、今日の〈アベカ派〉の魔術者に継承されている。……ここまではいいかな?」
オズ校長は新たに〝第三の術〟と宙に書いた。
「それから二百有余年の長きにわたり、魔術を使う術はその二通りだけだった。つまり自前のアートを使うか、自然のラフマを取り込み、自らのアートとして使用するか。しかし二十世紀の末にある魔術者が、突如として第三の方法を編み出した。その魔術者こそが、誰あろう君のお父さんだ」
僕は驚いて言葉を失くした。
「君のお父さんはその〈第三の術〉を使い、四大霊剣をたった一人で集めてみせた。魔術界の歴史のなかで、誰もなしえなかった偉業だよ。しかし残念なことに、君のお父さんはその〈第三の術〉の詳細を誰にも明かさないまま、帰らぬ人となってしまった。君のお父さんが残した〈第三の術〉――今日その謎の追求をするのが、〈ニバル派〉と呼ばれる魔術者たちだ」
オズ校長は葉巻の火をもみ消すと、ちょっと難しかったかな、と言って笑った。
「まあ、心配しなくていい。今すべてを理解する必要はないよ。このあたりのことは、今後、あらゆる講義で耳にすることになるはずだ」
カミラが隣で頷いて、紅茶のカップに口をつける。僕とオズ校長も、つられたようにカップを持ちあげ、お皿のクッキーに手を伸ばした。
「まだ続けてもいいかな?」
オズ校長が首をかしげる。僕が頷くと、彼は再び話はじめた。
「では四大霊剣について話しておこう。今しがた私は、魔術を使う方法は長らく二通りだけだった、と話したが、実は一つだけ例外がある。それが四大霊剣を使う方法だ」
オズ校長が視線を落とす。僕もつられて、カミラの首飾りに目をやった。
「四大霊剣はもともと天使だった、という話は聞いたかな。天使たちは元来、ラフマから万物を創造する力を受けついでいたが、神の怒りに触れ、大幅に力を制限された形で地上に規定しなおされた。それが四大霊剣だ。ゆえにこの四つの霊剣は、それ自体が莫大なアートを有している。その力は、アベカ派の司祭クラスの魔術者、千人分とも言われている」
「千人分?」
思わず訊き返すと、オズ校長は神妙な顔で頷いた。
「もっとも数的に計れるものではないがね。霊剣にはそれぞれ固有の能力があり、扱う魔術者によって引き出される力も大幅に異なる。四本の剣すべてに名前があり、発見された順にグングニル、フラガハラ、エクスカリバー、パラストラとなる。霊剣の能力についてはレジメにまとめてあるから、一度、寮で読んでみるといい」
オズ校長はマジックのように、耳の穴から丸めた紙を出すと、広げて僕に渡してくれた。カミラがうんざりした表情で、きちゃない、きちゃない、と苦笑いする。そのときちょうど鐘の音が鳴って、僕らは部屋をあとにすることになった。
五分ほどしてようやく、跳ね橋のところまで来ることができた。深い堀には水が溜まっていて、お城のような講義棟が逆さまに映っていた。
アーチ状の入口からなかへ入ると、広いロビーに大きな二股階段が見えた。放射状に埋め込まれた敷石、星座図の描かれた吹き抜けの天井。暖炉の談話スペースには、色あせた地球儀や、すすけた甲冑が並んでいる。僕はカミラに案内されて、中央の階段をのぼっていった。最上階のいちばん奥で、カミラはふいと立ち止まった。
「ここが大司教室だよ」
「大司教?」
「ここは大学なんだけど、同時にアベカ派の教会でもあるの」
カミラは少し緊張した面持ちで扉を叩いた。
はい、と年老いた男性の声が聞こえて、そのすぐ後に扉が開いた。
「待っていましたよ。君がエド・ホード君か。若いころのお父さんにそっくりだ」
出てきたのは白髪の坊主のおじいさんだった。大柄で、たぶん身長は一八〇センチ以上ある。グレーのスーツ姿で、左耳には銀のリングが光っていた。
「私の名はオズ。この大学の校長をしています。遠い昔、君のお父さんは私のゼミ生でした」
オズ校長は手を出して、僕に握手を促した。両手で握り返すと、千年も前からある木に触ったような、静かで不思議な感じがした。
「お父さんの眼だね」
オズ校長は僕の顔を覗き込んで言った。
「父さんはどんな学生でしたか?」
と尋ねると、
「暗い子だったなあ」
顔をくしゃくしゃにして高笑いした。カミラも隣でくすくす笑って、後ろ手に僕の背中を叩いてきた。
「冗談だよ。たしかに暗かったが、それも君のお母さんに出会うまでだ」
「母さんのことも知ってるんですか?」
「まあ入ってくれ。贈答用の紅茶が山ほどあるんだ」
僕はカミラと一緒に部屋に入って、三人掛けの革張りのソファに座った。灰色の絨毯に、ローテーブル、葉巻の箱とガラスの灰皿。壁際の本棚には、藁で編まれた人形が敷き詰めてある。オズ校長は、自ら奥の給湯スペースで紅茶を入れると、クッキーを添えて机に出してくれた。自分は向かいの椅子に座る。
「最初の講義は、私がする決まりなんだ」
オズ校長は葉巻を一本、手に取ると、マッチもライターも使わずに、指を鳴らして火をつけてみせた。思わず声をあげて驚くと、
「新入生は反応がよくていいな」
「反応が鈍くてすみません」
カミラが皮肉っぽく言って笑いを取った。
「今からするのは、魔術使いの基本の基、〈ラフマ〉と〈アート〉についての話だ」
オズ校長は葉巻をくゆらせて、白い煙で〝RAHMA〟〝ĀT〟と宙に書いた。
「万物のもとになったラフマの神話については、監督生のラルフ君から聞いてるかな。神はラフマをもとに太陽を創り、海を創り、大地を創った。実は私たちの身体にも、微量ながらラフマが含まれている。それが〈アート〉だ。魔術者たちは太古の昔から、精霊たちにこのアートを分け与えることで、自然法則に背く術を培ってきた」
オズ校長は宙に浮いた文字を吹き消して、新たに〝アートの精製〟と書き記した。
「十八世紀のまだ初頭、ある高名な魔術者が、泉に漂うラフマを自らのアートとして使う術を編み出した。それを皮切りに研究は進み、海や森、果ては大地や大気にいたるまで、あらゆる場所からアートを精製する術が開発されていった。その技術や思想は、今日の〈アベカ派〉の魔術者に継承されている。……ここまではいいかな?」
オズ校長は新たに〝第三の術〟と宙に書いた。
「それから二百有余年の長きにわたり、魔術を使う術はその二通りだけだった。つまり自前のアートを使うか、自然のラフマを取り込み、自らのアートとして使用するか。しかし二十世紀の末にある魔術者が、突如として第三の方法を編み出した。その魔術者こそが、誰あろう君のお父さんだ」
僕は驚いて言葉を失くした。
「君のお父さんはその〈第三の術〉を使い、四大霊剣をたった一人で集めてみせた。魔術界の歴史のなかで、誰もなしえなかった偉業だよ。しかし残念なことに、君のお父さんはその〈第三の術〉の詳細を誰にも明かさないまま、帰らぬ人となってしまった。君のお父さんが残した〈第三の術〉――今日その謎の追求をするのが、〈ニバル派〉と呼ばれる魔術者たちだ」
オズ校長は葉巻の火をもみ消すと、ちょっと難しかったかな、と言って笑った。
「まあ、心配しなくていい。今すべてを理解する必要はないよ。このあたりのことは、今後、あらゆる講義で耳にすることになるはずだ」
カミラが隣で頷いて、紅茶のカップに口をつける。僕とオズ校長も、つられたようにカップを持ちあげ、お皿のクッキーに手を伸ばした。
「まだ続けてもいいかな?」
オズ校長が首をかしげる。僕が頷くと、彼は再び話はじめた。
「では四大霊剣について話しておこう。今しがた私は、魔術を使う方法は長らく二通りだけだった、と話したが、実は一つだけ例外がある。それが四大霊剣を使う方法だ」
オズ校長が視線を落とす。僕もつられて、カミラの首飾りに目をやった。
「四大霊剣はもともと天使だった、という話は聞いたかな。天使たちは元来、ラフマから万物を創造する力を受けついでいたが、神の怒りに触れ、大幅に力を制限された形で地上に規定しなおされた。それが四大霊剣だ。ゆえにこの四つの霊剣は、それ自体が莫大なアートを有している。その力は、アベカ派の司祭クラスの魔術者、千人分とも言われている」
「千人分?」
思わず訊き返すと、オズ校長は神妙な顔で頷いた。
「もっとも数的に計れるものではないがね。霊剣にはそれぞれ固有の能力があり、扱う魔術者によって引き出される力も大幅に異なる。四本の剣すべてに名前があり、発見された順にグングニル、フラガハラ、エクスカリバー、パラストラとなる。霊剣の能力についてはレジメにまとめてあるから、一度、寮で読んでみるといい」
オズ校長はマジックのように、耳の穴から丸めた紙を出すと、広げて僕に渡してくれた。カミラがうんざりした表情で、きちゃない、きちゃない、と苦笑いする。そのときちょうど鐘の音が鳴って、僕らは部屋をあとにすることになった。
0
あなたにおすすめの小説

異世界帰りの勇者、今度は現代世界でスキル、魔法を使って、無双するスローライフを送ります!?〜ついでに世界も救います!?〜
沢田美
ファンタジー
かつて“異世界”で魔王を討伐し、八年にわたる冒険を終えた青年・ユキヒロ。
数々の死線を乗り越え、勇者として讃えられた彼が帰ってきたのは、元の日本――高校卒業すらしていない、現実世界だった。
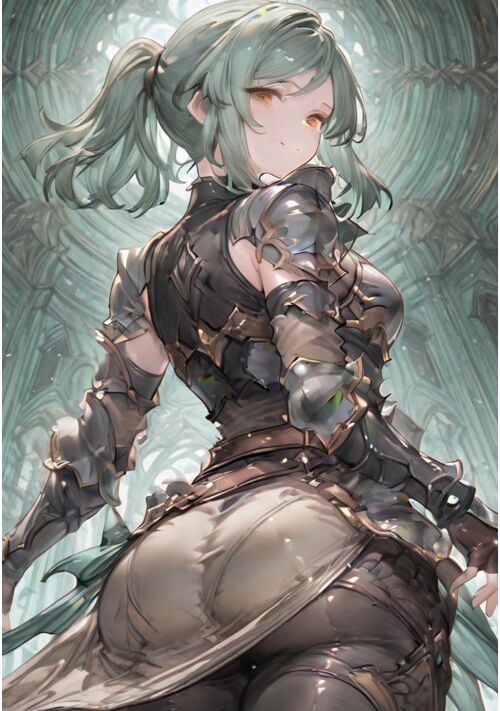
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

氷の精霊と忘れられた王国 〜追放された青年、消えた約束を探して〜
fuwamofu
ファンタジー
かつて「英雄」と讃えられた青年アレンは、仲間の裏切りによって王国を追放された。
雪原の果てで出会ったのは、心を閉ざした氷の精霊・リィナ。
絶望の底で交わした契約が、やがて滅びかけた王国の運命を変えていく――。
氷と炎、愛と憎しみ、真実と嘘が交錯する異世界再生ファンタジー。
彼はなぜ忘れられ、なぜ再び立ち上がるのか。
世界の記憶が凍りつく時、ひとつの約束だけが、彼らを導く。

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。


第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

転生社畜、転生先でも社畜ジョブ「書記」でブラック労働し、20年。前人未到のジョブレベルカンストからの大覚醒成り上がり!
nineyu
ファンタジー
男は絶望していた。
使い潰され、いびられ、社畜生活に疲れ、気がつけば死に場所を求めて樹海を歩いていた。
しかし、樹海の先は異世界で、転生の影響か体も若返っていた!
リスタートと思い、自由に暮らしたいと思うも、手に入れていたスキルは前世の影響らしく、気がつけば変わらない社畜生活に、、
そんな不幸な男の転機はそこから20年。
累計四十年の社畜ジョブが、遂に覚醒する!!

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜
KeyBow
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞
ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。
諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。
そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。
捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。
腕には、守るべきメイドの少女。
眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。
―――それは、ただの不運な落下のはずだった。
崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。
その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。
死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。
だが、その力の代償は、あまりにも大きい。
彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――
つまり平和で自堕落な生活そのものだった。
これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、
守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、
いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。
―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















