3 / 9
風船
しおりを挟む
さらに二、三分すると、風船は普通に話ができるところまで近ずいていました。
シャボン玉は風船というのは自分と同じようなシャボン玉の仲間なのだろうと思ったのですが、近くで見るとどうも違うようでした。シャボン玉よりも大分大きいし、形も完全な球ではなくて楕円状です。その上、下側に紐が一本ついているのもどうしてなのかよく分かりません。
お互いを、不思議に思う想いは風船も同じだったようで、
「君はずいぶん小さいんだね」と見た感想を漏らします。
「シャボン玉だから当たり前だよ」
「シャボン玉って? 」
シャボン玉は風船に、シャボン玉が何なのかを説明しなければなりませんでした。シャボン玉にもくわしいところはよく分かっていなかったのですが、がんばって分かる範囲で話をします。
風船は何とか納得してくれたようでした。
「すると君の体はゴムじゃあなくてシャボンの水で出来ているんだね。体の中には人間の女の子の息が入っているのか。いいなあ。ぼくの体に詰まっているのは化学合成した変てこな気体だけなんだもの」
そう言われたシャボン玉は、ちょっと誇らしい気持ちがしてきました。今まで考えたことも無かったのですが、マユミちゃんはとても可愛らしかったので、その息も大事なもののように思えてきます。
「君の体の中に入っているのは空気じゃないの? 」
聞いてみると、風船は困ったように、
「スイソとかヘリウムとか言う軽い気体らしいけどさ。難しくてよくわかんないよ。ぼくは動物園で人間の子供に配られる風船だったんだ。お父さんに連れられた男の子に渡されたんだよ。その子はソフトクリームをなめながら動物を見て歩いていたんだけど、本物の象があんまり大きいのにびっくりしてぼくをつなぎ留めていた紐を放しちゃったんだ。ぼくは宙に放たれて、そのまま果てしなく空へ昇ってきたという訳さ」
シャボン玉には風船の話がよく飲み込めないところがありました。いろいろ聞きたいところはあったのですが、とりあえずこんな言葉が口をついて出ます。
「・・・・・・象ってそんなに大きいの? 」
「大きいよ。ぼくの体の千倍もあるんだぜ」
「えええっ!! 」シャボン玉は目を丸くしました。人間以上に大きな生き物が、この世にいるとは思わなかったのです。「そんなに大きくて、その生き物は空を飛べるのかい」
「飛べるはずがないじゃないか。空を飛べる動物は鳥だけなんだぜ」
「ええっ!! 」
これはシャボン玉にとってはちょっとした驚きでした。生き物というのはみんな空を飛べるものかと思っていたのです。地面に立っている人間も、ただ休んでいるだけで本当は飛べるのだろうと考えていたのです。
人間が空を飛べないのだとすると、シャボン玉は自分を作ってくれたマユミちゃんにも、もう会うことはできないのでしょうか。シャボン玉は、マユミちゃんにちゃんと挨拶してお礼を言っておけばよかったと後悔しました。
「ぼくは動物園にいたので動物のことはよく分かっているよ」
「君は物知りなんだなあ」
「そんなこともないけどね・・・・・・」
風船は謙遜しながらも、ちょっと誇らし気でした。
二人はその後も仲良く話をしました。
シャボン玉は初めて本当の友達ができた気がしました。タカは親切にしてくれたのですが大分歳は上の感じでしたし、タカとシャボン玉では立場が違いすぎます。同じような立場でなければ、なかなか本当のお友達にはなれないのでした。
でもその友達とも、別れなければいけない時が近ずいてきます。
気流に押し上げられているだけのシャボン玉より体の中に軽い気体が入っている風船の方が上昇するスピードは早いので、風船がシャボン玉の上へ行って距離が離れ始めたのです。
「もうすぐお別れだね」
風船は寂しそうに言いました。
「うん。もっと長くいっしょに居たかったんだけど」
「しかたないさ・・・・・・。ところで一つ聞きたかったんだけど」
「何だい」
「ぼくは・・・・・・少し変じゃないかな。いや、見た目がさ。最初見た時より大きくなったとか、そんなことは無いかい? 」
シャボン玉は風船が何を言っているのか分かりませんでした。
「変わらないと思うけど・・・・・・」
そうは言ったものの、シャボン玉にも自信はありませんでした。空には比べるものが無いですし、距離も近ずいたり離れたりしたので大きさを計りにくいところがあったのです。シャボン玉は自分の体とくらべてみて、風船の大きさは変わっていないと判断しました。
「それなら・・・・・・いいけどさ」
そう言いながらも、風船はとても不安そうです。
「どうしてそんなことを聞くの? 」
「うん。・・・・・・実はぼくはすごく怖いことを聞いたんだ。ぼくの紐を持っていた男の子がお父さんに聞いていたんだけど。その子は「風船を空に放しちゃったらどうなるの? 」ってお父さんに聞いたんだ。何でも「どうなるの? どうなるの? 」って聞くのが口癖の子だったんだよね。そうしたらお父さんはこう答えたんだ。「ずっと空に昇って行くよ。だけどすごく上まで行くと空気が薄くなるので風船はどんどん膨らんで行って、最後には割れてしまうだろうな」って」
これはシャボン玉にとっても怖い話でした。風船が膨らんで割れてしまうのなら、シャボン玉も高い空へ行ったらそうなってしまうのではないでしょうか。
「そっ、そんな恐いことが」
「あるらしいんだよう・・・・・・」
風船は泣きそうな顔をしていました。その声はすごく暗くて、タカが「世界は真っ暗になってしまうんだよ」と言った時よりももっと怪談話をするような調子に近かったのですが、シャボン玉は風船の言うことを疑ったりはしませんでした。風船君は自分と同じくまだ子供なので、わざと嘘を言ってからかったりはしないだろうと思ったのです。
でもそうすると風船君は間もなく膨らんで割れてしまうことになります。シャボン玉もそうなるかもしれません。そうは思いたくありません。
「そっ、そんなことは無いよ。そのお父さんは嘘を言ったのさ。だってこんな高さまで来ても君は体が大きくなってきてはいないじゃないか」
シャボン玉はそう言いましたが、すぐにそうではないのかもしれないと気づきました。シャボン玉が風船の体が大きくなってきてはいないと判断したのは自分の体とくらべてのことなので、シャボン玉も同時に大きくなっていたとしたら風船が大きくなっても気づかないということになります。
まさか、僕らは二人とも、体が膨らんできているんじゃあないだろうな。そしてもうすぐ破裂してしまうんじゃあ・・・・・・。
シャボン玉は、不吉な思いを打ち消せませんでした。
でも風船はそれに気がつかないようで、
「そうだよね。体がどんどん膨らむなんて、そんなこと、ある訳ないよね」
「そうさ」
「うん。元気が出てきたよ。・・・・・・さようなら。君と出会えて良かったよ」
風船はもう話をするのが難しいほどシャボン玉から離れてしまっていました。シャボン玉もがんばって「さようならー。元気でねー」と大きな声で答えたのですが、風船に届いたかどうかは分かりません。
赤い風船の姿はどんどん小さくなって、空に浮かぶ点になっていきました。
そのすぐ上にはもくもくした真っ白な雲が、驚くほど巨大に広く広く拡がっています。いつの間にか風船は、雲のすぐ近くまで達っしていたのでした。
じっと見ていると、赤い点になった風船は、雲の白色に滲むようにして消えてしまいました。雲の中に入ってしまったのでしょうか。
雲の中に入ったのだとしたら、その中はいったいどうなっているのでしょう。想像もできません。シャボン玉は風船の無事を祈りました。
シャボン玉はふうっと息をつく思いで、あらためて下を見降ろしました。
シャボン玉はもう北側の高くて険しい山脈よりも高いところへ来ていました。なので、その山並みの向こう側が見通せます。ところがその後ろはやっぱり山で、同じような山々がずっと先まで続いていたのです。その間には平地もあるようなのですが、圧倒的に山の方が多かったのでした。
一方、その反対側の、南の低い山の向こうは、さらに広々と見渡せるようになっていました。先ほどは青い線のようのようだった海は、奥行きのある海原に変わっていました。海の方には太陽が出ているのか、海面は明るく照らされており、陽光を反射してキラキラと輝いていました。その輝きはひしめくように動いています。波があるので当たり前ですが、シャボン玉はその時海面は動いているらしいと初めて気づいたのです。シャボン玉のいるところはやや薄暗く曇りがちなので、それはなおさらくっきりと美しく見えました。ですが、シャボン玉にはそれが、怖いようにも思えました。どこまでも果てしなく続き、波うち続ける水面には、現実感を奪ってしまう力があるような気がしたのです。あの巨大なものが動いているというだけでも、シャボン玉にはまったく理由の分からない想像を絶することなのでした。
めまいがしたシャボン玉は真下を見おろしました。ですが、下の街並みもそれまでとは大分違って見えました。遠くなりすぎて細かいところが見分けにくくなってしまっていたのです。建物の多い所と田んぼや畑の多い所は分かるのですが、建物の一つ一つは見分けられるかどうかあやしいものでした。大きなビルは分かっても、小さな家はもう分からないのです。高圧電線の鉄塔も、地面からツンと生えた棘のようにしか感じられません。
町中の木々は滲んだような緑の集まりで、道も、はっきりしているのは広いバイパス道くらいでした。そこを走る車もよく分からないのです。少し前にはその上には、一列になって葉っぱの上を歩くテントウムシのようにノロノロ移動する車が見えたものですが、もう小っちゃいアリンコほどにも見てとれません。
マユミちゃんがシャボン玉を吹いてくれた家も、もうどのへんにあるのか見当がつきませんでした。
ずいぶん高いところまで来てしまったものです。
それでもシャボン玉は、まだ自分を下から押し上げる空気の動きを感じ続けていました。どうやらシャボン玉も、雲に近ずきつつあるようでした。
その頃からでしょうか。シャボン玉は何だか肌にヒリヒリする感触を感じ始めていました。紙やすりのようなもので擦られて、肌が薄くなっていくような感じ、とでも言ったらいいでしょうか。わずかな空気の動きにも敏感になり、人間が服を脱いで裸になった時のような感覚がしたのです。
それに、気温も下がってきました。上へ行くほどに寒くなる一方なので、シャボン玉は体が震えてきました。
ただでさえ肌が敏感になっているところなのに、これじゃあ体の芯まで冷えてしまってどうにかなっちゃうんじゃないか。
シャボン玉がそう思ったのも無理はありません。実はその時には、シャボン玉がいる高さの気温は十五度を下回っていたのです。地上は暑くて三十度くらいでしたから、夏から一気に秋の終わりになってしまったようなものです。山の上に昇るほど気温が下がるのと同じ理屈で、空の上も高さが増すほどどんどん寒くなっていくのです。
今はまだ寒いくらいですんでいますが、もっと高度が上がり、もしも冷蔵庫なみの温度になったらどうなるのでしょう。もしも気温が零度を下回るようなことがあったら、体が凍ってしまう恐れさえあります。そうなったら体がカチンコチンになって、肌に裂けめができてしまいます。とても旅を続けることはできないでしょう。
ですがそれよりも、シャボン玉にはもっと差し迫った危機がありました。
肌がヒリヒリするのは、恐ろしい危険の兆候なのでした。
シャボン玉の体は、回りの空気が薄くなった関係で、膨らんできていたのです。自分では気づいていなかったのですが、最初はピンポン玉よりちょっと大きいくらいだったシャボン玉の体は、この時にはテニスボールくらいの大きさになってしまっていたのでした。体が大きくなったから、大きくなった分、肌が引き伸ばされて薄くなってしまっていたのです。その上、空を旅するうちに、わずかながら水分が蒸発して、体を作っている水の量が減っていたということもありました。
「ふうっ、何だか体が突っ張るなあ。寒くなってきたからかなあ・・・・・・」
絶対絶命だとも知らず、シャボン玉はつぶやきました。
シャボン玉の肌はパンパンでした。人間だったら食べ過ぎてもう動けないという感覚に近かったでしょうか。シャボン玉は自分を押し上げてくる空気の動きがうっとうしく感じられるようになってきました。太った人があまり動きたくないように、どこへも行かずに止まっていたかったのでした。
でも上昇気流はまだ続いています。
シャボン玉はそのうちに、何だか肌が痒くなってきました。もし手があったなら体の表面を掻きたかったのですが、そうもいかずにもどかしい思いをします。
カラスにつつかれた時に変なばい菌でももらったのかなあ・・・・・・。
シャボン玉はのんきに考えました。でもまもなく痒みが強まってきて痛みに変わると、さしものシャボン玉もこれはただ事ではないと気づきました。
僕の体がおかしくなってる。肌が痛くてこのままじゃあ裂けてしまいそうだ。ひょっとしたら、風船君が言っていたように、体が膨らんできているんじゃないだろうか。
そう分かった時にはシャボン玉の体はソフトボール大にまで膨らんでいたのです。まさに破裂寸前で、ここまで膨らんでもまだ割れないでいたのは驚きでした。
大変だ。体が膨らまないようにこれ以上高いところへは行かないようにしなくっちゃあ。
シャボン玉はそう思って必死になりましたが、シャボン玉の哀しさで、風や空気に運ばれる他は、移動のしようもないのでした。どんなにジタバタしても駄目なのです。シャボン玉はさらにふわふわと、少しづつ少しづつ上へと運ばれて行きます。
シャボン玉はどうしようもないのが分かると、せめてもの抵抗で、ギュッと体に力を入れて、割れないようにと踏ん張りました。
せっかくここまで旅をしてきたんだ。割れる訳にはいかない。僕は早く消えてしまった兄弟たちの分までも、この広い世界を見なければいけない。シャボン玉は、それが自分に課せられた使命のように思えてきました。奇跡的にここまで割れずに来れたのは、大空を見られなかった他のシャボン玉たちの想いが自分の後を押してくれたからではないかという気がしたのです。
もしそうなら、どんなに苦しくとも頑張らなくてはならないというものでした。シャボン玉は必死に踏ん張り続けます。
シャボン玉のはるかかなた上の空で、パーンと何かが弾ける音がしたのはそんな時でした。
シャボン玉はこの音をはっきりとは聞き取ることができなかったのですが、ふっと冷たい風が自分のそばを通り過ぎるのを感じたような気がしました。
そして、シャボン玉はそんな状態のままで、ついに雲のすぐ真下にまで来てしまったのです。
シャボン玉は風船というのは自分と同じようなシャボン玉の仲間なのだろうと思ったのですが、近くで見るとどうも違うようでした。シャボン玉よりも大分大きいし、形も完全な球ではなくて楕円状です。その上、下側に紐が一本ついているのもどうしてなのかよく分かりません。
お互いを、不思議に思う想いは風船も同じだったようで、
「君はずいぶん小さいんだね」と見た感想を漏らします。
「シャボン玉だから当たり前だよ」
「シャボン玉って? 」
シャボン玉は風船に、シャボン玉が何なのかを説明しなければなりませんでした。シャボン玉にもくわしいところはよく分かっていなかったのですが、がんばって分かる範囲で話をします。
風船は何とか納得してくれたようでした。
「すると君の体はゴムじゃあなくてシャボンの水で出来ているんだね。体の中には人間の女の子の息が入っているのか。いいなあ。ぼくの体に詰まっているのは化学合成した変てこな気体だけなんだもの」
そう言われたシャボン玉は、ちょっと誇らしい気持ちがしてきました。今まで考えたことも無かったのですが、マユミちゃんはとても可愛らしかったので、その息も大事なもののように思えてきます。
「君の体の中に入っているのは空気じゃないの? 」
聞いてみると、風船は困ったように、
「スイソとかヘリウムとか言う軽い気体らしいけどさ。難しくてよくわかんないよ。ぼくは動物園で人間の子供に配られる風船だったんだ。お父さんに連れられた男の子に渡されたんだよ。その子はソフトクリームをなめながら動物を見て歩いていたんだけど、本物の象があんまり大きいのにびっくりしてぼくをつなぎ留めていた紐を放しちゃったんだ。ぼくは宙に放たれて、そのまま果てしなく空へ昇ってきたという訳さ」
シャボン玉には風船の話がよく飲み込めないところがありました。いろいろ聞きたいところはあったのですが、とりあえずこんな言葉が口をついて出ます。
「・・・・・・象ってそんなに大きいの? 」
「大きいよ。ぼくの体の千倍もあるんだぜ」
「えええっ!! 」シャボン玉は目を丸くしました。人間以上に大きな生き物が、この世にいるとは思わなかったのです。「そんなに大きくて、その生き物は空を飛べるのかい」
「飛べるはずがないじゃないか。空を飛べる動物は鳥だけなんだぜ」
「ええっ!! 」
これはシャボン玉にとってはちょっとした驚きでした。生き物というのはみんな空を飛べるものかと思っていたのです。地面に立っている人間も、ただ休んでいるだけで本当は飛べるのだろうと考えていたのです。
人間が空を飛べないのだとすると、シャボン玉は自分を作ってくれたマユミちゃんにも、もう会うことはできないのでしょうか。シャボン玉は、マユミちゃんにちゃんと挨拶してお礼を言っておけばよかったと後悔しました。
「ぼくは動物園にいたので動物のことはよく分かっているよ」
「君は物知りなんだなあ」
「そんなこともないけどね・・・・・・」
風船は謙遜しながらも、ちょっと誇らし気でした。
二人はその後も仲良く話をしました。
シャボン玉は初めて本当の友達ができた気がしました。タカは親切にしてくれたのですが大分歳は上の感じでしたし、タカとシャボン玉では立場が違いすぎます。同じような立場でなければ、なかなか本当のお友達にはなれないのでした。
でもその友達とも、別れなければいけない時が近ずいてきます。
気流に押し上げられているだけのシャボン玉より体の中に軽い気体が入っている風船の方が上昇するスピードは早いので、風船がシャボン玉の上へ行って距離が離れ始めたのです。
「もうすぐお別れだね」
風船は寂しそうに言いました。
「うん。もっと長くいっしょに居たかったんだけど」
「しかたないさ・・・・・・。ところで一つ聞きたかったんだけど」
「何だい」
「ぼくは・・・・・・少し変じゃないかな。いや、見た目がさ。最初見た時より大きくなったとか、そんなことは無いかい? 」
シャボン玉は風船が何を言っているのか分かりませんでした。
「変わらないと思うけど・・・・・・」
そうは言ったものの、シャボン玉にも自信はありませんでした。空には比べるものが無いですし、距離も近ずいたり離れたりしたので大きさを計りにくいところがあったのです。シャボン玉は自分の体とくらべてみて、風船の大きさは変わっていないと判断しました。
「それなら・・・・・・いいけどさ」
そう言いながらも、風船はとても不安そうです。
「どうしてそんなことを聞くの? 」
「うん。・・・・・・実はぼくはすごく怖いことを聞いたんだ。ぼくの紐を持っていた男の子がお父さんに聞いていたんだけど。その子は「風船を空に放しちゃったらどうなるの? 」ってお父さんに聞いたんだ。何でも「どうなるの? どうなるの? 」って聞くのが口癖の子だったんだよね。そうしたらお父さんはこう答えたんだ。「ずっと空に昇って行くよ。だけどすごく上まで行くと空気が薄くなるので風船はどんどん膨らんで行って、最後には割れてしまうだろうな」って」
これはシャボン玉にとっても怖い話でした。風船が膨らんで割れてしまうのなら、シャボン玉も高い空へ行ったらそうなってしまうのではないでしょうか。
「そっ、そんな恐いことが」
「あるらしいんだよう・・・・・・」
風船は泣きそうな顔をしていました。その声はすごく暗くて、タカが「世界は真っ暗になってしまうんだよ」と言った時よりももっと怪談話をするような調子に近かったのですが、シャボン玉は風船の言うことを疑ったりはしませんでした。風船君は自分と同じくまだ子供なので、わざと嘘を言ってからかったりはしないだろうと思ったのです。
でもそうすると風船君は間もなく膨らんで割れてしまうことになります。シャボン玉もそうなるかもしれません。そうは思いたくありません。
「そっ、そんなことは無いよ。そのお父さんは嘘を言ったのさ。だってこんな高さまで来ても君は体が大きくなってきてはいないじゃないか」
シャボン玉はそう言いましたが、すぐにそうではないのかもしれないと気づきました。シャボン玉が風船の体が大きくなってきてはいないと判断したのは自分の体とくらべてのことなので、シャボン玉も同時に大きくなっていたとしたら風船が大きくなっても気づかないということになります。
まさか、僕らは二人とも、体が膨らんできているんじゃあないだろうな。そしてもうすぐ破裂してしまうんじゃあ・・・・・・。
シャボン玉は、不吉な思いを打ち消せませんでした。
でも風船はそれに気がつかないようで、
「そうだよね。体がどんどん膨らむなんて、そんなこと、ある訳ないよね」
「そうさ」
「うん。元気が出てきたよ。・・・・・・さようなら。君と出会えて良かったよ」
風船はもう話をするのが難しいほどシャボン玉から離れてしまっていました。シャボン玉もがんばって「さようならー。元気でねー」と大きな声で答えたのですが、風船に届いたかどうかは分かりません。
赤い風船の姿はどんどん小さくなって、空に浮かぶ点になっていきました。
そのすぐ上にはもくもくした真っ白な雲が、驚くほど巨大に広く広く拡がっています。いつの間にか風船は、雲のすぐ近くまで達っしていたのでした。
じっと見ていると、赤い点になった風船は、雲の白色に滲むようにして消えてしまいました。雲の中に入ってしまったのでしょうか。
雲の中に入ったのだとしたら、その中はいったいどうなっているのでしょう。想像もできません。シャボン玉は風船の無事を祈りました。
シャボン玉はふうっと息をつく思いで、あらためて下を見降ろしました。
シャボン玉はもう北側の高くて険しい山脈よりも高いところへ来ていました。なので、その山並みの向こう側が見通せます。ところがその後ろはやっぱり山で、同じような山々がずっと先まで続いていたのです。その間には平地もあるようなのですが、圧倒的に山の方が多かったのでした。
一方、その反対側の、南の低い山の向こうは、さらに広々と見渡せるようになっていました。先ほどは青い線のようのようだった海は、奥行きのある海原に変わっていました。海の方には太陽が出ているのか、海面は明るく照らされており、陽光を反射してキラキラと輝いていました。その輝きはひしめくように動いています。波があるので当たり前ですが、シャボン玉はその時海面は動いているらしいと初めて気づいたのです。シャボン玉のいるところはやや薄暗く曇りがちなので、それはなおさらくっきりと美しく見えました。ですが、シャボン玉にはそれが、怖いようにも思えました。どこまでも果てしなく続き、波うち続ける水面には、現実感を奪ってしまう力があるような気がしたのです。あの巨大なものが動いているというだけでも、シャボン玉にはまったく理由の分からない想像を絶することなのでした。
めまいがしたシャボン玉は真下を見おろしました。ですが、下の街並みもそれまでとは大分違って見えました。遠くなりすぎて細かいところが見分けにくくなってしまっていたのです。建物の多い所と田んぼや畑の多い所は分かるのですが、建物の一つ一つは見分けられるかどうかあやしいものでした。大きなビルは分かっても、小さな家はもう分からないのです。高圧電線の鉄塔も、地面からツンと生えた棘のようにしか感じられません。
町中の木々は滲んだような緑の集まりで、道も、はっきりしているのは広いバイパス道くらいでした。そこを走る車もよく分からないのです。少し前にはその上には、一列になって葉っぱの上を歩くテントウムシのようにノロノロ移動する車が見えたものですが、もう小っちゃいアリンコほどにも見てとれません。
マユミちゃんがシャボン玉を吹いてくれた家も、もうどのへんにあるのか見当がつきませんでした。
ずいぶん高いところまで来てしまったものです。
それでもシャボン玉は、まだ自分を下から押し上げる空気の動きを感じ続けていました。どうやらシャボン玉も、雲に近ずきつつあるようでした。
その頃からでしょうか。シャボン玉は何だか肌にヒリヒリする感触を感じ始めていました。紙やすりのようなもので擦られて、肌が薄くなっていくような感じ、とでも言ったらいいでしょうか。わずかな空気の動きにも敏感になり、人間が服を脱いで裸になった時のような感覚がしたのです。
それに、気温も下がってきました。上へ行くほどに寒くなる一方なので、シャボン玉は体が震えてきました。
ただでさえ肌が敏感になっているところなのに、これじゃあ体の芯まで冷えてしまってどうにかなっちゃうんじゃないか。
シャボン玉がそう思ったのも無理はありません。実はその時には、シャボン玉がいる高さの気温は十五度を下回っていたのです。地上は暑くて三十度くらいでしたから、夏から一気に秋の終わりになってしまったようなものです。山の上に昇るほど気温が下がるのと同じ理屈で、空の上も高さが増すほどどんどん寒くなっていくのです。
今はまだ寒いくらいですんでいますが、もっと高度が上がり、もしも冷蔵庫なみの温度になったらどうなるのでしょう。もしも気温が零度を下回るようなことがあったら、体が凍ってしまう恐れさえあります。そうなったら体がカチンコチンになって、肌に裂けめができてしまいます。とても旅を続けることはできないでしょう。
ですがそれよりも、シャボン玉にはもっと差し迫った危機がありました。
肌がヒリヒリするのは、恐ろしい危険の兆候なのでした。
シャボン玉の体は、回りの空気が薄くなった関係で、膨らんできていたのです。自分では気づいていなかったのですが、最初はピンポン玉よりちょっと大きいくらいだったシャボン玉の体は、この時にはテニスボールくらいの大きさになってしまっていたのでした。体が大きくなったから、大きくなった分、肌が引き伸ばされて薄くなってしまっていたのです。その上、空を旅するうちに、わずかながら水分が蒸発して、体を作っている水の量が減っていたということもありました。
「ふうっ、何だか体が突っ張るなあ。寒くなってきたからかなあ・・・・・・」
絶対絶命だとも知らず、シャボン玉はつぶやきました。
シャボン玉の肌はパンパンでした。人間だったら食べ過ぎてもう動けないという感覚に近かったでしょうか。シャボン玉は自分を押し上げてくる空気の動きがうっとうしく感じられるようになってきました。太った人があまり動きたくないように、どこへも行かずに止まっていたかったのでした。
でも上昇気流はまだ続いています。
シャボン玉はそのうちに、何だか肌が痒くなってきました。もし手があったなら体の表面を掻きたかったのですが、そうもいかずにもどかしい思いをします。
カラスにつつかれた時に変なばい菌でももらったのかなあ・・・・・・。
シャボン玉はのんきに考えました。でもまもなく痒みが強まってきて痛みに変わると、さしものシャボン玉もこれはただ事ではないと気づきました。
僕の体がおかしくなってる。肌が痛くてこのままじゃあ裂けてしまいそうだ。ひょっとしたら、風船君が言っていたように、体が膨らんできているんじゃないだろうか。
そう分かった時にはシャボン玉の体はソフトボール大にまで膨らんでいたのです。まさに破裂寸前で、ここまで膨らんでもまだ割れないでいたのは驚きでした。
大変だ。体が膨らまないようにこれ以上高いところへは行かないようにしなくっちゃあ。
シャボン玉はそう思って必死になりましたが、シャボン玉の哀しさで、風や空気に運ばれる他は、移動のしようもないのでした。どんなにジタバタしても駄目なのです。シャボン玉はさらにふわふわと、少しづつ少しづつ上へと運ばれて行きます。
シャボン玉はどうしようもないのが分かると、せめてもの抵抗で、ギュッと体に力を入れて、割れないようにと踏ん張りました。
せっかくここまで旅をしてきたんだ。割れる訳にはいかない。僕は早く消えてしまった兄弟たちの分までも、この広い世界を見なければいけない。シャボン玉は、それが自分に課せられた使命のように思えてきました。奇跡的にここまで割れずに来れたのは、大空を見られなかった他のシャボン玉たちの想いが自分の後を押してくれたからではないかという気がしたのです。
もしそうなら、どんなに苦しくとも頑張らなくてはならないというものでした。シャボン玉は必死に踏ん張り続けます。
シャボン玉のはるかかなた上の空で、パーンと何かが弾ける音がしたのはそんな時でした。
シャボン玉はこの音をはっきりとは聞き取ることができなかったのですが、ふっと冷たい風が自分のそばを通り過ぎるのを感じたような気がしました。
そして、シャボン玉はそんな状態のままで、ついに雲のすぐ真下にまで来てしまったのです。
0
あなたにおすすめの小説

緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。

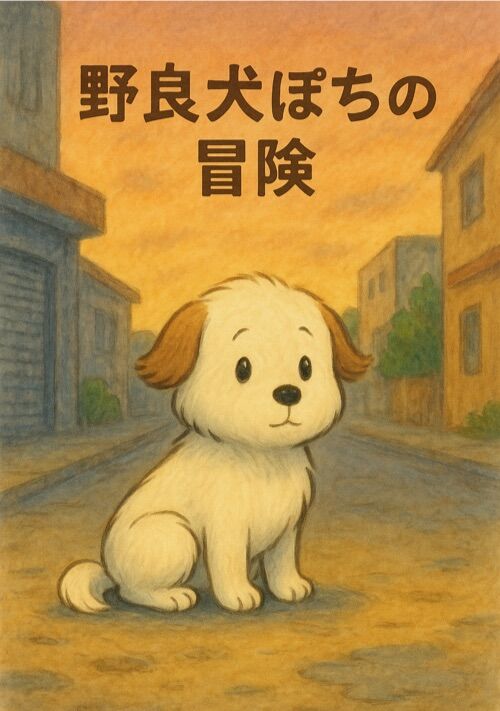
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

ナナの初めてのお料理
いぬぬっこ
児童書・童話
ナナは七歳の女の子。
ある日、ナナはお母さんが仕事から帰ってくるのを待っていました。
けれど、お母さんが帰ってくる前に、ナナのお腹はペコペコになってしまいました。
もう我慢できそうにありません。
だというのに、冷蔵庫の中には、すぐ食べれるものがありません。
ーーそうだ、お母さんのマネをして、自分で作ろう!
ナナは、初めて自分一人で料理をすることを決めたのでした。
これは、ある日のナナのお留守番の様子です。

【奨励賞】おとぎの店の白雪姫
ゆちば
児童書・童話
【第15回絵本・児童書大賞 奨励賞】
母親を亡くした小学生、白雪ましろは、おとぎ商店街でレストランを経営する叔父、白雪凛悟(りんごおじさん)に引き取られる。
ぎこちない二人の生活が始まるが、ひょんなことからりんごおじさんのお店――ファミリーレストラン《りんごの木》のお手伝いをすることになったましろ。パティシエ高校生、最速のパート主婦、そしてイケメンだけど料理脳のりんごおじさんと共に、一癖も二癖もあるお客さんをおもてなし!
そしてめくるめく日常の中で、ましろはりんごおじさんとの『家族』の形を見出していく――。
小さな白雪姫が『家族』のために奔走する、おいしいほっこり物語。はじまりはじまり!
他のサイトにも掲載しています。
表紙イラストは今市阿寒様です。
絵本児童書大賞で奨励賞をいただきました。

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394

少年イシュタと夜空の少女 ~死なずの村 エリュシラーナ~
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
イシュタは病の妹のため、誰も死なない村・エリュシラーナへと旅立つ。そして、夜空のような美しい少女・フェルルと出会い……
「昔話をしてあげるわ――」
フェルルの口から語られる、村に隠された秘密とは……?
☆…☆…☆
※ 大人でも楽しめる児童文学として書きました。明確な記述は避けておりますので、大人になって読み返してみると、また違った風に感じられる……そんな物語かもしれません……♪
※ イラストは、親友の朝美智晴さまに描いていただきました。

ふしぎなえんぴつ
八神真哉
児童書・童話
テストが返ってきた。40点だった。
お父さんに見つかったらげんこつだ。
ぼくは、神さまにお願いした。
おさいせんをふんぱつして、「100点取らせてください」と。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















