14 / 62
第14話 いろんな種類の危機
しおりを挟む
「おや。もう寒いのに、ジュースかい?」
「いいえ」
私は、目ざとく私を見つけた隣の商店主に答えた。
「今度は暖かいものを持ってきたの」
「ほお?」
おじさんは興味津々だった。
「これなの」
試供品として、私はドングリの入った袋を商店主のおじさんに提供した。
「あったかい! へえ。こりゃ、いいね!」
だが、ドングリの袋はあっという間に奥さんに取り上げられてしまった。
「いいじゃない! これ! 持ち運べるしさ!」
「そう長くはもちませんけど。何しろ中身はドングリなんで」
「ドングリ?」
「ドングリが少しずつ低温で燃えていくんです。火傷しないくらいの温度で」
そう言いながら、私は、果たして売れるかなと首を傾げた。
だって、私が住んでいる森の中は、もう雪が降っていたけれど、この街は、雪どころか暖かいのだ。私には暑いくらいだ。
「いや、もう、今日は寒くてたまらん!」
おじさんが身震いした。寒いですか?
「二つ売ってくれんかね? 背中と腹に付けるんだ」
「え? どうぞ」
そして、翌日にはドングリカイロは大評判になっていた。
昨日一日、不思議そうに、お試しで買い求めていった人たちが、知り合いを大勢連れて押し寄せてきたのだ。
私は接客で大わらわになった。
「大小あります。大きい方が長持ちしますよ?」
「じゃあ、大きい方を! うちの店員全員分、合わせて十個!」
後ろに並んでいた人から、抗議の声が上がった。
「ちょっと! そんなに大量に買われたら、列の後ろの人間は買えないじゃないか!」
「大丈夫です! 数は用意しましたから。でも、おひとり様二十個まででお願いします」
「あ、じゃあ、二十個頼むわ」
うわああ。
ちょっとだけ黄色いシャツの男がなつかしくなった。まあ、要らんけど。
ホットレモネードとホットジンジャーの方は、商店主の奥さんの方が売り子になってくれた。
だって、手が回らないのだもの。
こっちの飲み物の方は、どこでも売っているそうで、ドングリの順番待ちの間に売れる程度だったが、ジュースの時と同じで、二日、三日と経つうちに飲み物だけの客が増えてきた。
「体にいい」
そう言って、遠くからわざわざ買い求めに来る客も出て来た。
一週間ほど続けていたら、ドングリよりも、飲み物の客の方が多くなってきていた。
その場で飲むのではなく、ビンを持参して、大量に買い付けていく。
「あの人たち、転売しているんじゃないの?」
商店主の奥さんが耳元で囁いた。
私も不安になってきていた。買いつけていく連中の顔付きが不安だった。
あまりいい人相の人たちではなかった。
その上、みな、私の顔を見ていく。まるで顔を覚えようとしているかのようだ。
儲かりはしたが、私は予定より早く店じまいせざるを得なかった。
隣の商店主のおじさんは、長いこと商売をしているせいか、やっぱりしっかりしていた。
私の飲み物に並ぶ客たちの様子をちゃんと見ていた。
「女の子一人での商売は、危ない面もある。あんたを守ってくれる男衆は誰もいないのかね。兄とか弟とか。父親とか。恋人でもいいが」
「……いません」
「だったら、王都で誰かいい人を探しなよ。良さそうな男の客もいるよね。私の知っている商店の息子も毎日来ていた。大きな店の息子で、あれはあんたに気があるんだと思う」
まさか、あの黄色いシャツの男のことだろうか?
「違うよ。最近、来ている栗色の髪のおとなしそうな若い男だよ。仕事をしているので、毎日ではないけどね。来れる時は来ているらしい。うちのかみさんがそう言ってたよ。あれは縁結びが好きでね」
別な意味での危機が近付いている気がする。
「どうだね。まあ、お金は要るだろうけど、そのためにも腰を落ち着けて商売をする基盤も必要だろう」
「あんた、無茶いいなさんな。好きな男でもいたら、かわいそうだろ?」
おかみさんが割り込んだ。私の代わりに言ってくれているようだ。
「あれ? お前もワトソンさんならいいって言ってたじゃないか。いい人だって」
おかみさんは口ごもった。
「そりゃ、男前だし、人間は悪くないって、うわさだからね」
「まあ、ワトソンさんから頼まれたって言うのもあるんだよ。あんたは田舎から来たそうだから、知らないかも知れないけど、ワトソン商会っていう大商人の息子なんだ」
「でも、私……」
「好きな人がいるのかな? それなら何とか断っておくよ」
おかみさんはそう言ってくれたけど、商店主の方はこんなことを言った。
「目つきの悪い連中が、最近は混ざってきていることに気がついていたろ? 今のところ、ワトソンさんが抑えてくれているんだ。ワトソン商会の息子ににらまれたら厄介だからね」
ああ、なんてことだろう。
知らなかった。私、自分で自分を守ることもできないのか。
私は、伯母の言葉を思い出した。
『黙っておきましょうね。あなたの力を悪用しようとする者が現れたら困るから』
私の力は、多分強力なのだ。
強力すぎて危険なのだ。
ジュースどころではない。もし、本当の力、治癒の能力がバレたら……それこそ王家が乗り出してくる。
私がなぜ王家の婚約者だったのか。
それが答えだ。
まだ、バレていない。誰も何も知らない。
あの隠れ家は完璧だ。あそこに隠れていさえすれば、誰も手出しできない。
「私、とりあえず、店の方は閉めます」
「いいえ」
私は、目ざとく私を見つけた隣の商店主に答えた。
「今度は暖かいものを持ってきたの」
「ほお?」
おじさんは興味津々だった。
「これなの」
試供品として、私はドングリの入った袋を商店主のおじさんに提供した。
「あったかい! へえ。こりゃ、いいね!」
だが、ドングリの袋はあっという間に奥さんに取り上げられてしまった。
「いいじゃない! これ! 持ち運べるしさ!」
「そう長くはもちませんけど。何しろ中身はドングリなんで」
「ドングリ?」
「ドングリが少しずつ低温で燃えていくんです。火傷しないくらいの温度で」
そう言いながら、私は、果たして売れるかなと首を傾げた。
だって、私が住んでいる森の中は、もう雪が降っていたけれど、この街は、雪どころか暖かいのだ。私には暑いくらいだ。
「いや、もう、今日は寒くてたまらん!」
おじさんが身震いした。寒いですか?
「二つ売ってくれんかね? 背中と腹に付けるんだ」
「え? どうぞ」
そして、翌日にはドングリカイロは大評判になっていた。
昨日一日、不思議そうに、お試しで買い求めていった人たちが、知り合いを大勢連れて押し寄せてきたのだ。
私は接客で大わらわになった。
「大小あります。大きい方が長持ちしますよ?」
「じゃあ、大きい方を! うちの店員全員分、合わせて十個!」
後ろに並んでいた人から、抗議の声が上がった。
「ちょっと! そんなに大量に買われたら、列の後ろの人間は買えないじゃないか!」
「大丈夫です! 数は用意しましたから。でも、おひとり様二十個まででお願いします」
「あ、じゃあ、二十個頼むわ」
うわああ。
ちょっとだけ黄色いシャツの男がなつかしくなった。まあ、要らんけど。
ホットレモネードとホットジンジャーの方は、商店主の奥さんの方が売り子になってくれた。
だって、手が回らないのだもの。
こっちの飲み物の方は、どこでも売っているそうで、ドングリの順番待ちの間に売れる程度だったが、ジュースの時と同じで、二日、三日と経つうちに飲み物だけの客が増えてきた。
「体にいい」
そう言って、遠くからわざわざ買い求めに来る客も出て来た。
一週間ほど続けていたら、ドングリよりも、飲み物の客の方が多くなってきていた。
その場で飲むのではなく、ビンを持参して、大量に買い付けていく。
「あの人たち、転売しているんじゃないの?」
商店主の奥さんが耳元で囁いた。
私も不安になってきていた。買いつけていく連中の顔付きが不安だった。
あまりいい人相の人たちではなかった。
その上、みな、私の顔を見ていく。まるで顔を覚えようとしているかのようだ。
儲かりはしたが、私は予定より早く店じまいせざるを得なかった。
隣の商店主のおじさんは、長いこと商売をしているせいか、やっぱりしっかりしていた。
私の飲み物に並ぶ客たちの様子をちゃんと見ていた。
「女の子一人での商売は、危ない面もある。あんたを守ってくれる男衆は誰もいないのかね。兄とか弟とか。父親とか。恋人でもいいが」
「……いません」
「だったら、王都で誰かいい人を探しなよ。良さそうな男の客もいるよね。私の知っている商店の息子も毎日来ていた。大きな店の息子で、あれはあんたに気があるんだと思う」
まさか、あの黄色いシャツの男のことだろうか?
「違うよ。最近、来ている栗色の髪のおとなしそうな若い男だよ。仕事をしているので、毎日ではないけどね。来れる時は来ているらしい。うちのかみさんがそう言ってたよ。あれは縁結びが好きでね」
別な意味での危機が近付いている気がする。
「どうだね。まあ、お金は要るだろうけど、そのためにも腰を落ち着けて商売をする基盤も必要だろう」
「あんた、無茶いいなさんな。好きな男でもいたら、かわいそうだろ?」
おかみさんが割り込んだ。私の代わりに言ってくれているようだ。
「あれ? お前もワトソンさんならいいって言ってたじゃないか。いい人だって」
おかみさんは口ごもった。
「そりゃ、男前だし、人間は悪くないって、うわさだからね」
「まあ、ワトソンさんから頼まれたって言うのもあるんだよ。あんたは田舎から来たそうだから、知らないかも知れないけど、ワトソン商会っていう大商人の息子なんだ」
「でも、私……」
「好きな人がいるのかな? それなら何とか断っておくよ」
おかみさんはそう言ってくれたけど、商店主の方はこんなことを言った。
「目つきの悪い連中が、最近は混ざってきていることに気がついていたろ? 今のところ、ワトソンさんが抑えてくれているんだ。ワトソン商会の息子ににらまれたら厄介だからね」
ああ、なんてことだろう。
知らなかった。私、自分で自分を守ることもできないのか。
私は、伯母の言葉を思い出した。
『黙っておきましょうね。あなたの力を悪用しようとする者が現れたら困るから』
私の力は、多分強力なのだ。
強力すぎて危険なのだ。
ジュースどころではない。もし、本当の力、治癒の能力がバレたら……それこそ王家が乗り出してくる。
私がなぜ王家の婚約者だったのか。
それが答えだ。
まだ、バレていない。誰も何も知らない。
あの隠れ家は完璧だ。あそこに隠れていさえすれば、誰も手出しできない。
「私、とりあえず、店の方は閉めます」
15
あなたにおすすめの小説

夫に捨てられた私は冷酷公爵と再婚しました
香木陽灯
恋愛
伯爵夫人のマリアーヌは「夜を共に過ごす気にならない」と突然夫に告げられ、わずか五ヶ月で離縁することとなる。
これまで女癖の悪い夫に何度も不倫されても、役立たずと貶されても、文句ひとつ言わず彼を支えてきた。だがその苦労は報われることはなかった。
実家に帰っても父から不当な扱いを受けるマリアーヌ。気分転換に繰り出した街で倒れていた貴族の男性と出会い、彼を助ける。
「離縁したばかり? それは相手の見る目がなかっただけだ。良かったじゃないか。君はもう自由だ」
「自由……」
もう自由なのだとマリアーヌが気づいた矢先、両親と元夫の策略によって再婚を強いられる。相手は婚約者が逃げ出すことで有名な冷酷公爵だった。
ところが冷酷公爵と会ってみると、以前助けた男性だったのだ。
再婚を受け入れたマリアーヌは、公爵と少しずつ仲良くなっていく。
ところが公爵は王命を受け内密に仕事をしているようで……。
一方の元夫は、財政難に陥っていた。
「頼む、助けてくれ! お前は俺に恩があるだろう?」
元夫の悲痛な叫びに、マリアーヌはにっこりと微笑んだ。
「なぜかしら? 貴方を助ける気になりませんの」
※ふんわり設定です

平民とでも結婚すれば?と言われたので、隣国の王と結婚しました
ゆっこ
恋愛
「リリアーナ・ベルフォード、これまでの婚約は白紙に戻す」
その言葉を聞いた瞬間、私はようやく――心のどこかで予感していた結末に、静かに息を吐いた。
王太子アルベルト殿下。金糸の髪に、これ見よがしな笑み。彼の隣には、私が知っている顔がある。
――侯爵令嬢、ミレーユ・カスタニア。
学園で何かと殿下に寄り添い、私を「高慢な婚約者」と陰で嘲っていた令嬢だ。
「殿下、どういうことでしょう?」
私の声は驚くほど落ち着いていた。
「わたくしは、あなたの婚約者としてこれまで――」

はじめまして、旦那様。離婚はいつになさいます?
あゆみノワ@書籍『完全別居の契約婚〜』
恋愛
「はじめてお目にかかります。……旦那様」
「……あぁ、君がアグリア、か」
「それで……、離縁はいつになさいます?」
領地の未来を守るため、同じく子爵家の次男で軍人のシオンと期間限定の契約婚をした貧乏貴族令嬢アグリア。
両家の顔合わせなし、婚礼なし、一切の付き合いもなし。それどころかシオン本人とすら一度も顔を合わせることなく結婚したアグリアだったが、長らく戦地へと行っていたシオンと初対面することになった。
帰ってきたその日、アグリアは約束通り離縁を申し出たのだが――。
形だけの結婚をしたはずのふたりは、愛で結ばれた本物の夫婦になれるのか。
★HOTランキング最高2位をいただきました! ありがとうございます!
※書き上げ済みなので完結保証。他サイトでも掲載中です。

【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。
猫屋敷 むぎ
恋愛
没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――
私の願いは一瞬にして踏みにじられました。
母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、
婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。
「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」
まさか――あの優しい彼が?
そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。
子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。
でも、私には、味方など誰もいませんでした。
ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。
白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。
「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」
やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。
それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、
冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。
没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。
これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。
※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ
※わんこが繋ぐ恋物語です
※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

地味な私では退屈だったのでしょう? 最強聖騎士団長の溺愛妃になったので、元婚約者はどうぞお好きに
有賀冬馬
恋愛
「君と一緒にいると退屈だ」――そう言って、婚約者の伯爵令息カイル様は、私を捨てた。
選んだのは、華やかで社交的な公爵令嬢。
地味で無口な私には、誰も見向きもしない……そう思っていたのに。
失意のまま辺境へ向かった私が出会ったのは、偶然にも国中の騎士の頂点に立つ、最強の聖騎士団長でした。
「君は、僕にとってかけがえのない存在だ」
彼の優しさに触れ、私の世界は色づき始める。
そして、私は彼の正妃として王都へ……

白い結婚のはずが、騎士様の独占欲が強すぎます! すれ違いから始まる溺愛逆転劇
鍛高譚
恋愛
婚約破棄された令嬢リオナは、家の体面を守るため、幼なじみであり王国騎士でもあるカイルと「白い結婚」をすることになった。
お互い干渉しない、心も体も自由な結婚生活――そのはずだった。
……少なくとも、リオナはそう信じていた。
ところが結婚後、カイルの様子がおかしい。
距離を取るどころか、妙に優しくて、時に甘くて、そしてなぜか他の男性が近づくと怒る。
「お前は俺の妻だ。離れようなんて、思うなよ」
どうしてそんな顔をするのか、どうしてそんなに真剣に見つめてくるのか。
“白い結婚”のはずなのに、リオナの胸は日に日にざわついていく。
すれ違い、誤解、嫉妬。
そして社交界で起きた陰謀事件をきっかけに、カイルはとうとう本心を隠せなくなる。
「……ずっと好きだった。諦めるつもりなんてない」
そんなはずじゃなかったのに。
曖昧にしていたのは、むしろリオナのほうだった。
白い結婚から始まる、幼なじみ騎士の不器用で激しい独占欲。
鈍感な令嬢リオナが少しずつ自分の気持ちに気づいていく、溺愛逆転ラブストーリー。
「ゆっくりでいい。お前の歩幅に合わせる」
「……はい。私も、カイルと歩きたいです」
二人は“白い結婚”の先に、本当の夫婦を選んでいく――。
-
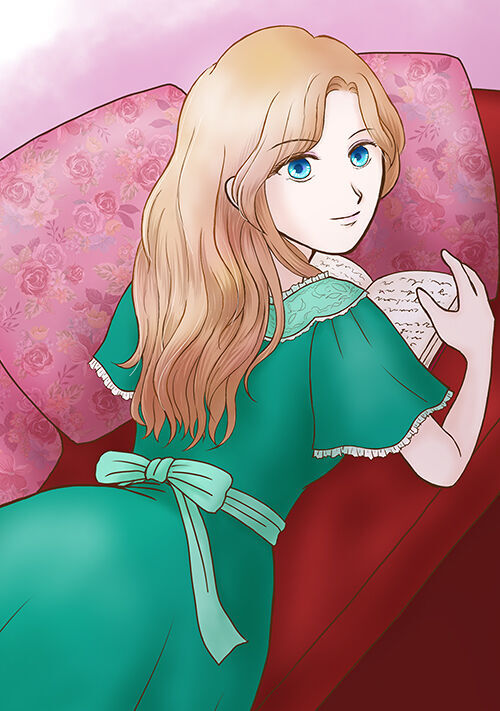
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

旦那様、離婚しましょう ~私は冒険者になるのでご心配なくっ~
榎夜
恋愛
私と旦那様は白い結婚だ。体の関係どころか手を繋ぐ事もしたことがない。
ある日突然、旦那の子供を身籠ったという女性に離婚を要求された。
別に構いませんが......じゃあ、冒険者にでもなろうかしら?
ー全50話ー
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















