1 / 14
1
しおりを挟む
その日まで、知花の生活は平穏そのものだった。
中学校と高校は女子校だったから、男子が同じ教室にいる大学生活は驚愕の連続だったし、大学の授業システムは高校までと違い過ぎて、戸惑うことも多かった。
だけど四月一日の入学式から3週間。
歓迎会やオリエンテーションなどの行事も滞りなくすぎ、いつも一緒に行動する友達と、それなりに仲のいい友達もできて、そろそろ自分が大学生ということにも慣れ始めたある日。
あの、赤い封筒が、知花の目の前に現れたのだ。
その封筒は、ごく普通の、無地の封筒だった。
深い赤は派手ではあるけれど綺麗な色で、クリスマスに外国製のカードと一緒に売られているような、まがまがしさなんてかけらもないものだった。
なのに、リビングの机の上にそれを見た時、なぜか知花の背筋がすっと寒くなった。
(あれは、よくないものだ)
なんの根拠もなく、そう思う。
そして、封筒から距離をおくように、後ずさりした。
ただの赤い封筒なのに、なぜか怖くて仕方がない。
馬鹿馬鹿しい、ただの封筒じゃないと思うのに、その封筒に近寄ることもできず、さりとて目を離すこともできず、知花は息をつめて、ただその封筒を見ていた。
そして、数秒後。
知花の目の前で、その封筒は、消えた。
すうっと、端のほうから幻のように。
「み、まちがい……?」
封筒が消えた瞬間、背筋の寒気も消えた。
ほっと息を吐きながら、知花は空笑いをしながら言った。
けれど言いながらも、見間違いなんかじゃないことは、知花自身がよくわかっていた。
ただの見間違いだと思うには、あまりにもその封筒は強烈な印象だった。
それに、あの寒気。
リビングは一面が全面窓ガラスになっていて、春の日差しがうららかに差し込んできている。
四月といえども寒い日もあるけれども、今日は春らしい陽気のあたたかな日だ。
時刻もまだ夕方の四時で、日暮れにはほど遠い。
それなのに、どんな冬の日も感じたことのないぞっとするような寒気がしていた。
(あれは、なんだったの……?)
知花は怖くなったが、ふるりと頭をふって、忘れることにした。
あの赤い封筒がなんなのかは、わからない。
だけど、あんなものを見たのは初めてだし、これきりのことのはずだ。
あれこれ考えるのは、かえってよくない、気がした。
だから、忘れることにしたのに……。
そう決めた瞬間、知花は気づいた。
なにかが、いる。
知花のななめうしろから、視線を感じる。
これも、気のせいなのか。
けれど、視線というのは、自分に向けられていると、案外感じるものだ。
気のせいだと思いたくても、それを無視することはできなかった。
おそるおそる、知花はゆっくりと振り返る。
誰も、いなかった。
だが、リビングの入口のすりガラスの向こうに、なにかがいる気配を感じた。
視線は、そこからまっすぐに知花を眺めている。
「……っ」
知花の喉から、小さな悲鳴が漏れた。
その瞬間。
「なにか」は消えた。
すうっと、知花に向けられていた視線はなくなった。
知花は、へたへたとその場に座り込んだ。
「な、なんなの……?」
がくがくと震える自分の脚を見ながら、知花はぼんやりと声にだして言ってみた。
そして、母が仕事を終えて帰ってくるまで、ずっとその場に座り込んでいた。
後で思い出せば、これがすべての始まりだったのだ。
そのことを、あの日の知花は、知らなかった。
中学校と高校は女子校だったから、男子が同じ教室にいる大学生活は驚愕の連続だったし、大学の授業システムは高校までと違い過ぎて、戸惑うことも多かった。
だけど四月一日の入学式から3週間。
歓迎会やオリエンテーションなどの行事も滞りなくすぎ、いつも一緒に行動する友達と、それなりに仲のいい友達もできて、そろそろ自分が大学生ということにも慣れ始めたある日。
あの、赤い封筒が、知花の目の前に現れたのだ。
その封筒は、ごく普通の、無地の封筒だった。
深い赤は派手ではあるけれど綺麗な色で、クリスマスに外国製のカードと一緒に売られているような、まがまがしさなんてかけらもないものだった。
なのに、リビングの机の上にそれを見た時、なぜか知花の背筋がすっと寒くなった。
(あれは、よくないものだ)
なんの根拠もなく、そう思う。
そして、封筒から距離をおくように、後ずさりした。
ただの赤い封筒なのに、なぜか怖くて仕方がない。
馬鹿馬鹿しい、ただの封筒じゃないと思うのに、その封筒に近寄ることもできず、さりとて目を離すこともできず、知花は息をつめて、ただその封筒を見ていた。
そして、数秒後。
知花の目の前で、その封筒は、消えた。
すうっと、端のほうから幻のように。
「み、まちがい……?」
封筒が消えた瞬間、背筋の寒気も消えた。
ほっと息を吐きながら、知花は空笑いをしながら言った。
けれど言いながらも、見間違いなんかじゃないことは、知花自身がよくわかっていた。
ただの見間違いだと思うには、あまりにもその封筒は強烈な印象だった。
それに、あの寒気。
リビングは一面が全面窓ガラスになっていて、春の日差しがうららかに差し込んできている。
四月といえども寒い日もあるけれども、今日は春らしい陽気のあたたかな日だ。
時刻もまだ夕方の四時で、日暮れにはほど遠い。
それなのに、どんな冬の日も感じたことのないぞっとするような寒気がしていた。
(あれは、なんだったの……?)
知花は怖くなったが、ふるりと頭をふって、忘れることにした。
あの赤い封筒がなんなのかは、わからない。
だけど、あんなものを見たのは初めてだし、これきりのことのはずだ。
あれこれ考えるのは、かえってよくない、気がした。
だから、忘れることにしたのに……。
そう決めた瞬間、知花は気づいた。
なにかが、いる。
知花のななめうしろから、視線を感じる。
これも、気のせいなのか。
けれど、視線というのは、自分に向けられていると、案外感じるものだ。
気のせいだと思いたくても、それを無視することはできなかった。
おそるおそる、知花はゆっくりと振り返る。
誰も、いなかった。
だが、リビングの入口のすりガラスの向こうに、なにかがいる気配を感じた。
視線は、そこからまっすぐに知花を眺めている。
「……っ」
知花の喉から、小さな悲鳴が漏れた。
その瞬間。
「なにか」は消えた。
すうっと、知花に向けられていた視線はなくなった。
知花は、へたへたとその場に座り込んだ。
「な、なんなの……?」
がくがくと震える自分の脚を見ながら、知花はぼんやりと声にだして言ってみた。
そして、母が仕事を終えて帰ってくるまで、ずっとその場に座り込んでいた。
後で思い出せば、これがすべての始まりだったのだ。
そのことを、あの日の知花は、知らなかった。
0
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

皆さんは呪われました
禰津エソラ
ホラー
あなたは呪いたい相手はいますか?
お勧めの呪いがありますよ。
効果は絶大です。
ぜひ、試してみてください……
その呪いの因果は果てしなく絡みつく。呪いは誰のものになるのか。
最後に残るのは誰だ……

百物語 厄災
嵐山ノキ
ホラー
怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。
小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。


なおこちゃんの手紙【モキュメンタリー】
武州青嵐(さくら青嵐)
ホラー
ある日、伊勢涼子のもとに、友人の優奈から「三沢久美の相談にのってあげてほしい」と連絡が入る。
三沢久美は子どもが持って帰ってきた「なおこちゃんの手紙」という手紙をもてあましていた。
その文面は、
「これは、なおこちゃんからの手紙です。
なおこちゃんは、パンがすきなおんなの子です。
かくれんぼをしています。ときどき、みつからないようにでてきます。
おともだちをぼしゅう中です。
だから、この手紙をもらったひとは、10日いないに、じぶんのともだち5人に、このなおこちゃんからの手紙をだしてください。文めんはおなじにしてください。
もし手紙をださなかったり、文めんを変えたら、なおこちゃんがやってきて、かくれんぼをするぞ。」
というもの。
三沢はこの手紙を写真に撮り、涼子にメールで送りつけてから連絡を絶つ。
数日後、近所の小学校でとある事件が発生。5人の女児がパニックを起こして怪我をする、というものだった。
その女児たちはいずれも、「なおこちゃんの手紙」を受け取っていた。
趣味で怪談実話をカクヨムで掲載している涼子は、この手紙を追っていくのだが……。
その彼女のもとに。
ひとりの女児が現れる。
※モキュメンタリー形式ですので、時系列に物語が進むわけではありません。
同名タイトルでカクヨムにも掲載
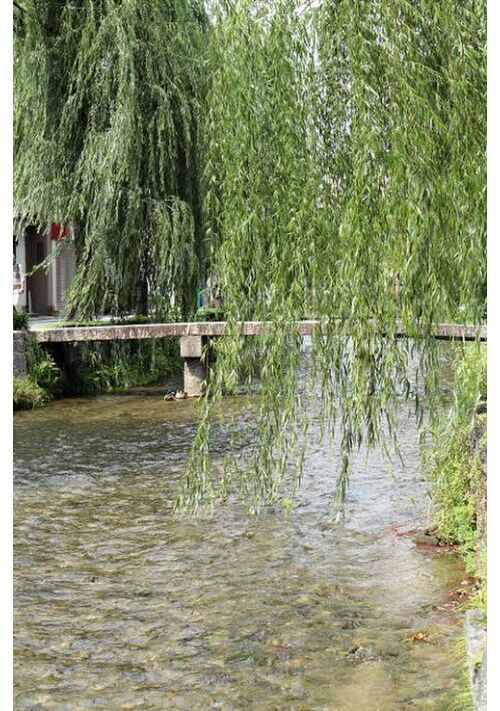

終焉列島:ゾンビに沈む国
ねむたん
ホラー
2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。
最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。
会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

偽夫婦お家騒動始末記
紫紺
歴史・時代
【第10回歴史時代大賞、奨励賞受賞しました!】
故郷を捨て、江戸で寺子屋の先生を生業として暮らす篠宮隼(しのみやはやて)は、ある夜、茶屋から足抜けしてきた陰間と出会う。
紫音(しおん)という若い男との奇妙な共同生活が始まるのだが。
隼には胸に秘めた決意があり、紫音との生活はそれを遂げるための策の一つだ。だが、紫音の方にも実は裏があって……。
江戸を舞台に様々な陰謀が駆け巡る。敢えて裏街道を走る隼に、念願を叶える日はくるのだろうか。
そして、拾った陰間、紫音の正体は。
活劇と謎解き、そして恋心の長編エンタメ時代小説です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















