2 / 14
2
しおりを挟む
「知花? 授業、終わってるよー」
ふにっと肩をつつかれて、目を覚ました。
隣の席に座っている瑠奈は、そんな知花を見て笑った。
「マジで寝てたの? 真面目な知花にしては、珍しいじゃん」
「瑠奈……、ごめん。本気で寝てたわ」
知花は、まばたきしながら応えた。
思いがけず深く眠っていたのだろう。
まだ頭がはんぶん眠っているようで、ぼんやりする。
コンタクトレンズをはめた目が、乾いてパシパシする。
まばたきを繰り返しながら、知花はのろのろとノートを片付けた。
それを見た瑠奈は、すこし心配そうに知花の顔を見る。
「なんかさぁ。知花、最近疲れてない? ぼんやりしていることとか多いし」
瑠奈が首をかしげると、金色に染めた長い髪も、さらさらと揺れた。
それをぼんやりと見ながら、知花は首を横に振る。
「べつに。なんでもないよ」
「そ? なら、いいけど。なんかあったら言ってよね。……ってかさぁ、気晴らしに平野神社にでも行く? そろそろ桜を見に来る人も減っているだろうし、のんびり見られそうじゃない?」
金色の長い髪と手の込んだメイク、すらりとした長い脚をショートパンツでさらしている瑠奈は、この京都守護大学では珍しい派手めな女の子だ。
服装は無難で目立たないのがいちばんだと思っている知花とは、見た目のタイプはぜんぜん違う。
けれど知花と瑠奈は、大学に入学してすぐ、一気に仲良くなった。
ふたりとも小学生のころから、寺社仏閣を擬人化したゲームアプリ「寺社仏閣奇譚」にハマり続けているという共通点があったからだ。
知花がつけていた「寺社仏閣奇譚」コラボの腕時計にめざとく気づいた瑠奈が入学式で声をかけてくれたのが、仲良くなったきっかけだ。
話してみればふたりとも、お金と時間に余裕ができる大学生になったら、京都の寺社仏閣めぐりを本格的にしようと思っていたのも一緒で、入学式の帰り道にさっそく大学最寄りの平野神社と北野天満宮で盛り上がり、それからずっと一緒に行動している。
知花は中学校と高校は別の女子校に通っていたが、瑠奈はこの京都守護大学附属の中学校と高校の内部進学者で、友達も多い。
瑠奈と一緒にいると、いろいろな人から声をかけられるおかげで、知花にも友達は増えた。
けれど知花ばかりが瑠奈を独占しているのは申し訳ない気もしていたのだが、瑠奈は笑って知花の不安を吹き飛ばしてくれた。
「もともと大学の間は、寺社仏閣めぐりに重点置くつもりで、サークルとかも入らないつもりだったし。知花と仲良くなれて、ふたりでいろいろ行けるの楽しいからいいんだよ」って。
その気持ちは、知花も一緒だ。
だから、ふだんなら大喜びで、瑠奈の提案に賛成して、平野神社に行ったと思う。
けれど。
「ごめん、ちょっとここのところ寝不足で……」
頭が重くて、体がだるい。
最近、知花は眠れていなかった。
昨日なんて、二時間も眠れたかどうか。
ふだんから本を読んだりゲームをしたりで、睡眠時間が数時間になってしまうことはある。
けれど楽しい時間を体力の限界まで楽しんでの寝不足と、今日の寝不足は種類が違い、体のダメージも大きかった。
寝不足の原因は、あの赤い封筒だ。
はじめてあの赤い封筒が知花の前に現れたのが月曜日で、今日は木曜日。
夕方のリビングの机の上に現れた赤い封筒は、その後も知花の自室の勉強机の上やバッグの中、玄関に置いた靴の上など、知花のすぐ目の前に何度も現れた。
赤い封筒が、知花の前にあるのは数秒だけだ。
現れたと思うと、すぐに消える。
そしてその後に、近くから知花をじっとりと眺める視線を感じるのも、毎回のことだった。
一度の怪異は、数分にも満たない短い時間のことだ。
けれども、いつ現れるかわからない赤い封筒と気味の悪い視線を日に何度も感じるせいで、知花の神経は削られていた。
そのうえ、この赤い封筒は、知花以外の誰にも見えないこともわかった。
月曜日の夜、お風呂あがりの知花は、机の上に置いてある本に目を止めた。
それは母が楽しみに買って読んでいるミステリのシリーズものの新作小説で、母が読んだ後、知花もいつも借りている本だった。
「これ、読み終わったの? 借りていい?」
知花は机の上の本を見ながら、カウンターでコーヒーを淹れていた母に声をかけた。
母はにんまり笑って、うなずいた。
「もちろん。今回も、すっごく面白かったわよ」
「そうなの……」
この時、知花は夕方に見た赤い封筒のことは、だいぶん意識の奥に追いやっていた。
時間がたつにつれ、目の前にあったものが消えるなんて非現実的だし、視線を感じたというのも、気のせいかもしれない、と思うようになっていたのだ。
父や母といつもどおりテレビを見ながら夕食を食べて話したりしていると、その気持ちは次第に強くなり、夕方の怪異は、知花の頭からほとんど追い出されていた。
けれど、母が置いていたそのミステリ小説の上に、こつぜんとまた赤い封筒が現れた。
知花はひゅっと息をのんだ。
「お、お母さん……。この封筒って……」
震える指で、その赤い封筒を指さして、母に尋ねた。
すると母は、コーヒーの入ったマグカップをふたつ、机に置きながら、知花の指したほうを見て、
「封筒って?」
と首をかしげた。
不思議そうな母の顔を見て、知花は察した。
この封筒は、自分にしか見えないのだと。
「なんでもない……」
言いながら、知花はまたあのじっとりとした視線を感じて、目をあげる。
視線は、さっき母がいたカウンターのあたりから、知花に向けられていた。
じぃっと上から下まで、舐めるように全身を見られている。
とっさに知花がパジャマの胸元を手で隠すように覆うと、母は怪訝そうに知花を見ていた。
「どうかした?」
「ううん、なんでもない。ちょっと冷えたのかも」
「あら。気をつけなさいよ。もうすぐゴールデンウイークなのに。友達と遊びに行く約束もしているんでしょ」
「うん。そうだね。今日は、もう寝るわ。この本、借りていくね」
知花は本を胸に抱いて、リビングを後にした。
封筒も、視線も、その時にはもう消えていたけれど、知花はこれが終わりじゃないのかも、と漠然とした不安を感じていた。
ふにっと肩をつつかれて、目を覚ました。
隣の席に座っている瑠奈は、そんな知花を見て笑った。
「マジで寝てたの? 真面目な知花にしては、珍しいじゃん」
「瑠奈……、ごめん。本気で寝てたわ」
知花は、まばたきしながら応えた。
思いがけず深く眠っていたのだろう。
まだ頭がはんぶん眠っているようで、ぼんやりする。
コンタクトレンズをはめた目が、乾いてパシパシする。
まばたきを繰り返しながら、知花はのろのろとノートを片付けた。
それを見た瑠奈は、すこし心配そうに知花の顔を見る。
「なんかさぁ。知花、最近疲れてない? ぼんやりしていることとか多いし」
瑠奈が首をかしげると、金色に染めた長い髪も、さらさらと揺れた。
それをぼんやりと見ながら、知花は首を横に振る。
「べつに。なんでもないよ」
「そ? なら、いいけど。なんかあったら言ってよね。……ってかさぁ、気晴らしに平野神社にでも行く? そろそろ桜を見に来る人も減っているだろうし、のんびり見られそうじゃない?」
金色の長い髪と手の込んだメイク、すらりとした長い脚をショートパンツでさらしている瑠奈は、この京都守護大学では珍しい派手めな女の子だ。
服装は無難で目立たないのがいちばんだと思っている知花とは、見た目のタイプはぜんぜん違う。
けれど知花と瑠奈は、大学に入学してすぐ、一気に仲良くなった。
ふたりとも小学生のころから、寺社仏閣を擬人化したゲームアプリ「寺社仏閣奇譚」にハマり続けているという共通点があったからだ。
知花がつけていた「寺社仏閣奇譚」コラボの腕時計にめざとく気づいた瑠奈が入学式で声をかけてくれたのが、仲良くなったきっかけだ。
話してみればふたりとも、お金と時間に余裕ができる大学生になったら、京都の寺社仏閣めぐりを本格的にしようと思っていたのも一緒で、入学式の帰り道にさっそく大学最寄りの平野神社と北野天満宮で盛り上がり、それからずっと一緒に行動している。
知花は中学校と高校は別の女子校に通っていたが、瑠奈はこの京都守護大学附属の中学校と高校の内部進学者で、友達も多い。
瑠奈と一緒にいると、いろいろな人から声をかけられるおかげで、知花にも友達は増えた。
けれど知花ばかりが瑠奈を独占しているのは申し訳ない気もしていたのだが、瑠奈は笑って知花の不安を吹き飛ばしてくれた。
「もともと大学の間は、寺社仏閣めぐりに重点置くつもりで、サークルとかも入らないつもりだったし。知花と仲良くなれて、ふたりでいろいろ行けるの楽しいからいいんだよ」って。
その気持ちは、知花も一緒だ。
だから、ふだんなら大喜びで、瑠奈の提案に賛成して、平野神社に行ったと思う。
けれど。
「ごめん、ちょっとここのところ寝不足で……」
頭が重くて、体がだるい。
最近、知花は眠れていなかった。
昨日なんて、二時間も眠れたかどうか。
ふだんから本を読んだりゲームをしたりで、睡眠時間が数時間になってしまうことはある。
けれど楽しい時間を体力の限界まで楽しんでの寝不足と、今日の寝不足は種類が違い、体のダメージも大きかった。
寝不足の原因は、あの赤い封筒だ。
はじめてあの赤い封筒が知花の前に現れたのが月曜日で、今日は木曜日。
夕方のリビングの机の上に現れた赤い封筒は、その後も知花の自室の勉強机の上やバッグの中、玄関に置いた靴の上など、知花のすぐ目の前に何度も現れた。
赤い封筒が、知花の前にあるのは数秒だけだ。
現れたと思うと、すぐに消える。
そしてその後に、近くから知花をじっとりと眺める視線を感じるのも、毎回のことだった。
一度の怪異は、数分にも満たない短い時間のことだ。
けれども、いつ現れるかわからない赤い封筒と気味の悪い視線を日に何度も感じるせいで、知花の神経は削られていた。
そのうえ、この赤い封筒は、知花以外の誰にも見えないこともわかった。
月曜日の夜、お風呂あがりの知花は、机の上に置いてある本に目を止めた。
それは母が楽しみに買って読んでいるミステリのシリーズものの新作小説で、母が読んだ後、知花もいつも借りている本だった。
「これ、読み終わったの? 借りていい?」
知花は机の上の本を見ながら、カウンターでコーヒーを淹れていた母に声をかけた。
母はにんまり笑って、うなずいた。
「もちろん。今回も、すっごく面白かったわよ」
「そうなの……」
この時、知花は夕方に見た赤い封筒のことは、だいぶん意識の奥に追いやっていた。
時間がたつにつれ、目の前にあったものが消えるなんて非現実的だし、視線を感じたというのも、気のせいかもしれない、と思うようになっていたのだ。
父や母といつもどおりテレビを見ながら夕食を食べて話したりしていると、その気持ちは次第に強くなり、夕方の怪異は、知花の頭からほとんど追い出されていた。
けれど、母が置いていたそのミステリ小説の上に、こつぜんとまた赤い封筒が現れた。
知花はひゅっと息をのんだ。
「お、お母さん……。この封筒って……」
震える指で、その赤い封筒を指さして、母に尋ねた。
すると母は、コーヒーの入ったマグカップをふたつ、机に置きながら、知花の指したほうを見て、
「封筒って?」
と首をかしげた。
不思議そうな母の顔を見て、知花は察した。
この封筒は、自分にしか見えないのだと。
「なんでもない……」
言いながら、知花はまたあのじっとりとした視線を感じて、目をあげる。
視線は、さっき母がいたカウンターのあたりから、知花に向けられていた。
じぃっと上から下まで、舐めるように全身を見られている。
とっさに知花がパジャマの胸元を手で隠すように覆うと、母は怪訝そうに知花を見ていた。
「どうかした?」
「ううん、なんでもない。ちょっと冷えたのかも」
「あら。気をつけなさいよ。もうすぐゴールデンウイークなのに。友達と遊びに行く約束もしているんでしょ」
「うん。そうだね。今日は、もう寝るわ。この本、借りていくね」
知花は本を胸に抱いて、リビングを後にした。
封筒も、視線も、その時にはもう消えていたけれど、知花はこれが終わりじゃないのかも、と漠然とした不安を感じていた。
0
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

皆さんは呪われました
禰津エソラ
ホラー
あなたは呪いたい相手はいますか?
お勧めの呪いがありますよ。
効果は絶大です。
ぜひ、試してみてください……
その呪いの因果は果てしなく絡みつく。呪いは誰のものになるのか。
最後に残るのは誰だ……

意味がわかると怖い話
邪神 白猫
ホラー
【意味がわかると怖い話】解説付き
基本的には読めば誰でも分かるお話になっていますが、たまに激ムズが混ざっています。
※完結としますが、追加次第随時更新※
YouTubeにて、朗読始めました(*'ω'*)
お休み前や何かの作業のお供に、耳から読書はいかがですか?📕
https://youtube.com/@yuachanRio

百物語 厄災
嵐山ノキ
ホラー
怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。
小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。
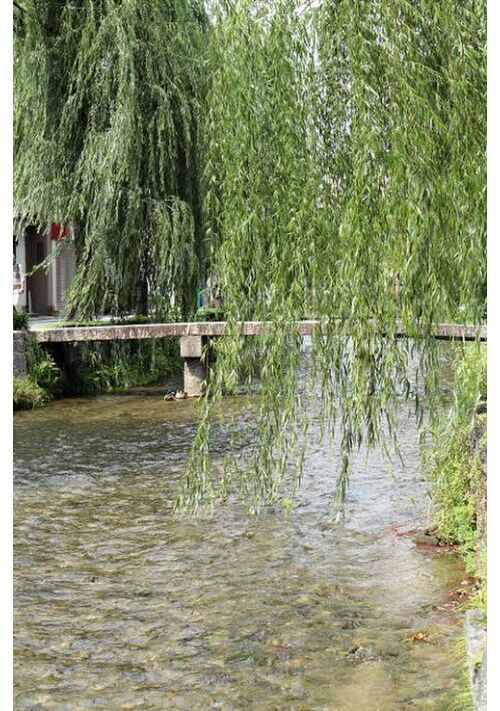

偽夫婦お家騒動始末記
紫紺
歴史・時代
【第10回歴史時代大賞、奨励賞受賞しました!】
故郷を捨て、江戸で寺子屋の先生を生業として暮らす篠宮隼(しのみやはやて)は、ある夜、茶屋から足抜けしてきた陰間と出会う。
紫音(しおん)という若い男との奇妙な共同生活が始まるのだが。
隼には胸に秘めた決意があり、紫音との生活はそれを遂げるための策の一つだ。だが、紫音の方にも実は裏があって……。
江戸を舞台に様々な陰謀が駆け巡る。敢えて裏街道を走る隼に、念願を叶える日はくるのだろうか。
そして、拾った陰間、紫音の正体は。
活劇と謎解き、そして恋心の長編エンタメ時代小説です。

終焉列島:ゾンビに沈む国
ねむたん
ホラー
2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。
最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。
会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

ヤンデレ美少女転校生と共に体育倉庫に閉じ込められ、大問題になりましたが『結婚しています!』で乗り切った嘘のような本当の話
桜井正宗
青春
――結婚しています!
それは二人だけの秘密。
高校二年の遙と遥は結婚した。
近年法律が変わり、高校生(十六歳)からでも結婚できるようになっていた。だから、問題はなかった。
キッカケは、体育倉庫に閉じ込められた事件から始まった。校長先生に問い詰められ、とっさに誤魔化した。二人は退学の危機を乗り越える為に本当に結婚することにした。
ワケありヤンデレ美少女転校生の『小桜 遥』と”新婚生活”を開始する――。
*結婚要素あり
*ヤンデレ要素あり
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















