15 / 181
再会が告げた戦の引き金
しおりを挟む
外が騒がしい。
どうやら兵が村に来たようだ。あの賊のことだろうか。書状とベルトが王に渡っていたのであればいいのだが...。
教会の前に置いたのはセラだ。もし王都が把握しているなら証拠の一つになるだけだが、把握していないなら国家レベルの問題になりかねない。村長に話すことも考えたが、それではどうやってベルトを手に入れたのかと聞かれてしまう。考えた末、教会前に置くのが1番王に渡る可能性が高くリスクも少ないと判断した。
「なんだろ?誰か来てるのかな」
「兵みたいだね。」
セラの予想通りなら村長はこの家の戸を叩くはずだーーー
その予想は正しかった。
「セラや」
エレンが煮詰めた薬草を混ぜる手を止めた。
「村長、どうされたんですか。」
「王弟殿下....軍の長の方が西に詳しい者を出せとのことだ。お前ぐらいだろう。西へ行くのは。」
「分かりました。直ぐに向かいます。」
まさか王族が出てくるとは。どうやら事態は思ったより重いらしい。
表へ歩いていくと美しいブロンドの髪が見えた。髪の持ち主はセラの方を見た。その瞬間、彼は絶句した。
「..........セラ?」
「..........レオ様?」
流れるのは気まずい沈黙。会うのは市だけでよかったのに。
「殿.....レオポルト様。もしやこの方が....」
「ああ....こんなところで会うとは思わなかった。」
村の者の視線が痛い。王族と知り合いだとなれば当然なのだが、そうとは知らなかったのだから許して欲しい。
「西の方のことでお聞きになりたいことがあるとか。」
無理やり話を変える。あんな書状出すんじゃなかったと後悔したところでもう遅い。
「ああ、そうだったな。」
セラの意図を察してくれたのだろう。レオは軍司令官の顔に戻っていた。
「西の道、それから賊のことについて聞きたい。」
「....場所を変えてもいいですか?賊のこととなれば村人が怯えてしまいます。」
「それもそうだな。案内してくれ。」
本来王弟を家に通すなどもっての外だがレオならば気にしないだろう。家の前にはルディが立っていた。レオを見た彼の目には怒りの火が宿った身体は震えている。
「お前ら王族がなんでこんな村に来るんだ....!父さんはお前らのせいで....!」
木剣を握り、血で手を滲ませた彼は今にも襲いかかりそうだった。
「ルディ」
「!セラ姉...!でも....!」
「目的を履き違えてはいけないと言ったはずよ。今ここで貴方が間違えば家族は路頭に迷うわ。」
ルディの唇は震え、目は迷いに揺れていた。
「.......分かってるよ.....」
手からすり抜けた木剣は乾いた音を立てて地に落ちた。
「貴様、殿下に向かって剣を向けるなど...!」
「クシェル。いい。セラ、この子の手当てをしてやれ。」
「よいのですか?」
「ああ。」
その時、エレンが戸を開けた。
「セラ姉、王弟殿下が来たって.....ってえ!?」
その本人が家の前にいるとは思わなかったようだ。深刻な面持ちで手から血を流しているルディと初めてみる王族。エレンの混乱が手に取るように見えた。
「エレン、ルディを連れて行って手当てしてあげてくれる?それから誰もしばらくここへ近づけないようにしておいて。」
「え、あ、うん。えっと....ルディ、行こっか。」
誰もいなくなった家にレオとクシェルと呼ばれた側近を招き入れるとお茶を出す。リンデンと蜂蜜の甘い香りが部屋を包み込んだ。
「先ほどは村の者が無礼をいたしました。どうぞお許しください。」
「やめろ、セラ。......だから嫌だったんだ。」
最後の呟きは聞かなかったことにしておく。
深いため息が部屋を支配する。
「お前も座れ。茶も飲めばいい。」
「では失礼します。」
本来、王弟の前で共に茶を飲むなど許されるはずがない。レオはそういうのが嫌だったのだろうけれど。
「音が鳴らないな。」
「え?」
「無意識か?カップを置く時に音がしない。」
「あ....」
「こうやって見ると本当に教育を受けた娘のようだ。」
「食器の当たる音が苦手なのです。それ以上も何もありません。」
疑いの目がこちらを向く。納得してくれという目を向け返すと再度ため息をついた。
「..........疫病か?」
唐突な質問に戸惑うが、すぐに何を言っているのか思い当たった。
「ああ、ルディですか?」
「そうだ。」
「ええ。父が疫病に罹り連れて行かれた末、帰らなかったようです。母親は当時乳飲み子とルディを抱え、異国の血も混じっているので村では疎外されていました。」
「父王の病に罹ったもの全てを隔離、ましてや末期のものには治療も施さぬという政策は多くの人から反感を買ったことは理解している。だが異国の血を理由に未亡人を疎外するとは見上げたものだな。」
「先王の政策は医療の理論的には筋が通っていました。ただ人々が理解するには大胆過ぎたのかもしれませんが。」
「その父が病で倒れた時は俺ですら呪いかと思ったよ。まあある意味そのお陰で民の反感は抑えられたんだがな。」
淡々と言う彼には王族として生きてきた重みがあった。
父王の死ですら政治の一環と思わねばならない。これが王族の現実だ。
「まあ今は西の賊だ。村長がお前が1番詳しいと言ったが、間違いないか?」
「はい。間違い無いと思います。」
「賊の噂は?」
「賊が減ったとの噂ならあります。私が感じていた違和感もそれでした。」
「というと?」
「西へは薬草を採りに行くことも多いのですが、普段いる賊がいない。一見すると平和になったようですが、裏を返せば賊が必要な物資をどこかから得ているということになります。」
「その通りだ。実は教会の前に書状が届いてな。北西に賊ありと言うので斥候を送ったところ1000人規模の軍に膨れ上がっていた。放っておけば一月で3倍になる。不味いだろう?」
1000。思ったより多い。セラが無事に帰れたのは奇跡というべきだろう。
「それは...かなりの規模ですね。策はあるのですか?」
「そのためにこの村に来たんだ。恐らく表の道は警戒されている。斥候は少数だからバレなかったが、出来れば裏道を使いたい。」
「獣道でも構わなければあることにはありますが。」
「構わん。慣れたものばかりだ。地図で教えてくれればいい。」
「地図では少し難しいかもしれません。よろしければ案内しますが。」
「危ないだろう。....そういえば聞きたかったんだが、市にはどうやって行ってるんだ?近くじゃなかったのか?」
この際仕方がない。観念して答えることにした。
「馬に乗れば数時間で着きます。」
「馬に乗るのか?」
「はい。昔拾われた師に教わりました。」
「賊に襲われたりはしなかったのか?」
「多少、腕は立ちます。」
訝しげに見てくるレオの視線に気づかないフリをする。
「.....探らない約束では?」
「俺は晒したぞ。これ以上隠してることはない。」
「意には反していたでしょう。」
「お前な....まあいい。賊には詳しいのか?」
あまり聞かれたくない質問ばかりだ。
もうここまで来たらある程度は仕方がない。
「それなりには。何故でしょう?」
「さっき賊が必要な物資を得ていると言っただろう。これが意味することは?」
「裏で物資を提供している商家、もしくは貴族がいるのでしょうね。」
「ああ。出来れば賊の頭は生かして捕らえたい。何か目印になるものなどがあればいいんだが....」
「賊の頭の目印は様々ですが、額のルーン、骨飾り、血染めの外套などがあり得るでしょうか。」
「よく知っているな。」
「旅をしているうちに覚えました。すぐに出られますか?日の暮れないうちに進んだ方がいいかと。」
「俺はまだ案内を頼むとは言ってないぞ。」
「菓子の礼だとでも思ってください。割に合わないと思っていたのです。」
「仕方がないな.......言う通り出るとするか。」
出かける用に鞄は常に用意してある。薬箱だけ詰めると家を出た。
「エレン」
村の中央で子供達と遊んでいたエレンを呼ぶ。
「私は少し出る。数日以内には帰ると思うからあとお願いね。」
「ええ、どこ行くの?」
「それは内緒。あとルディのことも、よろしくね。」
「あの王族の方と何かあったの?」
耳元で囁くエレンはセラが罰せられるのではないかと心配しているらしい。
「悪いことは何もないよ。ただ道を案内するだけ。」
「それならいいけど....気をつけてね。」
「うん、ありがとね。」
振り返ると馬に跨ったレオがこちらを見ていた。
「お待たせしました。向かいましょう。」
馬に乗り、風を切って駆け出した。誰かと並走するのはいつ以来だろうか。
「軍は森に隠しているのですか?」
「ああ。まずはそこへ向かう。」
森に潜んだ軍の元へ着くと何故女がいるのかという目線が飛んできた。
「殿下、そちらの女性は?」
「西の道に詳しいらしい。案内してもらうことになった。」
「馬に乗れるんですか?すぐに向かうので?」
「ああ。今日中に移動し、明日の明朝に仕掛ける。時間をかけるほど不利だからな。」
「分かりました。」
レオの言った通り、兵は慣れているようだった。細い獣道で速度を上げても問題なくついてくる。
「遅過ぎますか?」
「もう少し上げられるか?」
「はい。」
数時間の後、開けた地に出た。
日は沈み、仄明るい月が影を見せ始めている。
「今日はここで夜営だ!」
レオの言葉に兵たちは夜営の準備を始める。セラもいつものように木の陰に行こうとしたのだが。
「どこへ行く。」
「あちらの方で私は休みます。」
「ダメだ。テントを用意するからそこを使え。」
「野宿は慣れていますが....」
「1人ならいい....わけでもないがとにかく男だらけの場所で外で寝るな。」
そんな王弟直属の軍が、女に飢えているわけもあるまいに。そう思ってもレオの目は真剣だ。
「数は足りるのですか?」
「足りる。嫌だと言えば俺の隣で寝ることになるが、その方がいいか?」
「勘弁してください。使わせていただきます。」
「そう言われるとちょっとな....」
自分で言っておいて勝手なものだ。王弟と寝たなど、どんな恐ろしい噂に巻き込まれるか分からない。
「ところでお前は戦には参加しないよな?」
「参加するつもりでしたが。」
「ダメだ。帰れ。」
今日はダメ出しが多い。実は口うるさかったのだろうか。
「1人で帰る方が危険だと思いますが。」
別にそんなことはない。ただ、貰ってばかりで落ち着かなかった。それだけだ。
「せめてこの場所で森の陰にでも隠れておかないか?」
「賊は敵に襲われたと知れば恥も全て捨てて逃げ出すのですよ。森の中などすぐに戦いの海です。」
レオはしばし無言になった。
「お前、最初からこのつもりだったな?」
「承知の上かと思っていました。」
「俺は朝帰らせるつもりだった。」
「それは....少し無理がありましたね。」
「なんでお前が憐れむんだ。いいか。俺の側を離れるなよ。お前に死なれるのは困るんだ。」
「そんな簡単に死にません。死ねるものならとっくに死んでます。」
「余計に恐ろしくなった。頼むから無茶はしないでくれ。」
こんな顔もするのか。懇願する顔はなんとなく可愛らしいと思ってしまった。
「分かりました。大人しくしておきます。」
「ああ。戦に出るなら軍議にも参加してくれ。作戦を知っておいてもらう方がいい。」
「村娘が軍議に参加すれば不審に思われると思いますが。」
「気にするな。俺の独断行為には皆慣れている。」
軍の人間の苦労が偲ばれる。
「その前に食事だな。行くぞ。」
「うさぎか鳥でも取ってきましょうか?」
「取れるのか?」
「1、2羽なら取れると思いますが。」
「....鳥もか?」
「弓さえあれば。」
「.....もうお前が何をできると言っても驚かん。獣なら兵が取ってるはずだ。お前は大人しく食べろ。」
呆れられただろうか。菓子の礼が獣では格好がつかないかもしれない。
肉の香ばしい匂いが空に上っていた。セラが普段する野宿とは違って快適な夜営だ。
「殿下、戻られましたか。肉が焼けていますよ。」
「ああ、美味そうだ。セラ、お前も食べろ。」
「いただきます。」
口の中に香ばしさと肉汁が広がる。こんな風に食べるのは久しぶりだ。
「なんだ、ちゃんと食べれるじゃないか」
「肉が美味しかったことを思い出しました。」
「その細い身体をなんとかしろ。普段ロクに食べてないだろ。」
「面倒で....」
半分嘘、半分本当だ。弟たちに優先して食べさせているうちにあまりお腹が空かなくなった。
「次会う時は肉でも持ってくるか?」
「それはちょっと....菓子の方が。」
「菓子の方が贅沢品だぞ?」
「うっ.....」
「甘いのが好きなんだろう?ちゃんと持ってきてやるから食べればいい。」
ニヤリと笑うこの男は狡い男だ。
(殿下が女性相手にこんな顔をなさるとは...)
噂で聞き及んでいた以上に入れ込んでいるらしい主の様子にクシェルはため息をついた。
軍議に参加していたのはクシェル、そして近衛長と思われる男だった。
皆戦には慣れているようだ。
「敵は1000もしくはそれ以上。対する我が軍も1000。仕掛けるのは明朝だ。異論は?」
近衛長と思われる男が口を開いた。
「ありません。しかし攻め方は?分けるほどの兵力はない。」
「兵は二つに分ける。夜の間に城の裏の森へ500を送る。空が白んでくる頃を見計らって2方向から狼煙を上げ、笛を鳴らす。出てきた賊は頭を除いて1人残らず討ち取って構わない。」
王弟という立場ながらレオは戦の経験が豊富なようだった。直属の軍があるくらいだ。普段から戦に出ることがあるのだろう。
「頭だと見分ける方法は?」
「額にルーン文字、骨飾り、血染めの外套などだそうだ。それ以外なら...難しいな。だがなんとしても捕まえたいところだ。」
「承知しました。」
「以上だ。他には?」
「ありません。」
「では解散だ。明日に備えて休め。」
どうやら兵が村に来たようだ。あの賊のことだろうか。書状とベルトが王に渡っていたのであればいいのだが...。
教会の前に置いたのはセラだ。もし王都が把握しているなら証拠の一つになるだけだが、把握していないなら国家レベルの問題になりかねない。村長に話すことも考えたが、それではどうやってベルトを手に入れたのかと聞かれてしまう。考えた末、教会前に置くのが1番王に渡る可能性が高くリスクも少ないと判断した。
「なんだろ?誰か来てるのかな」
「兵みたいだね。」
セラの予想通りなら村長はこの家の戸を叩くはずだーーー
その予想は正しかった。
「セラや」
エレンが煮詰めた薬草を混ぜる手を止めた。
「村長、どうされたんですか。」
「王弟殿下....軍の長の方が西に詳しい者を出せとのことだ。お前ぐらいだろう。西へ行くのは。」
「分かりました。直ぐに向かいます。」
まさか王族が出てくるとは。どうやら事態は思ったより重いらしい。
表へ歩いていくと美しいブロンドの髪が見えた。髪の持ち主はセラの方を見た。その瞬間、彼は絶句した。
「..........セラ?」
「..........レオ様?」
流れるのは気まずい沈黙。会うのは市だけでよかったのに。
「殿.....レオポルト様。もしやこの方が....」
「ああ....こんなところで会うとは思わなかった。」
村の者の視線が痛い。王族と知り合いだとなれば当然なのだが、そうとは知らなかったのだから許して欲しい。
「西の方のことでお聞きになりたいことがあるとか。」
無理やり話を変える。あんな書状出すんじゃなかったと後悔したところでもう遅い。
「ああ、そうだったな。」
セラの意図を察してくれたのだろう。レオは軍司令官の顔に戻っていた。
「西の道、それから賊のことについて聞きたい。」
「....場所を変えてもいいですか?賊のこととなれば村人が怯えてしまいます。」
「それもそうだな。案内してくれ。」
本来王弟を家に通すなどもっての外だがレオならば気にしないだろう。家の前にはルディが立っていた。レオを見た彼の目には怒りの火が宿った身体は震えている。
「お前ら王族がなんでこんな村に来るんだ....!父さんはお前らのせいで....!」
木剣を握り、血で手を滲ませた彼は今にも襲いかかりそうだった。
「ルディ」
「!セラ姉...!でも....!」
「目的を履き違えてはいけないと言ったはずよ。今ここで貴方が間違えば家族は路頭に迷うわ。」
ルディの唇は震え、目は迷いに揺れていた。
「.......分かってるよ.....」
手からすり抜けた木剣は乾いた音を立てて地に落ちた。
「貴様、殿下に向かって剣を向けるなど...!」
「クシェル。いい。セラ、この子の手当てをしてやれ。」
「よいのですか?」
「ああ。」
その時、エレンが戸を開けた。
「セラ姉、王弟殿下が来たって.....ってえ!?」
その本人が家の前にいるとは思わなかったようだ。深刻な面持ちで手から血を流しているルディと初めてみる王族。エレンの混乱が手に取るように見えた。
「エレン、ルディを連れて行って手当てしてあげてくれる?それから誰もしばらくここへ近づけないようにしておいて。」
「え、あ、うん。えっと....ルディ、行こっか。」
誰もいなくなった家にレオとクシェルと呼ばれた側近を招き入れるとお茶を出す。リンデンと蜂蜜の甘い香りが部屋を包み込んだ。
「先ほどは村の者が無礼をいたしました。どうぞお許しください。」
「やめろ、セラ。......だから嫌だったんだ。」
最後の呟きは聞かなかったことにしておく。
深いため息が部屋を支配する。
「お前も座れ。茶も飲めばいい。」
「では失礼します。」
本来、王弟の前で共に茶を飲むなど許されるはずがない。レオはそういうのが嫌だったのだろうけれど。
「音が鳴らないな。」
「え?」
「無意識か?カップを置く時に音がしない。」
「あ....」
「こうやって見ると本当に教育を受けた娘のようだ。」
「食器の当たる音が苦手なのです。それ以上も何もありません。」
疑いの目がこちらを向く。納得してくれという目を向け返すと再度ため息をついた。
「..........疫病か?」
唐突な質問に戸惑うが、すぐに何を言っているのか思い当たった。
「ああ、ルディですか?」
「そうだ。」
「ええ。父が疫病に罹り連れて行かれた末、帰らなかったようです。母親は当時乳飲み子とルディを抱え、異国の血も混じっているので村では疎外されていました。」
「父王の病に罹ったもの全てを隔離、ましてや末期のものには治療も施さぬという政策は多くの人から反感を買ったことは理解している。だが異国の血を理由に未亡人を疎外するとは見上げたものだな。」
「先王の政策は医療の理論的には筋が通っていました。ただ人々が理解するには大胆過ぎたのかもしれませんが。」
「その父が病で倒れた時は俺ですら呪いかと思ったよ。まあある意味そのお陰で民の反感は抑えられたんだがな。」
淡々と言う彼には王族として生きてきた重みがあった。
父王の死ですら政治の一環と思わねばならない。これが王族の現実だ。
「まあ今は西の賊だ。村長がお前が1番詳しいと言ったが、間違いないか?」
「はい。間違い無いと思います。」
「賊の噂は?」
「賊が減ったとの噂ならあります。私が感じていた違和感もそれでした。」
「というと?」
「西へは薬草を採りに行くことも多いのですが、普段いる賊がいない。一見すると平和になったようですが、裏を返せば賊が必要な物資をどこかから得ているということになります。」
「その通りだ。実は教会の前に書状が届いてな。北西に賊ありと言うので斥候を送ったところ1000人規模の軍に膨れ上がっていた。放っておけば一月で3倍になる。不味いだろう?」
1000。思ったより多い。セラが無事に帰れたのは奇跡というべきだろう。
「それは...かなりの規模ですね。策はあるのですか?」
「そのためにこの村に来たんだ。恐らく表の道は警戒されている。斥候は少数だからバレなかったが、出来れば裏道を使いたい。」
「獣道でも構わなければあることにはありますが。」
「構わん。慣れたものばかりだ。地図で教えてくれればいい。」
「地図では少し難しいかもしれません。よろしければ案内しますが。」
「危ないだろう。....そういえば聞きたかったんだが、市にはどうやって行ってるんだ?近くじゃなかったのか?」
この際仕方がない。観念して答えることにした。
「馬に乗れば数時間で着きます。」
「馬に乗るのか?」
「はい。昔拾われた師に教わりました。」
「賊に襲われたりはしなかったのか?」
「多少、腕は立ちます。」
訝しげに見てくるレオの視線に気づかないフリをする。
「.....探らない約束では?」
「俺は晒したぞ。これ以上隠してることはない。」
「意には反していたでしょう。」
「お前な....まあいい。賊には詳しいのか?」
あまり聞かれたくない質問ばかりだ。
もうここまで来たらある程度は仕方がない。
「それなりには。何故でしょう?」
「さっき賊が必要な物資を得ていると言っただろう。これが意味することは?」
「裏で物資を提供している商家、もしくは貴族がいるのでしょうね。」
「ああ。出来れば賊の頭は生かして捕らえたい。何か目印になるものなどがあればいいんだが....」
「賊の頭の目印は様々ですが、額のルーン、骨飾り、血染めの外套などがあり得るでしょうか。」
「よく知っているな。」
「旅をしているうちに覚えました。すぐに出られますか?日の暮れないうちに進んだ方がいいかと。」
「俺はまだ案内を頼むとは言ってないぞ。」
「菓子の礼だとでも思ってください。割に合わないと思っていたのです。」
「仕方がないな.......言う通り出るとするか。」
出かける用に鞄は常に用意してある。薬箱だけ詰めると家を出た。
「エレン」
村の中央で子供達と遊んでいたエレンを呼ぶ。
「私は少し出る。数日以内には帰ると思うからあとお願いね。」
「ええ、どこ行くの?」
「それは内緒。あとルディのことも、よろしくね。」
「あの王族の方と何かあったの?」
耳元で囁くエレンはセラが罰せられるのではないかと心配しているらしい。
「悪いことは何もないよ。ただ道を案内するだけ。」
「それならいいけど....気をつけてね。」
「うん、ありがとね。」
振り返ると馬に跨ったレオがこちらを見ていた。
「お待たせしました。向かいましょう。」
馬に乗り、風を切って駆け出した。誰かと並走するのはいつ以来だろうか。
「軍は森に隠しているのですか?」
「ああ。まずはそこへ向かう。」
森に潜んだ軍の元へ着くと何故女がいるのかという目線が飛んできた。
「殿下、そちらの女性は?」
「西の道に詳しいらしい。案内してもらうことになった。」
「馬に乗れるんですか?すぐに向かうので?」
「ああ。今日中に移動し、明日の明朝に仕掛ける。時間をかけるほど不利だからな。」
「分かりました。」
レオの言った通り、兵は慣れているようだった。細い獣道で速度を上げても問題なくついてくる。
「遅過ぎますか?」
「もう少し上げられるか?」
「はい。」
数時間の後、開けた地に出た。
日は沈み、仄明るい月が影を見せ始めている。
「今日はここで夜営だ!」
レオの言葉に兵たちは夜営の準備を始める。セラもいつものように木の陰に行こうとしたのだが。
「どこへ行く。」
「あちらの方で私は休みます。」
「ダメだ。テントを用意するからそこを使え。」
「野宿は慣れていますが....」
「1人ならいい....わけでもないがとにかく男だらけの場所で外で寝るな。」
そんな王弟直属の軍が、女に飢えているわけもあるまいに。そう思ってもレオの目は真剣だ。
「数は足りるのですか?」
「足りる。嫌だと言えば俺の隣で寝ることになるが、その方がいいか?」
「勘弁してください。使わせていただきます。」
「そう言われるとちょっとな....」
自分で言っておいて勝手なものだ。王弟と寝たなど、どんな恐ろしい噂に巻き込まれるか分からない。
「ところでお前は戦には参加しないよな?」
「参加するつもりでしたが。」
「ダメだ。帰れ。」
今日はダメ出しが多い。実は口うるさかったのだろうか。
「1人で帰る方が危険だと思いますが。」
別にそんなことはない。ただ、貰ってばかりで落ち着かなかった。それだけだ。
「せめてこの場所で森の陰にでも隠れておかないか?」
「賊は敵に襲われたと知れば恥も全て捨てて逃げ出すのですよ。森の中などすぐに戦いの海です。」
レオはしばし無言になった。
「お前、最初からこのつもりだったな?」
「承知の上かと思っていました。」
「俺は朝帰らせるつもりだった。」
「それは....少し無理がありましたね。」
「なんでお前が憐れむんだ。いいか。俺の側を離れるなよ。お前に死なれるのは困るんだ。」
「そんな簡単に死にません。死ねるものならとっくに死んでます。」
「余計に恐ろしくなった。頼むから無茶はしないでくれ。」
こんな顔もするのか。懇願する顔はなんとなく可愛らしいと思ってしまった。
「分かりました。大人しくしておきます。」
「ああ。戦に出るなら軍議にも参加してくれ。作戦を知っておいてもらう方がいい。」
「村娘が軍議に参加すれば不審に思われると思いますが。」
「気にするな。俺の独断行為には皆慣れている。」
軍の人間の苦労が偲ばれる。
「その前に食事だな。行くぞ。」
「うさぎか鳥でも取ってきましょうか?」
「取れるのか?」
「1、2羽なら取れると思いますが。」
「....鳥もか?」
「弓さえあれば。」
「.....もうお前が何をできると言っても驚かん。獣なら兵が取ってるはずだ。お前は大人しく食べろ。」
呆れられただろうか。菓子の礼が獣では格好がつかないかもしれない。
肉の香ばしい匂いが空に上っていた。セラが普段する野宿とは違って快適な夜営だ。
「殿下、戻られましたか。肉が焼けていますよ。」
「ああ、美味そうだ。セラ、お前も食べろ。」
「いただきます。」
口の中に香ばしさと肉汁が広がる。こんな風に食べるのは久しぶりだ。
「なんだ、ちゃんと食べれるじゃないか」
「肉が美味しかったことを思い出しました。」
「その細い身体をなんとかしろ。普段ロクに食べてないだろ。」
「面倒で....」
半分嘘、半分本当だ。弟たちに優先して食べさせているうちにあまりお腹が空かなくなった。
「次会う時は肉でも持ってくるか?」
「それはちょっと....菓子の方が。」
「菓子の方が贅沢品だぞ?」
「うっ.....」
「甘いのが好きなんだろう?ちゃんと持ってきてやるから食べればいい。」
ニヤリと笑うこの男は狡い男だ。
(殿下が女性相手にこんな顔をなさるとは...)
噂で聞き及んでいた以上に入れ込んでいるらしい主の様子にクシェルはため息をついた。
軍議に参加していたのはクシェル、そして近衛長と思われる男だった。
皆戦には慣れているようだ。
「敵は1000もしくはそれ以上。対する我が軍も1000。仕掛けるのは明朝だ。異論は?」
近衛長と思われる男が口を開いた。
「ありません。しかし攻め方は?分けるほどの兵力はない。」
「兵は二つに分ける。夜の間に城の裏の森へ500を送る。空が白んでくる頃を見計らって2方向から狼煙を上げ、笛を鳴らす。出てきた賊は頭を除いて1人残らず討ち取って構わない。」
王弟という立場ながらレオは戦の経験が豊富なようだった。直属の軍があるくらいだ。普段から戦に出ることがあるのだろう。
「頭だと見分ける方法は?」
「額にルーン文字、骨飾り、血染めの外套などだそうだ。それ以外なら...難しいな。だがなんとしても捕まえたいところだ。」
「承知しました。」
「以上だ。他には?」
「ありません。」
「では解散だ。明日に備えて休め。」
0
あなたにおすすめの小説

愛とオルゴール
夜宮
恋愛
ジェシカは怒っていた。
父親が、同腹の弟ではなく妾の子を跡継ぎにしようとしていることを知ったからだ。
それに、ジェシカの恋人に横恋慕する伯爵令嬢が現れて……。
絡み合った過去と現在。
ジェシカは無事、弟を跡継ぎの座につけ、愛する人との未来を手にすることができるのだろうか。

好感度0になるまで終われません。
チョコパイ
恋愛
土屋千鶴子(享年98歳)
子供や孫、ひ孫に囲まれての大往生。
愛され続けて4度目の転生。
そろそろ……愛されるのに疲れたのですが…
登場人物の好感度0にならない限り終わらない溺愛の日々。
5度目の転生先は娘が遊んでいた乙女ゲームの世界。
いつもと違う展開に今度こそ永久の眠りにつける。
そう信じ、好きなことを、好きなようにやりたい放題…
自覚なし愛され公女と執着一途皇太子のすれ違いラブロマンス。

ヤクザのお嬢は25人の婚約者に迫られてるけど若頭が好き!
タタミ
恋愛
関東最大の極道組織・大蛇組組長の一人娘である大蛇姫子は、18歳の誕生日に父から「今年中に必ず結婚しろ」と命じられる。
姫子の抵抗虚しく、次から次へと夫候補の婚約者(仮)が現れては姫子と見合いをしていくことに。
しかし、姫子には子どもの頃からお目付け役として世話をしてくれている組員・望月大和に淡い恋心を抱き続けていて──?
全25人の婚約者から真実の愛を見つけることはできるのか!?今、抗争より熱い戦いの幕が上がる……!!

結婚したくない腐女子が結婚しました
折原さゆみ
恋愛
倉敷紗々(30歳)、独身。両親に結婚をせがまれて、嫌気がさしていた。
仕方なく、結婚相談所で登録を行うことにした。
本当は、結婚なんてしたくない、子供なんてもってのほか、どうしたものかと考えた彼女が出した結論とは?
※BL(ボーイズラブ)という表現が出てきますが、BL好きには物足りないかもしれません。
主人公の独断と偏見がかなり多いです。そこのところを考慮に入れてお読みください。
※番外編に入り、百合についても語り始めました。
こちらも独断と偏見が多々あるかもしれないのでご注意ください。
※この作品はフィクションです。実際の人物、団体などとは関係ありません。
※番外編を随時更新中。

【完結】捨てられた皇子の探し人 ~偽物公女は「大嫌い」と言われても殿下の幸せを願います~
ゆきのひ
恋愛
二度目の人生は、前世で慕われていた皇子から、憎悪される運命でした…。
騎士の家系に生まれたリュシー。実家の没落により、生きるために皇宮のメイドとなる。そんなリュシーが命じられたのは、廃屋同然の離宮でひっそりと暮らすセレスティアン皇子の世話係。
母を亡くして後ろ盾もなく、皇帝に冷遇されている幼い皇子に心を寄せたリュシーは、皇子が少しでも快適に暮らしていけるよう奮闘し、その姿に皇子はしだいに心開いていく。
そんな皇子との穏やかな日々に幸せを感じていたリュシーだが、ある日、毒を盛られて命を落とした……はずが、目を開けると、公爵令嬢として公爵家のベッドに横たわっていた。けれどその令嬢は、リュシーの死に因縁のある公爵の一人娘……。
望まぬ形で二度目の生を享けたリュシーと、その死に復讐を誓った皇子が、本当に望んでいた幸せを手に入れるまでのお話。
※本作は「小説家になろう」さん、「カクヨム」さんにも投稿しています。
※表紙画像はAIで作成したものです
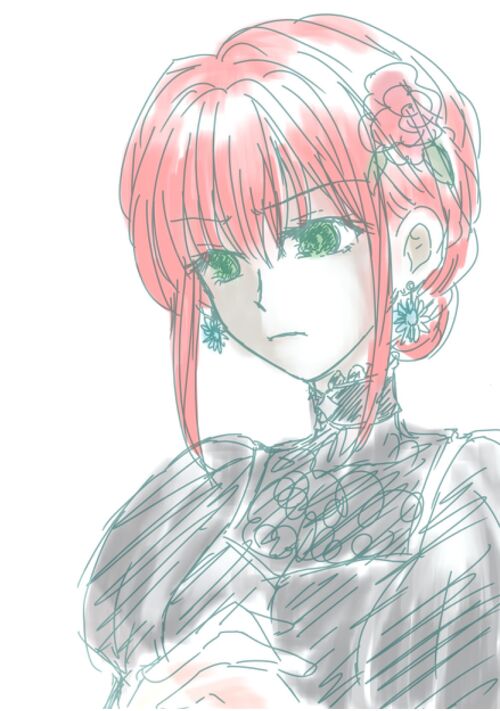
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

公爵家の養女
透明
恋愛
リーナ・フォン・ヴァンディリア
彼女はヴァンディリア公爵家の養女である。
見目麗しいその姿を見て、人々は〝公爵家に咲く一輪の白薔薇〟と評した。
彼女は良くも悪くも常に社交界の中心にいた。
そんな彼女ももう時期、結婚をする。
数多の名家の若い男が彼女に思いを寄せている中、選ばれたのはとある伯爵家の息子だった。
美しき公爵家の白薔薇も、いよいよ人の者になる。
国中ではその話題で持ちきり、彼女に思いを寄せていた男たちは皆、胸を痛める中「リーナ・フォン・ヴァンディリア公女が、盗賊に襲われ逝去された」と伝令が響き渡る。
リーナの死は、貴族たちの関係を大いに揺るがし、一日にして国中を混乱と悲しみに包み込んだ。
そんな事も知らず何故か森で殺された彼女は、自身の寝室のベッドの上で目を覚ましたのだった。
愛に憎悪、帝国の闇
回帰した直後のリーナは、それらが自身の運命に絡んでくると言うことは、この時はまだ、夢にも思っていなかったのだった――
※月曜にから毎週、月、水曜日の朝8:10、金曜日の夜22:00投稿です。
小説家になろう様でも掲載しております。

【13章まで完結】25人の花嫁候補から、獣人の愛され花嫁に選ばれました。
こころ ゆい
恋愛
※十三章まで完結しました。🌱
お好みのものからお読み頂けますと幸いです。🌱
※恋愛カテゴリーに変更です。宜しくお願い致します。🌱
※五章は狐のお話のその後です。🌱
※六章は狼のお話のその後です。🌱
※七章はハシビロコウのお話のその後です。🌱
※九章は雪豹のお話のその後です。🌱
※十一章は白熊のお話のその後です。🌱
ーーそれは、100年ほど前から法で定められた。
国が選んだ25人の花嫁候補。
その中から、正式な花嫁に選ばれるのは一人だけ。
選ばれた者に拒否することは許されず、必ず獣人のもとに嫁いでいくという。
目的はひとつ。獣人たちの習性により、どんどん数を減らしている現状を打破すること。
『人間では持ち得ない高い能力を持つ獣人を、絶やしてはならない』と。
抵抗する国民など居なかった。
現実味のない獣人の花嫁など、夢の話。
興味のない者、本気にしない者、他人事だと捉える者。そんな国民たちによって、法は難なく可決された。
国は候補者選びの基準を、一切明かしていない。
もちろん...獣人が一人を選ぶ選定基準も、謎のまま。
全てをベールに包まれて...いつしかそんな法があること自体、国民たちは忘れ去っていく。
さて。時折、絵本や小説でフィクションの世界として語られるだけになった『花嫁たち』は...本当に存在するのだろうかーー。
皆が知らぬ間に、知らぬところで。
法によって...獣人の意思によって...たった一人の花嫁として選ばれた女の子たちが、個性豊かな獣人たちに溺愛される...これはそんなお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















