24 / 77
24.お手伝いさんの正体
しおりを挟む
24.お手伝いさんの正体
「なっがいトイレだなあ。腹でもこわしてるのかなあ」
おばさんはイライラして言った。
「おばさんが怖くて出られないんじゃないの?」
「ご冗談を」
ぼくはあまり冗談を言うタイプではないと思うんだけど。
「トイレまで様子を見に行こうか?」
おばさんがそう言うので、ぼくたちは1階に降りていき、トイレをノックしてみた。
返事はなかった。
開けてみた。
開いた。
中はもぬけのからだった。
「あなたたち、二人してトイレを覗いたりして、どうしたの?」
ママが不審そうな顔をしてやってきた。
「いや、お手伝いさんが、トイレから逃げた」とおばさんは説明した。
「あらあ、どうしちゃったのかしら? まだ通いにスタンプも押してないのに?」
ママは疑問に思うところが少しぼくたちと違うように思えるんだけれど、まあ、いいか。おばさんはママの言葉に、なにか思いついたように言った。
「ねえ、お手伝いさんの会社の住所わかる?」
「え?住所?どうだったかしら?」
「契約書があるでしょう?」
「あら?そんなものあったかしら?」
「じゃあ、料金はどうやって払うの? 手渡し?」
「いえ、多分、パパが払ってくれるのだと思うわ。わたしが知っているのは緊急の場合の電話番号だけ」
「契約者はパパか・・・ところで、お手伝いさんが仕事中に消えちゃったんだから、とりあえずそこに電話しましょうよ」
「わたしが?」
なんだかママはしぶっているようだった。
「じゃ、わたしがしましょうか?」
「本当? ありがとう。ひかるちゃん、お願い」
ママはもめごととか、めんどくさいことが嫌いなんだ。
ぼくたちはぞろぞろと居間にとって返し、電話機を取り囲んだ。
しかし、この前と同じだった。留守電になっていた。が、今度は折り返しの電話もなかった。
「使えない会社だこと!」
おばさんはぷりぷりして言った。
「こうなったら、なんだわ。別のルートをしめあげるしかないな」
別のルートとは座敷オヤジのことかな? お手伝いさんは座敷オヤジのことは知っているって言ってたもんな。
「いくよ、ヨシヒコ」
「あ、ハ、ハイ」
ぼくたちは二階にとって返した。行き際、ママを振り返ったら、ママはちょっと淋しげな悲しそうな顔をしていた。ぼくはいつぞやの晩、ママがお酒とアマノジャクの力を借りて「里子さんとヨシヒコはいつもひそひそ話し」と嘆いていたのを思い出して気になったが、そのままおばさんの後に従った。
「座敷オヤジ!」
おばさんは椅子に座るとちょっと俯き加減で低く呼ばわった。凄みがあった。一度きりしか呼ばなかったが、しばらくして座敷オヤジが天井の隅の方からじわじわじわっとスライドインしてきた。
姿をあらわすなり、座敷オヤジは苦々しげに言った。
「固定電話でかけるから、コールバックがこないんじゃ。非通知じゃからの。携帯でかけなおしてみ。ちゃーあんと返事が戻ってくるぞ」
「あ、そうか」
おばさんは思わず携帯を取り出し、ボタンをおしかけたが、すぐに思いなおして叫んだ。
「そんなことより、こらっ!座敷オヤジ!オヤジはあのお手伝いさんが何者か知ってるんでしょう? 包み隠さずお言い!」
「いや、包み隠さずだなんて・・・わしは聞かれたことにはちゃんと答えておりますがな。あやつはわしらの眷属か? って聞かれたから、違うと答え、わしがたのんだのか? と聞かれたから違うと、ちゃーんと答えておりましたでしょうが」
「聞かれたことだけに答えて、よけいなことは言わんでおこうという意図がみえみえだよ。なんでそう隠したがるの?」
「いや、別に隠しているわけでは・・・あやつは変化といわれている種類のものだという、ただそれだけのことで・・・この話、まだせんかったかいな? ほれ、昔からよく言われておるじゃろう。妖怪変化とな。その変化のほうじゃ。まだ、話しておらんかったか?」
「聞いてない!」
「さよか」
座敷オヤジは話さなかったのは故意ではないことをさりげなくアピールしながら、もったいをつけつつ話し始めた。
「よくキツネやタヌキに化かされるという話を聞くじゃろう。
実はあれはキツネでもタヌキでもない。
変化とよばれる全く別の生き物でな、高度な擬態能力を持つ生物なのじゃ。ほれ、カメレオンがよく体の色を変えて姿を隠すじゃろう? それの高度なものと思えばよろしい。あやつらは姿も表皮の素材感も変化させることができる。それで、あやつらは時と場所によって姿を変化させて暮らしておるんじゃ。街中にいるときは人間に、山中にいるときはケモノにという具合にな」
「へーそんなのがいたのか。こりゃ初耳だわ」
おばさんは感心したように言った。
「うむ。化け猫といわれているのもほんとうのところは猫ではなくて変化によるものじゃ。あれは飼い猫が歳をとって化けられるようになったのではなくて、飼い猫が歳をとって死んだために変化がその飼い猫になりすまして後釜に納まったというのが真相じゃ。
その証拠に、歳をとったタヌキやキツネやネコをつかまえて、ほら化けろ、ほら化けろといっても化けはせんじゃろう? 人間がキツネやタヌキが化けると思い込んでいるのは、あやつらが正体をあらわして逃げるとき、人間が身近な動物を連想するせいじゃ。そのほうが変化にとっても都合がいいからわざとそういう姿をとって逃げることもあるみたいじゃがの。それでな、」
座敷オヤジは一膝前に進み出て、声をひそめて言った。
「これはちょっとお願いなのじゃが、彼らのことはあまり書かんでやってほしい」
「えー? 書いちゃだめって、そりゃまたなぜに?」
おばさんはもったいないというような顔つきをして言った。
「うむ、なぜなら、あやつらは生身の体を持っているでな、食べて生きていかねばならない。今までは人間と自然の境目のようなところに住んでおって、山には木の実、川には魚、というように食べ物も豊富にあったが、今は木の実が採れるような山も魚が獲れるような川もない。あやつらは人間の格好をして、人間の社会で働いて食べていかねばならない。
わしらのように都合が悪ければ出てこなくてすませる、というわけにはいかんのじゃ。正体がばれるというのは死活問題でかわいそうじゃ」
「うーん・・・書いたところでフィクションと受け取られるだけだ思うけど……しかし、危険なことってないかな?」
「あやつらにとって? 人間にとって?」
「人間にとって。例えばさ、先ほどの化け猫の話だけど、飼い猫を殺して、その猫に成りすますとかさ」
「ふうむ、人間を殺してその人間に成りすますことがないか、ということが聞きたいのかな?」
「ええ、まあ・・・」
「まあ、普通はない。なぜなら、やつらは非常に臆病じゃ。気が小さい。頭も人間ほどよくはない。また、化けるのには相当なエネルギーを必要とする。つまり化けるのはしんどいんじゃ。また、化けていられる時間も限られていて、一定の周期で姿が元に戻る。その時間には個人差があるが、たいていはトイレに駆け込むことで姿を整えているみたいじゃな。人を殺して、その人間に成りすます、なんてことは人間の考えることじゃ。考えてみたら人間が一番凶暴じゃな」
ぼくは座敷オヤジが「普通はない」ということに引っかかっていた。「普通はない」ということは、特別の場合ならあるということなのか? 人間にも犯罪者はいる。変化の中にもそうした犯罪者がいるのではないか?
ぼくがそんなことをぼんやり考えていたら、目の前の座敷オヤジが大きなため息をついた。
「そんなことより、ちと心配なことがあってな」
「あれ、座敷オヤジでも心配なことってあるのかいな?」
おばさんがからかうように言った。
「そりゃあある。昨日からオキビキとアマノジャクが飲みにいったっきり帰ってこんのじゃ。アマノジャクは渡り者だから別として、オキビキは家付きじゃから、帰ってこないというのは珍しい。なんかあったのか心配しておる。また、わしが行け、と言ったので責任も感じておるんじゃが・・・」
「なっがいトイレだなあ。腹でもこわしてるのかなあ」
おばさんはイライラして言った。
「おばさんが怖くて出られないんじゃないの?」
「ご冗談を」
ぼくはあまり冗談を言うタイプではないと思うんだけど。
「トイレまで様子を見に行こうか?」
おばさんがそう言うので、ぼくたちは1階に降りていき、トイレをノックしてみた。
返事はなかった。
開けてみた。
開いた。
中はもぬけのからだった。
「あなたたち、二人してトイレを覗いたりして、どうしたの?」
ママが不審そうな顔をしてやってきた。
「いや、お手伝いさんが、トイレから逃げた」とおばさんは説明した。
「あらあ、どうしちゃったのかしら? まだ通いにスタンプも押してないのに?」
ママは疑問に思うところが少しぼくたちと違うように思えるんだけれど、まあ、いいか。おばさんはママの言葉に、なにか思いついたように言った。
「ねえ、お手伝いさんの会社の住所わかる?」
「え?住所?どうだったかしら?」
「契約書があるでしょう?」
「あら?そんなものあったかしら?」
「じゃあ、料金はどうやって払うの? 手渡し?」
「いえ、多分、パパが払ってくれるのだと思うわ。わたしが知っているのは緊急の場合の電話番号だけ」
「契約者はパパか・・・ところで、お手伝いさんが仕事中に消えちゃったんだから、とりあえずそこに電話しましょうよ」
「わたしが?」
なんだかママはしぶっているようだった。
「じゃ、わたしがしましょうか?」
「本当? ありがとう。ひかるちゃん、お願い」
ママはもめごととか、めんどくさいことが嫌いなんだ。
ぼくたちはぞろぞろと居間にとって返し、電話機を取り囲んだ。
しかし、この前と同じだった。留守電になっていた。が、今度は折り返しの電話もなかった。
「使えない会社だこと!」
おばさんはぷりぷりして言った。
「こうなったら、なんだわ。別のルートをしめあげるしかないな」
別のルートとは座敷オヤジのことかな? お手伝いさんは座敷オヤジのことは知っているって言ってたもんな。
「いくよ、ヨシヒコ」
「あ、ハ、ハイ」
ぼくたちは二階にとって返した。行き際、ママを振り返ったら、ママはちょっと淋しげな悲しそうな顔をしていた。ぼくはいつぞやの晩、ママがお酒とアマノジャクの力を借りて「里子さんとヨシヒコはいつもひそひそ話し」と嘆いていたのを思い出して気になったが、そのままおばさんの後に従った。
「座敷オヤジ!」
おばさんは椅子に座るとちょっと俯き加減で低く呼ばわった。凄みがあった。一度きりしか呼ばなかったが、しばらくして座敷オヤジが天井の隅の方からじわじわじわっとスライドインしてきた。
姿をあらわすなり、座敷オヤジは苦々しげに言った。
「固定電話でかけるから、コールバックがこないんじゃ。非通知じゃからの。携帯でかけなおしてみ。ちゃーあんと返事が戻ってくるぞ」
「あ、そうか」
おばさんは思わず携帯を取り出し、ボタンをおしかけたが、すぐに思いなおして叫んだ。
「そんなことより、こらっ!座敷オヤジ!オヤジはあのお手伝いさんが何者か知ってるんでしょう? 包み隠さずお言い!」
「いや、包み隠さずだなんて・・・わしは聞かれたことにはちゃんと答えておりますがな。あやつはわしらの眷属か? って聞かれたから、違うと答え、わしがたのんだのか? と聞かれたから違うと、ちゃーんと答えておりましたでしょうが」
「聞かれたことだけに答えて、よけいなことは言わんでおこうという意図がみえみえだよ。なんでそう隠したがるの?」
「いや、別に隠しているわけでは・・・あやつは変化といわれている種類のものだという、ただそれだけのことで・・・この話、まだせんかったかいな? ほれ、昔からよく言われておるじゃろう。妖怪変化とな。その変化のほうじゃ。まだ、話しておらんかったか?」
「聞いてない!」
「さよか」
座敷オヤジは話さなかったのは故意ではないことをさりげなくアピールしながら、もったいをつけつつ話し始めた。
「よくキツネやタヌキに化かされるという話を聞くじゃろう。
実はあれはキツネでもタヌキでもない。
変化とよばれる全く別の生き物でな、高度な擬態能力を持つ生物なのじゃ。ほれ、カメレオンがよく体の色を変えて姿を隠すじゃろう? それの高度なものと思えばよろしい。あやつらは姿も表皮の素材感も変化させることができる。それで、あやつらは時と場所によって姿を変化させて暮らしておるんじゃ。街中にいるときは人間に、山中にいるときはケモノにという具合にな」
「へーそんなのがいたのか。こりゃ初耳だわ」
おばさんは感心したように言った。
「うむ。化け猫といわれているのもほんとうのところは猫ではなくて変化によるものじゃ。あれは飼い猫が歳をとって化けられるようになったのではなくて、飼い猫が歳をとって死んだために変化がその飼い猫になりすまして後釜に納まったというのが真相じゃ。
その証拠に、歳をとったタヌキやキツネやネコをつかまえて、ほら化けろ、ほら化けろといっても化けはせんじゃろう? 人間がキツネやタヌキが化けると思い込んでいるのは、あやつらが正体をあらわして逃げるとき、人間が身近な動物を連想するせいじゃ。そのほうが変化にとっても都合がいいからわざとそういう姿をとって逃げることもあるみたいじゃがの。それでな、」
座敷オヤジは一膝前に進み出て、声をひそめて言った。
「これはちょっとお願いなのじゃが、彼らのことはあまり書かんでやってほしい」
「えー? 書いちゃだめって、そりゃまたなぜに?」
おばさんはもったいないというような顔つきをして言った。
「うむ、なぜなら、あやつらは生身の体を持っているでな、食べて生きていかねばならない。今までは人間と自然の境目のようなところに住んでおって、山には木の実、川には魚、というように食べ物も豊富にあったが、今は木の実が採れるような山も魚が獲れるような川もない。あやつらは人間の格好をして、人間の社会で働いて食べていかねばならない。
わしらのように都合が悪ければ出てこなくてすませる、というわけにはいかんのじゃ。正体がばれるというのは死活問題でかわいそうじゃ」
「うーん・・・書いたところでフィクションと受け取られるだけだ思うけど……しかし、危険なことってないかな?」
「あやつらにとって? 人間にとって?」
「人間にとって。例えばさ、先ほどの化け猫の話だけど、飼い猫を殺して、その猫に成りすますとかさ」
「ふうむ、人間を殺してその人間に成りすますことがないか、ということが聞きたいのかな?」
「ええ、まあ・・・」
「まあ、普通はない。なぜなら、やつらは非常に臆病じゃ。気が小さい。頭も人間ほどよくはない。また、化けるのには相当なエネルギーを必要とする。つまり化けるのはしんどいんじゃ。また、化けていられる時間も限られていて、一定の周期で姿が元に戻る。その時間には個人差があるが、たいていはトイレに駆け込むことで姿を整えているみたいじゃな。人を殺して、その人間に成りすます、なんてことは人間の考えることじゃ。考えてみたら人間が一番凶暴じゃな」
ぼくは座敷オヤジが「普通はない」ということに引っかかっていた。「普通はない」ということは、特別の場合ならあるということなのか? 人間にも犯罪者はいる。変化の中にもそうした犯罪者がいるのではないか?
ぼくがそんなことをぼんやり考えていたら、目の前の座敷オヤジが大きなため息をついた。
「そんなことより、ちと心配なことがあってな」
「あれ、座敷オヤジでも心配なことってあるのかいな?」
おばさんがからかうように言った。
「そりゃあある。昨日からオキビキとアマノジャクが飲みにいったっきり帰ってこんのじゃ。アマノジャクは渡り者だから別として、オキビキは家付きじゃから、帰ってこないというのは珍しい。なんかあったのか心配しておる。また、わしが行け、と言ったので責任も感じておるんじゃが・・・」
0
あなたにおすすめの小説

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。


9日間
柏木みのり
児童書・童話
サマーキャンプから友達の健太と一緒に隣の世界に迷い込んだ竜(リョウ)は文武両道の11歳。魔法との出会い。人々との出会い。初めて経験する様々な気持ち。そして究極の選択——夢か友情か。
(also @ なろう)

【完結】カラフルな妖精たち
ひなこ
児童書・童話
星野愛虹(ほしの・あにー)は小学五年女子。絵を描くのが大好き。ある日、絵を描いていると色の妖精・彩(サイ)の一人、レッドに出会う。レッドはガスの火を変化させて見せる。サイは自分の色と同じ物質をあやつり、人の心にまで影響できる力を持つ。さらにそのサイを自由に使えるのが、愛虹たち”色使い”だ。
最近、学校では水曜日だけ現れるという「赤の魔女」が恐れられていた。が、実はサイの仲間で凶悪な「ノワール」が関わっていた。ノワールは、人間の心の隙間に入り込むことを狙っている。彼を封印するには、必要な色のサイたちをうまく集めなくてはいけない。愛虹の所有するサイは、目下、赤と白。それでは足りず、さらに光のカギもないといけない。一体どこにあるの?仲間を探し、サイを探し。
これは愛虹と仲間たちが、たくさんの色をめぐって奮闘する冒険物語。児童向け、コミカルタッチの色彩ファンタジーです。

荒川ハツコイ物語~宇宙から来た少女と過ごした小学生最後の夏休み~
釈 余白(しやく)
児童書・童話
今より少し前の時代には、子供らが荒川土手に集まって遊ぶのは当たり前だったらしい。野球をしたり凧揚げをしたり釣りをしたり、時には決闘したり下級生の自転車練習に付き合ったりと様々だ。
そんな話を親から聞かされながら育ったせいなのか、僕らの遊び場はもっぱら荒川土手だった。もちろん小学生最後となる六年生の夏休みもいつもと変わらず、いつものように幼馴染で集まってありきたりの遊びに精を出す毎日である。
そして今日は鯉釣りの予定だ。今まで一度も釣り上げたことのない鯉を小学生のうちに釣り上げるのが僕、田口暦(たぐち こよみ)の目標だった。
今日こそはと強い意気込みで釣りを始めた僕だったが、初めての鯉と出会う前に自分を宇宙人だと言う女子、ミクに出会い一目で恋に落ちてしまった。だが夏休みが終わるころには自分の星へ帰ってしまうと言う。
かくして小学生最後の夏休みは、彼女が帰る前に何でもいいから忘れられないくらいの思い出を作り、特別なものにするという目的が最優先となったのだった。
はたして初めての鯉と初めての恋の両方を成就させることができるのだろうか。
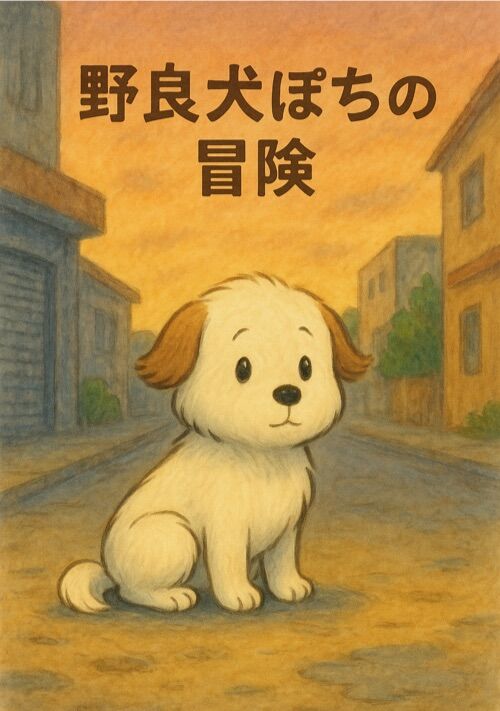
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

生まれたばかりですが、早速赤ちゃんセラピー?始めます!
mabu
児童書・童話
超ラッキーな環境での転生と思っていたのにママさんの体調が危ないんじゃぁないの?
ママさんが大好きそうなパパさんを闇落ちさせない様に赤ちゃんセラピーで頑張ります。
力を使って魔力を増やして大きくなったらチートになる!
ちょっと赤ちゃん系に挑戦してみたくてチャレンジしてみました。
読みにくいかもしれませんが宜しくお願いします。
誤字や意味がわからない時は皆様の感性で受け捉えてもらえると助かります。
流れでどうなるかは未定なので一応R15にしております。
現在投稿中の作品と共に地道にマイペースで進めていきますので宜しくお願いします🙇
此方でも感想やご指摘等への返答は致しませんので宜しくお願いします。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















