100 / 315
第100話 謎が増えていく
しおりを挟む
「ね、眠ろうとしていたわけではありません。目を伏せて考えをまとめようとしまして」
眠りかけていた私だったけれど、ちゃんと言い訳してみた。
「で。まとまったか?」
殿下は即座に答えを求めてくる困ったお方だ。
私は笑って誤魔化しながら話してみる。
「ええっと。そういえば、過去にネロのような影祓いする存在はありましたか?」
「いや。調べた範囲では無かったな。だからこそ君の存在に驚いたわけだが」
「そうですか」
これまでの王族がそういった人物に出会っていなかっただけなのか。そもそも存在しなかったのか。
「でしたら、これまでの王族の方は大変でしたでしょうね。呪術師様による影祓いはつらいと殿下はおっしゃっておりましたし」
「そうだな。自分である程度避けるにしても、どうしても近距離で接触しなければならない時は取り憑かれてしまうからな」
ある程度避ける、避けるかぁ……。影が見られることも一概に悪いわけではな――あれ。
「殿下、影を見慣れたとおっしゃっていましたね」
「ああ。それが?」
「恐怖で精神がおかしくなったりはしないのですか?」
「……ご覧の通りだが?」
おかしく見えるかと殿下は手を広げて笑ってみせる。
「失礼いたしました。では、過去にそういう方はいらっしゃいましたか?」
「精神が崩壊した人間か? いや、そんな記録は無いな。肉体が病に侵されて精神を病んだ者はいるようだが、恐怖でということはない。皆、幼少期からで慣れてしまっているのだろう。私も幼い頃は怖かったが、今じゃ慣れた」
まあ、ネロは驚いたがと殿下は気まずそうに付け加えた。
私もいつもなら突っ込むところを本日は突っ込まない。今浮かんできた考えをまとめることに必死だからだ。
「そうですか。だとしたら呪う対象者が慣れてしまっては、復讐にはならないのでは?」
「何が言いたい?」
私の真剣な様子に殿下もまた眉をひそめた。
「呪われた者の共通点として、皆一様に影が見えるのですよね。おそらくこの能力も呪いと共に引き継いでいるのでしょう。ですが、ルイス王太子殿下の恋人であった魔術師様は、果たして呪いの中に影を見せる能力を付加させる必要があったのでしょうか」
原因不明の病として発症させる方が、余程恐ろしいのではないだろうか。
「確かにそうだが、彼女の呪いだと思い知らせるためにそうしたのでは?」
ああ、そっか。なるほど。少々考えが先走りしすぎていたかな。でも一応考えを伝えよう。
「そうですね。そういう考えもありましたね。しかし、その視覚能力で原因が影によるものだと判明した場合、その影を避けるよう行動することができてしまいます。それだと――あ! そ、そうだわ」
今、急激にふっとある考えが思いつき、私は自分の左手首内側を指してみせる。
「呪いだと分からせるためなら、殿下もお持ちの星紋だけでも十分では?」
星紋のことは殿下から聞いたではないか。確かこれも共通点だったはず。
「……そうだな。呪いを受けた者に共通している点ではある」
「でしょう! 前回でも書物の絵を指してわたくしにおっしゃったではありませんか」
もちろん影が見えることありきで調べていく内に、呪いを掛けられた者には星紋が出るというところに辿り着いた事実も否定はできないけれども。
「だとしたらなぜ彼女は呪いに影が見える能力を付加した?」
「それはですね」
私は生唾をごくんと飲み込んだ。
「それは?」
「それは……」
真剣な表情の殿下に、私もまた硬い表情を作ってみせる。
「それは――わ」
「分かりません、だな?」
「……ええ。その通りです。分かりません。申し訳ございません」
諦めてしおらしく謝ると殿下は笑った。
「いや。これまで何年も何百年も関わってきた私たち王族ですら分からなかったことだ。君に答えを求めるのは間違っている」
私は気が抜けたようにため息を吐く。
「わたくしが謎を解こうと関われば関わるほど、かえって増えていきますね」
それとも私が勝手に難しくしているだけで、この事実を事実として受け入れるべきなのだろうか。
「確かに謎は増える一方だ。しかし客観的な目が入ることで、物の見方が変わるのはいいことだと思う」
「ありがとうございます、殿下」
「いや。こちらこそありがとう。――とにかく疲れたし、今日はここまでにしよう」
というわけで、本日はこれにてお開きとなった。
眠りかけていた私だったけれど、ちゃんと言い訳してみた。
「で。まとまったか?」
殿下は即座に答えを求めてくる困ったお方だ。
私は笑って誤魔化しながら話してみる。
「ええっと。そういえば、過去にネロのような影祓いする存在はありましたか?」
「いや。調べた範囲では無かったな。だからこそ君の存在に驚いたわけだが」
「そうですか」
これまでの王族がそういった人物に出会っていなかっただけなのか。そもそも存在しなかったのか。
「でしたら、これまでの王族の方は大変でしたでしょうね。呪術師様による影祓いはつらいと殿下はおっしゃっておりましたし」
「そうだな。自分である程度避けるにしても、どうしても近距離で接触しなければならない時は取り憑かれてしまうからな」
ある程度避ける、避けるかぁ……。影が見られることも一概に悪いわけではな――あれ。
「殿下、影を見慣れたとおっしゃっていましたね」
「ああ。それが?」
「恐怖で精神がおかしくなったりはしないのですか?」
「……ご覧の通りだが?」
おかしく見えるかと殿下は手を広げて笑ってみせる。
「失礼いたしました。では、過去にそういう方はいらっしゃいましたか?」
「精神が崩壊した人間か? いや、そんな記録は無いな。肉体が病に侵されて精神を病んだ者はいるようだが、恐怖でということはない。皆、幼少期からで慣れてしまっているのだろう。私も幼い頃は怖かったが、今じゃ慣れた」
まあ、ネロは驚いたがと殿下は気まずそうに付け加えた。
私もいつもなら突っ込むところを本日は突っ込まない。今浮かんできた考えをまとめることに必死だからだ。
「そうですか。だとしたら呪う対象者が慣れてしまっては、復讐にはならないのでは?」
「何が言いたい?」
私の真剣な様子に殿下もまた眉をひそめた。
「呪われた者の共通点として、皆一様に影が見えるのですよね。おそらくこの能力も呪いと共に引き継いでいるのでしょう。ですが、ルイス王太子殿下の恋人であった魔術師様は、果たして呪いの中に影を見せる能力を付加させる必要があったのでしょうか」
原因不明の病として発症させる方が、余程恐ろしいのではないだろうか。
「確かにそうだが、彼女の呪いだと思い知らせるためにそうしたのでは?」
ああ、そっか。なるほど。少々考えが先走りしすぎていたかな。でも一応考えを伝えよう。
「そうですね。そういう考えもありましたね。しかし、その視覚能力で原因が影によるものだと判明した場合、その影を避けるよう行動することができてしまいます。それだと――あ! そ、そうだわ」
今、急激にふっとある考えが思いつき、私は自分の左手首内側を指してみせる。
「呪いだと分からせるためなら、殿下もお持ちの星紋だけでも十分では?」
星紋のことは殿下から聞いたではないか。確かこれも共通点だったはず。
「……そうだな。呪いを受けた者に共通している点ではある」
「でしょう! 前回でも書物の絵を指してわたくしにおっしゃったではありませんか」
もちろん影が見えることありきで調べていく内に、呪いを掛けられた者には星紋が出るというところに辿り着いた事実も否定はできないけれども。
「だとしたらなぜ彼女は呪いに影が見える能力を付加した?」
「それはですね」
私は生唾をごくんと飲み込んだ。
「それは?」
「それは……」
真剣な表情の殿下に、私もまた硬い表情を作ってみせる。
「それは――わ」
「分かりません、だな?」
「……ええ。その通りです。分かりません。申し訳ございません」
諦めてしおらしく謝ると殿下は笑った。
「いや。これまで何年も何百年も関わってきた私たち王族ですら分からなかったことだ。君に答えを求めるのは間違っている」
私は気が抜けたようにため息を吐く。
「わたくしが謎を解こうと関われば関わるほど、かえって増えていきますね」
それとも私が勝手に難しくしているだけで、この事実を事実として受け入れるべきなのだろうか。
「確かに謎は増える一方だ。しかし客観的な目が入ることで、物の見方が変わるのはいいことだと思う」
「ありがとうございます、殿下」
「いや。こちらこそありがとう。――とにかく疲れたし、今日はここまでにしよう」
というわけで、本日はこれにてお開きとなった。
37
あなたにおすすめの小説

王宮に薬を届けに行ったなら
佐倉ミズキ
恋愛
王宮で薬師をしているラナは、上司の言いつけに従い王子殿下のカザヤに薬を届けに行った。
カザヤは生まれつき体が弱く、臥せっていることが多い。
この日もいつも通り、カザヤに薬を届けに行ったラナだが仕事終わりに届け忘れがあったことに気が付いた。
慌ててカザヤの部屋へ行くと、そこで目にしたものは……。
弱々しく臥せっているカザヤがベッドから起き上がり、元気に動き回っていたのだ。
「俺の秘密を知ったのだから部屋から出すわけにはいかない」
驚くラナに、カザヤは不敵な笑みを浮かべた。
「今日、国王が崩御する。だからお前を部屋から出すわけにはいかない」
※ベリーズカフェにも掲載中です。そちらではラナの設定が変わっています。(貴族→庶民)それにより、内容も少し変更しておりますのであわせてお楽しみください。

身分差婚~あなたの妻になれないはずだった~
椿蛍
恋愛
「息子と別れていただけないかしら?」
私を脅して、別れを決断させた彼の両親。
彼は高級住宅地『都久山』で王子様と呼ばれる存在。
私とは住む世界が違った……
別れを命じられ、私の恋が終わった。
叶わない身分差の恋だったはずが――
※R-15くらいなので※マークはありません。
※視点切り替えあり。
※2日間は1日3回更新、3日目から1日2回更新となります。
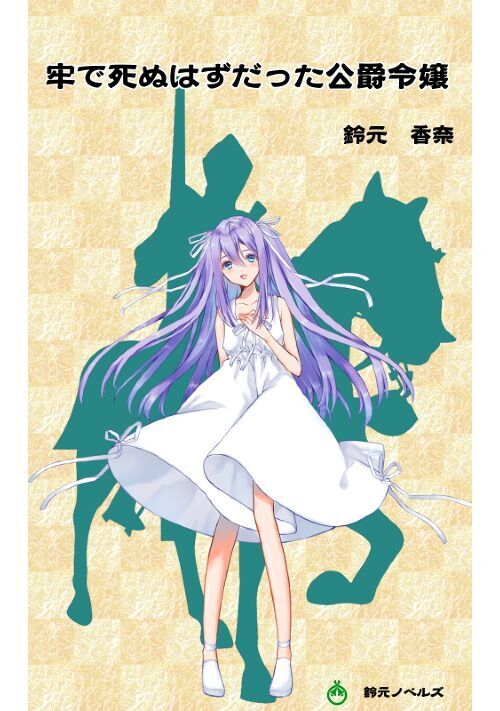
牢で死ぬはずだった公爵令嬢
鈴元 香奈
恋愛
婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。
表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。
小説家になろうさんにも投稿しています。

アンジェリーヌは一人じゃない
れもんぴーる
恋愛
義母からひどい扱いされても我慢をしているアンジェリーヌ。
メイドにも冷遇され、昔は仲が良かった婚約者にも冷たい態度をとられ居場所も逃げ場所もなくしていた。
そんな時、アルコール入りのチョコレートを口にしたアンジェリーヌの性格が激変した。
まるで別人になったように、言いたいことを言い、これまで自分に冷たかった家族や婚約者をこぎみよく切り捨てていく。
実は、アンジェリーヌの中にずっといた魂と入れ替わったのだ。
それはアンジェリーヌと一緒に生まれたが、この世に誕生できなかったアンジェリーヌの双子の魂だった。
新生アンジェリーヌはアンジェリーヌのため自由を求め、家を出る。
アンジェリーヌは満ち足りた生活を送り、愛する人にも出会うが、この身体は自分の物ではない。出来る事なら消えてしまった可哀そうな自分の半身に幸せになってもらいたい。でもそれは自分が消え、愛する人との別れの時。
果たしてアンジェリーヌの魂は戻ってくるのか。そしてその時もう一人の魂は・・・。
*タグに「平成の歌もあります」を追加しました。思っていたより歌に注目していただいたので(*´▽`*)
(なろうさま、カクヨムさまにも投稿予定です)

いくら政略結婚だからって、そこまで嫌わなくてもいいんじゃないですか?いい加減、腹が立ってきたんですけど!
夢呼
恋愛
伯爵令嬢のローゼは大好きな婚約者アーサー・レイモンド侯爵令息との結婚式を今か今かと待ち望んでいた。
しかし、結婚式の僅か10日前、その大好きなアーサーから「私から愛されたいという思いがあったら捨ててくれ。それに応えることは出来ない」と告げられる。
ローゼはその言葉にショックを受け、熱を出し寝込んでしまう。数日間うなされ続け、やっと目を覚ました。前世の記憶と共に・・・。
愛されることは無いと分かっていても、覆すことが出来ないのが貴族間の政略結婚。日本で生きたアラサー女子の「私」が八割心を占めているローゼが、この政略結婚に臨むことになる。
いくら政略結婚といえども、親に孫を見せてあげて親孝行をしたいという願いを持つローゼは、何とかアーサーに振り向いてもらおうと頑張るが、鉄壁のアーサーには敵わず。それどころか益々嫌われる始末。
一体私の何が気に入らないんだか。そこまで嫌わなくてもいいんじゃないんですかね!いい加減腹立つわっ!
世界観はゆるいです!
カクヨム様にも投稿しております。
※10万文字を超えたので長編に変更しました。

0歳児に戻った私。今度は少し口を出したいと思います。
アズやっこ
恋愛
❈ 追記 長編に変更します。
16歳の時、私は第一王子と婚姻した。
いとこの第一王子の事は好き。でもこの好きはお兄様を思う好きと同じ。だから第二王子の事も好き。
私の好きは家族愛として。
第一王子と婚約し婚姻し家族愛とはいえ愛はある。だから何とかなる、そう思った。
でも人の心は何とかならなかった。
この国はもう終わる…
兄弟の対立、公爵の裏切り、まるでボタンの掛け違い。
だから歪み取り返しのつかない事になった。
そして私は暗殺され…
次に目が覚めた時0歳児に戻っていた。
❈ 作者独自の世界観です。
❈ 作者独自の設定です。こういう設定だとご了承頂けると幸いです。

【完結】地味な私と公爵様
ベル
恋愛
ラエル公爵。この学園でこの名を知らない人はいないでしょう。
端正な顔立ちに甘く低い声、時折見せる少年のような笑顔。誰もがその美しさに魅了され、女性なら誰もがラエル様との結婚を夢見てしまう。
そんな方が、平凡...いや、かなり地味で目立たない伯爵令嬢である私の婚約者だなんて一体誰が信じるでしょうか。
...正直私も信じていません。
ラエル様が、私を溺愛しているなんて。
きっと、きっと、夢に違いありません。
お読みいただきありがとうございます。短編のつもりで書き始めましたが、意外と話が増えて長編に変更し、無事完結しました(*´-`)

【完結】一番腹黒いのはだあれ?
やまぐちこはる
恋愛
■□■
貧しいコイント子爵家のソンドールは、貴族学院には進学せず、騎士学校に通って若くして正騎士となった有望株である。
三歳でコイント家に養子に来たソンドールの生家はパートルム公爵家。
しかし、関わりを持たずに生きてきたため、自分が公爵家生まれだったことなどすっかり忘れていた。
ある日、実の父がソンドールに会いに来て、自分の出自を改めて知り、勝手なことを言う実父に憤りながらも、生家の騒動に巻き込まれていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















