183 / 315
第183話 ベルモンテ侯爵家の噂
しおりを挟む
門扉から屋敷までは遠いため、馬車のまま中へどうぞと通されたので、私たちは一度馬車の中に戻る。
「あのさ、ロザンヌ嬢」
「はい」
「マリアンジェラ嬢の見舞いを強行したかったのは、先日のクラウディア・ベルモンテ嬢との一件があったから?」
「え?」
セリアン様は座席に手を置いて足を組むと肩をすくめた。
「ベルモンテ侯爵家の黒い噂は公然の秘密みたいなもんだよ。皆、知っているけど、もし万が一目を付けられたらと怖くて誰も口に出さないだけ。君もそうだろ?」
ここは素直に頷いておく。他にマリアンジェラ様のお見舞いに来たかった理由を見付けることができないから。
「はい。とは言え、クラウディア様がマリアンジェラ様にのろ、ど、毒を盛ったとか何かしたという確信も証拠ももちろん無いのですが。……ところでセリアン様はベルモンテ侯爵家のどんな噂をご存知ですか」
「例えばその昔、政敵にスパイを忍び込ませたり、嵌めたり、暗殺などを請け負っていたとかかな」
呪いではなくても、手出しはいくらでもできるということ?
思わず青ざめてしまった私にセリアン様は小さく笑う。
「噂だよ、噂。ベルモンテ侯爵家と言えど、今の地位を確立している以上、そうそう黒いことに手を染められないよ。……と思うよ」
思うよ、が怖い!
当然ながら、私の噂話とは桁違いのお話である。
「何より証拠が無いし。――あ、これは内緒ね。過去には王家も血族同士の争いで、彼らを利用したとされているから王族も手を出せない案件らしい。別名、王家お抱え始末屋、または掃除屋かな」
同じく掃除婦として共感を――するわけない。
「わたくしにそんなお話をして構わないのですか」
「これも噂だよ。それに君は友達だからね」
にっと笑うセリアン様は私に罪悪感をここぞとばかりに与えてくる。しかし、もしかしたらそれが彼の手かもしれないので、ここは罪悪感を軽く無視しておくことにする。
それにしてもベルモンテ家が呪術師ということは知られていないのかな。
「あと、呪いを掛けたりとか」
「――っ! の、呪いですか?」
考えを読まれたようで、私は思わず顔を引きつらせて笑った。しかしそれは私が怖がっているという信憑性を増したようだ。
「ベルモンテ侯爵家は元々、呪術師家系だったんだよ。そこから貴族にまで成り上がったんだ」
殿下もそのような事を言っていた。さらに突き詰めると、王家お抱え占術師の分家だったと。
「そうなのですか」
「うん。それなりに歴史のある貴族はベルモンテの出自を知っていて、未だ忌み嫌っているよ。成り上がりの掃除屋ごときがってね。由緒ある伯爵家の貴族ですら陰では彼らを蔑んでいる」
「侯爵家まで上り詰めてなおですか?」
セリアン様は自嘲するように笑う。
「君も知っての通り、貴族っていうのはさ、見栄と体裁で成り立っているからね。出自については何年経っても何百年経ってもうるさいんだよ」
クラウディア嬢が侯爵令嬢ながら、下級貴族に対してあれだけの尊大な態度を取るのはそれが原因なのかもしれない。力を誇示しないと威厳が保たれないのだろう。
「セリアン様は呪術や呪いを信じますか?」
「まあ、あるんじゃない」
意外だ。セリアン様なら笑い飛ばすかと思っていた。
「人の悪意っていうのは目に見えなくても時に強い力を持って、周りに伝播させたりするからね。呪術や呪いが存在していてもおかしくない。君はどう? 信じる?」
「正直、自分の目に見えないもの、証明できないものを絶対存在するとは、わたくしの口からは言い切れません。ですが、信頼できる人や信頼したい人の言葉ならわたくしは信じたいと思っていますし、信じます」
「なるほど。それはいいね」
今度は皮肉っぽくではなく、セリアン様は穏やかな笑みを浮かべた。
「ところで……お話が変わりまして一つ疑問があるのですが、よろしいでしょうか」
さっきの会話で引っかかった所を尋ねてみる。
「うん。何?」
「先ほど侍従長様は、本日もお嬢様は今おもてなしできる状態ではないとおっしゃいました。本日はではなく、本日もとはどういうことでしょうか」
「え?」
「セリアン様、前にもお見舞いに来られていたのですか?」
誤魔化される前に私は直接言葉をぶつけてみた。するとセリアン様は参ったなと髪をがしがしと掻いた。
「まあね。一応、マリアンジェラとは幼なじみだからね。容易く動けないエルベルトと違って見舞いぐらいするよ」
「ほほう。マリアンジェラとな」
しかもやはり殿下が簡単に動けないと分かっていたんだ。本当に食えない人。
「その余裕ぶった顔、止めてくれない? むかつくんだけど」
「ありがとう存じます」
「何でそこで礼を言う」
セリアン様の嫌そうな突っ込みが入ったその時、馬車は緩やかに止まった。
「あのさ、ロザンヌ嬢」
「はい」
「マリアンジェラ嬢の見舞いを強行したかったのは、先日のクラウディア・ベルモンテ嬢との一件があったから?」
「え?」
セリアン様は座席に手を置いて足を組むと肩をすくめた。
「ベルモンテ侯爵家の黒い噂は公然の秘密みたいなもんだよ。皆、知っているけど、もし万が一目を付けられたらと怖くて誰も口に出さないだけ。君もそうだろ?」
ここは素直に頷いておく。他にマリアンジェラ様のお見舞いに来たかった理由を見付けることができないから。
「はい。とは言え、クラウディア様がマリアンジェラ様にのろ、ど、毒を盛ったとか何かしたという確信も証拠ももちろん無いのですが。……ところでセリアン様はベルモンテ侯爵家のどんな噂をご存知ですか」
「例えばその昔、政敵にスパイを忍び込ませたり、嵌めたり、暗殺などを請け負っていたとかかな」
呪いではなくても、手出しはいくらでもできるということ?
思わず青ざめてしまった私にセリアン様は小さく笑う。
「噂だよ、噂。ベルモンテ侯爵家と言えど、今の地位を確立している以上、そうそう黒いことに手を染められないよ。……と思うよ」
思うよ、が怖い!
当然ながら、私の噂話とは桁違いのお話である。
「何より証拠が無いし。――あ、これは内緒ね。過去には王家も血族同士の争いで、彼らを利用したとされているから王族も手を出せない案件らしい。別名、王家お抱え始末屋、または掃除屋かな」
同じく掃除婦として共感を――するわけない。
「わたくしにそんなお話をして構わないのですか」
「これも噂だよ。それに君は友達だからね」
にっと笑うセリアン様は私に罪悪感をここぞとばかりに与えてくる。しかし、もしかしたらそれが彼の手かもしれないので、ここは罪悪感を軽く無視しておくことにする。
それにしてもベルモンテ家が呪術師ということは知られていないのかな。
「あと、呪いを掛けたりとか」
「――っ! の、呪いですか?」
考えを読まれたようで、私は思わず顔を引きつらせて笑った。しかしそれは私が怖がっているという信憑性を増したようだ。
「ベルモンテ侯爵家は元々、呪術師家系だったんだよ。そこから貴族にまで成り上がったんだ」
殿下もそのような事を言っていた。さらに突き詰めると、王家お抱え占術師の分家だったと。
「そうなのですか」
「うん。それなりに歴史のある貴族はベルモンテの出自を知っていて、未だ忌み嫌っているよ。成り上がりの掃除屋ごときがってね。由緒ある伯爵家の貴族ですら陰では彼らを蔑んでいる」
「侯爵家まで上り詰めてなおですか?」
セリアン様は自嘲するように笑う。
「君も知っての通り、貴族っていうのはさ、見栄と体裁で成り立っているからね。出自については何年経っても何百年経ってもうるさいんだよ」
クラウディア嬢が侯爵令嬢ながら、下級貴族に対してあれだけの尊大な態度を取るのはそれが原因なのかもしれない。力を誇示しないと威厳が保たれないのだろう。
「セリアン様は呪術や呪いを信じますか?」
「まあ、あるんじゃない」
意外だ。セリアン様なら笑い飛ばすかと思っていた。
「人の悪意っていうのは目に見えなくても時に強い力を持って、周りに伝播させたりするからね。呪術や呪いが存在していてもおかしくない。君はどう? 信じる?」
「正直、自分の目に見えないもの、証明できないものを絶対存在するとは、わたくしの口からは言い切れません。ですが、信頼できる人や信頼したい人の言葉ならわたくしは信じたいと思っていますし、信じます」
「なるほど。それはいいね」
今度は皮肉っぽくではなく、セリアン様は穏やかな笑みを浮かべた。
「ところで……お話が変わりまして一つ疑問があるのですが、よろしいでしょうか」
さっきの会話で引っかかった所を尋ねてみる。
「うん。何?」
「先ほど侍従長様は、本日もお嬢様は今おもてなしできる状態ではないとおっしゃいました。本日はではなく、本日もとはどういうことでしょうか」
「え?」
「セリアン様、前にもお見舞いに来られていたのですか?」
誤魔化される前に私は直接言葉をぶつけてみた。するとセリアン様は参ったなと髪をがしがしと掻いた。
「まあね。一応、マリアンジェラとは幼なじみだからね。容易く動けないエルベルトと違って見舞いぐらいするよ」
「ほほう。マリアンジェラとな」
しかもやはり殿下が簡単に動けないと分かっていたんだ。本当に食えない人。
「その余裕ぶった顔、止めてくれない? むかつくんだけど」
「ありがとう存じます」
「何でそこで礼を言う」
セリアン様の嫌そうな突っ込みが入ったその時、馬車は緩やかに止まった。
33
あなたにおすすめの小説

王宮に薬を届けに行ったなら
佐倉ミズキ
恋愛
王宮で薬師をしているラナは、上司の言いつけに従い王子殿下のカザヤに薬を届けに行った。
カザヤは生まれつき体が弱く、臥せっていることが多い。
この日もいつも通り、カザヤに薬を届けに行ったラナだが仕事終わりに届け忘れがあったことに気が付いた。
慌ててカザヤの部屋へ行くと、そこで目にしたものは……。
弱々しく臥せっているカザヤがベッドから起き上がり、元気に動き回っていたのだ。
「俺の秘密を知ったのだから部屋から出すわけにはいかない」
驚くラナに、カザヤは不敵な笑みを浮かべた。
「今日、国王が崩御する。だからお前を部屋から出すわけにはいかない」
※ベリーズカフェにも掲載中です。そちらではラナの設定が変わっています。(貴族→庶民)それにより、内容も少し変更しておりますのであわせてお楽しみください。

身分差婚~あなたの妻になれないはずだった~
椿蛍
恋愛
「息子と別れていただけないかしら?」
私を脅して、別れを決断させた彼の両親。
彼は高級住宅地『都久山』で王子様と呼ばれる存在。
私とは住む世界が違った……
別れを命じられ、私の恋が終わった。
叶わない身分差の恋だったはずが――
※R-15くらいなので※マークはありません。
※視点切り替えあり。
※2日間は1日3回更新、3日目から1日2回更新となります。
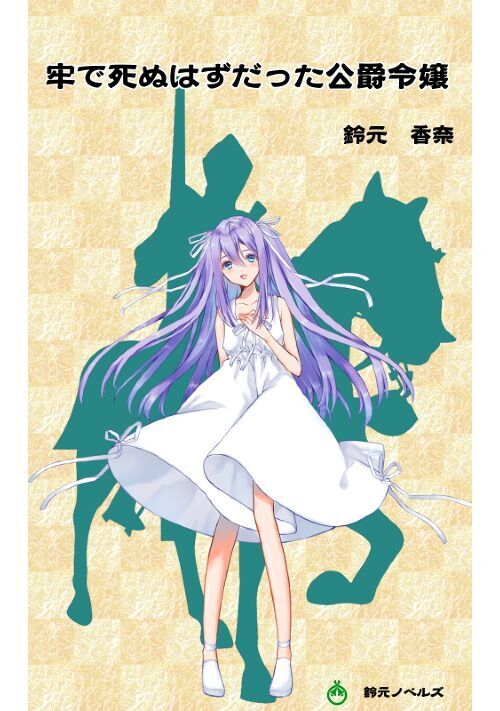
牢で死ぬはずだった公爵令嬢
鈴元 香奈
恋愛
婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。
表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。
小説家になろうさんにも投稿しています。

アンジェリーヌは一人じゃない
れもんぴーる
恋愛
義母からひどい扱いされても我慢をしているアンジェリーヌ。
メイドにも冷遇され、昔は仲が良かった婚約者にも冷たい態度をとられ居場所も逃げ場所もなくしていた。
そんな時、アルコール入りのチョコレートを口にしたアンジェリーヌの性格が激変した。
まるで別人になったように、言いたいことを言い、これまで自分に冷たかった家族や婚約者をこぎみよく切り捨てていく。
実は、アンジェリーヌの中にずっといた魂と入れ替わったのだ。
それはアンジェリーヌと一緒に生まれたが、この世に誕生できなかったアンジェリーヌの双子の魂だった。
新生アンジェリーヌはアンジェリーヌのため自由を求め、家を出る。
アンジェリーヌは満ち足りた生活を送り、愛する人にも出会うが、この身体は自分の物ではない。出来る事なら消えてしまった可哀そうな自分の半身に幸せになってもらいたい。でもそれは自分が消え、愛する人との別れの時。
果たしてアンジェリーヌの魂は戻ってくるのか。そしてその時もう一人の魂は・・・。
*タグに「平成の歌もあります」を追加しました。思っていたより歌に注目していただいたので(*´▽`*)
(なろうさま、カクヨムさまにも投稿予定です)

【完結】地味な私と公爵様
ベル
恋愛
ラエル公爵。この学園でこの名を知らない人はいないでしょう。
端正な顔立ちに甘く低い声、時折見せる少年のような笑顔。誰もがその美しさに魅了され、女性なら誰もがラエル様との結婚を夢見てしまう。
そんな方が、平凡...いや、かなり地味で目立たない伯爵令嬢である私の婚約者だなんて一体誰が信じるでしょうか。
...正直私も信じていません。
ラエル様が、私を溺愛しているなんて。
きっと、きっと、夢に違いありません。
お読みいただきありがとうございます。短編のつもりで書き始めましたが、意外と話が増えて長編に変更し、無事完結しました(*´-`)

0歳児に戻った私。今度は少し口を出したいと思います。
アズやっこ
恋愛
❈ 追記 長編に変更します。
16歳の時、私は第一王子と婚姻した。
いとこの第一王子の事は好き。でもこの好きはお兄様を思う好きと同じ。だから第二王子の事も好き。
私の好きは家族愛として。
第一王子と婚約し婚姻し家族愛とはいえ愛はある。だから何とかなる、そう思った。
でも人の心は何とかならなかった。
この国はもう終わる…
兄弟の対立、公爵の裏切り、まるでボタンの掛け違い。
だから歪み取り返しのつかない事になった。
そして私は暗殺され…
次に目が覚めた時0歳児に戻っていた。
❈ 作者独自の世界観です。
❈ 作者独自の設定です。こういう設定だとご了承頂けると幸いです。

幼馴染の生徒会長にポンコツ扱いされてフラれたので生徒会活動を手伝うのをやめたら全てがうまくいかなくなり幼馴染も病んだ
猫カレーฅ^•ω•^ฅ
恋愛
ずっと付き合っていると思っていた、幼馴染にある日別れを告げられた。
そこで気づいた主人公の幼馴染への依存ぶり。
たった一つボタンを掛け違えてしまったために、
最終的に学校を巻き込む大事件に発展していく。
主人公は幼馴染を取り戻すことが出来るのか!?

【完結】一番腹黒いのはだあれ?
やまぐちこはる
恋愛
■□■
貧しいコイント子爵家のソンドールは、貴族学院には進学せず、騎士学校に通って若くして正騎士となった有望株である。
三歳でコイント家に養子に来たソンドールの生家はパートルム公爵家。
しかし、関わりを持たずに生きてきたため、自分が公爵家生まれだったことなどすっかり忘れていた。
ある日、実の父がソンドールに会いに来て、自分の出自を改めて知り、勝手なことを言う実父に憤りながらも、生家の騒動に巻き込まれていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















