257 / 315
第257話 偉大なる先人
しおりを挟む
「お待たせいたしました」
父が一冊の本を手に戻ってきた。
「いえ。ご足労をおかけいたしました」
「とんでもないお話でございます」
殿下の労いの言葉に父は恐縮しつつ、それでは失礼いたしますとソファーに身を沈める。
別に王宮にあるような門外不出となるような記録書ではないとは言え、殿下も遠慮するだろうと思い、父の横にいる私が受け取って読んでみることにした。
風格のある表紙とずしりと重みから歴史を感じるのは同じだけれど、表紙の文字を読むことができることだけは決定的に違う。
――ん!? 読める!?
読めるということは、この記録書はルイス王朝時代以降のものになるということ。ダングルベール家はいつ爵位を叙せられたのだろうか。
「お、お父様。ダングルベール家ができたのは、今から遡っていつ頃になりますか」
父はまだ一ページ目すら開こうとしない私の手の中にある本に手を伸ばし、ぱたりと開くと指差した。
「ここにあるように今からだと……約三百八十年前のことかな?」
「三百八十年前ですか!?」
ルイス王朝時代が四百年ほど前。ブラックウェル様がリアーナ様のお家に入ったと仮定するまではいい。だがリアーナ様がルイス殿下の侍女であったということは、貴族の娘であったはずだ。
うちができたのが約三百八十年前で二十年の開きがある。つまり、リアーナ様は……ダングルベール家の人間ではない!
せっかくお父様に記録書を持ってきていただいたのに申し訳ないが、ご先祖様のお名前を確認するまでもなく、ブラックウェル様は私のご先祖様ではないことが確実となってしまった。
「そ、そんなぁ……」
ちょっと嫌な予感はしていたものの、事実を目の前にするとわずかに残っていた希望すら打ち砕かれた。何よりも自分の推理が根底から覆されてしまった。もう、何を信じれば良いのか分からない。
本を抱きかかえるように私は前のめりに崩れる。
「え、え、え? な、何が? 何を落ち込んでいるんだい? あ、それより。こら、ロザンヌ! 殿下を御前に無作法だよ」
「いえ。私のことはお気になさらず。ところでダングルベール子爵殿」
萎れきった私の対応に困惑しつつ、たしなめる父を気遣って殿下が呼びかけた。
「はい。何でしょうか」
「この地、サンルーモはとても良い土地ですね。馬車の中から拝見しましたが、自然に恵まれており、土地は肥沃で農業も盛んの上、畜産業も行われているとお見受けいたしました。この広大で、美しく麗らかな土地に囲まれて育って来られたからお嬢様は天真爛漫なのでしょうね」
「お、お恥ずかしい限りでして」
お恥ずかしい限りって酷いです、お父様。素直に良い意味で受け取ってくださいよ。殿下も褒め言葉でおっしゃって……本当に褒め言葉でおっしゃったのだろうか。
顔を上げて殿下の分まで恨めしげに父の横顔を見つめると、父は焦ったようにこほんと咳払いした。
「実はこの地が豊かなのも全ては先人の方々のおかげなのです。今でこそ、サンルーモの名にふさわしく自然豊かですが、その昔、ここは大凶作の時代の後に不毛の地になったそうです」
うちが爵位を受けたということは何らかの功績を残したはずなのに、不毛な地を寄越すとはたいした王族礼儀だこと。
こっそり一人白けていると。
「しかしダングルベール家より前に統治されていた貴族の方々がこの地を育て――」
「え、お父様!」
「な、何だい?」
勢いよく身を乗り出したことで、父は驚きと共に視線を私に移した。
「今。今、ダングルベール家より前に統治されていた貴族がいたとおっしゃいました!?」
うちとその貴族の方とが何らかの縁があるかもしれない。仮に血縁がなかったとしても、彼らと繋がる線があるかもしれない。その線はもしかしたらブラックウェル様に繋がるものかも。
「あ、ああ。言ったよ。最後の代の方はこの地の開拓に特にご尽力いただいた方だそうだ。そういえば王宮勤めもされた方だったというお話もあったかな」
「っ!」
殿下と視線を交わして頷くと、私はまた父に顔を戻す。
「そ、それで。最後の代の方とおっしゃいましたが、お子様はいらっしゃらなかったのですか?」
「ああ。そのご夫婦は子に恵まれず、その代で廃絶なさったようだね」
「そうですか。お父様、その貴族の名はブラックウェル様と申しませんか?」
「え? いや、違うね。お名前はルーベンスとおっしゃるよ」
やっぱり関係がない? ……でもブラックウェル様がリアーナ様のお家に入られていたとしたら、姓を残していないとも考えられる。ただ、リアーナ様の姓がブラックウェル様の手記には載っておらず、分からないから何とも言えないのだけれど。
「そんなに気になるのなら、墓苑に訪れてみたらどうかな」
私はぶつぶつと呟いていたらしい。お父様がお言葉をかけてくださった。
「え!? 今もあるのですか?」
「もちろんだとも。この地を作ってくださった偉大なる先人を敬うために、お墓はダングルベール家が代々墓守として担わせていただいているよ。ロザンヌにも、何度かそのお話をしたことがあったと思うんだけどねぇ」
「そ、そうでしたか。きっと難しすぎて、わ、わたくしには理解が及ばなかったのだと……思われますハイ」
父に苦笑されたので、私はそっと視線をそらした。
父が一冊の本を手に戻ってきた。
「いえ。ご足労をおかけいたしました」
「とんでもないお話でございます」
殿下の労いの言葉に父は恐縮しつつ、それでは失礼いたしますとソファーに身を沈める。
別に王宮にあるような門外不出となるような記録書ではないとは言え、殿下も遠慮するだろうと思い、父の横にいる私が受け取って読んでみることにした。
風格のある表紙とずしりと重みから歴史を感じるのは同じだけれど、表紙の文字を読むことができることだけは決定的に違う。
――ん!? 読める!?
読めるということは、この記録書はルイス王朝時代以降のものになるということ。ダングルベール家はいつ爵位を叙せられたのだろうか。
「お、お父様。ダングルベール家ができたのは、今から遡っていつ頃になりますか」
父はまだ一ページ目すら開こうとしない私の手の中にある本に手を伸ばし、ぱたりと開くと指差した。
「ここにあるように今からだと……約三百八十年前のことかな?」
「三百八十年前ですか!?」
ルイス王朝時代が四百年ほど前。ブラックウェル様がリアーナ様のお家に入ったと仮定するまではいい。だがリアーナ様がルイス殿下の侍女であったということは、貴族の娘であったはずだ。
うちができたのが約三百八十年前で二十年の開きがある。つまり、リアーナ様は……ダングルベール家の人間ではない!
せっかくお父様に記録書を持ってきていただいたのに申し訳ないが、ご先祖様のお名前を確認するまでもなく、ブラックウェル様は私のご先祖様ではないことが確実となってしまった。
「そ、そんなぁ……」
ちょっと嫌な予感はしていたものの、事実を目の前にするとわずかに残っていた希望すら打ち砕かれた。何よりも自分の推理が根底から覆されてしまった。もう、何を信じれば良いのか分からない。
本を抱きかかえるように私は前のめりに崩れる。
「え、え、え? な、何が? 何を落ち込んでいるんだい? あ、それより。こら、ロザンヌ! 殿下を御前に無作法だよ」
「いえ。私のことはお気になさらず。ところでダングルベール子爵殿」
萎れきった私の対応に困惑しつつ、たしなめる父を気遣って殿下が呼びかけた。
「はい。何でしょうか」
「この地、サンルーモはとても良い土地ですね。馬車の中から拝見しましたが、自然に恵まれており、土地は肥沃で農業も盛んの上、畜産業も行われているとお見受けいたしました。この広大で、美しく麗らかな土地に囲まれて育って来られたからお嬢様は天真爛漫なのでしょうね」
「お、お恥ずかしい限りでして」
お恥ずかしい限りって酷いです、お父様。素直に良い意味で受け取ってくださいよ。殿下も褒め言葉でおっしゃって……本当に褒め言葉でおっしゃったのだろうか。
顔を上げて殿下の分まで恨めしげに父の横顔を見つめると、父は焦ったようにこほんと咳払いした。
「実はこの地が豊かなのも全ては先人の方々のおかげなのです。今でこそ、サンルーモの名にふさわしく自然豊かですが、その昔、ここは大凶作の時代の後に不毛の地になったそうです」
うちが爵位を受けたということは何らかの功績を残したはずなのに、不毛な地を寄越すとはたいした王族礼儀だこと。
こっそり一人白けていると。
「しかしダングルベール家より前に統治されていた貴族の方々がこの地を育て――」
「え、お父様!」
「な、何だい?」
勢いよく身を乗り出したことで、父は驚きと共に視線を私に移した。
「今。今、ダングルベール家より前に統治されていた貴族がいたとおっしゃいました!?」
うちとその貴族の方とが何らかの縁があるかもしれない。仮に血縁がなかったとしても、彼らと繋がる線があるかもしれない。その線はもしかしたらブラックウェル様に繋がるものかも。
「あ、ああ。言ったよ。最後の代の方はこの地の開拓に特にご尽力いただいた方だそうだ。そういえば王宮勤めもされた方だったというお話もあったかな」
「っ!」
殿下と視線を交わして頷くと、私はまた父に顔を戻す。
「そ、それで。最後の代の方とおっしゃいましたが、お子様はいらっしゃらなかったのですか?」
「ああ。そのご夫婦は子に恵まれず、その代で廃絶なさったようだね」
「そうですか。お父様、その貴族の名はブラックウェル様と申しませんか?」
「え? いや、違うね。お名前はルーベンスとおっしゃるよ」
やっぱり関係がない? ……でもブラックウェル様がリアーナ様のお家に入られていたとしたら、姓を残していないとも考えられる。ただ、リアーナ様の姓がブラックウェル様の手記には載っておらず、分からないから何とも言えないのだけれど。
「そんなに気になるのなら、墓苑に訪れてみたらどうかな」
私はぶつぶつと呟いていたらしい。お父様がお言葉をかけてくださった。
「え!? 今もあるのですか?」
「もちろんだとも。この地を作ってくださった偉大なる先人を敬うために、お墓はダングルベール家が代々墓守として担わせていただいているよ。ロザンヌにも、何度かそのお話をしたことがあったと思うんだけどねぇ」
「そ、そうでしたか。きっと難しすぎて、わ、わたくしには理解が及ばなかったのだと……思われますハイ」
父に苦笑されたので、私はそっと視線をそらした。
32
あなたにおすすめの小説

身分差婚~あなたの妻になれないはずだった~
椿蛍
恋愛
「息子と別れていただけないかしら?」
私を脅して、別れを決断させた彼の両親。
彼は高級住宅地『都久山』で王子様と呼ばれる存在。
私とは住む世界が違った……
別れを命じられ、私の恋が終わった。
叶わない身分差の恋だったはずが――
※R-15くらいなので※マークはありません。
※視点切り替えあり。
※2日間は1日3回更新、3日目から1日2回更新となります。
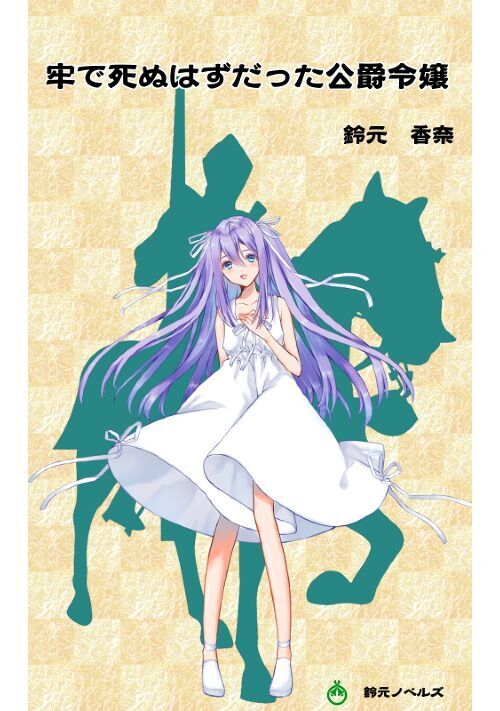
牢で死ぬはずだった公爵令嬢
鈴元 香奈
恋愛
婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。
表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。
小説家になろうさんにも投稿しています。

アンジェリーヌは一人じゃない
れもんぴーる
恋愛
義母からひどい扱いされても我慢をしているアンジェリーヌ。
メイドにも冷遇され、昔は仲が良かった婚約者にも冷たい態度をとられ居場所も逃げ場所もなくしていた。
そんな時、アルコール入りのチョコレートを口にしたアンジェリーヌの性格が激変した。
まるで別人になったように、言いたいことを言い、これまで自分に冷たかった家族や婚約者をこぎみよく切り捨てていく。
実は、アンジェリーヌの中にずっといた魂と入れ替わったのだ。
それはアンジェリーヌと一緒に生まれたが、この世に誕生できなかったアンジェリーヌの双子の魂だった。
新生アンジェリーヌはアンジェリーヌのため自由を求め、家を出る。
アンジェリーヌは満ち足りた生活を送り、愛する人にも出会うが、この身体は自分の物ではない。出来る事なら消えてしまった可哀そうな自分の半身に幸せになってもらいたい。でもそれは自分が消え、愛する人との別れの時。
果たしてアンジェリーヌの魂は戻ってくるのか。そしてその時もう一人の魂は・・・。
*タグに「平成の歌もあります」を追加しました。思っていたより歌に注目していただいたので(*´▽`*)
(なろうさま、カクヨムさまにも投稿予定です)

【完結】地味な私と公爵様
ベル
恋愛
ラエル公爵。この学園でこの名を知らない人はいないでしょう。
端正な顔立ちに甘く低い声、時折見せる少年のような笑顔。誰もがその美しさに魅了され、女性なら誰もがラエル様との結婚を夢見てしまう。
そんな方が、平凡...いや、かなり地味で目立たない伯爵令嬢である私の婚約者だなんて一体誰が信じるでしょうか。
...正直私も信じていません。
ラエル様が、私を溺愛しているなんて。
きっと、きっと、夢に違いありません。
お読みいただきありがとうございます。短編のつもりで書き始めましたが、意外と話が増えて長編に変更し、無事完結しました(*´-`)

0歳児に戻った私。今度は少し口を出したいと思います。
アズやっこ
恋愛
❈ 追記 長編に変更します。
16歳の時、私は第一王子と婚姻した。
いとこの第一王子の事は好き。でもこの好きはお兄様を思う好きと同じ。だから第二王子の事も好き。
私の好きは家族愛として。
第一王子と婚約し婚姻し家族愛とはいえ愛はある。だから何とかなる、そう思った。
でも人の心は何とかならなかった。
この国はもう終わる…
兄弟の対立、公爵の裏切り、まるでボタンの掛け違い。
だから歪み取り返しのつかない事になった。
そして私は暗殺され…
次に目が覚めた時0歳児に戻っていた。
❈ 作者独自の世界観です。
❈ 作者独自の設定です。こういう設定だとご了承頂けると幸いです。

いくら政略結婚だからって、そこまで嫌わなくてもいいんじゃないですか?いい加減、腹が立ってきたんですけど!
夢呼
恋愛
伯爵令嬢のローゼは大好きな婚約者アーサー・レイモンド侯爵令息との結婚式を今か今かと待ち望んでいた。
しかし、結婚式の僅か10日前、その大好きなアーサーから「私から愛されたいという思いがあったら捨ててくれ。それに応えることは出来ない」と告げられる。
ローゼはその言葉にショックを受け、熱を出し寝込んでしまう。数日間うなされ続け、やっと目を覚ました。前世の記憶と共に・・・。
愛されることは無いと分かっていても、覆すことが出来ないのが貴族間の政略結婚。日本で生きたアラサー女子の「私」が八割心を占めているローゼが、この政略結婚に臨むことになる。
いくら政略結婚といえども、親に孫を見せてあげて親孝行をしたいという願いを持つローゼは、何とかアーサーに振り向いてもらおうと頑張るが、鉄壁のアーサーには敵わず。それどころか益々嫌われる始末。
一体私の何が気に入らないんだか。そこまで嫌わなくてもいいんじゃないんですかね!いい加減腹立つわっ!
世界観はゆるいです!
カクヨム様にも投稿しております。
※10万文字を超えたので長編に変更しました。

ぐうたら令嬢は公爵令息に溺愛されています
Karamimi
恋愛
伯爵令嬢のレイリスは、今年で16歳。毎日ぐうたらした生活をしている。貴族としてはあり得ないような服を好んで着、昼間からゴロゴロと過ごす。
ただ、レイリスは非常に優秀で、12歳で王都の悪党どもを束ね揚げ、13歳で領地を立て直した腕前。
そんなレイリスに、両親や兄姉もあまり強く言う事が出来ず、専属メイドのマリアンだけが口うるさく言っていた。
このままやりたい事だけをやり、ゴロゴロしながら一生暮らそう。そう思っていたレイリスだったが、お菓子につられて参加したサフィーロン公爵家の夜会で、彼女の運命を大きく変える出来事が起こってしまって…
※ご都合主義のラブコメディです。
よろしくお願いいたします。
カクヨムでも同時投稿しています。

【完結】一番腹黒いのはだあれ?
やまぐちこはる
恋愛
■□■
貧しいコイント子爵家のソンドールは、貴族学院には進学せず、騎士学校に通って若くして正騎士となった有望株である。
三歳でコイント家に養子に来たソンドールの生家はパートルム公爵家。
しかし、関わりを持たずに生きてきたため、自分が公爵家生まれだったことなどすっかり忘れていた。
ある日、実の父がソンドールに会いに来て、自分の出自を改めて知り、勝手なことを言う実父に憤りながらも、生家の騒動に巻き込まれていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















