1 / 24
バラバラドール
1
しおりを挟む
「行ってきます……」
平日の朝、決まった時間に家を出る一人の少女がいた。俯きながらの登校スタイルは、板についたデフォルトで。そんな彼女の表情は、もちろんだが晴れていない。
幼い頃から、引っ込み思案で俯きがちだったが、ここ最近は特にひどくなってしまった。理由は、誰の目から見ても明らかだ。そばで笑っていた彼女が、いなくなってしまった。そのこと以外に、原因は存在しない。
サラサラとした綺麗な黒髪に隠された表情は、自室の外で笑顔を見せることはなくなった。今の彼女は一つの例外を除けば、何を見ても、何を食べても、何をしても、心が動かされることなどなかった。
少女の願いは、今となってはただ一つ――いつまでも、かなでと一緒にいたい。その一点だけだった。これ以上なんて、何も望んでいなかった。いや、これ以上のことなんて、存在すらしなかった。
「夜が明けなければいいのに……。朝なんて、こなければいいのに……。他なんて、何もいらないのに……。かなで以外なんて、何もいらない。だから、ずっと部屋にこもっていたい。かなでのそばに、ずっといたい……」
ぼそぼそと呟く彼女は、通学カバンの持ち手をぎゅっと握り締めた。
「だけどそれは、わからずやの両親が叶えてくれない……。抗えないわたしは、彼女を奪われないために、学校へ行くしかない……。学生として、最低限の本分をまっとうしていると示すために、こうして行きたくもない学校に、行かなくちゃならない……」
少女は、中学生になったら、少しは大人になれると思っていた。しかし、現実はまったく違っていた。
どこまでいっても、日々の延長――何も変わらない。
年を重ねても、進学しても、勝手に何かが変わることはなかった。
今日も今日とて、彼女は引っ込み思案で影の薄い、 斉藤初のままだった。
大人に従うしかない、ただの無力でちっぽけな子どもにすぎなかった。
「早く、家に帰りたい……」
ぼそりと呟く少女が脳裏に浮かべるのは、いつだってそう……。部屋で待っている、愛しいかなでの姿ばかりだった。
あの日から、変わらない。初は、何も変わらない。変わりたくもないとさえ、思っている。
それでも、無常に世の中は移りゆく。時は、変わらず動き続ける。
早いもので、痛ましい事故から、既に一週間が経とうとしていた。
――斉藤初、中学一年の春。
地元の学校へ進学した初のそばには、小学校一年生の頃からずっと一緒だった、沖田奏がいた。
他の子よりも大人っぽくて、綺麗で、クールだけど優しくて、頭が良くて、いつも堂々としている、初の憧れの人。
初は、いつも思っていた。彼女は「わたしとは、全然違う人」だと。
いつ見ても眩しくて、初は奏のようになりたいと、ずっと思っていた。
いつまでも見ていられて、元気をくれるアイドルのような存在。
誰よりも大好きなクラスメイト。
大好きすぎて、初は奏に会うために学校へ行っていた。それだけのためと言っても、過言ではなかった。
朝目を覚ますのも、奏に会うため。
勉強を頑張るのも、奏のそばにいるため。
初の生活の何もかもが、奏を中心に回っていた。
彼女のそばにいるための努力なら、初は何だってできた。
それくらい、初にとって奏は、大好きで、大事な人だった。
――そんな彼女が、ある日突然亡くなった。
入学したばかりの頃だった。生まれて初めて初は、運命というものを呪った。
道路に飛び出した子どもを助けようとして、奏は大型トラックに撥ね飛ばされたのだ。
運転手も子どもも、まったくの無傷で無事だったが、奏は頭部と全身の強打により、手の施しようのないほどの即死だった。
アスファルトを染めていく鮮血はじわじわと動いて広がっていくのに、初の目の前の彼女は、ぷつりと糸の切れたマリオネットのように、呆気なく動かなくなったのだ。
まるで、弾むボールのように軽々と宙を舞う華奢な体を、初は生涯忘れないだろう。
彼女の見開かれた瞳に映った、初の驚愕に染まった顔さえ、焼き付いて離れることはない。
そうして同時に、初の時間もその瞬間、止まってしまった。
彼女はしばらく、その場から動くことができなかった。まるで、石になってしまったかのように指一本すら動かせず、心が急くばかりで、奏の体へ駆け寄ることすら、できなかったのだ。
今や、自身を顧みず行動した奏の勇気は、当人のことを知らないどこかの誰かでさえ涙する、悲しき美談となった。
彼女の行動は運命として、悲劇と感動に彩り飾られてしまった。綺麗に纏められてしまった。それはあたかも、フィクションであるかのように……。
初にはどうしても、それが奏のことを早く忘れるためにしている行動にしか見えなかった。
遺された者が、前を向くために。彼女の生や死に、意味を持たせるために。
ただそれだけのために、沖田奏という一人の人間の人生を、物語としたかのようにしか、見えなかった。
「奏ちゃんが、そう望んだわけでもないのに――」
初には、それがわからない。理解ができない。
どうして、前を向かなくちゃならないのか。どうして、留まってはいけないのか。
生まれてきたことに、生きていたことに、死んだことに、いちいち意味や理由が必要なのか。
それは、すべて遺された側の都合じゃないのか。
彼女は、創作された物語なんかじゃない。ドラマ性のある、仕組まれたフィクションじゃない。ちゃんと生きていた、一人の人間だ。意思を持って息をしていた、人間なのに。
どうして、記憶の中にしまおうとするのか。どうして、過去のことにしようとするのか。
だったら、気紛れに語らないでほしい。忘れるならば、彼女との記憶をすべて自分に与えて欲しい。自分が知らない彼女を、全部教えてほしい。
それができないのなら、大好きな彼女のことを、わかったように口にするのは許さない。
話せなくなった彼女を好き勝手に語るなんて、そんなのは辱めだ。
「……そうだ。許さない。許しちゃいけない。守らなくちゃ。わたしが、やらなくちゃ。今まで、奏ちゃんに救われていたんだ。助けてもらってきたんだ。だから、今度はわたしが返す番だ。今度こそ、わたしが奏ちゃんを救う番だ」
初の瞳に、光が宿る。奏を失ってから初めて、彼女が生きる意味を見つけた瞬間だった。
「そうだ。わたしが、奏ちゃんを守ってみせるんだ。……ねえ、奏ちゃん。見守っていてね。きっと、わたしが奏ちゃんの尊厳を守ってみせるから。絶対に、守り抜いてみせるよ。だから、安心していて。これ以上は、誰にも汚させない。大丈夫。わたしは、ずっとそばにいたんだから。いつだって、どんな時だって、ずっとずっと見ていたんだから」
だから、きっと大丈夫。初は、自身にそう言い聞かせる。
「わたしなら、奏ちゃんのことをよく知っている。奏ちゃんのことなら、何でもわかる。知らないことなんて、何一つもないくらいに。だって奏ちゃんは、わたしのたった一人のかけがえのない人なんだから。ねえ、奏ちゃん。奏ちゃんのためなら、わたし、何だってできるよ。嘘じゃない。大袈裟でもない。苦手なことでも構わない。大事な大事な奏ちゃんのためだったら、わたしは何にだってなってみせるからね」
今の初には、何も怖いことなんてなかった。何も恐れることなんてなかった。
何故ならば、これで奏が救われるから。自身の手で、彼女を救えるのだから。
初にとって、これほど幸せなことがあるだろうか。
「このわたしが、奏ちゃんの役に立てるなんて……夢みたい……」
初は、空を見上げる。そうして、思い描いた奏の笑顔に向かって、心で語り掛けた。
ねえ、奏ちゃん。きっと、また微笑みかけてくれるよね。喜んでくれるよね。
わたし、頑張るからね。だから、見ていてね。絶対だよ。
今度こそ、ずっとそばにいようね。ねえ、いてくれるよね?
約束だよ。絶対の、絶対だからね……。
「ふふ……楽しみだなあ……」
――しかし、既に歯車は狂いだした後であった。それを知るのは、奏ただ一人であったのだった。
平日の朝、決まった時間に家を出る一人の少女がいた。俯きながらの登校スタイルは、板についたデフォルトで。そんな彼女の表情は、もちろんだが晴れていない。
幼い頃から、引っ込み思案で俯きがちだったが、ここ最近は特にひどくなってしまった。理由は、誰の目から見ても明らかだ。そばで笑っていた彼女が、いなくなってしまった。そのこと以外に、原因は存在しない。
サラサラとした綺麗な黒髪に隠された表情は、自室の外で笑顔を見せることはなくなった。今の彼女は一つの例外を除けば、何を見ても、何を食べても、何をしても、心が動かされることなどなかった。
少女の願いは、今となってはただ一つ――いつまでも、かなでと一緒にいたい。その一点だけだった。これ以上なんて、何も望んでいなかった。いや、これ以上のことなんて、存在すらしなかった。
「夜が明けなければいいのに……。朝なんて、こなければいいのに……。他なんて、何もいらないのに……。かなで以外なんて、何もいらない。だから、ずっと部屋にこもっていたい。かなでのそばに、ずっといたい……」
ぼそぼそと呟く彼女は、通学カバンの持ち手をぎゅっと握り締めた。
「だけどそれは、わからずやの両親が叶えてくれない……。抗えないわたしは、彼女を奪われないために、学校へ行くしかない……。学生として、最低限の本分をまっとうしていると示すために、こうして行きたくもない学校に、行かなくちゃならない……」
少女は、中学生になったら、少しは大人になれると思っていた。しかし、現実はまったく違っていた。
どこまでいっても、日々の延長――何も変わらない。
年を重ねても、進学しても、勝手に何かが変わることはなかった。
今日も今日とて、彼女は引っ込み思案で影の薄い、 斉藤初のままだった。
大人に従うしかない、ただの無力でちっぽけな子どもにすぎなかった。
「早く、家に帰りたい……」
ぼそりと呟く少女が脳裏に浮かべるのは、いつだってそう……。部屋で待っている、愛しいかなでの姿ばかりだった。
あの日から、変わらない。初は、何も変わらない。変わりたくもないとさえ、思っている。
それでも、無常に世の中は移りゆく。時は、変わらず動き続ける。
早いもので、痛ましい事故から、既に一週間が経とうとしていた。
――斉藤初、中学一年の春。
地元の学校へ進学した初のそばには、小学校一年生の頃からずっと一緒だった、沖田奏がいた。
他の子よりも大人っぽくて、綺麗で、クールだけど優しくて、頭が良くて、いつも堂々としている、初の憧れの人。
初は、いつも思っていた。彼女は「わたしとは、全然違う人」だと。
いつ見ても眩しくて、初は奏のようになりたいと、ずっと思っていた。
いつまでも見ていられて、元気をくれるアイドルのような存在。
誰よりも大好きなクラスメイト。
大好きすぎて、初は奏に会うために学校へ行っていた。それだけのためと言っても、過言ではなかった。
朝目を覚ますのも、奏に会うため。
勉強を頑張るのも、奏のそばにいるため。
初の生活の何もかもが、奏を中心に回っていた。
彼女のそばにいるための努力なら、初は何だってできた。
それくらい、初にとって奏は、大好きで、大事な人だった。
――そんな彼女が、ある日突然亡くなった。
入学したばかりの頃だった。生まれて初めて初は、運命というものを呪った。
道路に飛び出した子どもを助けようとして、奏は大型トラックに撥ね飛ばされたのだ。
運転手も子どもも、まったくの無傷で無事だったが、奏は頭部と全身の強打により、手の施しようのないほどの即死だった。
アスファルトを染めていく鮮血はじわじわと動いて広がっていくのに、初の目の前の彼女は、ぷつりと糸の切れたマリオネットのように、呆気なく動かなくなったのだ。
まるで、弾むボールのように軽々と宙を舞う華奢な体を、初は生涯忘れないだろう。
彼女の見開かれた瞳に映った、初の驚愕に染まった顔さえ、焼き付いて離れることはない。
そうして同時に、初の時間もその瞬間、止まってしまった。
彼女はしばらく、その場から動くことができなかった。まるで、石になってしまったかのように指一本すら動かせず、心が急くばかりで、奏の体へ駆け寄ることすら、できなかったのだ。
今や、自身を顧みず行動した奏の勇気は、当人のことを知らないどこかの誰かでさえ涙する、悲しき美談となった。
彼女の行動は運命として、悲劇と感動に彩り飾られてしまった。綺麗に纏められてしまった。それはあたかも、フィクションであるかのように……。
初にはどうしても、それが奏のことを早く忘れるためにしている行動にしか見えなかった。
遺された者が、前を向くために。彼女の生や死に、意味を持たせるために。
ただそれだけのために、沖田奏という一人の人間の人生を、物語としたかのようにしか、見えなかった。
「奏ちゃんが、そう望んだわけでもないのに――」
初には、それがわからない。理解ができない。
どうして、前を向かなくちゃならないのか。どうして、留まってはいけないのか。
生まれてきたことに、生きていたことに、死んだことに、いちいち意味や理由が必要なのか。
それは、すべて遺された側の都合じゃないのか。
彼女は、創作された物語なんかじゃない。ドラマ性のある、仕組まれたフィクションじゃない。ちゃんと生きていた、一人の人間だ。意思を持って息をしていた、人間なのに。
どうして、記憶の中にしまおうとするのか。どうして、過去のことにしようとするのか。
だったら、気紛れに語らないでほしい。忘れるならば、彼女との記憶をすべて自分に与えて欲しい。自分が知らない彼女を、全部教えてほしい。
それができないのなら、大好きな彼女のことを、わかったように口にするのは許さない。
話せなくなった彼女を好き勝手に語るなんて、そんなのは辱めだ。
「……そうだ。許さない。許しちゃいけない。守らなくちゃ。わたしが、やらなくちゃ。今まで、奏ちゃんに救われていたんだ。助けてもらってきたんだ。だから、今度はわたしが返す番だ。今度こそ、わたしが奏ちゃんを救う番だ」
初の瞳に、光が宿る。奏を失ってから初めて、彼女が生きる意味を見つけた瞬間だった。
「そうだ。わたしが、奏ちゃんを守ってみせるんだ。……ねえ、奏ちゃん。見守っていてね。きっと、わたしが奏ちゃんの尊厳を守ってみせるから。絶対に、守り抜いてみせるよ。だから、安心していて。これ以上は、誰にも汚させない。大丈夫。わたしは、ずっとそばにいたんだから。いつだって、どんな時だって、ずっとずっと見ていたんだから」
だから、きっと大丈夫。初は、自身にそう言い聞かせる。
「わたしなら、奏ちゃんのことをよく知っている。奏ちゃんのことなら、何でもわかる。知らないことなんて、何一つもないくらいに。だって奏ちゃんは、わたしのたった一人のかけがえのない人なんだから。ねえ、奏ちゃん。奏ちゃんのためなら、わたし、何だってできるよ。嘘じゃない。大袈裟でもない。苦手なことでも構わない。大事な大事な奏ちゃんのためだったら、わたしは何にだってなってみせるからね」
今の初には、何も怖いことなんてなかった。何も恐れることなんてなかった。
何故ならば、これで奏が救われるから。自身の手で、彼女を救えるのだから。
初にとって、これほど幸せなことがあるだろうか。
「このわたしが、奏ちゃんの役に立てるなんて……夢みたい……」
初は、空を見上げる。そうして、思い描いた奏の笑顔に向かって、心で語り掛けた。
ねえ、奏ちゃん。きっと、また微笑みかけてくれるよね。喜んでくれるよね。
わたし、頑張るからね。だから、見ていてね。絶対だよ。
今度こそ、ずっとそばにいようね。ねえ、いてくれるよね?
約束だよ。絶対の、絶対だからね……。
「ふふ……楽しみだなあ……」
――しかし、既に歯車は狂いだした後であった。それを知るのは、奏ただ一人であったのだった。
0
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております
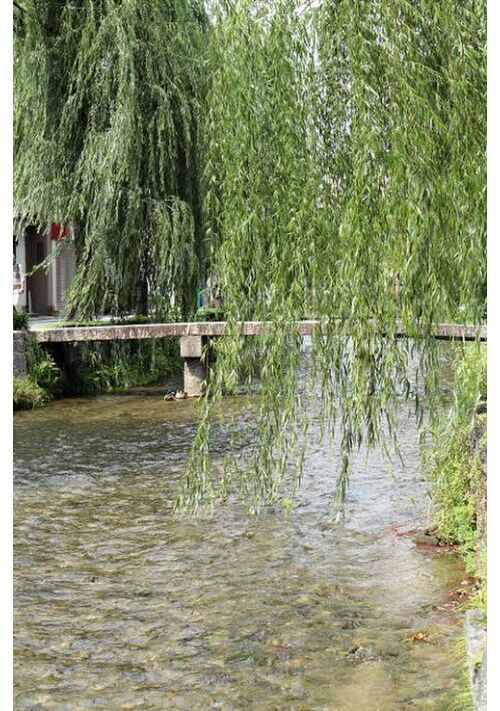

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】
絢郷水沙
ホラー
普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。
下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。
※全話オリジナル作品です。

それなりに怖い話。
只野誠
ホラー
これは創作です。
実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。
本当に、実際に起きた話ではございません。
なので、安心して読むことができます。
オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。
不定期に章を追加していきます。
2026/2/6:『きんようび』の章を追加。2026/2/13の朝頃より公開開始予定。
2026/2/5:『かれー』の章を追加。2026/2/12の朝頃より公開開始予定。
2026/2/4:『あくむ』の章を追加。2026/2/11の朝頃より公開開始予定。
2026/2/3:『つりいと』の章を追加。2026/2/10の朝頃より公開開始予定。
2026/2/2:『おばあちゃん』の章を追加。2026/2/9の朝頃より公開開始予定。
2026/2/1:『かんしかめら』の章を追加。2026/2/8の朝頃より公開開始予定。
2026/1/31:『うしろ』の章を追加。2026/2/7の朝頃より公開開始予定。
※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

皆さんは呪われました
禰津エソラ
ホラー
あなたは呪いたい相手はいますか?
お勧めの呪いがありますよ。
効果は絶大です。
ぜひ、試してみてください……
その呪いの因果は果てしなく絡みつく。呪いは誰のものになるのか。
最後に残るのは誰だ……

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















