37 / 157
35 騏驥の願望、欲望 空に向かって手を伸ばす
しおりを挟む
そうしたら……。
シィンはこちらが拍子抜けするほど「普通」で。
いつも通りで……。
なんだか……。
なんだかとてもがっかりしてしまったのだ。
やはり彼にとっては自分に触れることなど些細なことなのか、と。
薬を飲ませてくれたことも、それがもしかしたら口移しだったことも、単に「一晩面倒を診る」ことの延長で、こちらが思ったような、動揺してしまったような深い意味はないのか、と。
(でも……考えてみれば当然だ……)
そう。考えてみればそんなこと問題にもならないようなことなのだ。
そもそも、普通の騎士にとってだって、騏驥はただの兵器だ。
元が人で、人の知性を宿し人の姿の時は人と同じものを食べ同じものを着るだけで、実態は「馬に変わる人間」——異形なのだ。
普通の人とは決定的に違う。もちろん騎士とも。
そんな相手をどうして同じ人間のように扱えるだろう。
騏驥を徹底的に道具として用いる騎士がいる一方、愛着を持ち、優しく触れる者もいないことはない。
が、それは「手に合う騏驥」「使いやすい騏驥」「乗りやすい騏驥」を気にかけているだけだ。愛用の道具の手入れをするように。
——そういうことだ。
騏驥は人ではないのだから。
そして、そんな騎士たちをさらに従えているのが彼なのだ。
王子。
いずれ王位を継ぐお方。
そんな方が、騏驥の自分を「自らと同じ立場」に考えるわけがない。思うわけがない。
あの行為だって——口付けだって、まさしく「お戯れ」だったのだろう。
彼は多分、巫山戯ていただけだ。
こちらがどんな反応をするか、見てみたかっただけだろう。
もしくは、大会の前に試してみたかったのかもしれない。
咄嗟の時にどんな反応をするか。思いがけない事態にぶつかった時にどう対処するか……。
なのに自分は自分の醜い衝動に流されてシィンを抱きしめるような真似をしてしまった。欲望に流されて彼の唇を貪るような真似をして……。
挙句、それを彼のせいにしたのだ。
彼がからかってきたからだ、と。
そんなこと言える立場ではないのに。
王子である彼が騏驥である自分を揶揄うことに、何の問題があろうものか。試すことのなにが悪かろうか。
なのに自分は恐れ多くも、そんな彼に対して憤りを覚えたのだ。
まるで対等な存在であるかのように。
「どうしてこんなことを」と。
自分に疚しさがあるから……だからそれを誤魔化そうとして……。
戯れはやめて欲しいなんて言っておいて、その実自分はそれを悦んだくせに。
ダンジァはぎゅっと拳を握りしめる。
だからシィンは早々に部屋を出て行ったのではないだろうか。
失望したのだろう、こちらの態度に。
騏驥の分際で、しかも彼に大きな世話になった騏驥の分際で、彼の当然の行為を責めるようなことを言ったのだから。
でなければ、こちらの欲を知られた。騎士に対して、王子に対して想った言い訳がない欲を知られて……失望されたのだ。自分は。
きっと。
ならば翌日、そして今日まで普通に朝の調教に乗ってくれていることは、喜びこそすれ、がっかりするなどもってのほかのことだろう。
自分のせいで二人の間にある空気をぎこちないものに変えてしまったのに、シィンはそれを見なかったことにしてくれている……。
(殿下……)
ダンジァは、今朝も自分に乗ってくれたシィンを思う。
少し前までは、王の騏驥でもない自分に、特別に乗ってもらえていることが嬉しかった。でも今は、当たり前のように、普通に、自然に乗ってくれることが嬉しい。
(殿下……)
ダンジァは噛み締めるように胸中でつぶやく。
嬉しい。けれど嬉しいから切ない。
欲が出て、もっと乗っていて欲しいと思ってしまう。大会が終わってからも、ずっと。
ずっと、彼のそばにいられたら。
彼のためだけに駆けることができたなら……。
(……違う)
違う。
それだけじゃない。
もう、それだけじゃない。
ダンジァは一層きつく拳を握りしめた。
自分が抱く希望は、願望は、欲は、もうそれだけじゃない。
自分は騏驥として仕えるだけでなく、ただ乗ってもらうだけでなく、ただ駆けるだけでなく——もっと深く、彼と繋がりたいと思っている。
もっと強く信じられたいし、もっと深く想われたい。
もっと見てほしいしもっと見ていたい。誰よりも側で。彼の側で。より近くで。
できるなら、他愛無く触れ合えるような、そんな距離で。
なんと大それた望み……!
けれどそれが偽らざる本心だ。
シィンの「戯れ」で気付かされた本心だ。
そんなはずはない、と目を逸らし続けていた本心。
自分は、彼を求めているのだ。
彼のものになりたいし、同時に——。
(ああ……)
想像して、ダンジァは眉を寄せる。
自分はいつからこんな——不埒極まりない欲望を抱く男になったのか。
しかもよりによって相手は王子。願いが叶うことなどありえないだろう。
あの美しい星が欲しい、と天空を見上げて手を伸ばしているようなものだ。どれだけ欲しくても背伸びをしても、どれだけ跳んでみても触れることすら叶わないのに。
そう。相手は王子なのだ。
ダンジァは、サイ師から聞かされた話を思い出す。
シィンの部屋から厩舎地区に戻ったその日。
王城での出来事は既にサイ師にも報告されていたのだろう。ダンジァは師に呼ばれたのだ。
大丈夫だったか、と心配され、気をつけなければな、と優しく助言された。そして教えられたのだ。
「王の騏驥」という存在の意義、そして、そもそもそれがどうしてできたかを。
サイ師のもとへは、ツォ師からの謝罪もあったらしい。「騏驥たちの管理が行き渡らなくて申し訳ない」と。
それを受けてか、サイ師はダンジァに「騏驥たちを恨むなよ」と言った。
ダンジァは素直に頷いた。
恨んではいない。ただ、シィンから渡されていたものに触れられそうになったのが許せなかっただけだ。
そしてそんな思いは、師から「王の騏驥」の成り立ちを聞いて一層強くなったが、ダンジァが一番ショックを受けたのはそのことではなかった。
「王の騏驥」がいる意味は、王や王族が他の騎士の騏驥を召し上げないようにするため。
そしてまた同時に、政に食い込むことを企み王族に近づかんとする愚かな騏驥を寄せつけぬようにするため……。
その説明をサイ師から聞いた時、ダンジァは「そうですね」と頷いた。
なるほど、そうですね。納得しました。そういう理由だったのですね……。
けれど胸の内は言葉にできないほどの恐怖でいっぱいだった。
自分は違う、と叫びたかった。
自分は違うのです。政など興味はなく、ただただ殿下の側に居たいだなのです、と。
だが、心の中など誰にわかるだろう?
欲望の種類など、どう区別できるというのか。
いやそもそも。
そんな風に望むことが禁忌なのだ。
側にいたいと望むことが。下心があると思われても仕方がないことなのだ。
しかも自分は「ただ」側にいたいだけじゃない。
ただ騏驥として側にいたいだけじゃない。
それ以上の欲がある。
ならばもし。
自分の気持ちがシィンに知れたら……?
「……おい? 大丈夫か」
と、その時。軽く肩を揺さぶられる。
はっとみると、シュウインが気遣うような顔でこちらを覗き込んできていた。
「話……聞こえてたか? それともどこか具合が?」
「あ……いえ」
慌ててダンジァは首を振る。
そうだ。せっかく彼が案内してくれていたのに、すっかり他のことを考えていた。シィンのことを考えていた。
「その、すみません。ちょっと……ええと……」
何か言わなければと焦るものの、なにを言っても言い訳だ。
申し訳なくてなにも言えなくなってしまうと、シュウインは一瞬戸惑うような顔を見せたのち、ポンと肩を叩いてきた。
「すまない。歩き通しで疲れさせたな。少し休もう。こっちへ——」
そして彼は、近くの中庭に誘ってくれる。そのまま、そこにある椅子に座らされた。
「何か飲み物でも持ってくるよ」
次いで彼はそう言うと、ダンジァが止める間もなく、いそいそと踵を返す。
ダンジァは申し訳なさに苛まれつつ、木陰でふうっと息をついた。
厚意に甘えておきながら、それを無下にするような真似をしてしまうなんて……。まったく、何から何までダメじゃないか。
シィンのことは、もう考えないようにすべきなのだろう。
諦めるべきなのだ。そもそも懸想することさえ許されない相手なのだから。
(懸想、か)
馬鹿だな、と自嘲が漏れた。
思慮深いとか賢いとか。そんなふうに評価されることが多かったから、自分は「そう」なのだろうと思っていた。
愚かなことはしない騏驥なのだと。我慢ができる騏驥なのだと。過ちに気づけば正せる騏驥なのだと——いや、過ちになる前に回避できるのだと。
それが。
こんな有様だ。
どうやら自分は思っていたより賢くも思慮深くもなかったらしい。
それとも、誰かを恋い慕う気持ちは理性の外側にあるものなのだろうか。
いずれにせよ、耐えて諦めるしかないのだけれど。
大会まではこみ上げてくる自分の気持ちに耐えて、ただただ忠実に結果のために、彼のために走り、そしてそれが過ぎれば諦めるように努力するしかない……。
(できるのかな……)
しかし果たして、そんな器用なことが自分にできるのだろうか。
「思慮深い」「賢い」と言われるのと同じぐらい、真面目で不器用な自分に……。
また一つため息をつきかけた時。
「——はい、どうぞ。爽草水だよ。これなら大会前でも大丈夫だろう?」
シュウインが戻ってくる。
差し出されたのは、玻璃杯に入った薬草水だ。少し青みがかっているのが美しい。恐縮しつつも「ありがとうございます」と受け取り、一気に飲む。
冷えたそれはさっぱりとした味わいでとても美味しかった。
「わざわざありがとうございます。しかも気を遣ってくださって……」
自分のために持ってきてくれただけでなく、大会前だということに配慮して、口に入れても大丈夫なものを選んでくれたことが嬉しい。そう、現在のダンジァはそろそろ飲食物に制限がかかっているのだ。飲食物、薬……。大会当日の薬物検査に引っかからないようにするために。
すると、シュウインは「当然だよ」と笑った。
「そのためにわたしが付いているんだから。大会前のきみに何かあってはね」
明るく言って、彼も同じ物を飲む。「美味しい」と笑った。
「シュウイン……さんは大会に出たことはあるんですか?」
ダンジァが尋ねると、シュウインは「”さん”はいらないよ」と微笑む。
「同じ育成厩舎だった仲なんだ。同期といえば同期なんだから」
「……はい……」
ダンジァとしてはあまりそんな実感はないのだが、気さくに言われれば悪い気はしない。シュウインは続ける。
「王の騏驥たちの代表として、何度か出たことはあるかな。実は、今回の大会も出場の話はあったんだ。殿下の騎乗でね」
「えっ!?」
初耳だ。
戸惑うダンジァに、シュウインは「違う違う」というように首を振った。
「まだ大会の話が具体化する前だよ。かなり前の話で……当初は、殿下の主催なら殿下も何か出た方が、っていう話があったんだ。まだ構想段階の頃の話だよ」
「……」
「でもその話は正式化する前に立ち消えになって……殿下は出ない、っていう形での開催になったというわけ」
「それは……」
どう言えばいいのだろう。
構想段階とはいえ、出るかもしれない、という話が「出ない」になり、再度「出る」ということになったというわけか。
二転三転したわけだ。シィンの都合で。
そしてその「都合」にはダンジァも関わっていて……。
もちろんそれだけが理由ではないかもしれないけれど。
黙り込んだダンジァを気にしたのだろう。シュウインが苦笑混じりに続ける。
「きみが気にすることはないんだ。大会の形式は変わるものだし、出場するかしないかだって、登録が終わっても決まらなかったりするのはザラなんだから。それに、出場しないことで今回は裏方として大会を見ることができるし」
「? 裏方?」
「ああ」
どうやら、今回の大会では、王の騏驥たちは数頭の参加者のほか大会の運営側として携わることになったらしい。要は、手伝いだ。
「初めての試みなんだけど、ツォ先生が殿下に提案されたようでね。王の騏驥たちなら、城の中のことには詳しいだろう? なら、大会の手伝いとして役に立つんじゃないか、ということらしい。あとは、少し他の騏驥たちの様子も知れた方がいい、ということのようだね。わたしたちは他の騏驥たちをほとんど見ることがないから」
「……」
なるほど、とダンジァは頷く。ツォ師は色々と考えてくださっているようだ。
流石に王の騏驥たちの調教師——というところか。
いつだったか——。
朝、殿下に調教をつけてもらい、坂路を順調に二本駆け登りクールダウンをしていたとき。
何かの話の流れで、ツォ師のことになったことがあった。
シィンに、『ツォをどう思う?』と尋ねられたのだ。サイ師とは調教の方針も違うだろうから、やり辛くはないか、と。
だがダンジァは「大丈夫です」と答えた。
師は、いつも少し離れて調教を見ている。
騏驥に乗ることはなく、見ようによってはただ漠然と見ているだけにも思えるのに、どの騏驥に対しての指示も的確で、だから常々すごいなと思っている、とダンジァは話した。
すると、シィンも師について話してくれた。ずいぶん昔から二人は親しいようだった。
『父の代から仕えてくれている。父親を訪ねて城にやってきたりもしていたから、子供の頃から互いを知っているな。馬に乗るのも上手かった。わたしよりも上手かったほどだが……結局は父親と同じ道を選んでわたしを支えてくれている』
調教後でいささか昂っているダンジァの気持ちを宥め、激しい運動後で震える全身の筋肉を緩やかに平常に戻すようにゆっくりと森の中を歩かせてくれながら、背の上からシィンは話してくれたのだった。
その声は落ち着いていて穏やかで、「仕えてくれている」「支えてくれている」と話しながらも友人のことを語っているようでもあった。
以前の「話し合い」の時にも感じたが、側近のうちの一人なのだろう。
こんなふうにシュウインを側につけてくれていることにも、感謝しきりだ。
なのに、そんなシュウインの話よりもシィンのことを考える方に夢中になってしまうなんて……。
反省しなければ、と思いながら、ダンジァは「そうなんですね」と相槌を打った。
「そういうことになっているとは知りませんでした。でも確かに城に慣れていない騏驥は助かると思います。当日は、シュウインさ……シュウインも、その手伝いに?」
「加わる予定ではいるよ。規模の大きな大会は華やかだから、携われるだけでも楽しそうだし……。ああ、もちろん与えられた仕事はちゃんとやりつつ楽しむ、ってことだけどね」
言って、シュウインはにっこり微笑む。ダンジァもつられるように笑みを浮かべた。
「じゃあ、当日も会えるかもしれませんね。……よろしくお願いします」
「わからないことがあったらなんでも訊いてくれ」
シュウインは言うと、「じゃあ、続きを案内しようか」と立ち上がる。
ダンジァも腰を上げ、シュウインに再び案内してもらっていると、城内の雰囲気も心なしか以前より慌ただしい気がしてくる。なんとなく伝わってくる。
と言っても、以前城の中に足を踏み入れたのは、シィンの部屋に連れられた時とその帰りのことだから、周りなんて見ていたようで見ていなかったのだけれど……。
それでも、いよいよ大会が近いのだ、緊張が高まってくる。
あと何回、シィンに乗ってもらえるだろう。
そして当日の最後の騎乗の後、自分は彼を忘れられるのだろうか……。
(っ……)
また考えている——と、ダンジァが人知れず顔を顰め、振り切るように頭を振った、その時。
「……ダンジァ?」
声が届く。
聞き覚えのある声に振り返ると、そこには、以前乗ってもらいたいと焦がれた騎士——リィがいた。
シィンはこちらが拍子抜けするほど「普通」で。
いつも通りで……。
なんだか……。
なんだかとてもがっかりしてしまったのだ。
やはり彼にとっては自分に触れることなど些細なことなのか、と。
薬を飲ませてくれたことも、それがもしかしたら口移しだったことも、単に「一晩面倒を診る」ことの延長で、こちらが思ったような、動揺してしまったような深い意味はないのか、と。
(でも……考えてみれば当然だ……)
そう。考えてみればそんなこと問題にもならないようなことなのだ。
そもそも、普通の騎士にとってだって、騏驥はただの兵器だ。
元が人で、人の知性を宿し人の姿の時は人と同じものを食べ同じものを着るだけで、実態は「馬に変わる人間」——異形なのだ。
普通の人とは決定的に違う。もちろん騎士とも。
そんな相手をどうして同じ人間のように扱えるだろう。
騏驥を徹底的に道具として用いる騎士がいる一方、愛着を持ち、優しく触れる者もいないことはない。
が、それは「手に合う騏驥」「使いやすい騏驥」「乗りやすい騏驥」を気にかけているだけだ。愛用の道具の手入れをするように。
——そういうことだ。
騏驥は人ではないのだから。
そして、そんな騎士たちをさらに従えているのが彼なのだ。
王子。
いずれ王位を継ぐお方。
そんな方が、騏驥の自分を「自らと同じ立場」に考えるわけがない。思うわけがない。
あの行為だって——口付けだって、まさしく「お戯れ」だったのだろう。
彼は多分、巫山戯ていただけだ。
こちらがどんな反応をするか、見てみたかっただけだろう。
もしくは、大会の前に試してみたかったのかもしれない。
咄嗟の時にどんな反応をするか。思いがけない事態にぶつかった時にどう対処するか……。
なのに自分は自分の醜い衝動に流されてシィンを抱きしめるような真似をしてしまった。欲望に流されて彼の唇を貪るような真似をして……。
挙句、それを彼のせいにしたのだ。
彼がからかってきたからだ、と。
そんなこと言える立場ではないのに。
王子である彼が騏驥である自分を揶揄うことに、何の問題があろうものか。試すことのなにが悪かろうか。
なのに自分は恐れ多くも、そんな彼に対して憤りを覚えたのだ。
まるで対等な存在であるかのように。
「どうしてこんなことを」と。
自分に疚しさがあるから……だからそれを誤魔化そうとして……。
戯れはやめて欲しいなんて言っておいて、その実自分はそれを悦んだくせに。
ダンジァはぎゅっと拳を握りしめる。
だからシィンは早々に部屋を出て行ったのではないだろうか。
失望したのだろう、こちらの態度に。
騏驥の分際で、しかも彼に大きな世話になった騏驥の分際で、彼の当然の行為を責めるようなことを言ったのだから。
でなければ、こちらの欲を知られた。騎士に対して、王子に対して想った言い訳がない欲を知られて……失望されたのだ。自分は。
きっと。
ならば翌日、そして今日まで普通に朝の調教に乗ってくれていることは、喜びこそすれ、がっかりするなどもってのほかのことだろう。
自分のせいで二人の間にある空気をぎこちないものに変えてしまったのに、シィンはそれを見なかったことにしてくれている……。
(殿下……)
ダンジァは、今朝も自分に乗ってくれたシィンを思う。
少し前までは、王の騏驥でもない自分に、特別に乗ってもらえていることが嬉しかった。でも今は、当たり前のように、普通に、自然に乗ってくれることが嬉しい。
(殿下……)
ダンジァは噛み締めるように胸中でつぶやく。
嬉しい。けれど嬉しいから切ない。
欲が出て、もっと乗っていて欲しいと思ってしまう。大会が終わってからも、ずっと。
ずっと、彼のそばにいられたら。
彼のためだけに駆けることができたなら……。
(……違う)
違う。
それだけじゃない。
もう、それだけじゃない。
ダンジァは一層きつく拳を握りしめた。
自分が抱く希望は、願望は、欲は、もうそれだけじゃない。
自分は騏驥として仕えるだけでなく、ただ乗ってもらうだけでなく、ただ駆けるだけでなく——もっと深く、彼と繋がりたいと思っている。
もっと強く信じられたいし、もっと深く想われたい。
もっと見てほしいしもっと見ていたい。誰よりも側で。彼の側で。より近くで。
できるなら、他愛無く触れ合えるような、そんな距離で。
なんと大それた望み……!
けれどそれが偽らざる本心だ。
シィンの「戯れ」で気付かされた本心だ。
そんなはずはない、と目を逸らし続けていた本心。
自分は、彼を求めているのだ。
彼のものになりたいし、同時に——。
(ああ……)
想像して、ダンジァは眉を寄せる。
自分はいつからこんな——不埒極まりない欲望を抱く男になったのか。
しかもよりによって相手は王子。願いが叶うことなどありえないだろう。
あの美しい星が欲しい、と天空を見上げて手を伸ばしているようなものだ。どれだけ欲しくても背伸びをしても、どれだけ跳んでみても触れることすら叶わないのに。
そう。相手は王子なのだ。
ダンジァは、サイ師から聞かされた話を思い出す。
シィンの部屋から厩舎地区に戻ったその日。
王城での出来事は既にサイ師にも報告されていたのだろう。ダンジァは師に呼ばれたのだ。
大丈夫だったか、と心配され、気をつけなければな、と優しく助言された。そして教えられたのだ。
「王の騏驥」という存在の意義、そして、そもそもそれがどうしてできたかを。
サイ師のもとへは、ツォ師からの謝罪もあったらしい。「騏驥たちの管理が行き渡らなくて申し訳ない」と。
それを受けてか、サイ師はダンジァに「騏驥たちを恨むなよ」と言った。
ダンジァは素直に頷いた。
恨んではいない。ただ、シィンから渡されていたものに触れられそうになったのが許せなかっただけだ。
そしてそんな思いは、師から「王の騏驥」の成り立ちを聞いて一層強くなったが、ダンジァが一番ショックを受けたのはそのことではなかった。
「王の騏驥」がいる意味は、王や王族が他の騎士の騏驥を召し上げないようにするため。
そしてまた同時に、政に食い込むことを企み王族に近づかんとする愚かな騏驥を寄せつけぬようにするため……。
その説明をサイ師から聞いた時、ダンジァは「そうですね」と頷いた。
なるほど、そうですね。納得しました。そういう理由だったのですね……。
けれど胸の内は言葉にできないほどの恐怖でいっぱいだった。
自分は違う、と叫びたかった。
自分は違うのです。政など興味はなく、ただただ殿下の側に居たいだなのです、と。
だが、心の中など誰にわかるだろう?
欲望の種類など、どう区別できるというのか。
いやそもそも。
そんな風に望むことが禁忌なのだ。
側にいたいと望むことが。下心があると思われても仕方がないことなのだ。
しかも自分は「ただ」側にいたいだけじゃない。
ただ騏驥として側にいたいだけじゃない。
それ以上の欲がある。
ならばもし。
自分の気持ちがシィンに知れたら……?
「……おい? 大丈夫か」
と、その時。軽く肩を揺さぶられる。
はっとみると、シュウインが気遣うような顔でこちらを覗き込んできていた。
「話……聞こえてたか? それともどこか具合が?」
「あ……いえ」
慌ててダンジァは首を振る。
そうだ。せっかく彼が案内してくれていたのに、すっかり他のことを考えていた。シィンのことを考えていた。
「その、すみません。ちょっと……ええと……」
何か言わなければと焦るものの、なにを言っても言い訳だ。
申し訳なくてなにも言えなくなってしまうと、シュウインは一瞬戸惑うような顔を見せたのち、ポンと肩を叩いてきた。
「すまない。歩き通しで疲れさせたな。少し休もう。こっちへ——」
そして彼は、近くの中庭に誘ってくれる。そのまま、そこにある椅子に座らされた。
「何か飲み物でも持ってくるよ」
次いで彼はそう言うと、ダンジァが止める間もなく、いそいそと踵を返す。
ダンジァは申し訳なさに苛まれつつ、木陰でふうっと息をついた。
厚意に甘えておきながら、それを無下にするような真似をしてしまうなんて……。まったく、何から何までダメじゃないか。
シィンのことは、もう考えないようにすべきなのだろう。
諦めるべきなのだ。そもそも懸想することさえ許されない相手なのだから。
(懸想、か)
馬鹿だな、と自嘲が漏れた。
思慮深いとか賢いとか。そんなふうに評価されることが多かったから、自分は「そう」なのだろうと思っていた。
愚かなことはしない騏驥なのだと。我慢ができる騏驥なのだと。過ちに気づけば正せる騏驥なのだと——いや、過ちになる前に回避できるのだと。
それが。
こんな有様だ。
どうやら自分は思っていたより賢くも思慮深くもなかったらしい。
それとも、誰かを恋い慕う気持ちは理性の外側にあるものなのだろうか。
いずれにせよ、耐えて諦めるしかないのだけれど。
大会まではこみ上げてくる自分の気持ちに耐えて、ただただ忠実に結果のために、彼のために走り、そしてそれが過ぎれば諦めるように努力するしかない……。
(できるのかな……)
しかし果たして、そんな器用なことが自分にできるのだろうか。
「思慮深い」「賢い」と言われるのと同じぐらい、真面目で不器用な自分に……。
また一つため息をつきかけた時。
「——はい、どうぞ。爽草水だよ。これなら大会前でも大丈夫だろう?」
シュウインが戻ってくる。
差し出されたのは、玻璃杯に入った薬草水だ。少し青みがかっているのが美しい。恐縮しつつも「ありがとうございます」と受け取り、一気に飲む。
冷えたそれはさっぱりとした味わいでとても美味しかった。
「わざわざありがとうございます。しかも気を遣ってくださって……」
自分のために持ってきてくれただけでなく、大会前だということに配慮して、口に入れても大丈夫なものを選んでくれたことが嬉しい。そう、現在のダンジァはそろそろ飲食物に制限がかかっているのだ。飲食物、薬……。大会当日の薬物検査に引っかからないようにするために。
すると、シュウインは「当然だよ」と笑った。
「そのためにわたしが付いているんだから。大会前のきみに何かあってはね」
明るく言って、彼も同じ物を飲む。「美味しい」と笑った。
「シュウイン……さんは大会に出たことはあるんですか?」
ダンジァが尋ねると、シュウインは「”さん”はいらないよ」と微笑む。
「同じ育成厩舎だった仲なんだ。同期といえば同期なんだから」
「……はい……」
ダンジァとしてはあまりそんな実感はないのだが、気さくに言われれば悪い気はしない。シュウインは続ける。
「王の騏驥たちの代表として、何度か出たことはあるかな。実は、今回の大会も出場の話はあったんだ。殿下の騎乗でね」
「えっ!?」
初耳だ。
戸惑うダンジァに、シュウインは「違う違う」というように首を振った。
「まだ大会の話が具体化する前だよ。かなり前の話で……当初は、殿下の主催なら殿下も何か出た方が、っていう話があったんだ。まだ構想段階の頃の話だよ」
「……」
「でもその話は正式化する前に立ち消えになって……殿下は出ない、っていう形での開催になったというわけ」
「それは……」
どう言えばいいのだろう。
構想段階とはいえ、出るかもしれない、という話が「出ない」になり、再度「出る」ということになったというわけか。
二転三転したわけだ。シィンの都合で。
そしてその「都合」にはダンジァも関わっていて……。
もちろんそれだけが理由ではないかもしれないけれど。
黙り込んだダンジァを気にしたのだろう。シュウインが苦笑混じりに続ける。
「きみが気にすることはないんだ。大会の形式は変わるものだし、出場するかしないかだって、登録が終わっても決まらなかったりするのはザラなんだから。それに、出場しないことで今回は裏方として大会を見ることができるし」
「? 裏方?」
「ああ」
どうやら、今回の大会では、王の騏驥たちは数頭の参加者のほか大会の運営側として携わることになったらしい。要は、手伝いだ。
「初めての試みなんだけど、ツォ先生が殿下に提案されたようでね。王の騏驥たちなら、城の中のことには詳しいだろう? なら、大会の手伝いとして役に立つんじゃないか、ということらしい。あとは、少し他の騏驥たちの様子も知れた方がいい、ということのようだね。わたしたちは他の騏驥たちをほとんど見ることがないから」
「……」
なるほど、とダンジァは頷く。ツォ師は色々と考えてくださっているようだ。
流石に王の騏驥たちの調教師——というところか。
いつだったか——。
朝、殿下に調教をつけてもらい、坂路を順調に二本駆け登りクールダウンをしていたとき。
何かの話の流れで、ツォ師のことになったことがあった。
シィンに、『ツォをどう思う?』と尋ねられたのだ。サイ師とは調教の方針も違うだろうから、やり辛くはないか、と。
だがダンジァは「大丈夫です」と答えた。
師は、いつも少し離れて調教を見ている。
騏驥に乗ることはなく、見ようによってはただ漠然と見ているだけにも思えるのに、どの騏驥に対しての指示も的確で、だから常々すごいなと思っている、とダンジァは話した。
すると、シィンも師について話してくれた。ずいぶん昔から二人は親しいようだった。
『父の代から仕えてくれている。父親を訪ねて城にやってきたりもしていたから、子供の頃から互いを知っているな。馬に乗るのも上手かった。わたしよりも上手かったほどだが……結局は父親と同じ道を選んでわたしを支えてくれている』
調教後でいささか昂っているダンジァの気持ちを宥め、激しい運動後で震える全身の筋肉を緩やかに平常に戻すようにゆっくりと森の中を歩かせてくれながら、背の上からシィンは話してくれたのだった。
その声は落ち着いていて穏やかで、「仕えてくれている」「支えてくれている」と話しながらも友人のことを語っているようでもあった。
以前の「話し合い」の時にも感じたが、側近のうちの一人なのだろう。
こんなふうにシュウインを側につけてくれていることにも、感謝しきりだ。
なのに、そんなシュウインの話よりもシィンのことを考える方に夢中になってしまうなんて……。
反省しなければ、と思いながら、ダンジァは「そうなんですね」と相槌を打った。
「そういうことになっているとは知りませんでした。でも確かに城に慣れていない騏驥は助かると思います。当日は、シュウインさ……シュウインも、その手伝いに?」
「加わる予定ではいるよ。規模の大きな大会は華やかだから、携われるだけでも楽しそうだし……。ああ、もちろん与えられた仕事はちゃんとやりつつ楽しむ、ってことだけどね」
言って、シュウインはにっこり微笑む。ダンジァもつられるように笑みを浮かべた。
「じゃあ、当日も会えるかもしれませんね。……よろしくお願いします」
「わからないことがあったらなんでも訊いてくれ」
シュウインは言うと、「じゃあ、続きを案内しようか」と立ち上がる。
ダンジァも腰を上げ、シュウインに再び案内してもらっていると、城内の雰囲気も心なしか以前より慌ただしい気がしてくる。なんとなく伝わってくる。
と言っても、以前城の中に足を踏み入れたのは、シィンの部屋に連れられた時とその帰りのことだから、周りなんて見ていたようで見ていなかったのだけれど……。
それでも、いよいよ大会が近いのだ、緊張が高まってくる。
あと何回、シィンに乗ってもらえるだろう。
そして当日の最後の騎乗の後、自分は彼を忘れられるのだろうか……。
(っ……)
また考えている——と、ダンジァが人知れず顔を顰め、振り切るように頭を振った、その時。
「……ダンジァ?」
声が届く。
聞き覚えのある声に振り返ると、そこには、以前乗ってもらいたいと焦がれた騎士——リィがいた。
0
あなたにおすすめの小説

追放された『呪物鑑定』持ちの公爵令息、魔王の呪いを解いたら執着溺愛ルートに入りました
水凪しおん
BL
「お前のそのスキルは不吉だ」
身に覚えのない罪を着せられ、聖女リリアンナによって国を追放された公爵令息カイル。
死を覚悟して彷徨い込んだ魔の森で、彼は呪いに蝕まれ孤独に生きる魔王レイルと出会う。
カイルの持つ『呪物鑑定』スキル――それは、魔王を救う唯一の鍵だった。
「カイル、お前は我の光だ。もう二度と離さない」
献身的に尽くすカイルに、冷徹だった魔王の心は溶かされ、やがて執着にも似た溺愛へと変わっていく。
これは、全てを奪われた青年が魔王を救い、世界一幸せになる逆転と愛の物語。

【完結】極貧イケメン学生は体を売らない。【番外編あります】
紫紺
BL
貧乏学生をスパダリが救済!?代償は『恋人のフリ』だった。
相模原涼(さがみはらりょう)は法学部の大学2年生。
超がつく貧乏学生なのに、突然居酒屋のバイトをクビになってしまった。
失意に沈む涼の前に現れたのは、ブランドスーツに身を包んだイケメン、大手法律事務所の副所長 城南晄矢(じょうなんみつや)。
彼は涼にバイトしないかと誘うのだが……。
※番外編を公開しました(2024.10.21)
生活に追われて恋とは無縁の極貧イケメンの涼と、何もかもに恵まれた晄矢のラブコメBL。二人の気持ちはどっちに向いていくのか。
※本作品中の公判、判例、事件等は全て架空のものです。完全なフィクションであり、参考にした事件等もございません。拙い表現や現実との乖離はどうぞご容赦ください。

箱庭の子ども〜世話焼き侍従と訳あり王子〜
真木もぐ
BL
「他人に触られるのも、そばに寄られるのも嫌だ。……怖い」
現代ヨーロッパの小国。王子として生まれながら、接触恐怖症のため身分を隠して生活するエリオットの元へ、王宮から侍従がやって来る。ロイヤルウェディングを控えた兄から、特別な役割で式に出て欲しいとの誘いだった。
無理だと断り、招待状を運んできた侍従を追い返すのだが、この侍従、己の出世にはエリオットが必要だと言って譲らない。
しかし散らかり放題の部屋を見た侍従が、説得より先に掃除を始めたことから、二人の関係は思わぬ方向へ転がり始める。
おいおい、ロイヤルウエディングどこ行った?
世話焼き侍従×ワケあり王子の恋物語。
※は性描写のほか、注意が必要な表現を含みます。
この小説は、投稿サイト「ムーンライトノベルズ」「エブリスタ」「カクヨム」で掲載しています。

イケメン俳優は万年モブ役者の鬼門です
はねビト
BL
演技力には自信があるけれど、地味な役者の羽月眞也は、2年前に共演して以来、大人気イケメン俳優になった東城湊斗に懐かれていた。
自分にはない『華』のある東城に対するコンプレックスを抱えるものの、どうにも東城からのお願いには弱くて……。
ワンコ系年下イケメン俳優×地味顔モブ俳優の芸能人BL。
外伝完結、続編連載中です。

前世が教師だった少年は辺境で愛される
結衣可
BL
雪深い帝国北端の地で、傷つき行き倒れていた少年ミカを拾ったのは、寡黙な辺境伯ダリウスだった。妻を亡くし、幼い息子リアムと静かに暮らしていた彼は、ミカの知識と優しさに驚きつつも、次第にその穏やかな笑顔に心を癒されていく。
ミカは実は異世界からの転生者。前世の記憶を抱え、この世界でどう生きるべきか迷っていたが、リアムの教育係として過ごすうちに、“誰かに必要とされる”温もりを思い出していく。
雪の館で共に過ごす日々は、やがてお互いにとってかけがえのない時間となり、新しい日々へと続いていく――。

死に戻り騎士は、今こそ駆け落ち王子を護ります!
時雨
BL
「駆け落ちの供をしてほしい」
すべては真面目な王子エリアスの、この一言から始まった。
王子に”国を捨てても一緒になりたい人がいる”と打ち明けられた、護衛騎士ランベルト。
発表されたばかりの公爵家令嬢との婚約はなんだったのか!?混乱する騎士の気持ちなど関係ない。
国境へ向かう二人を追う影……騎士ランベルトは追手の剣に倒れた。
後悔と共に途切れた騎士の意識は、死亡した時から三年も前の騎士団の寮で目覚める。
――二人に追手を放った犯人は、一体誰だったのか?
容疑者が浮かんでは消える。そもそも犯人が三年先まで何もしてこない保証はない。
怪しいのは、王位を争う第一王子?裏切られた公爵令嬢?…正体不明の駆け落ち相手?
今度こそ王子エリアスを護るため、過去の記憶よりも積極的に王子に関わるランベルト。
急に距離を縮める騎士を、はじめは警戒するエリアス。ランベルトの昔と変わらぬ態度に、徐々にその警戒も解けていって…?
過去にない行動で変わっていく事象。動き出す影。
ランベルトは今度こそエリアスを護りきれるのか!?
負けず嫌いで頑固で堅実、第二王子(年下) × 面倒見の良い、気の長い一途騎士(年上)のお話です。
-------------------------------------------------------------------
主人公は頑な、王子も頑固なので、ゆるい気持ちで見守っていただけると幸いです。

ヒールオメガは敵騎士の腕の中~平民上がりの癒し手は、王の器に密かに溺愛される
七角@書籍化進行中!
BL
君とどうにかなるつもりはない。わたしはソコロフ家の、君はアナトリエ家の近衛騎士なのだから。
ここは二大貴族が百年にわたり王位争いを繰り広げる国。
平民のオメガにして近衛騎士に登用されたスフェンは、敬愛するアルファの公子レクスに忠誠を誓っている。
しかしレクスから賜った密令により、敵方の騎士でアルファのエリセイと行動を共にする破目になってしまう。
エリセイは腹が立つほど呑気でのらくら。だが密令を果たすため仕方なく一緒に過ごすうち、彼への印象が変わっていく。
さらに、蔑まれるオメガが実は、この百年の戦いに終止符を打てる存在だと判明するも――やはり、剣を向け合う運命だった。
特別な「ヒールオメガ」が鍵を握る、ロミジュリオメガバース。
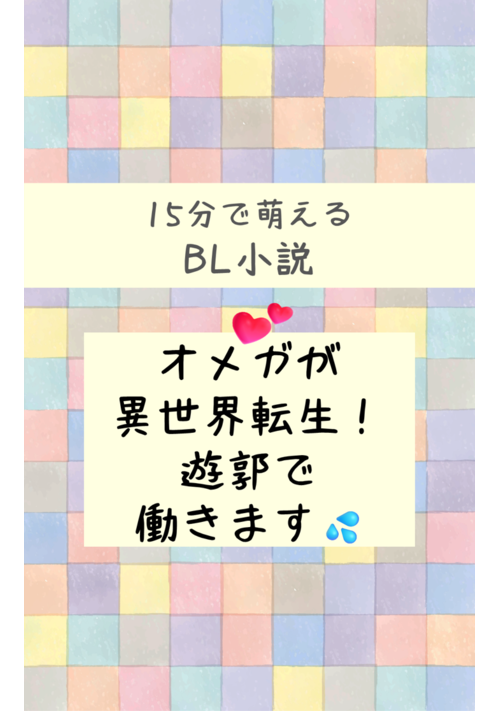
異世界の遊郭に拾われたオメガは、ただ一人に愛される
雪代鞠絵/15分で萌えるBL小説
BL
オメガであることでさんざんな目に遭ってきたオメガちゃん。
オメガである自分が大嫌い!
ある日事故に遭い、目が覚めたらそこは異世界。
何故か遊郭に拾われますが、そこはオメガだけが働くお店で戸惑う
ことばかり。
しかも、お客であるアルファ氏には毎日からかわれて?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















