1 / 35
第一章 皇妃候補から外れた公爵令嬢
第一話 軌道から外れた日
しおりを挟む水が張られたガラス容器に、黄緑色の若葉がぷかぷかと浮いている。
この日、二十六歳の誕生日を迎えたソフィリア・ビス・ロートリアスのもとにやってきたのは、そんな瑞々しい存在だった。
泰平の大国グラディアトリア。
帝都の中ほどに立つ王城の敷地内には大きな池があり、毎年この時期になると北からやってきた渡鳥が卵を産んで子育てをする。
そんな池に臨む王宮の一角にソフィリアが部屋をもらってから、もう七年の歳月が過ぎようとしていた。
一人用のベッドと備え付けのクローゼット、それから窓際に小さなテーブルと椅子があるだけのこぢんまりとした部屋は、王宮に仕える者が与えられる一般的なものだ。
グラディアトリアの四公爵家の一つ、ロートリアス公爵家の令嬢であるソフィリアが住まうにはいささか質素だが、彼女自身はこの部屋をとても気に入っていた。
質素といえば、今の彼女の服装もそうだろう。
濃紺のワンピースは、侍女のお仕着せ同様王城から支給されるものだ。
その日の気分で選んだスカーフを襟元に巻いてブローチで留めるのは、気持ちばかりのお洒落である。
窓の向こうでは、いつの間にか頭上を通り過ぎた太陽が西へと傾き始めた。
部屋の中に差し込む光にも、かすかに夕暮れの気配が混ざってくる。
それに照らされたテーブルの上には、普段は王城の図書館で借りた歴史書や古文書などといった小難しい文献が山積みになっていた。
しかしこの日、それらの代わりに載っていたのは大きな白い箱。
その中身はというと、つい先ほど六等分に切り分けられ、一つはすでにソフィリアの胃袋に収まっていた。
旬の果物がふんだんに使われた、スポンジとレアチーズが二層になったケーキだ。
そして、ソフィリアと一緒にそれを食べたのが、彼女の誕生日を祝おうとこのケーキを作ってきた本人である。
その人は今、椅子に腰掛けたソフィリアの後ろに立って、せっせと手を動かしていた。
腰ほどまで伸ばした彼女の深い栗色の髪を、華奢な手が一つに束ねて縄のように捻り上げながらその根本にしっかりと巻き付けていく。
そうして最後、後頭部でまとめた髪を留めるために上から挿し込まれたのは、ソフィリアには馴染みのない形状の髪留めだった。
大きな串のような格好をしており、ころんと丸い白磁の飾りの上からは、ソフィリアの瞳によく似た色のペリドットが金のビーズでぶら下がっている。
黄緑色が美しいペリドットには、身に着けた者の後悔や嫉妬、恨みなどといった負の感情を払拭し、夢や希望を叶えるために前向きな気持ちにさせる力があるという。
しかし何より、この日それを贈ってくれた人物こそが、ソフィリアをいつも明るい心地にさせてくれた。
「うんうん、ステキ! 簪、とっても似合ってるよ、ソフィ!」
髪留めを付け終わったその人が、ソフィリアの肩に両手を置いて声を弾ませる。
質素な服装のソフィリアとは違い、贅を凝らしたドレスで華奢な身体を包んだ妙齢の女性。
ソフィリアに、〝ソフィ〟という愛称をくれたのも、彼女だった。
「カンザシ、というのですね。ありがとう、大切にしますね――スミレ」
スミレ・ルト・レイスウェイク。
世にも珍しい黒い髪と、アメジストみたいな紫色の瞳をした彼女は、グラディアトリアの先の皇帝陛下にして、現在この国で唯一大公爵を名乗るヴィオラント・オル・レイスウェイクの妻である。
そして、ソフィリアの人生の軌道が大きく変わるきっかけとなった人物でもあった。
「あなたは皇妃となり、国母となるのよ」
ソフィリアは、物心ついた頃からずっと、母にそう言われて育ってきた。
現皇帝ルドヴィーク・フィア・グラディアトリアとは同い年。
他の三つの公爵家には彼と年齢の釣り合う女子がいない上、ソフィリアの父であるロートリアス公爵は先々代皇帝の治世より財務大臣を務め、先の皇帝ヴィオラントの大改革も支えた忠臣中の忠臣である。
つまりソフィリアは名実ともに、生まれた時からルドヴィークの皇妃最有力候補だったのだ。
エリザベス・フィア・グラディアトリア母后陛下――ルドヴィークの生母の覚えもめでたく、王宮を訪れた際には個人的にお茶に誘われることもしばしば。
ソフィリアが、自分が皇帝家にも優遇される特別な存在であると自認し、またそれが公然たる事実であると思い込んでも無理からぬことだろう。
ゆえに、他の令嬢達が若き皇帝の気を引こうと躍起になっていても気にならなかったし、余裕があった。
それなのに――
現皇帝ルドヴィークが玉座に就いて二年目。
彼が公私ともに落ち着き、そろそろ皇帝家からロートリアス公爵家に婚約の打診があるのではと噂され始めていた頃、事件が起こる。
――いや。
事件を起こしたのは、ソフィリア自身だった。
それは今から八年前――ちょうどソフィリアが十八歳になったばかりのことだ。
分家出身の幼馴染である護衛騎士ダリスとともに王城を訪れていたソフィリアは、母后陛下に挨拶を済ませて廊下を歩いている途中、ルドヴィークと出会した。
ただしこの時、彼の側にはソフィリアの胸をざわつかせる存在があった。
見たこともない黒いふわふわの髪と、先帝ヴィオラントと同じ稀少な紫色の瞳を持つ少女である。
そのあどけないかんばせは、ソフィリアお気に入りの――いや、グラディアトリア中の女の子を虜にした永遠の妹、ドール・クリスティーナにそっくり。
しかも、少女は甘い声でもってソフィリアを〝お姉様〟と呼び、ドレスを摘んで〝ごきげんよう〟と挨拶をして見せたのだ。
まさしく、愛玩人形のごとき愛らしさである。
しかし、ソフィリアが何より衝撃を受けたのは、その少女に向けられるルドヴィークの視線だった。
傍らの少女を映す彼の青い瞳に、恋情を思わせるほのかな熱が込められていることに気づいてしまったのである。
遠からずソフィリアを妻に迎えるはずの男が、ソフィリア以外の女に目を奪われている。
その事実を、彼女は受け入れることができなかった。
そんな事実は、あってはならないことだった。
(では、どうすればいい?)
そう問うたのは、ソフィリア自身。
そして――
(簡単だわ。あの少女を、私のものにしてしまえばいいのよ)
答えたのも、ソフィリア自身だった。
だって少女はさっき、ソフィリアのことを〝お姉様〟と呼んだではないか。
ふわふわのシフォンのドレスを両手で摘み、ちょこんと小首を傾げて〝お姉様〟と微笑んだではないか。
ソフィリアの前で乙女の永遠の妹ドール・クリスティーナを演じたからには、責任を持って愛玩人形になってもらおうではないか。
あれは、あの少女は、ソフィリアのクリスティーナだ。
皇帝ルドヴィークの心を掴んだのはクリスティーナであり、そのクリスティーナはソフィリアのもの。
ルドヴィークの心も、ソフィリアのもの。
「あの子が欲しいわ、ダリス」
ルドヴィークと少女の後ろ姿を見つめながら、ソフィリアは傍らに立つダリスに向かってそう言った。
この時、かすかに狂気を帯びたペリドットが凝視していた少女こそが、スミレであった。
「スミレにこうして誕生日を祝ってもらえる日がくるなんて……あの時は夢にも思いませんでした」
「まーだ、そんなこと言ってんの? ソフィ、毎年同じこと言ってるよ?」
頬に片手を当ててしみじみと呟くソフィリアに対し、スミレは聞き飽きたとばかりに呆れた顔をする。
八年前のあの日――愚かなソフィリアはダリスを使って、スミレが廊下で一人になった隙に拉致した。
自分のものと定めた愛玩人形を自分の屋敷に連れ帰る――その時のソフィリアに罪の意識などあるはずがなかった。
スミレの意思さえ、慮る必要などないと思い込んでいたのだ。
しかし、気を失ったスミレを押し込めて走っていた馬車の中で騒動が起き、街道で立ち往生しているところで、すでに彼女と浅からぬ仲であったレイスウェイク大公爵ヴィオラントが騎士団副長とともに駆けつけた。
スミレは元々ヴィオラントに連れられて、母后陛下に会うために王城を訪れていたのだ。
ソフィリアが彼女を無断で連れ去ったことは、その時点ですでに皇帝ルドヴィークの耳にまで入っていたらしい。
その後の街道でのやりとりは、馬車の中で起こった騒動の衝撃で気を失っていたソフィリアは詳しくは知らない。
ただ目覚めた時にはレイスウェイク大公爵家の馬車はすでに去った後。
ソフィリアは己の置かれた状況も理解できないまま、ダリスや侍女、御者ともども捕縛されて騎士団の簡素な馬車に乗せられた。
そうして身柄を王城に戻される道中、ソフィリアは自分が犯した罪の重さを思い知ったのである。
かつて、〝冷帝〟とも呼ばれて恐れられた先帝陛下は、愛玩人形のような黒髪の少女に心を奪われていた。
その少女を断りもなく連れ去ったソフィリア達に対する彼の怒りは、それはそれは凄まじかったという。
スミレがいなければ、自分達は先帝陛下によって首を刎ねられ、今こうして再び相見えることも叶わなかったであろう。
当時、ダリスは真っ青な顔をして、そうソフィリアに語った。
「年を重ねるごとに、当時の自分の愚かしさが身に染みます。なんて馬鹿なことをしてしまったのか、とあの時の自分の頬をひっぱたいてやりたい……」
「そんな黒歴史、もういいじゃない。思い出したって、つまんないだけでしょ」
過去に思いを馳せては後悔のため息を重ねるソフィリアに、スミレが肩を竦めて苦笑いを浮かべた。
その肩に付くか付かないかくらいの長さだった黒髪は、あの頃より随分と伸びている。
当時、彼女は十六歳。年齢よりずっとあどけなく見えた表情にも、今は少しばかり艶やかさが加わった。
八年が経ち、スミレは大人になった。
しかし、どれだけ時が経とうとも、ソフィリアはあの出来事を決して忘れることなどできない。
あれから、彼女の人生は大きく変わった。
父ガトール・ディ・ロートリアス公爵は娘の行いを恥じ、皇妃候補の一番上に掲げられていたその名前を削除させた。
ソフィリアに半ば約束されていた、皇妃となり、次期皇帝の母となる道は断たれたのだ。
そんな娘に対する母の失望は凄まじかった。
――皇妃にも国母にもなれないソフィリアには何の価値もない
そう、はっきりと母の口から聞かされ時、ソフィリアはひどく悲しかったのを覚えている。
「ところで、スミレ。あれは?」
当時の胸の痛みを思い出したソフィリアは、それをぐっと堪えて笑みで誤魔化した。
話題を変えようと、窓辺のテーブルに置かれたガラス容器――そこでぷかぷかしている黄緑色の若葉を指差して問う。
それをちらりと見やったスミレは、ソフィリアのベッドに腰を下ろしながら口を開いた。
「セバスチャンからソフィへ、誕生日プレゼントだって」
「セバスチャンから……?」
セバスチャンとは、レイスウェイク大公爵家の執事である。
といっても、ただの執事ではない。
なんと人間ではなく、ポトスと呼ばれる蔦植物なのだ。
さらに言うと、ただの蔦植物でもない。
黄緑色の葉と蔓を自由自在に動かせるばかりか、ペンを掴んで字を書くことで人間と意思の疎通までできる、摩訶不思議な植物なのである。
そんな蔦執事セバスチャンの眷属こそが、かつてスミレを勾引したソフィリアの馬車を足止めし、犯人達をヴィオラントの前に突き出した功労者だった。
「何日か前に、ユーリがカーティス兄さまのお供でうちに来たのよね。その時、セバス相手に相談してたんだ」
「ユリウスが、ですか?」
さらに、ユリウスとはソフィリアの二つ下の弟で、騎士団第一隊に属する騎士である。
母から極限まで甘やかされて育ったことにより甚だ問題があった彼の性格も、剣術の才能を認められて騎士団に入ると、先輩騎士達にみっちりと扱かれて矯正された。
おかげで今では人間的にも随分と成長し、スミレの名目上の兄に当たる第一隊の隊長カーティスの信頼も厚く、後輩にも慕われる立派な青年になっている。
そんな弟がレイスウェイク大公爵家の蔦執事相手にいったい何を相談したのか。
大体の予想ができたソフィリアは、いやだわ、とため息をついた。
「ユリウスったら、どうせ行き遅れの姉を何とかできないか、とかそんなことを言ったのでしょう?」
「もうちょっと、可愛い言い方をしてたよー。姉上が結婚する気になるよう仕向けるにはどうしたらいいか、とか」
「言いたいことは一緒でしょう。もう……勝手なことばかり言って」
「ユーリだってまだ独身なのにねー」
眉をきゅっと顰めて不満げな顔をするソフィリアに、スミレがくすくすと笑う。
ソフィリアは今日、二十六歳の誕生日を迎えた。
貴族の娘としては、確かにもう行き遅れと言われる年齢かもしれない。
しかし、妻として母として生きることとは別の生き甲斐を見つけたソフィリアは、現在のところ結婚するつもりも相手もなかった。
同じく騎士として脂が乗ってきたユリウスも、剣術の腕を磨くことや後輩の育成に心血を注いでおり、結婚など考えてもいない様子。
どうやら彼は、姉のソフィリアに縁談話が持ち上がれば、ロートリアス公爵家の跡継ぎとして早く身を固めろとうるさい母の気を一時でも逸らせると考えたらしい。
しかし、ユリウスは知らないのだろうか。
(お母様は、とっくに私のことなんて見限ってしまっているというのに……)
ソフィリアは、八年前の事件以来自分に向けられることのなくなった母の顔を思い出し、心の中で自嘲した。
「それで、なぜ若葉を?」
とはいえ、ユリウスから姉の縁談の相談をされたレイスウェイク家の蔦執事は、何を思って自身の一部を与えたのか。
ひやりと冷たいガラス容器を手に取りながら、ソフィリアは首を傾げる。
スミレはそんな彼女を眺めながら、にこにこして言った。
「まずはソフィに子育てをさせて、母性本能をくすぐろうって作戦なんじゃない?」
「子育てって……植物を育てるだけで、人間の母性本能ってくすぐられるものかしら?」
「だって、セバスチャンの子達はただの植物じゃないからね。水や肥料をあげてお日様に当てておくだけじゃだめだもの。時々かまってあげないと拗ねちゃうし、愛情不足になると最悪枯れちゃうかもしれないから、ソフィ、よろしくね」
「あらあら、それは責任重大ね」
スミレの言葉に同調するように、水面に浮かんだ若葉がふにふにと蠢いた。
まるで、よろしく、と挨拶しているようで可愛らしい。
ついでに、ベッドにちょこんと座ってにこにこしているスミレも可愛らしくて、ソフィリアはそんな可愛いもの達を交互に見比べてから、じゃあ、と続けた。
「スミレが、この子に名前を付けてあげてくれませんか?」
「えー、私? いやいや、ソフィんちの子になるんだから、ソフィが付けなよ」
「恥ずかしながら、気の利いた名前を思い付ける自信がありません」
「もー、仕方ないなぁ。ええっと……このちびっ子の名前……なまえねぇ……」
なんだかんだと言いながらも結局のところ面倒見のいいスミレは、胸の前で両腕を組んでうーんと唸り始める。
それを眺めるのさえ、ソフィリアにとっては至福の時間。
「ちび、はクロちゃんちの子に使っちゃったし、子セバスってのも何だか味気ないなぁ。他に小さい感じを表す言葉って、ないかな……」
クロちゃんとは、この国の現在の宰相であり皇帝の腹違いの兄にして、四公爵家の一つリュネブルク公爵家の現当主クロヴィス・オル・リュネブルクのことだ。
母后陛下の侍女と結婚してからは随分と丸くなったが、かつては〝泣く子も黙る鬼宰相〟と恐れられた彼を愛称で呼ぶのは、いまだにスミレただ一人。
そんなクロヴィスの執務室にも、かつてセバスチャンから分けられた若葉が根付いており、壁中に蔓を這わせて当たり前のように宰相の仕事を手伝っている。
それに、ちびセバスと名付けたのはスミレだという。
命名感覚の良し悪しはともかくとして、彼女の付けた名前には力が宿る、と感じるのはソフィリアの主観ばかりではあるまい。
「ミニセバス……ちんまいセバス……プチセバス……」
「あっ、それ。今のがいいです」
「え? どれ? どれのこと?」
「最後の〝プチセバス〟がいいんじゃないかしら。〝プチ〟って、響きが可愛らしいですもの」
ついでに言うと、プチ、と発音した時の、唇を尖らせたスミレの顔がとびきり可愛らしかったから、というのも理由である。
いまだ彼女に永遠の妹ドール・クリスティーナを重ねて、ソフィリアの頬が緩んでしまうのはご愛嬌。
そうとは知らないスミレは心得たとばかりに頷くと、ガラス容器の中でぷかぷかしている若葉にびしりと人差し指を突き付けて言った。
「よっく聞いて、プチセバス。君のご主人様はソフィだからね。立派に育って、ソフィにいっぱい幸せを運んでくるんだよ?」
「あらあら、この子も責任重大ね」
かくしてプチセバスと名付けられた若葉は、スミレの言葉にうんうんと頷くみたいに小さな緑を上下させた。
11
あなたにおすすめの小説

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。
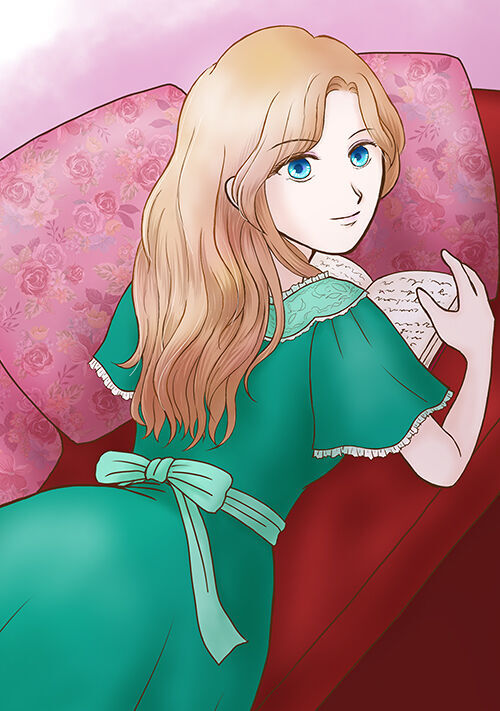
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

残念な顔だとバカにされていた私が隣国の王子様に見初められました
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
公爵令嬢アンジェリカは六歳の誕生日までは天使のように可愛らしい子供だった。ところが突然、ロバのような顔になってしまう。残念な姿に成長した『残念姫』と呼ばれるアンジェリカ。友達は男爵家のウォルターただ一人。そんなある日、隣国から素敵な王子様が留学してきて……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















