1 / 10
第1話:『人生どん詰まり、神様拾いました』
しおりを挟む
東京の西陽は、人を馬鹿にするみたいに綺麗だった。
福永こがね、二十八歳。
彼女の六畳一間のアパートの、壁紙のシミさえもアートのように照らし出すオレンジ色の光の中で、その現実感のない美しさが、かえって胸を抉った。
手の中のスマートフォンには、青いトーク画面が開かれている。
『ごめん。他に好きな人ができた』
たった一行。
そこに、二年という月日の重さは微塵も感じられなかった。
そのメッセージを打ち込む彼の指も、表情も、声も、もうこがねには関係がない。
追い打ちをかけるように、机の上には昨日手渡されたばかりの茶封筒。
中身は解雇通知。
理由は、会社の業績不振。
「……ははっ」
乾いた笑いが漏れた。
なんだこれ。
まるで出来の悪いドラマだ。
仕事も、恋人も、住む場所さえも、もうすぐここにはなくなる。
東京で描いた夢なんて、最初から蜃気楼だったのかもしれない。
埃が光に照らされて、きらきらと舞っている。
それが、粉々になった自分の未来のように見えた。
荷物をまとめる気力も湧かず、こがねは吸い寄せられるように、スマートフォンの予約サイトを開いていた。
行き先は一つしかない。
あんなに「錦を飾るまで帰らない」と息巻いて飛び出した、あの田舎町へ。
◆◇◆
夜行バスの窓に映る自分の顔は、ひどい有様だった。
隈の浮き出た目元、生気のない肌。
隣の席の知らないおじさんの寝息を聞きながら、こがねはただぼんやりと外を流れる光の帯を眺めていた。
こんな形で帰りたくなかった。
せめて、もう少し、何か一つでも掴んだと胸を張れるものが欲しかった。
バスが、明け方の冷たい空気が漂うバスターミナルに滑り込む。
懐かしい、土と草いきれの匂い。
東京の排気ガスに慣れた肺が、その濃さに少し驚いている。
ここから実家の駄菓子屋までは、歩いて十分ほどだ。
「……ただいま」
誰に言うでもなく呟き、錆び付いたシャッターを苦労して押し上げる。
ぎぎぎ、と耳障りな音が静かな早朝の商店街に響いた。
途端に、埃と、甘いような、酸っぱいような、懐かしい匂いが鼻腔をくすぐった。
駄菓子屋「ふくや」。
それが、こがねの実家だった。
店内は、時間が止まったかのようだった。
壁には西日で色褪せたアイドルのポスター。
子供たちの背比べの跡が残る柱。
止まったままの振り子時計。
うまい棒、よっちゃんイカ、あんず飴。
かつては宝石のように見えたそれらは、今はうっすらと埃を被り、寂しそうにこがねを迎えていた。
両親が相次いで亡くなってから、もう五年。
店は誰も継ぐことなく、こうして放置されていた。
思い出が、埃と共に胸に積もる。
涙が出そうになるのを、こがねは奥歯を噛んでこらえた。
泣いている場合じゃない。
今日からここが、私の城であり、砦なのだ。
腕まくりをし、まずは換気だと窓を開ける。
新鮮な空気が流れ込み、埃っぽい店内の空気が少しだけ動いた。
掃除だ。
感傷に浸るのは、全部終わってからでいい。
半日かけて、店の床を磨き、商品を整理し、どうにか人が入れるくらいの状態にはなった。
問題は、店の奥にある居住スペースだ。
そして、そのさらに奥。
子供の頃、祖母から「あそこには大事な神様がいるから、絶対に開けちゃだめだよ」と固く言われていた「奥の間」があった。
好奇心はあったが、祖母の真剣な顔を思い出すと、これまで一度も足を踏み入れたことはなかった。
だが、今日は違う。
ここも掃除しなければ。
「……お邪魔します」
襖を開けると、そこは他の部屋よりもさらに濃い、古木の匂いと黴の匂いがした。
窓はなく、薄暗い。
部屋の中央に、ぽつんと小さな祠が鎮座していた。
高さは一メートルほどだろうか。
黒ずんだ木製の祠には、古びて変色した注連縄が何重にも巻かれている。
「神様、ねぇ……」
いるなら、私のこの惨状をどうにかしてほしいものだ。
こんなボロボロの祠に閉じ込められて、ご利益なんて期待できるわけもない。
むしろ、こんな粗末な場所に押し込めていて、罰当たりだったかもしれない。
「ごめんなさいね、綺麗にしてあげるから」
こがねは独り言を呟きながら、祠に巻かれた注連縄に手をかけた。
硬く、乾いている。
力を込めると、ぷつり、ぷつりと音を立てて、それはあっけなく千切れた。
そして、まるで何かに導かれるように、祠の小さな観音開きの扉に指をかける。
ぎぃ、と軋む音と共に扉を開けた、その瞬間だった。
ごぉっ、と冷たい風が祠の奥から吹き出し、こがねの髪を乱した。
古木の匂いに混じって、嗅いだことのない、清冽な香りが立つ。
「うわっ、けほっ、けほっ!」
煙か、あるいは濃い霧か。
白い何かが溢れ出し、視界を奪う。
思わず腕で顔を覆い、咳き込んでいると、不意に、すぐ目の前から声がした。
「……ああ、よく寝た」
それは、驚くほど低く、穏やかで、そしてひどく気怠げな、男の声だった。
煙がゆっくりと晴れていく。
こがねはおそるおそる顔を上げた。
そこに、男が立っていた。
色素の薄い、銀灰色にも見える髪。
陽光を弾くのではなく、溶かしてしまいそうな、儚い色合い。
伏せられた睫毛は人形のように長く、その下の瞳は、まだ覚醒しきっていないのか、ぼんやりと宙を彷徨っている。
すっと通った鼻筋、薄い唇。
人間離れした、と形容するのが最も近い、完璧な造形美。
こがねは、息を呑んだ。
神様。
祖母の言っていたことは、本当だったんだ。
こんな、こんな美しい人が……。
見惚れたのは、ほんの一瞬。
次の瞬間、こがねの期待と感動は、木っ端微塵に砕け散った。
その神様(仮)が着ていたのは、首元がヨレヨレに伸びきった、灰色のジャージ上下だったのである。
「……どちら様、ですか?」
こがねがようやく絞り出した声に、男はゆっくりと此方を見た。
夜の湖面のような、静かな瞳。
彼は小さくあくびを一つすると、面倒くさそうに口を開いた。
「我か? 我は、この地に祀られし神ぞ」
「か、神様……」
「うむ。名は、薄氷(うすらい)。しがない貧乏神だが」
……びんぼうがみ?
「え、えっと、聞き間違いですかね? 今、貧乏神って……」
「そう言うたが。何か問題でも?」
男──薄氷は、心底不思議そうに首を傾げた。
その仕草すら絵になるのが腹立たしい。
「問題しかないでしょう! なんで神様なのにジャージなの!? もっとこう、威厳とか! 白い狩衣とか着てないんですか!」
「威厳は腹の足しにならぬ。それに、こっちの方が楽だ」
けろりと言い放つ薄氷に、こがねは眩暈を覚えた。
その時、ちか、ちか、と天井の蛍光灯が気味悪く点滅を始めた。
「あれ? 蛍光灯、替えたばっかりなのに……」
こがねが呟いた、その時だった。
手の中のスマートフォンが、何の脈絡もなく、つるりと滑り落ちた。
パリンッ。
床に落ちたスマホの画面には、綺麗な蜘蛛の巣模様が広がっていた。
「あ…………」
言葉を失うこがねを尻目に、薄氷はふらふらと部屋を見渡し、柱に寄りかかってずるずると座り込んだ。
「あー……腹が減った。何か食うものはないか、依り代よ」
「よりしろ……?」
「そなたが祠を開けたのだろう。我は依り代なしでは顕現できぬ。故に、今やそなたが我の新しい依り代だ」
「は……?」
意味が分からない。
混乱するこがねの耳元で、薄氷はさらに残酷な事実を告げた。
「そういうわけで、しばらくはそなたから離れられぬ。よろしく頼む」
「いやいやいや! よろしくされても困ります! 出てってください!」
「無理だと言うておる」
むにゃむにゃと、早くも二度寝に入りそうな薄氷。
その時、こがねはふと、自分のハンドバッグがやけに軽く感じていることに気づいた。
まさか、と思って中を改める。
ない。
さっきコンビニで下ろしたばかりの一万円札が、綺麗さっぱり消えている。
「ああああああああああ!」
こがねの絶叫が、埃っぽい駄菓子屋に木霊した。
人生どん底。
仕事なし、恋人なし、貯金なし。
そして今日、神様(ただし貧乏神)つき物件になりました。
福永こがね、二十八歳。
彼女の明日は、果たしてどっちだ。
福永こがね、二十八歳。
彼女の六畳一間のアパートの、壁紙のシミさえもアートのように照らし出すオレンジ色の光の中で、その現実感のない美しさが、かえって胸を抉った。
手の中のスマートフォンには、青いトーク画面が開かれている。
『ごめん。他に好きな人ができた』
たった一行。
そこに、二年という月日の重さは微塵も感じられなかった。
そのメッセージを打ち込む彼の指も、表情も、声も、もうこがねには関係がない。
追い打ちをかけるように、机の上には昨日手渡されたばかりの茶封筒。
中身は解雇通知。
理由は、会社の業績不振。
「……ははっ」
乾いた笑いが漏れた。
なんだこれ。
まるで出来の悪いドラマだ。
仕事も、恋人も、住む場所さえも、もうすぐここにはなくなる。
東京で描いた夢なんて、最初から蜃気楼だったのかもしれない。
埃が光に照らされて、きらきらと舞っている。
それが、粉々になった自分の未来のように見えた。
荷物をまとめる気力も湧かず、こがねは吸い寄せられるように、スマートフォンの予約サイトを開いていた。
行き先は一つしかない。
あんなに「錦を飾るまで帰らない」と息巻いて飛び出した、あの田舎町へ。
◆◇◆
夜行バスの窓に映る自分の顔は、ひどい有様だった。
隈の浮き出た目元、生気のない肌。
隣の席の知らないおじさんの寝息を聞きながら、こがねはただぼんやりと外を流れる光の帯を眺めていた。
こんな形で帰りたくなかった。
せめて、もう少し、何か一つでも掴んだと胸を張れるものが欲しかった。
バスが、明け方の冷たい空気が漂うバスターミナルに滑り込む。
懐かしい、土と草いきれの匂い。
東京の排気ガスに慣れた肺が、その濃さに少し驚いている。
ここから実家の駄菓子屋までは、歩いて十分ほどだ。
「……ただいま」
誰に言うでもなく呟き、錆び付いたシャッターを苦労して押し上げる。
ぎぎぎ、と耳障りな音が静かな早朝の商店街に響いた。
途端に、埃と、甘いような、酸っぱいような、懐かしい匂いが鼻腔をくすぐった。
駄菓子屋「ふくや」。
それが、こがねの実家だった。
店内は、時間が止まったかのようだった。
壁には西日で色褪せたアイドルのポスター。
子供たちの背比べの跡が残る柱。
止まったままの振り子時計。
うまい棒、よっちゃんイカ、あんず飴。
かつては宝石のように見えたそれらは、今はうっすらと埃を被り、寂しそうにこがねを迎えていた。
両親が相次いで亡くなってから、もう五年。
店は誰も継ぐことなく、こうして放置されていた。
思い出が、埃と共に胸に積もる。
涙が出そうになるのを、こがねは奥歯を噛んでこらえた。
泣いている場合じゃない。
今日からここが、私の城であり、砦なのだ。
腕まくりをし、まずは換気だと窓を開ける。
新鮮な空気が流れ込み、埃っぽい店内の空気が少しだけ動いた。
掃除だ。
感傷に浸るのは、全部終わってからでいい。
半日かけて、店の床を磨き、商品を整理し、どうにか人が入れるくらいの状態にはなった。
問題は、店の奥にある居住スペースだ。
そして、そのさらに奥。
子供の頃、祖母から「あそこには大事な神様がいるから、絶対に開けちゃだめだよ」と固く言われていた「奥の間」があった。
好奇心はあったが、祖母の真剣な顔を思い出すと、これまで一度も足を踏み入れたことはなかった。
だが、今日は違う。
ここも掃除しなければ。
「……お邪魔します」
襖を開けると、そこは他の部屋よりもさらに濃い、古木の匂いと黴の匂いがした。
窓はなく、薄暗い。
部屋の中央に、ぽつんと小さな祠が鎮座していた。
高さは一メートルほどだろうか。
黒ずんだ木製の祠には、古びて変色した注連縄が何重にも巻かれている。
「神様、ねぇ……」
いるなら、私のこの惨状をどうにかしてほしいものだ。
こんなボロボロの祠に閉じ込められて、ご利益なんて期待できるわけもない。
むしろ、こんな粗末な場所に押し込めていて、罰当たりだったかもしれない。
「ごめんなさいね、綺麗にしてあげるから」
こがねは独り言を呟きながら、祠に巻かれた注連縄に手をかけた。
硬く、乾いている。
力を込めると、ぷつり、ぷつりと音を立てて、それはあっけなく千切れた。
そして、まるで何かに導かれるように、祠の小さな観音開きの扉に指をかける。
ぎぃ、と軋む音と共に扉を開けた、その瞬間だった。
ごぉっ、と冷たい風が祠の奥から吹き出し、こがねの髪を乱した。
古木の匂いに混じって、嗅いだことのない、清冽な香りが立つ。
「うわっ、けほっ、けほっ!」
煙か、あるいは濃い霧か。
白い何かが溢れ出し、視界を奪う。
思わず腕で顔を覆い、咳き込んでいると、不意に、すぐ目の前から声がした。
「……ああ、よく寝た」
それは、驚くほど低く、穏やかで、そしてひどく気怠げな、男の声だった。
煙がゆっくりと晴れていく。
こがねはおそるおそる顔を上げた。
そこに、男が立っていた。
色素の薄い、銀灰色にも見える髪。
陽光を弾くのではなく、溶かしてしまいそうな、儚い色合い。
伏せられた睫毛は人形のように長く、その下の瞳は、まだ覚醒しきっていないのか、ぼんやりと宙を彷徨っている。
すっと通った鼻筋、薄い唇。
人間離れした、と形容するのが最も近い、完璧な造形美。
こがねは、息を呑んだ。
神様。
祖母の言っていたことは、本当だったんだ。
こんな、こんな美しい人が……。
見惚れたのは、ほんの一瞬。
次の瞬間、こがねの期待と感動は、木っ端微塵に砕け散った。
その神様(仮)が着ていたのは、首元がヨレヨレに伸びきった、灰色のジャージ上下だったのである。
「……どちら様、ですか?」
こがねがようやく絞り出した声に、男はゆっくりと此方を見た。
夜の湖面のような、静かな瞳。
彼は小さくあくびを一つすると、面倒くさそうに口を開いた。
「我か? 我は、この地に祀られし神ぞ」
「か、神様……」
「うむ。名は、薄氷(うすらい)。しがない貧乏神だが」
……びんぼうがみ?
「え、えっと、聞き間違いですかね? 今、貧乏神って……」
「そう言うたが。何か問題でも?」
男──薄氷は、心底不思議そうに首を傾げた。
その仕草すら絵になるのが腹立たしい。
「問題しかないでしょう! なんで神様なのにジャージなの!? もっとこう、威厳とか! 白い狩衣とか着てないんですか!」
「威厳は腹の足しにならぬ。それに、こっちの方が楽だ」
けろりと言い放つ薄氷に、こがねは眩暈を覚えた。
その時、ちか、ちか、と天井の蛍光灯が気味悪く点滅を始めた。
「あれ? 蛍光灯、替えたばっかりなのに……」
こがねが呟いた、その時だった。
手の中のスマートフォンが、何の脈絡もなく、つるりと滑り落ちた。
パリンッ。
床に落ちたスマホの画面には、綺麗な蜘蛛の巣模様が広がっていた。
「あ…………」
言葉を失うこがねを尻目に、薄氷はふらふらと部屋を見渡し、柱に寄りかかってずるずると座り込んだ。
「あー……腹が減った。何か食うものはないか、依り代よ」
「よりしろ……?」
「そなたが祠を開けたのだろう。我は依り代なしでは顕現できぬ。故に、今やそなたが我の新しい依り代だ」
「は……?」
意味が分からない。
混乱するこがねの耳元で、薄氷はさらに残酷な事実を告げた。
「そういうわけで、しばらくはそなたから離れられぬ。よろしく頼む」
「いやいやいや! よろしくされても困ります! 出てってください!」
「無理だと言うておる」
むにゃむにゃと、早くも二度寝に入りそうな薄氷。
その時、こがねはふと、自分のハンドバッグがやけに軽く感じていることに気づいた。
まさか、と思って中を改める。
ない。
さっきコンビニで下ろしたばかりの一万円札が、綺麗さっぱり消えている。
「ああああああああああ!」
こがねの絶叫が、埃っぽい駄菓子屋に木霊した。
人生どん底。
仕事なし、恋人なし、貯金なし。
そして今日、神様(ただし貧乏神)つき物件になりました。
福永こがね、二十八歳。
彼女の明日は、果たしてどっちだ。
0
あなたにおすすめの小説

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月
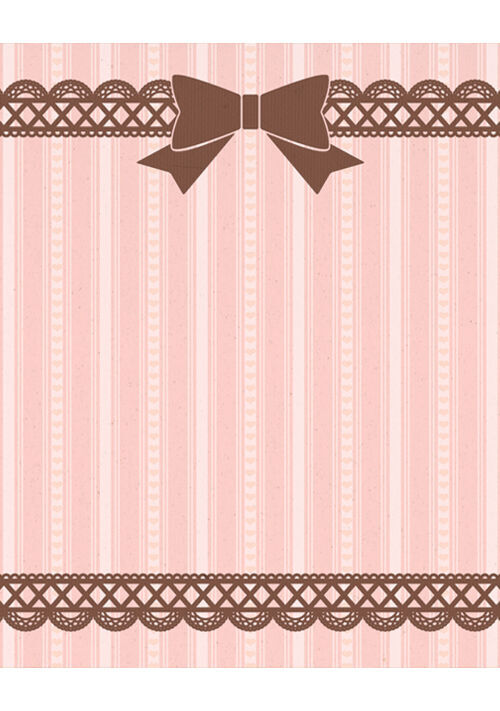
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

花嫁御寮 ―江戸の妻たちの陰影― :【第11回歴史・時代小説大賞 奨励賞】
naomikoryo
歴史・時代
名家に嫁いだ若き妻が、夫の失踪をきっかけに、江戸の奥向きに潜む権力、謀略、女たちの思惑に巻き込まれてゆく――。
舞台は江戸中期。表には見えぬ女の戦(いくさ)が、美しく、そして静かに燃え広がる。
結城澪は、武家の「御寮人様」として嫁いだ先で、愛と誇りのはざまで揺れることになる。
失踪した夫・宗真が追っていたのは、幕府中枢を揺るがす不正金の記録。
やがて、志を同じくする同心・坂東伊織、かつて宗真の婚約者だった篠原志乃らとの交錯の中で、澪は“妻”から“女”へと目覚めてゆく。
男たちの義、女たちの誇り、名家のしがらみの中で、澪が最後に選んだのは――“名を捨てて生きること”。
これは、名もなき光の中で、真実を守り抜いたひと組の夫婦の物語。
静謐な筆致で描く、江戸奥向きの愛と覚悟の長編時代小説。
全20話、読み終えた先に見えるのは、声高でない確かな「生」の姿。

【完結】偽りの華は後宮に咲く〜義賊の娘は冷徹義兄と食えない暗愚皇帝に振り回される〜
降魔 鬼灯
キャラ文芸
義賊である養父を助けるため大貴族の屋敷に忍び込んだ燕燕は若き当主王蒼月に捕まる。
危うく殺されかけた燕燕だが、その顔が逃げた妹、王珠蘭に似ていることに気付いた蒼月により取引を持ちかけられる。
逃げた妹の代わりに顔だけは綺麗な暗君である皇帝の妃を決める選秀女試験に出て不合格になれば父の解放を約束するという密約を交わした。
記憶力抜群、運動神経抜群、音楽的才能壊滅の主人公が父のために無難な成績での選秀女試験不合格を勝ち取れるのか。
実は食えない性格の皇帝と冷徹だがマメな義兄蒼月に振り回され溺愛される燕燕は無事2人から解放されるのか。
後宮コメディストーリー
完結済

後宮の幻華 -死にかけ皇帝と胡乱な数日間ー
丹羽 史京賀
キャラ文芸
瞬 青波は大昔に滅んだ王族の末裔で、特殊な術を受け継いでいた。
その術を使い、幼馴染みで今は皇帝となった春霞の様子を見守っていたが、突然、彼に対して術が使えなくなってしまう。
春霞が心配で、後宮で働き始める青波。
皇帝が死にかけているという話を聞くが、相変わらず術は使えないまま……。
焦る青波の前に現れたのは、幽体となった春霞だった!?
こじらせ皇帝×ツンデレ術師=恋愛コメディ

椿の国の後宮のはなし
犬噛 クロ
キャラ文芸
架空の国の後宮物語。
若き皇帝と、彼に囚われた娘の話です。
有力政治家の娘・羽村 雪樹(はねむら せつじゅ)は「男子」だと性別を間違われたまま、自国の皇帝・蓮と固い絆で結ばれていた。
しかしとうとう少女であることを気づかれてしまった雪樹は、蓮に乱暴された挙句、後宮に幽閉されてしまう。
幼なじみとして慕っていた青年からの裏切りに、雪樹は混乱し、蓮に憎しみを抱き、そして……?
あまり暗くなり過ぎない後宮物語。
雪樹と蓮、ふたりの関係がどう変化していくのか見守っていただければ嬉しいです。
※2017年完結作品をタイトルとカテゴリを変更+全面改稿しております。

『後宮祓いの巫女は、鬼将軍に嫁ぐことになりました』
由香
キャラ文芸
後宮で怪異を祓う下級巫女・紗月は、ある日突然、「鬼」と噂される将軍・玄耀の妻になれと命じられる。
それは愛のない政略結婚――
人ならざる力を持つ将軍を、巫女の力で制御するための契約だった。
後宮の思惑に翻弄されながらも、二人は「契約」ではなく「選んだ縁」として、共に生きる道を選ぶ――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















