8 / 13
第7話:学びへの渇望
しおりを挟む
第7話:学びへの渇望
病棟の図書室は、古い紙の匂いと、微かな日向の匂いが混ざり合っていた。
両親との面会から数週間。新菜は、瀬戸から「もし気が向いたら、これを整理するのを手伝ってくれないか」と頼まれた数冊の専門書を抱えていた。
「心理学……社会福祉概論……」
表紙の文字をなぞる。かつて、新菜にとって「介護」や「福祉」という言葉は、自分を縛り付け、自由を奪い、指先をあかぎれだらけにする呪文でしかなかった。
けれど、図書室の机に広げた本の中に記されていたのは、彼女が知っている泥臭い苦役とは違う、整然とした「知恵」だった。
「どうかな、にいなさん。少しは面白そうなことが書いてある?」
いつの間にか後ろに立っていた瀬戸が、缶コーヒーを二つ、机に置いた。パキッという小気味いい音とともに、香ばしい苦い香りが鼻をくすぐる。
「……不思議なんです。ここに書いてある『セルフケア』とか『境界線』っていう言葉……。私、あんなに毎日おばあちゃんの世話をしてきたのに、こんな言葉、ひとつも知りませんでした」
新菜は、本の一節を指でなぞった。
「私、……介護って、ただ我慢することだと思ってた。自分がぼろ雑巾になればなるほど、それが『正解』なんだって。でも、この本には『支援者が倒れては意味がない』って書いてある。自分を大切にすることが、最初の仕事なんだって。……そんなの、誰も教えてくれなかった」
新菜の声が、少しだけ震えた。
九年間、彼女がやってきたのは「介護」ではなく、ただの「自己犠牲」だった。それを学問として、客観的な技術として見つめ直したとき、視界を覆っていた霧が晴れていくような感覚を覚えた。
「にいなさん。君はもう、現場を知っている。誰よりも深く、痛みを知っている。それは、どんな教科書を読み耽るよりも得難い、君だけの『土台』なんだよ」
「私だけの……土台……」
「そう。君には才能がある。瀬戸際で踏みとどまり、命と向き合ってきた才能だ。それを『搾取』の道具にさせるのは、社会の損失だと僕は思う」
瀬戸は、真剣な眼差しで新菜を見つめた。
新菜は、思わず息を呑んだ。才能。そんな言葉、自分には一生縁がないと思っていた。ただ言われたことを、叱られないようにこなすだけの、空っぽな自分だと思っていた。
「瀬戸さん……私、もっと知りたいです。どうして人は、あんなに優しかったおばあちゃんが、あんな風に変わってしまうのか。どうして私の両親は、あんな風にしか人を愛せないのか。それを知るための力が、欲しい」
新菜は、拳をぎゅっと握りしめた。
掌に残る、あかぎれの痕。それは、かつては奴隷の印のように見えたけれど、今は「戦ってきた証」のように思えた。
「……でも、私。高校も休みがちだったし、もう十八歳だし……。こんなボロボロな私でも、大学にいっていいのかな。勉強なんて、してもいいのかな」
不安が、冷たい水のように胸に広がる。
母の「あんたには地味な仕事が向いてるのよ」という呪いの声が、耳の奥で微かに再生される。
「もちろんだ」
瀬戸は、迷いなく力強く頷いた。
「年齢なんて関係ない。ましてや、君には君の人生を守る権利がある。おばあ様が遺してくれたあの手帳、覚えているかい?」
新菜は、病室の引き出しに大切にしまってある、あの古びた手帳を思い出した。
『自分のために生きなさい』
あの言葉は、単なる励ましではなかった。未来への入場券だったのだ。
「あのお金は、君の血と汗の結晶だ。誰に遠慮する必要がある? 君の人生を豊かにするために、君自身が使い道を決めればいい。……にいなさん。君が大学に行って、いつか僕の同業者や、介護のスペシャリストになったら。それは、君を支配しようとした人たちに対する、最高の『勝利』になると思わないかい?」
勝利。
その言葉が、新菜の心に鮮やかな火を灯した。
やり返すことでも、論破することでもない。
自分自身が幸せになり、プロとして自立し、誰の助けも借りずに胸を張って生きること。それが、毒親から最も遠い場所へ行く方法なのだ。
「……私、行きたいです。大学。福祉の大学に行って、ちゃんと勉強して、資格を取って……。今度は自分の意志で、誰かの支えになりたい」
新菜の瞳に、九年間失われていた「希望」という名の光が、はっきりと宿った。
窓の外から差し込む光が、机の上に広げた本の白いページを、眩しいほどに照らしている。
「いい顔だ。よし、まずは願書を取り寄せるところから始めようか」
瀬戸の言葉に、新菜は初めて、心の底から「はい!」と返事をした。
あんなに重かった専門書の重みが、今は、自分の未来を支える確かな手応えに変わっていた。
祖母が遺したお金で、教科書を買おう。
新しいペンを買おう。
そして、まだ見ぬ自分の人生を買おう。
新菜は、深く、深く息を吸い込んだ。
肺に満ちた空気は、もう病院の匂いではなく、新しい春の予感を含んだ、自由の匂いがした。
病棟の図書室は、古い紙の匂いと、微かな日向の匂いが混ざり合っていた。
両親との面会から数週間。新菜は、瀬戸から「もし気が向いたら、これを整理するのを手伝ってくれないか」と頼まれた数冊の専門書を抱えていた。
「心理学……社会福祉概論……」
表紙の文字をなぞる。かつて、新菜にとって「介護」や「福祉」という言葉は、自分を縛り付け、自由を奪い、指先をあかぎれだらけにする呪文でしかなかった。
けれど、図書室の机に広げた本の中に記されていたのは、彼女が知っている泥臭い苦役とは違う、整然とした「知恵」だった。
「どうかな、にいなさん。少しは面白そうなことが書いてある?」
いつの間にか後ろに立っていた瀬戸が、缶コーヒーを二つ、机に置いた。パキッという小気味いい音とともに、香ばしい苦い香りが鼻をくすぐる。
「……不思議なんです。ここに書いてある『セルフケア』とか『境界線』っていう言葉……。私、あんなに毎日おばあちゃんの世話をしてきたのに、こんな言葉、ひとつも知りませんでした」
新菜は、本の一節を指でなぞった。
「私、……介護って、ただ我慢することだと思ってた。自分がぼろ雑巾になればなるほど、それが『正解』なんだって。でも、この本には『支援者が倒れては意味がない』って書いてある。自分を大切にすることが、最初の仕事なんだって。……そんなの、誰も教えてくれなかった」
新菜の声が、少しだけ震えた。
九年間、彼女がやってきたのは「介護」ではなく、ただの「自己犠牲」だった。それを学問として、客観的な技術として見つめ直したとき、視界を覆っていた霧が晴れていくような感覚を覚えた。
「にいなさん。君はもう、現場を知っている。誰よりも深く、痛みを知っている。それは、どんな教科書を読み耽るよりも得難い、君だけの『土台』なんだよ」
「私だけの……土台……」
「そう。君には才能がある。瀬戸際で踏みとどまり、命と向き合ってきた才能だ。それを『搾取』の道具にさせるのは、社会の損失だと僕は思う」
瀬戸は、真剣な眼差しで新菜を見つめた。
新菜は、思わず息を呑んだ。才能。そんな言葉、自分には一生縁がないと思っていた。ただ言われたことを、叱られないようにこなすだけの、空っぽな自分だと思っていた。
「瀬戸さん……私、もっと知りたいです。どうして人は、あんなに優しかったおばあちゃんが、あんな風に変わってしまうのか。どうして私の両親は、あんな風にしか人を愛せないのか。それを知るための力が、欲しい」
新菜は、拳をぎゅっと握りしめた。
掌に残る、あかぎれの痕。それは、かつては奴隷の印のように見えたけれど、今は「戦ってきた証」のように思えた。
「……でも、私。高校も休みがちだったし、もう十八歳だし……。こんなボロボロな私でも、大学にいっていいのかな。勉強なんて、してもいいのかな」
不安が、冷たい水のように胸に広がる。
母の「あんたには地味な仕事が向いてるのよ」という呪いの声が、耳の奥で微かに再生される。
「もちろんだ」
瀬戸は、迷いなく力強く頷いた。
「年齢なんて関係ない。ましてや、君には君の人生を守る権利がある。おばあ様が遺してくれたあの手帳、覚えているかい?」
新菜は、病室の引き出しに大切にしまってある、あの古びた手帳を思い出した。
『自分のために生きなさい』
あの言葉は、単なる励ましではなかった。未来への入場券だったのだ。
「あのお金は、君の血と汗の結晶だ。誰に遠慮する必要がある? 君の人生を豊かにするために、君自身が使い道を決めればいい。……にいなさん。君が大学に行って、いつか僕の同業者や、介護のスペシャリストになったら。それは、君を支配しようとした人たちに対する、最高の『勝利』になると思わないかい?」
勝利。
その言葉が、新菜の心に鮮やかな火を灯した。
やり返すことでも、論破することでもない。
自分自身が幸せになり、プロとして自立し、誰の助けも借りずに胸を張って生きること。それが、毒親から最も遠い場所へ行く方法なのだ。
「……私、行きたいです。大学。福祉の大学に行って、ちゃんと勉強して、資格を取って……。今度は自分の意志で、誰かの支えになりたい」
新菜の瞳に、九年間失われていた「希望」という名の光が、はっきりと宿った。
窓の外から差し込む光が、机の上に広げた本の白いページを、眩しいほどに照らしている。
「いい顔だ。よし、まずは願書を取り寄せるところから始めようか」
瀬戸の言葉に、新菜は初めて、心の底から「はい!」と返事をした。
あんなに重かった専門書の重みが、今は、自分の未来を支える確かな手応えに変わっていた。
祖母が遺したお金で、教科書を買おう。
新しいペンを買おう。
そして、まだ見ぬ自分の人生を買おう。
新菜は、深く、深く息を吸い込んだ。
肺に満ちた空気は、もう病院の匂いではなく、新しい春の予感を含んだ、自由の匂いがした。
0
あなたにおすすめの小説

サレ妻の娘なので、母の敵にざまぁします
二階堂まりい
大衆娯楽
大衆娯楽部門最高記録1位!
※この物語はフィクションです
流行のサレ妻ものを眺めていて、私ならどうする? と思ったので、短編でしたためてみました。
当方未婚なので、妻目線ではなく娘目線で失礼します。

思い出さなければ良かったのに
田沢みん
恋愛
「お前の29歳の誕生日には絶対に帰って来るから」そう言い残して3年後、彼は私の誕生日に帰って来た。
大事なことを忘れたまま。
*本編完結済。不定期で番外編を更新中です。


私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

月の後宮~孤高の皇帝の寵姫~
真木
恋愛
新皇帝セルヴィウスが即位の日に閨に引きずり込んだのは、まだ十三歳の皇妹セシルだった。大好きだった兄皇帝の突然の行為に混乱し、心を閉ざすセシル。それから十年後、セシルの心が見えないまま、セルヴィウスはある決断をすることになるのだが……。

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました
蒼羽咲
ファンタジー
つまらなかった乙女ゲームに転生⁈
絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。
絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!
聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!
ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!
+++++
・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)
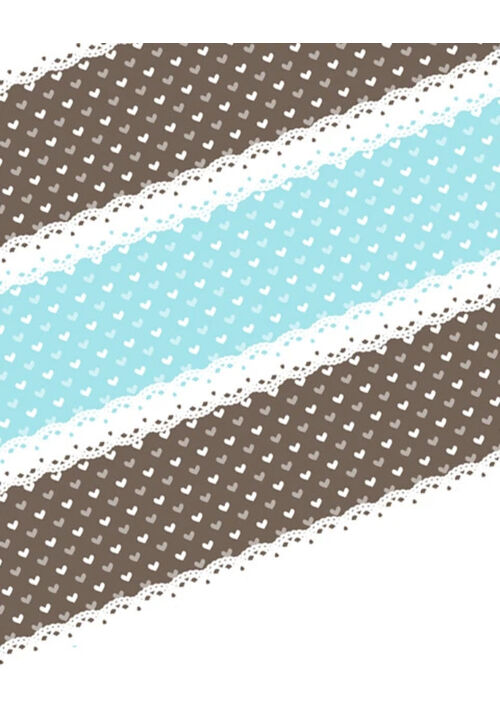
【完結】「私は善意に殺された」
まほりろ
恋愛
筆頭公爵家の娘である私が、母親は身分が低い王太子殿下の後ろ盾になるため、彼の婚約者になるのは自然な流れだった。
誰もが私が王太子妃になると信じて疑わなかった。
私も殿下と婚約してから一度も、彼との結婚を疑ったことはない。
だが殿下が病に倒れ、その治療のため異世界から聖女が召喚され二人が愛し合ったことで……全ての運命が狂い出す。
どなたにも悪意はなかった……私が不運な星の下に生まれた……ただそれだけ。
※無断転載を禁止します。
※朗読動画の無断配信も禁止します。
※他サイトにも投稿中。
※表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2022-九頭竜坂まほろん」
※小説家になろうにて2022年11月19日昼、日間異世界恋愛ランキング38位、総合59位まで上がった作品です!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















