2 / 7
隣のきみ。
しおりを挟む
翌日。田原はいつも通りに自らが通う豊明大学にいた。
白色を基調としたTシャツに、ジーパンという無難な服装で、肩から教科書類を入れたカバンを掛けている。
「よくやるよな、夜勤とか」
大理石風のタイルが張られた大学内の廊下。田原の隣を歩く天然なのか、理髪店でやってもらったのか分からない程のパーマがあたっている黒髪の男子生徒が言う。
「うっせぇ」
手短に答える田原は大きな欠伸をする。
「まぁ明日から夏休みだけどよ。普通テスト前に夜勤は入れないだろ」
牛乳瓶の底のようなレンズの厚い眼鏡をかけた男は、貧弱そうな体を揺らしながら歩く。
「森田くんこそ、勉強した?」
田原はその男子を森田、と呼び僅かに視線をくれる。
「当たり前だろ? 昨日はアニメ見るのも我慢して勉強したんだぜ?」
「ドヤ顔で言うのは自由だけど、それ普通に一夜漬けじゃん」
そう言う田原の手には、これからテストが行われる日本文化史の教科書が持たれている。
「いま暗記してる人には言われたくないかな」
至極当然の反論を聞こなかったふりでやり過ごし、田原と森田はテストが行われるA-32教室に入った。
「最後の方っすね」
教室に入るなり、声色が変わる森田。森田はかなりコミュニケーション能力が低いく、人が多くなる場所では普段より数段声色が硬くなり、何故だか語尾の方に「っす」が付く。
「時間ギリギリだしな」
教科書から顔を上げ、空いている席を探す。
「残念、二つ空いてるところないみたいだな」
二人で隣に座ってカンニングでもさせてもらおう、なんて考えが微塵もなかった訳では無い。田原はテストの点が1点でも上がる最終手段を失ったことを少し残念に思ったが、すぐに気持ちを切り替えた。
元々その手段に出るのは最終手段で、無くても困りはしない。
「嘘っすよね。離れないっすよね」
周りの誰にも聞こえないほどの、蚊の鳴くような声で森田は嘆いた。
「空いてないんだ、しょうがないだろ」
「誰かに頼んで……」
「いやいや、それこそ無理な話だろ」
森田はコミュニケーション能力が低い以前に人見知りなのだ。しかもかなりの人見知りで、知らない人が近くにいる状況はかなり緊張するらしい。
それが理由で、森田は電車を使えば直ぐ着くにも関わらず、わざわざ自転車を使って登校している。
「非人道的っすー」
「何言ってんだ、アホか」
先程までより少し声の大きさをあげた森田を短く罵倒し、田原は再度教科書に目を落とし、空いているまで歩いていく。
背後から何やら声が聞こえたが、無視して前から6番目の列──教室の中では真ん中より少し前──にあたる席に腰を下ろす。
──人なんて気にしなければいいのに。
椅子を引く、腰を下ろす、再度椅子を引く。田原の場合、その間に人と目が合うなんてことはない。特に今日は教科書に穴が空くのではと思われるほどに見つめているために、他人から見られているかなんてことに気づきもしない。
それからしばらくしてチャイムが鳴った。日本文化史を担当している50代半ばの女性が教壇に立ち、マイクを片手に「教科書や配布資料は閉まって」と声を上げた。
あちらこちらからため息が零れている。
「あぁ、詰みだわ」
「マジ無理ゲー」
などとこれから行われるであろうテストに対し、既に敗北宣言をしている生徒までいる始末だ。
「スマホ等携帯の電源は切って、カバンにしまって。それから机の上は筆記用具だけにするように」
その声すらも無視をして、女性は少し気だるげな声音で吐き捨てた。
「それじゃあ、テスト用紙を配っていく」
少し白髪混じりになった髪を肩くらいまで伸ばし、ヨレヨレになった灰色の服を着ているためにどこかみすぼらしさを感じさせる日本文化史の担当講師は、各列の先頭に適当に紙を渡していく。
「1人1部ずつとって後ろへ回して」
指示された通りに田原は1部を取り、振り返ることもせずに後ろへと流す。
頃合いを見てか、講師が始めの合図を出した。テスト用紙に視線を落とし問題を読んでいく。だが、テスト直前漬けで一夜漬けですらない田原にとってこれらの問題は難易度が高すぎた。
「夜勤、断っとけばよかった」
自分の大丈夫だろう、という浅はかな考えに嫌気がさし、小さな掠れた声で呟く。
あまりに小さな音のために、隣に座っている人ですらそれに気づいていない様子だ。田原は周りに視線をやることなく、集められる視線でそれを感じ取り、再び問題に意識を集める。
1問、2問。合ってるかどうか分からない答えを書いたところで、不意に田原の視界がブラックアウトする。
だがそれも一瞬。すぐに眼前には訳の分からない問題文で答えを導き出せ、という勉強をしていなければちんぷんかんぷんになってしまうテスト用紙がある。
数回頭を横に振ることで、どうにか吹っ飛んでしまいそうな意識を保ち、問題文を黙読する。
しかし、田原は理解できない問題文から誘われる睡魔に勝つことは出来ず、テスト開始からおよそ20分で意識を飛ばせてしまった。
これが中学や高校のテストならば、先生が回ってきて、肩をちょんちょんと指さされ起こされる。だが、大学になればその範囲ではない。
──寝てるやつは寝とけ。だが、単位はやらん。
そういうスタンスがほとんどだ。
だが、今日は違った。田原が眠りに落ちてから、数分が経ったところで田原は体に触れられる違和感を覚えた。
それは今まで起こされる時に触れられていた肩に感じるのではない。もっと下で、妙なこそばゆさを覚える。
その違和感を拭うことが出来ず、田原は薄っすらと目を開ける。
その違和感は脇腹から来ていることに田原は気づいた。ツン、ツン、とまるでいつぞやのおでんをつんつんしている人のように、隣に座っていた人は田原の脇腹をシャープペンシルでつついている。
「うっ」
目が覚めれば、ここからはこそばゆいという感覚しか襲ってこない。
「あ、あの」
森田と一緒にいることが多い田原は、人と話すのは得意ではない。森田程ではないが、普通の人よりは苦手であるのは間違いない。だからこそ、人があまり来ない上に時給がいい深夜のコンビニでバイトをしているのだ。
そんな田原だが、やはり何度も何度も脇腹をつんつんされるとこそばゆくて仕方がない。テスト中ということも鑑みて、田原は小声でそう声をかけた。
「起きたの?」
その声は明らかに女性だった。彼女もテスト中だということを理解しているのだろう。小さな声で話した。しかし、その声の中には田原とは違うハツラツさがあった。
「あ、はい」
担当講師にバレないように答え、自分を起こしてくれた女性の方に目をやる田原。
瞬間、彼女と目が合う。
「……」
声にならない声が喉の奥に詰まる。でもどうにかそれを声に出したくて、田原はエサを待つ金魚のように口をぱくぱくさせた。
「何やってるのよ」
楽しそうな笑顔を浮かべる女性。
「な、なんで……?」
どうにか絞り出した言葉はそれだった。田原は目を丸くし、驚きを隠しきれない。
なぜなら、隣に座っていたのは紛れもなく田原の見知った顔だったから。
4日も連続で深夜のコンビニに買い物に来ていた彼女──山下海春だったのだ。
白色を基調としたTシャツに、ジーパンという無難な服装で、肩から教科書類を入れたカバンを掛けている。
「よくやるよな、夜勤とか」
大理石風のタイルが張られた大学内の廊下。田原の隣を歩く天然なのか、理髪店でやってもらったのか分からない程のパーマがあたっている黒髪の男子生徒が言う。
「うっせぇ」
手短に答える田原は大きな欠伸をする。
「まぁ明日から夏休みだけどよ。普通テスト前に夜勤は入れないだろ」
牛乳瓶の底のようなレンズの厚い眼鏡をかけた男は、貧弱そうな体を揺らしながら歩く。
「森田くんこそ、勉強した?」
田原はその男子を森田、と呼び僅かに視線をくれる。
「当たり前だろ? 昨日はアニメ見るのも我慢して勉強したんだぜ?」
「ドヤ顔で言うのは自由だけど、それ普通に一夜漬けじゃん」
そう言う田原の手には、これからテストが行われる日本文化史の教科書が持たれている。
「いま暗記してる人には言われたくないかな」
至極当然の反論を聞こなかったふりでやり過ごし、田原と森田はテストが行われるA-32教室に入った。
「最後の方っすね」
教室に入るなり、声色が変わる森田。森田はかなりコミュニケーション能力が低いく、人が多くなる場所では普段より数段声色が硬くなり、何故だか語尾の方に「っす」が付く。
「時間ギリギリだしな」
教科書から顔を上げ、空いている席を探す。
「残念、二つ空いてるところないみたいだな」
二人で隣に座ってカンニングでもさせてもらおう、なんて考えが微塵もなかった訳では無い。田原はテストの点が1点でも上がる最終手段を失ったことを少し残念に思ったが、すぐに気持ちを切り替えた。
元々その手段に出るのは最終手段で、無くても困りはしない。
「嘘っすよね。離れないっすよね」
周りの誰にも聞こえないほどの、蚊の鳴くような声で森田は嘆いた。
「空いてないんだ、しょうがないだろ」
「誰かに頼んで……」
「いやいや、それこそ無理な話だろ」
森田はコミュニケーション能力が低い以前に人見知りなのだ。しかもかなりの人見知りで、知らない人が近くにいる状況はかなり緊張するらしい。
それが理由で、森田は電車を使えば直ぐ着くにも関わらず、わざわざ自転車を使って登校している。
「非人道的っすー」
「何言ってんだ、アホか」
先程までより少し声の大きさをあげた森田を短く罵倒し、田原は再度教科書に目を落とし、空いているまで歩いていく。
背後から何やら声が聞こえたが、無視して前から6番目の列──教室の中では真ん中より少し前──にあたる席に腰を下ろす。
──人なんて気にしなければいいのに。
椅子を引く、腰を下ろす、再度椅子を引く。田原の場合、その間に人と目が合うなんてことはない。特に今日は教科書に穴が空くのではと思われるほどに見つめているために、他人から見られているかなんてことに気づきもしない。
それからしばらくしてチャイムが鳴った。日本文化史を担当している50代半ばの女性が教壇に立ち、マイクを片手に「教科書や配布資料は閉まって」と声を上げた。
あちらこちらからため息が零れている。
「あぁ、詰みだわ」
「マジ無理ゲー」
などとこれから行われるであろうテストに対し、既に敗北宣言をしている生徒までいる始末だ。
「スマホ等携帯の電源は切って、カバンにしまって。それから机の上は筆記用具だけにするように」
その声すらも無視をして、女性は少し気だるげな声音で吐き捨てた。
「それじゃあ、テスト用紙を配っていく」
少し白髪混じりになった髪を肩くらいまで伸ばし、ヨレヨレになった灰色の服を着ているためにどこかみすぼらしさを感じさせる日本文化史の担当講師は、各列の先頭に適当に紙を渡していく。
「1人1部ずつとって後ろへ回して」
指示された通りに田原は1部を取り、振り返ることもせずに後ろへと流す。
頃合いを見てか、講師が始めの合図を出した。テスト用紙に視線を落とし問題を読んでいく。だが、テスト直前漬けで一夜漬けですらない田原にとってこれらの問題は難易度が高すぎた。
「夜勤、断っとけばよかった」
自分の大丈夫だろう、という浅はかな考えに嫌気がさし、小さな掠れた声で呟く。
あまりに小さな音のために、隣に座っている人ですらそれに気づいていない様子だ。田原は周りに視線をやることなく、集められる視線でそれを感じ取り、再び問題に意識を集める。
1問、2問。合ってるかどうか分からない答えを書いたところで、不意に田原の視界がブラックアウトする。
だがそれも一瞬。すぐに眼前には訳の分からない問題文で答えを導き出せ、という勉強をしていなければちんぷんかんぷんになってしまうテスト用紙がある。
数回頭を横に振ることで、どうにか吹っ飛んでしまいそうな意識を保ち、問題文を黙読する。
しかし、田原は理解できない問題文から誘われる睡魔に勝つことは出来ず、テスト開始からおよそ20分で意識を飛ばせてしまった。
これが中学や高校のテストならば、先生が回ってきて、肩をちょんちょんと指さされ起こされる。だが、大学になればその範囲ではない。
──寝てるやつは寝とけ。だが、単位はやらん。
そういうスタンスがほとんどだ。
だが、今日は違った。田原が眠りに落ちてから、数分が経ったところで田原は体に触れられる違和感を覚えた。
それは今まで起こされる時に触れられていた肩に感じるのではない。もっと下で、妙なこそばゆさを覚える。
その違和感を拭うことが出来ず、田原は薄っすらと目を開ける。
その違和感は脇腹から来ていることに田原は気づいた。ツン、ツン、とまるでいつぞやのおでんをつんつんしている人のように、隣に座っていた人は田原の脇腹をシャープペンシルでつついている。
「うっ」
目が覚めれば、ここからはこそばゆいという感覚しか襲ってこない。
「あ、あの」
森田と一緒にいることが多い田原は、人と話すのは得意ではない。森田程ではないが、普通の人よりは苦手であるのは間違いない。だからこそ、人があまり来ない上に時給がいい深夜のコンビニでバイトをしているのだ。
そんな田原だが、やはり何度も何度も脇腹をつんつんされるとこそばゆくて仕方がない。テスト中ということも鑑みて、田原は小声でそう声をかけた。
「起きたの?」
その声は明らかに女性だった。彼女もテスト中だということを理解しているのだろう。小さな声で話した。しかし、その声の中には田原とは違うハツラツさがあった。
「あ、はい」
担当講師にバレないように答え、自分を起こしてくれた女性の方に目をやる田原。
瞬間、彼女と目が合う。
「……」
声にならない声が喉の奥に詰まる。でもどうにかそれを声に出したくて、田原はエサを待つ金魚のように口をぱくぱくさせた。
「何やってるのよ」
楽しそうな笑顔を浮かべる女性。
「な、なんで……?」
どうにか絞り出した言葉はそれだった。田原は目を丸くし、驚きを隠しきれない。
なぜなら、隣に座っていたのは紛れもなく田原の見知った顔だったから。
4日も連続で深夜のコンビニに買い物に来ていた彼女──山下海春だったのだ。
0
あなたにおすすめの小説

診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写と他もすべて架空です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
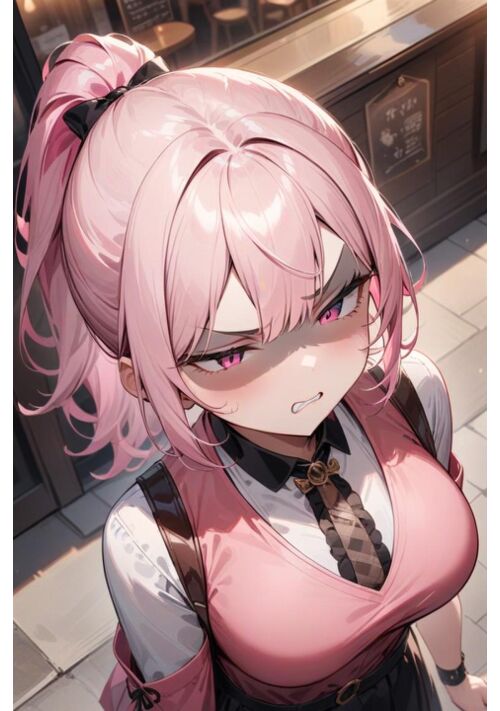
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。


あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。


天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















