2 / 2
番外編
【オムニバス】付き合って1週間記念日
しおりを挟む
待ち合わせをしているお店の前で、ショーウィンドウに映る自分の姿をまじまじと確認する。
膝丈まであるシックでありながらも暗すぎないスカートと、襟元と腕の部分がひらひらふわふわの白いトップス。少しだけアイロンで巻いてみた髪が、風に吹かれて揺れている。
今日で刈谷くんと付き合い始めて1週間。恋人として初めてのデートだから、可愛い服を買いに行って、それに合うようなメイクも練習してきた。私なりに、頑張ったつもりだ。
⋯⋯けれど、変じゃないだろうか。
買ったときは、とびきり素敵だと思っていた服も、今はまるで輝いて見えない。メイクも、髪を巻くことも、あまり慣れていないから、汚いかもしれない。アイラインがガタガタしてる気がしてきた。チークも濃い⋯⋯?髪もボサボサだと思われるかも⋯⋯クレンジング剤は家にしかないし、一旦家に帰ろうかな⋯⋯でも、今帰ったら予定の時間過ぎちゃうし⋯⋯
「真野ちゃんっ!」
そんな私の煩雑とした思考を遮るように、声がかけられた。顔をあげると、見知った明るい髪色が、私の視界の中に、眩しく入り込んでくる。
「遅れちゃってごめん!急な用事が出来て⋯⋯」
申し訳なさそうに謝るのは、待ち合わせ相手の刈谷くんだ。そんなに謝られると、こちらの方が申し訳なくなる。だって、予定時間より前に私がついてしまっただけだし、刈谷くんはバッチリ時間通りだから。悪いのは私だ。
「あ、いえっ、すみません。私が早く来すぎてしまったので、気を使わせてしまいましたよね?」
「いや、こっちが悪い。ごめんね!ホント⋯⋯あ、今日お洒落してきてくれたの?すごく可愛い。ありがとう」
刈谷くんは、申し訳なさそうに肩を落としたかと思えば、私の服装をみて表情を綻ばせる。私が可愛いだなんて、そんなことないのに。薄暗い感情が持ち上がりそうになって、振り切るように首を振った。いつもそうだ。刈谷くんは、私なんかに、いつも優しい言葉をくれる。
それは、ずっと幼い頃から変わらない。小さい頃、お隣の彼の家に、幾度となくお邪魔していた時も、笑顔で出迎えてくれたし、私が泣いていると「僕がいるからね」と声をかけてくれた。
そうやって、幼い頃はよく遊んだけれど、彼は、優しくて、かっこよくて、運動も勉強もできる人気者だった一方で、私は根暗でブスで面白みの欠けらも無い3流3軍女だったから、中学に進学すると、次第に話すことは少なくなっていた。それでも、時折、時間が合えば、彼の家でご飯を食べさせてもらうことがあった。そんな風に、腐れ縁の幼なじみとして、優しい彼が、私に対する同情と持ち前の責任感で続けてくれていたのが、私たちの関係だった。
⋯⋯だから正直、告白されるなんて思ってもいなかった。
普通に高校が別れた時点で、もう関わることはないんだろうな、と思っていた。⋯⋯以前このことをチラッと言ったら、全力で否定されたが、私はまだ信じられていない。
「楽しみだね、真野ちゃん!」
「⋯⋯うん!」
笑顔が爽やかで眩しい。浄化されて消えそうだ。多少、メイクや服をどうこうしたって、こんな素敵な人と釣り合うためには、自分は何もかもが足りなさすぎる。目下の目標は、今日のデートで敬語を外すことだ。まだ、下の名前で読んだり、ハグをしたりといったことはできないので、できることから地道にやって行きたい。3日前からいっぱい刈谷くんの写真に向かって練習したし、できる⋯⋯はずだ。
「まず、映画館にい、い⋯⋯いこっか!」
ぎこちない素振りで、私は笑顔を作った。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
「真野ちゃん無理してない?」
「⋯⋯してないよ?」
映画を見たあと、近くのケーキ屋さんに来たものの、いつもに増して言葉につまりまくる私の余りの不審さを見かねて、刈谷くんは尋ねた。
確かに、今の私は、敬語を外して喋ることと、刈谷くんの顔色を気にすることに精一杯で、大好物のショートケーキを一口も食べられていない。明らかに挙動不審だ。刈谷くんは不自然な私に対して、心做しか怪しんでいるような、訝しげな目を向けている。私は多量の冷や汗をかきながら、弁明しようと口を動かした。
「あ、え、変⋯⋯かな?私、いつも、あの、皆に敬語だから⋯⋯刈谷くんには、タメ口で話せるようになろうかなって、そう、思ったんだけど⋯⋯」
また、言葉に詰まりまくりだ。この話し方は、みっともないからやめろと、親にも散々言われてきたのに。刈谷くんも呆れてるかも。嫌だ。嫌われたくない。今、軽蔑の眼差しを向けられているのではないか。怖くて、刈谷くんの顔が見られない。泣きそうになって、フォークを握る手が強まった。
「いや、変とかそんなんじゃないよ。真野ちゃんのタメ口って、新鮮だなーって思っただけ」
私を落ち着かせるような、柔らかい言葉が響く。顔をあげると、想像とはまるで違う、穏やかな眼差しでこちらを見つめる刈谷くんがいた。安心して、ほっと息を吐く。
「そうなの⋯⋯?良かったぁ」
安堵の笑みを零し、手をつけていなかったショートケーキを頬張る。その美味しさを噛み締めている私を前に、今度は刈谷くんが取り乱し始めた。
「⋯⋯あれ?待って、敬語外そうとしてくれるの俺のためだったりする?自惚れていい?特別?えー!可愛い。嬉しい。」
刈谷くんは、こんな風によく私の事を「可愛い」と言ってくれるが、リップサービスが手馴れすぎていて怖い。以前、私が初めての彼女だと言っていた気がするが、あれも絶対嘘だ。女慣れしすぎている。歴代彼女数が2桁を余裕で超えてても違和感が無い。今は、私なんかに付き合ってもらっているけれど、これから先、たくさん素敵な人との出会いもあるんだろう。その中で、もしも、私の存在が刈谷くんの邪魔になったら──
「私、その時はすぐさまフェードアウトするから、安心してね」
「⋯⋯え?」
あ、今、凄く自然に喋れていた。自身の成長を感じる。こんな感じで今後も喋っていけたら⋯⋯と思って、気づく。そうだ。タメ口で喋れるようになったら、今度はいつでも彼女を辞められるように、敬語に戻す練習もしなくてはいけないのか。
「すぐさまフェードアウトってどういう意味?それにその時って?」
「⋯⋯?そのままの意味ですよ。もし、刈谷くんに新しく好きな人ができた時には、すぐに──」
続く言葉を遮るように、腕を掴まれた。
「⋯⋯あはは」
顔をあげると、刈谷くんは笑っていた。けれど、目の奥にまるで光がなく、怒りを全力で抑えていることがわかる。そうして、自分が酷い失言をしたことに気づく。まるで、刈谷くんが浮気するみたいな、信頼していないみたいな口ぶりだった。
「あ、ごめ、ごめんなさ⋯⋯」
「大丈夫。きっと、俺の伝え方が悪かったんだよね。」
「ずっと一緒にようね。真野ちゃん」
抱きしめられ、甘い愛の言葉が囁かれる。暖かい腕の中で、刈谷くんの不穏な意図を孕んだ目が、細められたまま、じっとりとこちらを見ていた。
◾︎side. 刈谷
目的の駅に着くと、以前から出没している真野ちゃんのストーカーを見つけた。真野ちゃんの背後で休憩のためにベンチに座っている──と見せかけて真野ちゃんの出した二酸化炭素を吸っていた。許せない。すぐに捕まえて、釘を刺す。刺しまくって、もう、息を吸えないようにしてやるしかない。
「なんだよ!なんで、お前なんかが静音さんの彼氏なんだよ!」
「あ゛?何?真野ちゃんのこと馴れ馴れしく名前で呼ぶなよ。」
こいつは、貧血かなんかで道端で倒れて、誰も助けてくれなかった時に、真野ちゃんが献身的に介抱してくれたことで、真野ちゃんに惚れ、ストーカー化した野郎だ。介抱されただけでも許せないのに、ストーカーになるとか意味がわからない。それに、調べていったら、真野ちゃんが通う予定の大学の奴だったし、名前勝手に呼んでるし、あーほんとに潰そう。今すぐ潰そう。幸い証拠は揃ってるし⋯⋯真野ちゃんはストーカーされてる自覚がないみたいだったけど、被害が出る前に潰しておきたい。あと単純に俺が不快。
そんなクソみたいなストーカーに構っていたら、結局、約束の時間になってしまった。なぜ、あんな野郎のために、俺と真野ちゃんの尊い時間が奪われなければならないのか。絶対許さない。いや、今はとにかく集合の場所へ急がなければ⋯⋯あ、真野ちゃんは、もう店の前で待ってくれているみたいだ。なんか、いつもより、オシャレしてくれてる⋯⋯?声をかけると、驚いたように肩を震わせて、声の主が俺であることがわかると、その表情を柔らかく緩めた。⋯⋯可愛すぎる、本当に癒し。ストーカーへの怒りも吹っ飛ぶ可愛さだ。
このふわふわぴょこぴょこの髪とか、触ってくれって俺におねだりしてるようにしか見えない。折角真野ちゃんが頑張ってセットしたんだろうから、鋼の理性で我慢するけど、ホントは今すぐ撫で回したい。きっと、蕩けるような触り心地なのだろう。こんなに可愛いのに、1人の時に誰にも声をかけられたりしなかっただろうか。怖いな。やはり、人の目に晒したくない。どこかに閉じ込めてしまいたい。俺がそんなことを考えていることなんか、微塵もわかっていない無垢な素振りで笑った。
⋯⋯こんなに可愛い真野ちゃんと恋人になれるなんて夢みたいだ。
今まで、逃げられないように真野ちゃんの家の事情につけこんで、じわじわこちら側に引き込んできた甲斐があった。ゆっくりしすぎたせいで、告白するのが遅くなってしまったけれど。
真野ちゃんの家は、父親があまり帰ってこない家だった。よくある話かもしれないが、真野ちゃんの母親はその原因を自分の子供に見出した。いつも、優秀な兄と真野ちゃんを比べて、欠点をあげつらい、罵倒していたのだ。その怒鳴り声は隣まで聞こえるほど、強く、暴力的だった。俺の両親も彼女を心配して、何かしようとしていたが、彼女の母親が家に怒鳴り込みに来たあと、干渉しづらくなっていた。彼女が外に締め出された日はよく家に来ていた。そういうとき、真野ちゃんが、泣きながら「ごめんなさい」とずっと繰り返していたのが痛々しくて、印象的だった。泣き止んで、笑って欲しくても、そのときの俺には、立ち尽くす他にどうすることも出来なかった。
俺たちが中学生になったころだったか、真野ちゃんの兄が事故で死んだ。それからは最悪だった。
真野ちゃんは家の中で、存在しない事になったのだ。彼女の母親は数日間荒れ、泣きわめいた。そして、その頃から両親が転勤し、一人暮らしを始めた俺の事を、自分の息子だと本気で信じるようになったのだ。俺と顔を合わせると真野ちゃんの母親は、俺を「幸樹」と呼ぶ。それは、真野ちゃんの死んだ兄の名前で、初めて呼ばれたときは驚いた。どうやら、勝手に、頭の中でそういう設定を作っていたらしい。しかも、真野ちゃんの母親は、自分の子供が「幸樹」1人だと思っていて、真野ちゃんの事は透明人間のように、当たり前に無視するし、ぶつかるし、食事も与えない。⋯⋯本当に虫唾が走る。
だから、真野ちゃんは、母親が「幸樹」に渡しに来る食事を俺の家で食べる。真野ちゃんが公園でコンビニのおにぎりを食べていた姿を見て、この提案を行った。俺が作ろうとしたら、申し訳ないから、と断られた。気を使っているのか、お母さんのご飯が良いということなのか、真意は不明だが、真野ちゃんがそういうなら、俺は従うだけだった。その時は、見る度に細くなっている真野ちゃんが心配で、真野ちゃんが、ご飯を食べているだけで良かったから。
毎回、「いつもごめんなさい」と、時折、手土産を片手に申し訳なさそうに家に入り、「いただきます」と遠慮がちに手を合わせてから食事を始める彼女が、酷く健気で、とても愛おしかった。
──この気持ちが恋であることに気づいたのは、高校生の時だった。でも、もっと前から本当は好きだったんだと思う。愛おしくて、手に入れたい。離したくない。そんな風に思ってしまうのは、真野ちゃんだけだから。同じ学区の持ち上がりで、公立の中学に入学したが、あまり学校で真野ちゃんと話すことはなかった。クラスが別れたため、単純に話す機会が少なかったのだ。それに、互いに意識しているのか、男女の分断が激しく、話しかければ、からかいの対象になることも目に見えていたから、話しかけに行っても迷惑かもしれないとか、変な気を使ってヘタレムーブをしていたのも要因かもしれない。
けれど、ある日、廊下を渡っている時、真野ちゃんがチャラそうな男と話しているところを見かけた。
男はどうみても真野ちゃんに気があり、距離を詰めようとしていた。真野ちゃんは、距離をとりながらも、苦笑いだったかもしれないが、笑っていた。怒りで視界が真っ白になる、という経験をしたのは初めてだった。なぜ、あのような軽薄そうな男が、真野ちゃんの隣に立っているのか。なぜ、彼女の笑顔を見ているのか?気持ち悪い、腹立たしい、許せない。考えるよりも先に足が動いて、気づけば声を掛けてしまっていた。
「真野ちゃんっ!」
彼女は、酷く狼狽していたと思う。入学してから一言も話していなかった幼なじみに急に話しかけられたから、すごく驚いたのだろう。
「え?わ、刈谷くん⋯⋯?何かあったんですか?」
そこで俺は、自分が全く話す内容を考えていなかったことに気づいた。
「あー⋯⋯あの⋯⋯あれ待ってない?和英辞典、今日使うのに忘れちゃってさ」
「和英辞典?持ってますよ。あ、でも次の授業で使うので、届けますね。」
明らかに見え透いた嘘なのに、真野ちゃんは全力で信じて、辞書を届けようともしてくれる。
「いや、流石に俺が借りさせてもらってる分際で届けさせないって、後で取りに来るよ!ごめんね!ありがと!」
「え、あ、はい、待ってます。」
全く疑う素振りもなく、簡単に約束してくれた。彼女の素直で疑うことをしらないところは、美点だと思うけど、ここまでくると少し心配だ。そこに漬け込む不貞な輩も出てくるだろうから⋯⋯先程まで真野ちゃんと喋っていた男を、軽く睨んで牽制する。男が気まずそうに顔を逸らすところを見るに、やはり下心ありきで話しかけていたらしい。これからは、理由をつけて頻繁にこちらへ来ようと決心した出来事だった。
その後、真野ちゃんが家にご飯を食べに来ていることをふんわり仄めかし、仲の良い素振りをみせることで付き合っているのではないかと周りに勘ぐらせた。変に真野ちゃんにちょっかいかけようとした奴らは、適当に間引いて対処した。その甲斐あって、真野ちゃんだけは気づいてなかったが、周囲からは公認カップル、ニコイチとして扱われていた。その後、卒業式の日に告白して、名実ともに付き合うことになった。
真野ちゃんは付き合い始めてから、恋人という関係に対して真摯に向き合ってくれているようで、今日は俺にだけ敬語を外す練習をしてくれていた。最初は、大好物のショートケーキを前に顔を真っ青にしているから、俺とのデート嫌なのかなーとか、体調悪いのかなーとか心配してたけど、めちゃくちゃ健気なだけだった。可愛い。幸せを噛み締めていた。
⋯⋯けれど、その後に紡がれた言葉によって、心が滅茶苦茶に掻き回される。びっくりして、思わず威圧するような声を出してしまった。何?『その時はすぐさまフェードアウトするから安心してね』って何?どういう意味?真野ちゃんの前では完璧な刈谷くんでいたいのに、どうしても動揺を隠せない。真野ちゃんの言葉の真意を探ろうと問いかけると、頑張ってタメ口で話してくれていた真野ちゃんの口調が変わっていた。
その時、俺は真野ちゃんが俺を捨てて、置いていこうとしていることに直感的に気づいた。
どうやら、愛しい彼女は、俺から逃げようとしているらしい。粘着質で薄暗い俺の本質に気づいて嫌になった?俺は愚直に真野ちゃんとの永遠を信じていたから、真野ちゃんの言葉に現実を突きつけられて、酷く失望し、こんな未来を想像もしていなかった自分に呆れて笑ってしまった。先程より一層青い顔をした真野ちゃんが普段と違う俺の様子に怯えている。怖がらせてしまったみたいで申し訳ない。
⋯⋯でも、まぁ、もういいや。
真野ちゃんとずっと一緒に過ごすなんて、そんな未来を信じていた俺が甘かったんだ。真野ちゃんは、そんなことは全く、微塵も考えてなくて、ただ終わりを待ってただけなんだ。俺の方がずっと想ってただけなんて一方通行すぎて吐きそう。合意とか、そんなこと言ってられない。逃げられてしまうのなら、丸呑みにして、いつか真野ちゃんがお腹の中で溶けてしまっても、俺の一部になって、ずっと、それこそ死んでも、一緒にいるしかないよ。
──ねぇ、一緒にいてよ。真野ちゃん。
そう思いながら、俺は彼女を腕の中に抱きしめた。
END
膝丈まであるシックでありながらも暗すぎないスカートと、襟元と腕の部分がひらひらふわふわの白いトップス。少しだけアイロンで巻いてみた髪が、風に吹かれて揺れている。
今日で刈谷くんと付き合い始めて1週間。恋人として初めてのデートだから、可愛い服を買いに行って、それに合うようなメイクも練習してきた。私なりに、頑張ったつもりだ。
⋯⋯けれど、変じゃないだろうか。
買ったときは、とびきり素敵だと思っていた服も、今はまるで輝いて見えない。メイクも、髪を巻くことも、あまり慣れていないから、汚いかもしれない。アイラインがガタガタしてる気がしてきた。チークも濃い⋯⋯?髪もボサボサだと思われるかも⋯⋯クレンジング剤は家にしかないし、一旦家に帰ろうかな⋯⋯でも、今帰ったら予定の時間過ぎちゃうし⋯⋯
「真野ちゃんっ!」
そんな私の煩雑とした思考を遮るように、声がかけられた。顔をあげると、見知った明るい髪色が、私の視界の中に、眩しく入り込んでくる。
「遅れちゃってごめん!急な用事が出来て⋯⋯」
申し訳なさそうに謝るのは、待ち合わせ相手の刈谷くんだ。そんなに謝られると、こちらの方が申し訳なくなる。だって、予定時間より前に私がついてしまっただけだし、刈谷くんはバッチリ時間通りだから。悪いのは私だ。
「あ、いえっ、すみません。私が早く来すぎてしまったので、気を使わせてしまいましたよね?」
「いや、こっちが悪い。ごめんね!ホント⋯⋯あ、今日お洒落してきてくれたの?すごく可愛い。ありがとう」
刈谷くんは、申し訳なさそうに肩を落としたかと思えば、私の服装をみて表情を綻ばせる。私が可愛いだなんて、そんなことないのに。薄暗い感情が持ち上がりそうになって、振り切るように首を振った。いつもそうだ。刈谷くんは、私なんかに、いつも優しい言葉をくれる。
それは、ずっと幼い頃から変わらない。小さい頃、お隣の彼の家に、幾度となくお邪魔していた時も、笑顔で出迎えてくれたし、私が泣いていると「僕がいるからね」と声をかけてくれた。
そうやって、幼い頃はよく遊んだけれど、彼は、優しくて、かっこよくて、運動も勉強もできる人気者だった一方で、私は根暗でブスで面白みの欠けらも無い3流3軍女だったから、中学に進学すると、次第に話すことは少なくなっていた。それでも、時折、時間が合えば、彼の家でご飯を食べさせてもらうことがあった。そんな風に、腐れ縁の幼なじみとして、優しい彼が、私に対する同情と持ち前の責任感で続けてくれていたのが、私たちの関係だった。
⋯⋯だから正直、告白されるなんて思ってもいなかった。
普通に高校が別れた時点で、もう関わることはないんだろうな、と思っていた。⋯⋯以前このことをチラッと言ったら、全力で否定されたが、私はまだ信じられていない。
「楽しみだね、真野ちゃん!」
「⋯⋯うん!」
笑顔が爽やかで眩しい。浄化されて消えそうだ。多少、メイクや服をどうこうしたって、こんな素敵な人と釣り合うためには、自分は何もかもが足りなさすぎる。目下の目標は、今日のデートで敬語を外すことだ。まだ、下の名前で読んだり、ハグをしたりといったことはできないので、できることから地道にやって行きたい。3日前からいっぱい刈谷くんの写真に向かって練習したし、できる⋯⋯はずだ。
「まず、映画館にい、い⋯⋯いこっか!」
ぎこちない素振りで、私は笑顔を作った。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
「真野ちゃん無理してない?」
「⋯⋯してないよ?」
映画を見たあと、近くのケーキ屋さんに来たものの、いつもに増して言葉につまりまくる私の余りの不審さを見かねて、刈谷くんは尋ねた。
確かに、今の私は、敬語を外して喋ることと、刈谷くんの顔色を気にすることに精一杯で、大好物のショートケーキを一口も食べられていない。明らかに挙動不審だ。刈谷くんは不自然な私に対して、心做しか怪しんでいるような、訝しげな目を向けている。私は多量の冷や汗をかきながら、弁明しようと口を動かした。
「あ、え、変⋯⋯かな?私、いつも、あの、皆に敬語だから⋯⋯刈谷くんには、タメ口で話せるようになろうかなって、そう、思ったんだけど⋯⋯」
また、言葉に詰まりまくりだ。この話し方は、みっともないからやめろと、親にも散々言われてきたのに。刈谷くんも呆れてるかも。嫌だ。嫌われたくない。今、軽蔑の眼差しを向けられているのではないか。怖くて、刈谷くんの顔が見られない。泣きそうになって、フォークを握る手が強まった。
「いや、変とかそんなんじゃないよ。真野ちゃんのタメ口って、新鮮だなーって思っただけ」
私を落ち着かせるような、柔らかい言葉が響く。顔をあげると、想像とはまるで違う、穏やかな眼差しでこちらを見つめる刈谷くんがいた。安心して、ほっと息を吐く。
「そうなの⋯⋯?良かったぁ」
安堵の笑みを零し、手をつけていなかったショートケーキを頬張る。その美味しさを噛み締めている私を前に、今度は刈谷くんが取り乱し始めた。
「⋯⋯あれ?待って、敬語外そうとしてくれるの俺のためだったりする?自惚れていい?特別?えー!可愛い。嬉しい。」
刈谷くんは、こんな風によく私の事を「可愛い」と言ってくれるが、リップサービスが手馴れすぎていて怖い。以前、私が初めての彼女だと言っていた気がするが、あれも絶対嘘だ。女慣れしすぎている。歴代彼女数が2桁を余裕で超えてても違和感が無い。今は、私なんかに付き合ってもらっているけれど、これから先、たくさん素敵な人との出会いもあるんだろう。その中で、もしも、私の存在が刈谷くんの邪魔になったら──
「私、その時はすぐさまフェードアウトするから、安心してね」
「⋯⋯え?」
あ、今、凄く自然に喋れていた。自身の成長を感じる。こんな感じで今後も喋っていけたら⋯⋯と思って、気づく。そうだ。タメ口で喋れるようになったら、今度はいつでも彼女を辞められるように、敬語に戻す練習もしなくてはいけないのか。
「すぐさまフェードアウトってどういう意味?それにその時って?」
「⋯⋯?そのままの意味ですよ。もし、刈谷くんに新しく好きな人ができた時には、すぐに──」
続く言葉を遮るように、腕を掴まれた。
「⋯⋯あはは」
顔をあげると、刈谷くんは笑っていた。けれど、目の奥にまるで光がなく、怒りを全力で抑えていることがわかる。そうして、自分が酷い失言をしたことに気づく。まるで、刈谷くんが浮気するみたいな、信頼していないみたいな口ぶりだった。
「あ、ごめ、ごめんなさ⋯⋯」
「大丈夫。きっと、俺の伝え方が悪かったんだよね。」
「ずっと一緒にようね。真野ちゃん」
抱きしめられ、甘い愛の言葉が囁かれる。暖かい腕の中で、刈谷くんの不穏な意図を孕んだ目が、細められたまま、じっとりとこちらを見ていた。
◾︎side. 刈谷
目的の駅に着くと、以前から出没している真野ちゃんのストーカーを見つけた。真野ちゃんの背後で休憩のためにベンチに座っている──と見せかけて真野ちゃんの出した二酸化炭素を吸っていた。許せない。すぐに捕まえて、釘を刺す。刺しまくって、もう、息を吸えないようにしてやるしかない。
「なんだよ!なんで、お前なんかが静音さんの彼氏なんだよ!」
「あ゛?何?真野ちゃんのこと馴れ馴れしく名前で呼ぶなよ。」
こいつは、貧血かなんかで道端で倒れて、誰も助けてくれなかった時に、真野ちゃんが献身的に介抱してくれたことで、真野ちゃんに惚れ、ストーカー化した野郎だ。介抱されただけでも許せないのに、ストーカーになるとか意味がわからない。それに、調べていったら、真野ちゃんが通う予定の大学の奴だったし、名前勝手に呼んでるし、あーほんとに潰そう。今すぐ潰そう。幸い証拠は揃ってるし⋯⋯真野ちゃんはストーカーされてる自覚がないみたいだったけど、被害が出る前に潰しておきたい。あと単純に俺が不快。
そんなクソみたいなストーカーに構っていたら、結局、約束の時間になってしまった。なぜ、あんな野郎のために、俺と真野ちゃんの尊い時間が奪われなければならないのか。絶対許さない。いや、今はとにかく集合の場所へ急がなければ⋯⋯あ、真野ちゃんは、もう店の前で待ってくれているみたいだ。なんか、いつもより、オシャレしてくれてる⋯⋯?声をかけると、驚いたように肩を震わせて、声の主が俺であることがわかると、その表情を柔らかく緩めた。⋯⋯可愛すぎる、本当に癒し。ストーカーへの怒りも吹っ飛ぶ可愛さだ。
このふわふわぴょこぴょこの髪とか、触ってくれって俺におねだりしてるようにしか見えない。折角真野ちゃんが頑張ってセットしたんだろうから、鋼の理性で我慢するけど、ホントは今すぐ撫で回したい。きっと、蕩けるような触り心地なのだろう。こんなに可愛いのに、1人の時に誰にも声をかけられたりしなかっただろうか。怖いな。やはり、人の目に晒したくない。どこかに閉じ込めてしまいたい。俺がそんなことを考えていることなんか、微塵もわかっていない無垢な素振りで笑った。
⋯⋯こんなに可愛い真野ちゃんと恋人になれるなんて夢みたいだ。
今まで、逃げられないように真野ちゃんの家の事情につけこんで、じわじわこちら側に引き込んできた甲斐があった。ゆっくりしすぎたせいで、告白するのが遅くなってしまったけれど。
真野ちゃんの家は、父親があまり帰ってこない家だった。よくある話かもしれないが、真野ちゃんの母親はその原因を自分の子供に見出した。いつも、優秀な兄と真野ちゃんを比べて、欠点をあげつらい、罵倒していたのだ。その怒鳴り声は隣まで聞こえるほど、強く、暴力的だった。俺の両親も彼女を心配して、何かしようとしていたが、彼女の母親が家に怒鳴り込みに来たあと、干渉しづらくなっていた。彼女が外に締め出された日はよく家に来ていた。そういうとき、真野ちゃんが、泣きながら「ごめんなさい」とずっと繰り返していたのが痛々しくて、印象的だった。泣き止んで、笑って欲しくても、そのときの俺には、立ち尽くす他にどうすることも出来なかった。
俺たちが中学生になったころだったか、真野ちゃんの兄が事故で死んだ。それからは最悪だった。
真野ちゃんは家の中で、存在しない事になったのだ。彼女の母親は数日間荒れ、泣きわめいた。そして、その頃から両親が転勤し、一人暮らしを始めた俺の事を、自分の息子だと本気で信じるようになったのだ。俺と顔を合わせると真野ちゃんの母親は、俺を「幸樹」と呼ぶ。それは、真野ちゃんの死んだ兄の名前で、初めて呼ばれたときは驚いた。どうやら、勝手に、頭の中でそういう設定を作っていたらしい。しかも、真野ちゃんの母親は、自分の子供が「幸樹」1人だと思っていて、真野ちゃんの事は透明人間のように、当たり前に無視するし、ぶつかるし、食事も与えない。⋯⋯本当に虫唾が走る。
だから、真野ちゃんは、母親が「幸樹」に渡しに来る食事を俺の家で食べる。真野ちゃんが公園でコンビニのおにぎりを食べていた姿を見て、この提案を行った。俺が作ろうとしたら、申し訳ないから、と断られた。気を使っているのか、お母さんのご飯が良いということなのか、真意は不明だが、真野ちゃんがそういうなら、俺は従うだけだった。その時は、見る度に細くなっている真野ちゃんが心配で、真野ちゃんが、ご飯を食べているだけで良かったから。
毎回、「いつもごめんなさい」と、時折、手土産を片手に申し訳なさそうに家に入り、「いただきます」と遠慮がちに手を合わせてから食事を始める彼女が、酷く健気で、とても愛おしかった。
──この気持ちが恋であることに気づいたのは、高校生の時だった。でも、もっと前から本当は好きだったんだと思う。愛おしくて、手に入れたい。離したくない。そんな風に思ってしまうのは、真野ちゃんだけだから。同じ学区の持ち上がりで、公立の中学に入学したが、あまり学校で真野ちゃんと話すことはなかった。クラスが別れたため、単純に話す機会が少なかったのだ。それに、互いに意識しているのか、男女の分断が激しく、話しかければ、からかいの対象になることも目に見えていたから、話しかけに行っても迷惑かもしれないとか、変な気を使ってヘタレムーブをしていたのも要因かもしれない。
けれど、ある日、廊下を渡っている時、真野ちゃんがチャラそうな男と話しているところを見かけた。
男はどうみても真野ちゃんに気があり、距離を詰めようとしていた。真野ちゃんは、距離をとりながらも、苦笑いだったかもしれないが、笑っていた。怒りで視界が真っ白になる、という経験をしたのは初めてだった。なぜ、あのような軽薄そうな男が、真野ちゃんの隣に立っているのか。なぜ、彼女の笑顔を見ているのか?気持ち悪い、腹立たしい、許せない。考えるよりも先に足が動いて、気づけば声を掛けてしまっていた。
「真野ちゃんっ!」
彼女は、酷く狼狽していたと思う。入学してから一言も話していなかった幼なじみに急に話しかけられたから、すごく驚いたのだろう。
「え?わ、刈谷くん⋯⋯?何かあったんですか?」
そこで俺は、自分が全く話す内容を考えていなかったことに気づいた。
「あー⋯⋯あの⋯⋯あれ待ってない?和英辞典、今日使うのに忘れちゃってさ」
「和英辞典?持ってますよ。あ、でも次の授業で使うので、届けますね。」
明らかに見え透いた嘘なのに、真野ちゃんは全力で信じて、辞書を届けようともしてくれる。
「いや、流石に俺が借りさせてもらってる分際で届けさせないって、後で取りに来るよ!ごめんね!ありがと!」
「え、あ、はい、待ってます。」
全く疑う素振りもなく、簡単に約束してくれた。彼女の素直で疑うことをしらないところは、美点だと思うけど、ここまでくると少し心配だ。そこに漬け込む不貞な輩も出てくるだろうから⋯⋯先程まで真野ちゃんと喋っていた男を、軽く睨んで牽制する。男が気まずそうに顔を逸らすところを見るに、やはり下心ありきで話しかけていたらしい。これからは、理由をつけて頻繁にこちらへ来ようと決心した出来事だった。
その後、真野ちゃんが家にご飯を食べに来ていることをふんわり仄めかし、仲の良い素振りをみせることで付き合っているのではないかと周りに勘ぐらせた。変に真野ちゃんにちょっかいかけようとした奴らは、適当に間引いて対処した。その甲斐あって、真野ちゃんだけは気づいてなかったが、周囲からは公認カップル、ニコイチとして扱われていた。その後、卒業式の日に告白して、名実ともに付き合うことになった。
真野ちゃんは付き合い始めてから、恋人という関係に対して真摯に向き合ってくれているようで、今日は俺にだけ敬語を外す練習をしてくれていた。最初は、大好物のショートケーキを前に顔を真っ青にしているから、俺とのデート嫌なのかなーとか、体調悪いのかなーとか心配してたけど、めちゃくちゃ健気なだけだった。可愛い。幸せを噛み締めていた。
⋯⋯けれど、その後に紡がれた言葉によって、心が滅茶苦茶に掻き回される。びっくりして、思わず威圧するような声を出してしまった。何?『その時はすぐさまフェードアウトするから安心してね』って何?どういう意味?真野ちゃんの前では完璧な刈谷くんでいたいのに、どうしても動揺を隠せない。真野ちゃんの言葉の真意を探ろうと問いかけると、頑張ってタメ口で話してくれていた真野ちゃんの口調が変わっていた。
その時、俺は真野ちゃんが俺を捨てて、置いていこうとしていることに直感的に気づいた。
どうやら、愛しい彼女は、俺から逃げようとしているらしい。粘着質で薄暗い俺の本質に気づいて嫌になった?俺は愚直に真野ちゃんとの永遠を信じていたから、真野ちゃんの言葉に現実を突きつけられて、酷く失望し、こんな未来を想像もしていなかった自分に呆れて笑ってしまった。先程より一層青い顔をした真野ちゃんが普段と違う俺の様子に怯えている。怖がらせてしまったみたいで申し訳ない。
⋯⋯でも、まぁ、もういいや。
真野ちゃんとずっと一緒に過ごすなんて、そんな未来を信じていた俺が甘かったんだ。真野ちゃんは、そんなことは全く、微塵も考えてなくて、ただ終わりを待ってただけなんだ。俺の方がずっと想ってただけなんて一方通行すぎて吐きそう。合意とか、そんなこと言ってられない。逃げられてしまうのなら、丸呑みにして、いつか真野ちゃんがお腹の中で溶けてしまっても、俺の一部になって、ずっと、それこそ死んでも、一緒にいるしかないよ。
──ねぇ、一緒にいてよ。真野ちゃん。
そう思いながら、俺は彼女を腕の中に抱きしめた。
END
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。

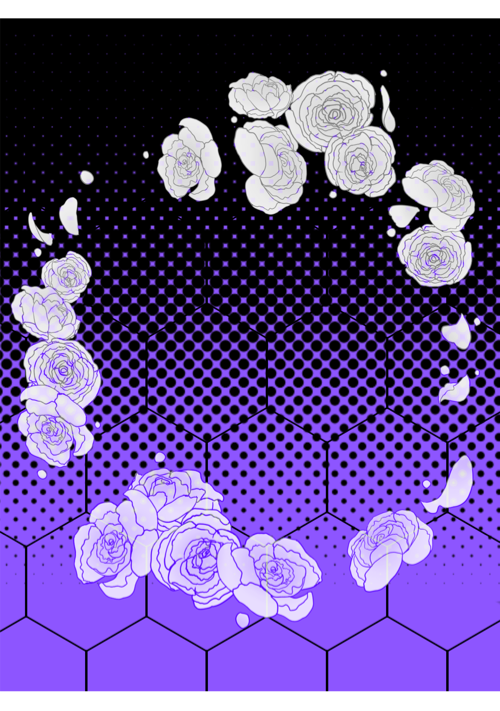
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?



転生したら4人のヤンデレ彼氏に溺愛される日々が待っていた。
aika
恋愛
主人公まゆは冴えないOL。
ある日ちょっとした事故で命を落とし転生したら・・・
4人のイケメン俳優たちと同棲するという神展開が待っていた。
それぞれタイプの違うイケメンたちに囲まれながら、
生活することになったまゆだが、彼らはまゆを溺愛するあまり
どんどんヤンデレ男になっていき・・・・
ヤンデレ、溺愛、執着、取り合い・・・♡
何でもありのドタバタ恋愛逆ハーレムコメディです。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















